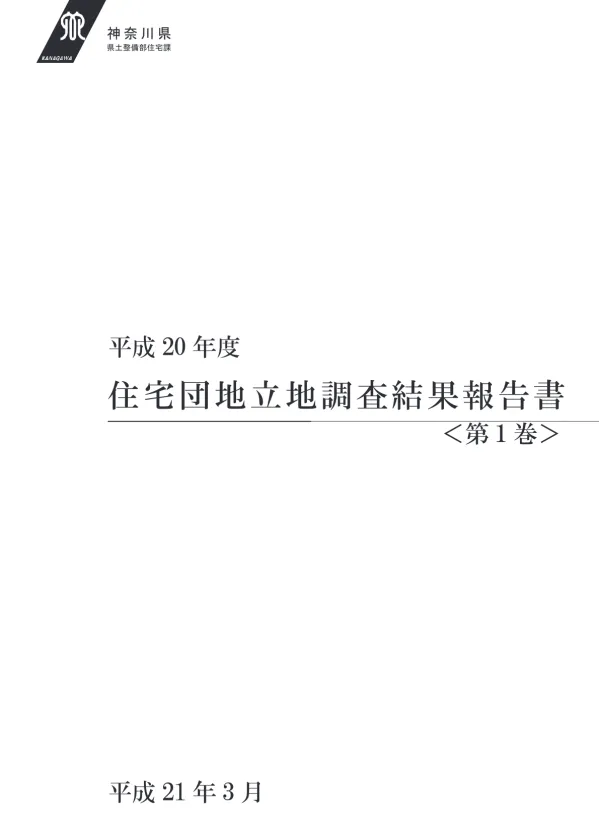
住宅団地立地調査報告書:概要
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.37 MB |
概要
I.横浜市における住宅団地 区画整理事業の調査概要
本調査は、横浜市および近郊地域における住宅団地と区画整理事業に関する情報を網羅的にまとめたものです。調査対象には、都市再生機構(UR) や神奈川県住宅供給公社が主体となって開発された大規模な住宅団地が多く含まれています。調査期間は昭和53年度から平成9年度まで、そしてそれ以降のデータも含まれており、第1種住専、第2種住専等の用途地域区分も考慮されています。調査対象の横浜市内の住宅団地は、緑区、港南区、金沢区、戸塚区、旭区、栄区、青葉区、泉区、神奈川区、磯子区、保土ヶ谷区、瀬谷区、中区、南区、都筑区などに広がっており、各区における事業主体、開発面積、戸数、建築年代などの詳細なデータが網羅されています。特に、都市再生機構(UR) と神奈川県住宅供給公社が開発に関与した住宅団地の数は非常に多く、本調査において重要な位置を占めています。 各住宅団地の情報は、事業主体、所在地、造成・建築時期、用途地域、敷地面積、戸数などに分類され、詳細なデータが提供されています。これらの情報は、今後の横浜市における都市計画や住宅政策に役立つ貴重な資料となると考えられます。
1. 調査対象と期間
本調査は、横浜市および近郊地域における一般住宅団地および土地区画整理事業に関する情報を対象としています。調査対象は、住宅団地の開発事業に携わった事業主体、所在地、開発面積、戸数、建築年代等の詳細な情報を網羅しています。特に、日本住宅公団(現都市再生機構(UR))、住宅・都市整備公団(現都市再生機構(UR))、都市公団(現都市再生機構(UR))、そして神奈川県住宅供給公社といった主要事業主体による大規模開発プロジェクトが多数含まれています。調査期間は昭和53年度から開始され、平成9年度の調査データに加え、それ以降の住宅団地に関する情報も可能な限り網羅し、追加・充実させています。昭和53年度以前のデータについても、判明した範囲で取りまとめられています。 用途地域に関しても、平成4年の法改正による新用途地域と旧用途地域の情報が混在しており、調査年度によって記載内容に差異があります。このため、調査データの解釈にあたっては、調査年度と用途地域の分類基準を十分に考慮する必要があります。調査資料としては、事業主体欄の記述から、都市再生機構(UR)の関与するプロジェクトの多さが読み取れます。これは、URが横浜市の住宅供給に大きな役割を果たしていることを示唆しています。
2. 調査内容と方法
本調査の調査内容・方法の概要は、「2 調査要領」に詳細に記されています。昭和53年度からの調査データに基づいており、特に「(2)調査一覧表」に示された内容は、年を追うごとに追加・充実されています。過去の調査分に関しては、判明している情報に基づいてまとめられています。重要な点として、用途地域の記載方法が調査年度によって異なります。平成9年度以降の調査分では、平成4年の法改正による新用途地域が記載されていますが、それ以前の調査分には旧用途地域が記載されている場合もあります。これは、横浜市における土地利用規制の変化を反映していると言えるでしょう。このため、異なる年度の調査データを比較・分析する際には、用途地域の定義の違いに注意を払う必要がある点に留意すべきです。 また、住宅団地に関する様々な属性データ(事業主体、所在地、開発面積、戸数、建築年代、用途地域など)の収集と整理が、本調査の主要な方法論として挙げられます。これらのデータは、多角的な視点からの横浜市の住宅団地開発状況の分析に不可欠な基盤となります。
3. データの構成と備考
本調査で用いられているデータは、主に表形式で整理されています。各住宅団地について、団地名および所在地、事業主体、造成または建築着工年度、用途地域、敷地面積、宅地面積、戸数、建売住宅戸数、賃貸住宅戸数といった項目が記載されています。さらに、備考欄には、区画整理区域への所属状況、交通局営業所併存などの追加情報、そして前述のように調査年度による用途地域の表記の差異などが含まれています。事業主体としては、都市再生機構(UR)、神奈川県住宅供給公社、横浜市、そして様々な民間企業が挙げられています。これらのデータは、それぞれの事業主体による横浜市における住宅団地開発への貢献度や、開発手法の特徴を分析する上で、重要な役割を果たします。また、備考欄に記載された情報は、住宅団地の立地条件や周辺環境、開発計画の変更などの歴史的背景を理解する上で役立つでしょう。特に、区画整理区域内の住宅団地については、その立地条件や開発計画の経緯を詳細に検討することで、今後の都市計画に役立つ知見が得られる可能性があります。
II.主要事業主体による横浜市住宅団地の開発状況
本調査で確認された主要事業主体である都市再生機構(UR)と神奈川県住宅供給公社による横浜市内の住宅団地開発状況は、それぞれの開発規模、年代、所在地の特徴を分析することで、横浜市の住宅供給における役割を明確に示しています。URは高層住宅を中心とした大規模開発を複数手がけており、特に港北ニュータウンなどにおける開発実績が目立ちます。一方、神奈川県住宅供給公社は中層住宅を主体とした開発を幅広い地域で行っており、地域住民の住宅需要に応える役割を担っていることがわかります。 それぞれの事業主体の開発実績を詳細に分析することで、横浜市の都市開発における戦略や課題を明らかにし、今後の都市計画に役立てることができます。
1. 都市再生機構 UR による横浜市住宅団地開発
本調査資料によると、都市再生機構(UR) は横浜市における大規模な住宅団地開発において、重要な役割を担っています。かつての日本住宅公団、住宅・都市整備公団、都市公団を統合した組織である都市再生機構(UR)は、資料中に繰り返し登場し、多くの住宅団地の開発主体となっています。これらの住宅団地は、高層住宅を多く含む大規模な開発プロジェクトであることが多く、港北ニュータウンなどの大規模開発事業にも関与していることがうかがえます。 資料からは、URが開発した住宅団地の所在地、開発規模(戸数、敷地面積)、建築時期などの具体的な数値データが確認できます。これらのデータから、URによる横浜市の住宅供給への貢献度や、開発手法の特徴を分析することができます。高層住宅の比率が高いことから、都市部の高密度開発への対応や、効率的な土地利用がURの開発戦略に含まれている可能性が示唆されます。さらに、第1種住専や第2種住専といった用途地域における開発状況も分析することで、URの開発における土地利用計画の特徴をより詳細に把握することができます。
2. 神奈川県住宅供給公社による横浜市住宅団地開発
神奈川県住宅供給公社も、横浜市における住宅団地開発事業において、重要な事業主体の一つです。資料からは、神奈川県住宅供給公社が開発主体となっている住宅団地のデータが複数確認できます。これらの住宅団地は、URのプロジェクトと比較して、規模は比較的小規模であり、中層住宅が中心となっている傾向が見られます。 神奈川県住宅供給公社の住宅団地は、横浜市の様々な区に分散して立地しており、地域住民の多様な住宅ニーズに対応していると考えられます。資料からは、神奈川県住宅供給公社が開発した住宅団地の所在地、開発規模(戸数、敷地面積)、建築時期、そして用途地域(第1種住専、第2種住専など)といった情報を抽出することができます。これらの情報から、神奈川県住宅供給公社の開発戦略や、横浜市における地域貢献、そして土地利用計画の特徴を分析することができます。 また、神奈川県住宅供給公社と**都市再生機構(UR)**の開発事業を比較することで、両者の開発規模や手法の違い、そして横浜市におけるそれぞれの役割をより明確に理解することができます。
3. その他事業主体による横浜市住宅団地開発
資料には、都市再生機構(UR)および神奈川県住宅供給公社以外にも、多くの事業主体が横浜市の住宅団地開発に関わっていることが示されています。 これらの事業主体には、民間企業(例:東急不動産、野村不動産、三井不動産など)や、地方自治体(例:横浜市)、そしてその他の組織が含まれています。それぞれの事業主体は、規模や特性の異なる住宅団地を開発しており、高層住宅、中層住宅、低層住宅、戸建住宅などが含まれます。 資料からは、これらの事業主体が開発に関わった住宅団地の所在地、開発時期、規模、そして用途地域(第1種住専、第2種住専、住居地域など)に関する情報を抽出することができます。これら多様な事業主体の開発状況を分析することで、横浜市の住宅供給における多様なアプローチや市場動向を理解することができます。さらに、それぞれの事業主体が開発した住宅団地の特性を比較することで、横浜市の住宅政策における課題や今後の方向性を検討する上で、貴重な知見が得られる可能性があります。
III.用途地域別の横浜市住宅団地分布
本調査では、住宅団地の用途地域を第1種住専、第2種住専、住居地域などに分類し、それぞれの地域における分布状況を示しています。第1種住専および第2種住専は、多くの住宅団地において主要な用途地域として指定されており、横浜市の住宅供給における重要な役割を担っています。これらの用途地域別の分布状況を分析することで、横浜市の都市計画における土地利用の現状と課題を明らかにすることができます。 特に、近年増加している**都市再生機構(UR)**のプロジェクトにおいては、用途地域の指定状況と開発規模との関係性などを分析することで、今後の都市計画における指針を導き出すことが期待できます。
1. 第1種住専地域と第2種住専地域の横浜市住宅団地分布
本調査資料は、横浜市内の住宅団地の用途地域別分布を分析しています。特に、第1種住専地域と第2種住専地域に焦点を当て、それぞれの地域における住宅団地の立地状況、開発規模、事業主体などを詳細に示しています。資料からは、多くの住宅団地が第1種住専または第2種住専の用途地域に属していることがわかります。これは、これらの用途地域が、横浜市における住宅供給において重要な役割を担っていることを示唆しています。 第1種住専地域と第2種住専地域における住宅団地の分布を比較することで、両者の立地条件や開発規模、そして事業主体の違いなどを分析することができます。例えば、都市再生機構(UR)や神奈川県住宅供給公社といった主要事業主体は、どちらの用途地域にも積極的に住宅団地を開発していることが確認できます。しかしながら、それぞれの事業主体が重点的に開発している用途地域に違いがある可能性があり、その詳細な分析は、今後の横浜市の住宅政策の策定に役立つでしょう。 また、区画整理事業との関連性も考慮することで、より詳細な分析を行うことができます。 区画整理事業によって造成された土地に、どのような用途地域が指定され、どのような種類の住宅団地が建設されているのかを分析することで、横浜市の都市計画における土地利用の効率性や、住宅政策の有効性を評価する上で重要な知見を得ることが期待できます。
2. 用途地域と住宅団地規模 形態の関係性
本調査資料からは、用途地域と住宅団地の規模や形態(高層住宅、中層住宅、低層住宅、戸建住宅など)との関係性を分析することができます。 例えば、第1種住専地域では、高層住宅を中心とした大規模な住宅団地が多く開発されている一方、第2種住専地域では、中層住宅や低層住宅を含む、より小規模な住宅団地が開発されている傾向が見られる可能性があります。 この関係性を分析することで、用途地域の指定基準と実際の住宅団地開発との整合性、そして土地利用計画の妥当性を評価することができます。さらに、それぞれの用途地域における住宅団地の平均戸数や敷地面積などの統計データを用いて、用途地域別の開発特性を明らかにすることができます。これらの分析結果から、横浜市における土地利用計画の改善点や、より効率的な住宅供給のための政策提言を行うことが期待できます。 また、区画整理事業との関連性も考慮することで、より詳細な分析を行うことが可能です。区画整理事業によって造成された土地の用途地域と、そこで建設された住宅団地の規模や形態を比較することで、区画整理事業の有効性や、今後の都市計画への示唆を得ることが期待されます。
3. 用途地域と事業主体の関係性
本調査資料は、横浜市内の住宅団地における用途地域と事業主体の関係性を分析する上で貴重なデータを提供しています。 第1種住専地域と第2種住専地域では、それぞれにどのような事業主体が多くの開発プロジェクトに関わっているのか、その違いを分析することが重要です。例えば、都市再生機構(UR)は高層住宅を中心とした大規模開発を多く手がけている可能性があり、そのため、第1種住専地域に多くの開発実績を持つ可能性があります。一方、神奈川県住宅供給公社は、中層住宅を主体とした比較的規模の小さい住宅団地開発に多く携わっている可能性があり、第2種住専地域への開発実績が多いかもしれません。 それぞれの事業主体が、用途地域の特性をどのように開発戦略に反映させているのかを分析することで、横浜市における住宅政策の現状と課題を明らかにすることができます。 さらに、民間事業者による開発状況も分析することで、市場メカニズムが用途地域の選択にどのような影響を与えているのかを理解することができます。 これらの分析結果を総合的に評価することで、横浜市におけるより効果的な土地利用計画や、今後の住宅政策の策定に資する知見を得ることが期待されます。
