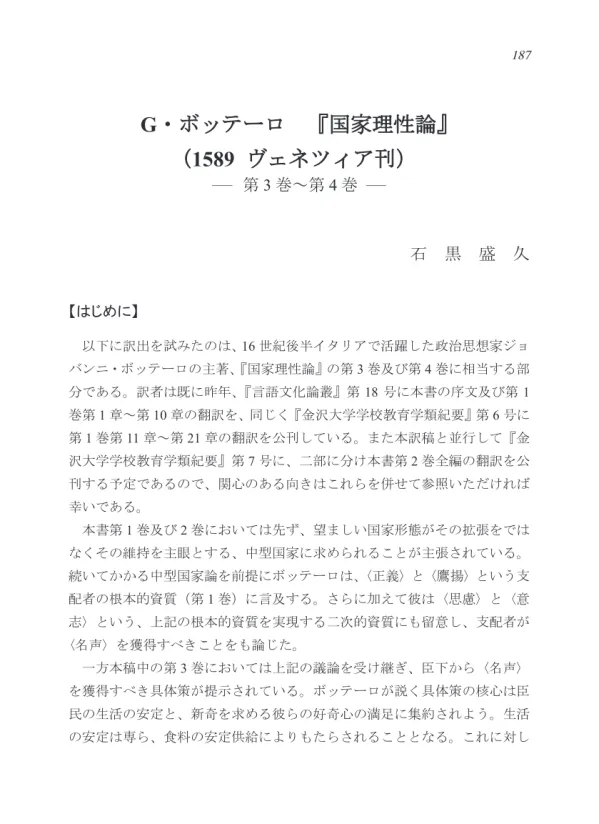
ボッテーロ国家理性論:食糧供給と国家安定
文書情報
| 著者 | Giovanni Bottero |
| instructor/editor | 石黒盛久 |
| school/university | 金沢大学 |
| subject/major | 政治思想史、政治哲学 |
| 文書タイプ | 翻訳論文 |
| city_where_the_document_was_published | ヴェネツィア |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.50 MB |
概要
I.理想的な国家統治 食糧供給 平和 そして 公正
本稿は、効果的な国家統治 (kokka tōchi) のための指針を提示しています。その要諦は、国民の満足度を高めること、そしてそれはまず食糧供給 (shokuryō kyūkyō) の安定、平和 (heiwa) の維持、公正 (kōsei) な社会の実現によって達成されると主張しています。古代エジプトにおけるイスラエル人の例や、ローマ帝国における様々な皇帝の政策(ヴェスパシアヌス帝、セヴェルス帝、アウレリアヌス帝など)は、食糧供給の重要性を裏付ける歴史的証拠として挙げられています。人民 (jimin) の満足を確保することで、反乱や内戦 (naisen) を防ぎ、安定 (antei) した国家統治を実現できると論じています。
1. 食糧供給の重要性と歴史的例証
本節では、安定した食糧供給 (shokuryō kyūkyō) が国家統治の基盤であると主張しています。国民は、外敵の侵略や内乱の恐怖がなく、安価で十分な食糧を手に入れられるならば、他の問題を顧みない傾向にあると指摘。古代エジプトにおけるイスラエル人の例が提示され、厳しい奴隷生活にあっても食糧の豊富さゆえに自由を求めなかった事実が強調されています。一方、食糧不足は容易に民衆の不満を招き、反乱の引き金となり得ることも、砂漠でのイスラエル人の行動を通して示唆されています。ローマ帝国においても、権力獲得を目指す者たちは、民衆への穀物分配や農業政策の推進を通して支持を得ようとした歴史的事例(カッシウス家、メリウス家、マンリウス家、グラックス家、カエサルなど)が数多く挙げられています。ヴェスパシアヌス帝やセヴェルス帝の食糧政策への注力、アウレリアヌス帝による計量単位の変更なども、食糧供給の重要性を裏付ける具体的な事例として提示されています。これらの歴史的事実を通して、安定した食糧供給が、国家の平和と安定を維持するために不可欠な要素であると結論付けています。
2. 平和と公正 国家安定のための不可欠な条件
食糧供給に加え、平和 (heiwa) と公正 (kōsei) が、国民の満足度を高め、国家の安定 (antei) を維持する上で不可欠な要素として論じられています。敵国の侵略や内乱といった不安定な状況下では、たとえ食糧が豊富にあっても、国民の幸福は保証されません。そのため、豊富な食糧供給は、平和と正義という条件を伴わなければ意味がないと強調されています。さらに、民衆は本質的に変化を好むため、君主は様々な手段を用いて民衆の機嫌を取り、国家への不満を抑制する必要があると述べられています。 ナポリなどの地で発生した事件が例として挙げられ、生活困窮や食糧不足が、民衆の怒りと反乱を招く危険性を示しています。つまり、効果的な国家統治 (kokka tōchi) は、食糧、平和、公正という三要素のバランスの上に成り立つものであると結論づけています。 ローマ市民の幸福を最優先に考えた君主の姿勢と、食糧不足による民衆の反発が、平和と公正が国家安定にどれほど重要かを如実に示しています。
II.国民の 安定 維持のための 娯楽 と 公共事業
国民の安定 (antei) を維持するためには、娯楽 (goraku) の提供と大規模な公共事業 (kōkyū jigyō) が有効であるとされています。ギリシャの祭典とローマの娯楽の比較を通して、国民の心身を活性化させる質の高い娯楽の重要性が強調されています。また、ペリクレスによるアクロポリス建設、プトレマイオスによるアレクサンドリア灯台建設、クラウディウスとトラヤヌスによるオスティア港の建設など、歴史上の公共事業の例が挙げられ、国家統治におけるこれらの有効性が示されています。ただし、費用対効果と国民への負担軽減のバランスが重要であると注意深く述べられています。
1. 娯楽の役割 ギリシャとローマの比較
国民の安定 (antei) を維持する上で、適切な娯楽 (goraku) の提供が重要であると論じられています。ギリシャとローマの祝祭を比較することで、娯楽の質の違いが強調されています。ギリシャのオリンピアやネメアの祭典は、心身ともに活性化させる効果があった一方、ローマのアポロン祝祭や剣闘士競技などは、単なる娯楽に留まり、国民の活性化には繋がらなかったとされています。アウグストゥス帝は、国民の娯楽として剣闘士競技などを開催しましたが、その危険性から、より安全で適切な娯楽の導入が必要であると示唆しています。トルコのスルタン・バヤジッドの弟ジェムの言葉が引用され、危険を伴う娯楽は国民の残忍性を助長する可能性があり、社会の安定を脅かす危険性があると警告しています。ホノリウス帝による剣闘士競技の廃止も、その危険性を示す事例として挙げられています。つまり、国民の安定を維持するには、心身を活性化させ、かつ安全で健全な娯楽の提供が重要であると結論づけています。
2. 公共事業の重要性と歴史的例証
国民の安定 (antei) 維持のためには、公共事業 (kōkyū jigyō) が有効な手段として提示されています。公共事業は、君主の権威を示し、国民生活の向上にも繋がるため、市民的な性格を持つ行為だと説明されています。ペリクレスによるアクロポリス神殿前門、プトレマイオスによるファロスの灯台、クラウディウスとトラヤヌスによるオスティア港の拡張、水道橋や道路建設(エミリア街道、アッピア街道、カッシア街道など)、ミラノの運河など、歴史上の様々な公共事業の例が挙げられています。アラゴン王アルフォンソ1世による巨大な艦船の建造や、ディメトリオスによる攻城兵器の発明も、公共事業の一種として位置づけられています。しかし、公共事業は有用であること、そして国民への過度な負担を避けることが重要だと注意喚起されています。エジプト王による過剰な建築事業が、国民への負担を増大させ、かえって安定を損ねた例が反面教師として示されています。セミラミスによる巨大な彫像や、ソロモン王の宮殿・保養山荘なども、費用対効果が低かった例として批判的に言及されています。これらの歴史的事例を通して、効果的な公共事業は、国民の利益と安定に直結するものでなければならず、その計画と実行には慎重さが求められると結論づけられています。
III.戦争と 国家統治 君主の役割と 外交
国家統治 (kokka tōchi) における戦争の役割と君主の関与について論じています。君主が自ら戦場に出るべきか否かは、君主の能力と状況によって異なるとしています。ユスティニアヌス帝やシャルル6世の例は、優れた将軍を指揮することで勝利を収めたケースとして挙げられています。また、スペインとフランスの対照的な例を用いて、外交 (gaikō) と国内政策のバランスの重要性を説いています。遠征軍の派遣は国民の不満の解消にも繋がり、国内の安定 (antei) を維持する効果があると述べられています。
1. 君主の戦争参加 能力と状況による判断
この節では、国家統治 (kokka tōchi) における君主の戦争への参加について、その是非を古今東西の歴史的例証に基づいて論じています。君主が優れた軍事的能力と判断力、そして幸運に恵まれている場合は、自ら率先して戦場に向かうべきだと主張しています。しかし、それらの資質に欠ける君主は、かえって軍の指揮を混乱させ、作戦の失敗を招く可能性があるため、優秀な将軍に指揮を委ねるべきだと説いています。ユスティニアヌス帝がコンスタンティノープルにとどまりながら、ベリサリオスやナルセスといった優秀な将軍を指揮し、ゴート人、ヴァンダル人、ペルシア人を撃退した例が挙げられています。同様に、シャルル6世もブリュージュにとどまりながら傭兵隊長を駆使してイギリス人をフランスから追放した事例も、君主が直接軍事に関与しない成功例として提示されています。つまり、君主の戦争への関与は、君主自身の能力と状況判断に依存する必要があると結論づけています。 優秀な将軍の指揮の下、君主は政治・行政に専念することで、より効果的な国家統治が実現すると主張しています。
2. 外交と内政 スペインとフランスの対比
スペインとフランスの対照的な状況を通して、外交 (gaikō) と内政のバランスの重要性が強調されています。スペインは海外での戦争(インド、低地諸国、トルコ、モーロ人との戦いなど)に積極的に関与することで、国内の安定 (antei) を保っていました。国民の関心が海外に向けられることで、国内の反乱や紛争が抑制されていたのです。一方、フランスは対外的には平和を維持しながらも、国内でカルヴァン派や新福音派といった宗教勢力による内戦に苦しんでいました。この対比を通して、国外での戦争が、国内の安定に貢献する可能性がある一方、内戦は国家の安定を著しく脅かす危険性を孕んでいることが示されています。 アテネのキモンが国内の若者の不満を解消するために、ペルシア遠征軍を派遣した例も、同様の戦略を示す歴史的証拠として提示されています。 つまり、効果的な国家統治 (kokka tōchi) には、適切な外交政策と、国内問題への対応が不可欠であり、そのバランスが重要であると結論づけています。
3. 戦争における君主の役割 近隣と遠隔地の戦争
戦争の場所が、君主の積極的な関与の必要性に影響を与える点を論じています。近隣諸国との戦争では、君主が自ら戦場に赴くことで、国民の感謝と愛着を増大させ、戦勝による恩恵をより大きく感じさせることができると述べています。スペインの諸王がモーロ人との戦いに親征した例、特にフェルディナンドとイザベラによるグラナダ征服が挙げられています。しかし、戦争が遠く離れた場所で行われる場合は、君主の直接的な関与は必ずしも必要ではないと主張しています。その代わり、君主は的確な判断、助言、監視、そして能力によって、国家の安定 (antei) を維持するべきだとされています。 カール・マルテルがキリデリク王の無策の間にフランスを蛮族から防衛し、その功績によりヒピンが容易に王位を継承した事例は、君主の無能と有能な臣下の対比として示されています。この節は、国家統治 (kokka tōchi) における君主の役割は、戦争の規模や場所、そして君主自身の能力によって柔軟に変化させるべきであることを示唆しています。 国民は世俗的な防衛者だけでなく、精神的なもの、宗教の維持者にも恩義を感じることから、君主の役割は多岐に渡ることが強調されています。
IV.社会階層と 安定 富裕層 貧民 そして 中間層 の統治
社会には富裕層 (fuyū-sō)、貧民 (hinmin)、そして中間層の三つの階層が存在し、中間層が最も統治しやすいと指摘されています。富裕層の悪行と貧民の不安定さを抑制し、安定 (antei) した社会を築くための政策の必要性が強調されています。ソロモン王の例やプラトンのキュレネ人への対応を通して、富と貧困のバランスの重要性が示唆されています。マキアヴェッリとの比較も交えながら、貧民の統治が国家統治の要諦であると主張しています。
1. 社会階層の分類と統治の難しさ
この節では、社会を富裕層 (fuyū-sō)、貧民 (hinmin)、そしてその中間に位置する中間層の三つの階層に分類し、それぞれの統治の難しさについて論じています。中間層は比較的温和で統治しやすい一方、富裕層と貧民は統治が難しいとされています。富裕層は富のゆえに腐敗しやすく、貧民は貧困ゆえに不正に手を染めやすいと指摘。ソロモン王が神に過剰な富と極度の貧困を避けるよう祈った逸話が、この点を裏付ける事例として挙げられています。また、富裕で家柄の良い者たちは、高い教育水準とプライドから、容易に支配下に従わない傾向にあると説明されています。逆に、貧民は道徳的な規範に従うことも、逸脱することも容易であるため、統治が困難であると分析されています。富裕層は幸福を浪費し、貧民は法律の下では生きられないという対比も提示され、それぞれの階層に対する統治の難しさが強調されています。マキアヴェッリの社会論との比較も触れられており、特に貧民層の統治に焦点を当てた本書の独自性が示唆されています。
2. 富と貧困のバランス 国家安定への影響
プラトンがキュレネ人の求めに応じて法を与えなかったエピソードが、富裕層 (fuyū-sō) の統治の難しさを示す例として提示されています。既に幸福を享受している富裕層に法を適用することは困難であり、彼ら自身の自制心による統治が理想的であると示唆しています。一方で、貧民 (hinmin) は法律の下でしか生きられない存在であり、貧民の統治には、法律の整備と執行が不可欠であると強調されています。 ソロンや中国の法律、エジプト王アマシスの政策、アテネのアレオパゴス会議の事例などが、貧民の統治、特に労働の確保と怠惰の抑制に関する様々なアプローチを示す例として挙げられています。これらの事例を通して、富裕層と貧民の双方に対する適切な統治が、国家の安定 (antei) を維持するために不可欠であると結論付けられています。 マキアヴェリの二元論的な社会観と対比的に、本書では中間層を含む三層構造に基づいたより現実的な社会観が示され、国家安定のための社会統治のあり方が議論されています。
V.王位継承と 国家安定 内戦 回避のための戦略
王位継承問題と内戦 (naisen) の発生について論じています。トルコのスルタンによる兄弟殺害などの残虐な事例を挙げ、その危険性を指摘しています。中国やエチオピアの王室の慣習を比較することで、王位継承問題への様々なアプローチを示し、国家安定 (kokka antei) を維持するための賢明な政策の必要性を訴えています。安定 (antei) した**国家統治 (kokka tōchi)**のためには、正義と熟慮に基づいた政策と、正当な継承者による統治が不可欠であると結論付けています。
1. 王位継承問題と内戦の危険性
この節では、王位継承を巡る問題が、内戦 (naisen) を引き起こす大きな要因であると指摘しています。 特に、トルコのオスマン帝国のスルタンたちが、帝位継承のために兄弟や親族を殺害した数々の残虐な事例が挙げられています。 現在のムラト3世ですら、妊娠中の父帝の愛妾を殺害したと記述されています。 ホルムズの君主たちが、ポルトガルによる征服以前、王位継承者となる可能性のある親族の目を潰していたことも、同様の事例として挙げられています。 これに対し、中国やエチオピアでは、王位継承の可能性のある親族を特定の場所に幽閉することで、内戦を回避しようとする習慣があったと説明されています。 中国ではアマラ山、エチオピアではアマラ山と呼ばれる場所が、親族の幽閉場所として用いられていたと記述されています。 しかし、これらの方法も、必ずしも内戦の発生を防ぐ効果があったとは限らないとされており、中国では王の殺害や残虐な僭主の出現、エチオピアでもアプディメレクがアラビアから呼び戻されて女王になったという事例が挙げられています。これらの歴史的例証から、王位継承問題の適切な解決が、国家安定 (kokka antei) にとって非常に重要であることが強調されています。
2. 異なる王位継承システムの比較 オスマン帝国とキリスト教諸国
オスマン帝国とキリスト教諸国における王位継承システムの違いが、内戦 (naisen) の発生頻度に影響を与えていると分析されています。オスマン帝国のスルタンたちは、王位を継承した者が、他の親族を殺害するという慣習がありました。セリム1世が多くの兄弟、親族を殺害した事例や、バヤジッド2世とその息子ジェム、セリム2世とその兄弟バヤジッドの間の争い、そしてバジャジッドがペルシア王タマスによって殺害された事例などが挙げられています。これらから、オスマン帝国における内戦の頻発は、王位継承者による殺害という慣習に起因すると結論付けられています。一方、スペイン、ポルトガル、フランス、ドイツなどのキリスト教諸国では、王位継承に複数の候補者が存在するにもかかわらず、内戦が比較的少ないとされています。これは、これらの国々では、王位継承者以外の人物に、騒乱を引き起こしたり武器を取らせたりするような動機が少ないため、野心をうまく制御することが可能となっているためだと推測されています。 しかし、幽閉された王族が、反乱によって王位に就く可能性も完全に否定できず、カラブリア公の事例が挙げられています。 これらの対比を通して、王位継承に関する政策が、国家の安定 (antei) に大きな影響を与えることが示されています。
3. 王位継承と国家の 安定 正義と熟慮による統治
この節では、正当な継承権を持つ君主が、国家の安定 (kokka no antei) を維持するための唯一の方法は、正義と熟慮であると結論付けています。 血縁者による王位継承の重要性も強調されており、繁栄を分かち合うことができる血縁者がいない王国は、幸福とは言えないと述べられています。 トルコのサルタンたちが兄弟を殺害した結果、内戦が頻発し、帝国の衰弱につながるという予測も示されています。 これに対し、マルクス・アントニヌス帝が兄弟を共同皇帝に任命したり、グラティアヌス帝がテオドシウスを共同皇帝とした例は、対照的な事例として挙げられています。 しかし、兄弟皇帝間の不和も指摘されており、血縁者による王位継承が必ずしも安定を保証するものではないことが示唆されています。 ムラト3世の例のように、多くの子供を持つスルタンにおいて、継承争いが避けられないことを指摘し、将来的なオスマン帝国の崩壊を予言しています。 最終的には、正義と熟慮に基づいた王位継承と統治が、国家安定の要諦であると結論づけています。
VI.官僚機構と権力 安定 のための制度設計
権力者の腐敗や専制を防ぎ、国家の安定 (kokka no antei) を維持するための官僚機構のあり方について議論しています。終身職の官職の危険性を指摘し、その権限を制限する必要性を強調しています。フランスの大元帥やスペインの大法官などの例を挙げ、権力の分散と任期制限の重要性を説いています。アリストテレスの思想を引き合いに出し、権力の集中を防ぎ、バランスのとれた国家統治 (kokka tōchi) を目指すべきだと論じています。
1. 権力の集中と官僚機構の危険性
この節では、過剰な権力を持つ官僚機構が、国家の安定 (antei) を脅かす危険性について論じています。 至上権に近い司法権や行政権を持つ官職は、設置しない方が望ましいと主張。 命令を下すことの快楽が、官僚の誠実さや公正さを損なう可能性があると指摘しています。 もし既にそのような強力な官職が存在する場合は、その権力者を秘密裏に抑制する必要があると述べられています。 フランスの大元帥や、スペインのサン・ジャコモ・ダルカンテラ、カラトラバの大法官などの例が、この問題の具体例として挙げられています。 これらの官職を完全に抑制できない場合は、権限の縮小、特に任期の短縮を通して権力を弱体化させるべきだと提案しています。 長期にわたる権力は、当初の制約を忘れさせ、官僚に本来の任務を超えた行動を促す可能性があるためです。 キリスト教諸国において、大元帥、大提督、元帥職などが終身職である現状を批判的に捉え、フランスにおける諸王族への終身的な州総督職の授与も問題視しています。 これらの事例を通して、強力な官職の権限と任期を適切に制限することが、国家の安定維持に重要であると結論づけています。
2. 権力バランスと人材登用 アリストテレスの思想と対策
アリストテレスの思想を引き合いに出しながら、権力と富の集中を防ぐことの重要性が論じられています。 権威と富裕において、特定の人物が突出することを防ぐことで、国家は維持されるとアリストテレスは考えていたと説明されています。 しかし、栄華を享受しながらも節制を保つ人物は稀であるため、対策が必要だと述べられています。 その対策として、まず第一に、尊大で厚顔な人物を重要な地位に任命しないことを提案。 そのような人物は常に新しい企みを好み、権力と結びついた厚顔さは制御困難であるためです。 狡猾で陰険な人物に対しても、同様に警戒する必要性を強調し、そのような人物は、君主を巧みに操り、自身の利益を追求する危険性があると警告しています。 また、アリストテレスの思想と同様の観点から、陶片追放の導入が、個人の権力集中を防ぐ手段として有効であったと述べられています。つまり、国家の安定 (antei) を維持するためには、権力者の選定と配置に細心の注意を払い、権力バランスを保つことが不可欠であると結論づけています。
3. 官僚の任期と権限 終身職の弊害と代替案
この節では、終身職の官僚がもたらす危険性と、その対策について考察しています。 特に、フランスにおける大元帥や大提督といった終身職の官職を例に挙げ、その権力と任期の長期化が、国家の安定 (antei) を脅かす可能性を指摘しています。 終身職の官僚は、当初の職務の制約を忘れ、自身の権力行使を優先する傾向があるためです。 この問題に対する解決策として、終身職ではない知事や将軍、城代といった官僚に加え、実権を持たない終身職の顧問官を置くことを提案しています。 顧問官は、変化の激しい情勢の中、国家運営に一定の安定性をもたらす役割を果たすためです。 君主と顧問官による会議で、戦争や平和、行政、軍事などに関する重要事項を審議することで、より健全な国家統治 (kokka tōchi) が実現できると主張しています。 ティベリウス帝やアントニウス・ピウス帝の例が、有能な官僚を長期にわたって任用した成功例として紹介されています。 これらの事例から、官僚機構の適切な設計と人材配置が、国家の安定と国家統治に不可欠であることが結論付けられています。
VII. 貧民 対策と社会 安定 追放と雇用創出
社会安定 (shakai antei) を脅かす貧民 (hinmin) 対策として、追放と雇用創出の二つの手段を提示しています。スパルタ、ヴェネツィア、そしてスペインにおける歴史的例を挙げ、それぞれのメリット・デメリットを分析しています。また、エジプト、アテネ、そして中国の政策を比較検討することで、国民の雇用と生産性を向上させる政策の重要性を強調しています。貧民対策は、社会安定と国家統治 (kokka tōchi) の維持に不可欠であると結論付けています。
1. 貧民の危険性と歴史的教訓
この節では、貧困層(貧民 (hinmin))が社会の安定 (antei) に対して重大な脅威となる可能性を論じています。 貧しい生活を送る人々は、失うものが少ないため、容易に反乱やクーデターといった危険な行動に走ると指摘。 リウィウスの記述を引用し、ペルセウス王とローマの戦争において、貧しい人々は社会の変革を望んでペルセウス側に、富裕層は現状維持を望んでローマ側に付いたという事例を挙げています。 カティリナがローマ共和政を混乱させたのも、自身の貧困と不満が原因の一つであったと述べられています。 これらの歴史的事例を通して、貧民の不満は、社会不安や国家崩壊に繋がりかねない危険性を孕んでいると強調されています。 したがって、貧民対策は、社会の安定を維持するために不可欠な要素であると結論づけています。 ローマ共和国崩壊の一因となったカティリナの反乱は、貧民対策の重要性を示す、重要な歴史的教訓と言えます。
2. 貧民対策 追放と雇用創出の二つの戦略
社会の安定 (antei) を脅かす貧民 (hinmin) を制御するための二つの戦略、すなわち追放と雇用創出が提示されています。 追放に関しては、スパルタがパルテニア人を植民地に送り出した例、ヴェネツィアがキプロス戦争に参加したならず者を戦争に派遣した例、フェルディナンド王がジプシーをまとめて追放した例などが挙げられています。 これらの事例から、貧民の追放は、社会不安の抑制に有効な手段となる可能性があることが示唆されています。 しかし、同時に、貧民を社会に統合し、彼らの生活を安定させるための対策も必要だと主張されています。 そのため、農業や工芸などの活動を通して、貧民に生計を立てる手段を提供することが重要だとされています。 エジプト王アマシスによる職業申告制度、アテネのアレオパゴス会議員による怠け者への罰則、ソロンの法律、そして中国の法律などが、貧民の就労を促す様々な政策の例として挙げられています。 これらの政策によって、技術の向上と職業の継承が促進され、失業者や怠け者が減ることで社会安定が図られると結論づけています。 黄帝による中国の技術発展や、古代ローマにおける不動産所有の促進も、貧民対策の成功例として示唆されています。
