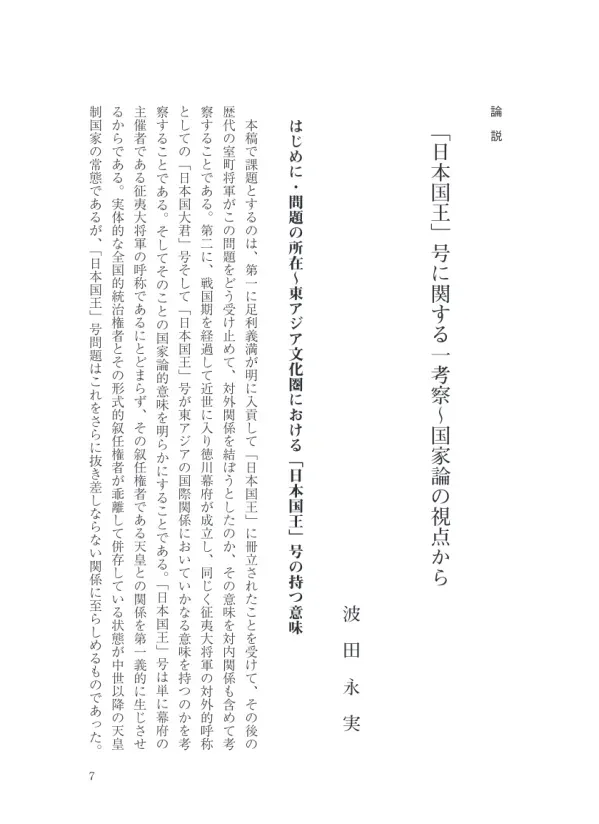
「 日 本 国 王 」 号 に 関 す る 一 考 察 〜 国 家 論 の 視 点 か ら
文書情報
| 学校 | 〇〇大学 (具体的な大学名は不明のため仮置き) |
| 専攻 | 政治学、国際関係学、歴史学など (具体的な専攻は不明のため複数候補) |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論文、研究発表資料など (具体的な種類は不明) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.21 MB |
概要
I.室町時代の 日本国王 号 華夷秩序と足利義満
本稿は、室町時代の足利義満が明から「日本国王」に冊封された事実に焦点を当て、その意味を国家論の視点から考察する。義満の日本国王号受領は、華夷秩序の枠組みの中で、国内政治(皇位簒奪計画との関連性など)と外交政策(日明関係の構築)の両面から分析される。今谷明氏らの説を紹介しつつ、日本国王号の国内における受容と、その政治的影響を検討する。特に、日本国王号が国内で積極的・公的に用いられたか否か、天皇との関係、そして征夷大将軍としての権力との関連性を考察する点が重要である。
1. 足利義満の 日本国王 冊封と皇位簒奪計画
足利義満が明から「日本国王源道義」として冊封された事実は、従来日明貿易の利益独占のためと考えられていた。しかし、今谷明『室町の王権』は、この冊封を義満の皇位簒奪計画の一環と主張する。義満は征夷大将軍として権力を掌握し、太政大臣、准三后と昇進、廷臣を家臣のように扱い、天皇の祭祀権まで掌握しようとした。さらに、妻を天皇の准母とし、次子を親王に準じて元服させ、天皇の准父として義嗣の即位を図り、自らが治天の君となる一歩手前まで行ったが、急死により計画は頓挫したとされる。この皇位簒奪計画において、国際的に『国王』と認知されることが、簒奪の正当性を担保する唯一の方法であったと今谷氏は分析している。天皇を否定した場合、国内に義満の権威を保障する存在は皆無となるため、明からの冊封が極めて重要だったと推測できる。
2. 日本国王 号の国内的受容と批判
しかし、義満自身は『日本国王』号を国内で積極的に用いたり、明からの冊封事実を喧伝したりした形跡はないと指摘する研究者もいる。冊封儀礼も、義満の昵懇の公家衆や僧侶のみが参加する閉鎖的なものであった。これは、義満が明国皇帝の「臣」となることを意味する日本国王号を、国内、特に朝廷に対しては公的に用いることを避けていた可能性を示唆している。当時、廷臣、幕臣、五山禅僧などから種々の批判があったことはよく知られている。日本国王号の受容は、国内における天皇との関係、征夷大将軍としての権力、そして華夷秩序における日本の位置づけといった複雑な要素が絡み合っていたと考えられる。義満の意図、そして日本国王号の国内における真の意味を理解するには、これらの要素を総合的に分析する必要がある。
3. 後世における 日本国王 号の解釈と国家論的考察
義満以降の足利将軍家には皇位簒奪の意志はなく、公的に「日本国王」号を国内で使用することは考えられない。これは、日本国王=天皇、執政=覇者=将軍という図式が成立することを意味する。室町前期に「将軍=日本国王」という図式を描いたのは誰かという点が問題となる。橋本氏は、義満の明向け外交文書が公家(廷臣)によるものだったこと、国内史料では国王=天皇であることが明らかな点を指摘し、義満は国内向けに『日本国王』号の使用を避けていた可能性が高いと主張する。五山禅林、特に夢窓派勢力だけが、義満による身分制の超克を期待していたと考えられる。この分析は、室町幕府の権勢を評価する際に、五山側の史料に偏りすぎている可能性を指摘している点で重要である。日本国王号をめぐる議論は、華夷秩序という国際関係の枠組みと、天皇と将軍という国内政治構造の複雑な相互作用を示している。
II.室町幕府と 日本国王 号 国内的意味と国際的認識のずれ
足利義満以降の将軍による日本国王号の使用は、対外的な外交儀礼における便宜的なものだった可能性が高い。今谷明氏と橋本雄氏の見解の相違点を踏まえつつ、室町幕府における日本国王号の国内的意味合いと、明からの冊封という国際的認識とのずれを分析する。満済准后記などの史料を用い、日本国王号が天皇の権威とどう関連づけられていたか、また幕府内部や朝廷における受け止め方を検討する。
1. 室町期将軍の 日本国王 号 対内的使用の限定性
足利義満以降の室町幕府将軍による「日本国王」号の扱いは、義満の時代とは異なっていた可能性が高い。本文では、義満の「日本国王」号受領は、明との外交における便宜的な側面が強かったとする見解が示されている。特に、『満斎准后記』の記述を引用し、将軍の「日本国王」号は明側がそう認識しているに過ぎず、国内、特に朝廷に対しては公的に使用されることを前提としていなかった可能性が指摘されている。これは、義満以降の将軍家が皇位簒奪を企図していなかったという事実とも整合性を持つ。つまり、室町時代の「日本国王」号は、国際的な外交上の称号として用いられた一方で、国内政治においては、天皇の権威を脅かすことなく、将軍の権威を明確に示すものではなかった可能性が高い。
2. 日本国王 号をめぐる今谷明氏と橋本雄氏の見解の相違
今谷明氏は、義満の「日本国王」号受領を皇位簒奪計画の一部と解釈する一方、橋本雄氏は、義満自身は国内で積極的に「日本国王」号を用いなかったと主張する。両者の見解の相違は、義満の政治的意図と「日本国王」号の国内における役割理解の違いに起因する。橋本氏は、義満の明への外交文書が公家による作成であった点や、国内史料における「国王=天皇」という認識を根拠に、義満が国内向けに「日本国王」号の使用を避けていたと推測する。この相違点は、「日本国王」号の国際的認識と国内的受容のずれを理解する上で重要な論点となる。つまり、国際的には「日本国王」として認められていたものの、国内では天皇の権威との関係から、その称号は限定的な使用にとどまった可能性が示唆される。
3. 室町前期における 将軍 日本国王 図式の成立と五山禅林の影響
もし室町前期に「将軍=日本国王」という図式が存在したとすれば、誰がそれを描いたのかが重要な問いとなる。橋本氏は、義満の外交文書が公家によって作成され、国内史料では国王=天皇であることが明白である点を指摘し、義満は国内、特に朝廷に対しては「日本国王」号の使用を避けていたと主張する。一方、義満による身分制の超克を期待していたのは、五山禅林、特に夢窓派勢力であった可能性が高い。足利将軍家が五山夢窓派の大檀越であった点を考慮すると、この関係は必然的なものだったと言える。この分析は、室町幕府の権勢を評価する際に、五山側の史料に偏りすぎている可能性を指摘するものであり、「日本国王」号の国内的受容を理解する上で、五山禅林という宗教勢力の影響を考慮する必要性を示している。
III.戦国末期における 日本国王 号 外交戦略と中央政権回復への志向
応仁の乱以降、衰微した室町幕府においても、最後の将軍義昭は日本国王号に執着した。これは、朝鮮との関係を通じて明との国交回復を図り、日本国王として中央政権に復帰しようとする外交戦略の一環と考えられる。日本国王号が、戦国時代における政治的・外交的な権威主張の手段としてどのように機能していたのかを考察する。
1. 戦国末期の室町将軍と 日本国王 号の衰微
応仁の乱以降、室町幕府は衰微し、将軍は全国支配の実態を持たないまま「日本国王」を自称するにとどまっていた。明からの冊封もなく、単なる外交上の呼称として用いられていたと言える。しかし、最後の将軍である足利義昭は、織田信長によって京都を追われ、毛利氏を頼って備後鞆の津に亡命した後も、「日本国王」号に固執した。これは、室町幕府の権威の象徴としての「日本国王」号への執着であり、同時に、その称号を用いることで、失われた権威の回復、すなわち中央政権への復帰を目指す外交戦略の一部であったと推測できる。
2. 義昭と 日本国王 号 朝鮮外交と明との国交回復への期待
義昭の「日本国王」号への執着は、対馬宗氏を仲介とした朝鮮との関係を通じて明との国交を回復し、再び中央政権に返り咲こうとする外交戦略に繋がる。既に室町幕府は衰退しており、全国的な支配力は失われていたが、「日本国王」という称号は、国際的な舞台で一定の政治的影響力を行使するための、重要な外交カードとして認識されていた可能性がある。このことは、戦国時代末期においても、「日本国王」号が、国内政治の混乱の中でも、外交戦略、特に朝鮮・明との関係において重要な意味を持っていたことを示唆している。義昭の行動は、権力奪回を目指す政治的思惑と、国際的な承認を得ようとする外交的思惑が複雑に絡み合ったものである。
IV.白石の歴史認識と国家構想 義満批判と独自の国家観
新井白石の国家論における足利義満への批判と、独自の国家観を分析する。白石は、日本国王号の使用を批判的に捉え、天皇と征夷大将軍(または将軍)の役割分担、そして華夷秩序における日本の位置付けについて独自の解釈を示している。彼の歴史認識、特に義満の政策や室町幕府の政治体制に対する評価が、日本国王号に関する彼の見解にどのように影響しているかを検討する。白石のヨーロッパ諸国の王侯制度に関する理解と、それを日本における天皇と将軍の関係に当てはめる試みも重要な考察対象となる。
1. 新井白石による足利義満批判と 日本国王 号
この節では、新井白石による足利義満とその時代の「日本国王」号に対する批判的な見解が中心的に論じられている。白石は、義満を「驕恣の主」と見なし、その専制的な政治が天下の乱れの原因の一つだと批判している。これは、白石が理想とする徳治政治、特に家宣時代の正徳の治という政治理念と対比されている。白石は、義満の時代を、天下の財が尽き、民が窮乏し、大名が貧しくなることで混乱が生じた時代として捉えている。これは、綱吉時代の元禄時代の否定的な評価と関連づけられ、家宣による理想的な統治への模索と捉えることができる。義満の「日本国王」号受領についても、この批判的な視点を基に、その政治的影響や妥当性を再検討していると考えられる。
2. 白石の国家観と天皇 将軍の役割分担
白石は、独自の国家観に基づいて天皇と将軍の役割を明確に区別している。天皇を春秋時代の周王のように名目上の主権者、将軍を覇者=天下成敗権を行使する実質的な支配者と見なしている。この国家観は、『藩翰譜』の「天命が革まった」という記述にも反映されており、『読史余論』における源義家の置文の解釈にも見られる。「執柄の家」(藤原摂関家)の権力を奪い、自らの後継者に与えるという解釈は、白石の国家観を理解する上で重要である。さらに、白石は家康を「伯」すなわち覇者と位置づけ、天皇を名目上の支配者とする独自の秩序観を示している。この秩序観に基づいて、白石は対外関係において「日本国王」号の称号を将軍が用いることを正当化しようとしていると考えられる。
3. 白石のヨーロッパ理解と国家秩序への適用
白石は、ヨーロッパ諸国の王侯の位階・称号を比較的正確に理解していた。西欧の知識を、既知の中国の国家的位階秩序を援用しながら理解しようとする試みが見られる。フレンス(公爵)やホルスト(諸侯)を軍事指揮官のように理解するなど、現代の視点からは不十分な点もあるものの、ローマ法王、皇帝、王、公爵、諸侯、総督といった秩序立てた認識を示している。このヨーロッパにおける宗教的権威と世俗権力の関係を、日本に当てはめる際に、天皇を宗教的権威(教化を興すことを主る者)と見なし、将軍を国王またはそれに相当する地位に位置付けることで、征夷大将軍を「王」と認識することを論理的に正当化しようとしていると解釈できる。これは、白石独自の国家観と密接に関連している。
4. 白石の 天命 解釈と家康の評価
白石の秩序観において重要なのは、「天命が革まった」という認識である。これは、『読史余論』における源義家の置文の解釈や、家康への評価と関連している。『難太平記』の「我七代の子孫に生れ代わりて天下を取ルべし」という記述を、藤原摂関家の権力を奪い、武家による支配への移行と解釈する。そして、家康を後漢の光武帝や宋の太祖を凌駕する「伯」(覇者)と位置付ける。これは、天皇を実権を持たない名目上の主権者、将軍を天下成敗権を行使する実質的支配者とする白石の国家観を裏付けるものとなる。この家康への評価は、白石が家康を「我神祖受命」と見なす歴史認識と深く結びついている。つまり、白石は、家康の支配を天命による正当なものと捉え、その政治体制を正当化しようとしていたと考えられる。
