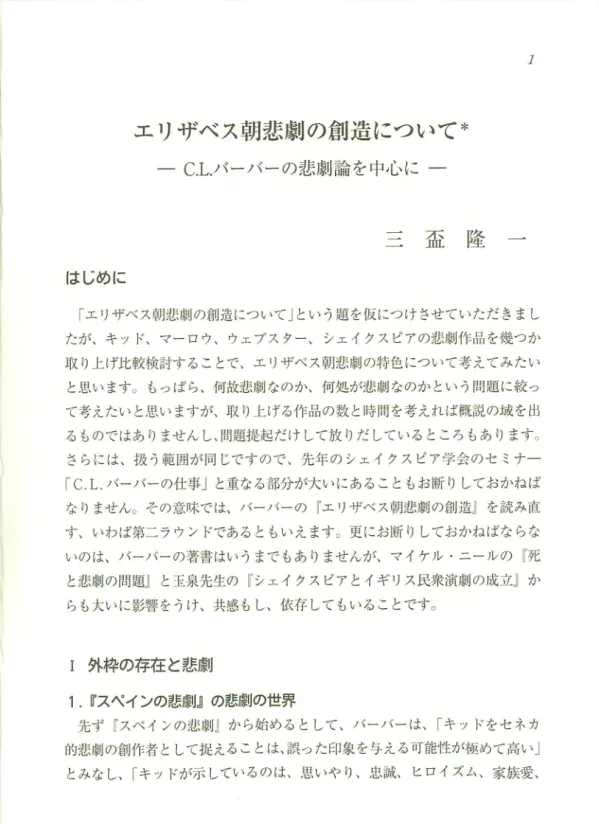
エリザベス朝悲劇:バーバー論を中心に
文書情報
| 著者 | 三盃 隆 |
| 専攻 | 英国文学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 12.64 MB |
概要
I.1 スペインの悲劇 英雄的虚無主義 と 悲劇 の定義
本稿は、キッドの『スペインの悲劇』をエリザベス朝悲劇の観点から分析します。C.L. バーバーの解釈を踏まえ、主人公ヒエロニモの復讐劇を考察。正義の喪失、冥界の決定への無知、そして主人公の苦悩が、現代的な意味での社会的抗議とは異なる、虚無主義的な世界観を創出している点を指摘。悲劇とは何かを問い直し、スタイナーとシューウォールの『ヨブ記』解釈を対比させながら、バーバーの『スペインの悲劇』論を展開します。
1.1 スペインの悲劇 におけるバーバーの解釈と英雄的虚無主義
このセクションでは、C.L. バーバーの『エリザベス朝悲劇の創造』における『スペインの悲劇』の解釈が中心的に議論されています。バーバーは、この劇を単なるセネカ的悲劇の模倣ではなく、独自の「英雄的虚無主義」を体現した作品と捉えています。これは、劇中で正義が暴力的に破壊され、主人公ヒエロニモが復讐という行為を通じて、天上の神にも地上の王にも救済を求めることができない、不条理な世界に突き落とされるという構造に根ざしています。バーバーのこの解釈は、先行研究、特にマイケル・ニールの『死と悲劇の問題』や玉泉先生の『シェイクスピアとイギリス民衆演劇の成立』からの影響も受けていると明記されています。 バーバーの視点を通して、従来の悲劇観とは異なる、ニヒリスティックな世界観が『スペインの悲劇』に存在することを示唆する分析が展開されています。
1.2 ヒエロニモの苦悩と正義の喪失 復讐劇の構造
『スペインの悲劇』の主人公ヒエロニモの苦悩は、息子ホレイショーの殺害という正義の喪失から生じるものです。ヒエロニモは、息子の遺体を埋葬せず、復讐を誓うという行動を通して、劇全体に貫かれる深い絶望と、揺るぎない復讐への執着を表現しています。 テキストでは、ヒエロニモの行動を「入れ子的発想」から解釈する試みが見られます。すなわち、ヒエロニモが息子の遺体を通して正義という象徴に取り組んでいるという見方です。この解釈は、ヒエロニモの苦悩の根底に「社会的・家庭的秩序に対する敬神 の念」と「道徳的な絶望によって生み出される圧迫感」があることを示唆しています。 しかし、この復讐劇の特異性は、ヒエロニモ自身も、冥界の意志によって復讐の成否が決まっていることを知らない点にあります。この無知ゆえに、彼は天上の神、地上の王、そして冥界の王へと、正義の執行を訴えるという皮肉な状況に陥ります。アンドレアの亡霊の苛立ちも、この不条理な状況と深く結びついています。
1.3 ヨブ記 解釈との比較 悲劇の定義を問い直す
このセクションでは、『スペインの悲劇』における悲劇の定義を問い直すために、『ヨブ記』をめぐる二つの対照的な解釈が提示されます。スタイナーは、『悲劇の死』の中で、悲劇はユダヤ的な世界観とは無縁であり、「償いがあるところには、正義はあっても悲劇はない」と主張しています。一方、シューウォルは、『ヨブ記』の中に悲劇の形式的基本要素を見出し、悲劇の深さと広さを異なる視点から論じています。 これらの対照的な解釈を通して、テキストは『スペインの悲劇』における「償い」の有無、そして主人公の無知という要素が、従来の悲劇観にどう関わってくるのかを問いかけています。 バーバーは、ヒエロニモの苦悩を、神託に相当する外枠の決定を知らない状況下での、命がけの正義の実現への取り組みとして捉え、それが意味豊かな苦悩であり、悲劇的アクションであると主張しています。しかし、同時に、主人公にとっての悲劇が、必ずしも観客にとっても悲劇であるとは限らないという複雑な問題提起もなされています。
II.2 ハムレット 死者との対話 と 近代的悲劇
シェイクスピアの『ハムレット』における悲劇性を探ります。C.L. バーバーは『ハムレット』を完成された悲劇ではなく、英雄的かつ予言的な劇と位置づけています。本稿では、亡霊の出自と正体、そしてハムレットと死者との対話に焦点を当て、ヒエロニモとの比較を通して、ハムレットの苦悩がより主体的で近代的な悲劇である点を明らかにします。キルケゴールの解釈も援用し、『ハムレット』の宗教的側面にも触れます。
2.1 バーバーの ハムレット 解釈 完成された悲劇ではない
このセクションでは、C.L. バーバーが『ホール・ジャーニー』で提示した『ハムレット』の解釈が論じられています。バーバーは、『ハムレット』を完全に完成された悲劇とはみなしておらず、「悲劇的な」結末を持つ英雄的で予言的な劇と位置づけています。これは、『タンバレイン大王』と類似した構造を持つとしながらも、伝統への直接的な攻撃ではなく、伝統的遺産の伝達における危機を呈示している点が相違点として挙げられています。 『スペインの悲劇』論と同様に、この解釈も独特で謎めいた表現を含んでおり、その解釈の深淵を探るための分析が試みられています。 特に、亡霊の出自や正体に関する問題が重要視され、「死者との対話」が主題の一つとして強調されています。亡霊の出自が天国か煉獄かで、物語の解釈が大きく変わる可能性も示唆されていますが、プロテスタントの観点から煉獄という概念をどう捉えるかという宗教的な問題点も同時に提示されています。
2.2 死者との対話とハムレットの主体的判断 近代的悲劇の視点
ハムレットの悲劇は、亡霊の正体と冥界の本質を解明するという、極めて主体的で困難な課題に直面することから生じます。この点において、ハムレットの苦悩は、スペインの悲劇のヒエロニモの苦悩とは異質のものであると分析されています。ヒエロニモは、冥界の王と王妃の意志によって既に結末が決まっていることを知らないまま、復讐劇に突き進みますが、ハムレットは自身の判断によって行動を選択する自由を持っています。 そのため、ハムレットの悲劇は、より主体的で、近代的な悲劇として理解できると主張されています。また、劇中劇の使い分けも対比されています。ヒエロニモは劇中劇を復讐の実行の場として用いるのに対し、ハムレットは復讐相手の発見、すなわち認識の場として利用しています。この違いが、二人の苦悩の質の違いを際立たせていると指摘されています。 さらに、ハムレットの苦悩は、より複雑で深刻で屈折していると評されており、その深層心理を探る分析がなされています。
2.3 キルケゴールとバーバーの解釈 宗教と悲劇の融合
このセクションでは、キルケゴールの『ハムレット』解釈が紹介され、バーバーの解釈との関連性が考察されています。キルケゴールは、『ハムレット』を「宗教的な戯曲」と位置づけつつも、同時に「宗教的戯曲になっていない」と指摘しています。これは、ハムレットの行動が、宗教的な英雄の範疇には収まらない複雑さを有していることを示唆しています。 バーバーの「『ハムレット』は完成された悲劇ではない」という見解は、キルケゴールの解釈と共通点を持つと示唆されています。特に、「宗教的な」という表現と「予言的な」という表現の密接な関係性が指摘され、両者の解釈の共通項が探られています。 最終的に、ハムレットの苦悩を通して観客が「憐れみと怖れ」を共有し、「浄化/純化」としてのカタルシスを得るという、観客の感情に焦点を当てた考察でこのセクションは締めくくられています。 ハムレットの「予言的な魂」という発言が、外枠の世界への自覚と信頼の芽生えを示唆している点も重要な論点として挙げられています。
III.3 タンバレイン大王 絶対美 と 暴力 の 英雄的叙事詩
マーロウの『タンバレイン大王』をエリザベス朝悲劇として考察します。プロローグにおけるマーロウの宣言、タンバレインの絶対美への追求、そしてその破滅へと至る過程を分析。バーバーは、タンバレインの行動を英雄的偉業として捉え、ゼノクラテイとの関係に焦点を当てます。シェイクスピアの『アントニーとクレオパトラ』との比較を通して、『タンバレイン大王』の悲劇的構造を解明します。重要な人物として、タンバレインとゼノクラテイを挙げ、暴力と聖なるものの融合というテーマを提示します。
3.1 マーロウの 文学宣言 とエリザベス朝悲劇の誕生
このセクションでは、クリストファー・マーロウの『タンバレイン大王』のプロローグにおける「文学宣言」が、エリザベス朝悲劇の成立において重要な役割を果たした点が論じられています。マーロウは、プロローグで従来の即興劇や聖劇を否定し、新たなルネサンス演劇、特にエリザベス朝悲劇の幕開けを宣言しています。これは、タールトンやケンプといった従来の役者たちの退場をも意味する、演劇界における革命的な宣言であったと指摘されています。 この宣言が持つ破壊的潜在能力は、社会的秩序だけでなく、精神の内的秩序にも脅威を与えるものでした。そのため、この「自由」をいかに制御するかが、エリザベス朝演劇における重要な課題として浮上してきたと分析されています。 従来のキリスト教的宗教劇や道徳劇が、当時の社会の宇宙観や道徳律と調和していたことと対比的に、マーロウの宣言が持つ革新性と、それがもたらす潜在的な危険性が強調されています。 この宣言は、単なる演劇形式の変化にとどまらず、当時の社会構造や思想に深く関わっていたことが示唆されています。
3.2 タンバレインの 絶対美 への追求と悲劇的必然性
『タンバレイン大王』におけるタンバレインの行動は、彼が「絶対美」を追求する過程として捉えられています。第一部だけで悲劇とみなすならば、その根拠は、タンバレインが「聖なる美」と「全能」への執着によって引き起こす危険、無謀さ、冒涜、虚無、絶望にあると分析されています。 第二部は、第一部の人気を受けて書かれたとされていますが、悲劇という観点からは、第一部と第二部の間に深い内的必然性があるとされています。 バーバーの解釈は、グリーンブラットやドリモアといった他の研究者とは異なる点があります。バーバーは、マーロウがタンバレインの行動を計画的かつ徹底的に「英雄的偉業」として提示していること、そしてゼノクラテイとの関係が劇全体の緊張感の中心になっていると解釈しています。 タンバレインの世界征服は、テイムールをモデルとしているものの、実際には西アフリカを中心とした地域であり、単なる拡大ではなく、サマルカンドの建設やゼノクラテイとの合一という中心点を持つとされています。この征服劇の背景には、エリザベス朝イングランドとエリザベス女王の存在を重ねて読むこともできると示唆されています。
3.3 タンバレインの最後と ハムレット との比較 バーバー的解釈
タンバレインの最後の言葉「タンバレインは、神の鞭は死なねばならぬ」は、彼の野望と絶望、そして限界を象徴する言葉として、悲劇的な重みを持つとされています。この言葉に対する様々な解釈が存在する中、テキストでは、この言葉がタンバレインの憧憬、野望、絶望、限界を凝縮した表現であると解釈されています。 また、ハムレットとの類似性や親近性を指摘する点も、バーバー的な解釈の特徴として挙げられています。 ハムレットが父の亡霊の正体と復讐に取り組む一方、比喩的に言えば、聖なるもの、あるいは美の象徴としての母ガートルードにも取り組んでいると解釈されています。 ハムレットの苦悩や母への告発の激しさは、聖なる存在と信じていた母の「性なる」正体の暴露によって生じる葛藤からくるものとされています。 さらに、『アントニーとクレオパトラ』との比較を通して、『タンバレイン大王』とシェイクスピア的悲劇世界の類似点と相違点をより明確に示すことが示唆され、マーロウとシェイクスピアのドラマツルギーの革新がエリザベス朝演劇の隆盛の基盤であったというホーナンの見解も紹介されています。
IV.4 アントニーとクレオパトラ 記念碑 としての 詩 と 愛憎地獄
シェイクスピアの『アントニーとクレオパトラ』は、ローマとエジプトの対立を背景に、アントニーとクレオパトラの破滅的な愛を描いています。ニールの解釈を参考に、クレオパトラの死を儀式的な行為、記念碑-としての-詩として捉えます。バーバー、ニール、ドリモアらの異なる視点から、この劇の悲劇性を多角的に分析し、タンバレイン大王との比較も加えます。重要な人物はアントニーとクレオパトラで、彼らの愛と死をキーワードに悲劇を考察します。
4.1 アントニーとクレオパトラの愛 ローマとエジプトの対立する視点
このセクションでは、シェイクスピアの『アントニーとクレオパトラ』において、アントニーとクレオパトラの愛が、ローマとエジプトという異なる文化的視点から、対照的に評価されている点が論じられています。ローマの観点からは、二人の愛は「度を越す溺愛」、「反自然的」な「肉欲」と捉えられ、アントニーは「娼婦の機嫌を取る道化役」に成り下がっていると評されます。一方、エジプトの視点からは、二人の愛の「度を越している」という点がこそ重要であり、その愛の世界を見極めるためには「必ずや新しい天地を見つけねばならぬ」とされています。 この対照的な評価は、『タンバレイン大王』におけるタンバレインに対する評価の対立と類似性を示唆しています。 テキストでは、この劇の冒頭が、作品のテーマを凝縮して提示している典型例であると指摘され、アントニーとクレオパトラの愛に対する評価の対立が、劇全体の重要なテーマとなっていることを強調しています。 ローマとエジプトの世界観の対立が、劇全体の構造を理解する上で鍵となることが示されています。
4.2 アントニーとクレオパトラの死 シェイクスピア的悲劇の到来
アントニーとクレオパトラの死の場面は、劇全体の大きな転換点となっています。クレオパトラの死を知らされたアントニーは、自害によって彼女と天国で再会することを願います。一方、クレオパトラは、アントニーの死後、彼を賛美し、シーザーを軽蔑する発言を繰り返し、自身の死を「このわびしさからより良い生活が始まる」と肯定的に捉えています。 二人の死の場面は、劇世界を大きく変容させ、典型的なシェイクスピア的悲劇の世界が出現させる契機となっています。 アントニーとクレオパトラの関係は、アクティウムの海戦におけるクレオパトラの裏切りなど、愛憎が複雑に絡み合ったものでした。しかし、クレオパトラの愛は、ゼノクラテイのタンバレインへの愛とは全く異なる、不安や恐怖、裏切り、欺瞞に満ちた、生身の女性の愛であると分析されています。 『アントニーとクレオパトラ』の世界には、タンバレイン的な女性崇拝やゼノクラテイ的な絶対美は存在しないと指摘されています。この劇世界の特異性が、他の作品との比較を通して強調されています。
4.3 ニールによる解釈 記念碑 としての 詩 とクレオパトラの死
このセクションでは、マイケル・ニールの『アントニーとクレオパトラ』解釈が紹介されています。ニールは、クレオパトラの死を、変化の激しい世界から絶対的存在の領域への移行、変化を終わらせる逆説的な変化と捉えています。 クレオパトラにとっての死は、「無上の自己成型的行為」、自身の肉体を「大理石のように円く冷たい彫刻作品」へと変容させる行為であり、過去の時間を作り直し、死を否定する行為であると解釈されています。 この解釈には、人間の肉体を石に変えることが伝統的には死の象徴であるにもかかわらず、クレオパトラはそれを異なる種類の拘束、すなわち無常や死そのものを閉じ込める拘束の記号に作り変えているというパラドックスが含まれていると指摘されています。 ニールは、『アントニーとクレオパトラ』を「記念碑-としての-詩」の観念を具体化した戯曲とみなし、時と死の破壊的力に対する人間の勝利を表すものとしています。 ニールの解釈は、バーバーとは異なるものの、奥深いところで共通点があり、さらに検討が必要であるとされています。また、政治と権力を重視するドリモアの見解との対比も提示されています。
V.5 ファウスト博士 宗教改革 と ルネサンス の狭間で
マーロウの『ファウスト博士』は、宗教改革とルネサンスという時代背景の中で生まれた悲劇です。ファウストの堕落と絶望の過程を、神学博士としての過去(A)、魔術への傾倒(B)、そして救済への希求(C)という三つの段階に分け、バーバーの解釈を参考に、カルヴィニズム的な予定説との関連性や、神に対する不信と正義への執着を分析します。ダンテの影響なども考察。重要なキーワードはdamnation(永遠の罰)、resolution(決意)、repentance(悔悟)、despair(絶望)です。
5.1 ファウストの選択 栄光ある過去からの決別と三つの生き方
このセクションでは、マーロウの『ファウスト博士』におけるファウストの苦悩の根源が分析されています。ファウストは、神学博士としての輝かしい過去(A)を捨て、魔術という道(B)を選びます。この選択が、彼の後の絶望へと繋がる大きな転換点となります。 テキストでは、ファウストのその後の人生を、A(栄光ある過去)、B(魔術を選択したエロス的な人生)、C(神の恩寵を求めるアガペー的な人生)の三つの生き方を通して分析しています。24年間のファウストの人生は、Aを否定してBを選びながらも、Cへの関心を抑えきれない葛藤に満ちたものとして描かれています。 しかし、この三つの生き方は単純な選択ではなく、BとCの間には本質的な対立があり、BとCを両立させることは不可能であると示唆されています。ファウストは、Cへの道(神の恩寵への道)を意識的に回避し、Aを歪曲しながらBを選んだと分析されています。この選択への執着がresolution(決意)、Bの否定とCへの転向がrepentance(悔悟)、そして悔悟できないままBへの執着を深める状態がdespair(絶望)と定義付けられています。
5.2 神の正義と神の愛 ファウストの信仰と絶望
ファウストは、魔術によって永遠の命を求めましたが、最終的にはその「終わりがないこと」への恐怖に直面します。彼は、天に流れるキリストの血潮を目撃し、その半滴でもあれば救われる可能性を認識しますが、キリストの血潮が消えるとすぐに神の怒りに触れるという経験をします。 この神の怒りと神の愛は、神性の両面であり、キリストの十字架は両者の相克の場であるとされていますが、バーバーは、ファウストは神の愛を信じることができず、神の正義だけを信じていると指摘しています。 ファウストの「堕地獄」(damnation)は、信仰の象徴である老人を追放し、ヘレンと神秘的な合一を図ったことで決定づけられると論じられています。 しかし、マーロウがカルヴィン主義的な「予定説」に基づく永罰の自覚をファウストの絶望の基盤としていない点は重要な指摘として挙げられています。ファウストは永遠を求めながら、最終的にその永遠に恐怖し、絶望するのです。
5.3 宗教改革とルネサンス ファウストの物語と初期近代イングランドの歴史
このセクションでは、『ファウスト博士』が、宗教改革とルネサンスがイングランドで同時発生したという事実を明確に示す作品であるとされています。 ファウストの物語は、初期近代イングランドの歴史を反映する鏡のような役割を果たしていると分析されています。 宗教と演劇が不可分な関係にある中で、ファウストの「冒涜」という破壊的な行動は、演劇を通して制御され、均衡が保たれ、悲劇的なアイロニーを生み出していることが指摘されています。 バーバーは、この劇をイギリス最初の偉大な悲劇と位置づけており、その見解が支持されています。 ファウストの行動は、神になることを目指す冒涜ではなく、むしろ冒涜的形式で聖なるものを取り戻そうとする努力と解釈されています。 宗教改革とルネサンスという二つの大きな流れが、この劇の中で複雑に絡み合い、表現されている点が強調されています。
VI.6 マクベス 想像力 が生み出す恐怖と マン の在り方
シェイクスピアの『マクベス』は、マクベスの野望と罪悪感、そして破滅を描いた悲劇です。マクベスとマクベス夫人の罪の意識の変遷、王殺しという行為における「男としてのマン」と「人間としてのマン」の対立を分析します。『ファウスト博士』との比較を通して、オクシモロン的な苦悩と悲劇の成立条件を探ります。重要なキーワードはマン(人間)、罪悪感、想像力です。
6.1 マクベスの罪悪感と想像力 王殺し以前からの恐怖
このセクションは、シェイクスピアの『マクベス』におけるマクベスの罪悪感と想像力の関係に焦点を当てています。マクベスの王殺しには、想像力が生み出す恐怖という罪の意識が深く関わっていると分析されています。 テキストでは、王殺し以前の「眼前の恐怖は想像力の生み出す恐怖にはくらべようもない」というマクベスの台詞が引用されており、彼の内面における罪悪感の深さが強調されています。 王殺し直後の「アーメン」の一言がいえないこと、城の南門を叩く音に恐怖することなども、マクベスの心の内にある罪の意識の表れと解釈されています。 彼は王殺しの手段や結果、発覚を恐れているのではなく、彼の心の奥底にある良心、すなわち罪悪感が彼を苦しめているのです。 この罪悪感は、マクベスの行動を規定し、悲劇の展開を決定づける重要な要素として位置づけられています。 マクベス自身の内面における葛藤が、この悲劇を特徴づけていると述べられています。
6.2 二つの マン の論理 マクベスの魂の死闘
『マクベス』の世界観において頻繁に登場する「マン」(man)という言葉に注目し、マクベスの行動を分析する試みがなされています。 王殺しを実行するためには「男としてのマンの論理」、王殺しを阻止するためには「人間としてのマンの論理」が必要であると論じられています。 つまり、マクベスの魂の中では、「男としてのマン」と「人間としてのマン」という二つの相反する論理が死闘を繰り広げているという解釈が提示されています。 この劇において問われているのは、まさに「マン」の在り方、すなわち人間のあり方であると結論づけられています。 ファウストと異なり、マクベスは神になることを目指してはいません。彼の行為は、ファウストのような冒涜的な神殺しとは異なる性質を持つとされています。 この「二つのマンの論理」の対立が、マクベスの内面における葛藤と悲劇的な結末を導く原動力となっていると分析されています。
6.3 マクベスの三つの生と ファウスト博士 との比較 オクシモロン的呪縛
このセクションでは、『マクベス』と『ファウスト博士』を比較することで、両作品の共通点と相違点を考察しています。 マクベスの人生を、A(栄光ある過去)、B(王殺しを実行した野望に満ちた現在)、C(罪悪感と罰の意識に苦しむ未来)の三つの段階に分け、ファウストの三つの生(A、B、C)と対比させています。 マクベスは、Aを否定してBを選びましたが、Cへの関心が彼の魂を蝕んでいきます。BとCの間には、お互いの存在を賭けた死闘があり、両者は互いに全面的に否定し合います。 マクベスは、Bに徹しようとしたり、Cに殉じようとしたりと、揺れ動く存在として描かれています。 このマクベスの揺れ動く様は、オクシモロン的な状態にあり、善悪の両義的な性質が彼に内在していると解釈されています。 最終的に、このオクシモロン的な呪縛に由来する認識の苦悩こそが、悲劇の成立に不可欠の条件であると結論づけられています。
VII.7 モルフィ公爵夫人 反自然 と 儀式的定形性
シェイクスピアの『モルフィ公爵夫人』は、公爵夫人の再婚を巡る家族の葛藤を描いた悲劇です。ファーディナンドの異常なまでの妹への嫌悪と、公爵夫人の死の儀式的定形性に注目し、『ハムレット』や『アントニーとクレオパトラ』との比較を通して、自然と反自然、プロテスタントの家族観といった観点を盛り込みます。ニールの解釈も参考に、悲劇世界の特異性を分析します。
7.1 ファーディナンドの異常な嫌悪 再婚への執着と中世的世界観
このセクションでは、シェイクスピアの『モルフィ公爵夫人』において、公爵夫人の兄であるファーディナンドが、妹の再婚に異常なまでの嫌悪を示す理由が考察されています。 ファーディナンドの嫌悪と恐怖は、単に妹の再婚が「反自然」であると非難しているだけではないとされています。 むしろ、彼は中世的な自然法的世界観を体現する存在として描かれており、自身の肉体と血への強い意識が、妹の行動への拒絶反応を生み出している可能性が示唆されています。 ファーディナンドは、肉体と血に忠実な生き方を自然な生き方と捉えており、妹の再婚が、彼自身の内なる秩序を脅かす存在として映っていると考えられます。 彼の異常な反応は、肉体的な繋がりと血縁関係への強い執着、そして再婚によって崩れるかもしれない家族秩序への不安や恐怖から来るものだと解釈されています。このファーディナンドの反応が、この劇の独特の悲劇性をもたらしている要因の一つだと分析されています。
7.2 公爵夫人の愛と死 儀式的定形性と反自然の対比
公爵夫人のアントニオに対する愛は、身分や地位の垣根を超えた、情熱的で純粋で高貴なものであるとされています。しかし、この愛は、ファーディナンドらからは「反自然」と見なされています。 公爵夫人はアントニオへの求婚において、「わたしのこの身体は生身の肉体、血が流れているのです」と述べており、自身の肉体性と生への肯定を表明しています。 この発言は、ファーディナンドの中世的な自然観とは対照的な、近代的な価値観を反映していると解釈できます。 一方で、公爵夫人の死は、ニールが指摘するように「儀式的定形性」を備えているとされています。これは、他の登場人物の死の「非儀式的無定形性」と対照的なものです。 彼女の死は、クレオパトラの死と同様に、大理石のような輝きを持つ死、つまり、ある種の崇高さを帯びた死として表現されています。 「最高の贈り物」として自らの死を受け入れる公爵夫人の姿勢が、この劇における「反自然」と「儀式的定形性」という対比をより際立たせています。
7.3 シェイクスピア悲劇とプロテスタントの家族観 ポスト キリスト教的状況
このセクションでは、シェイクスピアの悲劇、特に『モルフィ公爵夫人』における家族観が、プロテスタントの台頭と関連付けて考察されています。 バーバーは、シェイクスピアの作品において家族、特に女性の役割が重視されているのは、プロテスタントによる聖母マリア崇拝の廃止を反映していると主張しています。 シェイクスピアの悲劇は、キリスト教的な期待や価値を若干残しつつも、「神もなく聖家族もない、あるのはただ人間家族だけである」というポスト・キリスト教的な状況を呈示していると解釈されています。 この解釈は、宗教改革後の社会変化とシェイクスピア悲劇の密接な関係を示唆しています。 『モルフィ公爵夫人』における家族の葛藤は、このようなポスト・キリスト教的な状況における人間関係の複雑さを反映していると考えられます。 ファーディナンドの反応や公爵夫人の死の「儀式的定形性」なども、この観点から再解釈される余地があります。
VIII.8 リア王 人間 内の 聖 と キリスト教的愛
シェイクスピアの『リア王』は、リア王の家族崩壊と苦悩を描いた悲劇です。コーデイーリアとの関係、そしてリア王の煉獄体験に焦点を当て、バーバーの解釈を基に、キリスト教的愛の表現、そして人間-内の-聖という概念を探求します。ドリモアとの対比を通して、この悲劇における神秘性の解釈を考察します。重要なキーワードはコーデイーリア、キリスト教的愛、人間-内の-聖、煉獄です。
8.1 リア王の苦悩とコーデイリアのキリスト教的愛 超自然の欠如
このセクションでは、シェイクスピアの『リア王』におけるリア王の苦悩と、娘コーデイリアの行動が、キリスト教的愛の表現としてどう解釈できるかが論じられています。 テキストでは、リア王が「お前の姉たちはわしをひどいめに合わせた」と訴えるのに対し、コーデイリアが「なにもありません」と答える場面が重要視されています。 バーバーは、このコーデイリアの「なにもありません」という台詞に、キリスト教的な超自然を欠いた、純粋なキリスト教的愛の完全な表現があると解釈しています。 コーデイリアは、リア王の犯した罪を償い、彼を救おうとする行動をとっており、その愛は無償のものであるとされています。 この解釈は、コーデイリアを自然の愛娘、あるいはリアの贖罪の象徴として捉える従来の解釈とは異なる視点から、『リア王』の悲劇性を分析する試みです。 コーデイーリアをキリストと単純に結びつける解釈には抵抗があるものの、コーデイーリアの遺体を抱くリア王の姿を逆さまのピエタ像として捉えるバーバーの解釈が紹介され、その説得力のある側面が指摘されています。
8.2 人間 内の 聖 の概念 シェイクスピア悲劇における聖性の在り方
このセクションでは、シェイクスピア悲劇における「聖なるもの」の概念、特に『リア王』における「聖なるもの」の在り方が、バーバーの視点から論じられています。 バーバーは、シェイクスピアの悲劇において「聖なるもの」は、神や聖母マリアといった超越的な存在ではなく、人間自身の中に存在すると主張しています。 リア王とコーデイーリアは、人間であると同時にイコンとしての側面も持ち合わせていますが、超越的な存在を表象しているわけではないと明確にされています。 コーデイーリアの行動は、天上の父である神のためではなく、生身の人間である実の父を救うためのものと解釈されます。 この「人間-内の-聖」という概念は、シェイクスピア悲劇における宗教と人間の複雑な関わりを理解する上で重要な鍵となります。 「嵐の荒野」の体験を通して、リア王が貧者への同情や人間本性への自覚を深め、コーデイーリアとの和解を経て「煉獄体験」をし、失われた「内なる聖」を取り戻したというバーバーの解釈が提示されています。
8.3 悲劇と宗教の融合 縦軸の世界観とドリモアとの対比
このセクションは、『リア王』における悲劇と宗教の不可分な関係をまとめ、その世界観を説明しています。 テキストでは、『リア王』の世界を、宗教と密接に関わるオクシモロン的反転と変容の世界であると捉えています。 リア王が愛娘の遺体を遺体ではないと幻想を抱きながら死ぬという場面は、オクシモロン的悲劇世界の典型例として挙げられています。 しかし、政治と権力を重視するドリモアの見解からは、この種の解釈は「本質主義的ヒューマニズム」にすぎず、キリスト教的解釈と同様に苦悩を神秘化していると批判されています。 それでも、エリザベス朝悲劇の世界は、悲劇と宗教が深く結びついたものであり、人間存在の醜さや愚かさ、存在の浅さが徹底的に追求され、人間存在の本質が問われる縦軸の世界であると主張されています。 ルカーチの「悲劇には一つの次元しかない。高さの次元だ」という言葉を引用し、この縦軸的な世界観が、シェイクスピア悲劇の魅力を決定づけていると結論づけられています。
