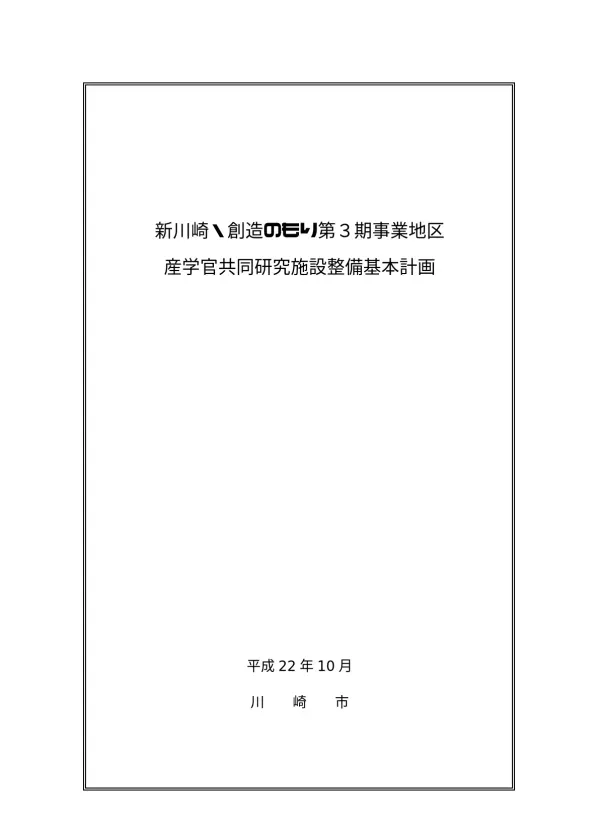
新川崎産学官連携研究拠点整備計画
文書情報
| 学校 | 川崎市 |
| 専攻 | 都市計画、産業振興、ナノテクノロジー |
| 場所 | 川崎市 |
| 文書タイプ | 基本計画 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.06 MB |
概要
I.川崎市の ナノ マイクロテクノロジー 研究開発拠点整備計画
川崎市は、京浜工業地帯の中核としてものづくり企業が集積しており、次世代のものづくり技術であるナノ・マイクロテクノロジー分野の強化を目指しています。特に、製品の小型化・精密化に対応した微細加工技術のニーズが高まっており、市内企業の技術向上と新産業創出が喫緊の課題です。この計画では、慶應義塾大学、早稲田大学、東京工業大学、東京大学の4大学コンソーシアムと連携し、新川崎・創造のもり第3期事業地区に産学官連携による研究開発拠点を整備します。 この拠点では、クリーンルームと最先端のファブリケーション設備を備え、MEMS/NEMS等の研究開発から試作・加工、計測・評価までの一貫した支援体制を提供します。中小企業への技術高度化支援も重要な柱です。
1. 川崎市の産業状況とナノ マイクロテクノロジーの重要性
川崎市は京浜工業地帯の中核として、鉄鋼、石油、化学、電機など大企業の生産拠点と、優れたものづくり技術を持つ中小企業が多数集積する工業都市です。しかし、近年は製品の小型化・精密化、高機能化・省エネ化が加速し、従来の技術では対応できない課題が生じています。そこで、次世代のものづくり技術として注目されるナノ・マイクロテクノロジーが、川崎市の産業競争力強化に極めて重要となります。 特に、ミクロン単位からナノ単位の微細加工・精密計測技術が求められており、市内企業もナノ・マイクロテクノロジーへの取り組みを活発化させています。具体的には、A社によるナノレベル精密加工に対応する高度な金型の開発、B社によるナノインプリント成型受託、C社によるナノインプリント受託転写やMEMS試作から量産までの受託加工など、様々な企業が最先端技術の開発・応用に取り組んでいます。これらの取り組みは、川崎市の産業構造転換と国際競争力強化に大きく貢献する可能性を秘めています。 しかし、現状では大規模なクリーンルーム不足や高額な設備投資の負担、専門知識の不足などが、中小企業のナノ・マイクロテクノロジー分野への参入障壁となっています。この課題を克服し、多くの企業がナノ・マイクロテクノロジーを活用できる環境整備が、本計画の重要な目的です。
2. 4大学コンソーシアムとの連携と産学官連携体制
川崎市は、ナノ・マイクロテクノロジー研究において最先端を走る慶應義塾大学、早稲田大学、東京工業大学、東京大学からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムと連携協力に関する基本合意を締結しました。この連携により、4大学コンソーシアムが持つ高度な研究開発力と、川崎市のものづくり産業基盤を融合させることで、ナノ・マイクロテクノロジー分野における研究成果の産業化を加速させます。 具体的には、4大学コンソーシアムは新川崎・創造のもりに活動拠点を設置し、最先端の研究機器を用いた研究開発を行います。この産学官連携体制は、大学、企業、行政が緊密に協力し、研究開発から試作・評価、量産化までの一連のプロセスを効率的に推進するための体制です。 4大学コンソーシアムの専門知識・技術と、川崎市内の企業が持つ実用化のためのノウハウを組み合わせることで、従来は困難だった技術開発や製品化が実現可能となります。この連携による相乗効果は、新産業の創出、地域経済の活性化、ひいては日本のものづくり産業全体の強化に貢献すると期待されています。 特に、中小企業にとって、高額な設備投資や専門知識の不足といった参入障壁を乗り越える上で、この産学官連携体制は大きな助けとなるでしょう。
3. 新川崎 創造のもり第3期事業地区への研究開発拠点整備
本計画の中核となるのは、新川崎・創造のもり第3期事業地区への産学官共同研究拠点の整備です。この拠点では、ナノ・マイクロテクノロジーの研究開発から試作・加工、計測・評価までを網羅した一貫体制を構築します。そのため、大規模なクリーンルームの設置が不可欠であり、750㎡を初期段階とし、将来的には1300㎡への拡張を視野に入れています。 施設には、次世代のものづくり技術に必要な最先端の加工機器や計測機器が導入され、これらの機器は、市内企業も共同利用できる体制とします。これは、個々の企業では容易に所有できない高額な設備を共有することで、中小企業を含めた多くの企業がナノ・マイクロテクノロジーを活用した研究開発を進められる機会を創出することを目的としています。 また、共同研究を円滑に進めるための会議室や、短期滞在者向けのビジタールームなども設置し、利用者の利便性を向上させます。これらの機能と設備により、研究開発期間の短縮や開発費用の低減、大学等の知見の活用などが期待され、新製品開発や新分野への進出を促進します。 特に、中小企業の技術力向上、産業構造の転換、新技術の習得、製品の高付加価値化、新事業・新製品の開発支援に重点を置き、環境・エネルギー分野やライフサイエンス分野といった成長分野への貢献を目指します。 さらに、ファウンダリーサービス(受託製造)を提供し、試作品製造支援も行います。これにより、中小企業の技術開発を強力にサポートし、国際競争力強化に繋げます。
4. 拠点の運営体制と費用負担
研究開発拠点の建設主体は川崎市となり、迅速な整備と国の補助金活用を可能にします。一方、クリーンルーム内にあるナノ・マイクロ関連機器の導入と管理運営は4大学コンソーシアムが行います。これにより、川崎市はファブリケーション機器に関する費用負担を軽減できます。4大学コンソーシアムは、企業や複数大学からの共同利用による高い稼働率を見込み、利用料収入で設備の維持・更新費用を賄う計画です。 運営面では、指定管理者制度を活用し、迅速かつ効率的な運営を目指します。市、指定管理者、4大学コンソーシアム間で協定・契約を締結することで、設備の一般開放や市内企業への支援(共同研究・人材育成・技術相談・ファウンダリーなど)といった公共性を担保します。 費用負担については、ファブリケーション設備の維持管理費用は、原則として設備・機器利用者である受益者負担とします。これは、利用者にとって直接的なメリットと費用負担のバランスを考慮した、持続可能な運営体制を構築するための重要な要素です。このシステムを通じて、高度な技術と設備を効率的に活用し、多くの企業が恩恵を受けられる環境を目指します。
II.川崎市の産業構造と強み
川崎市は、鉄鋼、石油、化学、電機など大手企業の生産拠点に加え、優れたものづくり技術を持つ多数の中小企業が集積しています。しかし、グローバル競争激化の中で、高付加価値製品の開発が不可欠です。ナノ・マイクロテクノロジーは、情報、環境、エネルギー、医療など幅広い分野で応用が期待される次世代技術であり、川崎市の産業競争力強化に貢献すると考えられます。 具体的な企業事例として、ナノレベルの精密加工に対応する金型開発を行うA社、ナノインプリント成型を行うB社、MEMS試作から量産までを請け負うC社などが挙げられます。
1. ものづくり企業の集積と優れた技術力
川崎市は、京浜工業地帯の中核都市として、日本経済の発展を支えてきました。現在も鉄鋼、石油、化学、電機など大企業の主要生産拠点が数多く立地しており、これらの企業は高度な技術力を有しています。さらに、川崎市には優れたものづくり技術を持つ中小企業が多数集積しており、これらの企業は、長年培ってきた独自の技術やノウハウを活かし、様々な分野で活躍しています。これらの企業の存在は、川崎市の産業基盤を支える重要な要素であり、地域の経済発展に大きく貢献しています。 特に、精密加工や表面処理など、高度な技術力を必要とする分野において、川崎市の中小企業は高い競争力を誇っています。長年の経験と蓄積された技術は、他地域にはない独自の強みとなっています。 しかし、近年は中国などの海外企業との競争が激化しており、従来の技術力だけでは国際競争力を維持することが困難な状況です。そのため、新たな技術開発や高付加価値製品の生産体制の構築が、川崎市のものづくり産業にとって喫緊の課題となっています。
2. ものづくり環境の変化とナノ マイクロテクノロジーへの対応
光学機器、情報通信機器、医療機器、自動車部品など、多くの最終製品は小型化、軽量化、複雑化が進んでいます。このため、製造現場ではより微小で精密な加工技術が求められるようになっています。従来はミクロン単位の精度が主流でしたが、近年ではナノレベルの精度が求められるケースが増えています。 こうした変化に対応するため、川崎市内の企業はナノ・マイクロテクノロジーの導入・活用に積極的に取り組んでいます。ナノ・マイクロテクノロジーは、低コスト高効率太陽光電池の開発や拒絶反応のない人工臓器の実現など、幅広い分野で革新的な技術革新をもたらす可能性を秘めています。 具体的には、A社は小径のガラスやシリコンなどのナノレベルでの精密加工に対応する高度な金型を開発し、B社は次世代の微細加工技術であるナノインプリント成型を受託、C社はナノインプリントの受託転写やMEMSの試作から量産までの受託加工などを行っています。 これらの企業事例からもわかるように、川崎市の中小企業は、積極的にナノ・マイクロテクノロジー技術を取り入れ、新たなビジネスチャンスの創出に挑んでいます。しかし、高額な設備投資や専門知識の不足などが課題であり、支援体制の整備が求められています。
3. 国内外のナノ マイクロテクノロジー関連拠点の現状と課題
海外では、ナノ・マイクロテクノロジー分野への積極的な投資が進められており、ベルギーのIMEC、アメリカのCNSE Albany、フランスのMINATEC、シンガポールのFusionopolisなど、大規模な研究開発拠点が整備されています。これらの拠点は、3000㎡以上のクリーンルームを複数備え、研究開発から試作・加工、計測・評価までを一貫して行える体制を構築しています。 一方、日本は大学などの研究開発機関における研究開発水準は高いものの、研究開発拠点の整備においては諸外国に遅れを取っています。国内には、東北大学、産業技術総合研究所、物質・材料研究機構などがナノ・マイクロテクノロジー関連の機器を企業に供用する拠点としてありますが、大規模なクリーンルームは不足しており、研究開発から試作・加工、計測・評価までの一貫ラインが十分に形成されていません。 そのため、日本の大手企業の多くは海外の研究拠点に研究者を派遣して開発を進めているのが現状です。この状況を改善し、国内でナノ・マイクロテクノロジーを活用した研究開発を促進するためには、大規模なクリーンルームを含む充実した研究開発拠点の整備が不可欠です。中小企業にとって、高額な設備投資や専門知識の不足は大きな参入障壁となっています。これらの課題を解決することで、日本のものづくり産業の国際競争力強化に大きく貢献できると考えられます。
III.4大学コンソーシアムとの連携と研究開発
本計画は、ナノ・マイクロテクノロジーに関する基礎研究の産業化を目指し、「4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム」(慶應義塾大学、早稲田大学、東京工業大学、東京大学)と連携して進められます。コンソーシアムは、新川崎・創造のもりに拠点を置き、最先端機器を用いた研究開発を行います。この産学官連携体制により、研究開発拠点での成果を迅速に産業化し、ものづくり技術の高度化を促進します。
1. 4大学コンソーシアムとの連携協力の基本合意
川崎市は、ナノ・マイクロテクノロジー分野における基礎研究の産業化を推進するため、慶應義塾大学、早稲田大学、東京工業大学、東京大学からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムと連携協力に関する基本合意を締結しました。この合意は、ナノ・マイクロテクノロジーに関する基礎研究を産業化に繋げ、我が国経済を牽引するような技術・製品を生み出すことを目的としています。 基本合意に基づき、川崎市と4大学コンソーシアムは、新川崎・創造のもり第3期事業地区に産学官共同研究拠点を整備し、最先端の研究開発を推進していきます。 この連携は、大学が持つ高度な研究開発力と、川崎市が持つものづくり産業基盤を融合させることで、相乗効果を生み出し、研究成果の迅速な産業化を実現することを目指しています。4大学コンソーシアムは、平成21年度からKBICに活動拠点を設置し、ナノ・マイクロ技術に関する世界最先端の機器を用いた研究活動を開始しています。この連携は、川崎市の産業振興に大きく貢献すると期待されています。
2. 研究開発拠点における研究活動と機器共用機能
4大学コンソーシアムは、新川崎・創造のもりに拠点を置き、ナノ化学、ナノ光科学、MEMS/NEMS、ナノバイオなど、ナノ・マイクロテクノロジーに関する様々な分野の先端的な研究機器を導入し、活発な研究活動を行っています。これらの研究活動は、基礎研究にとどまらず、産業界への技術移転や人材育成にも繋がることを目指しています。 次世代のものづくり技術で必要となる最先端の加工機器や計測機器は、数億円規模の高額なものが多く、個々の企業が所有することは困難です。そこで、新川崎・創造のもりでは、科学技術振興機構の地域産学官共同研究拠点整備事業により、地域での共用を目的としたナノ・マイクロ領域の先端研究機器が整備されています。 新たに整備される施設にも、ナノ・マイクロテクノロジーの研究開発から試作・加工、計測・評価までの一貫ラインを形成できるクリーンルームを設置し、先端機器を共同利用に供することで、多くのものづくり企業に次世代技術習得の機会を提供します。4大学コンソーシアムが保有する研究機器も地域への開放を予定しており、より広範な共同利用が期待されます。
3. 産学官共同研究推進とものづくり技術高度化支援
新川崎・創造のもり周辺には、精密加工や表面処理など優れたものづくり技術を持つ中小・中堅企業が多数集積しており、K2タウンキャンパスやKAST、KSPなど、先端的な産学官共同研究を担う施設も立地しています。これらの強みを活かし、国際競争力の源泉となる新たな技術・産業創出を目指し、産学官共同研究を推進します。 この共同研究拠点では、ものづくり企業や研究機関が集う共同研究の場を提供し、各主体をつなぐコーディネート支援なども実施することで、共同研究を促進します。 また、川崎市内のものづくり企業の技術力向上と産業構造の転換に対応するため、微小・精密な加工技術の習得支援や、ファウンダリーサービス(受託製造)による試作品製造支援を行います。さらに、産業界への教育機能だけでなく、見学の受入れや展示・広報、オープンラボの開催などを通じて、次世代を担う子どもたちへの科学技術教育にも貢献します。 特に、環境・エネルギー分野やライフサイエンス分野などの成長分野をターゲットに、幅広い産業分野で基盤技術となるナノ・マイクロテクノロジーの研究開発を支援することで、川崎市の産業振興に貢献します。
IV.研究開発拠点の機能と設備
整備される研究開発拠点は、ナノ・マイクロテクノロジー関連の研究開発、試作・加工、計測・評価までを一貫して行えるクリーンルームを備えます。共同研究を推進するための会議室、短期利用者向けの滞在スペース(ビジタールーム)も設置予定です。 クリーンルームの面積は当初750㎡を計画し、将来的には1300㎡への拡張を視野に入れています。設備としては、数億円規模の高額な最先端機器が導入され、中小企業も利用可能な共同利用設備となります。ファウンダリー・サービス(受託製造)も提供し、中小企業の技術高度化を支援します。
1. クリーンルームとファブリケーション設備
研究開発拠点の中核となるのは、ナノ・マイクロテクノロジーの研究開発から試作・加工、計測・評価までを一貫して行える大規模クリーンルームです。初期段階では750㎡を整備し、将来的には1300㎡程度への拡張を可能とする設計とします。このクリーンルームには、ナノ・マイクロ領域の加工や計測が可能な最先端機器が導入されます。これらの機器は共同利用に供され、市内の多くのものづくり企業に次世代のものづくり技術習得の機会を提供します。 数億円規模の高額な最先端加工機器や計測機器は、個々の企業では所有が困難なため、共同利用体制を構築することで、中小企業を含む多くの企業が最先端技術を活用できる環境を整備します。 施設全体の設計においては、共用機器の配置による清浄度の維持、将来的な拡張性、微振動・静電気・磁場対策なども考慮し、研究開発に最適な環境を確保します。特に、鉄道軌道が近接していることから、建築物による振動対策が重要になります。
2. 産学官共同研究推進機能とものづくり技術高度化支援機能
本施設は、産学官共同研究を推進するための機能も備えます。新川崎・創造のもり周辺には、精密加工や表面処理など優れたものづくり技術を持つ中小・中堅企業が多数集積していることから、これらの企業と研究機関、大学が連携して研究開発を進められる環境を整備します。 共同研究の場を提供するだけでなく、各主体をつなぐコーディネート支援を実施し、産学官連携を促進します。 また、中小・中堅企業の技術力向上と産業構造の転換に対応するため、微小・精密な加工技術の習得支援、ファウンダリーサービス(受託製造)による試作品製造支援を行います。さらに、製品の高付加価値化や新事業・新製品開発を支援し、環境・エネルギー分野やライフサイエンス分野などの成長分野への貢献を目指します。 教育機能としては、日常的な見学の受入れや展示・広報、オープンラボ等の開催を通じて、子どもたちに最先端の科学技術を分かりやすく伝える取り組みも実践します。
3. その他の共用機能
共同研究拠点として、打ち合わせや会議の機会が多いことを想定し、少人数から大人数まで対応可能な柔軟な会議スペースを確保します。 現在、新川崎・創造のもり内には会議室が不足しているため、本施設に十分な会議室を整備する必要があります。 また、クリーンルームに隣接する研究室は、将来的なクリーンルーム拡張を視野に入れ、クリーンルームへの転換が可能な仕様とします。 さらに、1~2週間から数ヶ月程度の短期利用も多いと想定されることから、短期利用者向けの滞在スペースとしてビジタールームも必要となります。これらの機能により、利用者にとって快適で効率的な研究環境を提供します。
V.運営体制と費用負担
施設の建設は川崎市が行い、設備・機器の管理・運営は4大学コンソーシアムが担います。維持管理費用は、原則として受益者負担となります。市とコンソーシアム、指定管理者間で協定を締結し、設備の一般開放や市内企業への支援(共同研究、人材育成、技術相談、ファウンダリーなど)を行います。 この産学官連携による効率的な運営体制により、ナノ・マイクロテクノロジー分野の研究開発を促進し、川崎市の産業振興に貢献することを目指します。
1. 施設の建設と運営体制
研究開発拠点の建設は川崎市が主体となり、迅速な整備と国の補助金活用を可能にします。これは、迅速な拠点整備と事業の早期効果発現を優先する戦略です。一方、クリーンルーム内に設置されるナノ・マイクロ関連の主要研究開発機器は、4大学コンソーシアムが有する先端機器を導入します。機器の管理・運営は、4大学コンソーシアムが担うことで、市への費用負担を軽減します。4大学コンソーシアムは、企業や複数大学からの共同利用による高い稼働率を見込み、利用料収入で設備の維持・更新費用を賄う計画です。 施設の運営は、指定管理者制度を活用することで、効率的な運営を目指します。迅速な整備と、事業のライフサイクル全体での費用負担、建設後の事業運営の柔軟性などを考慮し、この体制が最適と判断されました。 市と指定管理者、4大学コンソーシアムは、協定・契約を締結し、設備の一般開放や市内企業への支援(共同研究、人材育成、技術相談、ファウンダリーサービスなど)を行い、公共性を担保します。
2. 費用負担の考え方
ファブリケーション設備(最先端加工設備、計測機器)の維持管理費用は、原則として受益者(設備・機器の利用者)負担となります。これは、公設工業試験場では共通の課題となるメンテナンス費用や設備更新費用を、利用者負担によって確保する仕組みです。 4大学コンソーシアムは、企業の共同利用や複数大学の利用により、通常大学で使用するよりも高い稼働率が見込まれ、利用料収入が確保できるため、設備維持・更新の負担が軽減されると見込まれています。 この費用負担の考え方は、利用者にとって直接的なメリットと費用負担のバランスを考慮した、持続可能な運営体制を構築するための重要な要素です。 設備の故障時におけるバックアップ体制や、給水の汚染対策なども考慮した、安全で安定した運営体制を構築します。 建物の設計においては、給水ポイントの柔軟な変更対応や、予備・増設対応も考慮した計画とします。また、鉄道軌道が近接しているため、微振動対策、静電気対策、磁場対策なども実施します。
