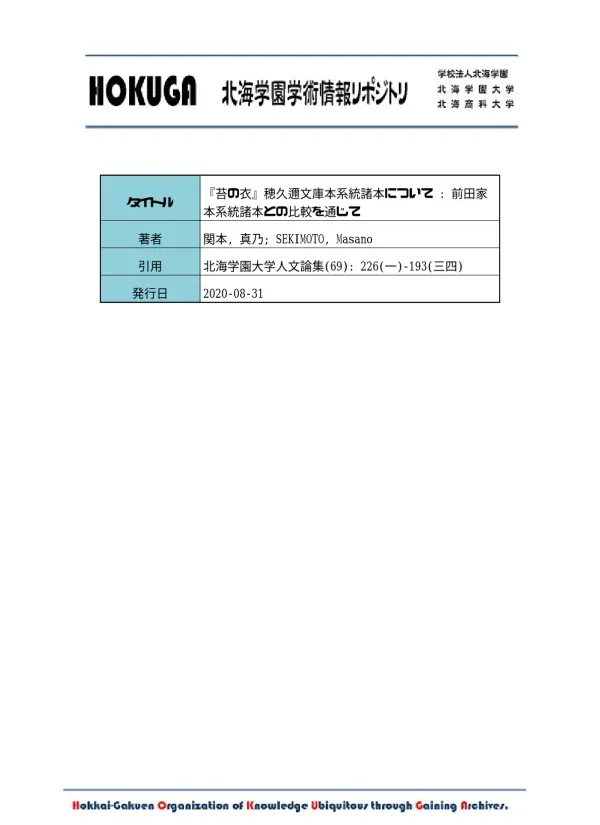
『苔の衣』諸本比較研究:穂久邇文庫本を中心に
文書情報
| 著者 | 関本 真乃 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 人文科学 |
| 場所 | 札幌市 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.53 MB |
概要
I. 穂久邇文庫本系統諸本と他系統諸本の比較 苔の衣 の本文異同研究
本稿は、『苔の衣』の穂久邇文庫本系統(穂久邇文庫蔵本、黒川四冊本、盛岡本、龍門文庫本)の本文を詳細に比較検討し、その特徴を明らかにするものです。特に、系譜が不明瞭な西園寺文庫本および前田家本との比較を通して、各本の本文の異同、特に誤脱の有無や、系譜・官職記述の正確性などを分析します。これらの比較によって、『苔の衣』の本文の成立過程や、各系統本の信頼性の評価に繋がる知見が得られます。研究対象となる重要な写本は、穂久邇文庫蔵本、黒川四冊本、盛岡市中央公民館蔵本、龍門文庫蔵本、西園寺文庫蔵本、そして前田家尊経閣本です。
1. 研究の目的と対象文献
本稿の目的は、『苔の衣』の本文異同を精査し、各系統本の特徴を明らかにすることにある。特に、穂久邇文庫本系統(穂久邇文庫蔵本、黒川四冊本、盛岡本、龍門文庫本)の四本の完本を比較検討する。 先行研究において、麻原氏以降、穂久邇文庫本系統諸本の詳細な本文比較は行われていないことを指摘し、その空白を埋めることを目指す。比較対象として、系譜が不明瞭で、穂久邇文庫本系統と前田家本系統の両方の特徴を持つとされる西園寺文庫本、そして前田家本も検討対象とする。各文献の入手方法も明記されており、穂久邇文庫本は翻刻、龍門文庫本と西園寺文庫本はインターネット上の画像、前田家本は複製を用いている。これらの多様な資料を用いることで、より多角的な分析が可能となる。
2. 穂久邇文庫本系統諸本の概要と本文の特徴
穂久邇文庫本系統の四本の完本について、外題、冊数、略称を示し、本文の異同を検討する。穂久邇文庫蔵本、黒川四冊本、盛岡本、龍門文庫本の特徴を比較することで、それぞれの写本の本文上の特徴を明らかにする。例えば、龍門文庫本と盛岡本には共通の脱落が見られる箇所が複数あり、本文の解釈に影響を与える可能性がある。また、穂久邇文庫本にのみ見られる校異も存在する。これらの分析を通して、穂久邇文庫本系統の本文の成立過程や、各写本間の関係性を明らかにすることを目指す。 各写本の物理的な特徴についても触れられており、例えば前田家本は複製であり、本文は12行、墨による書き入れがあることなどが記述されている。
3. 前田家本と西園寺文庫本の分析
前田家本は、複製であるため、錯簡などの問題を抱えている可能性があり、本文の信頼性について注意深い検討が必要となる。西園寺文庫本は巻三・四に相当する部分のみが残っており、完本ではないため、他の写本との比較においては、その断片的な性質を考慮する必要がある。立命館大学アートリサーチセンター古典籍ポータブルデータベースの詳細書誌情報が西園寺文庫本の分析に用いられている。これらの写本は、穂久邇文庫本系統とは異なる系譜を持つ可能性があり、系譜や官職記述の正確性といった点において、穂久邇文庫本系統との比較を通して、それぞれの写本の独自性や信頼性を評価する。
4. 黒川四冊本の本文の信頼性と価値
黒川四冊本は、系譜や官職記述において高い正確性を示しているという分析結果が示されている。他の穂久邇文庫本系統の写本に見られる誤りや脱落が、黒川四冊本では修正されているケースが多数確認されている。そのため、穂久邇文庫本系統の校訂を行う際には、黒川四冊本を重要な基準として用いることが有効であると結論づけられている。ただし、黒川四冊本の本文が生成された過程については不明な点が残されているものの、その高い正確性から、校訂における重要な役割を担う文献であると言える。 前田家本や西園寺文庫本も系譜の正確性において必ずしも完璧ではなく、黒川四冊本と比較することで、それらの写本の信頼性をより客観的に評価することができる。
5. その他の参考文献と今後の展望
本研究では、今井源衛校訂・訳注『中世王朝物語全集七 苔の衣』などの先行研究や、実践女子大学図書館蔵『苔の衣』、奈良女子大学学術情報センター阪本龍門文庫善本電子画像集などの資料も参照されている。これらの多様な資料を比較検討することで、より詳細な分析が可能になっている。 本稿では、『苔の衣』の本文異同を多角的に検討し、各系統本の特質を明らかにすることで、今後の『苔の衣』研究に貢献する基盤となる知見を提供することを目指している。特に黒川四冊本の高い信頼性と、穂久邇文庫本系統の本文の成立過程に関する新たな知見は、今後の研究に大きな影響を与える可能性がある。
II. 穂久邇文庫本系統の本文の特徴
穂久邇文庫本系統の四本の完本(穂久邇文庫蔵本、黒川四冊本、盛岡本、龍門文庫本)の本文比較において、共通する誤りや脱落、独自の異文などが確認されました。特に、龍門文庫本と盛岡本は共通の脱落が見られ、本文の読解に支障をきたす箇所が複数存在します。一方、黒川四冊本は、系譜や官職記述において他の本に比べて高い正確性を示す傾向があり、校訂の際の重要な拠り所となり得ることが示唆されています。
1. 穂久邇文庫本系統四本の完本における本文の異同
本稿では、『苔の衣』の穂久邇文庫本系統に属する四本の完本、すなわち穂久邇文庫蔵本、黒川四冊本、盛岡本、龍門文庫本について、本文の異同を詳細に分析する。これらの写本は、いずれも『苔の衣』の全巻を収録した完本であるが、本文には様々な差異が存在する。これらの差異を丁寧に比較検討することで、各写本の本文上の特徴や、それらの写本間の関係性を明らかにすることを目指している。 分析の結果、龍門文庫本と盛岡本には共通して本文の脱落が見られる箇所が複数存在することが判明し、このことは、両写本が共通の祖本から派生した可能性を示唆している。また、穂久邇文庫本独自の校異も確認されており、穂久邇文庫本系統内での本文の変遷を考察する上で重要な情報となる。
2. 系統本における共通の誤りと個別的な校異
穂久邇文庫本系統の複数の写本に共通して見られる誤りも分析対象となる。例えば、本文の解釈上、明らかに誤りと判断できる箇所が複数存在し、それらの誤りは、読解の際に注意が必要な点として指摘されている。具体的には、関白とその北の方の場面における、配慮のありがたさを「おろか」と読む穂久邇文庫本・龍門文庫本・盛岡本の解釈が本文の読解上誤りであると指摘されている。 一方、穂久邇文庫本にのみ見られる校異も存在し、これは他の系統本にはない穂久邇文庫本独自の本文上の特徴を示すものとして、重要な考察対象となる。これらの共通した誤りや、個別的な校異を分析することで、『苔の衣』の本文成立過程の解明に繋がる重要な手がかりを得ることができる。
3. 本文の比較を通じた各写本の位置づけ
穂久邇文庫本系統の四本の完本を比較検討することにより、各写本の本文上の特徴を明らかにし、それらの写本の相互関係や、本文成立過程における位置づけを明確にする。 例えば、系譜や官職に関する記述の正確性において、黒川四冊本が高い信頼性を示す一方で、龍門文庫本と盛岡本には共通の脱落が見られることから、これらの写本間の関係性や、本文の伝播経路について考察を進める。 さらに、これらの比較分析を通して、穂久邇文庫本系統以外の写本との比較検討へと繋げ、より包括的な『苔の衣』の本文研究を進めるための基礎的な知見を得ることを目指す。
III. 前田家本と西園寺文庫本の位置づけ
前田家本は、複製からの検討であり、本文に錯簡が見られます。西園寺文庫本は断片的な巻三・四に相当する部分のみが残存しており、完本ではありません。これらの写本は、穂久邇文庫本系統と直接的な関連性は見られませんが、比較対象として、特に系譜・官職記述の正確性の検証に役立てられています。立命館大学アートリサーチセンター古典籍ポータブルデータベースなどが、西園寺文庫本の調査に利用されました。
1. 前田家本の本文と特徴
前田家本は、複製からの検討が行われている写本である。本文は12行で、墨による書き入れがあり、巻四に相当する部分から一丁の錯簡が見られると記述されている。表紙は藍色で、雷文繋ぎ文様、左上部に金箔散らし題簽が貼られている。 料紙は楮紙、金襴裂地の胡蝶装で、縦7寸7分5厘、横5寸5分である。書写者や書写年代は不明であるが、寛永・延宝頃の公卿の筆によるものと考えられている。 前田家本は、穂久邇文庫本系統とは独立した系譜を持つ可能性があり、本文の比較検討を通して、穂久邇文庫本系統との関係性、そして系譜・官職記述の正確性について検証が行われる。特に系譜に関する記述の正確性については、黒川四冊本と比較検討することで、その信頼性を評価する。
2. 西園寺文庫本の断片的な本文と情報源
西園寺文庫本は、巻三と巻四に相当する部分のみが残存している不完全な写本である。 本稿では、立命館大学アートリサーチセンター古典籍ポータブルデータベースの詳細書誌情報などを参照しながら、西園寺文庫本の本文を分析している。 西園寺文庫本は、穂久邇文庫本系統とも前田家本系統とも明確に分類できない、両者の混合本文を持つ可能性を示唆する記述があり、その本文の特徴を穂久邇文庫本系統、前田家本と比較することで、その独自性を明らかにしようとしている。 西園寺文庫本は断片的なため、完全な比較はできないものの、特に系譜や官職の記述において、他の系統本とどのような差異を示すのか、その比較を通して本文の成立過程を考察する手がかりとなる。
3. 前田家本と西園寺文庫本の比較による本文成立過程の考察
前田家本と西園寺文庫本は、それぞれ異なる特徴を持つ写本であり、穂久邇文庫本系統との比較を通して、これらの写本が『苔の衣』の本文成立過程においてどのような役割を果たしたのかを考察する。 具体的には、系譜や官職に関する記述の正確性、本文における誤りや脱落の有無などを比較検討することで、それぞれの写本の信頼性や、本文の伝播経路について考察する。 特に、系譜記述においては、黒川四冊本を基準として、前田家本と西園寺文庫本の記述の正確性を評価し、これらの写本が、本文の成立過程においてどのような影響を与えたのかを分析する。この比較検討を通して、黒川四冊本の本文の優位性も改めて確認されることになる。
IV. 黒川四冊本の重要性
系譜・官職記述の正確性において、黒川四冊本は穂久邇文庫本系統諸本の中でも特に優れていると評価されています。本文に明らかな脱落は少ない一方で、他の系統本に見られる誤りや脱落が修正されている箇所が多数確認されています。その成立過程は不明な点も多いものの、本研究においては、重要な校訂の基準として活用されています。
1. 黒川四冊本の高い正確性と校訂への貢献
黒川四冊本は、穂久邇文庫本系統の他の写本と比較して、系譜や官職に関する記述の正確性が高いことが本稿で指摘されている。 他の写本に見られる誤りや脱落が、黒川四冊本では修正されている箇所が多数存在する。このことから、黒川四冊本は『苔の衣』の本文校訂において、極めて重要な基準となる写本であると結論づけられている。 穂久邇文庫本系統の諸本を校訂する場合、系譜や官職に関する記述については、ほぼ全面的に黒川四冊本に基づいて校訂を進めることが可能であると示唆されている。これは、黒川四冊本の本文が、他の系統本に比べて高い信頼性を有することを示す重要な発見である。
2. 黒川四冊本の成立過程と研究上の価値
黒川四冊本の本文が生成された具体的な過程については、現時点では不明な点が多い。しかしながら、本稿では、その本文の正確性に着目し、黒川四冊本が持つ研究上の価値を強調している。 黒川四冊本は、他の穂久邇文庫本系統の写本に共通して見られる誤りを修正しているだけでなく、本文の脱落も少ないことから、高い信頼性を有する写本として位置づけられる。 その成立過程は不明な点が多いものの、本文の正確性という点においては、他の系統本を凌駕する質の高い写本であるため、今後の『苔の衣』研究においても、重要な資料として活用されるべきであると結論づけられている。
3. 黒川四冊本と他の系統本の比較による検証
黒川四冊本の高い正確性は、他の穂久邇文庫本系統の写本(穂久邇文庫蔵本、龍門文庫本、盛岡本)と比較検討することで、より明確に示されている。これらの写本と黒川四冊本を比較することで、共通して見られる誤りや脱落、そして黒川四冊本にのみ存在する独自の記述などが明らかになる。 特に系譜や官職に関する記述においては、黒川四冊本がより正確な記述を示すケースが多い。 この比較を通して、黒川四冊本の本文の優位性が示されるとともに、穂久邇文庫本系統の本文の成立過程や、各写本間の関係性についても、新たな知見が得られる。 さらに、前田家本や西園寺文庫本との比較においても、黒川四冊本の高い正確性は相対的に際立つものとなる。
V. その他の重要文献と人物
本研究では、今井源衛校訂・訳注『中世王朝物語全集七 苔の衣』(笠間書院、一九九六年)の解題なども参照されています。また、実践女子大学図書館蔵『苔の衣』(五本)、奈良女子大学学術情報センター阪本龍門文庫善本電子画像集なども重要な資料として活用されています。これらの文献やデータベースの情報から、各写本の本文の差異や特徴がより明確に示されています。
1. 今井源衛校訂 中世王朝物語全集 と他の重要文献
本稿では、今井源衛校訂・訳注『中世王朝物語全集七 苔の衣』(笠間書院、一九九六年)の解題を参考に、既存研究との比較検討を行っている。 この解題においては、苔の衣の完本を穂久邇文庫本と盛岡公民館本のみとしているが、本稿では、その記述が誤りであることを指摘している。 その他にも、古典文庫『苔の衣』(一九五四年)、実践女子大学図書館蔵『苔の衣』(横井孝氏による研究、実践女子大学文芸資料研究所年報一一号、一九九二年三月)、そして奈良女子大学学術情報センター阪本龍門文庫善本電子画像集(http://mahoroba.lib.nara-wu.ac.jp/y05/y055/ 二〇二〇年七月一日最終閲覧)などが、本研究の重要な参考文献として挙げられている。これらの文献を参照することで、多角的な視点からの分析が可能となる。
2. 西園寺文庫本に関する情報源とデータベース
西園寺文庫本に関する情報は、立命館大学アートリサーチセンター古典籍ポータブルデータベース(https://www.dh-jac.net/db1/books/results-detail.php?f1=SB3475&enter=portal 二〇二〇年七月一日最終閲覧)の詳細書誌情報などを用いて収集・分析されている。 このデータベースは、西園寺文庫本に関する貴重な情報を提供しており、本研究において重要な役割を果たしている。 西園寺文庫本は断片的な資料であるため、他の完本との比較においては、その断片的な性質を考慮した上で分析を行う必要がある。データベースなどのデジタルアーカイブの活用は、古典籍研究においてますます重要になっていることを示している。
3. 関連研究と類似事例の提示
本稿では、国文研所蔵の『卑懐集』(姉小路基綱の歌集)を例に、同様の研究手法が用いられている事例を紹介している。これは、本研究の分析方法の妥当性を示唆するものであり、関連研究との比較を通して、本研究の位置づけを明確にしている。 また、本研究は、先行研究の成果を踏まえつつ、新たな知見を提示することを目指しており、今後の『苔の衣』研究の発展に貢献することを期待されている。 これらの参考文献や類似事例の提示を通して、本研究が、既存の研究成果とどのように関わっているのか、そしてどのような新たな貢献をもたらすのかが、明確に示されている。
