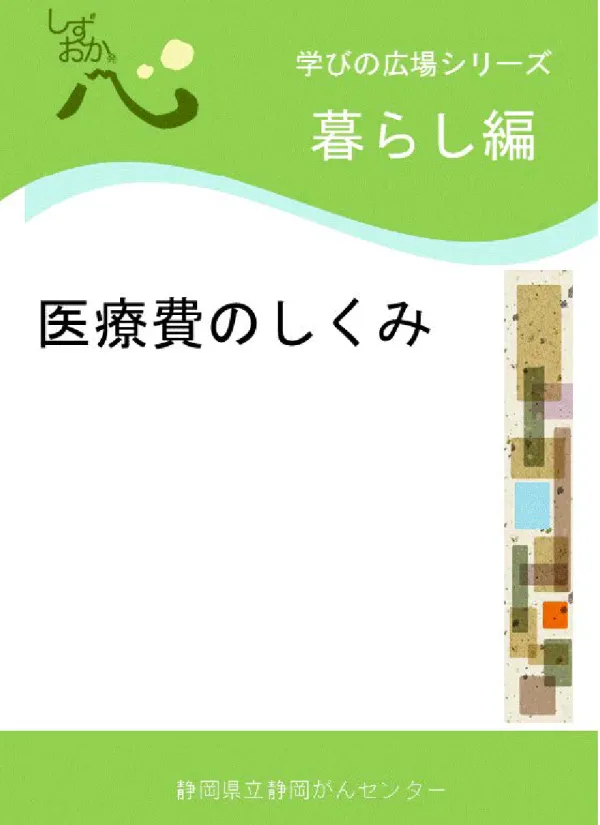
がん医療費ガイド:高額療養費制度解説
文書情報
| 著者 | 静岡がんセンター よろず相談 |
| 場所 | 静岡 |
| 文書タイプ | パンフレット |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.78 MB |
概要
I.公的医療保険と医療費の負担
このパンフレットは、静岡がんセンターにおける医療費、特に高額療養費制度に関する情報を提供しています。多くの診療は保険診療でカバーされますが、自己負担額は年齢と所得によって異なります。外来通院と入院では計算が別々に行われ、差額ベッド代や食事代は保険適用外です。放射線治療などの費用も個別に計算されます。
1. 公的医療保険制度の概要
日本の国民皆保険制度は、国民全員が何らかの医療保険に加入することを義務付けています。この制度は、国民の医療費負担を軽減し、誰もが安心して医療を受けられるようにすることを目的としています。保険料を支払うことで、医療機関での受診、往診、訪問看護などの保険サービスを受けることができます。がんの診療も、多くの場合、この保険診療の対象となります。保険診療では、医療費は全国共通の基準(診療点数、診療報酬)に基づいて算定され、基本的には治療を受ける場所に関わらず同じ金額になります。ただし、公的医療保険が適用されない診療もあります。
2. 保険診療における医療費の支払い
保険診療の場合、医療費の支払い方法は大きく分けて2種類あります。一つは包括払い方式で、検査回数に関わらず1日あたりの医療費が定額になります。入院日数に定額料金をかけることで総医療費が決まります。もう一つは出来高払い方式で、手術、放射線治療、リハビリテーションなど、包括払いに含まれない治療に対しては、実際に提供された医療サービスの量に応じて費用が計算されます。緩和ケア病棟入院料は、入院日数によって3段階の料金体系となっており、公的医療保険が適用されます。しかし、差額ベッド代や食事代などは保険適用外となり、患者さんの自己負担となります。食事代は1食360円(住民税非課税世帯で認定証を持つ方は減額)で、平成30年度からは1食460円に値上げされる予定です。請求書は多くの場合、1ヶ月単位で送付され、支払期限までに会計窓口で支払う必要があります。
3. 保険適用外の医療費と先進医療
差額ベッド代や入院中の食事代は、公的医療保険の適用外となります。 また、保険診療と自由診療(保険適用外)を組み合わせた混合診療は日本では禁止されています。ただし、厚生労働省が認可した先進医療という制度があり、通常の検査や入院などは保険診療で行いますが、先進技術の費用は患者さんが全額負担する仕組みです。先進医療は、一般の保険診療で認められている医療水準を超えた最新技術であり、厚生労働省が将来性があると認めた医療行為です。費用は医療機関によって異なるため、治療を受ける前に必ず確認することが重要です。
4. 医療費の支払いで困った場合の相談窓口
医療費の支払いで困っている場合、病院の医療相談室などの相談窓口を利用することができます。医療相談室には、医療ソーシャルワーカーが常駐している場合があり、経済的な問題を含め様々な相談に対応してもらえます。ソーシャルワーカーがいない場合は、会計担当者への相談も可能です。 さらに、全国のがん診療連携拠点病院には相談支援センターがあり、がんに関する情報提供や様々な相談に対応しています。経済的な負担軽減策として、高額療養費制度が紹介されています。
II.高額療養費制度の利用方法
高額療養費制度は、医療費の自己負担額が高額になった場合に、負担を軽減する制度です。自己負担限度額は年齢と所得で異なり、事前に限度額適用認定証などの**所得区分の『認定証』**を申請することで、窓口での支払いを限度額まで抑えることができます。70歳以上の方は、医療機関の種類に関わらず合算計算されます。認定証の申請には保険証、印鑑、マイナンバー証明書類などが必要です。高額療養費は窓口で全額支払い、後日保険者に申請して払い戻しを受ける方法と、事前に認定証を提示する方法があります。
1. 高額療養費制度の概要と自己負担限度額
高額療養費制度は、医療費の自己負担が一定額を超えた場合に、その超過分を払い戻す制度です。この制度を利用することで、毎月の医療費の自己負担を限度額まで抑えることができます。自己負担限度額は、年齢と所得によって異なり、70歳以上の方は、病院、診療所、歯科、調剤薬局にかかった費用を合算して計算されます。70歳以上の方には、外来診療のみの上限額も設定されています。計算例として、70歳未満のAさんが医療費150万円の3割負担(45万円)の場合や、70歳以上のBさんが放射線治療のため通院し、医療費50万円の2割負担(10万円)の場合などが示されていますが、外来のみの限度額は12,000円なので、窓口での支払いは12,000円となります。保険適用外の医療費(差額ベッド代や食事代など)は、高額療養費制度の対象外である点に注意が必要です。過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる可能性があります。
2. 所得区分の 認定証 の取得と提示
高額な医療費の支払いを予定している場合、事前に『認定証』(70歳未満の方は限度額適用認定証、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担限度額認定証)を、加入している保険者に申請することで、窓口での支払いを自己負担限度額まで抑えることができます。この認定証を医療機関の窓口に提示することで、入院・外来診療にかかわらず、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます(差額ベッド代や食事代は除く)。認定証の申請には、保険証、印鑑、必要に応じてマイナンバーを証明する書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など)などの書類が必要です。国民健康保険の場合は、世帯主のマイナンバーを証明する書類が必要となる場合もあります。70歳以上で所得が一般、現役並みの方は、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになります。認定証の有効期限は保険者によって異なるため、各保険者へ問い合わせる必要があります。
3. 高額療養費の事後申請手続き
窓口で医療費の自己負担分をいったん全額支払い、後日保険者に申請することで払い戻しを受ける方法もあります。この手続きは、医療機関にかかった翌月以降に行い、払い戻しには通常申請から約3ヶ月かかります。申請は診療を受けた翌月の初日から2年以内に行う必要があります。申請に必要な書類などは、保険者によって異なる可能性がありますので、事前に確認することをお勧めします。高額療養費の算定外の費用として、入院時の食事代などが挙げられており、これらの費用は払い戻しの対象となりません。国民健康保険の場合は、市区町村によって制度の実施の有無、実施内容(貸付を受けられる金額など)、窓口が異なるため、市区町村の国民健康保険担当課に問い合わせる必要があります。
4. 高額療養費貸付制度と世帯合算
医療費が高額で一時的な支払いが困難な場合、高額療養費貸付制度を利用できます。これは、後で払い戻される高額療養費を前借りする制度で、貸付金額は保険者によって異なります(高額療養費の8~10割相当額)。また、世帯内で複数の人が同月に医療機関を受診した場合、または1人が複数の医療機関を受診した場合、自己負担額を世帯で合算することができます。合算した金額が自己負担限度額を超えた場合は、後日保険者に申請することで高額療養費が支給されます。ただし、75歳未満の方と75歳以上の方の医療費、夫婦共働きで個別に医療保険に加入している場合などは、世帯合算できない場合があります。入院時の食事負担や差額ベッド代などは、高額医療・高額介護合算療養費の対象外です。高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療と介護の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に超えた金額を支給する制度です。基準額は世帯員の年齢構成や所得区分によって異なります。
III.高額療養費制度に関するよくある質問
高額療養費制度の利用に関するよくある質問として、認定証の有効期限、月の途中で認定証が交付された場合の適用開始日、申請に必要な期間などが解説されています。世帯合算についても説明があり、世帯内で複数の人が医療機関を受診した場合、自己負担額を合算して計算できる場合があります。ただし、75歳未満と75歳以上の医療費、夫婦別々の保険加入など、世帯合算できないケースもあります。高額医療・高額介護合算療養費制度も紹介され、医療と介護の自己負担を合計して基準額を超えた場合に支給される制度です。
1. 認定証の有効期限と適用開始日
高額療養費制度における認定証の有効期限は、保険者によって異なりますので、各保険者へお問い合わせください。月の途中で認定証が交付された場合、その月の初日から遡って適用されますが、医療機関に認定証を提示しなければ利用できません。この場合、後日改めて高額療養費の申請手続きが必要になります。 高額療養費の申請は、医療機関にかかった翌月以降に行う必要があり、払い戻しには通常申請から約3ヶ月かかります。申請期限は、診療を受けた翌月の初日から2年以内です。 これらの手続きに関する詳細は、保険証に記載されている保険者へ問い合わせることで確認できます。
2. 高額療養費の事後申請と世帯合算
高額療養費制度では、窓口で医療費の自己負担分をいったん全額支払い、後日保険者に申請して払い戻しを受ける方法があります。 また、世帯合算についても説明があります。世帯内で複数の方が同月に医療機関を受診した場合、または1人で複数の医療機関を受診した場合は、自己負担額を世帯で合算できます。合算額が自己負担限度額を超えた場合、後日保険者に申請することで高額療養費が支給されます。ただし、75歳未満の方と75歳以上の方の医療費、夫婦共働きで個別に医療保険に加入している場合など、世帯合算できないケースもあります。入院時の食事負担や差額ベッド代などは、高額医療・高額介護合算療養費の対象外となります。高額療養費の貸付制度も存在し、医療費が高額で一時払い困難な場合、後から払い戻される高額療養費を前もって借りることができます。貸付金額は保険者によって異なります。
3. 高額医療 高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、同一世帯の同一医療保険加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。 対象となる世帯に70歳未満の方と70歳から74歳の方が混在する場合、まず70歳から74歳の方の自己負担額の合算額に自己負担限度額が適用され、次に残りの自己負担額と70歳未満の方の自己負担額の合算額に自己負担限度額が適用されます。基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分によって異なります。入院時の食事負担や差額ベッド代などは、この制度の対象外です。詳細は、加入している医療保険または介護保険の窓口にお問い合わせください。
IV.医療費の支払いに関する相談窓口
医療費の支払いで困った場合は、病院の医療相談室や会計担当者に相談できます。また、全国のがん診療連携拠点病院の相談支援センターも利用可能です。医療ソーシャルワーカーが相談に対応してくれる場合があります。
1. 病院内の相談窓口
医療費の支払いで困った場合、まず病院内の相談窓口を利用することを勧めています。多くの病院では「医療相談室」などの相談窓口を設置しており、医療ソーシャルワーカーが常駐している場合があります。医療ソーシャルワーカーは、医療費に関する相談だけでなく、様々な問題について相談に乗ってくれる専門職です。医療ソーシャルワーカーがいない場合でも、会計担当者に相談することが可能です。 医療相談室は、医療費の支払いに関する具体的な問題や、経済的な負担の軽減策について相談できる窓口として機能しています。 パンフレットでは、相談窓口の存在と活用を促すことで、患者や家族の不安軽減に繋げようとしています。
2. 病院以外の相談窓口
病院内に相談窓口がない場合や、より専門的な相談が必要な場合は、他の機関への相談も可能です。全国のがん診療連携拠点病院には、相談支援センターが設置されており、がんに関する情報提供や様々な相談に対応しています。この相談支援センターは、医療費の問題だけでなく、がん治療に関する様々な悩みや不安に対応する包括的な支援を提供する機関として位置付けられています。 経済的な負担軽減策として、高額療養費制度の利用を検討することも提案されています。 つまり、病院内外の複数の相談窓口を紹介することで、患者や家族が適切な支援を受けられるよう導くことを目的としています。
V.高額療養費貸付制度
一時的な支払い困難な場合のために、高額療養費貸付制度があります。これは、後で払い戻される高額療養費を事前に借りることができる制度です。金額は保険者によって異なります。
1. 高額療養費貸付制度の概要
医療費が高額で、一時的な支払いが困難な場合に利用できる制度として、高額療養費貸付制度が紹介されています。この制度は、後で払い戻される高額療養費を、事前に一部借りることができる仕組みです。借りることができる金額は、加入している保険者によって異なり、高額療養費の8~10割相当額とされています。この制度を利用することで、高額な医療費の支払いを一時的に猶予し、経済的な負担を軽減することができます。貸付金は、あくまで後に払い戻される高額療養費の前渡しという位置づけであり、借金ではないと説明されています。医療機関への支払いは、この貸付金と本人負担分を合わせて行う必要があります。
文書参照
- 高額療養費制度を利用されるみなさまへ (厚生労働省)
