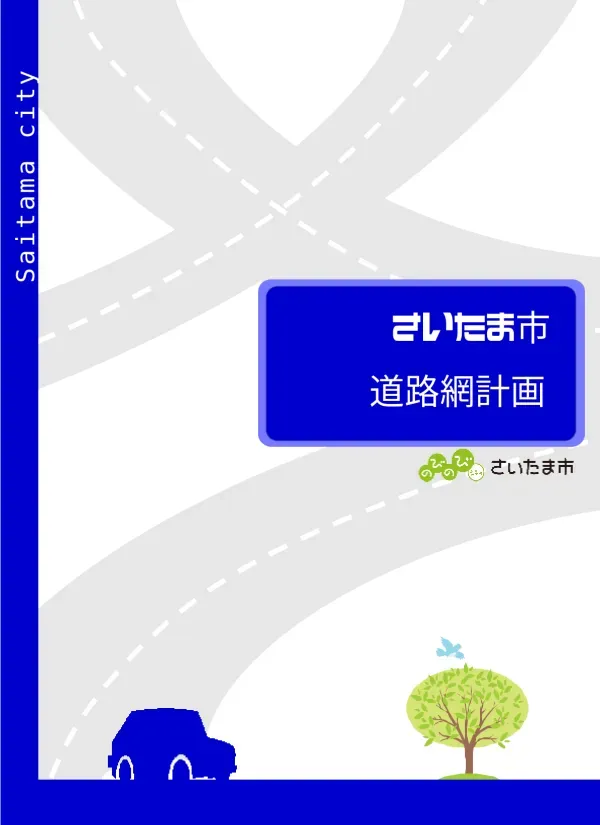
さいたま市持続可能な道路網計画
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.77 MB |
概要
I.さいたま市の持続可能なまちづくりと道路網計画
本計画は、少子高齢化と人口減少が進むさいたま市において、持続可能なまちづくりを実現するための道路網計画を策定したものです。都市計画道路の現状課題として、社会情勢の変化への対応、長期未整備道路の問題、計画の透明性確保を挙げ、これらへの解決策を提示しています。さいたま市は、平成24年3月時点で164路線、総延長約392kmの都市計画道路を有し、大宮、さいたま新都心、浦和などに集中しています。計画では、将来の都市構造(都市づくりの基本戦略)を踏まえ、コンパクトシティ化を目指し、必要性の高い道路を厳選、財政計画と連動した整備を進めることを提案しています。具体的には、都市計画道路の類型化による時間管理、市民参加によるパブリックコメントの活用、交通ネットワークの最適化などを盛り込んでいます。目標年次である平成42年(2030年)の夜間人口は約120万人と想定しています。
1. 持続可能なまちづくりの方向性と道路網計画の必要性
さいたま市では、少子高齢化、人口減少、財政逼迫といった社会経済状況の変化を踏まえ、「持続可能なまちづくり」の考え方を重視しています。その方向性として、「超高齢社会においても誰もが安心して快適に暮らせるまちづくり」、「多様な住宅・住環境の選択肢を提供できるまちづくり」、「都市の活力向上となる産業の活性化と人口減少時代における健全な財政の維持」が示されています。これらの実現には、まちづくりの重要な要素である道路網の検討が不可欠です。 既存の都市計画道路は、過去の急激な人口・経済集中を前提に計画・整備されてきましたが、現状の社会情勢変化に対応するため、見直しが必要となっています。地球環境問題への対応も求められ、環境負荷軽減の観点も考慮する必要があります。本計画は、これらの課題を整理し、将来の道路網計画の基本的な考え方を示すものです。平成24年3月現在の都市計画道路は164路線、総延長約392kmで、大宮、さいたま新都心、浦和などの中心部に集中しています。この現状を踏まえ、持続可能なまちづくりに資する道路網計画の策定を目指します。
2. 都市計画道路の現状と課題 社会情勢の変化への対応
少子高齢化や地球温暖化などの社会情勢の変化は、さいたま市の都市計画、ひいては都市計画道路にも大きな影響を与えています。従来、都市計画道路の変更は慎重に行われてきましたが、長期的な視点では都市の将来像も変化するため、柔軟な対応が求められます。国の都市計画運用指針も、必要に応じた変更を推奨しています。さいたま市においても、少子高齢化の進行や将来的な人口減少に対応した都市計画道路の見直しが必要不可欠です。見直しにあたっては、個々の路線の必要性を検証するだけでなく、都市全体として道路網がどのようにあるべきかを検討することが重要です。都市の将来像や土地利用計画との関係性を意識し、新たな道路網を構築し、定期的な見直しによって、社会情勢の変化に柔軟に対応できる体制を整える必要があります。
3. 都市計画道路の現状と課題 長期未整備道路の問題
さいたま市の都市計画道路には、昭和30年代に計画された路線が多く、未整備道路の約8割が40年以上前に計画されたものです。財源の制約から、既存インフラの維持・更新費用が膨らむ一方、新規整備への予算は減少しており、整備に時間がかかる路線が生じています。しかし、本市の一般道路の混雑時の平均旅行速度は政令市の中で最下位であり、渋滞緩和のためには道路整備が不可欠です。さらに、都市計画道路の計画区域内では建築行為が制限されており、長期未整備の計画区域では長期間にわたる制限が継続されています。これらの問題への対応として、長期未整備道路の増加抑制、財政状況を考慮した計画・整備が不可欠です。効果の高い道路を厳選し、優先順位をつけて整備を進めることで、限られた財源を有効活用する必要があります。財政計画と連動した計画、整備を進めることが重要です。
4. 都市計画道路の現状と課題 計画 事業の透明性と公正性の確保
都市計画道路の計画・整備にあたっては、計画地域住民だけでなく、広域的に影響を受ける地域住民への配慮も不可欠です。道路に対するニーズを踏まえ、より良い計画にするためには、情報公開と意見聴取が重要です。 パブリックコメントなどを活用し、市民参加型の計画づくりを進めることで、計画の透明性と公平性を確保する必要があります。道路計画は、単なる個別路線の計画ではなく、都市全体の計画と連携して行われるべきです。将来の都市像を明確にし、道路計画と他の分野の計画を調整することで、全体として機能する計画体系の構築が求められます。財政計画を考慮し、道路の必要性や事業化の見込みに合わせて、時間管理を行うことも重要です。さいたま市道路整備計画やさいたま市行財政改革推進プランなども参考にし、計画の進捗を管理する必要があります。
II.都市計画道路が抱える課題と対策
さいたま市の都市計画道路は、過去の急激な人口・経済集中を前提とした計画に基づいて整備されてきました。しかし、現在では少子高齢化、人口減少、財政逼迫などの社会情勢の変化により、見直しが必要となっています。具体的な課題として、社会情勢の変化への柔軟な対応、長期未整備道路の増加による問題、計画・事業の透明性・公正性の確保が挙げられます。対策としては、都市全体の交通ネットワークを再考し、必要性の検証、財政計画との連携による効率的な整備、市民参加による透明性の向上などが示されています。
1. 社会情勢の変化への対応 柔軟な道路網の形成
少子高齢化、地球温暖化、人口減少といった社会情勢の変化は、さいたま市の都市計画道路にも大きな影響を与えています。従来、都市計画道路は一度決定されると変更が困難でしたが、時代のニーズに対応するため、柔軟な見直しが必要となっています。国の都市計画運用指針も、必要に応じて変更を検討することを推奨しています。さいたま市においても、現状の社会情勢変化に対応するため、都市計画道路の見直しが必要です。この見直しは、個々の路線の必要性を検証するだけでなく、都市全体としての道路網のあり方を検討することが重要です。都市の将来像や土地利用計画との関係性を考慮し、新たな道路網を構築する必要があります。さらに、将来の社会情勢の変化にも対応できるよう、新たな道路網は定期的な見直しを行う必要があります。これは、持続可能な都市発展のための重要な要素となります。
2. 長期未整備道路の問題への対応 財政計画との連携
さいたま市の都市計画道路には、昭和30年代に計画された路線が多く、未整備道路の約8割が40年以上前に計画されたものです。財源の制約から、既存インフラの維持・更新費用が膨らむ一方で、新規整備への予算は減少傾向にあり、整備に時間がかかる路線が多く存在しています。しかし、本市の一般道路の混雑時の平均旅行速度は政令市の中で最下位であり、渋滞緩和のためには道路整備が不可欠です。都市計画法により、都市計画道路の計画区域内では建築行為が制限されますが、長期未整備の道路では長期間にわたる制限が続き、地域経済にも影響を及ぼしています。これらの問題への対応として、今後、長期未整備道路の増加を抑制し、財政状況が厳しい中でも必要な道路整備を着実に進める必要があります。そのためには、必要な道路を厳選し、効果の高いものから優先的に整備するなど、財政計画と連動した計画・整備を進めることが重要です。これは、限られた予算を効果的に活用するための戦略です。
3. 道路計画 事業の透明性と公正性の確保 市民参加の促進
都市計画道路の計画・整備にあたっては、計画地域住民だけでなく、広域的に影響を受ける地域住民への十分な配慮が必要です。道路に対するニーズを踏まえ、より良い計画とするためには、これまで以上に情報を公開し、広く意見を聴取することが重要です。そのため、計画の検討過程において、パブリックコメントなどの手法を用いて、市民参加型の計画づくりを進める必要があります。これにより、計画の透明性と公平性を確保し、住民の理解と協力を得ながら事業を進めることができます。計画の段階から市民の意見を反映させることで、より地域の実情に合った道路計画を実現し、持続可能なまちづくりに貢献します。また、計画情報については、Webサイトや説明会などを通じて積極的に情報提供を行い、市民の理解を促進する必要があります。
III.将来の道路網計画と検討プロセス
将来の道路網計画は、都市計画の目標と都市づくりの基本戦略(将来都市構造のあり方)に整合性を図り、持続可能なまちづくりに貢献するものです。検討プロセスでは、路線の評価、ネットワークパフォーマンスの検証、予定路線の抽出などが行われました。評価指標には、拠点間の連携強化、ボトルネック交差点の解消、移動時の安全性の向上、公共交通との連携などが含まれています。自動車交通量の増加などの不確実性を考慮し、柔軟な対応が可能な計画となっています。高速埼玉中央道路(与野以北)の整備状況なども考慮されています。計画では、道路整備量に応じた複数のケース(ケースA, B, C, C+, C-)を設定し、平均旅行速度、移動時間、CO2排出量などを指標として、最適な道路網を検討しています。
1. 望ましい道路網の検討 路線評価と将来交通流への影響分析
本計画では、都市構造と道路の役割・機能の2つの観点から路線を評価し、さいたま市に適した道路網か検討しています。評価においては、拠点のあり方、骨格的な交通体系、骨格的な土地利用のあり方を考慮した4つの指標を設定しました。具体的には、適切な市街地の誘導、拠点間の相互補完、ボトルネック交差点の解消、移動時の安全性の向上、救急医療施設へのアクセス性などを評価基準としています。路線評価の結果をまとめ、廃止候補路線を廃止した場合の将来交通流への影響を検証しました。また、将来起こりうる様々な状況を想定し、それらへの対応についても検討しています。これは、不確実な将来を見据えた上で、柔軟な対応が可能な道路網計画を策定するために行われています。評価結果に基づき、持続可能なまちづくりにそぐわない路線は、大胆に廃止することを検討しています。
2. ネットワークパフォーマンスの検証 平均旅行速度 移動時間 CO2排出量の分析
将来の自動車交通の流れに対して、計画された道路網が適切かどうかを検証するために、ネットワークパフォーマンスの分析が行われています。この検証では、「産業力の強化」、「都市活動の低炭素化」、「良好な生活環境の形成」という目標達成のための代理指標として、市全域の平均旅行速度、移動時間、CO2排出量を用いています。これらの指標と道路整備量の関係性を分析することで、道路網整備の効果を定量的に評価しています。ケーススタディとして、整備量を変化させた複数のケース(ケースA, B, C, C+, C-)を設定し、それぞれのケースにおける平均旅行速度の変化を比較検討しています。ケースBとケースCを比較した結果、走行性に大きな違いは見られませんでした。また、目標年次における自動車分担率増加が見込まれるものの、様々な交通施策を総合的に実施し、現況並みの自動車分担率を維持できれば、未整備都市計画道路を全て整備した場合と同程度の走行速度が期待できるという結果が得られています。
3. 予定路線の抽出 不確実性への対応と将来的な整備可能性の確保
将来人口の見込みや幹線道路の整備進捗状況など、路線評価の前提条件には不確実性が含まれています。そこで、将来の自動車交通量の増加など、想定外の状況を考慮し、廃止候補路線の中でも、前提条件が変化した場合に整備の意義が生じる路線を「予定路線」として位置づけています。これは、将来的な人口増加や自動車分担率の増加といった不確実な要因を考慮し、必要となる可能性のある路線を事前に特定しておくことで、柔軟な対応を可能にするための措置です。具体的には、高速埼玉中央道路(与野以北)が整備されない場合に備え、大谷場高木線(指扇〜佐知川)を予定路線として位置づけています。予定路線は、都市計画決定前の段階から建築行為を制限することなく、将来的に道路を整備する可能性のある場所を示すものです。計画区域は定めず、概ねの位置を示すことで、将来の状況変化に柔軟に対応できるようになっています。平成42年(2030年)の自動車利用分担率増加が見込まれますが、交通施策によって現況並みに維持できれば、ケースC-のように全線整備と同等の平均旅行速度が期待できると分析されています。
4. 道路網の検討結果と今後の見直し 時間管理プログラムと5年ごとの見直し
ネットワークパフォーマンスの検証と予定路線の抽出による検討結果では、全線整備と路線評価結果から求められる道路網の走行性に大きな違いはないと結論づけられています。計画では、これらの取り組みをプログラムで時間管理し、市民の意見も反映することで、計画や事業の透明性・公平性を確保していきます。道路網計画は、さいたま市都市計画マスタープランの見直し時期に合わせて、おおむね5年ごとに社会経済状況の変化や道路交通状況などを考慮し、見直しを行う予定です。現時点で着手予定が定まっていない路線については、優先順位を見極め、代替措置の可能性や財源を考慮しながら、多様な実現手法を検討していきます。また、今回道路網計画に位置付けられていない都市計画道路については、地元の合意形成の後、廃止に向けた取り組みを進めていきます。
IV.計画の透明性と今後の見直し
本計画は、市民参加によるパブリックコメントを積極的に活用し、計画の透明性と公平性を確保することを目指しています。計画情報はWebサイトや説明会を通じて公開され、市民からの意見を反映していきます。また、さいたま市都市計画マスタープランの見直し時期に合わせて、おおむね5年毎に見直しを行うことで、社会経済状況の変化や道路交通状況の変化に柔軟に対応していきます。計画に位置付けられていない都市計画道路については、地元の合意形成後、廃止に向けた手続きを進めていく予定です。
1. 開かれた計画づくりの推進 情報公開と市民参加
計画の段階から開かれた計画づくりを進めるためには、市民の積極的な参加が不可欠です。計画の検討にあたっては、より多くの情報を公開し、市民の意見を広く聴取することが重要です。計画情報は、ウェブサイトや説明会などを通じて積極的に提供されます。これは、市民が計画内容を十分に理解し、意見を述べる機会を確保するためです。市民からの意見は、計画に反映されるよう努め、計画の透明性と公平性を確保していきます。 市民参加型の計画づくりによって、より地域の実情に合った道路網計画を実現し、持続可能なまちづくりに貢献することを目指しています。この取り組みは、単に情報を公開するだけでなく、市民の意見を真摯に受け止め、計画に反映させることを通じて、信頼性の高い計画を目指しています。
2. 道路計画 整備の時間管理 類型化と優先順位付け
長期未整備となっている都市計画道路については、さいたま市道路整備計画やさいたま市行財政改革推進プランなどの財政計画を考慮し、道路の必要性や事業化の見込みに応じて時間管理を行うための類型化を進めます。これは、限られた予算の中で効果的な道路整備を行うための重要な取り組みです。それぞれの路線の必要性や実現可能性を評価し、優先順位を決定します。優先順位の高い路線から順次整備を進めることで、限られた資源を効果的に活用し、整備の遅れを解消していきます。今後整備手法を検討する路線については、優先度を見極め、代替措置の可能性や財源を考慮しながら、多様な実現手法を検討していきます。これは、柔軟な対応と効率的な予算執行を目的としています。
3. 今後の見直し 5年ごとの定期的な見直しと廃止に向けた取り組み
本計画は、さいたま市都市計画マスタープランの見直し時期に合わせて、おおむね5年ごとに社会経済状況の変化や道路交通状況などを考慮し、定期的な見直しを行います。これは、常に変化する社会情勢に柔軟に対応し、計画の有効性を維持するためです。 見直しにおいては、市民からの意見も積極的に取り入れ、計画の改善に役立てていきます。計画に位置付けられていない都市計画道路については、地元住民との合意形成を図り、その後、都市計画手続きの検討を進め、廃止に向けた取り組みを進めていきます。これは、不要となった道路を効率的に整理し、資源の有効活用を図るためです。 計画の透明性と公平性を確保し、持続可能な道路網の維持管理を行うために、継続的な見直しと改善を繰り返すことが重要です。
