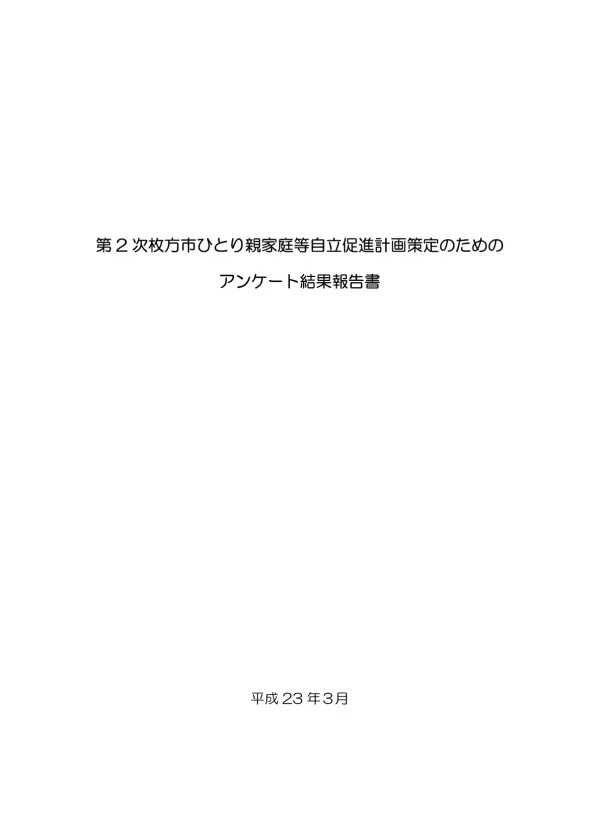
ひとり親家庭実態調査報告書
文書情報
| 会社 | 枚方市 |
| 場所 | 枚方市 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 771.38 KB |
概要
I.枚方市ひとり親家庭等自立促進計画に関する調査概要
本調査は、枚方市において平成23年3月に期限を迎える「枚方市ひとり親家庭等自立促進計画」の後継となる「第2次計画」策定のための基礎資料を得ることを目的として実施されました。調査対象は、児童扶養手当を受給する【ひとり親家庭】(【母子家庭】、【父子家庭】を含む)と【寡婦】です。調査内容は、これらの世帯の現状把握に焦点を当て、経済状況、就労状況、子育てに関する課題やニーズ、必要な【自立支援】、【就業支援】、【子育て支援】策などを多角的に分析しています。特に、【寡婦】については、枚方市母子寡婦福祉会の協力を得て実施されました。
1. 調査の目的と実施方法
この調査は、枚方市が平成23年3月に期限を迎える「枚方市ひとり親家庭等自立促進計画」の次期計画である「第2次計画」を策定するための基礎資料を得ることを目的として実施されました。計画には、母子家庭、父子家庭、寡婦の自立促進のための生活面・就業面の支援策が盛り込まれる予定です。そのため、ひとり親家庭等の現状、具体的なニーズ、課題などを把握することが調査の主要な目的となっています。調査の実施方法は、主に2通りです。1つは、児童扶養手当関連の届出のために市役所を訪れたひとり親家庭の方々に、設置された回収箱にアンケート用紙を投入してもらう方法です。回収箱は、子育て支援室、年金児童手当課、医療助成課に設置されました。もう1つは、寡婦を対象とした調査で、枚方市母子寡婦福祉会の協力を得て、会員にアンケート用紙を配布する方法がとられました。この調査によって得られたデータは、計画策定以外の目的には使用されません。また、個人情報や回答内容は厳重に管理され、外部に漏洩することはありません。
2. 調査票の構成と回答方法
調査票には、様々な質問項目が含まれており、回答方法は質問によって異なります。選択肢から一つを選ぶもの、複数選択できるもの、自由記述式のものなど、多様な形式が用いられています。例えば、複数回答を許容する質問では、選択肢の数に制限がある場合と、いくつでも選択できる場合が明示されています。図表において「N」は回答者数を表し、「複数回答」の記載がある場合は、複数回答が許容されていることを示しています。例えば、「複数回答2」とあれば、選択肢から2つまで○をつけることができます。回答者への配慮として、答えたくない質問には回答しなくても構わない旨が明記されています。回答済みの調査票は、指定された窓口または母子寡婦福祉会役員に提出するよう指示されています。回収期限も設定されており、期限内に提出するよう依頼されています。調査対象者は、児童扶養手当を受給している世帯の中から無作為に抽出されたひとり親家庭と寡婦です。調査は、平成22年8月1日現在の状況を反映するよう依頼されています。
II.ひとり親家庭の就労状況と課題
【母子家庭】では、無職が17.0%、就業者の職種は「事務的な仕事」が最も多く、次いで「専門知識・技術を生かした仕事」です。【父子家庭】では、無職以外の方は「専門知識・技術を生かした仕事」が最多でした。多くの【ひとり親家庭】が【経済的支援】を必要としており、特に【養育費】を受け取れていない世帯が多く、「相手方に支払う意思がない」ことが主な理由となっています。また、仕事を探す際に「時間・曜日について条件の合う仕事がなかった」、「子どもの【保育】の手立てがなかった」などの課題が浮き彫りになりました。
1. ひとり親家庭の就業状況
調査結果によると、母子家庭における無職率は17.0%となっています。就労している母子家庭の職種別内訳では、「事務的な仕事(一般事務、経理事務、医療事務など)」が29.5%と最も多く、次いで「専門知識・技術を生かした仕事(教員、ホームヘルパー、看護師、システムエンジニアなど)」が25.3%、「営業・販売の仕事(商店店員、セールス、外交員など)」が22.1%となっています。一方、父子家庭では、無職以外の方の職種は「専門知識・技術を生かした仕事(教員、ホームヘルパー、看護師、システムエンジニアなど)」が24.2%と最も多く、次いで「製造・技能・労務の仕事(製造技能工、建設技能工など)」が21.2%となっています。これらのデータから、ひとり親家庭の就労状況は、母子家庭と父子家庭で若干の違いが見られるものの、安定した雇用を得ることが課題であることが伺えます。特に、専門性の高い仕事に従事する割合が高い一方で、事務職や営業・販売職も一定数存在することが分かります。父子家庭のデータは母子家庭に比べてサンプル数が少ないため、より詳細な分析にはさらなるデータが必要となるでしょう。
2. 無職になった理由
調査では、ひとり親家庭になった直後に無職になった、もしくは無職を続けた理由についても分析されています。母子家庭の場合、「自分が働ける健康状態ではなかった」が39.1%と最も多く、次いで「時間・曜日について条件の合う仕事がなかった」(27.3%)、「子どもの保育の手立てがなかった」(24.5%)となっています。これらの結果から、健康問題、仕事と育児の両立の困難さ、保育サービスの不足などが、無職となる主な要因であることが分かります。 その他の理由としては、「仕事の探し方がわからなかった」、「収入について条件の合う仕事がなかった」、「年齢制限のため仕事がなかった」、「仕事に必要な専門知識や資格がなかった」、「子どもが問題を抱えていた(健康上の不安など)」、「自分が問題を抱えていた(離婚調停など)」、「仕事をする気持ちになれなかった」、「他の家族の世話や介護をしなければならなかった」、「働く必要がなかった」などが挙げられています。これらの多様な要因に対応するためには、個々の状況に応じたきめ細やかな支援策が不可欠であることが示唆されます。
3. 養育費に関する課題
養育費の受給状況についても調査が行われ、母子家庭においては、かつて養育費を受け取っていたものの、現在は受け取っていない世帯で、「相手方に支払う意思がない」が51.7%と最も多く、次いで「相手方に経済的な問題がある」が45.7%、「子どもや自分が相手方と関わりたくない」が12.1%となっています。この結果から、養育費未払いの主な原因は、父親側の支払い意思の欠如と経済的な困窮であることが分かります。また、親子関係の悪化も無視できない要因の一つであることが示唆されます。これらの状況を改善するためには、養育費の確実な支払いを促すための制度的支援、経済的な支援、そして親子関係修復のためのサポート体制の構築が必要と考えられます。養育費問題は、ひとり親家庭の経済的な自立を阻む大きな要因の一つであり、早急な対策が求められます。
III.住居に関する課題
【ひとり親家庭】と【寡婦】双方において、「家賃が高い」ことが賃貸住宅を探す上での最大の【困りごと】です。「府営住宅・市営住宅になかなか入れない」という声も多く聞かれ、住宅確保の困難さが示唆されました。
1. ひとり親家庭の賃貸住宅に関する課題
調査では、転居経験のあるひとり親家庭を対象に、賃貸住宅を探す際および入居する際の困難さが尋ねられました。その結果、最も多くの割合を占めた課題は「家賃が高い」であり、56.3%にのぼりました。次いで「府営住宅・市営住宅になかなか入れない」(31.9%)、「保証金(敷金等)などの一時金が確保できない」(24.4%)といった経済的な問題が大きな障壁となっていることが明らかになりました。これらの結果から、ひとり親家庭にとって、住宅の確保は経済的な負担が大きく、公的住宅の不足も深刻な問題であることがわかります。特に、家賃の高騰は多くの家庭にとって大きな負担であり、低所得のひとり親家庭にとって安定した住居を確保することは困難な状況にあると考えられます。保証金の確保についても、初期費用を捻出することが難しい世帯が多く、より現実的な入居支援策の必要性が示唆されています。
2. 寡婦の賃貸住宅に関する課題
寡婦を対象とした調査でも、賃貸住宅に関する課題が明らかになっています。寡婦にとって、賃貸住宅を探す際、入居する際の最大の困りごとは「家賃が高い」ことで、12.0%がこれを挙げています。次いで「府営住宅・市営住宅になかなか入れない」(6.3%)、「希望する場所(駅・職場に近い)に住宅が見つからない」(5.6%)といった問題が挙げられています。これらの結果から、寡婦もひとり親家庭と同様に、高額な家賃や公的住宅の不足、立地の制約など、住宅確保において多くの困難を抱えていることが分かります。特に、希望する場所に住宅が見つからないという点は、通勤・通学の利便性や生活環境の面から、寡婦の生活の質に大きく影響を与えていると考えられます。これらの課題を解決するためには、家賃補助制度の充実や公的住宅の供給拡大、そして希望する場所に物件を見つけやすいような情報提供体制の整備が必要となります。
IV.望まれる支援策
【ひとり親家庭】からは、子育てに関する支援として「学童保育の拡充」、「病気の子供の世話」に関する支援、「【資格取得】のための経済的援助」や「就業支援」などが強く求められています。【寡婦】も同様のニーズに加え、「パソコンスキル習得」の支援への希望が高い傾向が見られました。
1. 子育てに関する望ましい支援策
調査では、子どもを育てながら働き続けるための支援策として、子育てに関する支援策の希望について尋ねています。父子家庭を対象とした調査結果によると、最も要望が多かったのは「学童保育の対象や保育時間が延長されること」で、回答者の28.6%を占めました。次いで「子どもの世話などで必要なときの休暇制度の充実」(25.7%)、「子どもが病気のときに、子どもの世話をしてくれる人や場所」(22.9%)といった、時間的な制約や子供の病気への対応に関する支援が求められています。これらの結果から、父子家庭においては、子どもの保育に関する制度の充実と、育児と仕事の両立を支援する柔軟な就労環境の整備が喫緊の課題であることが分かります。特に、学童保育の拡充や長時間保育の提供、病気の際に子どもを預けられる場所の確保などは、多くの家庭にとって切実なニーズであると言えるでしょう。 これらのニーズに対応するためには、行政による保育サービスの拡充や企業における育児支援制度の充実が不可欠です。
2. 技能 資格習得に関する望ましい支援策
父子家庭を対象とした調査では、技能や資格の習得に関する支援策についても質問が行われました。その結果、「訓練受講などへの経済的援助」が37.1%と最も多く、次いで「技能や資格習得後の一貫した就業支援」(28.6%)という回答が得られました。このことから、父子家庭においては、資格取得のための費用負担軽減と、資格取得後の就職活動を支援する仕組みの構築が強く求められていることがわかります。経済的な援助は、資格取得を目指す大きな障壁を解消する上で非常に重要であり、訓練費用や教材費の補助などが有効な支援策として考えられます。また、資格取得後も就職活動がスムーズに進むよう、就職支援機関との連携強化や就職相談窓口の設置なども効果的でしょう。これらの支援策によって、父子家庭における就労機会の拡大と経済的自立の促進が期待されます。
3. その他の支援策に関する要望
調査では、上記以外にも様々な支援策に関する要望が寄せられています。例えば、保育所の入所困難さ、子どもの世話をしてくれる人の不足、就職活動と保育所の入所を同時に行うことの困難さ、児童扶養手当や子ども手当の将来的な不安、土日祝日の相談窓口の不足などが挙げられています。これらの課題は、個々の状況やニーズに合わせたきめ細やかな支援策が必要であることを示しています。 さらに、父子家庭からは、ひとり親家庭を採用してくれる企業の増加、収入の不安定さへの対応、資格取得のための学習と仕事の両立の困難さといった課題も指摘されています。これらの問題に対処するためには、企業側の理解促進、経済的な支援制度の充実、学習と仕事の両立を支援する制度の整備など、多角的なアプローチが必要となります。
V.調査対象と回答者数
調査は、児童扶養手当受給世帯から無作為抽出した【ひとり親家庭】と【寡婦】を対象に行われました。具体的な回答者数は本文からは読み取れませんでしたが、平成21年の年間総収入に関するデータではN=1,015と記載されています。これは、全ての回答者数を表しているとは限りません。
1. 調査対象世帯
本調査の対象は、児童扶養手当を受給している世帯の中から無作為に抽出されたひとり親家庭です。母子家庭、父子家庭の両方が含まれており、さらに寡婦についても、枚方市母子寡婦福祉会の協力を得て会員を対象に調査が行われました。調査は、平成22年8月1日時点の状況を把握することを目的としており、対象世帯の属性や生活実態を詳細に把握することで、より効果的な支援策の検討に役立てることを目指しています。調査対象の選定にあたっては、児童扶養手当の受給状況を基準とすることで、経済的に支援を必要とする世帯を効率的に抽出することを意図しています。この選定基準により、調査結果の精度を高め、政策立案に役立つ実効性のあるデータの収集を目指しています。調査結果の活用は、「第2次ひとり親家庭等自立促進計画」の策定に限定されており、その他の目的には使用されません。
2. 回答者数に関する情報
調査報告書には、具体的な回答者数は明記されていませんが、平成21年の年間総収入に関するデータにおいて、「N=1,015」という記述があります。この数値が全体の回答者数を示しているのか、特定の質問項目への回答者数なのかは本文からは明確に判断できません。調査の実施にあたり、母子家庭、父子家庭、寡婦のそれぞれを対象にアンケートが行われており、それぞれの回答者数については、個別の集計結果が示されている可能性があります。また、寡婦に関する調査は枚方市母子寡婦福祉会の協力を得て実施されているため、その会員数も回答者数に関連する重要な情報と考えられます。しかしながら、これらの具体的な数値は本文からは読み取れないため、より詳細な回答者数の把握には、調査報告書の他の部分を参照する必要があります。 調査データの正確性と信頼性を確保するために、回答者数の正確な把握と、その内訳に関する情報も重要です。
