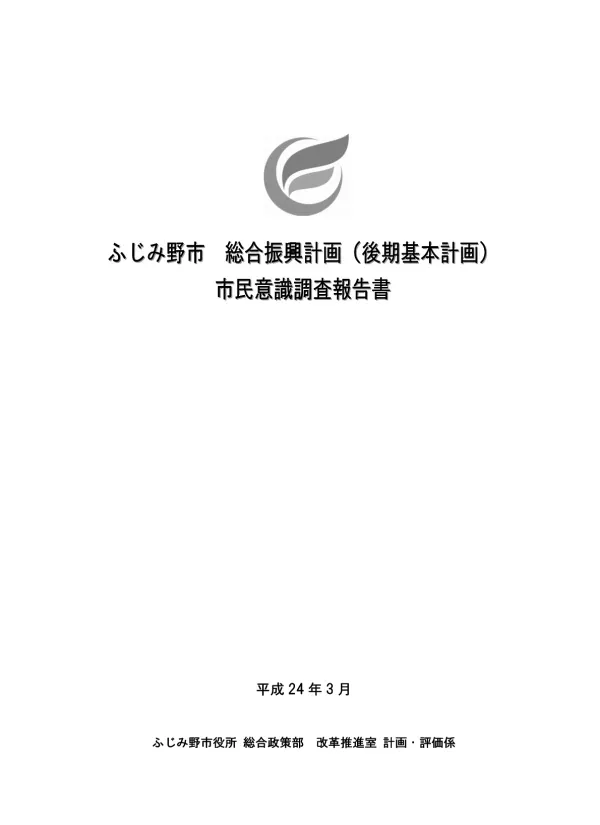
ふじみ野市総合振興計画:市民意識調査報告書
文書情報
| 著者 | ふじみ野市役所 |
| 場所 | ふじみ野市 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 8.31 MB |
概要
I.ふじみ野市市民意識調査 市民のニーズとまちづくりへの満足度
本調査は、埼玉県ふじみ野市における市民意識調査の結果をまとめたものです。20歳以上の市民3,000名を対象に、まちづくりへの満足度、重要度、そして具体的な政策ニーズについてアンケートを実施しました。 分析の結果、市民は健康・福祉サービスの充実(保健医療サービス、高齢者福祉、子育て支援など)、安全・安心なまちづくり(防犯・防災、交通安全など)、生活基盤の整備(交通網、都市空間、環境整備など)を特に重要視していることが明らかになりました。特に、高齢者への支援、保育サービスの充実、安心して暮らせるまちづくりへの要望が強く、これらの分野への政策強化が求められています。満足度が高い項目としては「循環型社会の推進」、「広域行政の推進」、「生活基盤の整備」が挙げられ、低い項目には「交通網の整備・充実」、「行財政改革の推進」、「快適で魅力ある都市空間の整備」が含まれていました。中学校区別の分析では、各地区で異なるニーズや課題が確認されました。
1. まちづくりへの満足度と重要度
アンケート調査では、ふじみ野市のまちづくりに対する市民の満足度と重要度が調査されました。満足度が高い項目として、1位「循環型社会の推進」、2位「広域行政の推進」、3位「生活基盤の整備」が挙げられました。これらの政策は、環境問題への意識の高まりや、広域的な連携による行政サービスの向上への期待、そして生活に直結するインフラ整備へのニーズの高さを反映していると考えられます。一方、満足度が低い項目として、23位「交通網の整備・充実」、22位「行財政改革の推進」、21位「快適で魅力ある都市空間の整備」が挙げられました。交通渋滞や公共交通機関の不便さ、行財政改革への理解不足、都市空間の整備不足などが、市民の不満につながっている可能性があります。重要度については、「健康づくりの推進と医療の充実」、「安心して暮らせるまちづくりの推進」、「社会保障の充実」が上位を占め、市民の健康、安全、安心への強いニーズが示されました。これらの結果から、市民は生活の質の向上に直結する政策を重要視していることが分かります。
2. 中学校区別分析 地域特性に応じたニーズ
居住地域の中学校区別に満足度と重要度を分析した結果、地域によってまちづくりに対する評価やニーズに違いがあることが明らかになりました。例えば、福岡中学校区では「社会保障の充実」と「生活基盤の整備」への満足度が高く、「快適で魅力ある都市空間の整備」への満足度が低い一方、葦原中学校区、花の木中学校区でも「快適で魅力ある都市空間の整備」への不満が目立ちました。大井中学校区では「快適で魅力ある都市空間の整備」への満足度が高く、大井西中学校区では「生涯学習の推進」、「学校教育の充実」、「市民文化の振興と文化財の保存・活用」、「安心して暮らせるまちづくりの推進」への満足度が高い傾向が見られました。これらの結果は、各地域における人口構成、地域特性、既存のインフラ整備状況などによって、市民のニーズや満足度に違いが生じていることを示唆しています。地域ごとの具体的な課題や要望を詳細に分析し、地域特性に応じたまちづくり政策を展開していくことが重要です。
3. 魅力あるふじみ野市像 市民が求める優先事項
魅力あるふじみ野市像に関するアンケートでは、「事故や犯罪が少なく災害にも強い安全なまちづくり」が58.0%と最も高い支持を得ました。これは、市民の安全・安心への強い意識の高さを示しています。次いで、「医療体制や健康づくりの充実など市民の健康支援」が42.9%、「誰もがその人らしく安心して生活が送れるような福祉の充実」が42.1%と、健康と福祉に関する政策へのニーズが非常に高いことが明らかになりました。これらの項目は、高齢化社会における課題を反映しており、高齢者だけでなく、子育て世代を含む幅広い年齢層の市民が、安全で健康的な生活環境を望んでいることが分かります。また、これらの結果から、ふじみ野市が目指すべき方向性として、安全・安心、健康・福祉を重視したまちづくりが重要であることが示唆されます。具体的には、防災対策の強化、医療・福祉サービスの充実、高齢者や子育て世代へのきめ細やかな支援など、市民の生活の質を高める政策を優先的に展開していくべきです。
4. 市民の声 多様な意見と課題
自由記述欄には、市民から様々な意見や要望が寄せられました。中には、市政への関心の低さや情報不足を指摘する声や、行政サービスの改善を求める声、地域コミュニティの活性化を訴える声などがありました。また、旧上福岡市と旧大井町との合併後も、地域間の連携強化が課題として挙げられており、一体感のあるまちづくりが求められています。その他、財政状況の厳しさや、行政の効率化、市全体の活性化のための施策、具体的なまちづくりの方向性の提示など、多岐にわたる意見が寄せられました。これらの意見を踏まえ、市民参加を促進し、より透明性が高く、市民ニーズを反映した市政運営を行うことが重要です。特に、情報発信の強化や、市民参加しやすい仕組みづくり、そして財政状況を踏まえた上で、効果的で効率的な政策の選択と集中が求められます。
II.高齢者の安心と健康 優先すべき施策
高齢化社会における課題として、高齢者への支援が喫緊の課題となっています。アンケートでは、「健康診断などの保健医療サービスの充実」、「高齢者や障がいのある方の入所施設の充実」、「住民が共に支え合う仕組みづくりへの支援」が2割以上の回答を得ており、これらの政策が優先されるべきであることが示唆されました。さらに、「ひとり暮らしの高齢者への支援」、「在宅・施設福祉サービスの充実」、「医療体制の充実」も2~3割を越える高い優先度を示しました。 市内循環バスの今後については、「高齢者や障がい者など対象を特定したタクシーチケット交付などの運賃補助」への転換が最も支持されていました。
1. 高齢者の住み慣れた地域での生活支援
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、何が必要かという問いに対して、アンケートでは「健康診断などの保健医療サービスの充実」、「高齢者や障がいのある方の入所施設の充実」、「住民が共に支え合う仕組みづくりへの支援」がそれぞれ2割を超える回答を得て、高い優先度を示しました。これは、高齢化が進む社会において、高齢者の健康維持、介護サービスの充実、そして地域社会全体による支え合いが不可欠であるという認識が、多くの市民に共有されていることを示しています。具体的なサービスとしては、定期的な健康診断の機会の提供、高齢者向け入所施設の増設・充実、地域住民による見守り活動の支援などが挙げられます。これらのサービスの質と量を向上させることで、高齢者の生活の質を向上させ、安心して暮らせる環境を整備することが重要です。また、高齢者のニーズに合わせた、柔軟で多様なサービス提供体制の構築も必要不可欠です。
2. 高齢社会における福祉サービスの充実
高齢社会を迎えるにあたり、市民は「ひとり暮らしの高齢者への支援」、「在宅・施設福祉サービスの充実」、「医療体制の充実」を優先すべき事項として挙げ、2~3割以上の回答を得ました。これは、高齢化の進展に伴い、単独世帯の高齢者や要介護高齢者の増加が社会問題化しており、これらの層に対する具体的な支援策が求められていることを示しています。具体的には、ひとり暮らしの高齢者への定期的な訪問、安否確認サービスの提供、在宅介護サービスの拡充、介護施設の整備、そして質の高い医療サービスの提供体制の強化などが挙げられます。また、高齢者が地域社会に積極的に参加できるような機会の創出や、世代間交流の促進も重要です。これらの施策を通じて、高齢者が健康でいきがいのある生活を送れるよう、包括的な支援体制の整備が求められます。
3. 市内循環バスの課題と今後のあり方
高齢者の生活を支える交通手段として、市内循環バスの今後のあり方についてもアンケート調査が行われました。その結果、「自主運行バスは廃止し、高齢者や障がい者など対象を特定したタクシーチケット交付などの運賃補助に切り替えるべき」という意見が40.1%と最も多く、次いで「財政負担の大きい自主運行バスはやめ。デマンド型タクシーなど別のやり方に変えるべき」が37.9%と、現状のバス運行維持に疑問を呈する意見が多数を占めました。「財政負担の大小にかかわらず利用者のある限り、現状のまま続けるべき」という意見は25.0%にとどまりました。性別による違いとしては、男性の方が「タクシーチケットへの切り替え」や「デマンド型タクシーへの移行」を支持する傾向が高い一方で、年代別では20代は現状維持を、30代は現状維持とデマンド型タクシーへの移行を同率で支持するなど、年代によっても意見が分かれていることが示されました。これらの結果から、高齢者の移動手段確保をどのように効率的かつ効果的に実現していくかが今後の課題となります。
III.子育て世代の安心 保育サービスの充実が最重要
子育て支援に関する質問では、「乳児保育、延長保育、一時保育などの保育サービスの充実」が40%と最も多く、圧倒的な支持を得ています。続いて「公園や児童センターなど子どもが安全に安心して遊べる場の整備」、「子どもが安心して登下校できる交通安全対策、防犯対策、教育・保育施設の耐震化」、「産科・小児科医療の充実」が20%前後と高い優先度を示しました。これらの結果から、保育サービスの充実が、安心して子育てできる環境を作る上で最も重要な要素であることが分かります。
1. 保育サービスの充実 圧倒的なニーズ
安心して子育てをする上で優先すべき事項として、40%もの回答者が「乳児保育、延長保育、一時保育などの保育サービスの充実」を挙げました。これは、子育て世帯にとって保育サービスの不足が大きな課題であり、その充実が喫緊の課題であることを示しています。特に、乳幼児期の保育ニーズは高く、年齢や状況に応じた柔軟な保育サービスの提供が求められていると言えるでしょう。この高いニーズは、共働き世帯の増加や、育児負担の軽減を求める声の大きさを反映していると考えられます。保育所の定員不足や待機児童問題の解消、保育の質の向上、そして保育料の負担軽減など、具体的な対策が求められています。 保育サービスの充実によって、親は安心して仕事に就くことができ、子供の健やかな成長を支えることができる環境が整備されるでしょう。
2. 子どもの安全と安心な環境整備
保育サービスの充実以外にも、「公園や児童センターなど子どもが安全に安心して遊べる場の整備」が20.9%、「子どもが安心して登下校できる交通安全対策、防犯対策、教育・保育施設の耐震化」が20.6%と、子どもの安全・安心を確保するための環境整備も重要な課題として挙げられています。これは、子どもの安全に関する不安が、多くの親たちの間で共有されていることを示しています。具体的には、遊べる公園の整備や増設、児童センターの充実、通学路の安全対策、防犯カメラの設置、そして学校や保育施設の耐震化などが挙げられます。これらの対策によって、子どもたちが安全に遊んだり、通学したりできる環境が整備され、親たちの安心感が高まるでしょう。安全な環境は、子どもの健やかな成長にとって不可欠な要素であり、積極的に取り組むべき課題です。
3. 産科 小児科医療の充実とその他のニーズ
「産科・小児科医療の充実」も20.1%と、重要な課題として認識されています。これは、妊娠から出産、そして子供の成長過程における医療へのアクセスが重要であることを示しています。特に、産科医や小児科医の不足が問題視されている地域においては、医療体制の強化が急務です。 また、年代別回答からは、20代では「産科・小児科医療の充実」、30代では「子育て家庭に対する経済的な支援」、40代と60~70歳以上では「子どもが安全に安心して遊べる場の整備」、50代では「地域の人がボランティアで手伝う体制の整備」と「産科・小児科医療の充実」が同率で2位となるなど、年齢層によって異なるニーズがあることも示されています。これらの多様なニーズに応えるためには、それぞれの年代層の特性を考慮した、きめ細やかな政策展開が重要となるでしょう。経済的な支援、地域コミュニティの活用など、多角的なアプローチが必要とされています。
IV.教育の充実 学校環境と学力向上の両立
子どもの教育に関するアンケートでは、「教職員の資質の向上」と「子どもの基礎的な知識や技能向上への取り組み」が上位を占めました。 中学校区別では、学力向上への取り組みと個性を生かした学校生活の実現へのニーズが地域によって異なることが分かりました。学校施設の老朽化や耐震性への懸念も寄せられています。
1. 教職員の資質向上と基礎学力育成
アンケートでは、子どもの教育の充実に関して、「教職員の資質の向上」と「子どもの基礎的な知識や技能向上への取り組み」が上位を占めました。これは、教員の質の高さや、基礎学力の定着が、子どもの教育において非常に重要視されていることを示しています。教員の資質向上に関しては、研修機会の充実や、教員のモチベーション向上のための施策などが考えられます。また、基礎学力育成においては、学習内容の見直しや、効果的な学習方法の導入、そして学習支援体制の整備などが重要です。これらの取り組みを通じて、教員の専門性と指導力を高め、子どもたちの基礎学力をしっかり身につけるための環境を整備することが求められます。さらに、地域社会全体による教育支援体制の構築も重要です。
2. 個性重視の学校教育と学力向上への取り組み
上位2項目に加え、「個性を生かしのびのびとした学校生活の実現」と「子どもの学力の向上への取り組み」も重要な項目として挙げられました。 これは、学力向上と個性の尊重という一見相反する要素の両立が、市民にとって重要な課題であることを示しています。学力向上のためには、学習内容の充実や指導方法の改善、学習環境の整備などが重要です。一方で、個性を生かす教育においては、多様な学習方法の提供や、子どもの自主性を尊重する教育、そして一人ひとりの個性に合わせた指導などが重要となります。これらの要素をどのようにバランス良く実現していくかが、今後の教育政策の課題となります。 少人数学級制の推進なども検討されるべき事項として挙げられており、より質の高い教育の実現に向けた多角的なアプローチが必要となります。
3. 学校環境と安全対策 老朽化と耐震化への懸念
アンケートでは、学校環境に関する意見も寄せられており、「子どもの登下校を含めた学校の安全・安心対策」、「学校施設や設備の改善・教材や備品等の充実」といった項目が挙げられています。これは、学校施設の老朽化や安全面への懸念が、保護者や地域住民の間で共有されていることを示しています。具体的な課題としては、学校施設の老朽化に伴う耐震化、設備の更新、そして安全な通学路の確保などが挙げられます。また、教材や備品の充実も教育の質を向上させる上で不可欠です。これらの課題を解決するためには、財政状況を考慮しつつ、学校施設の改修や新設、安全対策の強化、そして教材・備品の充実など、具体的な対策を講じる必要があります。子どもたちが安全で快適な環境の中で学習できるよう、早急な対応が求められます。 地域住民との連携による安全対策なども効果的です。
4. 地域特性とニーズの多様性 中学校区別分析
中学校区別の分析結果によれば、上位2項目は全地区で共通していますが、3位以降は地域によって異なる傾向が見られました。「福岡中学校区」、「葦原中学校区」、「花の木中学校区」では「子どもの学力向上への取り組み」が重視されており、「大井中学校区」、「大井西中学校区」、「大井東中学校区」では「個性を生かした学校生活の実現」が重視されていることが分かりました。この地域差は、各地区の人口構成や地域特性、教育に対する価値観の違いなどを反映していると考えられます。 したがって、教育政策を立案する際には、これらの地域特性を考慮し、各地区のニーズに合わせたきめ細やかな対応を行うことが重要です。地域住民との連携を強化し、地域の実情に即した教育環境の整備を進めることで、より効果的な教育政策の実現を目指すべきです。
V.地域活性化 市民参加と多様な施策の必要性
市民からは、地域活性化に向けた様々な意見が寄せられました。具体的には、上福岡駅周辺の活性化、市民参加型のまちづくり、観光事業の推進、産業振興、環境保全など多岐にわたります。 財政状況の悪化への懸念も示されており、選択と集中による効率的な行政運営が求められています。また、旧上福岡市と旧大井町との統合後も、地域間の連携強化が課題として挙げられています。
1. 市民参加の促進 現状の課題と改善策
地域活性化においては、市民参加の促進が不可欠であることが多くの意見から読み取れます。現状では、自治会などの役員を務めない限り、市民が市政に参加しにくいという課題が指摘されています。特に若い世代の参加が不足している点も問題視されており、より多くの市民、特に若い世代の参加を促進するための仕組みづくりが求められています。 市民参加を促進するための具体的な方法としては、アンケート調査結果の積極的な情報公開、市民フォーラムやワークショップなどの開催、そしてインターネットなどを活用した情報発信の強化などが考えられます。また、自治会活動の活性化や、市民が気軽に意見交換できる場を設けることも重要です。さらに、行政側が市民の意見を真摯に受け止め、政策に反映していく姿勢を示すことも、市民参加を促進する上で不可欠です。 市民の積極的な関与が、より良い地域社会づくりに繋がります。
2. 地域経済の活性化 多様な施策の必要性
地域経済の活性化に向けた取り組みとして、観光事業の推進、中小企業への支援、農業の振興など、多様な施策の必要性が指摘されています。 観光事業の推進には、ふじみ野市の魅力を発信するPR活動の強化、イベントの開催、そしてふじみ野市PR大使「ふじみん」の積極的な活用などが考えられます。中小企業への支援としては、融資制度の充実や、企業間の交流促進などが挙げられます。農業の振興には、耕作放棄地の有効活用や、地産地消の推進などが重要です。これらの施策は、それぞれ独立して行われるのではなく、相互に連携し、相乗効果を生み出すような取り組みが求められます。 また、高齢者の知恵や経験を活かした産業振興なども検討されるべきです。 これらの施策を通じて、地域経済の活性化を図り、雇用創出や地域への愛着の醸成につなげていく必要があります。
3. 上福岡駅周辺の活性化 シャッター通り問題への対応
上福岡駅周辺はふじみ野市の顔とも言われ、その活性化が重要視されています。しかし、シャッター通りの問題など、課題も指摘されています。 上福岡駅周辺の活性化には、商店街の活性化策、魅力的な店舗誘致、そして駅周辺の環境整備などが重要になります。具体的には、空き店舗の活用策、魅力ある街並みの形成、そして地域住民や事業者による協働による取り組みなどが考えられます。 これらの施策は、単なる商業施設の誘致だけでなく、地域住民の交流を促進し、地域全体の活性化に繋がるような、より包括的な視点が必要とされます。 上福岡駅周辺の活性化は、ふじみ野市のイメージ向上にも繋がる重要な課題です。
4. 財政状況と政策の優先順位 選択と集中
厳しい財政状況の中で、市民は行政サービスの維持・充実と新たな事業の展開のバランスに課題を感じていることが示唆されています。 そのため、市民からは、政策の優先順位付けや、選択と集中によるメリハリのある行政運営が求められています。 具体的には、不要な事業の見直しや、民間への委託、そして市民への負担軽減策の検討などが挙げられます。 また、国や県との連携による事業の重複排除なども検討すべき事項でしょう。 財政状況を透明化し、市民への理解を得ながら、限られた予算の中で、市民のニーズに応えるための効率的な政策運営が求められます。
