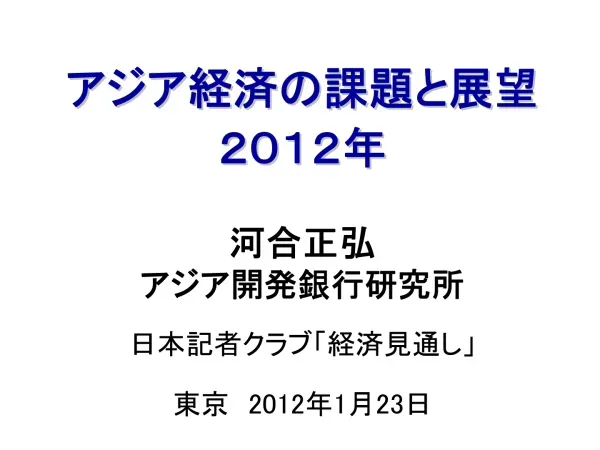
アジア経済:課題と展望2012
文書情報
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 講義資料 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.92 MB |
概要
I.世界経済の現状とリスク 特に欧州 米国 新興アジアに焦点を当てて
本資料は、世界経済、特に【欧州債務危機】と【銀行危機】、【米国経済】の低迷、そして急成長する【新興アジア経済】の現状と将来展望を分析しています。欧州の債務問題は、ユーロ圏経済の【景気後退】リスクを高め、米国では高止まりする【家計部門の債務】と低迷する住宅価格が回復を阻んでいます。一方、新興アジアは著しい成長を遂げていますが、【資本流出】や【インフレ】、そして【中所得国の罠】といった課題も抱えています。これらの課題を克服し、安定的な成長を維持するには、【構造改革】と健全な【マクロ経済政策】(金融政策と財政政策)が不可欠です。特に、【マクロプルーデンシャル金融監督】の強化が重要視されています。
1. 欧州経済の危機と欧米経済の不透明感
欧州のソブリン債務危機と銀行危機は、欧米経済全体の不透明感を増幅させています。この危機は、ユーロ圏経済に深刻な影響を与え、GDP成長率の低迷や金融市場の不安定化を引き起こしています。特に、ユーロ圏内での成長・安定化協定の遵守を強制するメカニズムの欠如、財政政策における協調体制の不足(財政統合やユーロ共同債の議論)、ECBの「最後の貸し手」機能の不十分さ、そしてソブリン債を抱える銀行のバランスシート問題などが、危機の拡大に拍車を掛けています。さらに、この危機はユーロ圏外、例えばハンガリーやポーランドなどにも波及するリスクがあると指摘されています。これらの問題の本質は、ユーロ圏における制度的な枠組みが不十分である点にあり、抜本的な改革が求められています。世界銀行の2012年1月時点の報告書では、これらの問題が世界経済全体に暗い影を落としていると分析されています。
2. 米国経済の低迷 家計債務と住宅価格問題
米国経済は緩やかな回復を見せているものの、家計部門の過剰債務が大きな課題となっています。債務と可処分所得の比率は2005年の水準まで低下したものの、依然として110%程度と高く、家計の消費意欲を抑制しています。また、住宅価格のボトムアウトも確認されておらず、住宅市場の回復は遅れています。さらに、失業率も8.6%と高水準にあり、雇用情勢の改善も進んでいません。これらの要因から、米国の経済回復は脆弱であり、世界経済の成長を牽引する力としては不十分であると判断されています。家計債務の高止まりと住宅価格の低迷は、米国経済の持続的な成長にとって大きなリスク要因であると言えます。世界銀行の経済予測では、これらの問題が米国経済の回復ペースを鈍化させる要因として示されています。
3. 新興アジア経済の急成長と潜在的リスク
新興アジア経済は世界経済の中でもっとも成長がめざましい地域ですが、同時に大きな課題も抱えています。当面の最大の懸念は、欧米経済の大幅な落ち込み(債務危機・銀行危機の拡大、米国経済の景気後退)です。これにより、アジアへの外需の減少や海外からの投資資金の流出(銀行融資・証券投資の引き上げ、貿易信用の減少)が生じ、為替レートの下落も招く可能性があります。2008年のリーマンショック後の韓国のミニ通貨危機やインドネシアのルピア大幅下落は、こうしたリスクの顕在化を示す事例です。新興アジアの長期的な成長を確保するためには、健全なマクロ経済政策運営(金融・財政政策)、マクロプルーデンシャル金融監督の強化、適切な債務管理、国際流動性危機への備え(IMF、通貨スワップ、世銀・ADBとの連携)、そして地域サーベイランスとCMIMの強化が不可欠です。為替レートの柔軟性強化、特に人民元レートの柔軟化も重要な課題です。これらの課題への対応が、新興アジア経済の持続的な成長にとって重要な鍵となります。
II.日本の現状と課題 少子高齢化と貿易依存度の低さ
日本経済は、2011年Q3にようやくプラス成長に転じましたが、【少子高齢化】と膨大な【公的債務】が大きな課題です。また、【貿易/GDP比率】と【直接投資/GDP比率】が他国に比べて低いことも指摘されており、経済の国際化と活性化が求められています。具体的な対策としては、消費税増税を含む【社会保障・税一体改革】、さらなる【経済連携協定(EPA)】の締結(TPP、日韓中EPA、ASEAN+6 EPAなど)を通じた【市場の拡大】、そして【グリーン産業】や【高齢者向け産業】といった新産業の開拓が挙げられます。
1. 少子高齢化と公的債務問題
日本経済は、少子高齢化と膨大な公的債務という深刻な問題を抱えています。少子高齢化は生産年齢人口の減少、社会保障費の増大をもたらし、経済成長の大きな制約となっています。一方、増加し続ける公的債務は、財政負担を増大させ、将来世代への負の遺産となる可能性があります。これらの問題は、日本経済の持続可能性を脅かす重大なリスクであり、早急な対策が必要です。特に、社会保障制度の改革と財政健全化は喫緊の課題です。これらの課題への対策として、消費税の増税による財源確保や年金・医療制度の改革などが挙げられますが、国民への負担増と制度改革のバランスが重要となります。これらの問題への対応は、日本経済の将来を左右する重要なポイントです。
2. 貿易依存度の低さと経済の国際化
日本の貿易/GDP比率と直接投資(残高)/GDP比率は、他国と比較して低い水準にあります。これは、日本経済が国際貿易への依存度が低いことを示しており、世界経済の変動に対する脆弱性を高める要因となっています。より積極的な貿易政策と国際的な経済連携強化が求められています。そのため、日本経済のさらなる国際化が重要となります。具体的には、TPP、日韓中EPA、ASEAN+6 EPA、FTAAP、日EU EPAといった様々な経済連携協定への積極的な参加が挙げられます。これにより、市場の拡大、日本企業のサプライチェーン強化、技術移転などが期待できます。しかし、TPPなどについては、農業など一部産業への影響を考慮し、適切な調整が必要となるでしょう。これは、構造改革の契機とも捉えることができます。国際的な競争力強化のためには、貿易依存度の向上と経済の国際化が不可欠です。
3. 成長戦略の必要性 新産業の開拓と構造改革
日本の持続的な経済成長のためには、新たな成長戦略の策定が不可欠です。少子高齢化社会に対応した高齢者向け産業(健康、介護)や環境問題への対応を重視したグリーン産業(環境、省エネ、新エネルギー)などの新産業開拓が重要です。さらに、農業の産業化も検討されるべきです。また、これらの産業育成を支えるための安定的なエネルギー供給(再生可能エネルギーの活用、効率的な電力供給システムの構築)も重要です。これらの新産業の育成は、雇用創出や経済活性化に繋がるだけでなく、社会構造の変化に対応した持続可能な経済社会の実現に貢献します。同時に、社会保障・税の一体改革、特に消費税引き上げと少子高齢化対応型の年金・医療制度改革は、財政健全化と社会保障制度の持続可能性を確保するために不可欠です。これらの政策を通じて、日本経済の構造改革を進めることが、将来の経済成長の基盤となります。
III.日本と新興アジアの経済連携 成長戦略の鍵
日本は、ダイナミックに成長する【新興アジア】(中国、ASEAN、アジアNIEs、インドなど)との経済連携なしに持続的な経済成長は望めません。そのため、ASEAN+3またはASEAN+6を中心とした東アジア主導型と、TPPを中心とした米国主導型の二つのアプローチを両立させる「ブリッジ戦略」が提案されています。これにより、【FTAAP】構築への参加、中国への貿易依存度の多様化、そしてEUとのEPA締結の可能性も期待できます。この連携強化は、日本経済の【構造改革】を促進し、【成長戦略】の鍵となるでしょう。同時に、アジアにおける金融安定化(CMIM強化、通貨スワップ)やインフラ整備への協力も重要です。
1. 新興アジアとの経済連携の必要性
日本は、ダイナミックに成長する新興アジア(中国、ASEAN、アジアNIEs、インドなど)との経済連携なしに、持続的な経済成長は望めないとされています。新興アジア市場は巨大な潜在力を持っており、日本企業にとって重要なビジネス機会を提供しています。しかし、現状では日本はASEANやインドなど個々の国とEPAを結んでいるものの、新興アジア全体との広域的な経済連携はまだ不十分です。この現状を打破し、より緊密な経済連携を構築することで、日本企業は市場アクセス拡大、サプライチェーンの強化、技術移転などのメリットを得ることができ、経済成長を促進することができます。アジア中間層の拡大による需要の伸びも、長期的な経済予測可能性を高める重要な要素となります。
2. 東アジア広域経済連携の構築 ASEAN 3 6とTPPの連携
東アジアにおける経済統合は、ASEAN+3(日中韓)またはASEAN+6(日中韓、インド、豪州、ニュージーランド)を中心とした東アジア主導型と、TPPを中心とした米国主導型の二つの流れが存在しています。日本は、この両方の枠組みを重視し、橋渡し役となるべきだと考えられています。具体的には、日中韓EPAを結び、ASEAN+3/6のEPAを構築し、将来的にはASEAN+6とTPP、さらにASEAN+6とEUを連携させる構想が提示されています。TPP単独の経済効果は限定的ですが、ASEAN+3/6と連携し、FTAAPへと発展させることで、日本経済への便益はGDP比1.36%と大幅に増加すると予測されています。これらの連携強化は、日本経済の構造改革の推進力ともなりえます。
3. 多面的な協調 経済連携を越えた広範な協力
日本と新興アジアの関係強化は、経済連携にとどまらず、多面的な協調関係を築くことが重要です。具体的には、アジアの金融安定化のためのCMIMの強化や通貨スワップ協定の活用、アジアにおけるインフラ整備や環境ビジネスへの参入(高速鉄道、水資源開発、スマートコミュニティなど)、アジアからの観光客誘致(メディカルツーリズムを含む)、アジアからの優秀な人材の受け入れと日本からの技術や人材の供給、そしてアジアからの投資・資金の誘致などが挙げられます。日本の貯蓄をアジアに投資し高収益を目指すことも検討課題です。これらの多様な協力関係の構築は、日本経済の成長のみならず、アジア全体の安定と発展にも大きく貢献する可能性を秘めています。特に、日本は、少子高齢化や公的債務問題を抱えながらも、新興アジア諸国との国際分業の深化を通じて生産性を高め、明るい未来を切り開く可能性を秘めていると言えます。
IV.新興アジアの持続的成長のための戦略
新興アジアの持続的成長のためには、【成長のリバランシング】と【包摂的な経済成長】(inclusive growth)が不可欠です。具体的には、労働集約型経済からの脱却、国内消費の拡大、外貨準備の適切な管理、そして所得分配の改善による【社会的公平】の実現が求められます。また、環境問題への対応も重要であり、【経済成長】と【環境保全】の両立を目指す新たな成長モデルの構築が急務です。
1. 中所得国の罠からの脱却と経済構造の転換
新興アジア諸国は、著しい経済成長を遂げていますが、多くの国が「中所得国の罠」に陥るリスクを抱えています。これは、労働集約型の経済発展から脱却できず、高付加価値産業への移行が遅れることを意味します。そのため、高投資と欧米市場向け純輸出に依存した経済成長モデルからの脱却が急務であり、内需拡大、特に国内消費の重視が重要になります。外貨準備の累積、インフレ、資産バブルといった問題にも注意深く対応し、ソフトランディングを目指した政策運営が求められます。IMFの世界経済見通し(2011年9月)では、中国の経常収支黒字拡大が予測されていますが、中国の消費/GDP比率は極めて低いため、内需拡大に向けた政策転換が重要となります。これらの課題を克服することで、より安定した持続的な経済成長を実現することが可能になります。
2. 包摂的な成長と社会課題への対応
新興アジアにおける持続的な成長のためには、経済成長の果実を広く国民に分配する「包摂的な成長(inclusive growth)」を目指した政策が必要です。所得分配の悪化是正のためには、教育や医療への投資による機会均等化、マイクロファイナンスの活用、雇用創出などが不可欠です。高齢化社会への対応として、社会保障制度の整備も重要な課題です。これらの社会課題への適切な対応は、社会全体の安定と、長期的な経済成長の土台を築く上で不可欠です。国民の生活の質の向上は、経済成長の目的そのものであると同時に、社会の安定と発展に不可欠な要素となります。アジア開発銀行(ADB)の指標によると、多くの新興アジア諸国において、所得格差や社会インフラ整備の遅れといった課題が依然として残っており、これらへの対応が持続的成長には不可欠です。
3. 環境問題への対応と新たな成長モデルの必要性
新興アジア諸国は、経済成長に伴い深刻な環境問題に直面しています。汚染やCO2排出量の増加など、環境劣化は持続可能な発展を阻害する大きなリスクです。そのため、経済成長と環境保全を両立させる新たな成長モデルの構築が不可欠となっています。これは、パラダイム転換やリープフロッギングを伴う、抜本的な変化を必要とするでしょう。環境問題への積極的な対策は、将来世代への責任を果たすだけでなく、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となります。資源の有効活用、再生可能エネルギーへの転換、環境配慮型技術の開発・導入など、多角的なアプローチが必要となります。環境問題への対策はコストがかかる側面もありますが、長期的な視点で見れば、環境破壊による経済的損失を回避する上で非常に重要です。
