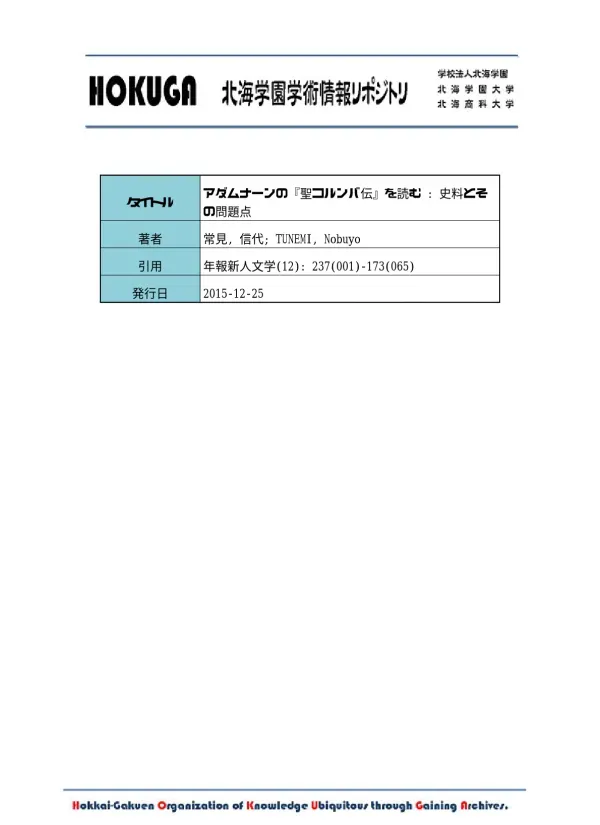
アダムナーン『聖コルンバ伝』:史料と問題点
文書情報
| 著者 | 常見 信代 |
| 専攻 | 歴史学、中世史、教会史 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.15 MB |
概要
I.アダムナーンの 聖コルンバ伝 アイルランド三大聖人の一人 聖コルンバの生涯とアイオナ修道院の隆盛
アダムナーンが著した『聖コルンバ伝(Vita Columba)』は、アイルランドの三大聖人である聖コルンバ(597年没)の生涯を描いた重要な史料です。コルンバ自身による著作は残っておらず、アダムナーンの作品がコルンバを知る上で主要な情報源となっています。この書は、中世初期のアイルランドとスコットランドの歴史を知る上で貴重な同時代史料としても高く評価されていますが、聖人伝特有の、歴史的事実とは必ずしも一致しない記述にも留意する必要があります。アダムナーンの執筆目的は、コルンバが「神のひと」であることを示し、キリスト教徒の模範を示すことで、アイオナ修道院の勢力を拡大することにあったと推測されます。
1. 聖コルンバと 聖コルンバ伝 情報源としての重要性と史料としての限界
本文は、アイルランドの三大聖人の一人である聖コルンバ(597年没)の生涯を、アダムナーンの『聖コルンバ伝』を通して考察しています。コルンバ自身の著作は現存しておらず、『聖コルンバ伝』がコルンバの生涯を知る上で唯一と言って良いほどの重要な情報源であると強調されています。同時に、中世初期のアイルランド・スコットランド史研究において、同時代の貴重な一次史料として『聖コルンバ伝』が広く利用されてきた事実も指摘されています。しかしながら、聖人伝という性質上、記述内容が必ずしも歴史的事実に忠実とは限らないという点に注意が必要であると述べられています。つまり、『聖コルンバ伝』は、聖コルンバの生涯を知る上で極めて重要な資料ではありますが、その記述内容を歴史的事実として鵜呑みにするのではなく、聖人伝特有の誇張や脚色、あるいは当時の社会的背景なども考慮に入れて読み解く必要があることを示唆しています。この点が、後の分析においても繰り返し強調される重要なポイントとなります。
2. アダムナーンの執筆目的と背景 アイオナ修道院の隆盛と聖人伝の役割
アダムナーンが『聖コルンバ伝』を執筆した目的、そしてその背景を探る事が、本文の主要な課題として提示されています。聖人伝の第一の目的は、その人物が「神のひと」であることを証明すること、そして、その人物の生き様を模範として示すことでキリスト教徒の信仰を深め、教会や修道院の権威と影響力を拡大することだと説明されています。聖人伝は、この目的を達成するための重要な手段であったと結論づけられています。本文では、ラテン語版だけでなくアイルランド語版の聖人伝も存在した事にも触れられています。これは、当時アイルランドにおいて聖人伝の作成が、修道士たちの強い要望に応える形で盛んに行われていたことを示唆しています。また、アダムナーンが『聖マルティヌス伝』を参考に『聖コルンバ伝』を執筆したことも言及されており、単なる修辞的なものではなく、アイオナ修道院にとって開祖であるコルンバの聖人伝の執筆が、当時極めて重要な課題であったことを示唆する記述となっています。聖パトリックと聖ブリジットの聖人伝が670年代から90年代にかけて相次いで作成されたことも、この背景を理解する上で重要な要素として挙げられています。
3. 聖コルンバ伝 の内容と特徴 奇跡と予言 アイオナ修道院中心の記述
『聖コルンバ伝』は、コルンバの予言や奇跡の記述に多くのページを割いている一方、アイオナ修道院の勢力拡大を意図したプロパガンダ的な要素はほとんど見られないと分析されています。予言や奇跡は聖人伝において重要な要素ではありますが、他の聖人伝、例えばパトリックの聖人伝と比較すると、その記述方法に違いが見られます。パトリックの聖人伝では、奇跡の記述と併せてパトリックの広範囲にわたる旅や活動が描かれ、アーマー教会の権威の根拠として用いられているのに対し、『聖コルンバ伝』では、物語の大半がアイオナ修道院とその周辺を舞台とし、登場人物も修道士が中心となっています。このため、『聖コルンバ伝』は、他の聖人伝と同様に扱われることは少ないと指摘されています。しかし、本文では、コルンバの予言や奇跡の描写を通じて、アダムナーンがローマ教会への服従を示唆していた可能性、そしてそれがアイオナ内部の保守派へのメッセージでもあった可能性が示唆されています。つまり、『聖コルンバ伝』は、コルンバの時代というよりも、アダムナーン自身の時代を反映した作品であると解釈されています。
4. 写本作成とコルンバ崇敬 アダムナーンの写本への関与と伝承の維持
アダムナーンは、『聖コルンバ伝』の写本作成にも深く関わっていたと推測されています。写本作成者であるドルベーネへの、正確な写本作成と原本との照合を行うという指示が本文に記されています。また、『聖コルンバ伝』第一巻23章には、写本作成と照合を行う修道士たちの様子が描かれており、アダムナーンが写本作成の過程に強い関心を抱いていたことがうかがえます。これは、コルンバ崇敬の拡大には写本の作成と普及が不可欠であり、同時に写本が粗悪なものにならないよう厳格な管理が必要であったことを示唆しています。さらに、コルンバが臨終間際に「詩篇」を書き写す場面が描かれ、その作業を弟子であるバイセーネに引き継がせる描写は、コルンバによる後継者指名を示唆する行為として解釈されています。そして、アイルランド語版『聖コルンバ伝』の存在も重要であり、16世紀初頭のオドンネルによる編纂は、宗教改革以前のアイルランドにおける信仰や慣習を知る上で貴重な史料となっています。これは、アダムナーン以降のコルンバに関する様々な伝承や解釈を知る手がかりを提供する資料ともなっています。
II. 聖コルンバ伝 の執筆背景 復活祭論争とアイオナ修道院の立場
『聖コルンバ伝』の執筆背景には、7世紀後半にアイルランドで盛んになった復活祭論争が深く関わっています。聖パトリックや聖ブリジットの聖人伝が相次いで作成された時代背景を踏まえ、アダムナーンもコルンバの聖人伝を書く必要性を感じたのでしょう。アイルランドの教会は、ローマ教会の復活祭の計算方法を巡り、長年に渡り論争を繰り広げていました。アイオナ修道院は保守派の中心に位置し、ローマ教会の方式を受け入れたのはアダムナーンの死後でした。『聖コルンバ伝』は、コルンバの奇跡や予言を通して、ローマに従う意思表明と、アイオナ内部の保守派への説教の両方の役割を果たしていたと解釈できます。重要な人物として、クメーネ(7世紀、アイオナ修道院長)とシェーゲーネ(624-652、アイオナ修道院長)が挙げられます。
1. 7世紀後半のアイルランドにおける聖人伝ブームと 聖コルンバ伝 の執筆
『聖コルンバ伝』の執筆背景として、7世紀後半のアイルランドにおける聖人伝執筆の盛況が挙げられています。聖パトリックや聖ブリジットといったアイルランド三大聖人の聖人伝が、比較的短い期間に相次いで作成されたことが示されており、この潮流の中で『聖コルンバ伝』も執筆されたと考えられます。具体的には、コギトススによる『聖ブリジット伝』(670年代末~80年代半ば)、アーマー教会によるパトリック伝三部作(『天使の書』、ティレハーンの『コレクタネア』、ムルフーの『聖パトリック伝』)などが先行例として挙げられています。これらの聖人伝は、聖人自身の時代よりも、むしろ聖人伝が書かれた時代の社会状況や宗教的風潮を反映しているという指摘も重要です。これらの作品が、復活祭論争という当時の重要な宗教的論争の最終局面を反映しているという指摘もなされています。聖コルンバ伝は、これらの作品に続く形で、700年前後頃に完成したと推測されています。
2. 復活祭論争とアイオナ修道院 ローマ教会との対立と保守的立場
『聖コルンバ伝』の執筆背景として、アイルランド教会を巻き込んだ大規模な復活祭論争が重要な役割を果たしていたことが示されています。この論争において、アイオナ修道院はローマ教会の復活祭計算方法を拒否し、伝統的なアイルランドの計算方法を堅持する保守的な立場をとっていました。アダムナーン自身は復活祭論争に直接言及していませんが、コルンバの奇跡や予言の記述を通して、ローマ教会への服従を示唆する意図があったと解釈されています。このメッセージは、外部のローマ教会だけでなく、アイオナ修道院内部の保守派にも向けられたもので、コルンバの権威と普遍教会への服従が矛盾しないことを示そうとしたものだと考えられます。すなわち、『聖コルンバ伝』は、アイオナ修道院の修道士たちに対するアダムナーンの説教とも解釈できるということです。このことから、『聖コルンバ伝』は、コルンバの時代ではなく、むしろアダムナーンの時代を反映した作品であることが示唆されています。
3. 聖コルンバ伝 と他の聖人伝との比較 記述内容の違いとアイオナの独自性
『聖コルンバ伝』は、他の聖人伝、特に聖ブリジット伝やパトリック伝とは内容が大きく異なるとされています。他の聖人伝では、聖人の広範な活動や、それによる教会の権威の拡大が強調されているのに対し、『聖コルンバ伝』では、コルンバの奇跡や予言が中心となっており、アイオナ修道院の勢力拡大を直接的に意図したプロパガンダ的な要素は少ないとされています。ただし、奇跡や予言は聖人伝の重要な構成要素であり、アダムナーンがそれらを記述したことは当然のことです。しかしながら、例えばパトリック伝における奇跡の記述は、パトリックの広範囲な旅を描き、アーマー教会の権威の根拠を確立するために用いられているのに対し、『聖コルンバ伝』はアイオナとその周辺を舞台とし、登場人物も修道士が中心である点が大きく異なっています。この点が、聖コルンバ伝が他の聖人伝と同一視されにくい理由の一つとなっています。つまり、アダムナーンはコルンバの奇跡を、アイオナ修道院の独自性を強調する、あるいはアイオナ内部の結束を強化する目的で用いた可能性があることが示唆されています。
III. 聖コルンバ伝 の写本と伝承 アイオナ修道院における写本の重要性と後世への影響
アダムナーンは『聖コルンバ伝』の写本作成にも深く関与し、写本の正確さを重視していました。写本作成者ドルベーネへの指示や、写本作成の様子が書中に描写されていることからも、コルンバ崇敬の拡大のためには写本の質が重要であったことが分かります。さらに、16世紀初頭には、M・オドンネルが様々なテキストを織り交ぜた**アイルランド語版『聖コルンバ伝』**を編纂しました。これは、宗教改革前のアイルランドの信仰や慣習を知るための重要な史料となっています。また、コルンバ哀悼詩のような、奇跡を起こす聖人像とは異なるコルンバ像を描いた作品も存在します。
1. アダムナーンの写本作成への関与と厳格な校正 コルンバ崇敬の拡大と写本制作の重要性
本文では、アダムナーンが『聖コルンバ伝』の写本作成に深く関わっていた可能性が示唆されています。写本作成者であるドルベーネへの指示として、「正しく書き写し、細心の注意を払って原本と写本を照合する」ことが記されており、アダムナーンが写本の正確性を重視していたことがわかります。さらに、『聖コルンバ伝』第一巻23章には、修道士が写本を読み上げ、もう一人が原文と照合する場面が描かれており、アダムナーンが推奨した校正方法の一端が示されています。このことから、アダムナーン自身も写本作成に関与していた可能性が高いと推測できます。コルンバ崇敬の拡大には写本の作成と普及が不可欠であった一方、写本の写し間違いや粗製乱造のリスクもあったため、アダムナーンは後世の写本作成者に対しても、アイオナで培われた厳格な校正方法を遵守するよう指示したと考えられます。これは、聖コルンバの思想や業績の正確な伝達を重視するアダムナーンの姿勢を反映していると言えるでしょう。
2. 聖コルンバ伝 第三巻23章の写本継承の描写 コルンバによる後継者指名としての解釈
『聖コルンバ伝』第三巻23章では、コルンバが臨終間際に書斎で「詩篇」を写し、34篇10節まで書き写したところで作業を弟子であるバイセーネに託す場面が描かれています。この描写は、アダムナーンによって、コルンバによる後継者指名という象徴的な行為として解釈されています。この記述から、アイオナ修道院において、写本制作や読書が単なる作業ではなく、修道院の運営や伝統の継承において極めて重要な役割を担っていたことが推測されます。修道院長にとって、写本制作や読書は重要な任務であり、むしろ職務の条件の一つであった可能性さえ示唆されています。このように、聖コルンバ伝はアダムナーンの時代における写本制作の実態や、アイオナ修道院における写本の重要性を理解するための貴重な資料と言えるでしょう。同時に、アダムナーンがどのようにしてコルンバの思想や業績を後世に伝えていこうとしたのかを示す、重要な描写となっています。
3. アイルランド語版 聖コルンバ伝 16世紀の編纂と宗教改革前アイルランドの信仰
本文では、ラテン語版に加えてアイルランド語版『聖コルンバ伝』の存在が言及されています。これは、ドニゴールのクランの支配者でコルンバの血縁を主張したM・オドンネルによって1532年に編纂されたものです。オドンネルは、アイルランド各地の古書に散らばるコルンバに関する情報を集め、それらを統合することで新たな『聖コルンバ伝』を創作しました。このアイルランド語版は、6世紀の聖コルンバに関する史料というよりは、宗教改革やテューダー朝による征服前の16世紀初頭のゲーリック・アイルランドにおける信仰や慣習を反映した作品と言えるでしょう。そこに織り込まれた様々なテキストは、アダムナーン以降のコルンバに関する伝承や解釈を知る手がかりを与えてくれる重要な史料となっています。このアイルランド語版は、単なる歴史資料としてだけでなく、特定の時代・地域における信仰のあり方や、聖コルンバの受容のされ方を知る上で非常に貴重な資料と言えるでしょう。
IV. 聖コルンバの奇跡に関する書 と復活祭論争 クメーネ本とアイオナの抵抗
クメーネが著したとされる『聖コルンバの奇跡に関する書』(クメーネ本)は、断片的にしか残っていませんが、ウィットビー教会会議(664年)でのアイオナ修道院の敗北への対応として書かれた可能性が指摘されています。アイオナは、ローマ教会の復活祭期日算定方式を拒否し、伝統的なアイルランド方式を固執していました。これは、コルンバの権威に基づく方式とみなされ、「コルンバの奇跡」がその根拠とされていました。この論争において、クミアンとシェーゲーネの間で論争があったことが知られています。また、アレクサンドリア/ディオニュシウス方式とヴィクトリウス復活祭表の違いも重要な論点でした。
1. クメーネ本とウィットビー教会会議 アイオナ修道院の復活祭論争への対応
この節では、クメーネが著したとされる『聖コルンバの奇跡に関する書』(クメーネ本)を取り上げています。クメーネ本は、断片的にしか残っておらず、その全容は不明ですが、クメーネがアイオナ修道院の第7代修道院長を務めていた時期(657-669年)に発生したウィットビー教会会議(664年)との関連が指摘されています。ウィットビー教会会議では、復活祭の計算方法を巡り、アイオナ修道院がローマ教会の方式に反対する立場を取ったため、ノーサンブリアにおけるアイオナの布教活動は撤退を余儀なくされました。このため、クメーネ本は、ウィットビー教会会議での敗北を受けて、アイオナ修道院が自らの立場を擁護するために書かれた可能性が考えられています。しかし、この説は決定的な証拠に基づいているわけではなく、あくまでも可能性の一つとして提示されている点が重要です。クメーネは、アイオナ修道院第5代修道院長シェーゲーネの甥にあたる人物であり、シェーゲーネ自身も復活祭論争に深く関わっていた人物であるため、クメーネ本と復活祭論争の関連性を考える上で重要な情報となっています。
2. 復活祭論争の経緯とアイオナ修道院の堅持 伝統的アイルランド方式とコルンバの権威
復活祭の計算方法をめぐる論争(復活祭論争)は、キリスト教会がユダヤ教の過越祭から復活祭を切り離すために独自に期日を算定する必要性に端を発しています。この論争は、ニカイア公会議で復活祭を過越祭の後の日曜日とする原則が確認された後も、太陰暦と太陽暦の調整、春分の日の決定、月齢範囲など、様々な解釈の余地がある要素をめぐって長期化しました。ローマ教会は、5世紀半ばから7世紀中葉にかけてヴィクトリウス復活祭表を採用していましたが、この方式には多くの欠陥があり、アイルランドでもその欠陥は広く知られていたとされます。アイオナ修道院は、シェーゲーネの時代から、ローマ教会からの警告にも関わらず、伝統的なアイルランドの計算方法を堅持し、ローマ教会の方式を拒否していました。アイオナ修道院は、このアイルランド方式を「コルンバの権威」に基づくものと捉え、「天の印とその卓抜した奇跡」をその証拠としていました。ウィットビー教会会議においても、コルンバの権威が主張されましたが、ローマ教会のペトロの権威には及ばないと反論されました。アイオナの伝統的計算方法への固執は、コルンバの権威を維持するという強い意志の表れと言えるでしょう。
3. アダムナーンの 聖コルンバ伝 とクメーネ本 情報源と復活祭論争への言及の有無
アダムナーンは『聖コルンバ伝』の信頼性を強調していますが、その情報源として、先輩からの伝承、既存の記録、年配者からの証言の三つを挙げています。その中の「以前に書かれていた記録」がクメーネ本を指している可能性がありますが、アダムナーンがどのようにクメーネ本を利用したのかは明らかではありません。アダムナーンは『聖コルンバ伝』の中で復活祭論争に直接触れていませんが、コルンバの奇跡や予言の描写を通して、ローマ教会への服従を示唆している可能性が示唆されています。これは、アイオナ修道院が復活祭論争においてローマ教会の方式に抵抗した背景と、アダムナーンの立場を理解する上で重要な点です。アイオナ修道院が独自の復活祭計算方法を堅持した理由は、その方法がコルンバ自身によって定められたものと認識されていたからであり、ローマ教会の方式への転換はコルンバの権威を否定することになると考えられていたためだと推測されています。つまり、アダムナーンは『聖コルンバ伝』において、ローマ教会への服従を示唆しつつも、コルンバの権威を維持することで、アイオナ修道院の独自性を保とうとした可能性があるということです。
V.ベーダの イングランド人の教会史 コルンバとアイオナ修道院への言及
ベーダの『イングランド人の教会史(Ecclesiastical History of the English People)』は、アングロ・サクソン教会の歴史を記した重要な作品で、コルンバやアイオナ修道院にも言及しています。ベーダは、コルンバの布教活動や、アイオナとローマ教会との関係について記述していますが、それらはベーダ自身の視点に基づいた解釈であることに注意が必要です。特に、ニニアンの布教活動との比較において、ウィットホーンの教会堂建設など、考古学的知見と食い違う記述も見られます。ウィットビー教会会議についても記述しており、この会議がノーサンブリアの政治的野心に宗教的正当性を付与した側面も指摘しています。ウェアマス・ジャロウ修道院の隆盛も重要な要素です。
1. ベーダの イングランド人の教会史 の概要と執筆背景 ウェアマス ジャロウ修道院とベーダ
この節では、ベーダの『イングランド人の教会史』が、中世初期のブリテン諸島史、特にアイルランドとアイオナ修道院に関する記述を含んでいる点を指摘しています。ベーダは、生涯の大半をウェアマス・ジャロウ修道院で過ごしたとされ、同修道院の豊富な蔵書がベーダの著作に大きな影響を与えたと推測されています。ウェアマス・ジャロウ修道院は、ベネディクト・ビスコプによって674年に創設され、後にジャロウにも修道院が設立されました。ビスコプはローマを6回訪問し、多くの書籍や聖遺物を持ち帰ったとされ、その蔵書はベーダの著作の基礎となっています。また、修道院では『アミアティヌス本』のような豪華な写本も制作されており、その写本制作技術や聖書解釈の高度な水準が示されています。『アミアティヌス本』は、ヴェラム皮紙を使用し、アンシャル体で書かれた大型の写本で、金銀や紫で彩色された豪華な装飾が施されています。この修道院の優れた写本制作技術と聖書研究の質の高さが、ベーダの『イングランド人の教会史』の執筆に大きく貢献したと推測されます。
2. イングランド人の教会史 におけるコルンバとアイオナ修道院への言及 ピクトの改宗と復活祭論争
ベーダの『イングランド人の教会史』は、イングランドだけでなく、ピクトやアイルランド、アイオナ修道院にも言及しており、中世初期のブリテン諸島全体の史料として重要だとされています。しかし、これらの記述は『教会史』のテーマに沿ったものであり、必ずしも事実を正確に記しているとは限らないと注意が促されています。例えば、ピクトの改宗について、南ピクトはニニアンによって、北ピクトはコルンバによって改宗されたと記述していますが、この記述はベーダの解釈に基づくものであり、考古学的知見とは必ずしも一致しない可能性が指摘されています。ニニアンに関しては、アイルランドのUinniauと同一人物であるという説も紹介されています。また、ベーダは復活祭問題にも触れていますが、ウィットビー教会会議のみに言及し、それ以前の論争には触れていません。これは、ベーダがローマ教会の復活祭計算方法が確立する以前の時代を重要視しなかったため、あるいは、ノーサンブリア教会がローマ教会の方式を受け入れたウィットビー教会会議を重視したためだと解釈できます。つまり、ベーダの記述は、彼の視点や目的によって選択的に行われたものである可能性を考慮する必要がある事を示しています。特にウィットビー会議は、神学的な論争としてだけでなく、政治的側面も強く持っていたと解説されています。
3. ベーダの記述における視点と意図 歴史記述における選択性とノーサンブリアの政治的背景
ベーダの『イングランド人の教会史』は、イングランド教会の歴史を記述することを目的としていますが、その記述においては選択性や意図性が働いていると指摘されています。例えば、ピクトの改宗に関して、ニニアンとコルンバの活動が対照的に描かれていますが、これはベーダがノーサンブリアの教会支配権を主張するためにニニアンの活動範囲を拡大解釈した可能性が示唆されています。アバコーン司教座を失ったノーサンブリアが、フォース湾岸の支配権回復を狙い、ニニアンをフォース湾の北まで旅させたという解釈が提示されています。また、ベーダが復活祭問題についてウィットビー教会会議のみに言及している点も、彼の意図性を示す一例として挙げられています。ベーダにとって、ローマ教会が復活祭計算方法について迷走していた時代は、書くに値しない時代であったと考えられる一方、ノーサンブリア教会がローマ教会の方式を受け入れたウィットビー教会会議は、イングランド教会統合の障害が取り除かれた重要な出来事として描かれています。さらに、ベーダがブリトン人に対して批判的な記述をしている点も、彼のイングランド中心主義的な視点や、ノーサンブリアの政治的野心を反映している可能性が指摘されています。つまり、ベーダの『イングランド人の教会史』は、客観的な歴史記述というよりも、特定の視点に基づいた歴史解釈であることを理解する必要があると結論づけられています。
