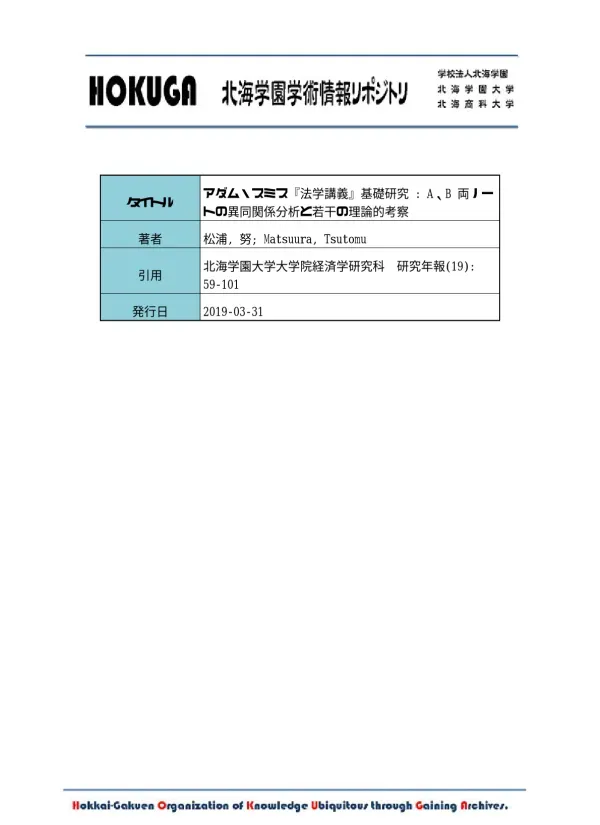
アダム・スミス法学講義:A・Bノート比較研究
文書情報
| 著者 | Matsuura, Tsutomu |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.66 MB |
概要
I.アダム スミスの法学講義ノート 未発表原稿の発見と意義
本稿は、アダム・スミス(Adam Smith)の未発表の法学講義ノート、特にLJ(A)とLJ(B)ノートを中心に、その内容と意義を考察する。1895年、エドウィン・キャナンによるLJ(B)ノートの発見は、スミスの経済思想(Wealth of Nations)の萌芽を明らかにした重要な出来事であった。さらに、近年発見されたLJ(A)ノートは、スミスの思想形成過程、特に自然法理論や同情の原理、所有権に関する考え方の発展を詳細に示している。これらのノートは、スミスの『道徳感情論(The Theory of Moral Sentiments)』、『国富論』の理解を深める上で不可欠な資料である。商業的社会というスミスの概念理解の鍵もこれらのノートに含まれる。
1. 未発表法学講義ノートの発見 その歴史的経緯
本稿は、アダム・スミスの未発表の法学講義ノートの発見と意義を論じています。特に、1895年にエドウィン・キャナンによって発見されたLJ(B)ノートと、後に発見されたLJ(A)ノートが中心的に扱われています。キャナンのLJ(B)ノート発見は、スコットランドのある旧家の蔵書の中から偶然に行われました。オックスフォードで『オックスフォード・マガジン』の編集者とスコットランド出身の弁護士チャールズ・マコノキーとの雑談中に、マコノキーがスミスの法学講義ノートを所持していることが明らかになり、そのノートがキャナンに提供されたという経緯が記述されています。これらのノートは、スミスの『国富論』発表以前の、経済理論の萌芽が含まれる可能性がある重要な資料であり、その発見は、スミス研究に大きな影響を与えました。さらに、W.R.スコットによる『国富論』草稿(ED)の発見も言及されており、これは1763年頃に書かれたと推定され、渡仏直前のスミスの思想形成を知る上で重要な資料となっています。これらの発見は、スミスの『道徳感情論』における「同情の原理」の解釈を深める上で役立つと同時に、『国富論』で展開された経済理論の源流を探る上で重要な役割を果たしています。
2. LJ A ノートとLJ B ノート 内容と特徴の比較
文書では、LJ(A)ノートとLJ(B)ノートの内容と特徴の比較がなされています。両ノートともアダム・スミスの法学講義の内容を記したものであり、特にLJ(B)ノートはキャナンによって発見された、現在広く知られているノートです。しかし、LJ(A)ノートの発見により、スミスの講義内容の理解がより深まりました。LJ(A)ノートは非常に詳細な記述が特徴で、LJ(B)ノートの内容を補足する情報も多く含まれています。また、過去の講義内容の要約なども含まれており、議論の要点の理解を容易にしています。一方、LJ(B)ノートはより簡潔な記述であり、論述の展開方法もLJ(A)ノートとは異なります。重要な違いとして、議論のソースがLJ(A)ノートの方が明確に示されている点が挙げられています。両ノートを比較することで、スミスの思想形成の過程や、彼の経済理論と法理論の関連性をより深く理解できることが示唆されています。特に、LJ(A)ノートでは自然法の論理が明確に示されている一方、LJ(B)ノートでは、モンテスキューの影響を受けた比較法的なアプローチがより顕著であるとされています。
3. スミスの経済思想への影響 商業的社会と道徳感情論
このセクションでは、スミスの法学講義ノートが彼の経済思想、特に「商業的社会」という概念や『道徳感情論』との関連性について考察しています。「商業的社会」とは、すべての人が商人(商品生産者)となる近代経済社会を指し、スミスはこの社会を道徳・法・経済の総体として捉えていました。同感・正義・等価交換は、この社会の統一的な基本原理として位置づけられています。スミスの「同情」の概念は、公平な第三者的観察者の是認ではなく、道徳的に中立的なものとして理解されるべきであると指摘しています。また、『道徳感情論』における「道徳」は、市民社会における生活感情と捉えられています。法の世界、正義の概念は、道徳の世界と経済の世界、同感と等価交換を統一的に理解するための鍵として位置づけられており、経済的世界が市民社会の中心として他の2つを規定するという関係が示唆されています。これらの考察を通じて、スミスの法学講義ノートが彼の経済思想全体を理解する上で重要な役割を果たしていることが強調されています。
II.LJ A ノートとLJ B ノートの比較 方法論と歴史的展開
LJ(A)ノートとLJ(B)ノートは、構成や方法論に違いが見られる。LJ(A)ノートは詳細な記述と豊富な歴史的、経済的事例を特徴とし、自然法に基づいた体系的な議論展開が見られる。一方、LJ(B)ノートはより簡潔で、モンテスキューの影響を受けた比較法的なアプローチが顕著である。スミスは、自然法論の枠組みから、ローマ法学者的な方法へとアプローチを変え、市民社会の発展と経済の自然法則との関係を論じている。両ノートの比較検討は、スミスの思想の深化と変遷を理解する上で極めて重要である。
1. 記述の詳細さと情報量の差異 LJ A ノートの特徴
アダム・スミスの法学講義ノートであるLJ(A)ノートとLJ(B)ノートを比較すると、記述の詳細さと情報量に大きな違いが見られます。LJ(A)ノートは全体的に記述が非常に詳細であり、LJ(B)ノートの内容を補足するような情報が多く含まれています。講義ノートという性質上、前回の講義内容の要約説明も多く見られ、これがノート全体の分量を多くしている要因の一つとなっています。単なる議論の繰り返し部分もありますが、これらの要約解説によって議論の要点が理解しやすくなっているという側面もあります。また、LJ(B)ノートと比較して、議論のソース(source)がより明確に示されていることもLJ(A)ノートの特徴です。これらの特徴から、LJ(A)ノートはLJ(B)ノートよりも詳細で、より包括的な理解を可能にする資料であると言えるでしょう。特に、スミスの思想形成過程を理解する上で、LJ(A)ノートは重要な手がかりを提供しています。 例えば、所有権の起源や成立に関する議論は、LJ(A)ノートの方が詳細で、スミスの考え方のニュアンスを捉えやすくなっています。
2. 方法論の相違 自然法論と比較法の採用
LJ(A)ノートとLJ(B)ノートの最も重要な違いの一つは、方法論にあります。LJ(A)ノートは、自然法論の枠組みを主に採用しており、権利の起源や基礎を自然状態から論証していくという、体系的な議論展開が見られます。一方、LJ(B)ノートでは、モンテスキューの影響を受けたと思われる比較法的なアプローチが顕著です。これは、近代自然法の人間本性論→自然法(市民社会)論→市民政府(国家)論という従来の論理構成を逆転させている点に表れています。LJ(B)ノートは、まず公法論を展開し、その後で私法(所有・契約)と経済の自然法則を明らかにするという構成をとっています。この構成は、政府を前提とした実定法原理論としても、経済学的な観点からもよりすっきりとした論理展開を示しています。この方法論の違いは、スミスの思想が時間とともにどのように変化し、深化していったのかを理解する上で重要な手がかりとなります。特に、モンテスキューの比較法、特にゲルマン法とアラブ人およびタタール人の法との対比が、スミスの思考にどのように影響を与えたのかが重要な考察点となります。
3. 歴史的叙述の違いとスミス思想への示唆
LJ(A)ノートとLJ(B)ノートは、歴史的叙述の方法においても違いが見られます。LJ(A)ノートは、法理論や法制度論を豊富な歴史的、経済的事象を提示することによって根拠づけていることが特徴です。スミスにとって、理論・制度(政策)・歴史は三位一体の関係にあり、法と経済は非常に立体的に結びついていたと考えられます。この歴史的叙述は、スミスの思想を理解する上で非常に重要であり、彼の理論が特定の歴史的状況や経済状況を背景にどのように形成されたのかを知る手がかりを与えてくれます。一方、LJ(B)ノートは、より簡潔な歴史的叙述となっています。両ノートの比較から、スミスの思想形成過程における歴史認識の変化、そして彼の理論と現実との関係性が浮かび上がってきます。例えば、イングランドにおける自由の回復に関する議論では、LJ(A)ノートはイングランドとスコットランドの合邦(1707年)を重要な要因として挙げているのに対し、LJ(B)ノートは地理的条件に言及するにとどまっています。これらの違いは、スミスの歴史認識や政治思想の変遷を理解するために重要な要素となります。
III.所有権と同情の原理 スミスの経済思想の根幹
スミスの所有権に関する考察は、LJ(A)とLJ(B)ノートにおいて詳細に展開されている。彼は、所有権の成立を単なる抽象的概念ではなく、人々の同情の原理に基づいた具体的な対象物の占有と関連付けて分析する。不偏な観察者という概念も、所有権や正義の理解において重要な役割を果たす。スミスの同情の原理は、利他心ではなく道徳的に中立的な概念であり、経済活動や社会秩序の維持に貢献する。
1. 所有権の起源と同情の原理 スミスの独自解釈
アダム・スミスは、法学講義ノートにおいて所有権の起源と成立を独自の視点から論じています。彼は、所有権の発展を所有権という抽象的概念自体からの発展としてではなく、人々の黙示的あるいは明示的な意識を媒介として、具体的な対象物の拡張(果実や動物(家畜)→土地)を介して発展するという観点から捉えています。この過程において、「同情の原理」が重要な役割を果たしており、ある人が侵害されたと感じる場合、中立的な観察者(不偏な観察者)がその意見に同意する時に初めて、侵害があったとみなされるという論理が展開されています。スミスは、所有権の成立とその権利保障に関して重要な視点を提示しており、単なる先占だけでなく、社会的な承認や同意が所有権の根拠として不可欠であることを示唆しています。これは、従来の自然法理論とは異なる、より社会的な視点を取り入れた所有権論と言えるでしょう。 この「同情の原理」は、利他心ではなく、道徳的に中立的なものとして捉えられており、個人の利己的な行動が、結果として社会全体の利益に繋がるというスミスの経済思想全体を理解する上で重要な概念です。
2. 同情の原理と法制度への批判的視点
スミスは、「同情の原理」を、法制度の背後に隠された欺瞞性を暴露・批判するための武器として用いています。グロチウスやプーフェンドルフが刑罰の根拠を公共の利益に求めるのに対し、スミスは、被侵害者の憤りに共感できるかどうかを刑罰の正当性の基準として提示しています。公共の利益という大義名分の下になされる刑罰と、被侵害者の感情に共感できる刑罰とは異なるものであると主張し、「全体の効用」という幻想を打ち砕いています。これは、法制度そのものに対する批判的な視点であり、法制度が必ずしも正義や公平性を担保するものではないという認識を示しています。特に、永久限嗣相続を批判する箇所では、死者が将来世代にまで及ぶ権利を持つという考え方が不自然であり、農村の改良にも不利であると指摘しています。この批判は、スミスが法制度の機能や限界を深く認識していたことを示すものであり、彼の経済思想と深く関連しています。 効率的な経済活動のためには、法制度は公平で信頼できるものでなければならないという彼の考え方が読み取れます。
3. 所有権と経済発展 スミスの歴史的視点
スミスは、所有権の発展と経済発展の歴史的関係についても論じています。彼は、牧畜民の時代を、統治が最初に始まる時代、そして人々が他人に依存するようになる時代として捉えています。羊や牛の群れの占有によって、狩猟社会とは異なり、富者と貧者の区別が生じ、所有権に関する確定した法律や協定が導入されるようになったと説明しています。この歴史的視点から、スミスは所有権の概念が、経済発展の過程でどのように形成され、変化してきたかを分析しています。 これは、彼の「商業的社会」の概念と密接に関連しており、所有権の制度化が、経済活動の活発化と社会の発展に不可欠な要素であることを示唆しています。さらに、スミスは、政府が樹立された目的についても論じており、所有権の保護と社会秩序の維持という役割を強調しています。これらの議論は、彼の経済思想と法思想が不可分のものであることを示しており、彼の講義ノート全体を通して一貫した視点が貫かれていることがわかります。
IV.社会契約説批判と統治の原理 スミスの政治思想
スミスは、ロックなどの社会契約説を批判し、統治の正当性を権威の原理と共通利益(効用)の原理に基づいて説明する。彼は、イギリスの政治体制を分析し、これらの原理が君主制と共和制、さらにはウィッグ党とトーリー党といった異なる政治勢力によってどのように受容されてきたかを考察する。抵抗権の問題についても触れ、社会契約に基づく正当化ではなく、より現実的な政治的・経済的要因に着目する。
1. 社会契約説批判 ロックやシドニーへの反論
アダム・スミスは、法学講義ノートにおいて、ロックやシドニーらに代表される社会契約説を批判しています。スミスは、統治の起源を自由意志による契約に置く社会契約説の想定が、歴史的事実と合致しないことを指摘しています。国民がそれぞれの権力を別の機関に委譲し、服従を約束するという社会契約は、現実には存在し得ないとするのです。たとえそのような契約があったとしても、主権者が権力を濫用した場合、国民には抵抗権があるとスミスは主張します。この抵抗権は、主権者の権力が国民によって委任された信託であるという前提に基づいています。つまり、スミスは、統治の正当性を、契約という抽象的な概念ではなく、より現実的な権力関係や国民の利益という視点から考察しているのです。特に、フランスやスペインなどの例を引き合いに出し、国民の同意なしに課税が行われている現実を挙げ、社会契約説が普遍的な説明力を持たないことを強調しています。 スミスの批判は、単なる理論的な反論ではなく、当時のヨーロッパにおける様々な政治体制を踏まえた現実的な分析に基づいています。
2. 統治の原理 権威と共通利益
社会契約説の代替として、スミスは統治の原理として「権威の原理」と「共通利益(あるいは効用)の原理」を提示しています。権威の原理は、特に君主政治において優勢であり、臣民は統治者への自然な服従を示す一方、共和制、特に民主制においては共通利益、効用が服従の根拠となります。イギリスの政治体制においては、下院の影響により、効用の原理も強く働いているとスミスは分析しています。ウィッグ党は効用の原理を、トーリー党は権威の原理を重視していたと指摘しており、当時のイギリス政治における党派対立にも言及しています。スミスは、これらの二つの原理が相互に関連しており、権威の原理は共通利益の原理の基礎となっていると述べています。また、人々が権威を尊重する傾向や、為政者による安全保障への期待も、統治の安定に寄与する要素として挙げられています。 これらの原理は、社会契約説とは異なり、歴史的・社会的な現実を踏まえた上で、統治の安定と国民の服従を説明するための枠組みを提供しています。
3. 忠誠と抵抗 現実的な政治分析
スミスは、国民の忠誠(服従)の根拠が暗黙の契約にあるという考え方を否定し、権威の原理と共通利益(効用)の原理を挙げています。彼は、これらの原理が、それぞれの政治体制や党派によってどのように受容されてきたかを説明し、ジェームズ2世によるステュアート王朝の終焉と名誉革命を論じることで、社会契約説批判を展開しています。スミスは、社会契約説に基づく抵抗権の正当化も批判し、統治者の権力が適度に用いられる限り、国民は抵抗する必要はないと主張しています。しかし、統治者が国民の財産を保護する役割を放棄し、権力を乱用した場合には、抵抗が正当化されるとし、抵抗の限界についても言及しています。この議論においては、現実的な政治的状況への考察が重視されており、抽象的な理論よりも、具体的な歴史的・政治的分析に基づいた政治思想が展開されています。スミスの政治思想は、彼の経済思想と同様に、現実社会の問題意識から出発したものであり、自由な社会秩序を維持するための具体的な条件を提示している点に特徴があります。
V.経済発展と法制度 スミスにおける三位一体の関係
スミスは、経済発展と法制度の密接な関係を強調する。特に、分業による生産性向上、自然価格の概念、そしてスコットランドやイングランドの経済状況を分析することで、当時の経済政策に対する批判を行う。彼は、理論、制度、歴史を三位一体として捉え、歴史的、経済的事象を法理論や法制度論の根拠として提示する。産業革命初期のイギリス社会における経済変化と、それに対応する法制度の役割を深く考察している。
1. 分業と生産力 スミスの経済論の核心
アダム・スミスの法学講義ノートにおいて、経済発展と法制度の関連性が論じられています。特に、分業による生産力増強が重要なテーマとして取り上げられています。スミスは、機械の発明が分業によるものであると指摘し、分業によって個々の作業の効率化が図られ、生産力が向上することを説明しています。シェフィールド、マンチェスター、バーミンガムなどのイギリスの工業都市における工場を例に挙げ、多くの機械が普通の職人によって発明されたと述べています。この分業による生産力向上は、高賃金をもたらし、社会全体の福祉の増大に繋がるという考え方が示されています。これは、産業革命初期のイギリスにおける経済的現実を背景としたものであり、人口増加分を吸収するほどの資本の蓄積があったことを示唆しています。スミスは、分業による生産性向上に対する過度の信頼を示しているとも解釈でき、それはイギリスにおける原始蓄積の高潮期という時代の状況を反映していると言えます。この経済論は、彼の「商業的社会」という概念と密接に関連しており、利己的な人間の行動が、市場メカニズムを通じて社会全体の富裕と適正な分配を生み出すという、彼の経済思想の核心が示されています。
2. 自然価格と労働賃金 経済理論の基礎概念
スミスは、「自然価格」という概念を定義しています。この定義は、必ずしも個々の商品価格を想定しているとは限らず、むしろ人が特定の業務に専念する気にさせるのに必要な価格、あるいは人が労働している間自分を維持し、教育費を支払い、ビジネスの成功まで生き延びるリスクを償うのに十分な労働の価格として理解できる可能性が示唆されています。さらに、新たな労働力の再生産費をも見込んだ労働の生産費を含む概念である可能性も指摘されています。この「自然価格」は、スミスの経済理論の基礎概念であり、市場価格の形成メカニズムや、労働賃金の決定要因を理解する上で重要な役割を果たしています。この概念は、彼の講義ノートにおける経済論と、後の『国富論』における価格論・貨幣論といったより洗練された経済理論の繋がりを示しています。 スミス経済学の成立は、講義ノートにおける経済論、特に「ポリース」篇で展開された一連の経済論が基礎となっているとされており、その後の『国富論』におけるより高度な体系化へと発展していきます。
3. 法制度と経済発展の三位一体 歴史的分析と政策批判
スミスは、法理論・法制度論を、豊富な歴史的・経済的事象によって根拠づけています。彼にとって、理論・制度(政策)・歴史は三位一体の関係にあり、法と経済は密接に結びついていると認識していました。スミスは、イングランドにおける近代的自由確立の要因を、常備軍の欠如とイングランドとスコットランドの合邦(1707年)に求めています。しかし、この歴史認識は、イギリス市民革命といった歴史的転換点への積極的な評価が見られないという点で、現代の西洋経済史の通説と異なる可能性が指摘されています。これは、スミスが近代社会の始まりを絶対主義の成立と捉えており、市民革命よりも絶対主義をヨーロッパ史上の最大の歴史的画期とみなしていたことによるものと考えられます。 スミスは、経済状況の分析を通じた政策批判を重視しており、それは彼の旺盛な現実に対する批判精神と、経済発展における法制度の役割への深い理解を示していると言えます。この三位一体の視点は、彼の経済思想を理解する上での重要な要素であり、彼の経済理論は単なる抽象的な概念ではなく、具体的な歴史的・社会的な文脈の中で理解されるべきであることを示唆しています。
VI.スコットランド法と大陸自然法の影響 スミスの法学形成
スミスの法学は、スコットランドの法制度と大陸の自然法理論、特にグロチウスやプーフェンドルフの影響を受けて形成された。スコットランドはイングランドとは異なり、ヨーロッパ大陸との繋がりがあり、自然法概念が強く根付いていた。スミスはホッブズの自然権論にも触れ、独自の自然法観を構築している。 この点は、ブラックストン、ベンサムといった後の法思想家との比較においても重要な意味を持つ。
