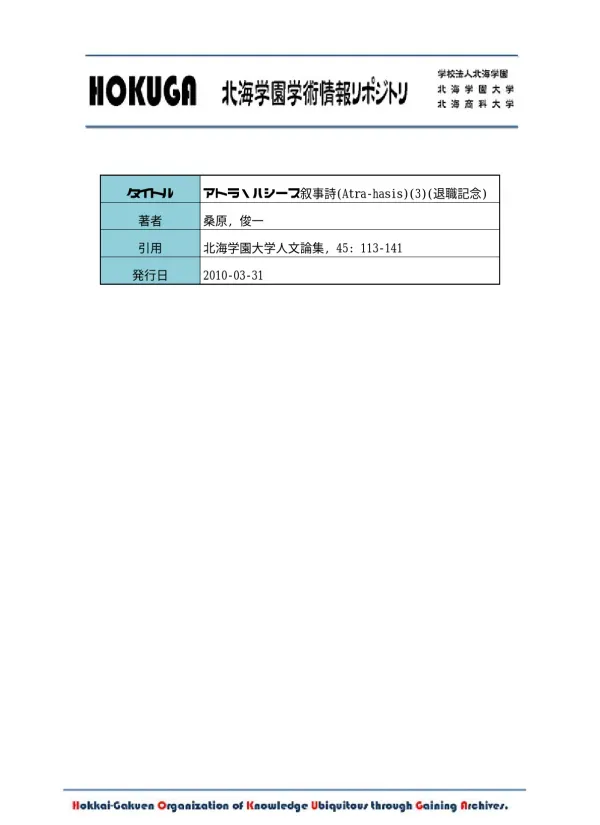
アトラ・ハシース叙事詩:古代メソポタミア神話
文書情報
| 著者 | 桑原俊一 |
| 専攻 | 古代メソポタミア研究、神話学 |
| 文書タイプ | 論考 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.31 MB |
概要
I.アトラ ハシース叙事詩における時間の概念と王権
本稿は古代メソポタミアのアトラ・ハシース叙事詩を論考するものです。叙事詩では、大洪水前に3600年(メソポタミアの60進法では無限大を意味する)が経過したと記述されていますが、シュメール王名表、特にエリドゥ王名表によると、大洪水以前の王の治世は数万年に及ぶと記されており、その記述と叙事詩の時間の概念との差異が注目されます。例えば、アルリム王は28800年、エンメンルアナ王は43200年の治世とされています。洪水以降は治世期間が劇的に短縮される点も重要な特徴です。
1. アトラ ハシース叙事詩における時間の記述とメソポタミアの60進法
アトラ・ハシース叙事詩では、大洪水前に1200年が3回繰り返され、合計3600年が経過したとされています。しかし、メソポタミアの60進法において3600年は非常に長い期間、事実上無限大の時間を象徴すると解釈できます。この叙事詩における時間の概念は、後のシュメール王名表と比較検討する上で非常に興味深いものです。この時間の尺度の違いは、神々の時間と人間の時間の認識の相違、あるいは神話と歴史記述の差異を示唆している可能性があります。叙事詩の記述と、現実の時間感覚との乖離が、この叙事詩の解釈において重要な論点となります。
2. シュメール王名表と大洪水以前の王たちの治世
対照的に、シュメール王名表、特にエリドゥ王名表には、大洪水以前の王たちの治世が数万年に及ぶと記されています。例えば、最初の王アルリム(Alulim)は28800年、3代目の王エンメンルアナ(En-men-lu-ana)は43200年の治世とされており、叙事詩の記述とは桁違いの期間です。この王名表の記述は、叙事詩とは異なる歴史認識、あるいは神話的な時間感覚を示唆していると考えられます。王名表における治世期間の長さは、王権の絶対性や神聖性を強調するための誇張表現である可能性や、異なる年代測定方法、あるいはそもそも異なる種類の記録である可能性も考慮する必要があります。これらの異なる記述の背後にある歴史的、文化的な背景を解明することは、古代メソポタミアの歴史理解にとって不可欠です。
3. 洪水以前と洪水以降の治世期間の対比
注目すべきは、大洪水以前の王たちの治世期間が極端に長く、一方、洪水以降の王たちの治世期間は1200年から300年と劇的に短縮されている点です。この著しい差異は、単なる記述上の偶然ではなく、何らかの意図的な文学的手法と解釈できるでしょう。大洪水という出来事を境に、歴史認識や時間の捉え方が変化した可能性、あるいは神々や人間に対する認識の変化を反映している可能性があります。この文学的手法は、聖書文学など他の古代近東文学と比較検討することで、その背景や意図をより深く理解できる可能性があります。この時間軸の変化は、古代メソポタミア社会における価値観や世界観の変化を反映している可能性があり、今後の研究課題となります。
II.神々の苦悩と人類の繁栄 エンリルとエンキの対立
アトラ・ハシース叙事詩では、人類の繁栄により神々の安寧が脅かされる様子が描かれています。特に、エンリルは人類の騒がしさに苦悩し、絶滅を決定します。嵐の神アダドに雨を降らせることを禁じ、食料を断つよう命じますが、知恵と魔術の神エンキ/エアは、疫病や飢饉から人類を救済します。このエンリルとエンキの対立が物語の中心軸となります。 古代メソポタミア神話において、神々と人間の関係、そして神々の内部抗争が重要なテーマとして提示されている点が読み取れます。
1. 人類の繁栄と神々の苦悩
アトラ・ハシース叙事詩では、神々の時間からすればそれほど長くはない1200年という期間に、人類は著しく繁栄し、人口は膨大になります。その結果、人間の騒音や喧騒は神々の世界にまで届き、神々は安寧を乱され、睡眠すら取れないほどに悩まされるようになります。特に、エンリルは、この人類の騒がしさに耐えかね、人類を絶滅させる決断を下します。この描写は、神々と人間の共存関係、あるいは神々の限界を暗示しており、古代メソポタミアにおける人間と神の関係性を考察する上で重要な要素となります。神々の苦悩は、単なる描写ではなく、物語の重要な転換点、そして後の洪水へと繋がる伏線として機能しています。
2. エンリルの裁定とアダドへの命令
エンリルは、人類の絶滅を決意し、嵐の神アダドに雨を降らせないように命じます。同時に、人間の食料となる草木を減らすよう指示を出します。これは、人類を飢餓と渇きによって滅ぼそうとする、エンリルの明確な意思表示です。このエンリルの行動は、彼の権力と厳格さを示す一方で、一方的な決定であることも示唆しています。この命令は、後のエンキによる介入との対比を際立たせ、物語の緊張感を高める効果を持っています。アダドへの命令は、エンリルの意志が確実に実行されるための重要なステップであり、エンキの介入がなければ人類の滅亡は避けられなかったでしょう。
3. エンキ エアの介入と人類の救済
しかし、知恵と魔術の神エンキ/エアは、エンリルの企みをすべて予測していました。エンキ/エアは、アトラ・ハシースに助言を与え、エンリルが送った疫病に対し、疫病神ナムタルを懐柔することで、人類を救済します。さらに、1200年後には日照りと飢饉が発生しますが、エンキ/エアは再び介入し、雷神アダドを取り込み、人類を滅亡から守ります。このエンキ/エアの介入は、人類の存続にとって不可欠であり、エンリルとの対立構造を明確に示しています。エンキ/エアの役割は、単なる救世主ではなく、神々の世界における秩序維持者、あるいは人間の守護者といった側面も持ち合わせています。この救済劇は、神々の意思決定の多様性と、人間と神との複雑な関係性を物語っています。
4. アダドへの神殿建設と献納
人類は、エンキ/エアの介入とアダドの協力を得て、危機を乗り越えます。その恩返しとして、人間たちはアダドのために神殿を建設し、彼に献納をすることで、雨の恵みを得るようになります。これは、神への信仰と感謝の表現であり、神と人間の相互作用を示す重要な場面です。この神殿建設と献納は、単なる宗教儀式ではなく、社会秩序の維持や安定に貢献する側面も持ち合わせています。雨乞いという行為は、古代メソポタミア社会において、人々の生活に深く関わっていた農業と密接に関連していることを示しています。この描写は、神々と人間との共存関係における、信仰と実践の側面を浮き彫りにしています。
III.人類の滅亡と救済 洪水とその後
エンリルによる人類絶滅の試みは、洪水神話として表現されています。しかし、エンキの介入により、アトラ・ハシースは人類を救済します。その後も、日照りや飢饉に見舞われるも、アダドへの神殿建設と献納によって雨の恵みを得て、人類は生き延びます。この洪水神話は、古代メソポタミアにおける自然災害と人間の信仰、そして神と人間の関わりについて考察する上で重要な手がかりとなります。テキストの欠損部分が多く、完全な理解にはさらなる研究が必要です。
1. エンリルによる滅亡の試みと洪水
エンリルは人類の騒がしさに業を煮やし、嵐の神アダドに命じて雨を降らせず、人間の食料となる草木を減らします。これは、人類を飢餓と渇きによって滅ぼそうとする計画です。この計画は、エンリルの権力と、人類に対する厳しい判断を示しています。この描写は、アトラ・ハシース叙事詩における主要な出来事である洪水を引き起こす直接的な原因となります。テキストには、エンリルの命令に従い、雨は降らず、食料が不足していく様子が詳細に記されているはずです(ただし、現時点のテキスト断片からは具体的な記述は読み取れません)。このエンリルの行動は、後のエンキによる救済との対比において、物語の劇的な展開を形成しています。
2. エンキ エアによる人類の救済
エンキ/エアは、エンリルの計画を予知し、アトラ・ハシースに警告します。アトラ・ハシースはエンキ/エアの助言に従い、疫病神ナムタルを懐柔し、疫病から人類を守ります。これは、エンキ/エアの知恵と魔術の力を示す重要な場面です。この救済劇は、エンリルとエンキ/エアの対立構造を浮き彫りにし、物語の中心テーマの一つとなっています。エンキ/エアは、単に人類を救うだけでなく、神々の間における均衡を保とうとする役割も担っています。この救済は、エンリルの計画の失敗を意味し、物語の展開に大きな影響を与えます。エンキ/エアの介入は、人類と神々との関係、そして神々自身の内部抗争を描写する上で、決定的な要素となっています。
3. 洪水後の世界とアダドへの信仰
洪水の後、再び日照りと飢饉に見舞われた際も、エンキ/エアはアダドを説得し、人類を救済します。この出来事の後、人々はアダドの神殿を建設し、献納をすることで雨の恵みを得るようになります。これは、神々への信仰と、自然災害に対する人間の対応を示す重要な描写です。アダドへの神殿建設と献納は、神々と人間との間の新たな関係性を示唆しています。災害を乗り越えた経験から、人々は神々への信仰を深め、自然の恵みへの感謝を捧げるようになったと解釈できます。この描写は、古代メソポタミア社会における宗教観と、自然災害への対応について貴重な情報を提供しています。テキストの断片的な部分から、この後の社会の再建や安定化の様子が伺えるかもしれません。
4. テキストの欠損部分と今後の研究
本稿で用いたテキスト(B 1-20, D 2-23, Q 1-13)には、欠字や欠損が多く、完全な理解には困難が伴います。特に、洪水後の世界についての記述は断片的にしか残っておらず、詳細な状況を知るためには、さらなる研究が必要です。テキストの復元や解釈は、今後の研究課題となります。様々なテキストを比較検討し、欠損部分を補う努力が必要となります。アトラ・ハシース叙事詩の完全な理解は、古代メソポタミア社会の理解に大きく貢献するでしょう。この叙事詩は、神話、宗教、社会構造など、様々な側面を解き明かすための重要な資料であり、その研究は今後も継続されるべきです。
IV.重要な神々 エンリル エンキ アダド ニサバ
物語には複数の神々が登場します。エンリルは天と地の主神であり、エンキ/エアは知恵と魔術の神、アダドは嵐の神、そしてニサバは穀物や書記術の女神として描かれています。それぞれの神々の役割と属性は、古代メソポタミア神話における神々の体系を理解する上で重要です。特に、エンリルとエンキの対立構造は、創造と破壊、秩序と混沌といった相反する概念の表現として解釈できます。
1. エンリル 天と地の主神 そして人類の滅亡を企てた神
エンリルはアトラ・ハシース叙事詩において、天と地を支配する主神として描かれています。しかし、彼は人間が増えすぎたこと、その騒がしさに悩まされ、人類の絶滅を決定します。この決定は、彼の権力と厳格さを示す一方、短絡的な判断であったとも解釈できます。彼は嵐の神アダドに命じて雨を降らせず、食料を断つことで人類を滅ぼそうと試みます。このエンリルの行動は、物語における重要な転換点であり、エンキとの対立構造を形成する中心的な要素となります。エンリルは、単に神としてではなく、物語の進展を促す重要な役割を担う存在と言えるでしょう。彼の行動は、古代メソポタミアにおける神々の権力と、人間に対する神の対応について多くの示唆を与えてくれます。
2. エンキ エア 知恵と魔術の神 そして人類の守護者
エンキ/エアは、知恵と魔術を司る神として描かれており、エンリルの企みを予知し、アトラ・ハシースに助言を与えて人類を救済します。疫病や飢饉といった災害から人類を守り、アダドを説得して雨を降らせるなど、幾度も人類を危機から救っています。彼は、エンリルとは対照的に、人類に慈悲深い側面を示しています。エンキ/エアの存在は、エンリルの絶対的な権力に対抗する力として機能しており、神々の世界における多様性と複雑性を象徴しています。彼の行動は、神々の間の対立と、人間への関与という点において、物語の重要な柱となっています。エンキ/エアの役割は、単なる救世主というだけでなく、神々の世界における均衡維持者、そして人類の守護神といった複雑な側面を持ち合わせています。
3. アダド 嵐の神 雨と雷を司る神
アダドは、シュメール語ではイシュクルと呼ばれ、雨と雷を司る嵐の神として描かれています。エンリルは、人類を滅ぼすためにアダドに雨を降らせないよう命じますが、エンキ/エアの介入により、最終的には人類を救済する役割も担います。 アッカド語ではAdad、西セム語ではウェルやメルなどと呼ばれ、古代オリエントで広く崇拝されていたと記述されています。彼の性格は、エンリルやエンキのように明確に善悪で区分されるわけではなく、エンリルの命令に従う一方で、エンキの介入によって人類を救済するといった複雑な側面を持っています。 この神は、自然現象を司る神として、古代メソポタミアの人々の生活に密接に関わっていたと考えられます。アダドへの神殿建設と献納は、人々の信仰と、自然災害に対する対応を示す重要な描写です。
4. ニサバ 穀物と書記術の女神
ニサバは、穀物と書記術の女神として登場します。テキストの一部には、ニサバの胸に鍵をかけるという記述があり、これは穀物の生産や管理を制限することを意味していると考えられます。グデアの碑文では書記術の守護神として言及されており、前2千年紀後半からはナブーがその役割を担うようになったとされています。ニサバは、AnとUrasの娘であり、Ninsunの妹、女神Sudの母、そして倉庫の神Hayaの妻であると記述があります。これらの記述は、ニサバが古代メソポタミア社会において、穀物生産という重要な経済活動と、知識・記録の伝承という文化的側面の両方に深く関わっていたことを示しています。彼女の役割は、他の神々とは異なる、社会と文化における重要な側面を担っていると言えるでしょう。
V.メソポタミア農業と塩害問題
テキストでは、メソポタミアにおける農業、特に塩害問題が言及されています。乾燥した気候と灌漑農業によって塩害が発生し、麦類の生産に大きな影響を与えていたことがわかります。古代メソポタミア文明の農業技術と、自然環境との関わりが、物語の背景として理解できます。塩害対策は、メソポタミアの生存に不可欠な課題だったことが窺えます。
1. メソポタミア農業の特徴と課題
アトラ・ハシース叙事詩の記述から、メソポタミアの農業が、高温乾燥気候の下で灌漑農業に依存していたことがわかります。麦類の生産増大のためには、土壌の塩化という大きな課題がありました。これは、南部の灌漑農業において特に深刻な問題であり、土壌の塩化を防ぐための技術と管理が不可欠でした。十分な運河や水路の管理、適切な水量の確保が、農業生産に大きく影響を与えていたと考えられます。これらの記述から、メソポタミアの農業が自然環境に大きく左右され、常に困難な条件下にあったことがわかります。この農業環境は、叙事詩における飢饉や日照りの描写と深く関連しており、物語の背景理解に不可欠な要素となります。
2. 塩害問題の深刻さとその対策
メソポタミア農業にとって、土壌の塩化は最も深刻な問題の一つでした。耕地が塩化により白くなる現象は、農業生産に壊滅的な打撃を与えます。この塩害への対策は、灌漑農業を行うメソポタミアにとって死活問題でした。灌漑管理の徹底が重要であった一方、自然条件が常に人々の努力を上回ることもあったと推測できます。運河や水路の維持管理の不足、水量の不足による土壌洗浄の不備などが、塩害を悪化させ、飢饉を引き起こしたと考えられます。この塩害問題への取り組みは、古代メソポタミアの人々の技術力と、自然環境への対応力を示す重要な指標となります。叙事詩における飢饉の描写は、この塩害問題と関連付けて解釈する必要があります。
3. 飢饉とナルドゥ草 生存のための苦闘
テキストには、飢饉によって人々の容貌が変化し、ナルドゥ草を食べて生き延びようとする様子が描かれています。二年目には倉庫が空になり、三年目には飢餓の深刻さがさらに増していきます。この描写は、メソポタミアにおける飢饉の現実と、人々の生存のための苦闘を克明に伝えています。 ナルドゥ草は、飢餓の際に食料として利用された植物と考えられます。この記述は、古代メソポタミアにおける食料事情と、その不安定さを示しています。 人々がアトラ・ハシースから神々への指針を得たという記述は、宗教と信仰が、厳しい自然環境下での生存において重要な役割を果たしていたことを示唆しています。この飢饉の描写は、メソポタミア社会の脆弱さと、人々の信仰心といった様々な側面を浮き彫りにしています。
