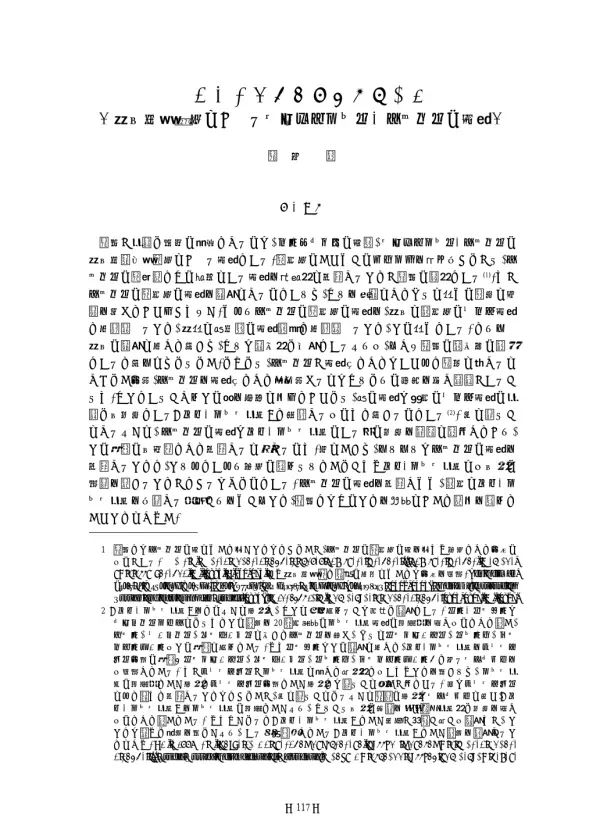
イワノフのネオ・スラヴ主義と第一次大戦
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 446.07 KB |
概要
I.ネオ スラヴ主義とイワノフの思想的背景
本稿は、第一次世界大戦期のヴャチェスラフ・イワノフの思想を、同時代のロシア思想、特にネオ・スラヴ主義との関連において考察する。イワノフの思想は、国民の無意識を言葉に変換する詩人を生み出すことや、ディオニュソス的な悲劇による国民的集団主体の生成といった、美学と密接に結びついた国民論を特徴とする。戦前の中心であった美学は、戦時期には西欧の普遍主義に対抗するロシア国民主体の創出という戦争論へと発展する。
1. 第一次世界大戦期におけるヴャチェスラフ イワノフの思想と研究目的
本稿は、シンボリズムの詩人、ヴャチェスラフ・イワノフの第一次世界大戦期における思想を主要な考察対象とする。戦時期のテクストを分析し、イワノフの戦争論と、その背景にある思想を批判的に検討することが目的である。イワノフは思想家としては傍系に属するため、彼の思想を取り上げるには、その根拠を示す必要がある。彼の思想は、当時のロシア思想における主要な傾向の一つである「ネオ・スラヴ主義」と共鳴すると言える。この点について、本稿ではネオ・スラヴ主義との関連性を明らかにすることで、イワノフの思想をロシア思想史の中に位置づけることを目指す。また、戦前のイワノフの思想の中心は美学にあったが、それは国民主体の創出を意図した政治的なものであり、戦後の国民論や戦争論と断絶はないとされている。
2. イワノフの美学と政治思想 国民主体の創出
イワノフの戦前の美学は、国民の無意識を言葉に変換する詩人を生み出すこと、あるいは、ディオニュソス的な悲劇を通して国民という集団的主体の生成を促すことを試みていた。国民の問題はイワノフの思想全体に貫流しており、戦前の美学と戦後の思想を繋ぐ重要な要素である。しかし、戦前の美学における国民論は、分裂した国民の統一という内的な問題に焦点を当てていたのに対し、戦時期の国民論は、ロシアの国民主体の創出を通じて西欧の普遍主義に対抗するという、より広範な外的な問題へと発展した。この戦時期の国民論を検討することで、戦前の美学についてもより深い理解が得られるとされている。イワノフの芸術による社会変革という思想は、西欧の合理性の外部にあるロシアの国民主体の確立と不可分であり、戦前の美学のみの検討では理解が不十分であると指摘されている。
3. イワノフの国民論とネオ スラヴ主義との関係性の考察
本稿では、イワノフの戦時期の思想を解明するために、ネオ・スラヴ主義との関連性、そしてイワノフの思想全体に貫流する国民の問題の解明という二つの課題に取り組む。ネオ・スラヴ主義は、ロシアを含むすべての国民の聖性を擁護し、世界戦争における対立軸を、ロシア対ドイツ、あるいはロシア対西欧といった単純な図式で捉えるのではなく、国民性一般とドイツの侵略性という対立構造として捉える傾向がある。この点においてイワノフも同様の立場を取っており、彼の思想のネオ・スラヴ主義的な特徴を明らかにすることが重要となる。 モスクワ宗教哲学協会の1914年10月6日の講演会(セルゲイ・ブルガーコフ、エルン、ラチンスキイ、エヴゲーニイ・トルベツコイらが出席)の記録と、セミョーン・フランクの論評が、ネオ・スラヴ主義の分析に役立つ重要な資料として提示されている。
II.イワノフにおける普遍主義批判とロシア的アイデンティティ
イワノフの普遍主義批判は、一つの原理を世界化しようとする普遍主義が国民性や文化の多様性を抑圧することを批判するものであった。しかし、その批判の裏面には、国民の特殊性を神秘化・本質主義化する特殊主義の傾向も存在する。戦時期のイワノフは汎スラヴ主義に傾斜し、スラヴ世界の統一を目指した。彼は、アポロン的なゲルマン・ロマンス系に対し、スラヴ人はディオニュソス的な生命力を持つと主張し、経験的な共通性ではなく、ソボールノスチといった深層的な精神的結合をスラヴのアイデンティティの根拠とした。
1. イワノフの普遍主義批判 多様性と特殊主義
イワノフは、一つの原理を世界化しようとする普遍主義が、諸国民の国民性や国民文化の多様性を抑圧し、隠蔽してしまうことを批判する。これはネオ・スラヴ主義の志向とも共通するが、イワノフの批判は、国民の特殊性を神秘化し、本質主義化する特殊主義の要素を伴っている点で複雑である。普遍主義への対抗として国民を神聖不可侵なものと見なすならば、今度はその国民が変更不可能な本来性となり、多様な差異が抑圧されるというジレンマが提示される。この普遍主義批判と特殊主義の両面を理解することが、イワノフ思想の理解に不可欠である。 彼の批判は、一見中立的に見える人間主義をも含む広範なものに及ぶ。
2. スラヴ アイデンティティの探求 アポロンとディオニュソス
イワノフは、戦時期に汎スラヴ主義に傾斜し、スラヴ世界の統一に関心を示した。しかし、スラヴ世界には政治的・宗教的・文化的統一がないことを認識していたため、血や言語や心理といった経験的な共通性ではなく、別のアイデンティティの根拠を探求した。そこで彼が提示したのが、ディオニュソス的なアイデンティティである。ゲルマン・ロマンス系のスラヴ諸民族がアポロン的秩序を基盤とするのに対し、スラヴ人は太古よりディオニュソスの忠実な奉仕者であり、奔放な生命力を持ち、統制から解き放たれた存在であるとイワノフは主張する。このディオニュソス的特性こそが、スラヴ人の本質であり、カント的な西欧的普遍主義の規範性を相対化し、スラヴ人を解放する根拠となる。
3. ソボールノスチとロシア的アイデンティティ 普遍主義批判の帰結
イワノフの特殊主義は、ソボールノスチという概念に集約される。ソボールノスチは、本来はキリスト教における全信仰者の結合を表す概念だが、イワノフはそれをロシア独自の共同体概念として用いる。個人主義や社会階級を解体し、国民を全体化しようとするこの共同体概念は、自由主義や社会主義に対するオルタナティブとして機能する。ドイツの「文化的組織」という普遍主義イデオロギーに対抗するものとして、イワノフはロシア固有のソボールノスチ、すなわち個々人が独自性を保ちつつ共同性を見出す結合様式を主張する。ソボールノスチは、ロシア国民の内面に先験的に書き込まれたものであり、西欧の普遍主義を相対化し、ロシアの特殊性を擁護する原理として機能する。イワノフはスラヴ主義を積極的に評価するが、それはスラヴ主義もまた国民共同体を神学化しようとした運動であったと捉えているためである。
4. ドイツの 文化 概念批判とイワノフの特殊主義
イワノフの普遍主義批判は、ドイツの「文化」概念にも向けられる。ラチンスキイがドイツ文化を聖域と見なすのに対し、イワノフは変質したドイツの「文化」を、新種の普遍主義イデオロギーとして告発する。ドイツは「文化」を「市民」、「教養」、「啓蒙」といった概念と取り替え、他のヨーロッパ諸国民に強制的に押し付けようとしているとイワノフは主張する。西川長夫の指摘を援用し、文明と文化という概念がフランスとドイツの対抗関係の中で国家イデオロギーとして発展してきたことを示し、イワノフがドイツの帝国主義化と「文化」概念の普遍主義的転化を見抜いていたと論じている。カント的主体という西欧的人間像を批判し、スラヴ人のディオニュソス性を本来的なものとすることで、普遍主義の規範性を奪おうとするイワノフの思想は、特殊主義と普遍主義批判が複雑に絡み合ったものである。
III.ソボールノスチと特殊主義からの普遍主義への転換
イワノフは、ドイツの「文化」概念を新種の普遍主義イデオロギーと批判する。一方、彼はロシア独自の共同体概念であるソボールノスチを提示する。最初はロシア固有の特殊性として捉えられていたソボールノスチが、やがてすべての国民共同体が平等に共存する世界秩序の原理を表す概念へと転化する。この転換は、特殊主義を徹底することで逆説的に普遍主義に到達する過程と言える。トルベツコイらのネオ・スラヴ主義者も、諸国民の特殊性を保持しつつ統一を目指すという点でイワノフと共通する理想を持つ。
1. ソボールノスチの概念と機能 ロシア的特殊性の原理
イワノフは、ドイツの普遍主義に対抗するロシアの特殊性の原理としてソボールノスチを提示する。ソボールノスチは、ロシア国民の内面に先験的に書き込まれた共同体の原理であり、自由主義やドイツの組織化とは異なる結合様式を表す。個々人が本来の独自性や創造的自由を保ちつつ、内面に共同性を見出す結合がソボールノスチの特徴である。 それは、ドイツが強制的に個人を結合させ人格を破壊するやり方とは対照的であり、ロシアの本来的な社会体制として位置づけられる。 ソボールノスチは、スラヴ人の内面に先験的に備わり、直観的に了解されるが、外国語には翻訳不可能なため、他国民には理解できないという特徴を持つ。 そのため、ソボールノスチは、スラヴのアイデンティティそのものと言える。
2. 特殊主義からの普遍主義への転換 ソボールノスチの二重性
イワノフの特殊主義は、どのように普遍主義へと転化するのかが論点となる。 彼の思想において、「ソボールノスチ」という概念は、ロシア固有の共同体原理を表すだけでなく、すべての国民共同体が平等に共存する世界秩序の原理も同時に表す。 同一の概念がオブジェクトレベル(ロシアの共同体)とメタレベル(世界秩序)で用いられることで、論理的な水準の混同が生じている。 しかし、イワノフの普遍主義は、同化主義的な普遍主義とは異なる。同化主義は自国民の特殊性を普遍化して他国民に押し付けるが、イワノフはロシアの特殊性を普遍化せず、むしろ他者の特殊性を擁護することで普遍主義を構築しようとする。特殊主義を徹底することで、逆説的に普遍主義に到達するという独特の論理構造を持つ。
3. ネオ スラヴ主義における共通の理想と差異 トルベツコイとの比較
イワノフの多元主義的な立場は、ネオ・スラヴ主義の文脈において理解される。ネオ・スラヴ主義者は、ロシア中心主義ではなく、諸国民の平等な共存を理想とする。 これは、ロシアを特権化するスラヴ主義とは異なる点である。イワノフは、このネオ・スラヴ主義の系譜に属する思想家であると同時に、スラヴ主義を積極的に評価する。これは矛盾ではなく、スラヴ主義も国民共同体を神学化しようとした運動であったというイワノフの見解に基づく。 トルベツコイは、諸国民の特殊性を保持しつつ精神生活の領域で統一を実現するという理想を掲げるが、これはイワノフの「全世界教会の多数の蝋燭を立てた燭台」という比喩で表される世界秩序の理想と一致する。 両者はスラヴ主義に対する立場は異なるものの、同じ理想を共有しており、それがネオ・スラヴ主義の特徴の一つと言える。ベルジャーエフとの比較を通して、国民共同体の神学化という共通基盤と、スラヴ主義解釈における相違点が示される。
IV.イワノフの戦争論 二つの全体性
イワノフの戦争論は、聖戦論とは異なる。彼はドイツをアンチ・キリスト、ロシアをキリストに喩えるが、それは空間的な世界の覇権争いではなく、経験的な全体とは異なる「深層的・精神的」な全体、вселенскийな全体をめぐる闘いである。この二つの全体性の概念は、西谷修のヘーゲルの歴史終焉論との関連で理解できる。イワノフにとっての世界戦争は、歴史を超越した先験的な秩序、世界秩序としてのソボールノスチを確立するための契機なのである。
1. イワノフの戦争論 聖戦論からの脱却
イワノフの戦争論は、一見聖戦論のように見えるが、決定的に異なる点がある。彼はドイツをアンチ・キリスト、ロシアをキリストに喩え、「全教会的=世界的な事業」と表現するが、これは世界の覇権争いではなく、別の次元での闘いと捉えている。イワノフは、ドイツの普遍主義(空間的な全体)とロシアの理念(深層的・精神的な全体、вселенскийな全体)を対立させる。スラヴ主義的な戦争論は、西欧的原理の崩壊後にロシア的原理が世界化する図式に基づくが、イワノフの戦争論は、空間的な全体とは異なる、深層的な全体を想定する点で異なっている。 ドイツは空間的な全体を領有しようとするが、ロシアはそれとは別の、ドイツが到達できない全体を目指しているため、両者の対立は対等なものではないとされている。
2. 二つの全体性 空間的全体と深層的 精神的全体
イワノフの戦争論の核心は、二つの全体性の概念にある。一つは、経験的な事実に基づく空間的な全体であり、これは恣意的に分割され、境界変更が可能で、偽りの普遍主義を生み出す。もう一つは、経験的な事実から遊離した深層的・精神的な全体(вселенскийな全体)であり、これは主観的な構成を許容する。西谷修のヘーゲル解釈を援用し、ヘーゲルの歴史終焉論における全体性と比較することで、イワノフの二つの全体性の概念がより明確に説明される。ヘーゲルにおける全体性はヨーロッパの全体性に過ぎなかったが、イワノフは、それを超えた、全ての国民の無意識的な本質が共有する全体性を想定している。世界戦争は、この深層的・精神的な全体へと移行するための契機と位置づけられる。
3. 世界戦争とソボールノスチ 歴史の超克と新たな世界秩序
イワノフにとって、世界戦争は、人類が自己の無意識を意識にもたらし、歴史を超越した先験的な秩序を確立する契機である。空間的な全体(ドイツの目指すもの)の領有をめぐる争いではなく、深層的な全体(ソボールノスチ)の開示が重要となる。 戦争が始まってからの三ヶ月間を「深淵」「時間の穴」と表現し、世界が外面的な歴史の段階から歴史を超越した段階へ移行したと捉える。この「時間の穴」の先には、諸国民が自身のヌーメン的な国民性を自覚し、世界秩序としてのソボールノスチを確立した世界が開かれる。 ソボールノスチの意味を直観的に把握できるロシア国民が、この移行を実現する使命を担うとイワノフは主張する。空間的な全体は、国民のヌーメン的本質を実現するための媒体であり、ドイツの侵略はそれを妨げるものと見なされている。
V.イワノフ思想の総括と今後の課題
イワノフの思想とネオ・スラヴ主義の共通点は、「国民共同体の神学化」という傾向にある。国民共同体を先験的に定められたものと見なすことで、ネーションに回収されない差異や矛盾を抑圧してしまうという問題点がある。また、ソボールノスチの概念を特殊なものと普遍的なもの両方に適用することで、新たな普遍主義に陥る危険性も孕んでいる。今後の課題としては、「国民共同体の神学化」が生じた背景の解明や、イワノフの美学と政治の相互関係の解明などが挙げられる。重要な人物として、セルゲイ・ブルガーコフ、エルン、ラチンスキイ、エヴゲーニイ・トルベツコイ、セミョーン・フランクなどが挙げられる。
1. イワノフ思想の総括 ネオ スラヴ主義との共通点と相違点
イワノフの戦時期の思想は、ネオ・スラヴ主義との共通点を多く持つ。両者の根幹にあるのは、「国民共同体の神学化」という傾向、つまり国民共同体を先験的に定められた変更不可能な統一体と見なす考え方である。この傾向から、普遍主義やメシアニズムへの批判、諸国民の平和共存への理想化といった共通の思想が派生する。しかし、イワノフはスラヴ主義とネオ・スラヴ主義を明確に区別し、国民的同一性の根拠を「歴史」から「無意識」へと転換したと分析する。ネオ・スラヴ主義、そしてイワノフの思想を貫くのは、「歴史」と「無意識」という二項対立であり、経験的な歴史を超越した先験的な無意識に国民共同体の本質を見出すという傾向が、両者を繋ぐ重要な要素となる。イワノフの国民論、戦争論、普遍主義批判は、すべてこの二項対立に方向付けられている。
2. イワノフ思想への批判的検討 二つの問題点
イワノフ思想への批判は、大きく分けて二つの点に集約される。一つ目は、ネオ・スラヴ主義全体に共通する問題点であり、国民共同体を先験的な統一体と見なすことで、ネーションに回収されない多様な差異や矛盾が抑圧されてしまうことである。「国民」を無意識的な本質と同一視することで、「階級」といった歴史的に生成された集団が、二次的、あるいは偽りのものと見なされる。二つ目は、イワノフの特殊主義が新たな普遍主義に陥る危険性である。彼は同化主義的な普遍主義を批判するが、ソボールノスチの原理を世界秩序にも適用することで、新たな普遍主義を生み出す可能性を秘めている。 ソボールノスチは、ロシア独自の特殊な共同体原理でありながら、同時に世界秩序の原理ともなってしまうという矛盾を抱えている。
3. 今後の研究課題 国民共同体の神学化と美学 政治の相互関係
今後の研究課題として、まず「国民共同体の神学化」の傾向が生じた理由の解明が挙げられる。時代状況、特に世界の全体化やロシアにおける階級対立の激化が重要な要因であると考えられるが、詳細な検討が必要である。また、イワノフの戦前の美学と戦時期の思想の関連性の解明も重要となる。彼の普遍主義批判は、ネーションを国際関係という外的な視点から問題化することで、戦前の美学における政治的志向がネーションの問題に回収される理由を明らかにする。しかし、イワノフの思想では美学の政治化だけでなく、政治の美学化も考慮しなければならない。特に戦争論における二つの全体性の概念は、経験的な空間的全体と、主観的な構成を許容する深層的・精神的全体という対比を示し、政治の美学化を示唆している。
