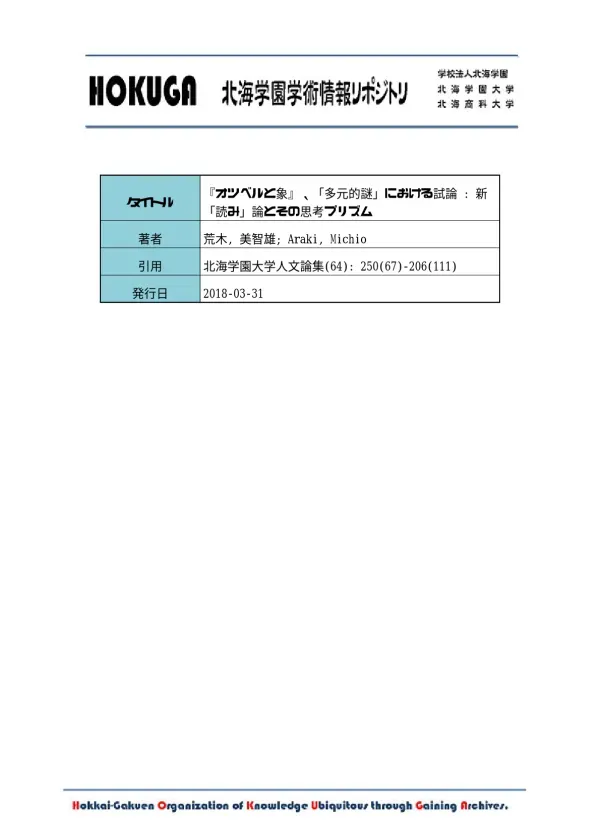
オツベルと象:多元的謎の新たな読み解き
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.88 MB |
| 著者 | Araki, Michio |
| 文書タイプ | 試論 (Essay) |
概要
I.第一日曜 賢治の宗教観と オツベルと象 の 読み
本稿は、宮沢賢治の童話『オツベルと象』における多元的謎を解き明かす試論です。特に、物語中に繰り返し現れる「のんのん」という擬音語の持つ意味や、賢治の宗教観(仏教、キリスト教、イスラム教の要素を含む)と作品世界との関連性を分析します。六という数字への賢治のこだわりや、最小の完全数への言及なども考察対象となります。第一日曜の描写から、物語全体の解釈(読み解き)のプリズムを探ります。
1. 宮沢賢治の 六 へのこだわりと神秘主義
この小節では、宮沢賢治の作品における「六」という数字への異常なまでのこだわりについて考察しています。単なる偶然の一致ではなく、賢治が雪の結晶や蜜蜂の巣の六角形構造、そして最小の完全数(全ての約数の和が自身に等しい数)といった数学的・自然科学的な事実に神秘的な意味を見出していた可能性を示唆しています。この考察は、彼の宗教観や作品世界を理解する上で重要な視点を提供し、後述する「のんのん」という擬音語の連続にも繋がります。賢治の科学者としての側面と、彼の作品に潜む神秘主義的な側面の両方を考慮することで、より多角的な解釈が可能になることを示唆しています。 彼の発想の源泉を探ることで、「オツベルと象」の奥深い意味を解き明かそうとしています。
2. のんのん の連続と六角形の反復 擬音語の持つ意味
本稿の核心的な部分として、物語中に繰り返し登場する「のんのんのんのんのんのん」という擬音語の連続に着目しています。この連続する「のん」は、六回繰り返されている点に注目し、前述の「六」への賢治のこだわりと関連付けて考察されています。この擬音語は単なる音の描写ではなく、作品全体の雰囲気やテーマを象徴的に表現していると捉え、その意味を深く掘り下げています。この「のんのん」の反復は、機械の動作音として描写されていますが、同時に、作品全体の構造や、物語に隠された謎を解き明かすための重要な鍵となる可能性を示唆しています。この擬音語を分析することで、作品全体の「読み」を大きく変える可能性を秘めていることを強調しています。
3. オツベルと象 本文の描写分析 導入部分の解釈
この小節では、『オツベルと象』の冒頭部分の描写、「オツベルときたら大したもんだ。稲扱機械の六台も据えつけて、のんのんのんのんのんのんと、おおそろしない音をたててやつてゐる。」を詳細に分析しています。 この描写は、物語全体の雰囲気やオツベルという人物像を把握する上で非常に重要であり、後の展開を理解する上で重要な手がかりとなります。「六台」という記述からも、前述の「六」への賢治のこだわりが再確認され、物語全体の構造を理解する上で重要な視点となります。 また、「おおそろしない音」という表現は、機械の動作音としての側面だけでなく、物語全体に漂う不穏な雰囲気や、物語の背後に潜む謎を暗示している可能性を示唆しています。この冒頭の描写分析を通して、物語全体への新たな「読み」の可能性を提示しています。
II.第二日曜 異次元の宗教論と経済論のプリズム
第二日曜に関する謎(白象への鎖や靴の贈与、オツベルの策略、赤い帽子の象徴性、サンタマリアへの嘆願など)を経済性と宗教性の両面から考察します。オツベルの行動を資本主義や小作争議と関連付ける従来の解釈に加え、『アメニモマケズ』におけるデクノボー論との関連性も探ります。白象の受動的な態度と、オツベルの巧妙な搾取行為の背後にある謎を解き明かします。重要な登場人物はオツベルと白象です。
1. 第二日曜の謎 経済性と宗教性の二面性
この小節では、『オツベルと象』の第二日曜に描かれる様々な謎を、経済的な側面と宗教的な側面の両方から分析しています。具体的には、オツベルが白象に時計、鎖、靴といった品物を強引に与える行為、川から水を汲むよう依頼するオツベルの意図、オツベルが両手を隠す仕草、オツベルの赤い帽子と第五日曜の童子の赤い着物の共通性、そして白象が月に向かって「ああ、せいせいした。サンタマリア。」と繰り返す行為などが挙げられます。これらの出来事を、単なる偶然の一致として片付けるのではなく、オツベルの経済的な搾取行為と、作品全体に潜む宗教的な象徴性を深く結びつけて解釈することで、物語の背後にある複雑な構造を解き明かそうとしています。 特に、白象の受動的な態度と、オツベルの巧妙な策略が、現代社会の資本主義や小作争議といった問題を暗示している可能性が考察されています。
2. デクノボー論との比較 白象の行動原理の探求
第二小節では、宮沢賢治の他の作品に登場する「デクノボー」という概念を導入し、白象の受動的な行動を分析しています。デクノボーは、困難や苦難に遭いながらも弱者救済のために行動する存在として描かれることが多いですが、白象はオツベルの策略に無関心であり、搾取される農民にも関心を示しません。この白象とデクノボーとの明確な差異に着目し、白象の行動原理を探る試みが行われています。白象がオツベルの要求を簡単に受け入れる「能天気さ」の裏に隠された意味、そして白象の行動が持つ意味を多角的に考察することで、白象というキャラクター像をより深く理解しようとしています。時計、鎖、靴といった品物は白象にとって無価値ですが、人間社会における「贅沢品」として捉えることで、オツベルの経済的な策略との関連性が示唆されます。
3. オツベルの経済性 策略と搾取のメカニズム
この小節では、オツベルの行動における「経済性」という側面に焦点を当てています。オツベルは白象から労働力を搾取するために、決して強制ではなく、策略を交えた提案という形で白象の「意志」を確認しながら、協力を得ています。この巧妙な搾取方法、そして白象の驚くべきまでの受動的な態度、さらに藁の量の巧妙な削減、そして白象の絶望的な嘆き「苦しいです。サンタマリア。」といった描写が詳細に分析されています。オツベルの行為を単なる策略として片付けるのではなく、その背後にあるより深い意味、例えば、神による試練といった解釈の可能性も示唆されています。 鎌田均氏の指摘も引用されながら、オツベルの行動の背後にある複雑な心理構造や意図を解き明かそうとしています。
III.童子と着飾る 赤 宗教的象徴としての考察
作品中に繰り返し登場する「赤」の象徴性(オツベルの帽子、童子の着物など)を分析します。赤の色が持つ意味を、仏教、キリスト教、イスラム教といった多様な宗教的文脈から考察し、サンタマリアや月の象徴性との関連性を探ります。勝徳赤衣菩薩との関連性も検討します。この章では、宮沢賢治が色に込めた意図を主題解明の鍵として捉えます。
1. 赤 の多様な解釈 辞書的意味と宗教的象徴性
この小節では、『オツベルと象』における「赤」という色の象徴性を多角的に分析しています。まず、「赤」を辞書的に解釈することで、「しゃくえ」(赤色の衣服)や「せきい」(赤い着物)といった言葉の意味を、広辞苑や新選漢和辞典を参照しながら解説しています。さらに、仏教、キリスト教、イスラム教といった異なる宗教的背景を考慮に入れながら、「赤」が持つ意味を多様な角度から考察しています。 例えば、童子の赤い着物が仏教徒の象徴なのか、それとも何か裏の意図を持つ人物の象徴なのかといった問いを立て、単一の宗教的解釈に留まらない多層的な解釈の可能性を示唆しています。宮澤賢治の作品に頻繁に登場する「赤」の色が、単なる描写ではなく、物語全体を理解する上で重要な象徴として機能していることを示唆し、その宗教的な意味合いを深く探求しています。
2. 赤衣と宗教 仏教 キリスト教 イスラム教の三位一体
この小節では、『オツベルと象』における「赤」の象徴性が、仏教、キリスト教、イスラム教という三つの宗教とどのように関連しているのかを考察しています。物語に仏教(白象)、キリスト教(サンタマリア)、イスラム教(月)の要素が混在している点を指摘し、それらの宗教を単独で適用するのではなく、三位一体として捉えることで、より多角的な「読み」が可能になることを示唆しています。 また、童子の赤い着物を仏教の「勝徳赤衣菩薩」と関連付ける解釈も提示され、多様な宗教的視点を取り入れることで、作品全体の理解を深められる可能性を示唆しています。清水正氏の聖書に基づいた解釈なども踏まえながら、多様な宗教的象徴性を理解することによって、作品世界をより深く理解できることを主張しています。
3. 月とサンタマリア 沈黙と対話 そして白象の内面
この小節では、白象が繰り返し呼びかける「サンタマリア」と、それに呼応するように登場する「月」の象徴性について考察しています。サンタマリアは沈黙を貫き、代わりに月が白象に語りかけます。この奇妙な構図を、白象の内面における「他者」との対話として捉える解釈が提示されています。月が突然男言葉で語りかけるという点も注目されており、白象自身の内面にある葛藤や矛盾を表している可能性が示唆されています。サンタマリアと月という異質な二つの宗教的象徴を対比させることで、白象というキャラクターの複雑な内面世界を深く探り、作品全体の主題に迫ろうとしています。 この解釈によって、作品に含まれる宗教的な要素をさらに多層的に捉え直す試みがなされています。
IV.第五日曜 死と労働 そして 読み の完結編
本稿の最終章は、第五日曜の謎を整理し、これまでの考察を踏まえて『オツベルと象』全体の主題を明らかにします。白象の死、労働の喜びと喪失、オツベルの経済性、そして物語の語り手である牛飼いの役割を分析し、作品全体の解釈を提示します。白象の正体、山の象、オツベルへの語り、そして白象の死といった重要な要素を読み解きます。重要なキーワードとして、理想郷の喪失、労働の価値などが挙げられます。
1. 白象の死と自己嫌悪 労働の虚しさ
この小節では、『オツベルと象』の第五日曜における白象の死とその背景にある心理状態を分析しています。白象の死は、単なる物語の終結ではなく、白象自身の内面的な葛藤と深い悲しみを表している可能性が示唆されています。 白象は、自身の甘さや弱さゆえにオツベルに利用され、不幸な結果を招いたという自己嫌悪を抱いていたと推測され、その死は、自己嫌悪からくる絶望の表れとして解釈されています。さらに、白象はオツベルの金儲け主義の道具でしかなかったという現実を理解し、深い悲しみを味わったと推測されています。単なる経済的な搾取だけでなく、労働の価値や自己存在意義といった、より深いレベルでの喪失感を白象が抱いていたという解釈が示されています。
2. 労働の価値と理想郷の喪失 多面的な読み解き
この小節では、白象の死を通して、労働の価値や理想郷の喪失といったテーマを考察しています。白象は、汗水たらして働く喜びを経験していたにも関わらず、その労働は農民への感謝と直接結びついておらず、オツベルによる経済的な搾取の道具でしかなかったという皮肉な現実が分析されています。この労働の状況をどう意味付けるか、という点が重要な問題として提示されています。白象の経験は、単なる経済的な搾取だけでなく、労働の喜びや目的意識といった、より深いレベルでの喪失感を示唆しています。 デクノボー論的な視点も取り入れながら、白象の労働に対する複雑な感情や、理想郷の喪失感といった多面的な解釈が提示されています。
3. 川に入る ことの象徴性 帰郷と死の暗示
この小節では、物語の結末部分で示唆されている「川に入る」という行為の象徴性を考察しています。 様々な研究者がこの部分について様々な解釈を示している点を踏まえつつ、新校本宮澤賢治全集第十二巻を主要なテキストとして、この行為が白象にとってどのような意味を持つのかを分析しています。 「川に入る」行為は、白象が森を離れ人里に進み、稲扱小屋に入る行為と同様に危険を伴う行動であると解釈されています。物語の語り手である牛飼いは、白象に危険を避けて故郷の森へ帰るよう諭す言葉をかけていると解釈され、この最後の言葉が、作者である賢治自身の願いを込めたものとして読み解かれています。 この解釈を通して、作品全体の主題をより深く理解する試みがなされています。
V.参考文献
本稿では、清水正、鎌田均、池上雄三、小森陽一、西田良子など、多くの研究者のオツベルと象に関する論考を参照しています。特に、『新校本宮澤賢治全集』第十二巻を主要なテキストとして使用しています。 これら研究者の解釈を踏まえつつ、独自の分析を進めています。
1. 主要参考文献 宮沢賢治研究の多様な視点
本稿では、『オツベルと象』の解釈を深めるために、多くの研究者の論考を参照しています。 清水正氏の著作は、特に重要な参考文献として挙げられており、聖書に基づいた深い読み解きが紹介されています。 また、鎌田均氏の鋭い「語り」の視点からの分析、池上雄三氏による資本主義や小作争議との関連付け、西田良子氏による経済的な視点からの再検討などが紹介されています。 さらに、小森陽一氏、田中実氏、須貝千里氏、横山信幸氏といった研究者たちの論考も参照されており、それぞれの研究者が異なる視点から『オツベルと象』を分析していることがわかります。 これらの多様な解釈を参考に、本稿独自の分析が展開されていることが示されています。特に、『新校本宮澤賢治全集』第十二巻は主要なテキストとして用いられていることが明記されています。
2. 参考文献の多様性と本稿の位置付け
参考文献リストからは、宮沢賢治研究における多様な解釈とアプローチが示されています。 例えば、資本主義的視点からの解釈(西田良子、宇佐美眞、門倉昭治、池上雄三)、宗教的視点からの解釈(清水正)、現象学的視点からの解釈(横山信幸、星川哲慈、永井晋、ウィトゲンシュタイン)、そして児童文学的な視点からの解釈などが挙げられます。これらの多様な解釈を踏まえつつ、本稿では独自の解釈を提示することで、既存の研究成果をさらに発展させることを目指していることがわかります。 それぞれの参考文献が、特定の解釈や分析手法を代表しているため、本稿はそれらを総合的に検討し、新たな解釈を構築しようとしていることが読み取れます。特に、『新校本宮澤賢治全集』第十二巻を主要なテキストとして用いている点が、本稿の解釈の基盤を明確に示しています。
