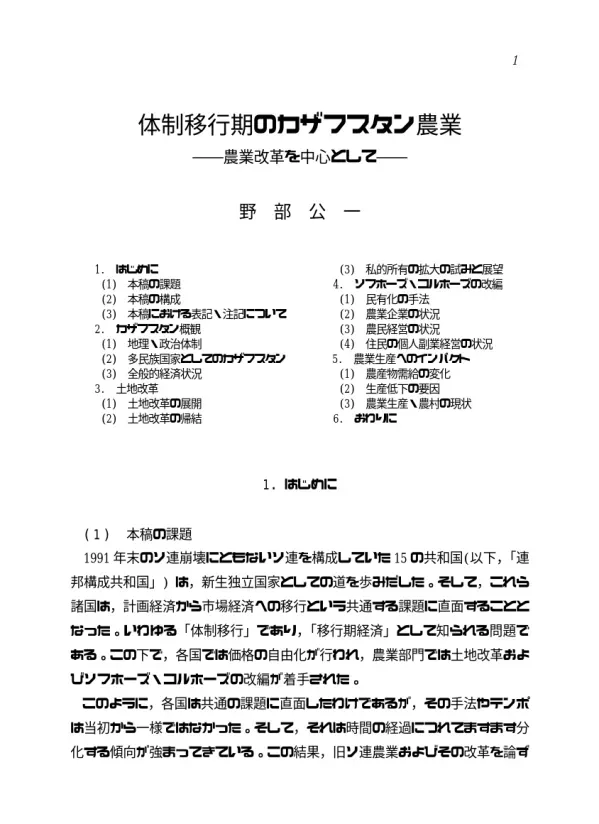
カザフスタン農業改革:体制移行期の生産変動
文書情報
| 著者 | 野部公一 |
| 専攻 | 農業経済学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 724.13 KB |
概要
I.カザフスタンにおける土地改革と農業生産の現状
本稿は、旧ソ連崩壊後のカザフスタン共和国における土地改革と農業生産の現状を分析し、ロシアとの比較を通じて旧ソ連農業の動向をより正確に把握することを目的とする。カザフスタン農業は、ソ連時代からの穀物生産を基盤とする一方、体制転換後の市場経済移行に伴い、深刻な問題に直面している。農業改革の中心は、ソフホーズ・コルホーズの改編と土地利用権市場の創出だが、収益性の低い農業生産という根本的な問題が解決されない限り、土地改革は生産回復の起爆剤とはなりえない。
1. カザフスタンの農業生産とソ連時代からの構造
カザフスタンは旧ソ連時代から穀物、羊毛、食肉供給基地として重要な役割を担い、特に高品質な穀物生産で知られていた。ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタンは綿花生産に特化し、カザフスタンの穀物に依存する食料供給体制が構築されていた。このため、カザフスタンでは国内需要を大幅に上回る生産能力が整備され、その農業はGDPの大きな部分を占めていた(1990年には25%)。しかし、ソ連崩壊後の体制転換により、計画経済から市場経済への移行が試みられ、カザフスタン農業は大きな変化を遂げることとなる。この体制転換がカザフスタン農業生産に与えた影響と、ロシアの事例との比較を通して旧ソ連農業の動向を分析することが本稿の目的である。特に、ソ連崩壊後の土地改革と農業生産の現状に焦点を当て、その課題を明らかにする。
2. 市場経済移行と農業政策の失敗
カザフスタン政府は、市場経済への移行に伴い、それまでの農業支援政策をほぼ完全に放棄した。ソ連時代から続く上流(生産財供給)・下流(農産物加工・流通)部門の独占構造も放置されたまま、価格自由化に踏み切った。その結果、価格自由化は生産要素の効率的な分配という本来の目的とは裏腹に、独占企業による価格支配を招き、農業生産の崩壊を加速させた。これは中東欧諸国や旧ソ連諸国で「市場の失敗」と呼ばれる現象であり、カザフスタンにおいて典型的に現れたと言える。更に、政府による補助金や低利融資の削減は、農業の近代化や技術革新を阻害し、農業生産の粗放化を招いた。例えば、1993年には羊毛への補助金が計画額のわずか1%しか支出されず、1994年以降は事実上全廃された。この農業政策の失敗は、1998年の歴史的な不作という形で顕著に現れた。
3. 土地改革の現状と課題 土地利用権市場の不活発と私的所有の問題
カザフスタンにおける土地改革は、土地所有権の問題を棚上げし、土地利用権市場の創出を通じて土地利用の効率化・流動化を目指した。しかし、農業生産が収益を上げない状況では、土地は資産としての価値をほとんどもたず、土地利用権の取引も不活発だった。土地持ち分の取引は行われたものの、それは農場内の取引に限定され、対価も小さく、法的保障も不足していた。結果として、土地持ち分はわずかな対価でかつてのソフホーズ・コルホーズの経営陣に集積され、生産の効率化には繋がらなかった。非カザフ系住民への所有制限導入も、反発を招き、カザフスタン憲法第14条(差別禁止)との矛盾も指摘されている。現状では、農用地への私的所有導入が検討されているが、農業生産の収益性向上という根本的な問題が解決されなければ、生産回復の起爆剤とはなりえない。
4. 農業企業の改編とインテグレーションの現状
ソフホーズ・コルホーズの改編は、市場経済に対応したコンパクトで機動的な経営形態の創出を目指していた。しかし、交易条件の悪化と政府支援の激減により、初期費用とリスクが大きい農民経営は敬遠された。統計上は農民経営が増加したものの、その多くは大規模農業企業であり、集団労働に基づく経営形態が維持された。1992年の民有化では、ソフホーズ資産の労働者集団への無償譲渡や割引価格での売却が行われたが、慢性的な赤字経営の企業が対象とされたものの、収益性の高い企業も売却されるケースがあった。また、資産の評価額はインフレにより市場価格の数分の一となっており、法令違反も指摘されている。穀物商社などの大企業による農業企業の買収(インテグレーション)も進み、1998年には穀物収穫の三分の一以上をインテグレーション化された経営が担うまでに至った。このインテグレーションは政府から肯定的に評価される一方で、「似非私有経営」として批判されている。
5. カザフスタン農業の危機的状況と今後の展望
カザフスタン農業の現状は危機的である。生産条件の悪化、経済関係の現物化、農業生産の粗放化が進行し、生産量は低下し、気象条件に大きく左右されるようになった。1998年の穀物生産は1955年以来の不作となり、食用穀物、種子用穀物、飼料用穀物を考慮すると穀物バランスはマイナスとなった。そのため、伝統的な穀物輸出国であったカザフスタンが穀物輸入国に転落する可能性が懸念されている。農村部の失業率は高く、約80%の農村住民が貧困境界線上に位置している。農業生産の落ち込みを受けて、農業政策の変更と国家支援の拡大を求める声が強まっている。1999年には、エネルギー・産業・通商大臣が農業への国家支援拡大を主張し、メディアで繰り返し報道された。農業の再生には、国家支援の再開、農業生産の収益性向上のための抜本的な対策が必要不可欠である。
II.土地改革の段階と課題
土地改革は、仮想土地持ち分による再配分(1990-1993年)、ソフホーズ・コルホーズの改編と民有化、そして将来的な私的所有拡大という三つの段階に分けられる。初期の改革では、効率的な土地利用を目指したが、非カザフ系住民への所有制限や、旧体制の特権層(ノメンクラトゥーラ)による資産の集中といった問題が発生した。仮想土地持ち分の取引は不透明で法的保障も不足しており、土地利用の効率化は進んでいない。
1. 仮想土地持ち分による土地再配分 1990 1993年
カザフスタンの土地改革は、1990年11月16日のカザフ・ソヴィエト社会主義共和国土地法典と、1991年6月28日の土地改革に関するカザフスタン共和国法に基づき開始された。初期段階では、ソ連土地基本法の枠内で、ソフホーズ・コルホーズの土地を再分配し、新たな農業経営を創出することが目標とされた。具体的には、未利用地や非効率的に利用されている土地を没収して「特別土地フォンド」を創設し、そこから農民経営や個人副業経営を希望する市民に優先的に土地が与えられた。コルホーズやその他の農業企業には土地の「恒常的占有権」が与えられ、個人副業経営用地の規模上限も緩和され、農業生産者間の土地賃貸も許可された。しかし、この段階では、土地の所有権問題は棚上げされており、あくまで土地利用権の再配分が中心であった。 この初期の土地改革は、シルダリア川やイリ川を中心とした灌漑地の整備とあいまって南部地域で急速に進展した一方で、多くのカザフ人が不毛な土地に移住を余儀なくされるなど、民族的な問題も孕んでいた。
2. 仮想土地持ち分の取引と問題点
1997年8月から12月にかけて東カザフスタン州とジャンブール州で行われた調査によると、「仮想土地持ち分」の取引は、主に農業企業の指導者やその親族間で行われ、家畜飼料や食料品、燃料などのサービス提供の約束と引き換えに譲渡または贈与されるのが一般的であった。一見すると市場が成立しているように見えるが、その実態は問題が多く、譲渡の約束は法的拘束力を持たない場合が一般的であり、契約が締結されたとしても、譲渡側の多くが契約内容を理解しておらず、契約書の写しも持っていなかった。この取引の不透明さや法的保障の欠如は、土地利用権市場の活性化を阻害する大きな要因となった。更に、非カザフ人に対する所有制限導入の試みは、非カザフ人からの強い反発を招き、カザフスタン憲法第14条(出自・民族による差別禁止)との矛盾も指摘されている。カザフ人側にも、帝政時代からの土地配分の不平等を是正すべきだという意見があり、土地私有化導入以前の問題として残されている。
3. 土地改革の今後の課題 私的所有導入の可能性と困難さ
現在、農用地への私的所有導入が検討されているが、記事では、農業生産が収益を上げないという根本的な条件が変化しない限り、私的所有導入は生産回復の起爆剤にはなりえないと指摘している。土地改革の初期段階においては、ソ連時代の法制度の枠組みの中で、土地利用権の再配分が行われた。しかし、この段階では、土地の所有権に関する問題は明確に解決されず、結果的に土地の効率的な利用や流動化は進んでいない。土地利用権の取引は限定的な規模でしか行われず、その対価も小さく法的保障も不十分であるため、土地は資産としての価値をほとんどもたない。そのため、土地持ち分は、わずかな対価でかつてのソフホーズ・コルホーズの経営陣に集中し、生産の効率化よりも旧来の関係維持という結果をもたらしている。土地改革の成功のためには、農業生産の収益性向上という根本的な課題への対応が不可欠であることが示唆されている。
III.農業企業の民有化とインテグレーション
ソフホーズ資産の民有化は、労働者集団への無償譲渡や割引価格での売却を伴ったが、多くの場合、大規模で非効率な企業がそのまま存続、あるいは形式的な改編にとどまった。一方、穀物商社などの大企業による農業企業の買収(インテグレーション)が進み、1998年には穀物収穫の三分の一以上をこうした大企業が担うようになった。カーギル社はカザフスタン企業と共同で「デン」を設立し、穀物輸出を行っている。このインテグレーションは、政府からは肯定的に評価されている一方、「似非私有経営」への批判も存在する。
1. ソフホーズ資産の民有化 1992年の大統領令と実際
1992年、カザフスタンではソフホーズ資産の民有化が開始され、慢性的な赤字を抱えるソフホーズを対象に、労働者集団への無償譲渡や割引価格での売却が行われた。これは1992年2月8日付け大統領令「農工コンプレックスの国有農業、調達、加工およびサービス企業の資産民有化に関する緊急諸方策について」に基づくもので、労働者集団が新たな企業を創出する場合は、資産は無償または割引価格で譲渡された。しかし、実際には収益性の高いソフホーズも売却されるケースがあり、1994年1月1日の評価額が基準とされたものの、インフレの影響で市場価格の数分の一に過ぎなかった。一部では法令の公然たる侵犯も見られたと記述されている。この民有化は、外見上は有償買い戻し方式を採用していたが、本質的にはロシアと同様の労働者集団への無償譲渡に近いものであった。また、1995年には新民法典が採択され、法人形態が限定されたため、ソフホーズ、コルホーズ、小企業、集団企業は新たな法人形態への改編を余儀なくされたが、多くの場合、労働組織や生産体制は維持され、単なる看板替えに終わったと批判されている。
2. ノメンクラトゥーラ民有化と資産の集中
ソフホーズの売却過程においては、「ノメンクラトゥーラ(旧体制の特権層)民有化」が問題視されている。売却対象は慢性的な赤字経営とされていたが、しばしば収益性の高い企業が売却され、例えば西カザフスタン州では年間39%の収益率を上げたソフホーズ「クウシウムスキー」が売却された例が挙げられている。また、「国有農業企業の市民の私的所有への売却に関する臨時規程」と「ソフホーズ資産の一部の所長への譲渡に関して」という大統領令によって、資産の特定層への集中が制度的に促進された。前者は慢性的な赤字経営の資産の20%を農場内競売で売却し、残りの有償資産の一部を落札者への5年以内の臨時利用権として与えるもので、後者は20年以上勤務したソフホーズ所長に有償資産の10%を無償譲渡、更に10%の5年以内の臨時利用権を与えるものである。これらの措置により、特定の個人への資産集中が容認されたと言える。
3. 農業企業のインテグレーション 大企業による買収と政府の評価
民有化や上記の措置を経て、穀物商社だけでなく、加工企業や投入財生産・供給企業が農場の所有権・管理権を獲得し、インテグレーションが急速に進展した。1998年の穀物収穫の三分の一はインテグレーション化された経営によって収穫され、1999年の春播においても、穀物商社の播種面積は全体の4割以上に達した。例として、アメリカのカーギル社はカザフスタン企業と共同出資で現地法人「デン」を1993年に設立し、ロシア・ウズベキスタン向けの穀物輸出を行っている(1998年5月には20万トンの輸出契約)。カザフスタン政府は、このインテグレーションを肯定的に評価し、能力のない経営者から能力のある経営者への所有権移転、市場の機能開始の証拠であるとしている。しかし、一方で「似非私有経営」として批判もされており、その実態は複雑である。
IV.農業生産の悪化と国家支援の縮小
価格自由化、国家支援の劇的な削減、農工間の価格差拡大などにより、農業生産は深刻な打撃を受けた。機械・トラクターの老朽化、肥料投入の激減、畜産の衰退など、農業の粗放化が進み、1998年には歴史的な不作となった。穀物生産量の減少は、旱魃だけでなく、粗放化によるものも大きい。国民経済における農業の割合は、1990年のGDPの25%から1998年には14.1%へと減少している。
1. 価格自由化と農業の交易条件悪化
カザフスタンでは、ロシアに倣い1992年1月に価格自由化が実施された。しかし、これは農業生産に大きな悪影響を与えた。価格自由化によって工業製品の価格は急騰したのに対し、農産物の生産者価格は低く抑えられた。これは、ソ連時代から続く農産物加工・流通企業の独占構造が維持されたためである。特定の地域の農業生産者は、特定の加工・流通企業に農産物を販売するしかなく、価格交渉において極めて不利な立場に置かれた。さらに、国家支援の劇的な削減、農工間の価格差拡大も、農業生産の悪化を招いた要因である。ソ連時代には投入財が補助金によって原価を下回る価格で供給されていたが、価格自由化によって投入財価格が是正されたことで、農業の交易条件は更に悪化した。ロシアの移行経済問題研究所の調査によると、ロシアで農産物価格と投入財価格の関係が世界価格に等しくなったのは1994年であり、カザフスタンでは1993年の時点で既に世界価格を基準としても著しく劣悪な交易条件になっていた。
2. 国家支援の縮小と農業機械 肥料の減少
国家による農業支援は、財源不足から1994年以降事実上全廃された。1993年には羊毛への補助金が3050億ルーブル計上されていたが、実際に支出されたのはわずか16億ルーブルにとどまった。この支援の縮小は、農業機械の老朽化・減少を招いた。1996年時点で穀物コンバインの減少は危機的状況にあり、1998年には満足な状態の農業機械は全体の3~6%程度、70~75%は償却期間を過ぎた状態であった。トラクターについても同様の状況であり、抜本的な対策がとられない限り、数年後には完全に使用不能になる可能性が指摘されている。肥料の投入も激減し、特に化学肥料は1997年には全播種面積のわずか0.9%にしか投入されておらず、穀物生産への影響は甚大であった。穀物経営研究所の試算によれば、肥料投入量の減少により最低でも200万トンの穀物減産が生じていると推定されている。
3. 畜産の衰退と農村の過放牧 労働力過剰
畜産においても、人工受精などの獣医学的サービスはほとんど利用されなくなり、燃料費や水源維持費の節約のため、遠隔地の放牧地が放棄されるようになった。1995年までに全放牧地の約20%が放棄され、家畜の飼育は村落周辺に集中するようになった。この結果、家畜頭数の減少と広大な放牧地の存在にもかかわらず、村落周辺では過放牧の状態となり、土壌浸食が各地で発生している。1997年の農業分野での直接労働支出は1990年と比べて約15億人時減少しており、農村には72万6000人以上の過剰労働力が存在すると推定されている。生産合理化が進めば、現在の労働者の50%までが解雇される可能性があり、農村・社会全体の安定に深刻な影響を与える可能性が指摘されている。1998年の穀物生産は1955年以来の歴史的な不作となり、これは旱魃に加え、農業政策の結果としての粗放化の進行が大きな要因であった。カザフスタンでは年間400万トン以上の食用穀物と200万トン以上の種子用穀物が最低限必要であり、飼料用穀物を考慮すると、1998年は穀物バランスがマイナスとなった。
4. 農業生産の粗放化と農業政策の転換の必要性
1995年の穀物経営研究所の実験では、同一の土壌で異なる農業技術を用いた場合の春小麦の収量を比較した結果、簡略化された現在の農業技術では、1980年代中盤の技術の半分以下の収量しか得られないことが明らかになった。これは農業の粗放化が生産量に大きな影響を与えていることを示している。農業生産の落ち込みを反映して、農業政策の変更、特に国家支援の拡大を求める声が強まっている。1999年1月から3月にかけて、エネルギー・産業・通商省大臣は、農業を市場に放り投げ、保護することを忘れていたと批判し、農業への投資の必要性を訴えた。カザフスタン農業の現状は危機的であり、正常な生産条件の確保、経済関係の現物化の是正、農業生産の粗放化の阻止が急務である。市場経済移行に伴う農業改革は、市場の失敗という結果を招き、農業生産の低下と農村の不安定化を招いていることが指摘されている。
V.農業政策の失敗と今後の課題
カザフスタンにおける農業改革は、「市場経済に移行すれば、すべての問題は自動的に解決する」という発想に基づいて行われたが、市場の失敗(Market Failure)が顕著に見られた。政府は農業への国家支援を放棄し、独占構造を放置した結果、価格自由化は生産崩壊を招いた。農業生産が収益を上げない状況では、土地は資産としての価値を持たず、土地利用権市場も不活発である。農業の再生には、農業への国家支援の拡大、生産条件の改善が不可欠である。
1. 市場経済移行と農業政策の誤算
カザフスタンの農業改革は、『市場経済に移行すれば問題は自動的に解決する』という前提で行われた。しかし、この発想は誤りであった。政府はそれまでの農業支援策をほぼ完全に放棄し、ソ連時代から続く上流・下流部門の独占構造も放置した。価格自由化は、生産要素の効率的な分配ではなく、独占企業による価格支配をもたらし、生産崩壊を加速させた。これは中東欧諸国や旧ソ連諸国で「市場の失敗」と呼ばれる典型的な現象である。生産調整は、価格自由化による農業の交易条件悪化という厳しい状況下で行われた。生産財供給企業と農産物加工・流通企業における独占構造は、交易条件の悪化を更に加速させ、短期間で世界価格を基準としても著しく劣悪なものとなった。政府は農業支援を大幅に削減し、その削減を市場経済への移行の進展と解釈した。農業企業の破産や債権者への売却も、市場経済の定着の証拠として扱われたが、これは資本主義国よりも市場原理を優先した結果と言える。
2. 農業生産の低迷と土地の価値低下
農業生産が収益を上げないという根本的な問題が解決されない限り、土地は資産としての価値を持たず、必要な資金調達も困難である。土地利用権の取引も不活発で、行われた取引も農場内取引に限定され、対価は小さく法的保障も欠如していた。土地持ち分は、かつてのソフホーズ・コルホーズの経営陣に集積され、生産の効率化には繋がらず、旧来の関係維持という結果になった。現在、農用地への私的所有導入が検討されているが、農業生産の収益性向上という根本的な条件が変化しない限り、生産回復の起爆剤とはなり得ない。ソフホーズ・コルホーズの改編は、市場経済に対応したコンパクトで機動的な経営形態の創出を目指していたが、交易条件の悪化と政府支援の激減によって、初期費用とリスクの高い農民経営は敬遠された。統計上は農民経営が増加したものの、その多くは集団労働に基づく大規模農業企業であった。
3. 1998年の不作と農村の危機的状況
1998年の穀物生産は、1955年以来の歴史的な不作となった。これは北部の旱魃という気象条件に加え、農業政策の結果としての粗放化の進行が大きな要因である。カザフスタンでは年間で食用穀物400万トン以上、種子用穀物200万トン以上が必要であり、飼料用穀物を考慮すると、1998年は穀物収支がマイナスとなった。このため、伝統的な穀物輸出国であったカザフスタンが輸入国に転落する可能性が懸念されている。農村では社会的緊張が高まっており、多くの農民がソフホーズ・コルホーズの改編で土地・資産を失い、失業率は極めて高い。農村住民の約80%が貧困境界線上に位置している。カザフスタン農業の現状は危機的で、正常な生産条件は確保されず、経済関係の現物化と農業生産の粗放化が同時進行した結果、生産は低下し、気象条件に大きく左右されるようになった。
4. 今後の課題 国家支援の再開と農業政策の転換
農業生産の落ち込みを反映し、農業政策の変更、特に国家支援の拡大を求める声が強まっている。1999年1月から3月にかけて、エネルギー・産業・通商大臣は、農業への国家支援拡大の必要性を訴えた。彼は『農業を市場に放り投げ、それを保護することを忘れていた』と述べ、農業においても収入を得るためには他のビジネスと同様に投資が必要であると主張した。今後の課題は、農業生産の収益性向上、農業機械の更新、肥料投入量の増加、畜産の活性化など多岐に渡る。そのためには、農業への国家支援の再開、生産条件の改善、市場メカニズムの適切な活用など、総合的な取り組みが求められる。 単純な市場原理の適用だけでは、農業の再生は困難であることが示唆されている。
