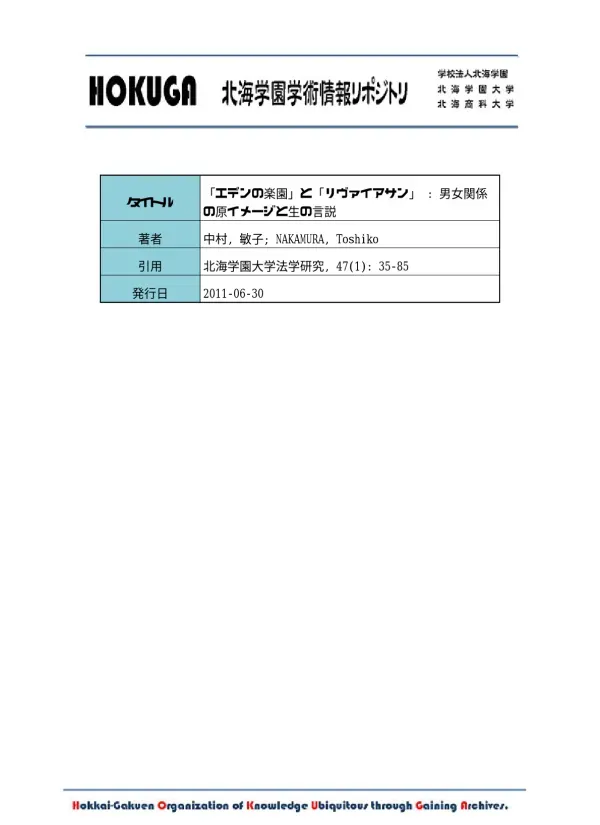
キリスト教と男女関係:原罪とジェンダー
文書情報
| 著者 | Nakamura, Toshiko |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 777.61 KB |
概要
I.初期キリスト教における 原罪 と 性 の概念
初期キリスト教では、創世記のアダムとイヴの物語が原罪の起源として解釈され、特に性と深く結び付けられました。イエスの処女懐胎は、性行為による罪からの自由を象徴し、ユダヤ社会の家族制度や結婚の概念とは対照的なものとして描かれています。初期の信者にとって、キリスト教は家族のしがらみからの解放をも意味しました。しかし、この初期の解釈は、後のキリスト教思想にどのように影響を与えたのでしょうか?
1. イエスとユダヤ社会の挑戦
このセクションでは、イエスの処女懐胎が、性行為による罪からの自由を象徴しているという点が強調されています。イエスはユダヤ社会において最も神聖視されていた家族の義務を拒否することで、当時のユダヤ社会のあり方に対する根本的な挑戦を行いました。当時のユダヤ社会では、結婚、つまり性行為の目的は生殖にあるとされていました。このイエスの行動は、キリスト教徒にとって、家族のしがらみから逃れて自由を獲得する道として機能した側面がある一方、多くのキリスト教徒にとって、性と関連するヒエラルキーに基づいた社会全体の構造を理解する上で重要な要素にもなっていました。初期のキリスト教徒たちは、性行為を完全に否定することはせず、それを結婚生活に限定しようとする試みが見られます。これは、原罪と性の概念がどのように初期キリスト教において理解されていたかを示す重要な部分です。イエスの行動が、後のキリスト教における性と原罪の解釈にどう影響したのか、その繋がりを考える上で重要な考察です。
2. 初期キリスト教における原罪と性の解釈の多様性
この部分では、初期のユダヤ人やキリスト教徒が、創世記において自由の契機を見出していたことと、後のアウグスティヌスの解釈との対比が示されています。神への背信によって善悪の判断力を得たとされる人間の罪は、徐々に性や肉体と関連して解釈されるようになりました。例えば、アダムが禁断の果実を食べたのは、神の命令に反することを認識していたにもかかわらず、女性と別れずに罪を共有したからだと解釈されています。この解釈は、男女の結婚と子どもの誕生に関する記述が、一見すると現代の状況と変わらないように見えるという点にも触れています。また、人間の肉において、現在では欲情を伴わずしては決して動かされない部分も、意志のみによって動かされると解釈することは困難ではなかったとされています。これら初期の解釈は、後のアウグスティヌスの厳格な原罪観とは対照的な多様性を示しており、原罪と性の概念がどのように理解され、変化してきたのかを示唆しています。創世記の解釈における多様性とその後のキリスト教思想への影響は、このセクションにおける重要なテーマです。
II.アウグスティヌスの 原罪 観と 女性
アウグスティヌスは、原罪を人間の性と密接に関連づけ、人間のすべての性と生を罪深いものと見なしました。彼は、アダムとイヴの物語を、人間の社会秩序の基礎とするパラダイムとして捉え、女性を原罪の重要な要因と位置づけています。アウグスティヌスの解釈は、女性への否定的な見解を強化し、後のキリスト教における女性の抑圧に大きな影響を与えました。彼の原罪観は、どのように後のキリスト教思想、特に女性の役割や地位に影響を与えたのかが注目されます。 彼の著作、特に創世記注解での議論が重要です。
1. アウグスティヌスの原罪観と性の関連性
アウグスティヌスは、人間の罪を性と深く結びつけて解釈しました。初期のユダヤ人やキリスト教徒が創世記に自由の契機を見出していたのに対し、アウグスティヌスはアダムとイヴの物語を、人間の社会秩序を規定する基本的なパラダイムとして捉えました。彼は、アダムの犯した罪の結果として人間に与えられた罰は、子を生むことによって全人類に伝えられると考えたのです。そして、アウグスティヌスは、すべての人間の性と生を原罪に関わる罪深いものとして位置づけました。これは、単にアダムとイヴの物語の解釈にとどまらず、人間の存在全体を原罪の文脈で捉え直す試みであり、後のキリスト教における原罪観に大きな影響を与えました。彼の解釈において、人間の肉体的側面、特に性が、原罪とどのように関連づけられているのかが焦点となっています。
2. 女性と原罪 アウグスティヌスの見解
アウグスティヌスの原罪観において、女性は重要な役割を担っています。彼は、他の教父のように女性を一方的悪と断罪するのではなく、アダムとイヴの物語における女性の役割に着目し、原罪の文脈で女性の罪を深く考察しました。アウグスティヌスは、アダムとイヴの物語を人間社会の秩序づけの基本的なパラダイムとして捉え、その物語の中で女性が果たした役割を分析することで、原罪がどのように人間社会に影響を与えたのかを説明しようと試みました。このことは、後のキリスト教において、女性が原罪とどのように関連づけられ、社会的にどのような位置づけを与えられてきたのかを考える上で重要な視点となります。アウグスティヌスの原罪観が、後のキリスト教における女性観に及ぼした影響は計り知れません。彼の解釈が、女性の抑圧や否定的なイメージの形成にどう関与したのか、その歴史的影響を検証していく必要があります。創世記注解において、彼は蛇と関連付けて悪魔について論じており、女性への批判的な視点が含まれています。
III.ホッブズの 自然状態 と 原罪 解釈
ホッブズは、アウグスティヌスの原罪観とは対照的に、人間の本性をより現実的に捉えています。彼の『リヴァイアサン』では、楽園追放後の自然状態における人間の生存闘争を論じ、原罪を、神からの完全な自由を失った状態として解釈しています。彼は、女性に関する記述は少ないものの、アウグスティヌスとは異なり、性差別的な見解を示していません。ホッブズは、原罪の解釈において、中世キリスト教文明の古い神話とは異なる独自の視点を持っていました。彼の『リヴァイアサン』における原罪と自然状態に関する議論は、アウグスティヌスとの対比を通して理解する必要があります。
1. ホッブズの原罪解釈 楽園追放後の自然状態
ホッブズは、アウグスティヌスの原罪観とは異なる視点から、原罪を解釈しました。彼は、アダムとイヴの楽園追放後の状態、つまり人間が神の庇護を失い、自らの知恵で生きなければならない自然状態に注目しています。ホッブズにとっての原罪は、神からの完全な自由を失った状態であり、それはアウグスティヌスの原罪観のように、人間の性や肉体と直接的に結びついているわけではありません。彼は、楽園から追放され、死すべき運命を負った人間が、いかにしてこの世で生き延びるかを考察しています。これは、アウグスティヌスの楽園に関する記述とは対照的なものであり、ホッブズはより現実的な人間の姿を自然状態という概念を通して提示していると言えるでしょう。彼の『リヴァイアサン』における議論は、この点においてアウグスティヌスとの重要な対比を示しています。
2. ホッブズとアウグスティヌスの原罪観の対比
ホッブズの原罪解釈は、アウグスティヌスのそれとは明確に異なっています。アウグスティヌスが原罪を人間の性と深く結びつけ、人間の生を罪深いものと見なしたのに対し、ホッブズは自然状態における人間の生存闘争に焦点を当てています。ホッブズは、アウグスティヌスの楽園に関する記述、特に死の概念と結びついた記述と対立する立場をとっています。アウグスティヌスが原罪を、人間の永遠の生命の喪失と結びつけて解釈したのに対し、ホッブズは、人間の生存というより現実的な問題を重視しています。この違いは、彼らがそれぞれ原罪をどのように捉え、人間の存在をどのように理解していたのかを示す上で非常に重要です。ホッブズは、中世キリスト教文明の古い神話を受け継ぎながらも、独自の原罪解釈を提示することで、アウグスティヌスとは異なる哲学的枠組みを構築しています。
3. ホッブズにおける性とジェンダー
ホッブズの著作において、性別に関する記述は非常に少ないですが、彼はアウグスティヌスとは異なり、女性を原罪の主要な原因とするような否定的な見解を示していません。彼は、強さや深慮において男性と女性との間に決定的な違いはないと述べており、自然状態における人間の平等性を主張しています。これは、アウグスティヌスが女性を原罪に深く関与させる解釈とは対照的です。ホッブズは、性差に基づく差別的な社会構造を批判するような立場ではなく、人間の平等性を強調する点で、キリスト教の歴史の中で形成されてきた女性に関する否定的な言説とは異なるアプローチをとっています。この点において、ホッブズは、アウグスティヌスとは異なる、現代的なジェンダー観に通じる部分があると解釈することもできます。
IV.キリスト教における 性 と 女性 の抑圧
アウグスティヌスの否定的な性に関する教説とパウロの肉体への嫌悪感は、キリスト教の歴史を通して女性を貶め、抑圧する言説を生み出しました。教会の権威を持つ男性たちによる禁欲主義が、女性に対する不平等な社会構造を強化したのです。この歴史的文脈において、女性の権利や地位の問題を考えることが重要です。キリスト教圏における女性の法的権利や社会的地位に関する比較研究が不可欠になります。
1. アウグスティヌスの否定的な性観とパウロの影響
このセクションでは、アウグスティヌスの性に対する否定的な教説と、パウロの肉体に対する嫌悪感が、キリスト教の歴史においてどのように女性を貶め、抑圧する言説を生み出してきたのかが論じられています。アウグスティヌスの性への否定的な見解は、パウロの思想とも合致し、キリスト教における性に関する規範形成に大きな影響を与えました。教会の権威者、つまり男性たちが禁欲を理想としたことが、女性に対する抑圧的な社会構造の構築に繋がったと指摘されています。この歴史的文脈において、性と女性の抑圧という問題が、どのようにキリスト教の教義や社会構造と結びついているのかが考察されています。特に、教会の権力構造と性規範の関連性を分析することで、歴史的な女性抑圧の背景を明らかにしようとしています。
2. キリスト教圏における女性の権利と家父長制
教会の言説が現実世界をも支配することで、現実の国家においても女性をめぐる家父長制的な支配体制が形成されていったとされています。この家父長制は、キリスト教の教義や社会規範と深く結びついており、女性の権利や地位を制限する要因となっています。文書では、キリスト教圏諸国の法制、特に民法における女性の権利がどのように規定されてきたのか、比較研究の必要性が示唆されています。また、家計的条件の制約が緩むことで、キリスト教的な結婚が主流になったという指摘も重要だとされています。この指摘は、社会経済的な要因が、キリスト教における性と結婚の規範、ひいては女性の地位にどう影響を与えたのかを示唆するものです。 ホッブズは、このキリスト教圏で形成されてきた家父長制的な体制とは対照的に、自然状態における人間の平等性を主張した点で注目されています。
