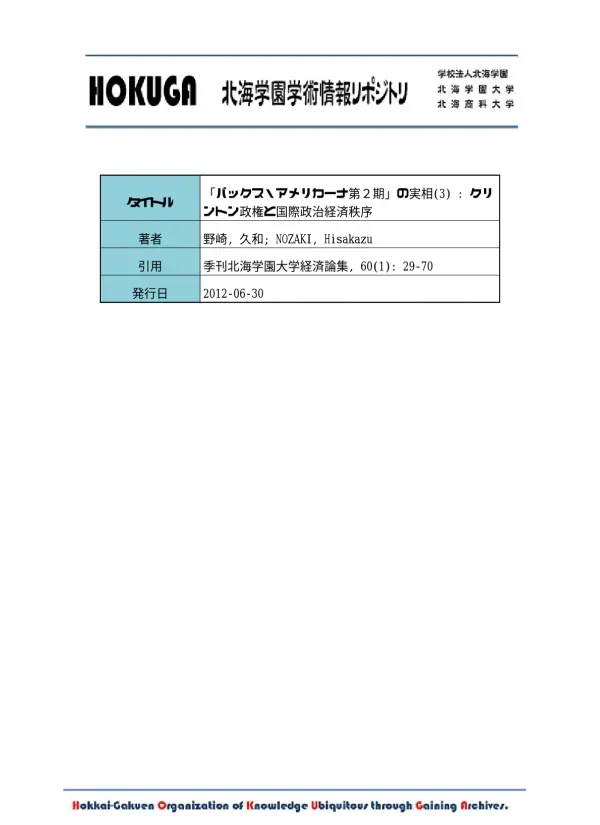
クリントン政権とパックス・アメリカーナ
文書情報
| 著者 | 野崎久和 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.15 MB |
概要
I.クリントン政権の対外経済政策 双子の赤字 克服と 中間層再生 の課題
クリントン政権(クリントン大統領)の主要課題はアメリカの再生であり、財政再建と中間層再生が中心でした。レーガン、ブッシュ父両政権による減税政策とドル高政策の結果生まれた双子の赤字問題への対応と、所得分配不平等の是正が求められました。しかし、雇用なき回復(Jobless Recovery)や中間管理職の削減などにより、中間層再生は思うように進まず、実質賃金は低下しました。WTO発足後、スーパー301条やVERといった一方的な貿易政策は制限されたものの、クリントン政権は二国間協議を重視し、特に日本との日米包括経済協議を通じて、アメリカ製品の輸出拡大を図りました。 日本との交渉では、自動車・自動車部品の市場開放などが焦点となりましたが、結果志向主義貿易政策は各国から批判を受けました。最終的に、アメリカの輸出は期待ほど伸びず、貿易収支赤字は拡大しました。
1. クリントン政権発足とアメリカの再生 双子の赤字問題への対応
クリントン政権の最優先課題は「アメリカの再生」であり、その柱として経済再生・雇用回復、教育改革、医療保険制度改革が挙げられました。特に経済再生・雇用回復に関しては、財政再建、中間層の再生、輸出拡大、IT化推進などが主要課題とされました。この背景には、レーガン、ブッシュ父両大統領の12年間の共和党政権下で、富裕層優遇の減税政策、軍事力拡大政策、ドル高政策が実施された結果、アメリカが深刻な双子の赤字問題に陥り、中間層が忘れ去られ、企業の海外進出が加速したという認識がありました。クリントン政権は、これらの問題を解決するために、積極的な政策を展開しようとしていました。
2. 中間層再生の停滞と所得分配不平等 雇用なき回復と経済構造の変化
しかし、クリントン政権下においても中間層の再生は思うように進展しませんでした。レーガン・ブッシュ父両政権時代から拡大傾向にあった所得分配不平等は、クリントン政権の8年間でもほとんど改善されませんでした。1990年代前半には、景気回復にもかかわらず雇用が伸びない『雇用なき回復(Jobless Recovery)』という現象が見られました。これは、企業によるリストラや、経済グローバル化・IT化に伴う中間管理職のスリム化、ホワイトカラーの没落といった構造的な問題が背景にありました。結果として、労働者の実質賃金は低下を続け、高額所得者の収入だけが伸びるという状況が続きました。
3. クリントン政権の貿易政策 二国間協議の重視と結果志向主義
GATT/WTOを軸とした多角的貿易交渉よりも、クリントン政権はブッシュ父政権以上に二国間協議に傾注しました。最大のターゲットは、対米貿易黒字国である日本でした。日本は新重商主義的な産業・貿易政策や円安によって国際競争力を高め、アメリカの主要産業を脅かしているとアメリカ世論は認識していました。クリントン政権はこの世論を利用し、日本との交渉において、アメリカ製品の輸入義務化や経常収支黒字削減の数値目標などを求める結果志向主義の貿易政策をとりました。この政策は、WTOに基づく多角的自由貿易体制を蝕むものとして各国から批判されました。日米包括経済協議では、自動車・自動車部品、半導体、金融サービスなどの分野で交渉が行われましたが、アメリカ製品の輸出拡大や貿易赤字削減という目標は、必ずしも達成されませんでした。EUとの二国間協議も展開されましたが、同様の結果に終わりました。日米自動車協議では、スーパー301条発動寸前まで交渉が難航したものの、最終的には妥協点が見出されました。
4. 通貨危機への対応 メキシコ アジア ロシア ブラジルなど
クリントン政権下では、メキシコ(1994年)、アジア(1997年)、ロシア(1998年)、ブラジル(1999年)、アルゼンチン(2001年)など、多くの国で通貨危機が発生しました。これらの国は、固定相場制や管理相場制を採用しており、米系ヘッジファンドなどの投資・投機筋による大規模な資本流出が危機を引き起こしました。クリントン政権は、メキシコやロシアに対しては積極的な対応を取りましたが、アジア通貨危機に対しては消極的な対応に終始し、新たな国際通貨制度の検討・構築には至りませんでした。日本政府は新宮澤構想を発表し、また、チェンマイ・イニシアティブによる通貨スワップ協定が締結されるなど、アジア地域における通貨危機対策は強化されていきました。ブラジル通貨危機においても、アメリカを中心としたIMFなどの支援が行われましたが、レアル売りが止まらず、ブラジルは変動相場制に移行せざるを得ませんでした。
II.クリントン政権の外交安全保障政策 拡大戦略 と NATO東方拡大
クリントン政権は冷戦後の新たな対外戦略として、拡大(Enlargement)と関与(Engagement)戦略を掲げ、民主主義と市場経済の拡大を目指しました。これはデモクラティク・ピース論に基づくものでした。特に、NATO東方拡大は大きな政策課題となり、ロシアとの関係悪化を懸念する声もありましたが、クリントン政権は積極的に推進しました。NATO・ロシア協力協定の締結やロシアのG7(のちのG8)参加を促すなど、ロシアとの協調関係を維持しつつNATO拡大を進めました。一方、旧ソ連諸国への経済支援では、IMF、世界銀行などが中心となり、ワシントン・コンセンサスに基づく政策が実施されました。ロシア経済の市場経済化は難航し、ショック療法は初期段階では成功しませんでした。 中東欧諸国では、EU加盟を目指した改革が加速し、西側からの直接投資が増加しました。
1. 冷戦後の新たな対外戦略 拡大と関与
1992年大統領選挙で当選したクリントンにとって、外交安全保障は弱点分野でした。民主党は12年間政権から遠ざかっており、人材不足も懸念されました。そこでクリントンは、冷戦終結後の新たな対外戦略として、「拡大(Enlargement)」と「関与(Engagement)」戦略を打ち出しました。これは、アメリカが誇る民主主義と市場経済を世界に拡大しようとする戦略です。その背景には、民主主義国家同士は戦争をしないという「デモクラティク・ピース論」があり、民主化と市場経済化を通じて世界の安全保障とアメリカの経済・雇用を向上させようという考えがありました。この戦略は、冷戦時代の「封じ込め政策」からの転換を意味していました。
2. ロシア経済の市場経済化と支援 ショック療法とワシントン コンセンサス
冷戦終結後、アメリカは旧ソ連諸国の経済改革を支援しました。1990年のG7ヒューストン・サミットで、IMF、世界銀行、OECD、EBRDの4機関がソ連経済への勧告を行い、翌年ソ連崩壊後、ロシアはこれらの勧告に基づき、価格自由化や国有企業の民営化などの急進的な経済改革(ショック療法)を実施しました。しかし、長年計画経済を続けてきたロシア経済には、ショック療法は少なくとも初期段階ではうまく機能せず、深刻な景気悪化、ハイパーインフレ、食料・物資不足、失業率上昇、貧困拡大など、深刻な問題を引き起こしました。アメリカは、IMFや世界銀行を通じて、財政規律、経済・貿易・投資自由化などを柱とする「ワシントン・コンセンサス」に基づく支援を行い、エリツィン大統領を支援しました。クリントンは、金融・経済支援に加え、個人的な親密さをアピールすることでエリツィン政権を支え、1996年の大統領選挙での再選を支援しました。
3. NATO東方拡大とロシアとの関係 NATO ロシア協力協定とG8への拡大
クリントン政権は、NATOの東方拡大を積極的に推進しました。NATO拡大には、クリントン政権内にも賛否両論がありました。反対派は、ロシアとの関係悪化やロシア国内の改革派への打撃を懸念していました。しかし、クリントンは1996年10月、1999年までにNATOの最初の東方拡大を行うと表明しました。ロシアの懸念を和らげるため、1997年3月の米ロ首脳会議でNATO・ロシア協力協定を提案し、NATO-ロシア常設合同理事会(PJC)の設立に合意しました。これにより、ロシアはNATOの政策方針を共有できるようになりました。さらに、クリントンは同年7月のG7デンバー・サミットでロシアの公式参加を実現させ、ロシアのWTO加盟も支援することを約束しました。中東欧諸国は、EU加盟を目指し改革を進め、IMF、世界銀行、EBRDからの支援を受けました。1990年代後半には、西側企業による中東欧諸国への直接投資が急増しました。EBRDは、ハンガリー、ポーランドなどの中東欧諸国における市場経済化と民主化の進展を評価しました。
III.クリントン政権下の地域紛争への対応 積極的多国間主義 から 選択的多国間主義 へ
クリントン政権は、初期には**積極的多国間主義 (assertive multilateralism)**を掲げ、国連の平和維持活動に積極的に関与しました。しかし、ソマリア紛争での失敗を経験した後、選択的・効率的多国間主義へと転換し、ルワンダ紛争への介入は行いませんでした。これはクリントンにとって大きな後悔となりました。旧ユーゴスラビア紛争では、ボスニア紛争では国連主導の対応が中心でしたが、コソボ紛争では、人道的介入を名目にNATO主導の空爆を実施しました。これは国連安保理を無視したもので、ロシアや中国からの反発を招きました。また、中東和平プロセスにおいては、オスロ合意を支持し、イスラエルとパレスチナ自治政府の交渉を仲介しましたが、和平合意には至りませんでした。 イスラエル首相ヤイツァーク・ラビンの暗殺や、イスラエルとPLOの衝突なども和平交渉の難航要因となりました。重要な人物として、イスラエル首相のラビンとネタニヤフ、パレスチナ議長のアラファトが挙げられます。
1. ソマリア紛争 積極的多国間主義と国連平和維持活動の限界
クリントン政権が最初に直面した地域紛争はソマリア紛争でした。ブッシュ父政権から引き継いだこの紛争では、クリントンはブッシュ父の多国間主義を踏襲し、国連の役割と平和維持活動を重視する「積極的多国間主義(assertive multilateralism)」を唱えました。国連安保理決議794に基づき、アメリカは多国籍軍(UNITAF)に主力として米軍2万8千人を派遣しました。しかし、UNOSOM(国連ソマリア活動)はアイディード派との武力衝突、市民の巻き添え、反国連感情の高まりなど、様々な問題に直面しました。1993年10月にはモガディシオでの戦闘で米兵18名を含む多数の兵士が殺害され、アメリカ国内ではソマリア撤退を求める世論が高まり、議会もそれに追随しました。このソマリアでの経験は、クリントン政権の対地域紛争への対応に大きな影響を与えました。
2. ルワンダ紛争 積極的多国間主義からの転換と介入の失敗
ルワンダでは、フツ族とツチ族の歴史的な対立が内戦へと発展しました。1993年10月には和平合意が成立し、国連ルワンダ支援団(UNAMIR)が和平監視活動を行っていましたが、1994年4月6日、ハビャリマナ大統領暗殺事件をきっかけに、激しい内戦が勃発し、フツ族過激派によるツチ族に対する大規模な虐殺(ルワンダ虐殺)が発生しました。クリントン政権は、このルワンダ紛争にほとんど関与しませんでした。ソマリア紛争での経験から、国連平和維持軍の限界を認識し、積極的多国間主義からより選択的なアプローチへと転換しつつありました。結果として、ルワンダでは大量虐殺が発生し、国際社会からの非難を浴びることになりました。クリントン自身も、ルワンダへの介入の失敗を大統領在任中の最大の後悔の一つとして挙げています。
3. ボスニア紛争とコソボ紛争 国連からNATOへの対応軸の転換
旧ユーゴスラビアでは、ボスニア紛争とコソボ紛争が発生しました。ボスニア紛争では、ブッシュ父政権は西欧主導と国連の権限下での共同行動を強調し、アメリカは直接介入しませんでした。国連保護軍(UNPROFOR)が活動しましたが、米軍は参加していませんでした。しかし、ソマリアとボスニアでの経験から、クリントン政権は国連平和維持軍の限界を認識し、次第にNATO重視へと政策転換していきました。コソボ紛争では、コソボ解放軍(KLA)とセルビア治安部隊の戦闘が激化し、セルビアによるジェノサイドが頻発する事態となりました。アメリカは当初KLAと距離を置いていましたが、1999年1月のラチャクの虐殺を契機に、NATOは国連の許可を得ずにコソボへの空爆を開始しました。これは、ロシアや中国の安保理での拒否権行使を回避するためでした。このコソボ空爆は、NATOの域外軍事行動という新たな役割を示すものであり、クリントン政権はNATOを中東欧にも拡大し、国際紛争への介入モデルとして活用していこうとしました。
4. 中東和平プロセス オスロ合意からキャンプ デービッド合意への展開と限界
クリントン政権は中東和平プロセスにも積極的に関与しました。ノルウェーで秘密裏に行われた交渉によって成立した「オスロ合意」は、パレスチナ暫定自治を認め、最終的地位交渉の開始を規定しました。1994年にはカイロ合意、1995年にはオスロ合意IIが締結され、和平プロセスは進展するかに見えました。しかし、ラビン首相暗殺事件(1995年)を機に、イスラエルとPLOの関係は再び緊張し、和平プロセスは停滞しました。その後、クリントンはネタニヤフ首相とアラファト議長との交渉を仲介し、「ワイ・リヴァー合意」をまとめました。さらに、クリントンはパレスチナ民族憲章からイスラエル敵視条項の削除を促すためパレスチナを訪問しました。しかし、2000年のキャンプ・デービッドでの首脳会談は決裂し、その後シャロン首相の就任、そして第二ブッシュ政権の開始により、中東和平はさらに遠のいていきました。
IV.クリントン政権と国際テロ 大量破壊兵器 問題
クリントン政権下では、アルカイダなどのイスラム原理主義過激派によるテロが深刻な問題となりました。1993年のニューヨーク世界貿易センター爆弾テロ事件は、アメリカ本土における最初のイスラム過激派による大規模テロでした。クリントン政権はテロ対策に努力しましたが、9.11テロを阻止することはできませんでした。また、旧ソ連の大量破壊兵器の拡散防止のため、**CTR(協調的脅威削減プログラム)**が実施されました。**CTBT(包括的核実験禁止条約)**にも署名しましたが、アメリカ上院の批准は得られませんでした。さらに、北朝鮮の核開発問題にも対応しましたが、阻止には至りませんでした。
1. 国際テロの脅威 1993年世界貿易センター爆弾テロ事件とCIAの対応
冷戦後、アルカイダなどのイスラム原理主義過激派によるアメリカを標的としたテロが頻発しました。その最初の大きな事件が、1993年2月26日に発生したニューヨーク世界貿易センター爆弾テロ事件です。この事件は、アメリカ本土でイスラム原理主義者によって起こされた初めての無差別・大規模テロであり、6名の死者と1000名以上の負傷者を出しました。犯行グループは有毒ガスを用いて多数の死傷者を出そうとしていたことが判明し、アメリカ国民に大きな恐怖を与えました。クリントン政権はテロ対策に注力しましたが、CIAはクリントンの指示に必ずしも従わず、2001年9月11日の同時多発テロを阻止することはできませんでした。このCIAの対応の遅れや、クリントン大統領がCIA長官を罷免しなかったことについては、様々な議論があります。クリントン大統領が軍部からの批判を恐れて、積極的な反テロ対策を実行できなかったという指摘もあります。
2. 大量破壊兵器問題 旧ソ連の核兵器管理とCTBT
冷戦終結後、旧ソ連が保有していた大量破壊兵器の管理・処分・不拡散が大きな国際問題となりました。核兵器の売却・横流しや、科学者・技術者の海外流出の懸念が高まりました。アメリカは、旧ソ連の大量破壊兵器の処分・管理・不拡散に対する支援、及び軍民転換の促進のため、1992年にブッシュ父政権が開始した「協調的脅威削減プログラム(CTR)」を引き継ぎました。また、長年交渉が続けられていた「包括的核実験禁止条約(CTBT)」は、1996年9月に国連総会で採択され、クリントン大統領は多くの世界の指導者の中で最初に署名しました。しかし、アメリカ上院は、核実験の禁止が査察不可能であるとしてCTBTの批准を拒否しました。クリントン自身も、軍や議会への配慮から、CTBTで禁止されていない未臨界実験を繰り返し、非核保有国からの批判を受けました。さらに、クリントンは1993年9月、兵器用核分裂物資生産禁止条約(カットオフ条約)の締結を提案しましたが、ジュネーブ軍縮委員会での交渉は進展しませんでした。
