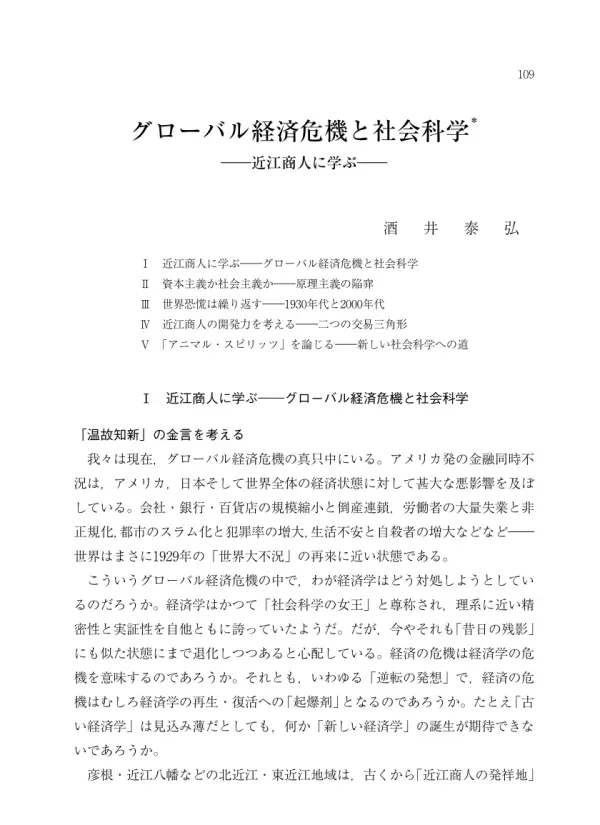
グローバル経済危機と近江商人道
文書情報
| 著者 | 酒井泰弘 |
| 学校 | 滋賀大学 |
| 専攻 | 経済学 |
| 出版年 | 平成( )年 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 821.89 KB |
概要
I.グローバル経済危機と社会科学 近江商人の知恵
本稿は、グローバル経済危機を背景に、現代社会が直面するリスクと、その解決策として近江商人の知恵を再考するものである。特に、近江商人の「三方よし」の精神や開発力、バランス感覚が現代社会の課題解決に繋がる可能性を考察している。経済学の限界を指摘し、アニマル・スピリッツの重要性と、従来の経済学に欠けていた歴史的視点、文化的視点を取り入れた「新しい社会科学」の必要性を主張している。 Joseph StiglitzやPaul Krugmanといった経済学者らの見解も引用しつつ、歴史的視点からの分析を通して、持続可能な社会のあり方を模索している。
1. グローバル経済危機の現状と社会科学の役割
本文は、現在のグローバル経済危機の深刻さを、企業倒産、失業増加、生活不安の増大といった具体的な問題点を挙げて説明から始める。アメリカ発の金融危機が世界経済に与えた壊滅的な影響を強調し、この危機に対する解決策を探ることが本稿の目的であると述べている。滋賀大学におけるリスク経済研究拠点の設立と、成瀬龍夫先生(当時学長)の貢献にも触れ、現在の経済状況と社会問題への関心の高さを示している。特に、近年の経済学や経済学者の実用価値が問われている点を指摘し、多くの著名な経済学者が沈黙を保つ現状を批判的に捉えている。これは、経済学、特にアメリカ学界における経済思想史の軽視という根本原因に起因すると分析している。具体的には、ケインズの『一般理論』やシュンペーターの『経済分析の歴史』といった古典的な著作が、アメリカの大学教育において十分に検討されていない現状を問題視している。
2. 経済学者の責任と歴史的視点の欠如
著者は、経済学者、特に保守主流派の沈黙を批判し、その責任の重さを指摘する。 ゼロ金利政策による「貯蓄より投資へ」というスローガンが、退職金を含む多くの資金をリスクの高い投資信託へと流入させ、人々の生活設計を狂わせた点を問題視している。 アメリカにおける経済思想史の軽視が、今回の危機を予見できなかった原因の一つとして挙げられている。著者のアメリカ留学経験に基づき、ケインズやシュンペーターといった経済学者の著作が大学院レベルでも十分に検討されていない現状を指摘し、歴史的視点の欠如を批判している。 過去の様々なリスクを伴う出来事(集団食中毒、企業倒産、テロなど)を振り返り、歴史から学ぶことの重要性を訴えている。 これは、単なる経済現象ではなく、社会全体に影響を及ぼす問題として捉えられている。
3. 近江商人の 三方よし と新しい社会科学への提言
著者は、近江商人の「三方よし」の精神、勤勉さ、バランス感覚といった伝統的な価値観を、現代社会の課題解決に活かすことを提案する。 近江商人の商人道が、現代の強欲資本主義とは対照的なモデルとして提示され、そこから学ぶべき教訓が多いと主張している。 近江商人の歴史や行動から得られる教訓が、現代社会におけるリスク管理や持続可能な経済発展の指針となる可能性を示唆している。 さらに、近江商人の成功事例を通して、単なる経済学にとどまらず、歴史、伝統、文化といったローカルな視点を考慮した「グローカルな視角」を持つ新しい社会科学の必要性を強調している。 これは、従来の経済学では解決できない問題を解決するための、新たな学問分野の構築を提唱するものである。
4. 過去の危機からの教訓と未来への展望
著者は、過去の経済恐慌や世界大戦といった歴史的事実を振り返り、人為的ミスや歴史的視点の欠如によって危機が繰り返されてきたことを指摘する。 グリーンスパンやクルーグマンといった経済学者の発言を例に、責任回避や危機の深刻さの認識不足を批判する。 1930年代の世界恐慌から第二次世界大戦への流れを説明し、著者の幼少期の体験に基づく戦争の悲惨さを描写している。 2001年の同時多発テロ事件を例に、予想外の出来事が社会に与える衝撃の大きさを強調し、歴史的教訓から学ぶことの重要性を再確認している。サブプライムローン問題を説明し、「もし仮に」という条件付きの思考の危険性を指摘し、歴史的視点に基づいたより現実的な思考の必要性を強調している。 これらの歴史的教訓を踏まえ、新たな価値観と生活様式、そして近江商人の「三方よし」の精神を現代社会に適用することで、持続可能な社会を築く可能性を探っている。
II.近江商人の開発力 二つの交易三角形比較
近世イギリスの奴隷貿易を基盤とした交易三角形と、近江商人の交易三角形を比較することで、両者の商業道徳とリスク管理の相違点を浮き彫りにする。イギリスの三角貿易は、強欲商業資本主義とモラルハザードを象徴する一方、近江商人の交易は、蝦夷地(北海道)、上方(京都・大阪)、江戸を結ぶネットワークを構築し、北前船や東前船を用いた海運による効率的な物流システムを確立していた。 近江商人は「三方よし」の精神に基づき、長期的視点と信頼関係を重視したリスク・プーリングの仕組みを構築していた点を強調している。 地理的な規模は異なれど、近江商人の開発力とフロンティア精神は高く評価されている。
1. イギリスの交易三角形 奴隷貿易と強欲資本主義
この節では、近世イギリスの交易三角形を分析し、その実態を明らかにする。三角形の頂点となるのはイギリス本土、西アフリカ、カリブ海諸島であり、イギリスから西アフリカへの航路では、金属製品、銃器などが運ばれ、西アフリカからカリブ海諸島へは奴隷が運ばれた。そして、カリブ海諸島からイギリスへは、砂糖などの農産物が運ばれた。この交易は、天候に左右される危険な航路であり、奴隷の過酷な扱いも指摘されている。著者は、このイギリスの交易三角形を「強欲商業資本主義の権化」と表現し、その行き過ぎた強欲と猛烈なモラルハザードを批判的に分析している。奴隷貿易という非人道的な行為が、短期的な利益追求のために行われた点を強調し、現代社会への警鐘を鳴らしている。 歴史家トリスタン・ハント氏(Tristan Hunt)の『オブザーバー』紙への寄稿記事「奴隷貿易:イギリスの悲しい歴史の長い奇跡」も紹介され、奴隷貿易廃止の歴史的背景と、その継続時間の長さ、そしてその終焉が「奇跡」として扱われていることに言及している。
2. 近江商人の交易三角形 三方よし と持続可能な発展
対照的に、この節では近江商人の交易三角形が取り上げられる。その頂点は、蝦夷地(主に函館、江差、津軽)、上方(京都、大坂)、江戸(および周辺地域)の三地域である。イギリスの交易三角形と比較して、規模は小さいものの、鎖国下の日本において、近江商人が広大な地域を網羅して交易を行っていた点を強調する。 交易ルートとしては、日本海沿岸を南下する「西回り航路」と、太平洋を南下して江戸へ直行する「東回り航路」があり、後者には「東前船」が使用された。西回り航路には、古いルートと新しいルートがあり、新しいルートでは「北前船」を用いて、効率的な輸送システムが構築されていたことが解説されている。 これらの航路は、「ハイリスク・ハイリターン」であったものの、商人たちは仲間内で海上積立金を通じてリスク・プーリングを行い、北方の海産物を江戸などの消費地へ運搬していた。 その商業道徳は「三方よし」の精神に基づき、長期的な信頼関係を重視していた点が、イギリスの奴隷貿易とは対照的に描かれている。蝦夷地の人々との共存共栄関係を「三方よし」の好例として紹介し、近江商人の倫理観の高さを示している。
3. 二つの交易三角形の比較 商業道徳とリスク管理の対比
この節では、イギリスと近江商人の交易三角形を比較することで、両者の商業道徳やリスク管理における大きな違いを分析する。イギリスの交易三角形は、短期的な利益追求と非人道的な行為を伴う一方、近江商人の交易三角形は、「三方よし」の精神に基づく長期的視点、信頼関係構築、そしてリスク・プーリングによる安定したシステムを特徴としている。 近江商人の交易ルートの開発と効率化、特に「北前船」と「東前船」の役割、そして「古いルート」と「新しいルート」の比較を通して、彼らの革新性と適応能力の高さを示している。 「西回り航路」と「東回り航路」それぞれのメリットとデメリット、そしてそれぞれの航路におけるリスクと、それを軽減するための商人たちの工夫が詳しく説明されている。 地理的規模や政治的状況の違いを考慮しても、近江商人の開発力とフロンティア精神は、バルト商人などの他の商人集団を凌駕するものであったと評価している。 この比較分析を通して、近江商人の成功要因が、単なる経済的な効率性だけでなく、倫理的な側面や持続可能な発展への配慮に深く根ざしている点を明確にしている。
III.アニマル スピリッツと近江商人 新しい社会科学への道
George A. AkerlofとRobert Shillerの共著『アニマル・スピリッツ』を紹介し、アニマル・スピリッツ(人間の心理が経済に与える影響)がグローバル経済危機の発生を予測できなかった点、そしてその対策の重要性を指摘している。Joan Robinsonの研究も引用し、アニマル・スピリッツの概念は決して新しいものではなく、近江商人の成功にも関連性があると主張。しかし、近江商人の成功を単純にアニマル・スピリッツで説明するのではなく、グローカルな視点、つまりグローバルな視点とローカルな歴史・文化の両方を考慮した分析の必要性を訴えている。 近江商人の家訓「星と天秤棒」に象徴される勤勉さ、バランス感覚、そして長期的な視点こそが、現代社会が学ぶべき重要な教訓であると結論づけている。
1. アニマル スピリッツ概念の導入と現代経済への示唆
この節では、AkerlofとShillerの共著『アニマル・スピリッツ』を紹介し、この概念が現代経済、特にグローバル経済危機の理解に不可欠であると論じている。 著者は、この本が人間の心理が経済に及ぼす影響を詳細に分析していることを指摘し、特に今回の大不況が予見できなかったのは、従来の経済理論がアニマル・スピリッツという要素を考慮していなかったからだと主張する。 一般大衆のみならず、学者や政府といった意思決定者もアニマル・スピリッツの概念を理解しておらず、人々の思考様式や経営パターンの変化が経済危機に繋がる可能性を度外視していた点を批判する。 『アニマル・スピリッツ』の結論として、アニマル・スピリッツの考え方と対策が重視される場合のみ、経済問題解決への道筋が見つかるという点を強調し、この概念の重要性を改めて提示している。 本の表紙デザインにも言及し、類人猿のイラストが経済の不安定さを象徴している点を興味深く分析している。
2. Joan Robinsonの研究とアニマル スピリッツ
著者は、AkerlofとShillerの著作においてJoan Robinsonの貢献が十分に評価されていない点を指摘する。 アメリカの大学や学界では、Robinsonの業績が「不完全競争の理論」に限定されて評価されている傾向があると述べ、その不当性を批判している。 既に数年前から、Robinsonがケインズ流のアニマル・スピリッツの重要性を強調していた点を明確にし、彼女の著作『異端の経済学』からの抜粋を紹介することで、アニマル・スピリッツ概念の先行研究としてのRobinsonの貢献を強調している。 Robinsonの主張を引用し、資本蓄積は利潤予想だけでは説明できず、企業の活動は設立趣意書通りとは限らないというケインズの指摘を踏まえ、資本主義発展におけるアニマル・スピリッツの重要性を再確認する。 近江商人の成功もアニマル・スピリッツと関連付けて解釈する一方で、彼らの活躍を単にアニマル・スピリッツ論の一例として扱うことの危険性を指摘し、歴史的、文化的背景を考慮した「グローカルな視角」からの分析の必要性を主張している。
3. 近江商人と 星と天秤棒 新しい社会科学の構築
近江商人の旺盛な開発力と近代的な経営方式を改めて紹介し、徳川時代の制約下においても、広範囲に及ぶ交易活動を行っていたことを高く評価している。 特に、松井家の家訓である「星と天秤棒」に注目し、勤勉さ(星)とバランス感覚(天秤棒)の重要性を強調する。 「星」は、日の出前からの出発と日没後の到着を意味し、勤勉と忍耐の象徴と捉えている。 「天秤棒」は、モノとモノ、カネとカネ、モノとカネのバランス、そして短期的な利益と長期的な信頼関係のバランスの重要性を示唆している。 現代社会においても、様々なバランス(経済的バランス、モラル、自然との共存など)が必要であり、近江商人の「星と天秤棒」の精神が、新しい社会科学の構築に役立つと結論付けている。 伝統的な経済学の限界を指摘し、より広い視野を持つ、文理融合型の「新しい総合的な社会科学」の必要性を訴え、その創造に向けて「星と天秤棒」の精神を肝に銘じるべきだと主張している。
