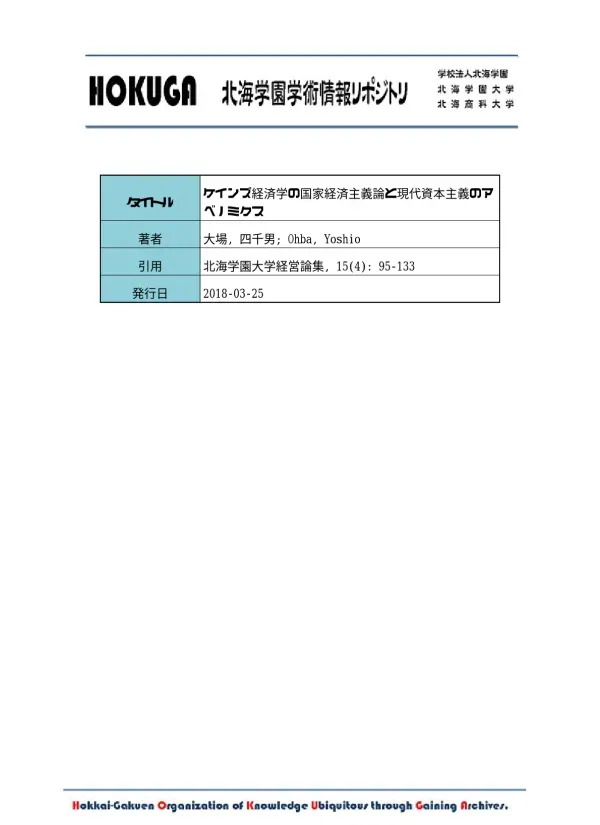
ケインズとアベノミクス:国家経済主義の探求
文書情報
| 著者 | 大場 四千男 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 731.39 KB |
概要
I.ケインズ経済学と国家経済主義 資本主義的個人主義の役割
本論文は、ケインズの国家経済主義とアベノミクスを比較検討し、その基盤となる資本主義的個人主義の役割を分析します。特に、プロテスタンティズムの倫理が禁欲主義と天職勤労観を通じて、金儲けの動機と私有財産制度を正当化し、経済成長の原動力となった点を強調します。ケインズは、一定の所得・富の不平等は人間の本性を促し、価値ある活動を生み出すと主張しますが、その不平等は過度であってはならないと指摘します。彼の思想は、有効需要の拡大、投資誘因の促進、そして流動性選好の管理を通じて完全雇用を実現することにあります。 古典派経済学のセイの法則に対する批判も重要な論点です。
1. 国家経済主義と資本主義的個人主義の融合
このセクションでは、ケインズが国家経済主義を推進する上で、資本主義的個人主義を重要な要素として位置づけている理由が論じられています。特に、イギリス国教会のプロテスタント倫理が、禁欲主義と天職勤労観を通じて、金儲けの動機と私有財産制度を道徳的に正当化してきた歴史的背景が強調されています。この倫理は、資本主義的個人主義者の勤労意欲と生産性向上心を育み、経済成長の原動力となると考えられています。ケインズは、資本主義的個人主義の利己心を、国家経済主義の発展に不可欠な人間の本性として捉え、ある程度の所得・富の不平等は、価値ある人間活動の推進力となると主張しています。しかし、その不平等は、今日のような大きな格差を正当化するものではないとも述べており、思慮深い政治術によって、適切なレベルの不平等を維持することが重要だと示唆しています。 この部分は、国家経済主義の根幹をなす資本主義的個人主義の性質と、その倫理的基盤を明確に示す重要な箇所です。
2. 所得 富の不平等と人間性 ケインズの視点
ケインズは、所得と富の不平等を完全に否定するわけではなく、ある程度の不平等は人間社会にとって必要悪であるという立場を取っています。彼は、「所得の不平等を正当化する若干の理由はあるにしても、それはそのまま富の不平等には当てはまらないからである」と述べ、社会的・心理的な理由から、ある程度の不平等は容認できるとしながらも、現在の水準を超えるほどの格差は正当化できないと主張します。重要なのは、金儲けの動機と私有財産制度が、人間が価値ある活動を行うためのインセンティブとなり、危険な人間性を比較的害の少ない方向へ導くという点です。 暴君になろうとする人間は、他者を支配するよりも、自分の富を蓄積することに満足する方が社会にとって良いとケインズは示唆しています。この考え方は、人間の本性を抑制することなく、そのエネルギーを経済活動に転換させることで、国家経済主義の目標である経済成長を実現しようとする彼の政策の根拠となっています。
3. 労働価値説と国家による人間性統御
このセクションでは、ケインズの国家経済主義が、労働価値説と密接に関連している点が強調されています。価値ある人間活動は、「金儲けの動機」と「私有財産制度」という二つの要素によって支えられており、国家はこれらの要素を通じて人間の本性を統御し、経済成長の果実を正当化すると考えられています。 この「国家による人間性統御」という表現は、一見すると自由主義的な考え方に反するように見えるかもしれませんが、ケインズは、人間の利己心を経済発展の原動力として積極的に活用することを意図しており、その上で、国家が適切な枠組みを提供することで社会全体の利益を最大化できると考えていたと考えられます。 つまり、彼の国家経済主義は、個人の自由を完全に否定するものではなく、むしろ個人の能力を最大限に発揮させるための環境を整えることを目的としていると言えます。 この労働価値説に基づいた人間性統御は、ケインズ経済学の根底にある重要な思想です。
II.イギリス資本主義の変遷と国家経済主義の系譜
イギリス資本主義は、重商主義、自由貿易主義を経て、ケインズによって提唱された国家経済主義へと発展しました。重商主義時代には、貿易黒字による貴金属流入が投資誘因となり、毛織物工業などの発展を促した一方、スペインにおける貴金属流入の過剰は価格革命を引き起こし、経済を弱体化させました。ケインズは、この歴史的経験から、国家が経済を積極的に調整する必要性を説き、投資の社会化を重視する国家経済主義を提唱しました。ジェラール・マリーンやエドワード・ミッセルデン、ペティーといった経済学者たちの考えも、ケインズの国家経済主義形成に影響を与えました。
1. イギリス資本主義における国家の役割 重商主義から国家経済主義へ
このセクションでは、イギリス資本主義の発展過程において、国家が果たしてきた役割を、重商主義、自由貿易主義、そして国家経済主義という三つの段階に分けて分析しています。まず重商主義時代には、貿易黒字による貴金属の流入が、国内の利子率を低下させ、投資誘因を強化することで、毛織物工業などの発展を促したと説明されています。 ケインズは、イギリスとスペインの対比を通して、重商主義における貴金属流入の投資誘因への影響を分析し、スペインの場合、過剰な貴金属流入が価格革命を引き起こし、経済の弱体化につながったと指摘しています。対照的にイギリスは、適切な投資誘因によって産業資本を発展させ、資本主義を確立できたと論じています。 そして、ケインズは、古典派経済学の自由貿易主義とは対照的に、国家が消費性向と投資誘因を調整する機能を積極的に果たす国家経済主義を、イギリス資本主義の新たな発展段階として位置付けています。 これは、国家の介入が経済発展に不可欠であるというケインズの重要な主張を示しています。
2. 重商主義の成功と失敗 イギリスとスペインの比較
イギリスとスペインの重商主義政策の成果を比較することで、ケインズは国家による経済政策の重要性を示唆しています。イギリスでは、貿易黒字による貴金属流入が、国内利子率の低下、ひいては投資誘因の強化につながり、毛織物工業(Woollen Industry)の発展といった産業構造の変革を促しました。これは、イギリス資本主義の成立と発展における重要なステップであったとされています。一方、スペインでは、アメリカ大陸からの莫大な貴金属流入が、価格革命を引き起こし、かえってスペインの高級毛織物産業の競争力を低下させました。対オランダ、イギリスとの宗教戦争による敗北と貴金属の大量流出も相まって、スペインの初期資本主義は弱体化していったと分析されています。ケインズは、このスペインの事例を、過剰な貴金属流入が経済を破壊する負の例として提示し、国家による適切な経済政策の必要性を強調しています。イギリスにおける毛織物産業の発展とスペインの失敗例は、ケインズの国家経済主義論の重要な根拠となっています。
3. 初期資本主義におけるイギリスの産業発展 家内工業からマンチェスター
このセクションでは、イギリスにおける初期資本主義の発展過程において、家内工業が果たした役割が述べられています。ランカシャー地方の例が取り上げられており、霧の深い湿度の高い気候や不毛地帯といった地理的条件が、農民を農業以外の生計手段を求めさせ、家内工業の発展を促進したと説明されています。 1740~1750年頃には、ファスティアン織親方と呼ばれる問屋制企業家階級が出現し、原料の購入と織布工への分配を行い、分業体制が構築されていきました。 紡績作業は農村部に分散していた一方、織布作業はマンチェスターを中心とした特定地域に集中する傾向が見られました。 この家内工業の発展は、イギリスにおける資本主義的発展の基盤となり、都市工業と農村工業の競争を通して産業資本が成長していく過程が示されています。マンチェスターは、この発展の中心的な地域として位置づけられています。 この事例は、イギリス資本主義の自生的発展と、その過程における国家の役割を理解する上で重要です。
4. 重商主義思想家と投資誘因 ジェラール マリーンら
ケインズは、重商主義思想家たちの主張を分析することで、国家経済主義の理論的基盤を構築しています。特に、ジェラール・マリーン(1622年)の「自由貿易の維持」と「商人の法律」における主張、エドワード・ミッセルデンの「自由貿易、あるいは貿易繁栄策」、そしてウィリアム・ペティー(1676年)の「政治算術」が注目されています。これらの経済学者たちは、貨幣の豊富さが高利を抑制し、利子率の低下による投資誘因を促進するという考え方を共有しています。 マリーンは貨幣の豊富さを貿易黒字による貴金属の流入と結びつけ、ミッセルデンは高利対策として貨幣量の増加を提案し、ペティーは貨幣量の増加による利子率の自然な低下を説明しています。 これらの思想は、ケインズが主張する国家による経済調整、特に利子率操作による投資誘因の促進という政策に繋がっていることが示されています。 これらの経済学者たちの貢献は、ケインズの国家経済主義の理論的背景を理解する上で欠かせません。
5. 古典派経済学批判と国家経済主義の確立 セイの法則と有効需要
このセクションは、ケインズが古典派経済学の静態的均衡論(セイの法則)を批判し、国家経済主義を確立していく過程を説明しています。マンデヴィルの「蜂の寓話」は、過剰貯蓄による有効需要の減少と資本の限界効率の低下が、失業と貧困をもたらすことを示しており、ケインズはこれを古典派経済学の限界を示す重要な例として提示しています。 マルサス、ゲゼル、ホブソンといった経済学者たちも、古典派経済学への批判者として紹介されており、特にマルサスはアダム・スミスの「国富論」における資本蓄積と消費の矛盾点を指摘しています。ケインズは、これらの批判者たちが、不完全ながらも真理を見出していたと評価し、彼らの考えを踏まえて、有効需要の拡大を通じて完全雇用を実現するケインズ経済学、そして国家経済主義を体系化していきます。 ロンドンのシティにおける銀行利率政策の失敗例も、古典派経済学の限界を示す事例として挙げられています。このセクションは、ケインズ経済学と国家経済主義の理論的根拠を理解する上で極めて重要です。
III.マンデヴィルの 蜂の寓話 と古典派経済学への批判
マンデヴィルの「蜂の寓話」は、過剰貯蓄による有効需要の減少と資本の限界効率の低下が経済危機をもたらすことを示唆しており、ケインズはこれを古典派経済学に対する批判として取り上げます。マルサス、ゲゼル、ホブソンなども、古典派経済学の静態的均衡論(セイの法則)を批判した重要な先駆者として挙げられています。特に、ホブソンはマムマリーとの共同研究を通じて、過剰貯蓄が貧困問題の原因であると主張しました。ケインズは、これらの批判者たちが直観的に真理を捉えていたと評価しています。
1. マンデヴィルの 蜂の寓話 と有効需要の減少
このセクションでは、バーナード・マンデヴィルの「蜂の寓話」が、古典派経済学に対する批判としてどのようにケインズによって用いられているかが解説されています。マンデヴィルは、個人の私利私欲が、結果として社会全体の繁栄をもたらすという寓話を通じて、過剰な節倹が有効需要の減少と資本の限界効率の低下を引き起こし、最終的に失業や貧困といった社会問題につながることを示唆しています。ケインズは、1929年の世界恐慌を目の当たりにし、マンデヴィルの寓話が現代社会における現実を反映していると捉え、古典派経済学の自動調整機能ではこの問題を解決できないと主張しています。 豊かな社会においてさえ、過剰な貯蓄による過少消費は有効需要の減少をもたらし、深刻な経済危機を招くとケインズは分析しています。この寓話は、ケインズが古典派経済学を批判し、国家による積極的な介入を必要とする国家経済主義を提唱する重要な論拠となっています。
2. 古典派経済学批判 マルサス ゲゼル ホブソンらの主張
ケインズは、マンデヴィル以外にも、古典派経済学を批判したマルサス、ゲゼル、ホブソンといった経済学者たちの主張を紹介し、それらが自身の国家経済主義論の形成に影響を与えたことを示しています。マルサスは、アダム・スミスの「国富論」に遡って、資本蓄積と消費のバランスの重要性を指摘し、過剰な貯蓄が生産の動機を破壊することを警告しています。ゲゼルは、政府紙幣に印紙を貼付する制度を提案することで、貨幣の流通速度を高め、利子率を調整しようとしていました。これは、ケインズの流動性選好理論と通じる部分があります。 ホブソンは、マムマリーとの共同研究を通じて、過剰貯蓄による有効需要の不足と投資誘因の破壊が貧困問題の根本原因であると主張し、古典派経済学者の過剰貯蓄否定の立場を批判しています。ケインズはこれらの批判者たちを、直観的に真理を見出していた者たちとして高く評価し、彼らからの影響を自身の理論構築に認めています。
3. 古典派経済学の静態的均衡論 セイの法則 への批判と有効需要の重要性
このセクションでは、古典派経済学の静態的均衡論、すなわちセイの法則が、現実の経済状況を正確に反映していないというケインズの批判が中心となっています。古典派経済学は、供給が需要を創造するというセイの法則に基づき、市場の自動調整機能を信じていましたが、ケインズは、過剰貯蓄による有効需要の不足が、不況の長期化と大量失業をもたらすと指摘します。 特に、マンデヴィルの「蜂の寓話」やマルサスの指摘は、この批判を裏付ける重要な論拠として提示されています。 ケインズは、有効需要の不足こそが完全雇用を阻む最大の障壁であり、それを克服するために国家による積極的な介入が必要だと主張しています。これは、彼の国家経済主義の核心部分であり、古典派経済学の見えざる手による調整メカニズムとは対照的なアプローチです。 ロンドンのシティにおける銀行利率政策の失敗例も、この批判を裏付ける現実的な証拠として挙げられています。
IV.ヴェブレンの有閑階級と資本主義の発展
このセクションでは、アメリカの経済学者、ソーントン・ヴェブレンの有閑階級に関する理論が取り上げられます。ヴェブレンは、有閑階級の衒示的消費が有効需要を拡大し、資本主義の発展を促進すると主張します。彼の理論は、ケインズの投資誘因と資本の限界効率の概念と共通点があります。また、ヴェブレンは、企業の独占や金融寡頭制といった資本主義の負の側面にも注目しており、株式会社制度や金銭的企業者の役割についても分析しています。特に、長頭ブロンド型の人種が掠奪的な気質を有し、資本主義の支配構造の形成に影響を与えたという議論も注目に値します。
1. ヴェブレンの有閑階級論 衒示的消費と資本主義の発展
このセクションでは、アメリカの経済学者、トーステン・ヴェブレンの有閑階級論が紹介され、その理論が資本主義の発展とどのように関連しているかが分析されています。ヴェブレンは、有閑階級が、消費する財貨の量や質において、慣習的な体面の基準を満たそうとする「見栄」の生活を送ることを指摘し、この「見栄」を競い合う行動が、金銭的な「見栄」として顕在化すると主張しています。 この「見栄」に基づく消費、つまり衒示的消費は、有効需要の拡大と消費性向の増大をもたらし、ひいては新たな投資を誘発するというメカニズムが説明されています。 ヴェブレンのこの理論は、ケインズの「投資誘因」と「資本の限界効率」の概念と共通する部分があり、資本主義の成長を促進する重要な要素として「見栄」に基づく消費行動が位置付けられています。 つまり、有閑階級の衒示的浪費が、産業的効率や財貨生産高の増加に貢献するという考え方が示されています。
2. 株式会社制度と有閑階級 金融寡頭制と二つの改革の道
ヴェブレンは、株式会社制度における有閑階級の役割に着目し、資本主義の発展に影響を与えていると分析しています。彼は、株式会社を、金銭的・営業的有閑階級と、産業の総帥(生産効率を追求する実業家)との対立と融合の経済組織として捉えています。 そして、資本主義の発展方向は、金銭的企業者による上からの改革か、あるいは産業合理化による下からの改革かの二つの道に分かれると論じています。 上からの改革は金融寡頭制資本主義の発展、J.P.モルガン商会のような金融帝国の台頭を招き、下からの改革は産業資本主義の発展につながるとヴェブレンは予想していました。 しかし、アメリカ資本主義は、ヴェブレンの予想とは異なり、金銭的企業者による上からの改革の結果、金融寡頭制資本主義を発展させ、1929年の世界恐慌を引き起こすことになったと、このセクションでは論じています。
3. 有閑階級の性格と資本主義の支配構造 掠奪的気質と所有の習俗
このセクションでは、ヴェブレンが、民族の経済性向と資本主義の支配構造との関係を分析している点が注目されます。彼は、人種を長頭ブロンド型、短頭ブルネット型、中間の地中海型に分類し、長頭ブロンド型(欧米人種)が特に掠奪的な気質を有すると主張しています。 この掠奪的な気質は、現代の文化における支配力と影響力の源泉であり、有閑階級が支配階級となる要因の一つであるとされています。 さらに、有閑階級の「見栄」を競い合う生活様式は、産業効率や金銭的利得の追求において、精神的な優位性をもたらすと論じています。 近代資本主義の支配構造は、「古代の掠奪文化の派生物」である「所有の習俗」を基礎として築かれており、有閑階級は金銭的・営利的関係を通して、実業の世界に寄生し、収奪する関係を築いていると分析されています。 この掠奪的気質と所有の習俗は、資本主義の発展と密接に関連しているというヴェブレンの独特の視点が示されています。
V.ケインズの雇用の一般理論とアベノミクス
ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』は、完全雇用の達成を目指した国家経済主義を体系化したものです。彼は、利子生活者の消滅を目指すゼロ金利政策など、異次元の金融緩和による投資の社会化と、累進課税による消費性向の向上を政策として提唱しました。アベノミクスは、このケインズ経済学の影響を強く受けており、異次元の金融緩和と財政支出政策を組み合わせ、脱デフレと完全雇用を目指しました。しかし、アベノミクスの官邸主導型、忖度に基づく政策決定プロセスは、ケインズの理想とするリベラルな国家経済主義とは異なる側面も持ち合わせています。 アベノミクスの成果と課題、そして所得の不平等の問題なども重要な論点です。J.P.モルガン商会のような巨大企業の独占構造も、ケインズの批判対象として挙げられています。
1. ケインズの雇用の一般理論 完全雇用達成のための政策
このセクションでは、ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』における完全雇用達成のための政策が解説されています。ケインズは、富と所得の不平等な分配、過剰貯蓄、流動性選好の高まりといった要因が完全雇用を阻むと分析し、それらを克服するための国家経済主義的な政策を提唱しています。 具体的には、財政支出政策による投資の社会化、累進課税制による消費性向の増大、そして中央銀行による貨幣量と利子率の統制を三位一体として推進することを提案しています。 彼の理論では、完全雇用達成によって消費財部門と投資財部門の拡大が連鎖的に起こり、国内総生産(GDP)の増加、ひいては経済成長が実現すると考えられています。 このセクションは、ケインズ経済学の中核となる完全雇用達成のための政策と、その背後にある経済メカニズムを理解する上で重要です。 特に、利子率の低下による投資の増大が、イギリス資本主義の発展にとって不可欠であるという考え方が強調されています。
2. 完全雇用への障害 所得不平等と過剰貯蓄
完全雇用を阻む要因として、所得と富の不平等な分配の拡大、マンデヴィルの「蜂の寓話」で示された過剰貯蓄、そしてヴェブレンが指摘した有閑階級による内部留保の高蓄積が挙げられています。これらの要因は、消費性向の低下、民間企業投資の不足傾向を引き起こし、景気後退と失業の拡大を招くとケインズは警告しています。 過剰貯蓄は、資本の限界効率の低下につながり、投資意欲を減退させます。 また、富の集中は消費性向の低下を招き、有効需要を減少させます。 ケインズは、これらの問題を放置すれば、豊かな社会が窮乏化し、人間性の喪失につながると危惧し、国家による積極的な介入、すなわち国家経済主義が必要だと主張しています。 M2(マネーストック)の上昇と利子率の上昇も、流動性選好の高まりを反映し、完全雇用への障害となる要因として指摘されています。
3. ケインズの国家経済主義 アベノミクスとの比較
ケインズの国家経済主義は、アベノミクスと比較検討されています。アベノミクスは、異次元の金融緩和と財政支出政策を組み合わせ、円安と株価高による経済成長、そして脱デフレを目指した政策でした。 幼児教育・保育・大学の無償化なども、消費性向の増大を促す政策として位置付けられています。 アベノミクスは、ケインズの「投資の社会化」と利子率の低下(ゼロ金利政策)という考え方を基盤にしていると言えるでしょう。 しかし、文書ではアベノミクスの官邸主導型、忖度に基づく政策決定プロセスが、ケインズの理想とするリベラルな国家経済主義とは異なる点として指摘されています。 ケインズは、利子生活者の消滅を目標としてゼロ金利政策を目指したのに対し、アベノミクスはその点では異なっているという比較がなされています。 また、アベノミクスが本当に脱デフレと完全雇用という目標を達成したのかどうかについても疑問が投げかけられています。J.P.モルガン商会のような巨大金融資本への批判も、ケインズとアベノミクスの共通点として挙げられます。
4. 資本の稀少性と利子率 ケインズの完全雇用戦略
このセクションでは、ケインズが完全雇用達成の障害として認識していた「資本主義の利子生活者的な側面」、つまり資本の稀少性に基づく利子率の高騰問題を取り上げています。ケインズは、労働価値説に基づき、資本の稀少性を解消することで、利子率を低下させ、投資を増大させることで完全雇用を達成できると考えていました。 彼は、利子率は土地の地代と同様に、本来的な稀少性に基づくものではなく、資本が豊富になれば利子率は低下し、資本家の累積的な圧力も減少すると主張しています。 J.P.モルガン商会を中心とした投資銀行が、のれん(goodwill)を資本化することで資本の稀少性を人工的に作り出し、差別的独占を展開している点を批判しています。ケインズは、国家の力を用いて資本を豊富にし、利子生活者的な側面を解消することで、より少ない投資量で完全雇用を実現できると主張しています。この戦略は、国家経済主義の重要な柱となっています。
5. ケインズの国家経済主義とリベラル主義
最後に、ケインズの国家経済主義がリベラル主義とどのように関連しているかが説明されています。 国家経済主義は、国家の政策を通じて国民の意志を実現することを目的としていますが、その国民とは資本主義的個人主義者であり、独裁者迎合主義や社会主義者ではないと強調されています。 ケインズの資本主義的個人主義は、私的所有制度と金儲けを基盤に、個人の利己心と創意工夫を発揮させるものであり、国家経済主義は、この資本主義的個人主義を担い手として完全雇用を実現しようとするものです。 そのため、プロテスタント倫理と個人の利己心を両輪とする資本主義的個人主義を基盤とするケインズの国家経済主義は、独裁主義的な国家組織や国家社会主義とは異なり、リベラルな思想として位置づけられると結論付けられています。 このリベラルな国家経済主義は、個人の自由と経済効率の両立を目指している点が強調されています。
