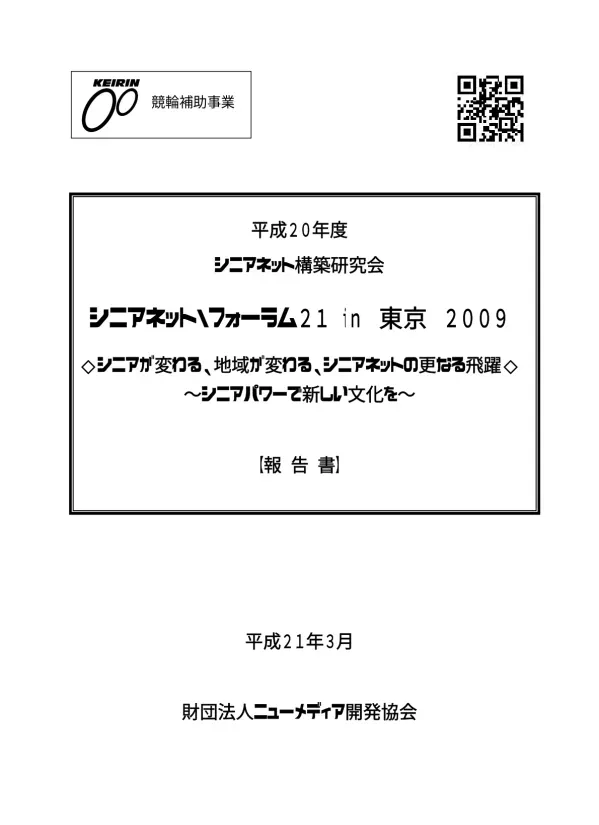
シニアネット活性化フォーラム2009報告書
文書情報
| 著者 | 財団法人ニューメディア開発協会 |
| 会社 | 財団法人ニューメディア開発協会 |
| 場所 | 東京 |
| 文書タイプ | 報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.27 MB |
概要
I.高齢化社会におけるシニアネットの役割と課題
本資料は、少子高齢化が加速する日本において、シニアネットが果たす役割と今後の課題を議論したフォーラムの内容をまとめたものです。特に、高齢者のICT活用による地域活性化、社会貢献、そしてシニア情報生活アドバイザーの育成・活躍が重要視されています。シニアネットは、高齢者の社会参加を促進し、生きがい創出の場を提供する重要な存在であり、自治体や企業との協働による事業展開が今後の発展のカギとなります。 高齢者の潜在能力を最大限に引き出し、活力ある高齢社会を実現するために、シニアネットの更なる普及と充実が求められています。 講演では、徳島大学吉田敦也教授がシニアネットの10年を振り返り、全国的なシニアネットセンター設立の必要性を提言しました。
1. 高齢化社会とシニアネットの台頭
高齢化が急速に進展する日本において、高齢者が社会の中心となる時代が到来しています。かつて団塊の世代が社会に大きな影響を与えたように、今後、高齢者のパワーが社会を変革していくことは避けられません。従来、新しい文化の創造は若者の特権と考えられてきましたが、高齢化社会においては、高齢者こそが新しい文化を創造し、社会を牽引する役割が求められています。このような状況下で、シニアネットは高齢者の情報化や地域活性化に大きな貢献を果たしており、その重要性はますます高まっています。 シニアネットの設立から10年以上が経過し、多くの組織が10周年を迎え、シニアへのIT普及や地域の情報化に多大な成果を上げてきました。少子高齢化が進む社会において、シニアネットはシニアパワーを社会に活かすための重要な牽引役として期待されています。 世界同時不況という厳しい経済状況下においても、シニアの生き方、社会参加、市民活動の意義について深く議論する必要性が高まっています。
2. シニアネットの機能と期待される役割
高齢社会において、シニアは地域社会における最大の社会的資源と言われています。シニアネットはその活動実績を通じて、シニアにとっての拠り所となり、資源の源泉としての役割を担っています。多くのシニアは、地域デビューを果たし、充実したシニアライフを送りたいと願っており、シニアネットはその実現のための重要な場となっています。高齢化が進む中、シニアネットは全国各地に広がり、シニアが地域社会で生き生きと暮らせる環境づくりに貢献することが求められています。 シニアネットの役割は大きく二つあります。一つは、ITスキルを活用して社会貢献したいシニアが集まり、活発な社会活動を展開し、高齢化社会の発展を牽引することです。もう一つは、高齢者のふるさと回帰の傾向に対応し、地域コミュニティの活性化や地方分権に貢献することです。そのためには、自治体や地域企業との連携が不可欠です。 盛況のうちに幕を閉じたフォーラムでは、シニアの生き方やシニアネットのあり方について活発な議論が交わされ、今後の発展のための重要な示唆が得られました。
3. 行政との協働とシニアネットの社会性
少子高齢化が加速する中、シニアネットと行政との連携(協働)は、地域振興と円滑な地域運営にますます重要になります。シニアネットの活動は高い社会性を持ち、地域を支える存在としての役割は、高齢化社会において必然的と言えるでしょう。自治体も、政策の企画・実行において、シニアの豊富な経験やノウハウを必要としています。 シニアネット交流広場では、過去最多の20ブースが出展され、全国各地のシニアネットの活動が紹介されました。展示内容や活動への高い評価とともに、シニアネットへの参加意欲や今後の活動への期待が示されました。 この交流会は、シニアネットの役割を再確認する絶好の機会となり、高齢者自身の自己実現の場を提供するとともに、地域コミュニティの活性化に貢献する役割を再認識させました。 行政との更なる協働の促進が、シニアネットの活動拡大と地域社会への貢献拡大に不可欠です。
4. シニアネットの現状と今後の課題 全国センター設立の提言
日本のシニアネットは、存在感、支援力、事業力の3つの側面から機能しています。「場の提供」は、定年退職後のシニアにとって非常に重要な役割を果たしており、新たな居場所や人との繋がりを築く場を提供しています。しかし、単に楽しい場を提供するだけでは不十分で、社会への提案機能も必要です。 今後の課題解決には、調査・分析が不可欠です。日本はこれまで工業生産型社会であり、効率的な専門組織である「会社」を重視してきましたが、食の安全や環境問題への対応に課題を抱えています。グローバル化と分散化が進む社会に対応するためには、発想の転換が必要です。 シニアネットフォーラムの継続のためには、過去の資産の蓄積と整理が重要です。その上で、全国的なシニアネットセンターの設立が提案されています。これは、情報発信、資源の活用、シニアネットモデルの確立、社会活動とICT技能講習の体系化など、様々な取り組みを促進するための重要なステップとなります。 シニアネットは、高齢者のみならず、自治体や企業にとっても重要な組織であり、その発展のために、関係者間の連携強化が不可欠です。
II.魅力あるシニアネット像 会員の満足度と持続可能性
フォーラムでは、会員の満足度を高め、シニアネットの持続可能性を確保するための議論が行われました。 魅力あるシニアネットとは、高齢者にとって居心地が良く、生きがいを感じられる場であるとともに、地域社会に貢献できる活動を提供する組織であることが強調されました。 具体的には、ICTスキル向上のための講座、地域貢献活動への参加機会の提供、会員同士の交流促進などが挙げられています。また、シニア情報生活アドバイザーのスキルアップ支援や、行政・企業との協働による事業展開も重要視されました。会員一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな対応が、シニアネットの成功に繋がるという意見もありました。
1. 会員満足度向上のための施策
魅力あるシニアネットを実現するためには、会員の満足度向上のための具体的な施策が不可欠です。高齢社会においてシニアネットは、シニアにとっての良き拠り所、資源の源泉として期待されています。多くのシニアは、地域デビューを果たし、豊かで実りあるシニアライフを送りたいと願っており、シニアネットはその実現を大きく期待されています。 そのためには、シニアが生きがいを感じ、積極的に参加できるような魅力的な活動の提供が重要となります。 これは、単にITスキルを教えるだけでなく、会員同士の交流促進や地域貢献活動への参加機会の提供など、多様なニーズに対応する必要があることを示唆しています。 また、フォーラムの成功事例として、活発な議論や質疑応答、深い交流が行われた点が挙げられており、会員参加型のイベントが会員満足度向上に効果的であることが示唆されています。 会員一人ひとりのニーズにきめ細かく対応することで、シニアネットの維持・発展に繋がるという意見も出ています。
2. シニアネットの持続可能性確保のための課題
シニアネットの持続可能性を確保するためには、いくつかの課題への対応が不可欠です。 高齢化社会において、シニアネット自身も高齢化が進んでおり、会員の高齢化による活動の衰退が懸念されています。 また、資金や場所、人材といった資源の確保も大きな課題です。 これらの課題を解決するために、行政や企業との協働(コラボレーション)が重要になります。 行政はシニアネットの活動に協力的であり、シニアの知見やノウハウを政策に活かそうという姿勢が見られます。 しかし、実際には資金・場所・人材といった課題の解決が依然として必要であり、これらの課題を乗り越えるための具体的な方策を検討していく必要があります。 また、会員の満足度を高め、継続的な参加を促すための工夫も必要です。 会員一人ひとりのニーズを把握し、きめ細やかな対応をすることが、シニアネットの持続可能性に大きく貢献すると考えられます。
3. 魅力あるシニアネットのあり方 多様なニーズへの対応
魅力あるシニアネット像を考える上で、会員の多様なニーズへの対応が重要となります。 単にITスキルを学ぶ場を提供するだけでなく、生きがい創出や社会参加を促進する活動、会員同士の交流を深める活動など、多様なプログラムを提供する必要があります。 沖縄ハイサイネットの例のように、地域文化の発信や国際交流といった活動も、シニアネットの魅力を高める上で有効です。 富山社会人大楽塾のように、ITスキルと健康増進や生きがいづくりを組み合わせたプログラムも、シニアにとって大きな魅力となります。 これらの事例から、シニアネットは単なるIT教室ではなく、高齢者の生活を豊かにし、社会参加を促進するための総合的な拠点としての役割が求められていることが分かります。 会員の年齢構成なども考慮し、幅広い世代が参加できるような工夫も必要です。 個々のシニアネットがそれぞれの地域特性や会員のニーズを踏まえ、魅力的な活動を提供していくことが重要です。
4. シニアネットの将来展望 情報発信とモデル確立
シニアネットの更なる発展のためには、これまで培ってきた資産の活用と、全国的なネットワーク構築が不可欠です。 これまで行ってきた活動の成果をきちんと評価し、情報発信することで、社会全体への理解と認知度を高める必要があります。 また、成功事例をモデルとして体系化し、全国のシニアネットが参考にできるような仕組みを作ることで、質の高い活動の普及促進を図ることができます。 シニア情報生活アドバイザーの育成・ステップアップも重要です。 そして、行政や企業との連携を強化し、より効果的な地域貢献活動を進めていく必要があります。 これらの活動を通して、高齢者と地域社会双方にとって有益な、みんながハッピーになれる活動の創造を目指していくことが重要です。 全国的なシニアネットセンターの設立は、これらの取り組みを促進するための重要な一歩となるでしょう。
III.シニアネットの活動事例と成功要因
様々なシニアネットの活動事例が紹介されました。沖縄ハイサイネットは、ICTを駆使した地域交流や文化発信に成功し、高齢者の社会参加を促進しています。また、富山社会人大楽塾は、シニア情報生活アドバイザー制度を活用したICT教育と生きがいづくり支援を展開し、高い評価を得ています。 これらの事例から、シニアネットの成功要因として、会員の主体的な活動、地域との連携、ICTスキルの活用、そして明確な目的意識が挙げられました。 特に、行政や企業との協働による事業展開は、シニアネットの活動を支える上で重要な要素となっています。 湖南市の事例では、外国人市民へのICT支援や幼児教育プログラムの提供といった、地域社会に貢献する活動が紹介されました。
1. 沖縄ハイサイネット ICT活用による地域交流と文化発信
沖縄ハイサイネットは、ICTを活用した地域交流と文化発信において成功例として紹介されています。沖縄から東京まで1500km離れた場所にあるにも関わらず、ICTを通して盛んな交流が行われています。会員の多くは、泡盛のルーツを探る、沖縄の芸能や料理について学ぶなど、個々の興味関心に基づいたICT活用を行っており、その活動はシニアの生きがい創出に大きく貢献しています。 沖縄特有の「横の繋がり」を重視する文化も、シニアネットの活発な活動に繋がっているようです。 会員数や具体的な活動内容は明記されていませんが、ICTをツールとして、地域文化の継承、情報共有、そして会員間の親睦を深めることに成功している事例として提示されています。 常に楽しくをモットーに活動している点も、成功の重要な要素と言えるでしょう。 沖縄の地理的な特性を踏まえ、遠隔地との交流をICTで実現している点も、注目に値します。
2. 富山社会人大楽塾 ITスキルと生きがいづくり支援の融合
富山社会人大楽塾は、ITスキルと生きがいづくり支援を融合させた活動が紹介されています。 富山県や市町村からの講演依頼も多く、テーマはITではなく生きがいづくりですが、その活動にITを活用しています。インターネット市民塾やシニア情報生活アドバイザー制度の活用を通じて、高齢者の社会参加と生きがい創出を支援している点が特徴です。 シニア情報生活アドバイザーのスキルアップ講座も実施しており、専門講師だけでなく、会員が得意分野を活かして講師を務めることで、多様なスキルを習得できる機会を提供しています。 また、「ピンピンコロリ」を理想とする考え方を示しており、寝たきり状態での長寿ではなく、健康で活力ある人生を送るための支援に力を入れている点が挙げられます。 会員数は明記されていませんが、シニア情報生活アドバイザーの育成と、ITスキル以外の付加価値を提供することにより、会員の満足度を高めている好事例と言えるでしょう。
3. 湖南市のシニアネット 外国人市民へのIT支援と幼児教育への貢献
湖南市では、外国人市民へのIT支援と幼児教育への貢献というユニークな活動が紹介されています。 外国人市民の割合が全国でも高い湖南市では、国際協会と協働して、外国人市民へのパソコン操作指導と日本語教育を実施しています。 アットホームな雰囲気の中で、家族で参加し、交流を深めている点が特徴的です。 さらに、計画段階ですが、幼稚園への幼児教育用プログラムのキット寄贈も予定されており、ICTを教育現場に活用しようという試みも積極的に行われています。 これらの活動は、シニアネットが地域社会に貢献できる多様な可能性を示しており、ICTスキルを活かした活動が地域課題の解決にも繋がることを示しています。 具体的な会員数や活動規模は明示されていませんが、地域特性を活かしたユニークな活動が成功要因となっている好事例です。 キッズスマートという幼児教育プログラムのキット寄贈は、今後の展開にも期待が持てます。
4. シニアネットの成功要因 会員の主体性 地域連携 ICT活用
紹介されたシニアネットの成功事例から共通して見られる成功要因は、会員の主体的な活動、地域との連携、ICTスキルの活用、そして明確な目的意識です。 会員が主体的に活動することにより、活動内容の充実化、会員間の結束強化、そして地域への貢献度向上に繋がります。 地域との連携は、行政や企業との協働を通じて、活動資金の確保や活動範囲の拡大、そして地域社会への貢献といった様々なメリットをもたらします。 ICTスキルの活用は、情報収集、情報発信、そして会員間のコミュニケーション効率化に役立ちます。 明確な目的意識を持つことは、活動の継続性や会員のモチベーション維持に不可欠です。 これらの要素がバランス良く組み合わさることで、シニアネットは高齢者の生きがい創出、地域活性化、そして社会貢献という重要な役割を果たすことができます。 今後、更なる発展のためには、これらの成功要因を踏まえ、それぞれのシニアネットが地域特性や会員ニーズに合わせた独自の活動を展開していくことが重要です。
IV.今後の課題と展望 全国的なシニアネットセンターの必要性
フォーラムでは、シニアネットの今後の課題として、高齢化による会員の高齢化、資金調達、人材確保などが挙げられました。 これらの課題を解決するためには、全国的なネットワークの構築と情報共有が不可欠であるとされ、全国的なシニアネットセンターの設立が提案されました。 また、シニアネットの活動実績を評価し、社会への貢献度を明確にするための仕組みづくりも重要視されています。 シニアネットは、高齢者の自立支援、地域活性化、社会貢献という重要な役割を担っており、その更なる発展のためには、継続的な改善と改革、そして関係者間の協働が不可欠です。 オープンソースソフトウェアの活用なども、今後の展開において検討されるべき事項として挙げられました。
1. シニアネットの現状分析 高齢化と課題
日本のシニアネットは設立から10年以上経過し、高齢者のICT活用促進に貢献してきました。しかし、設立当初の平均年齢が65歳前後だったのに対し、現在は70歳前後に高齢化していることが課題として挙げられています。 高齢化社会の現状とシニアネットの将来を考える上で、会員の高齢化は大きな問題です。 また、会員の高齢化だけでなく、シニア情報生活アドバイザーの養成講座の受講者数が減少していることなども、シニアネットの持続可能性を脅かす要因となっています。 これらの課題を踏まえ、シニアネットの魅力をどのように維持・向上させていくかが、今後の重要な課題となります。 魅力あるシニアネットとは何か、会員のニーズ、そして地域社会への貢献という視点から、改めてそのあり方を再考する必要性が指摘されています。 現状維持ではなく、若い世代の参加促進など、さらなる活性化に向けた取り組みが求められています。
2. 成功事例からの考察 会員の主体性と地域連携の重要性
資料では、沖縄ハイサイネット、富山社会人大楽塾、そして湖南市のシニアネットの3つの事例が紹介されています。 これらの事例から共通して言えることは、会員の主体的な活動、地域との連携が成功の鍵となっている点です。沖縄ハイサイネットは、会員の自主的な活動とICTの活用により、地域交流や文化発信を積極的に行っています。 富山社会人大楽塾は、シニア情報生活アドバイザー制度を活用したIT教育と生きがいづくり支援を融合することで、高い評価を得ています。 湖南市では、外国人市民へのIT支援や幼児教育への貢献といった、地域社会に密着した活動が展開されています。 これらの事例は、シニアネットが単なるIT教育の場にとどまらず、地域社会に貢献できる多様な可能性を示しています。 成功要因として、会員の主体性、地域との連携、ICTスキルの活用、そして明確な目的意識などが挙げられ、これらの要素がバランス良く組み合わさることが重要であると示唆されています。
3. 今後の展望 全国的なネットワーク構築と情報共有
シニアネットの更なる発展のためには、全国的なネットワークの構築と情報共有が不可欠です。 そのためには、全国的なシニアネットセンターの設立が強く求められています。 これは、情報発信、資源の有効活用、シニアネットモデルの確立、そして社会活動とICT技能講習の体系化などを促進するための重要な施策となります。 また、シニア情報生活アドバイザーのスキルアップ支援や、特色・役割を明確にした活動も重要です。 それぞれのシニアネットが、地域特性を活かした独自の活動を行いながらも、全国的なネットワークを通じて情報共有を行うことで、より効果的な活動展開が可能になります。 さらに、これまでの活動実績をきちんと評価し、社会への貢献度を明確にするための仕組みづくりも重要です。 これにより、シニアネットの活動に対する社会全体の理解と認知度を高め、今後の活動推進に繋げることが期待されます。
4. 課題解決へのアプローチ 調査 分析と発想転換
シニアネットの今後の課題解決には、調査・分析と発想転換が不可欠です。 日本はこれまで工業生産型社会を基盤としてきましたが、食の安全や環境問題など、新たな課題に対応する能力が不足しています。 グローバル化と分散化が進む社会に対応するためには、従来の考え方やシステムを見直し、新たなアプローチが必要です。 シニアネットフォーラムを継続的に発展させていくためには、過去の資産を蓄積・整理し、その活動実績を正確に評価できる材料を作る必要があります。 行政も、シニアネットとの協働において発想転換が必要であり、シニアの提案を積極的に政策に反映させる姿勢が求められます。 そして、シニアネットが社会に対して積極的に提案できる機能を強化していくことも重要です。 これらの取り組みを通じて、シニアネットは高齢化社会における重要な役割を担い続け、活力ある社会の実現に貢献していくことが期待されます。
