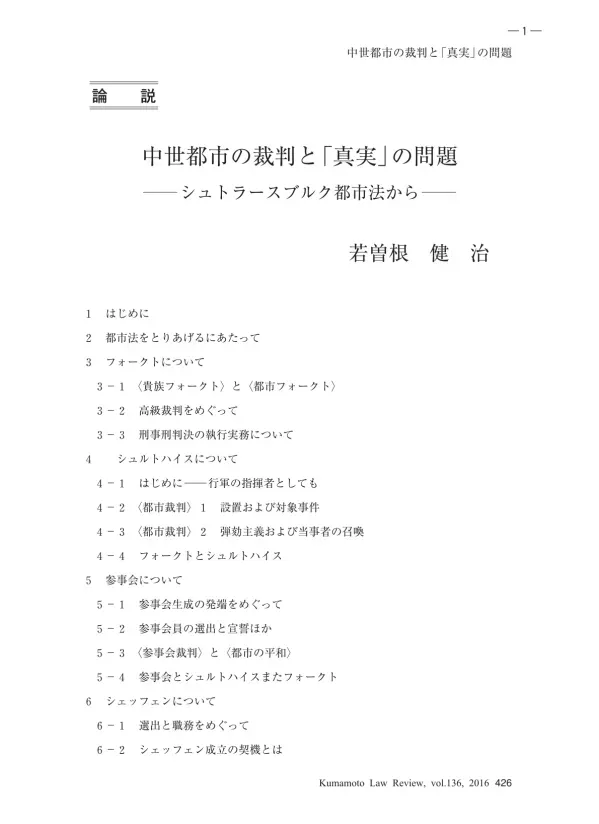
シュトラースブルク都市法と真実の裁判
文書情報
| 著者 | 若曽根 健治 |
| 専攻 | 歴史学、中世史、法制史など |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.97 MB |
概要
I.シュトラースブルク都市法における 真実の裁判 司教 参事会 そして裁判官たちの役割
本稿は、12世紀後期から13世紀中葉のシュトラースブルク都市法、特に第1~第3都市法を基に、**「真実の裁判」**のあり方を考察する。シュトラースブルクの都市統治は司教が中心であり、シュルトハイス、ブルクグラーフ、関税役、貨幣鋳造人長といった司教のミニステリアーレン出身の役人が都市運営・司法に関与していた。 参事会の役割の増大に伴い、シェッフェンと呼ばれる裁判官が登場し、「真実の裁判」の中核を担うようになる。 本稿では、これらの裁判官と他の都市役人(フォークト等)の職務、裁判権の分担と競合、そして「真実」の立証方法(宣誓、誓約、決闘、証言など)を分析する。
1. シュトラースブルク都市統治における司教とミニステリアーレン
日本の研究者、林毅による日本語訳によって、12世紀後期から13世紀中葉のシュトラースブルク都市法全容が明らかになった。宮下孝吉の研究は、特に第1都市法の成立年代と都市統治機関に焦点を当てている。宮下孝吉は「司教に対して市民の要求を代表した者こそ即ち都市統治の4種の役人達であった」と述べている。この4種の役人、シュルトハイス、ブルクグラーフ、関税役、貨幣鋳造人長は、いずれも司教のミニステリアーレン出身であり、司教都市における都市統治の特徴を示している。この記述から、シュトラースブルクにおける司法権の行使は、司教の強い影響下にあったことが読み取れる。司教の任命した役人たちによって、都市の運営と司法が担われていたという点が重要である。これらの役人たちは、市民の代表としての役割も担っていたと考えられるが、その権限と責任の範囲については、更なる考察が必要となる。 1214年の皇帝フリードリヒ二世の判決は、シュトラースブルク市参事会の歴史的出現を示す重要な事例であり、司教と市民の紛争の仲裁がなされた事実から、参事会の存在と役割が次第に重要性を増していく過程を理解する上で重要な手がかりとなる。
2. 真実の裁判 の概念と参事会裁判
シュトラースブルク第2都市法制定当時の「真実に基づく裁判」とは何か、その生成の契機と背景にある思考を探る必要がある。このためには、参事会と参事会裁判のありようを詳細に検討しなければならない。第2都市法においては、証言活動によって「真実に基づく裁判」の担い手となるシェッフェンという裁判官の職務が重要視されている。しかし、「真実の裁判」は参事会裁判に限定されるものではなく、フォークト、シュルトハイス、ブルクグラーフ、貨幣鋳造人長といった、参事会裁判以前から存在した役人たちの裁判権とも密接に関連している。そのため、これらの役人たちの職務、特に裁判における役割を包括的に考察する必要がある。第1都市法から第3都市法までの法令を手がかりに、初期の中世都市における裁判のあり方を理解しようと試みる。しかしながら、他の都市法史料との比較検討は今後の課題として残される。
3. 様々な裁判機関の役割と権限の分担 フォークト シュルトハイス 参事会
シュトラースブルクの都市裁判は、単一の裁判所ではなく、フォークト、シュルトハイス、参事会など複数の機関が関与する多層的な構造を持っていた。「真実に基づく裁判」も、これらの機関の活動全体と密接に関連している。市民立法者としての参事会は、現実の立法活動の中心を担っており、1214年の皇帝フリードリヒ二世の判決は、参事会の公式な歴史的登場を示す一例である。 司教の同意なしに参事会を設置し、世俗裁判権を持つことはできないという点も重要である。 フォークトは貴族フォークトでありながら、第2都市法ではシュルトハイスと同列、もしくは下位に位置づけられ、贖罪金の額もシュルトハイスと同一である。しかし、参事会はより高額な贖罪金を得るため、フォークトとシュルトハイスの裁判権と参事会の権限には、複雑な関係が存在していたと考えられる。
4. 刑罰執行権と バン 権限 司教 フォークト そして他の裁判官
シュルトハイスが「バン」の名で呼ばれる権利、つまり有罪判決を受けた者を強制・拘束する権利は、司教ではなくフォークトから授与される。これは、教会人が血を流す刑罰権を持たないためである。ブルクグラーフは、司教が任命する主要な都市役人であり、都市における裁判の担い手であるにもかかわらず、「バン」権限は持たない。これは、ブルクグラーフには刑事判決を下す権限がないため、刑事判決が必要な事件はシュルトハイスの裁判に移管されるからだと考えられる。貨幣鋳造人長も職務に応じた裁判権を持ち、貨幣偽造者に対する身体刑(手の切断)の判決を下す権限を持つ。関税役の裁判権については都市法に明記されていないが、職務上自明とみなされていた可能性がある。司教はオットー二世の特権状によって高級裁判権を有するが、フォークトは刑事判決の執行権(バン)を皇帝から授与されるという関係性にあると推測される。
II. 真実の裁判 の立証方法と裁判手続き 宣誓 証言 そして決闘の可能性
シュトラースブルク都市法における「真実の裁判」の立証には、宣誓、誓約、決闘といった伝統的な方法と、シェッフェンによる証言が用いられていた。 シェッフェンは、特に民事訴訟において重要な役割を果たし、彼らの証言は高い証明力を持っていた。 しかし、証人が得られない場合、被告は雪冤宣誓によって無罪を主張できる可能性があった。 また、決闘による解決も排除されておらず、様々な手続きが混在していたことがわかる。 参事会は、裁判手続きにおいて重要な役割を果たし、特に平和維持を目的とした「平和裁判所」としての側面も持ち合わせていた。
1. 宣誓 誓約 決闘 伝統的な立証方法
シュトラースブルク都市法における「真実の裁判」の立証方法は多様であった。 宣誓や誓約は、普遍性、典型性、儀礼性を持つことから好まれた方法であり、個々の偶発的な事実を超えた本質を有していたと解釈できる。 これらの方法は、神への誓いを前提としており、偽証は神罰を受けるという信仰に基づいていた。 一方で、決闘も立証手段として存在しており、公式には禁止されていなかったことが窺える。 これらの伝統的な方法は、現代の証拠法とは異なる考え方、すなわち、宣誓や誓約、決闘といった行為そのものが真実性を担保するものと考えられていたことを示唆している。 これらの方法は、後の時代におけるより洗練された証拠制度とは対照的であり、当時の社会における信仰と社会秩序の維持に重要な役割を果たしていたと考えられる。
2. シェッフェンによる証言 新たな立証方法の導入
シュトラースブルク第2都市法においては、シェッフェンによる証言が「真実の裁判」における重要な立証方法として登場する。 シェッフェンは、法廷における証言者としての役割を担い、特に私法分野においてその地位を確立していた。 彼らの証言は、法廷における所定の手続きに従った宣誓と同様に、無条件の証明効果を有していたとされる。 しかし、シェッフェンによる証言は、従来の宣誓や決闘といった方法と完全に置き換わったわけではなく、両者は並存していたと考えられる。 証人による立証が困難な場合、原告は訴訟を提起できないか、あるいは被告が雪冤宣誓を行うという従来の方法も残されていた可能性がある。 シェッフェンという新たな立証方法の導入は、中世都市における司法制度の変容を示す重要な要素の一つである。
3. 証人の数と証明力 形式的証拠主義の枠組み
シュトラースブルク第2都市法では、「2人または3人の証人」の証言が重視されていた。 この証言の数は、民事訴訟と刑事訴訟の両方で用いられていた可能性がある。 この「2人または3人の証人」の証言は、形式的な証拠法の枠組みを超えたものではなく、対審による審理が行われない限り、立証は常に形式的な性格を帯びざるを得なかったことを示唆する。 実体的真実主義が重視されるようになるのは、自由心証主義の時代になってからである。 自由心証主義では、たった1人の証言でも被告を有罪とすることができるが、シュトラースブルク第2都市法ではそうではない。 このことは、当時の司法制度において、形式的な手続きと証拠の提示が重視されていたことを示している。
4. 様々な手続きの混在と雪冤宣誓 伝統と革新の融合
シュトラースブルク第2都市法の書記の胸中には、シェッフェンの証言手続き、被告の雪冤宣誓、そして原告による決闘の申し込みという3つの手続きが混在していたと考えられる。 これらの手続きは、それぞれ異なる歴史的背景と法的根拠を持ち、互いに影響し合いながら運用されていた。 特に、雪冤宣誓は、伝統的な立証方法として、シェッフェンによる証言という新たな方法と並存していた。 被告は誓約によって立証を行うことが求められ、これは被告単独の雪冤宣誓と解釈できる。 都市法は、シェッフェン証人に頼らない原告を制裁する一方、被告にも宣誓を課すことで、被告の無罪を容易には認めない仕組みを有していた。 このことから、伝統的な手続きと新しいシェッフェン制度が融合し、複雑な司法手続きが形成されていたことがわかる。
III.参事会と他の裁判機関との関係 協働と競合のダイナミズム
参事会、シュルトハイス、フォークトは、しばしば協力しつつも、それぞれ独自の裁判権を有していた。 例えば、傷害事件においては、逃亡した被告の家宅が共有物となり、参事会、シュルトハイス、フォークトが共同で贖罪金の徴収を行うなど、協働と競合が複雑に絡み合っていた。 第3都市法においても、フォークトとシュルトハイスは、参事会の指示の下、裁判所に出頭しない市民への対応にあたっていた。 このことは、参事会が都市司法全体において中心的な役割を担っていたことを示唆している。
1. 参事会 シュルトハイス フォークトの役割分担と連携
シュトラースブルク都市法においては、参事会、シュルトハイス、フォークトの三者が、司法制度において複雑に絡み合った関係を築いていた。第2都市法には、これらの三者を並べて記述する箇条があり、傷害事件における加害者の逃亡時の対応などが示されている。 この場合、逃亡者の家宅は共有物となり、参事会、シュルトハイス、フォークト、そして都市が共同で贖罪金の徴収を行う。 有罪判決が下された場合、贖罪金の分配は、参事会が100ソリドゥス、シュルトハイスとフォークトがそれぞれ30ソリドゥスと、明確に規定されている。これは、これらの機関が協力して司法を運営していたことを示している。 しかし、それぞれの機関の権限は明確に区別されており、協力関係と同時に、権限や利権を巡る競合関係も存在していたことが予想される。 この様な、協働と競合の複雑なダイナミズムが、シュトラースブルクの司法制度を特徴づけている。
2. 第3都市法における参事会と他の裁判機関の連携
第3都市法においても、参事会と他の裁判機関との連携が見られる。 3度召喚されても裁判所に出頭しない市民に対して、フォークトとシュルトハイスが贖罪金の支払いを強制するよう規定されている。 一見自明のように思えるこの規定は、それまで裁判所への出頭義務が軽視されていたことを示唆している。 参事会は、シュルトハイスらに、不出頭者の責任をきちんと問うよう注意を促している。 この措置の本質は、贖罪金の徴収ではなく、何よりも裁判所への出頭させることにあると解釈できる。 しかし、それでも裁判所の呼び出しに従わない市民に対しては、参事会が積極的に介入する。 市長と参事会は、不出頭者を贖罪金の支払いに強制する権限を持つ。 このことは、参事会が都市の司法制度において中心的な役割を担い、他の裁判機関を統括する役割も持っていた可能性を示している。
3. 参事会の役割 平和維持と司法への関与
参事会は、都市の平和維持において重要な役割を担っていた。 市民間の紛争(「怒り」や「いさかい」)が発生した際には、市長は参事会員と共に休戦を仲介するよう努めることが求められていた。 休戦の仲介に協力しない参事会員やシェッフェンは職を失うという厳しい罰則が科せられる。 この規定から、参事会が紛争解決に積極的に関与し、都市の平和を維持する役割を担っていたことがわかる。 また、「休戦」を提唱するには、紛争の当事者や経緯といった事実関係をある程度明らかにすることが不可欠であり、参事会はそのための調査や仲介も担っていたと考えられる。 このことから、参事会は単なる立法機関ではなく、司法にも深く関与し、都市運営の中枢を担う機関であったことが明らかになる。
4. シュルトハイス フォークト 参事会の協働と競合 傷害事件への対応
第2都市法には、参事会、シュルトハイス、フォークトの三者を並べて記述する箇条が複数存在する。これらの箇条は、傷害事件で逃亡する加害者の対応に関する規定が含まれている。 逃亡者の家宅は共有物となり、窓と戸は取り外され、誰もが立ち入れる状態になる。 加害者は、参事会、シュルトハイス、フォークト、そして都市に対して贖罪金を支払わなければならない。 この贖罪金の額は、参事会が100ソリドゥス、シュルトハイスとフォークトがそれぞれ30ソリドゥスと、明確に規定されている。 これは、これらの機関が協力して犯罪者を追及し、被害者への補償を行う仕組みを示している。 しかしながら、各機関の権限の範囲や、相互関係については、より詳細な分析が必要である。第3都市法でも、3度召喚されても出頭しない市民を強制する役割を、フォークトとシュルトハイスが担い、参事会がその過程を監督するという連携が見られる。
IV.都市法における様々な事件と裁判管轄 商事事件 外来者 そして市民間の紛争
シュトラースブルク都市法は、商事事件、外来者に関わる事件、そして市民間の紛争など、多様な事件を扱っていた。 シュルトハイスは商事取引に関する裁判権を有し、ブルクグラーフは関税徴収に関与していた。 外来者、特に商人の扱われ方や、市民間の紛争における参事会の仲裁、そしてシェッフェンの証言が重要な役割を果たしていたことがわかる。 マインツやケルンといった都市との商業関係もシュトラースブルクの都市法に反映されている。
1. シュルトハイス裁判所と商事事件
シュルトハイス裁判所は金銭債務事件を扱うため、商人が訴訟に関わることは容易に想像できる。実際、都市法には「商人」が登場し、司教の使節としての役割も担っていたことがわかる。 シュルトハイスが商事取引に関する裁判権を持つことは、都市法の事例から明らかである。修道院や修道士の従者が商事に属する事件に関わり、商取引に従事していることを認めた場合は、シュルトハイスの裁判権に服さなければならない。 シュルトハイスとユーデックスの裁判権は、ミニステリアーレンや修道士の身柄には及ばないが、その所領の保有者には及ぶ。 従って、修道院や修道士の従者自身が聖界に属する者はシュルトハイスの裁判権の及ばない聖職者であるが、商事に従事する場合はこの限りではない。このことから、シュルトハイス裁判所が、都市における商取引の円滑化と秩序維持に重要な役割を果たしていたことがわかる。 マインツやケルンといった都市との商業関係も、シュトラースブルクの経済活動と密接に関連しており、都市法にも反映されている。
2. 外来者と都市 関税と通過税をめぐる紛争
外来者、特に商人との関係は、関税をめぐる規定に現れている。「商人が荷役獣に荷を積み本市を通過するとも、(市内で)売買せねば通過税を払うを要せず」という規定は、通過貿易の存在と、その規制を示している。 シュトラースブルクを訪れる商人の出身地はケルンなど多岐に渡り、ライン川を上下する交易は既に1世紀以上の歴史を持つ。 通過税の徴収・支払いをめぐる争いは起こりうるため、シュルトハイス、ブルクグラーフ、関税役が裁判権を主張する競合的な状況が考えられる。 ケルンからの船による物資輸送に関する規定は、シュトラースブルクと周辺都市との貿易関係を示す重要な事例である。 これらの規定から、シュトラースブルクが交易都市として機能していたこと、そしてその交易活動を支えるための制度と、その制度運用に伴う紛争解決の仕組みが、都市法の中に規定されていたことがわかる。
3. 市民間の紛争と参事会の役割 平和維持と仲裁
市民間の紛争、特に「怒り」や「いさかい」への対応についても、都市法は詳細な規定を設けている。 紛争の当事者だけでなく、幇助者も処罰の対象となる。 参事会員は、市民間の紛争を鎮める役割を担っており、武器の使用も許容されている。 市長は、市民間の紛争が起きた際には、平和がもたらす幸福のために休戦を仲介するよう努めなければならない。 休戦に協力しない参事会員やシェッフェンは職を失う。 この規定は、参事会が市民間の紛争の仲裁や解決に積極的に関与し、都市の平和維持に重要な役割を果たしていたことを示している。 聖マリア修道院前は、市民間の相談・協議・折衝の場として機能しており、参事会員が仲裁・仲介を行っていた可能性が示唆される。 このことから、参事会が都市の社会秩序維持に重要な役割を果たしていたことが改めてわかる。
4. 外来債務者と宿主の責任 都市裁判権の及ぶ範囲
外来債務者に関する規定は、都市と外来者との関係を示している。 債務者(外来者)が市民の家宅に滞在している場合、債権者(市民)が債務の支払いを求めてシュルトハイス裁判所に訴えることができる。 外来債務者が裁判に出頭しない場合、宿主に責任が及ぶ。 宿主は、たとえ聖堂参事会員やミニステリアーレであっても、客に代わり責任を問われる。 この規定は、外来者に対しても都市裁判権が及ぶことを示しており、都市の司法が、市民だけでなく外来者にも及ぶ範囲であったことを示している。 宿主に責任が課されるという規定は、外来者保護の観点からも解釈できるが、司教の教会裁判権との関係については不明な点が残る。 この規定は、都市における宿泊施設と司法制度との関連を示す貴重な資料となる。
V.貨幣偽造と刑事裁判 裁判官たちの権限と責任
貨幣鋳造人長は貨幣偽造事件の裁判権を有し、身体刑(手の切断)を執行する権限を持っていた。 しかし、その裁判手続きには期限が設定されており、6週間経過後の告訴は受け付けない。 シュルトハイスも刑事裁判に関与しており、フォークトは刑罰執行において重要な役割を担っていた。 これらの裁判官の権限と責任、そしてそれらの相互関係は、シュトラースブルク都市法の複雑さを示している。
1. 貨幣鋳造人長の裁判権と貨幣偽造
貨幣鋳造人長は、貨幣偽造事件の裁判権を持ち、偽造者に対しては身体刑(手の切断)を宣告する権限を持っていた。しかし、この裁判権には時間的な制限があった。 具体的には、偽造事件の告訴は、事件発生から6週間以内に行われなければならない。6週間を経過すると、鋳造人長は告訴を受理できず、自ら訴えを起こすこともできない。この規定の理由については、新貨幣の流通状況や、旧貨幣の保持に関する市民への周知度との関連が考えられる。 新貨幣の導入に伴い、旧貨幣の通用が禁止されたが、その周知が6週間以内では必ずしも十分ではなかった可能性がある。 そのため、6週間以内であれば旧貨幣を保持している者に対しては、鋳造人長の裁判権は及ばないと解釈できる。6週間経過後も旧貨幣を保持している者こそが、裁判の対象となるはずだが、実際はそうではない。 この時間制限の意図は、通貨制度の移行に伴う混乱を最小限に抑え、市民への影響を考慮したものであった可能性がある。
2. シュルトハイス フォークト そして他の役人の刑事裁判への関与
シュルトハイスは、フォークトから「バン」の権限を授与され、身体刑を含む刑事判決を下すことができた。 一方、ブルクグラーフは裁判権を持つものの、刑事判決を下す権限は持たないため、刑事判決が必要な事件はシュルトハイスの裁判に移管される。 関税役についても、都市法には明確な記載がないものの、職務上、脱税者などに対する刑事判決権限を持っていた可能性がある。 これらの裁判官たちの権限はそれぞれ異なっており、事件の性質や被告の身分によって、担当する裁判官が変わる複雑な仕組みであったことが推測される。 また、刑罰執行においては、司教側の役人(監視人)とフォークト側の刑吏(代理)が共同で、あるいは競合して権利を行使していたと考えられる。 この刑罰執行における役割分担や競合は、司教とフォークトの権力関係を反映している可能性があり、更なる考察が必要となる。
3. 裁判の場所と召喚 私宅裁判と出廷義務
当時の裁判は、役職者の私宅で行われることが多かった。 召喚が裁判の出発点であり、その成否が裁判の進行を左右した。 不出廷は重大な罪とされ、シュルトハイスの裁判所では、不出廷の贖罪金は30ソリドゥスと高額であった。 原告が出廷しない場合、被告は一定時間待機した後、退廷できる権利があった。 これは、被告の権利も考慮されていたことを示している。 一方、原告不出廷の理由(事実問題)は問われていなかった。 この召喚手続きや、裁判の場所に関する記述から、当時の司法手続きが、現代のそれとは大きく異なっていたことがわかる。 また、都市法における様々な規定から、当時、訴訟手続きにおける召喚や出廷の重要性が高く認識されていたことが推測される。
4. 聖職者と都市裁判権 異なる法の適用と例外
シュルトハイスらの都市裁判権は、ミニステリアーレンや修道士以外の者に適用された。 聖職者などは、都市法とは異なる法によって生活を享受するため、都市裁判権の例外となる。 しかし、修道院や修道士の従者が商事に従事する場合は、シュルトハイスの裁判権に服さなければならない。 司教領内の土地領主や、司教領外の都市からの商業者などについても、彼らの裁判籍が居住地にある場合は、都市裁判所に服さずともよい例外が存在したと考えられる。 これらの例外規定は、当時の社会構造と、異なる法体系が共存していた状況を反映している。 司教の高級裁判権とフォークトのバン権限の関係についても、これらの例外規定と関連付けて考察する必要がある。 このことから、シュトラースブルクの都市法は、単一の法体系ではなく、複数の法体系が複雑に絡み合って機能していたことがわかる。
