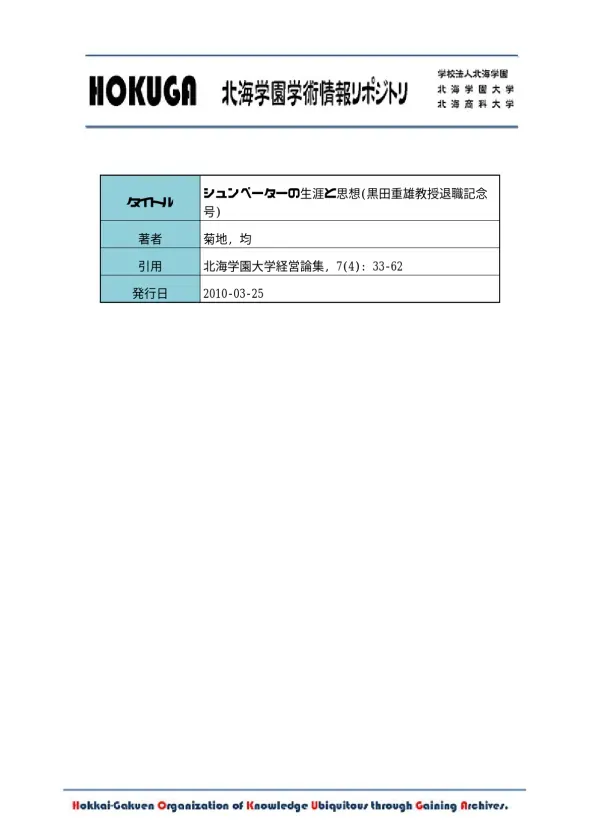
シュンペーター研究:生涯と思想
文書情報
| 著者 | 菊地 均 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.98 MB |
概要
I.日本のシュンペーター研究 初期から国際学会発足まで
日本の経済学研究は明治以降、海外文献の翻訳・解釈に重点が置かれ、世界的な業績を残しました。しかし、独自研究の世界への発信は不足していました。そのため、シュンペーター研究も初期は彼の純粋理論に偏っていました。吉田昇三『シュムペーターの経済学』(1956年)、大野忠男『シュムペーター体系研究』(1971年)といった研究が日本の近代経済学の発展に貢献しましたが、体系的解釈や批判的分析は不足していました。1931年のシュンペーター来日は日本の若手経済学者に大きな影響を与え、『理論経済学の本質と主要内容』、『経済発展の理論』、『経済学史』などの翻訳が出版されました。中山伊知郎と東畑精一はボン大学でシュンペーターの指導を受け、師弟関係を築きました。1986年の国際シュンペーター学会発足は、シュンペーター研究に大きな転換をもたらしました。彼の一般均衡理論、景気循環論、そして進化経済学、制度派経済学への先駆的貢献が再評価されています。
1. 日本のシュンペーター研究の現状と課題
日本の経済学研究は明治時代以降、西洋経済学の摂取に力を注ぎ、翻訳・解釈において目覚ましい成果を上げてきました。しかし、その一方で、独自の研究成果を積極的に海外に発信する動きは弱く、国際的な評価が低いという側面がありました。特に、マルクス経済学やケインズ経済学が主流を占める中、シュンペーターの研究は、彼の純粋理論に偏ったアプローチがなされてきました。これは、日本の近代経済学の発展に貢献した一方で、体系的な解釈や批判的な分析という点では明らかに偏っていたと言えるでしょう。 吉田昇三の『シュムペーターの経済学』(1956年)、大野忠男の『シュムペーター体系研究』(1971年)といった先駆的な研究はありましたが、これらの研究は、シュンペーターの全貌を網羅するものではなく、限定的な側面に焦点を当てている傾向が見られました。玉野井芳郎、金指基、塩野谷祐一らの研究も同様に、シュンペーターの思想の一部を切り取って論じている側面がありました。そのため、シュンペーター研究全体としては、多角的な視点や批判的な考察が不足しているという問題を抱えていたのです。
2. シュンペーター来日の影響と翻訳出版
1931年1月、シュンペーターは日本に招かれ、多くの若手経済学者に多大な影響を与えました。これは、世界的に見ても、比較的早い時期にシュンペーターの思想が日本に紹介されたことを意味します。木村健康、安井琢磨による『理論経済学の本質と主要内容』(1936年)、中山伊知郎、東畑精一による『経済発展の理論』(1937年)、そして『経済学史』(1950年)といった重要な著作の翻訳出版が、大手出版社から相次いで行われたことは注目に値します。『理論経済学の本質と主要内容』は、シュンペーター自身によって絶版とされていたため、日本語版が彼の生前における唯一の翻訳版となりました。これは、日本のシュンペーター研究が、世界的な研究動向に先駆けていたことを示唆する出来事と言えるでしょう。シュンペーターの著作の翻訳出版は、日本の経済学界におけるシュンペーター研究の基盤を築き、その後の研究発展に大きな影響を与えました。
3. 中山伊知郎 東畑精一とシュンペーターとの師弟関係
戦後の日本の経済学界を代表する人物である中山伊知郎と東畑精一は、若い頃にボン大学に留学し、シュンペーターの直接指導を受けました。この師弟関係は、日本のシュンペーター研究において極めて重要な役割を果たしました。中山伊知郎は、学生時代に東京商科大学(現・一橋大学)で高田保馬の講義を受講し、シュンペーターの学説に触れていました。さらに、福田徳三の下で経済学を学び、シュンペーターとの接点を持つことになったのです。中山と東畑以外にも、シュンペーターの下に留学した日本人はいましたが、彼ら二人は特に強い師弟関係を築き、その後の日本のシュンペーター研究に大きな影響を与えました。彼らによるシュンペーターの著作の翻訳出版や、彼らが日本の経済学界で果たした役割は、日本のシュンペーター研究の発展に大きく寄与したと言えるでしょう。
4. 国際シュンペーター学会の発足とシュンペーター研究の変容
1986年に国際シュンペーター学会(ISS)が発足したことは、日本のシュンペーター研究にとって大きな転換点となりました。それまで、シュンペーター研究は純粋理論に偏っていたり、体系的な解釈や批判的分析が不足していたりと、課題を抱えていました。しかし、国際シュンペーター学会の発足により、シュンペーターの理論体系全体に対する理解が深まり、進化経済学、制度派経済学、複雑系経済学などへの先駆的な貢献が改めて高く評価されるようになりました。シュンペーターの理論は、単なる経済学の枠を超えて、社会科学全体に影響を与えたと認識されるようになったと言えるでしょう。この学会の発足は、シュンペーター研究の国際化を促進し、より多角的で深みのある研究が進むきっかけとなったのです。 日本のシュンペーター研究も、この流れを受けて大きく変化し、国際的な研究水準に近づきました。
II.シュンペーターの生涯と学問的形成
シュンペーターは1893年、オーストリア=ハンガリー帝国で生まれました。ウィーン大学法学部で学び、オーストリア学派の影響を受けました。1906年に法学博士号を取得。その後、ウィーン大学で教鞭を執る準備として、処女作『理論経済学の本質と主要内容』を執筆。1909年にウィーン大学で私講師、その後チェルノヴィッツ大学員外教授となります。この時代は、グスタフ・マーラー、カール・クラウス、ジグムント・フロイトといった文化人が活躍した世紀末ウィーンの文化に触れた重要な時期でした。シュンペーターは、ワルラスの一般均衡理論、クールノー、そしてマッハの道具主義にも影響を受けながら独自の経済理論を構築していきます。
1. シュンペーターの生い立ちとウィーン大学時代
1893年、オーストリア=ハンガリー帝国で生まれたシュンペーターは、母が再婚したドイツ系ハンガリー人の陸軍中将、ジギスムント・フォン・ケラーの影響を受け、恵まれた環境で育ちました。1901年、ウィーン大学法学部(当時、法・国家学部)に進学。当時のヨーロッパの大学では経済学は法学部で学ぶのが一般的でした。ハプスブルク帝国の官史養成機関であったウィーン大学法学部は、オーストリア学派の拠点であり、シュンペーターはここで経済学への関心を深めました。1906年2月、ウィーン大学法学部を卒業し、法学博士号を取得。同時期に、イギリス国教会の聖職者の娘であるグレイディス・リカード=シーバーと結婚しました。結婚の立会人は、後の純粋法学者でオーストリア共和国憲法起草者となったハンス・ケルゼンだったと言われています。大学在学中は、メンガーの後継者であるヴィーザー教授の経済学演習や、イナマ・ステルネック名誉教授、F.ユラシェック宮廷官らの統計研究演習、さらにE.シュヴィン教授のゲルマン法演習にも参加するなど、多様な学びを通して経済学の基礎を築きました。世紀末ウィーンの文化的な刺激も、彼のアイデンティティ形成に大きな影響を与えたと考えられます。
2. ウィーン大学教授資格取得とチェルノヴィッツ大学時代
ウィーン大学法学部教授資格取得のため、シュンペーターは『理論経済学の本質と主要内容』を執筆しました。1909年2月には、「抽象的な定理の統計学による論証」と題する試験講義に合格し、教授資格を取得。同大学で政治経済学の私講師として講義を担当しましたが、翌年の冬学期は担当せず、チェルノヴィッツ大学員外教授(准教授)として赴任しました。チェルノヴィッツ(現在のウクライナのチェルニウツィ)は、多民族・多言語が混在する東欧の辺境都市でした。しかし、多くのオーストリアの若手研究者にとって学究生活の出発点となる大学であったため、シュンペーターにとって退屈な場所ではなかったようです。ウィーン大学での経験と、多様な文化が交錯するチェルノヴィッツでの生活は、彼の思想形成に大きな影響を与えたと言えるでしょう。この時期の彼の活動は、彼自身の学問的基盤を固め、後の研究活動の礎となりました。
3. シュンペーターの学問的影響
シュンペーターは、オーストリア学派の伝統を受け継ぎながらも、ワルラスの一般均衡理論やクールノーの研究にも深い関心を抱いていました。彼の初期の研究は、オーストリア学派の独自の視点と、ワルラスの数学的手法を巧みに融合したものとなっています。特に、ワルラスの一般均衡理論における数学的アプローチは、シュンペーターの経済理論構築に大きな影響を与えました。一方で、シュンペーターは、マッハの道具主義的な考え方にも影響を受けていました。彼は、『理論経済学の本質と主要内容』において、経済学を形而上学的に説明するのではなく、仮説の恣意性と理論の現実適合性を強調するマッハ的な思考を取り入れていたと考えられています。シュンペーターの経済学は、オーストリア学派の伝統と、ワルラスの一般均衡理論、そしてマッハの道具主義という多様な要素が融合した、独特のものです。
III.シュンペーターの政治活動とボン大学教授時代
第一次世界大戦後、シュンペーターはオーストリア共和国の大蔵大臣を務めますが、短期間で辞任します。その後、ボン大学教授として研究と教育に専念します。ボン大学では経済学史、社会学、財政学などを講義しました。この期間、巨額の借金を抱え、税務上の問題にも直面しました。 彼の方法論的個人主義は、マックス・ウェーバーとの比較を通して、吉田昇三らによって論じられました。
1. オーストリア共和国大蔵大臣としてのシュンペーター
第一次世界大戦後のオーストリアは、旧帝国解体後の混乱の中で、社会主義政権(社会民主党とキリスト教社会党による連合政府)が誕生しました。シュンペーターは1919年1月11日、グラーツを離れベルリンへ行き、カウツキー委員長率いるドイツ社会化委員会に参加しました。国有化を目指す社会化委員会への参加理由について問われた際、シュンペーターは「もし誰かが自殺したいというならば、医者がいた方が良いからだ」と答えたという逸話が残っています。その後、シュンペーターはオーストリア共和国の大蔵大臣に就任します。しかし、在任期間は短く、アルピーネ・モンターン社の株式売却問題をめぐり、閣議に諮らずに認可したことが辞任の理由とされています。レンナー内閣の外相オーットー・バウアーも、この件を批判しています。シュンペーターの政治家としての活動は、従来の研究では成功しなかったエピソードとして扱われることが多いですが、敗戦国オーストリアの再建という彼の意図をより深く探る必要があるでしょう。彼の辞任には様々な憶測があり、ロバート・L.アレンの聞き込み調査や、他の研究者による史実検証によって、今後詳細が明らかになる可能性があります。最終的には、サンジェルマン条約による戦時賠償金の減額と国際借款によってオーストリアの戦後経済危機は乗り越えられました。
2. ボン大学教授時代 研究と教育の再開
オーストリアでの政治活動の後、シュンペーターは1925年10月、ボン大学正教授に就任。初心者向けの経済学史、上級者向けの社会学、財政学などを講義し、研究と教育を再開しました。年度によっては貨幣論や数理経済学も担当し、ゼミでは社会階級論も扱ったようです。ボン大学はベートーベンの生地として知られ、新渡戸稲造も留学していた歴史を持つ大学です。シュンペーターはボン大学で本格的な研究活動と教育活動を行い、経済学の様々な分野で貢献しました。また、この頃、彼は巨額の借金を抱えており、税務上の問題にも悩まされていたようです。1929年のハーバーラー宛の書簡では、租税逃亡者としての境遇を嘆いている記述もあります。ボン大学での生活は、彼にとって経済学者としての再出発と同時に、個人的な苦悩を伴うものであったことがうかがえます。彼の母校であるウィーン大学には戻らなかった理由なども、彼の複雑な状況を反映しているのかもしれません。
3. ボン大学におけるシュンペーターの研究と社会階級論
ボン大学教授時代、シュンペーターは、マルクスの階級論を意識しつつも、社会階級を資本主義とだけ関連付けることの限界を指摘する研究を行いました。彼は、時代を遡り、一族や一家の階級移動にも目を向け、階級現象の根源が個々人の指導力と適正の差異にあると論じました。これは、マルクスの労資対立に基づく資本主義観を否定し、企業家のイノベーションによる経済発展を説明するための基礎となる研究です。シュンペーターの社会階級論は、単に資本主義社会における階級構造を分析しただけでなく、より広範な歴史的・社会学的視点を取り入れたものでした。この研究は、彼の多様な学問的関心の表れであり、経済学だけでなく、社会学や歴史学にも精通していた彼の能力の高さを示しています。この研究は、シュンペーターの後の経済発展理論の構築に繋がる重要な基礎研究と言えるでしょう。
IV.ハーバード大学時代と晩年
1935年、シュンペーターはハーバード大学教授に就任し、代表作である『景気循環論』(1939年)を出版します。この本はケインズの『一般理論』と比較されることも多いですが、政策提言を避け、理論構築に重点を置いた点で異なっています。ハーバード大学では、ケインズとの比較において、彼の業績が再評価されています。また、彼の私生活、特に同僚との関係や持続的な鬱病なども、最近の研究で明らかになってきています。 彼の著書『十大経済学者』には、ヴィクセルが含まれていない点なども論点となっています。
1. ハーバード大学教授就任と 景気循環論
1935年9月、シュンペーターはハーバード大学においてGeorge F. Baker Professor of Economicsという名誉ある称号付き教授職に就任。長年温めていた構想である『景気循環論』の執筆に本格的に着手しました。 しかし、当時、統計資料が十分に整備されていなかったため、彼は悪戦苦闘しながら、ほぼ独力で執筆を進めることになります。1939年に刊行された『景気循環論』は、マルクスの『資本論』やフォン・ノイマンとモルゲンシュテルンの『ゲームの理論と経済行動』と並んで、いまだに完全な理解に至っていない読まれざる古典と評されています。 シュンペーター自身、本書のはしがきで「私は、何の政策も勧告せず、何の計画も提案しない」と明言しており、当時の大不況への具体的な政策提言を試みたケインズの『一般理論』とは対照的でした。ケインズとは対照的に、シュンペーターは資本主義を本質的にダイナミックで成長によって導かれるものと捉えており、政府支出は不況時の社会的な困窮を和らげるための手段としては認めるものの、恒常的な補助エンジンとしては不必要と考えていたようです。 この著作は、世界15カ国語に翻訳され、現在も増刷を重ねていることから、その影響力の大きさが分かります。
2. ハーバード大学でのシュンペーター ケインズとの比較と評価
ハーバード大学でシュンペーターの講義を受けたロバート・L.ハイルブローナーは、シュンペーター自身が、自身の経済思想がケインズのそれとは相容れないことを最初に強調していたと述べています。両者は、教養あるブルジョア生活への賞賛や資本主義の価値への信頼を共有していましたが、未来への見通しは正反対でした。ケインズが資本主義のスタグネーションの可能性を懸念していたのに対し、シュンペーターは資本主義のダイナミックな成長性を強調したのです。 シュンペーターのハーバード大学における評価は、必ずしも高かったとは言えず、同僚との関係も良好ではなかったようです。 ポール・サミュエルソンは、シュンペーターがケインズを嫉妬していたと述べており、オタワ大学のベン・ヒギンスもそれを裏付ける証言をしています。シュンペーター自身も、大学における自身の威信は思ったほどではなかったと認めていました。これは、彼の性格的な欠点や駆け引きの苦手さ、自己顕示欲などが原因であったと考えられます。 彼のハーバード大学での影響力は、経済学部内では大きかったものの、大学全体としてはそれほどではなかったようです。
3. 晩年のシュンペーター 私生活と未解明な点
シュンペーターは1937年、エリザベス・ブーディと再婚しました。しかし、彼の米国での生活は、内面的には幸せとは言えず、祖国の崩壊や二度の世界大戦によるトラウマ、そして鬱病に悩まされ続けたようです。最近のロバート・L.アレンの研究などによって、これらの点が明らかになりつつあります。 また、彼が編集に関わった『十大経済学者』にヴィクセルが含まれていない点も、興味深い点です。シュンペーターはヴィクセルを「北欧のマーシャル」と評するほど高く評価していたにもかかわらずです。 彼の処女作の執筆場所や時期、ビーダーマン銀行頭取時代の借金、母校ウィーン大学に戻らなかった理由、ケインズとの関係の悪化、資本主義の崩壊論、社会主義観、独自の学派を作らなかった理由など、多くの謎が残されています。これらの謎解きは、今後のシュンペーター研究の重要な課題と言えるでしょう。
