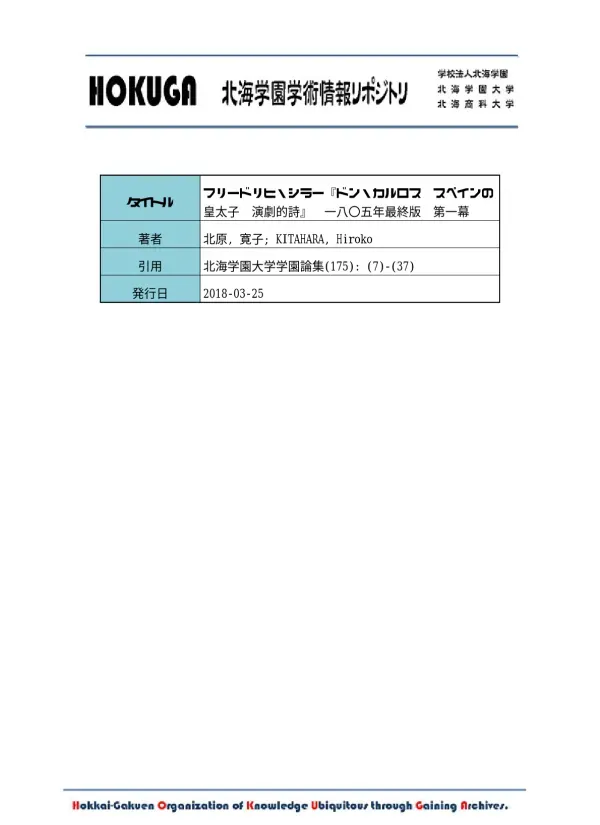
シラー『ドン・カルロス』第一幕解説
文書情報
| 著者 | Kitahara, Hiroko |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 不明 |
| 文書タイプ | 論集掲載論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 745.41 KB |
概要
I.フリードリヒ シラー ドン カルロス 第一幕 主要な場面と登場人物
北原寛子訳によるフリードリヒ・シラーの**『ドン・カルロス スペインの皇太子 演劇的詩』第一幕は、スペイン王フィリップ二世とその息子、皇太子ドン・カルロスの複雑な関係を中心に展開します。第一幕では、カルロスが宮廷での裏切りを悟り、父王への不信感を募らせていく様子が描かれています。重要な登場人物として、フィリップ二世、リザベート・フォン・ヴァロワ(王妃)、ドン・カルロス、パルマ王子、エボリ公女、モンデカー侯爵夫人などが登場し、それぞれの思惑と葛藤が物語に深みを与えています。特に、カルロスとマルキ・フォン・ポーザ**(ローデリヒ)の密談は、今後の反乱を予感させる重要な場面です。この幕は、スペインの宮廷を舞台に、権力闘争と個人的な苦悩が交錯するドラマの序章となっています。キーワード:ドン・カルロス、フリードリヒ・シラー、スペインの皇太子、フィリップ二世、カルロス、マルキ・フォン・ポーザ、エボリ公女、モンデカー侯爵夫人。
1. ドン カルロスの不信感と宮廷の陰謀
第一幕冒頭、ドン・カルロスは宮廷における自身の立場、特に父王フィリップ二世からの不信感を痛感している様子が描かれています。彼は、周囲の監視の目を強く意識し、自身の言葉が密告されていると確信しています。この場面では、カルロスの不安と怒りが、彼の言葉や行動を通して鮮やかに表現されています。「何百という目が僕を見張ろうと、こちらに向いているって、わかっているのだ、フィリップ王が唯一の息子を下僕にひどい値で売り渡したことを」というカルロスの言葉は、彼の深い絶望と、父王への強い不信感を示しています。 彼は、自分の行動や発言が常に監視されており、宮廷全体が陰謀と裏切りに満ちていると感じています。さらに、王の到着を告げるドミンゴとのやり取りを通して、カルロスの精神的な動揺が強調されています。ドミンゴが去った後、カルロスはフィリップ二世への深い嘆きと、自身の魂が猜疑心の毒に蝕まれていることを自覚している様子を独白します。「嘆かわしきフィリップよ、どんなにか息子が嘆かわしいか!」という彼の叫びは、父子の悲劇的な関係性を示す重要な台詞です。この場面は、第一幕全体のテーマである、ドン・カルロスの苦悩と、彼を取り巻く宮廷の陰謀を導入する重要な役割を果たしています。
2. 主要登場人物の紹介と彼らの関係性
第一幕では、物語を彩る主要な登場人物が複数紹介されています。スペイン王フィリップ二世、彼の妻であるリザベート・フォン・ヴァロワ王妃、そして彼らの息子であるドン・カルロス皇太子は、物語の中心人物です。この他にも、パルマ王子(王の甥)、エボリ公女、モンデカー侯爵夫人といった重要な女性キャラクターが登場し、それぞれが複雑な人間関係を形成しています。さらに、レルマ伯爵護衛長官やアルバ公爵といった権力者も登場し、宮廷内の権力構造を複雑にしています。特に、モンデカー侯爵夫人は、その後の展開において重要な役割を担う可能性が示唆されています。登場人物たちの関係性は、単なる親子関係や夫婦関係にとどまらず、権力闘争、嫉妬、陰謀といった要素が絡み合い、物語に緊張感と深みを与えています。それぞれの登場人物の個性や、彼らが抱える思惑は、今後の展開に大きな影響を与えるでしょう。この人物紹介の場面は、読者に登場人物たちの背景や関係性を理解させ、物語への理解を深めるための重要な役割を果たしています。それぞれの登場人物の行動や発言を通して、彼らの個性や、物語における役割が明らかになっていきます。
3. 宮廷の雰囲気と陰鬱な空気感
第一幕は、スペイン王宮という閉鎖的で陰鬱な空間を舞台に展開されます。カルロスの不安や不信感は、宮廷全体の重苦しい雰囲気と調和し、物語全体に陰鬱な空気感を醸し出しています。 この空気感は、単なる舞台設定にとどまらず、登場人物たちの心理状態や行動に大きな影響を与えています。カルロス自身の閉塞感や絶望感は、この宮廷の雰囲気と密接に関連しており、彼の内的葛藤をより際立たせています。また、登場人物たちの会話や行動からも、宮廷の息苦しさや陰謀渦巻く雰囲気が伝わってきます。 例えば、カルロスが宮廷での裏切りを悟る場面や、彼を取り巻く監視の目といった描写は、宮廷の不穏な空気感を強調しています。このような雰囲気描写は、物語の緊張感を高め、読者の感情を揺さぶる役割を果たしています。第一幕は、この陰鬱な雰囲気の中で、ドン・カルロスの運命がどのように展開していくのかを示唆する重要な幕開けとなっています。宮廷という舞台設定自体が、物語の重要な要素として機能していると言えるでしょう。
II.第一幕 第二場 カルロスとマルキ フォン ポーザの密談
第二場では、ドン・カルロスと彼の親友であるマルキ・フォン・ポーザ(ローデリヒ)が密かに会話を交わします。この場面は、カルロスが抱える苦悩と、反乱計画への関与を示唆する重要なシーンです。彼らは、フランドルへの支援や、フィリップ二世への対抗策について話し合っている様子がうかがえます。キーワード:ドン・カルロス、マルキ・フォン・ポーザ、密談、反乱、フランドル。
1. 再会と親愛の表現
第二場は、ドン・カルロスとマルキ・フォン・ポーザ(ローデリヒ)の再会から始まります。カルロスはポーザを「かの良き魂の主」「僕のローデリヒ」と呼びかけ、彼に対する深い信頼と親愛の情を表しています。これは、宮廷で孤独と裏切りに苦しむカルロスにとって、ポーザが唯一の理解者であり心の支えであることを示唆しています。過去の回想として「以前ハインリヒ王」という記述があり、二人の間には長く続く友情と信頼関係があることが窺えます。この再会のシーンは、緊迫した宮廷の雰囲気とは対照的に、二人の間の温かい友情を強調し、物語に短いながらも安らぎの瞬間を与えています。彼らの会話は、今後起こるであろう重要な出来事への伏線としても機能しています。
2. 緊急の事態と行動計画
二人の再会は短く、すぐに緊急の事態への対応へと移行します。ポーザは「一刻も無駄にしたくはありません」と述べ、時間的な制約を強調しています。カルロスも「そうしよう―そうしよう―では急ごう」と同意し、迅速な行動の必要性を示しています。この緊迫した状況は、彼らが抱えている問題の深刻さを示しています。具体的な内容は明かされていませんが、合図による連絡方法や、ポーザがカルロスの近侍として行動するという約束など、秘密裏に行動せねばならない状況が暗示されています。 モンデカー夫人に関する記述からも、彼らが計画を進める上で、慎重な対応が必要であることが分かります。「モンデカー夫人は、息子の以前…」という断片的な情報から、彼女が何らかの役割を担っていることが予測されますが、その詳細は明かされていません。この場面では、具体的な行動計画は明示されていませんが、緊急性と秘密裏の行動という要素が強調されており、今後の展開への期待を高めています。
3. カルロスの決意とポーザの献身
この短い場面において、カルロスはポーザに対して強い信頼を寄せている様子が見て取れます。「僕の小姓として勤めていたが、僕の為になってくれるはず」というカルロスの言葉は、ポーザの忠誠心と能力への信頼を示しています。また、侍女たちの処遇に関して、「カルロス様のお望みを…きっとすぐに心を… 」というポーザの言葉は、彼がカルロスの意向を汲み取り、状況に応じて適切な行動を取ることができる人物であることを示しています。 二人の会話は、簡潔ながらも、カルロスの決意とポーザの献身的な姿勢を明確に示しています。 このシーンは、今後の展開において、カルロスとポーザが協力して困難な状況を乗り越えていくことを暗示しています。彼らの関係性は、単なる友情を超え、信頼と相互理解に基づいた強い絆で結ばれていることが分かります。この緊密な関係性が、今後の物語において重要な役割を果たすことは間違いありません。
III.第一幕 第七場 カルロス フランドル支援を決意
第七場では、ドン・カルロスはフランドル支援を決意し、父王であるフィリップ二世への謁見を計画していることが分かります。彼はフランドル支援を願い出ることで、父王との関係修復を試みるのか、それとも別の思惑を抱いているのか、今後の展開に期待を持たせます。アルバ公爵の総督任命という情報も、物語の緊張感を高めています。キーワード:ドン・カルロス、フランドル、フィリップ二世、アルバ公爵、謁見。
1. フランドル支援の決意と時間との闘い
第七場では、ドン・カルロスがフランドル支援を決意したことが明らかになります。「僕は決めたよ。フランドルを助けないちゃ。あの方もそう望まれている。」という彼の言葉は、強い意志と決意を示しています。 この決意は、彼自身の正義感や、フランドルの人々への共感に基づいていると考えられます。しかし、同時に、時間との闘いも意識されています。「もうこれで一刻たりとも無駄にできない」というマルキ・フォン・ポーザの言葉は、状況の緊急性を強調しています。アルバ公爵がフランドルの総督に任命されたという情報も、彼らをさらに追い詰める要素となっています。この場面は、カルロスが行動を起こすための強い決意と、時間的制約といった困難な状況を描き出しています。彼の決意は、単なる同情や正義感から生まれたものではなく、より深い動機に基づいている可能性を示唆しています。
2. 父王への謁見と隠された思惑
カルロスは、フランドルの総督の地位を父王フィリップ二世に求めることを決意します。「僕はお父様に謁見をお願いしよう。この職を僕にと、お願いするんだ。」という彼の言葉は、一見すると、父王への素直な願いのように見えます。しかし、「これはお父様にする初めてのお願いだよ。あの人は、僕にそれを拒めないさ。」という彼の言葉からは、単なる願いではなく、何らかの策略や思惑が感じ取れます。長らく父王とマドリードで会っていなかったという事実と、「僕を遠ざけておけるなんて、なんていい言い訳じゃないか」というカルロスの言葉は、この謁見が、単なる職を求めるためだけでなく、父王との関係改善、もしくは対決を試みるために行われる可能性を示唆しています。 この謁見を通して、カルロスは父王との関係を修復するか、それとも対立を深めるのか、今後の展開が注目されます。
3. 真意と今後の展開への期待
カルロスは、ポーザに対して、謁見の真意を部分的に示唆しています。「君に言うべきかな、ローデリヒ?僕はもっと多くを望んでいるんだ」という彼の言葉は、フランドルの総督職獲得以上の目的があることを暗に示しています。 「ひょっとしたら、僕らは顔と顔を突き合わせて、また僕に好意を示してくれるかもしれない」という発言は、父王との関係修復への希望と、同時に、その可能性に対する懐疑的な見方を含んでいると解釈できます。「あの人は、まだ自然の声を聞いたことがまったくないんだ」という台詞は、父王の頑固さや冷酷さを表しています。 この場面は、カルロスの複雑な心情と、今後の展開への期待感で締めくくられています。 彼は、父王との関係改善を望みつつも、その困難さを認識している様子が分かります。 この第七場は、第一幕のクライマックスであり、今後の物語の展開を決定づける重要な場面となっています。
