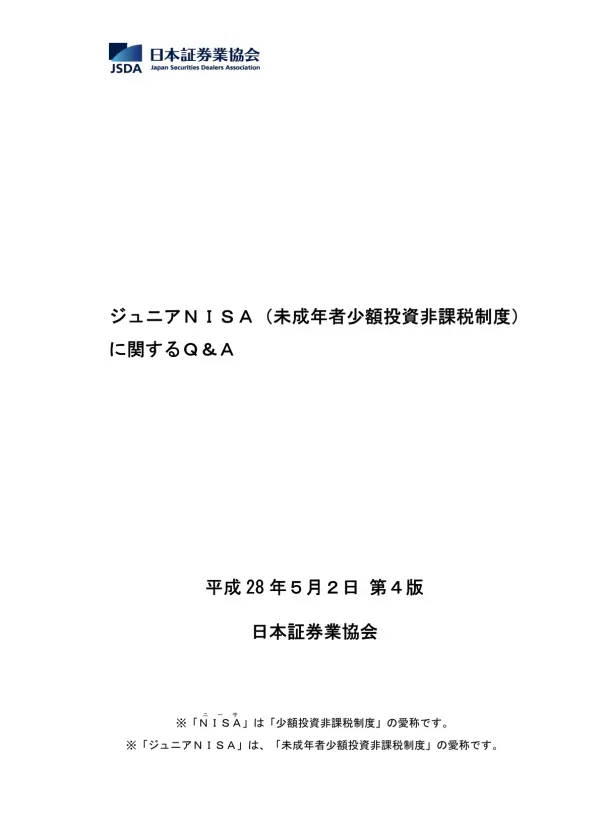
ジュニアNISA Q&A徹底解説
文書情報
| 著者 | 日本証券業協会 |
| 会社 | 日本証券業協会 |
| 文書タイプ | Q&A資料 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 252.45 KB |
概要
I.ジュニアNISA口座の開設と利用限度額
ジュニアNISA口座は、未成年者(19歳以下)が利用できる非課税の投資制度です。年間の投資上限金額は80万円、非課税期間は最長5年間です。口座開設にはマイナンバーの提示などが必要で、一人につき1口座のみ開設可能です。証券会社、銀行、郵便局などで開設できますが、口座開設後も税務署への情報提出が義務付けられています。既に特定口座や一般口座をお持ちの方も新たに開設できます。ただし、既存口座の配当金や売買益は非課税の対象外です。平成28年4月1日以降にジュニアNISA口座で購入した上場株式、ETF、REIT、株式投資信託等の配当金や売買益が非課税となります。
1. ジュニアNISA口座の概要と開設要件
ジュニアNISA口座は、0歳から19歳までの日本国内在住の未成年者が利用できる、年間80万円を限度額とする非課税の投資制度です。最長5年間、配当金や売買益が非課税となります。口座開設は証券会社、銀行、郵便局などの金融機関で行い、1人1口座のみ可能です。開設には未成年者非課税適用確認書の交付申請書とマイナンバーの提示が必要となります。既に特定口座や一般口座を保有している場合でも、新たにジュニアNISA口座を開設できます。ただし、新規開設しても、既存口座の資産に対する配当金や売買益は非課税の対象外となる点に注意が必要です。ジュニアNISA口座で運用管理を行う「親権者等」は、口座開設者本人の法定代理人、または法定代理人から書面による委任を受けた二親等以内の者に限定されます。これは、未成年者である口座開設者本人以外の者による名義口座利用を防ぐためです。平成28年4月1日から制度が始まりましたが、口座開設手続きの受付は平成28年1月から開始されました。
2. 投資対象と利用限度額
ジュニアNISA口座では、上場株式、ETF、REIT、そして公募の株式投資信託を購入できます。年間の投資限度額(非課税枠)は、一人につき年間80万円です。この限度額は買付代金ベースであり、手数料などは含まれません。例えば、年間非課税枠80万円のうち、既に50万円分の株式を購入済みの場合、残りの30万円までしか追加で投資できません。翌年になれば、新たな非課税枠80万円が適用されます。証券会社、銀行、郵便局など、利用可能な金融機関は複数ありますが、購入できる商品に違いはありません。重要なのは、既存の特定口座や一般口座に保有している上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益は、ジュニアNISA口座を開設したとしても非課税の対象にならない点です。非課税となるのは、平成28年4月1日以降にジュニアNISA口座で購入した資産からの配当金や売買益に限られます。
3. 資金の拠出に関する制限
ジュニアNISA口座への資金拠出には、資金の出し手に関する制限はありません。しかし、未成年者である口座開設者本人以外の者による名義口座利用を防ぐため、運用される資金は口座開設者本人に帰属するものである必要があります。そのため、証券会社などは、ジュニアNISA口座に拠出される資金が口座開設者本人に贈与済みのもの、両親や祖父母、その他の第三者に帰属するものではないことを確認する必要があります。資金の拠出方法は、口座開設者本人の銀行口座からの振込、口座開設者本人名義の他の証券口座からの振込、または口座開設者本人もしくは法定代理人による現金での入金に限られています。口座開設時には、法定代理人や運用管理者から「口座開設者本人に帰属する資金以外の資金によってジュニアNISA口座で投資が行われないこと」を証する書類の提出を求められる場合があります。
II.払出し制限と課税に関する注意点
18歳に達するまでは払出し制限があり、許可なく払出しを行うと、それまでに受け取ったすべての配当金や売買益に課税されます。災害などやむを得ない事情を除きます。払出し制限解除前であっても、課税ジュニアNISA口座への移管は可能です。また、株式数比例配分方式を選択することで、ジュニアNISA口座以外での売買損失と損益通算ができますが、選択しなかった場合は非課税とならず、確定申告が必要となる場合があります。 私立高校入学などまとまった資金が必要な場合、制限解除前に払出しを行うには特別な手続きが必要です。
1. ジュニアNISA口座の払出し制限
ジュニアNISA口座には、口座開設者(子・孫)が18歳に達するまでは、購入した上場株式等や配当金、売却代金等の払出しを制限する制度が設けられています。これは、子・孫の将来に向けた長期投資という制度の趣旨と、祖父母などが成人NISAの1人1口座の制限を回避することを防ぐためです。払出し制限期間中に払出しを行った場合、ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座の開設日以降に非課税で受領したすべての配当金や売買益等について、払出し時に配当金の支払や譲渡があったとみなして課税されます。ただし、災害などのやむを得ない事由による払出しの場合は、課税されません。例えば、子供が私立高校に入学が決まりまとまったお金が必要になった場合でも、払出し制限が解除される前に払出しを行うと、過去に非課税で受け取った利益に対して課税される可能性があります。払出しの際には特別な手続きが必要となります。
2. 株式数比例配分方式と税制上の注意点
ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金について、「株式数比例配分方式」を選択しなかった場合、非課税とならない可能性があります。この場合、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等に生じた売買損失と損益通算を行うことはできます。配当金等の受取方法は、①ゆうちょ銀行及び郵便局等で受け取る(配当金領収証方式)、②指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式)、③証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)の3種類から選択できます。ただし、ジュニアNISA口座で購入した上場株式の配当金について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択せずに郵便局や銀行で受け取ることも可能です。この場合、ジュニアNISA口座で購入した上場株式の配当金等は非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。確定申告を行うことで、総合課税を選択して配当控除の適用を受けるか、申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除を行うことができます。株式投資信託の分配金については、上記のような手続きは必要ありません。
3. 課税ジュニアNISA口座への移管
払出し制限の解除前に資金が必要になった場合、ジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座へ資産を移管することができます。課税ジュニアNISA口座への移管は、払出し制限期間中でも可能です。ジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座へ移管した場合、移管時までの値上がり益は非課税となります。移管後も、翌年の非課税枠80万円を利用して、80万円の限度額の範囲内でそのまま保有し続けることができます。また、ジュニアNISA口座で保有していた上場株式等を課税ジュニアNISA口座へ払出した場合、その上場株式等に係る払出し時までの値上がり益については非課税となります。ただし、課税ジュニアNISA口座への移管や、そのまま保有し続ける以外の方法で、払出し制限期間中に払出しを行うと、それまでに非課税で受け取った利益に課税されます。3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに海外へ移住する場合は、出国日の前日までに課税ジュニアNISA口座への移管が必要になります。
III.投資対象と売却 再投資について
ジュニアNISA口座では、上場株式、ETF、REIT、株式投資信託(公募のものに限る)を購入できます。購入商品は証券会社、銀行、郵便局によって違いはありません。購入した上場株式等はいつでも売却可能ですが、売買益が非課税となるのは、購入後5年以内です。売却資金は、その年の投資上限金額の範囲内で再投資できます。配当金の受け取り方法は、ゆうちょ銀行・郵便局、指定銀行口座、証券会社の取引口座(株式数比例配分方式)から選択できます。株式投資信託の分配金は、特別な手続きは不要です。
1. ジュニアNISA口座での投資対象
ジュニアNISA口座では、上場株式、ETF、REIT、そして公募の株式投資信託を購入することができます。これらの投資商品は、証券会社、銀行、郵便局といった金融機関によって取り扱いに違いはありません。 購入にあたっては、年間80万円の投資上限額(非課税枠)に注意が必要です。この限度額は買付代金ベースで計算され、手数料などは含まれません。既に投資上限額に達している場合は、翌年以降に新たな非課税枠を利用して追加投資を行う必要があります。また、新規にジュニアNISA口座を開設した場合でも、開設前に保有していた上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益は非課税の対象外となります。非課税となるのは、平成28年4月1日以降にジュニアNISA口座で購入した資産からの配当金や売買益のみです。株式数比例配分方式を選択することで、ジュニアNISA口座以外での売買損失と損益通算ができます。
2. 上場株式等の売却と非課税期間
ジュニアNISA口座で購入した上場株式や株式投資信託は、いつでも売却が可能です。しかし、売買益が非課税となるのは、原則として、ジュニアNISA口座で購入した年の1月1日から起算して5年以内です。例えば、平成28年4月に株式を購入した場合、平成32年12月末までに売却した場合のみ売買益が非課税となります。ただし、ジュニアNISA口座内で保有していた上場株式等を課税ジュニアNISA口座へ払出した場合、その上場株式等に係る払出し時までの値上がり益については非課税となります。配当金の受け取り方法には、ゆうちょ銀行及び郵便局等で受け取る方法(配当金領収証方式)、指定の銀行口座で受け取る方法(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式)、そして証券会社の取引口座で受け取る方法(株式数比例配分方式)があります。株式投資信託の分配金については、特別な手続きは必要ありません。
3. 売却資金の再投資
ジュニアNISA口座で保有する上場株式等を売却した資金は、売却した年のジュニアNISA口座の投資上限額の範囲内で再投資が可能です。ただし、その年に既に80万円分買付を行っていた場合は再投資できません。翌年以降であれば、新たな非課税枠を利用して再投資することが可能です。 ジュニアNISA口座で購入した上場株式等の配当金や、ETF、REITの分配金は、株式数比例配分方式を選択しない場合、非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。この場合、確定申告を行うことで、総合課税を選択して配当控除の適用を受ける、または申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除を行うことができます。 毎月3万円の積立投資を行う場合も、年間の投資上限額を超えないように注意が必要です。
IV.継続管理勘定と口座変更
非課税期間終了後の資産の継続保有のため、継続管理勘定が用意されています。ジュニアNISA口座で買付した上場株式等は、非課税期間終了時に継続管理勘定に移管することで、20歳になる年の前年末まで非課税で保有し続けることができます。ただし、継続管理勘定では新規買付はできません。金融機関の変更は可能ですが、払出し制限解除前に変更した場合、非課税で受け取った配当金や売買益に課税される可能性があります。20歳以降は成人NISAへの移管(ロールオーバー)も可能です。
1. 継続管理勘定の概要
ジュニアNISA口座で買付できる期間は平成28年4月1日から平成35年12月31日までと定められており、買付した上場株式等の非課税期間は最長5年間です。このため、非課税期間が終了する資産を継続して保有するために「継続管理勘定」が設けられています。例えば、平成28年6月に0歳でジュニアNISA口座を開設した場合は、7歳(平成35年)に新規買付が終了し、7歳時点で買付した上場株式等の非課税期間は11歳(平成39年)に終了します。継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの各年に設定されるロールオーバー専用の非課税枠として機能し、ジュニアNISA口座で平成31年から平成35年の間に買付した上場株式等を、それぞれの年の非課税期間の5年間が終了するタイミングで移管することで、1月1日において20歳である年の前年12月31日まで非課税の恩典を受けることができます。継続管理勘定では新規の買付はできず、他の年分の非課税管理勘定から移管した上場株式等で時価80万円を超えないもののみ受け入れることができます。
2. 金融機関の変更
ジュニアNISA口座は、証券会社、銀行、郵便局など複数の金融機関で開設できますが、開設後に金融機関を変更することも可能です。ただし、払出し制限が解除される前(3月31日時点で18歳である年の前年12月31日)に金融機関を変更した場合、災害などのやむを得ない事由による口座廃止を除き、非課税で受領したすべての配当金や売買益に課税される可能性があります。 また、ジュニアNISA口座を開設した後に、他の金融機関でジュニアNISA口座を開設することはできません。ジュニアNISA口座は一人につき一つしか開設できないため、新たな口座を開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります。口座廃止は、払出し制限が解除される年より前に実施すると、非課税で受領したすべての配当金・売買益に課税されます。一度開設されたジュニアNISA口座は、開設後に取消しのお申し出をされても、開設を取り消すことはできません。
3. 20歳到達後の手続きと成人NISAへの移管
口座開設者が20歳に達した後は、成人NISAを開設できます。ジュニアNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等を、成人NISAに移管(ロールオーバー)することも可能です。ただし、この移管は、ジュニアNISA口座と成人NISA口座の両方が同じ証券会社で開設されている場合に限られます。移管手続きには、「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」の提出が必要です。また、20歳になった後も、引き続き運用管理者による運用指図を希望する場合は、ジュニアNISA口座を開設している証券会社などに、予めその旨を届け出る必要があります。ジュニアNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託の非課税期間が終了する際も、同様の手続きで成人NISA口座への移管が可能です。ただし、これはジュニアNISA口座が開設されている証券会社に成人NISA口座が開設されている場合に限ります。
V.資金の拠出と運用管理者
資金の出し手に制限はありませんが、運用される資金は口座開設者本人に帰属する必要があります。証券会社などは、資金が口座開設者本人に贈与済みであることを確認します。未成年者である口座開設者本人以外の者によりジュニアNISA口座が名義口座として利用されることを防ぐため、運用管理者は法定代理人または法定代理人から書面による委任を受けた二親等以内の者に限定されます。
1. 資金拠出の制限と確認事項
ジュニアNISA口座への資金拠出に関して、資金の出し手自体に制限はありません。しかし、未成年者である口座開設者本人以外の者による名義口座利用を防ぐため、運用資金は厳格に口座開設者本人に帰属するものである必要があります。そのため、証券会社などでは、ジュニアNISA口座へ拠出される金銭について、口座開設者本人に贈与済みの資金であり、両親や祖父母、その他の第三者に帰属するものではないことを確認する必要があります。この確認を徹底するため、資金の拠出方法は、口座開設者本人の銀行口座からの振込、口座開設者本人名義の他の証券口座からの振込、または口座開設者本人もしくは法定代理人による現金での入金に限定されています。また、ジュニアNISA口座を開設する際には、法定代理人や運用管理者から、「口座開設者本人に帰属する資金以外の資金によってジュニアNISA口座で投資が行われないこと」を証する書類等の提出を求められる場合があります。これは、不正利用を防止するための重要な手続きです。
2. ジュニアNISAの運用管理者
ジュニアNISA口座の運用管理を行う「親権者等」は、口座開設者本人の法定代理人、または法定代理人から書面による明確な委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の者に限定されています。これもまた、未成年者である口座開設者本人以外の者による名義口座利用を防ぐための重要な規定です。両親や祖父母だけでなく、第三者も資金を拠出することは可能ですが、最終的に運用される資金は必ず口座開設者本人に帰属していなければなりません。証券会社などは、この点を厳しく確認し、不正利用を未然に防ぐための体制を整えています。運用管理者は、口座開設者の利益を最優先し、適切な運用を行う責任を負います。運用管理者変更の手続きについても、金融機関に確認する必要があります。口座開設者本人が18歳に達した後の運用についても、あらかじめ金融機関に届け出る必要があります。
