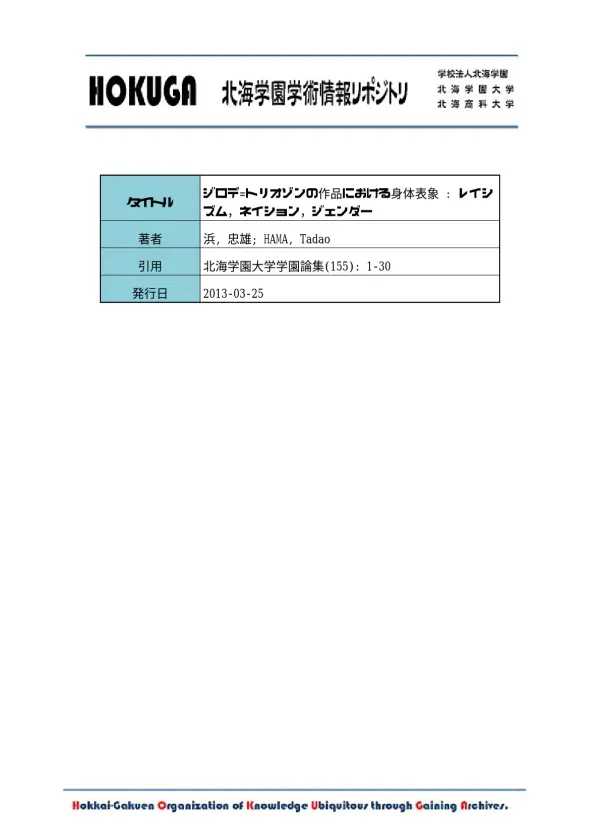
ジロデ=トリオゾンの身体表象:レイシズム、ネイション、ジェンダー
文書情報
| 著者 | Hama, Tadao |
| 学校 | 北海道大学 (Hokkaido University) |
| 専攻 | 美術史 (Art History), 歴史学 (History) |
| 場所 | 札幌 (Sapporo) |
| 文書タイプ | 論文 (Essay) / 著書の一部 (Part of a book) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.42 MB |
概要
I.アンヌ ルイ ジロデ トリオゾンと彼の代表作 エンデュミオンの眠り と ベレイの肖像
18世紀末から19世紀初頭のフランスを代表する画家、アンヌ=ルイ・ジロデ=トリオゾン(Anne-Louis Girodet-Trioson, 1767-1824)は、師であるジャック=ルイ・ダヴィッドの影響を受けつつ、新古典主義からロマン主義へと傾斜していった画家です。彼の代表作であるエンデュミオンの眠り(1791年)は、優美な表現で知られ、後のジェンダー論における議論を喚起する作品となっています。一方、ベレイの肖像は、ハイチ革命に貢献した黒人、ジャン=バティスト・ベレイを描いた作品で、黒人奴隷制廃止という歴史的文脈と、身体表象という観点から重要な意味を持つとされています。両作品は、同じ画家によるものでありながら、様式や表現方法において対照的な特徴を示し、1798年のサロンで同時に展示されました。
1. ジロデ トリオゾンの経歴と芸術的変遷
アンヌ=ルイ・ジロデ=トリオゾン(1767-1824)は、18世紀末から19世紀初頭のフランスを代表する画家です。1785年、ジャック=ルイ・ダヴィッドに師事し、1789年にはローマ賞大賞を受賞するなど、若くして才能を開花させました。ローマ滞在中の23~24歳頃には、後の代表作となる「エンデュミオンの眠り」(1791年)を制作し、1793年にはパリのサロンに出品、大きな反響を呼びました。1795年に帰国後はナポレオンからも注文を受けるほどになり、1815年には学士院会員に推薦、翌年にはレジオン・ドヌール勲章を受章しました。彼の作品は、当初は師ダヴィッドの影響を受けた新古典主義様式でしたが、次第にロマン主義的な様式へと傾斜していったとされています。この経歴と芸術的変遷は、彼の代表作である「エンデュミオンの眠り」と「ベレイの肖像」を理解する上で重要な要素となります。特に、新古典主義とロマン主義という異なる様式への移行は、彼の作品世界に多様性をもたらし、後の美術史における評価に影響を与えています。彼の芸術的変遷をたどることで、彼がいかにして独自の表現様式を確立したのか、そしてその表現様式がどのように時代背景と結びついているのかを深く理解することができます。
2. 代表作 エンデュミオンの眠り 新古典主義からの逸脱とジェンダー表現
「エンデュミオンの眠り」(1791年)は、ジロデ=トリオゾンの代表作の一つであり、新古典主義的な様式美とは異なる、ロマン主義的な優美さを備えた作品として知られています。絵画における人物の描写、特にエンデュミオンの繊細で優美な表現は、師であるダヴィッドの新古典主義的な英雄的で男性的な様式美とは対照的です。この作品におけるエンデュミオンは、あたかも女性であるかのように描かれていると評され、両性具有的な男性裸体像として解釈されることもあります。この点から、本作品は後のジェンダー論において重要な議論の対象となり、男性像の多様性や、当時の社会におけるジェンダー規範に対する新たな視点を提供する作品として位置づけられています。また、月の女神セレネが擬人化されず、月光として表現されている点も、作品全体の雰囲気や象徴性を理解する上で重要な要素となります。この作品は、単なる神話画にとどまらず、当時の社会状況やジェンダー意識を反映した、多様な解釈を可能にする作品と言えるでしょう。
3. 代表作 ベレイの肖像 ハイチ革命と黒人奴隷制廃止
「ベレイの肖像」は、フランス革命期にフランス議会で議席を得た最初の黒人、ジャン=バティスト・ベレイを描いた作品です。この肖像画は、1794年2月4日の黒人奴隷制廃止宣言という歴史的背景と深く結びついています。ベレイは、ハイチ革命において奴隷解放運動の中心的役割を担い、フランスに派遣された代表団の一員として、奴隷制廃止に貢献した人物です。この作品は、単なる肖像画にとどまらず、ハイチ革命、フランス革命、黒人奴隷制廃止という、18世紀後半から19世紀初頭の重要な歴史的出来事と深く関わり合っている点が注目されます。絵画におけるベレイの堂々とした姿勢や、その身体表現は、フランス革命における人権思想と、黒人に対する当時の社会通念との間の複雑な関係性を示唆していると言えるでしょう。また、作品発表後、ベレイの下半身の描写に関して、編集段階で修正が加えられたという事実も、当時の社会における黒人男性に対する視線や、身体表現に対する意識の変化を反映していると考えられます。
4. 二つの肖像画の同時出品と鑑賞者の反応
1798年、パリのサロンに「エンデュミオンの眠り」と「ベレイの肖像」が同時に出品されました。この二つの作品は、同じ画家によって描かれたにもかかわらず、様式、主題、表現方法において対照的です。新古典主義的な英雄的な様式美を備えた黒人男性像である「ベレイの肖像」と、一見女性と見まがうような優美なロマン主義的な白人男性像である「エンデュミオンの眠り」。鑑賞者たちは、これらの対照的な作品をどのように受け止めたのでしょうか。この点については、本文では言及されていませんが、当時の社会におけるジェンダーや人種に対する意識、そして美術批評の動向を研究することで、より深く考察できる可能性があります。二つの作品を比較検討することで、ジロデ=トリオゾンの芸術的才能、そして彼が意図したメッセージをより多角的に理解することができるでしょう。また、この同時出品は、彼の芸術における多様性、そして当時の社会状況を反映した非常に興味深い出来事と言えます。
II.ベレイの肖像とフランス革命における黒人像
ベレイの肖像は、フランス革命期における黒人奴隷制廃止と密接に関連しています。ベレイは、ハイチ革命後の奴隷解放運動でフランスに派遣された代表団の一員であり、1794年の黒人奴隷制廃止宣言に大きく貢献しました。この作品は、植民地主義、人権、フランス革命といった歴史的文脈の中で、当時のフランス人の黒人観や国民国家形成におけるアイデンティティ問題を反映していると解釈できます。また、絵画における身体表象を通して、**sexualization of 'black masculinity'**という問題提起も行われています。
1. ベレイの肖像 フランス革命と黒人奴隷制廃止の象徴
ジロデ=トリオゾンの「ベレイの肖像」は、フランス革命期の黒人奴隷制廃止という歴史的文脈において重要な意味を持ちます。モデルであるジャン=バティスト・ベレイは、フランス議会に議席を得た最初の黒人であり、1793年8月にサン=ドマング(現在のハイチ)で宣言された奴隷解放の知らせを携え、代表団の一員としてフランスに赴き、1794年2月4日の国民公会での黒人奴隷制廃止決議に貢献しました。この肖像画は、単なる人物画ではなく、フランス革命における人権思想と黒人奴隷制廃止運動、そしてハイチ革命といった歴史的出来事を象徴的に表現した作品として捉えることができます。絵画に描かれたベレイの堂々とした姿は、黒人解放運動の象徴であり、フランス革命の理念が、人種を超えた普遍的な自由を謳うものではなかったという複雑な歴史的現実を反映しているとも解釈できます。作者が自身の著作『ハイチ革命とフランス革命』の表紙にこの肖像画を使用したことも、その歴史的意義を強調する上で重要です。
2. ベレイの生涯とハイチ革命における役割
ジャン=バティスト・ベレイ(1746/47-1805)は、セネガルのゴレ島で生まれ、2歳の時にサン=ドマングに奴隷として連行されました。1791年夏に勃発したハイチ革命に身を投じ、奴隷解放運動に参加しました。レジェ=フェリシテ・ソントナクスというフランス政府代表委員は、ベレイを「新しいスパルタクス」と評し、黒人奴隷による解放運動が奴隷制廃止に決定的な役割を果たしたことを示唆しています。この「新しいスパルタクス」という表現は、歴史上のスパルタクスとは異なり、勝利を収めた解放の象徴としてベレイを位置付けている点で注目に値します。ベレイの生涯は、植民地支配下での苦難と、自由と平等を求める闘争の象徴であり、彼の経験は「両インド史」といった反植民地主義思想とも深く関わっています。彼の存在は、単なる個人の物語を超えて、黒人奴隷の抵抗と解放の歴史を象徴的に体現しています。
3. ベレイの肖像 における身体表象と黒人観
「ベレイの肖像」は、フランス革命期におけるフランス人の黒人観を反映した作品として、美術史、ジェンダー史、植民地史の観点から多角的な解釈が可能です。特に、ベレイの下半身の描写は、当初出版社側によって修正されたものの、そのことが身体表象史上の重要な意味を見落とす結果となりました。この修正の経緯は、当時の西洋社会における黒人男性に対する性的イメージや、そのイメージが持つ社会的な意味、そして身体表象の政治性を示唆しています。ヴィクトリア・シュミット=リンゼンホーフの論文は、この作品における「sexualization of 'black masculinity'」を論じており、ヨーロッパ人の黒人男性への性的幻想と、それに基づく差別意識を浮き彫りにしています。川島慶子の指摘する、黒人男性の性器に対する劣等意識が黒人差別思想の根底にあるという説も、この作品を解釈する上で参考になります。この肖像画は、単なる人物画を超えて、複雑な歴史的背景と社会構造を反映した、多層的な意味を持つ作品と言えるでしょう。
4. ベレイの肖像 と 文明化の使命
「ベレイの肖像」は、フランスの「文明化の使命(mission civilisatrice)」というイデオロギーを批判的に捉える視点からも解釈できます。「人権の国フランス」というイデオロギーや、植民地主義を共和主義理念の実現とする「植民地共和国フランス(La France, république coloniale)」といった考え方は、現代のフランスにおいても根強く残るものです。この肖像画は、そうしたイデオロギーの先駆け的な表現として読むことも可能です。1794年2月4日の黒人奴隷制廃止宣言は、植民地住民にフランス市民としての権利を認めたと謳われていますが、それは同時に、奴隷解放が「フランス市民」になることであり、フランスの文化や価値観への同化を前提としたものでした。「ベレイの肖像」は、フランス革命の思想が、このような高潔な黒人を生み出したという意識を巧妙に図像化したものとして解釈することもできます。この作品は、フランス革命の理念と現実の複雑な関係性を示す重要な資料と言えるでしょう。
III.西洋絵画におけるジェンダーと身体表象 ダヴィッド アングル ドラクロワとの比較
ジロデ=トリオゾンの作品は、ジャック=ルイ・ダヴィッドや、後のアングル、ドラクロワといった巨匠の作品と比較することで、その独自性がより明確になります。ダヴィッドの新古典主義作品では、男性像が英雄的で、女性像が補助的な役割を担っているのに対し、ジロデの作品、特にエンデュミオンの眠りは、両性具有的な男性像を通して、ジェンダーの枠組みを超えた表現を試みています。アングルとドラクロワの作品における女性の身体表象と比較することで、19世紀における女性の社会的地位と美術表現の変化を考察することができます。特に、自由の女神像の表現方法や、マリアンヌ像を通しての国民統合への考察が重要です。
1. ダヴィッドとジロデ トリオゾンの男性像の比較 新古典主義とロマン主義
本文では、ジロデ=トリオゾンの作品におけるジェンダー表現を分析する上で、彼の師であるジャック=ルイ・ダヴィッドの作品との比較が重要視されています。ダヴィッドの歴史画における男女の描写は、構図上ほぼ同等の位置と役割を占めるものの、理想化された男性像が物語の中心となり、道徳性や積極的な価値を体現するのに対し、女性像は物語の攪乱要因や、男性の英雄性を際立たせるための要素として描かれる傾向があります。一方、ジロデ=トリオゾンの「エンデュミオンの眠り」は、このダヴィッドの典型的な男性像とは異なる、優美で両性具有的な男性像を描いています。これは、新古典主義の英雄的な男性像とは対照的で、ロマン主義的な傾向を示すものと解釈できます。ダヴィッドの代表作である「ホラチウス兄弟の誓い」や「ブルートゥスの邸に息子たちの遺骸を運ぶ警士たち」における男女の役割分担の描き方と比較することで、ジロデ=トリオゾンの作品におけるジェンダー表現の独自性がより明確になります。特に、「エンデュミオンの眠り」における両性具有的な男性像は、後のフランスにおける国民統合のシンボル像の変化を考える上で、重要な意味を持つと指摘されています。
2. エンデュミオンの眠り における両性具有的な男性像と国民統合
シュミット=リンゼンホーフは、「エンデュミオンの眠り」をフランス革命の政治史、国民国家=国民統合の文脈で読み解いています。その結論は、この作品に描かれた両性具有的な男性像が、フランス共和国のシンボルが女性像(マリアンヌ像)から男性像(ヘラクレス像)へと移行する際の橋渡しとなった、というものです。この解釈では、フランス革命期における国民統合の過程において、ジェンダー表現がどのように変化し、政治的な役割を果たしたのかが考察されています。 共和国のシンボルが女性像から男性像へと変化する過程は、当時の社会におけるジェンダー役割の変化や、国民国家形成におけるアイデンティティの構築と密接に関連していると考えられます。 この解釈は、単なる美術史的な分析にとどまらず、フランス革命期における政治と社会、そしてジェンダーの複雑な関係性を示唆するものです。また、この解釈が、どの程度ジロデ=トリオゾンの制作意図と一致するのかという点も議論の余地が残されています。
3. 19世紀西洋絵画における女性の身体表現 アングルとドラクロワ
本文では、19世紀前半のアングルとドラクロワの作品における女性の身体表現と、ジロデ=トリオゾンの作品との比較が行われています。アングルとドラクロワは、それぞれアカデミズムとロマン主義を代表する画家であり、彼らの作品における女性の身体表現は、美術表現における「他者」としての女性の地位を再付与したものとして位置づけられています。アングルの「トルコの浴場」やドラクロワの「サルダナパロスの死」、「民衆を率いる自由の女神」などが例として挙げられています。これらの作品における女性の身体表現は、クールベ、マネ、ピカソといった後の近代絵画の男性芸術家たちによる実験の場となり、近代絵画の発展に影響を与えました。 この流れの中で、ジロデ=トリオゾンの作品におけるジェンダー表現の独自性や先駆性を改めて認識することができます。特に、「自由」や「共和国」といった概念が女性像で象徴されていた時代から、男性像へと移行していく過程において、ジロデ=トリオゾンの作品がどのような役割を果たしたのかという点が考察のポイントとなります。
IV.アルテミジア ジェンティレスキと女性芸術家の視点
アルテミジア・ジェンティレスキ(Artemisia Gentileschi, 1593-1653)の作品、特に「ユディットがホロフェルネスの首を斬る」は、女性芸術家の視点から見た力強い表現が特徴です。当時の女性が美術界で直面した制約や差別を反映し、男性画家とは異なる視点からの表現が、ジロデ=トリオゾンの作品におけるジェンダー表現の議論をさらに深めます。また、スザンナの沐浴を描いた作品群との比較も、男性と女性の視点の違いを示す上で重要なポイントとなります。
1. アルテミジア ジェンティレスキの生涯と創作活動における制約
アルテミジア・ジェンティレスキ(1593-1653)は、バロック期のイタリアの女性画家です。画家であった父の影響を受け、幼い頃から絵画を学びましたが、女性であることから多くの制約を受けていました。修道院で絵画の基礎を学んだ後、父の助手として働きましたが、女性が自由に絵を描くことは許されず、特に男性の裸体をモデルにすることは禁じられていました。彼女は、この制約を嘆き、絵の世界の半分が奪われていると訴えましたが、父からはローマ教皇の定めた規則だと説明されました。それでも彼女は才能を開花させ、アゴスティーノ・タッシに師事して遠近法を学び、父を凌駕する腕前になりましたが、19歳の時にタッシに強姦されたとして裁判にかけられ、「淫乱な女」という汚名を負わされました。こうした経験は、彼女の芸術観や表現に大きな影響を与え、後の作品に反映されています。この厳しい環境下での彼女の創作活動は、女性芸術家としての生き方の困難さと、その困難を乗り越えようとする強い意志を示しています。
2. ユディットとホロフェルネス ジェンダーと復讐の表現
アルテミジアの代表作の一つに「ユディットがホロフェルネスの首を斬る」があります。これは旧約聖書の外典、ユディット書を題材にした作品ですが、他の男性画家による同主題の作品と比較することで、女性芸術家としての彼女の独特な視点が際立ちます。男性画家による作品では、ユディットはホロフェルネスの首を斬った直後にもかかわらず、平然とした表情で描かれ、殺害行為の凄惨さが薄れています。一方、アルテミジアの作品では、ユディットは腕まくりをして、渾身の力を込めてホロフェルネスの首を斬ろうとする姿がリアルに描かれており、強い迫力を感じさせます。この違いは、アルテミジア自身の生い立ちや、当時の女性に対する社会的な制約、そして彼女自身の強い復讐心と結びついていると解釈できます。彼女の作品は、単なる宗教画ではなく、女性が社会から課せられた制約や差別への反抗と、自らの生き方への強い意志を表現したものと言えるでしょう。
3. スザンナの沐浴 男性と女性の視点の対比
本文では、旧約聖書のダニエル書を題材にした「スザンナの沐浴」という作品も取り上げられています。この作品も、男性画家と女性画家による作品を比較することで、ジェンダーによる視点の違いを浮き彫りにするのに役立つ例として挙げられています。男性画家、例えばティントレットの作品では、スザンナは覗き見されていることに気づいていないかのように平然と裸体を晒しており、「観る性=男性、観られる性=女性」という非対称性が見て取れます。一方、アルテミジアの作品では、スザンナは老人の視線と誘惑に対して激しい憎悪と拒否の態度を示しています。この対比を通して、同じ主題を描いても、男性画家と女性画家では視点や表現方法に大きな違いがあることが分かります。これは、ジェンダーバイアスが、芸術表現にどのように影響を与えるかを示す重要な例として挙げられています。アルテミジアの作品は、女性が置かれた状況や、彼女自身の経験が反映された、力強い表現に満ちた作品と言えます。
V.フランス革命の人権宣言とジェンダー オリエンタリズム
フランス革命における人権宣言は、表面上は普遍的な人権を謳っていますが、実際にはジェンダーやオリエンタリズム(ここではハイチ革命との関連性)といった視点から見ると、その限界や矛盾点が浮き彫りになります。オランプ・ドゥ・グージュの活動や、黒人奴隷制廃止宣言の背景にある複雑な事情も、この点において重要な考察材料です。人権、ジェンダー、オリエンタリズムの3つのキーワードからフランス革命を再考することで、新たな歴史的解釈が得られます。
1. フランス革命の人権宣言の限界 ジェンダーの視点
本文では、フランス革命の人権宣言が、ジェンダーの視点から見ると「男権宣言」に過ぎないという批判的な見解が示されています。中学校の歴史教科書では、人権宣言は身分や人種に関係なく普遍的な人権を謳ったものとして説明されていますが、この記述は必ずしも正しいとは言えないと指摘されています。特に、人権の男女平等を求め、女性の権利を訴えたオランプ・ドゥ・グージュは、その主張が全く無視され、むしろ「女性と女性市民の権利の宣言」を起草したことが反革命容疑の理由となり、処刑されたという事実が取り上げられています。このことは、フランス革命が、女性の人権を自明のこととして無視し、反女性的な性格を持っていたことを示唆しています。人権宣言は、形式的には普遍性を謳う一方で、実際にはジェンダーに基づく不平等が依然として存在していたという矛盾点が指摘されています。このことは、現代においても普遍的な人権の実現に向けて、ジェンダー平等という視点がいかに重要であるかを示しています。
2. オリエンタリズムとハイチ革命 人権宣言の適用範囲
フランス革命の人権宣言の適用範囲に関する問題点として、オリエンタリズム、特にハイチ革命との関連性が示されています。「子ども」「ジェンダー」「オリエンタリズム(またはハイチ)」という3つのキーワードによって、人権宣言を吟味することで、これまでとは異なるフランス革命像が見えてくるとされています。 ハイチ革命は、フランス革命の人権思想とは皮肉な関係にありました。フランス革命は奴隷制を廃止する一方、その廃止は黒人奴隷の蜂起という現実的な圧力があったからであり、人権宣言からの論理的帰結ではなかったとされています。 また、1794年2月4日の黒人奴隷制廃止宣言は、植民地住民をフランス市民として認める一方、フランス市民になることによって初めて自由が享受できるという条件付きのものでした。このことは、人権宣言の普遍性と、実際の植民地支配における矛盾を示しています。 ハイチ革命という、植民地における黒人奴隷の蜂起は、フランス革命の人権宣言の普遍性という理念の限界を明らかにする重要な事例として捉えられています。
3. ジェンダーバイアスの深刻な結果 歴史における女性の立場
本文では、ジェンダーバイアスが、女性の人生だけでなく、生命をも奪う深刻な結果を生むことを、歴史上の事例を挙げて指摘しています。オランプ・ドゥ・グージュの例は、その最も極端な事例と言えるでしょう。また、科学史における女性の貢献が忘れ去られてきた事実や、近代西洋絵画におけるジェンダー表現の偏りなども、ジェンダーバイアスが社会に及ぼす影響を示す例として挙げられています。 特に、アルテミジア・ジェンティレスキの生涯と作品は、女性が芸術活動を行う上での困難さと、その困難を乗り越えて創作活動を続けた女性の強さを示す、象徴的な例として提示されています。 これらの事例は、ジェンダーバイアスが、歴史の記述や解釈、そして個人の人生にいかに大きな影響を与えてきたのかを示しており、現代社会においてもジェンダー平等の実現が重要な課題であることを強く示唆しています。
