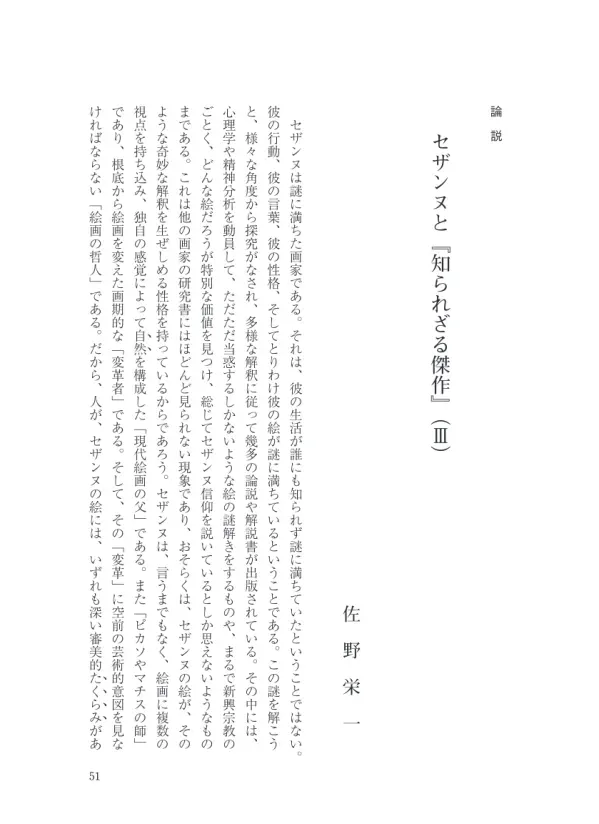
セザンヌとタンギー:絵画への情熱
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 12.49 MB |
概要
I.タンギーによるアシル アンプレールの肖像と絵画の経済性
本文冒頭では、画商タンギーが所有していた巨大な油彩作品『アシル・アンプレールの肖像』が廃棄されることを恐れた理由が説明されています。これは、タンギーが絵画の価格を大きさで決め、必要に応じて作品を分割して販売していたため、彼にとって非常に価値のある作品だったからです。このエピソードは、19世紀の絵画市場と画家の経済的状況、特に厚塗り絵画の価値観を理解する上で重要です。
1. アシル アンプレールの肖像 タンギーの懸念
本文の冒頭は、画商タンギーが所有していた『アシル・アンプレールの肖像』という絵画の破棄を極度に恐れていたという記述から始まります。その理由は、作品が縦2メートル、横1メートル22センチという大作であり、さらに絵具が厚塗りされていた点にあります。この厚塗りは、タンギーにとって新時代の絵画様式を象徴するものであり、彼の絵画に対する価値観を反映しています。彼は絵画の値段を寸法で決めており、顧客の支払いが不足する場合は作品を分割して「小売り」するほどでした。そのため、この大作『アシル・アンプレールの肖像』は、彼にとって非常に価値の高い、そしてかけがえのない作品だったのです。1890年頃、彼の店によく通っていたエミール・ベルナールは、様々な画家の作品が積み重ねられた中から、この作品を「発見」したと記されています。この記述は、タンギーの絵画に対する商業的な視点と、当時の画家の経済状況の一端を垣間見せています。絵画の大きさや技法(厚塗り)が、その経済的価値に直結していたことがわかります。また、多くの画家の作品がタンギーの店に集まっていたという事実は、当時の美術市場の状況を反映しており、画商と画家との間の複雑な関係を示唆しています。この大作の破棄を恐れたというエピソードは、タンギーの経済的な思惑と、彼にとっての芸術作品の意味合いを浮き彫りにしています。
2. 絵画の価格設定と販売方法
タンギーの画商としてのビジネスモデルが、このエピソードを通して明らかになります。彼は絵画の価格を、その寸法によって決定していました。これは、当時の絵画市場における一般的な価格設定とは異なる、独自のシステムと言えるでしょう。さらに、顧客の支払いが不足する場合には、絵画を分割して販売するという、大胆な方法をとっていました。これは、単なる商業的な行為ではなく、彼の絵画に対する価値観、そして顧客への対応方法を表しています。顧客の経済状況に合わせて、作品を柔軟に販売する彼の姿勢は、現代のビジネス感覚とは異なる、当時の独特な商習慣の一端を垣間見せています。『アシル・アンプレールの肖像』という大作も、この寸法による価格設定と分割販売というシステムの産物であり、その価値の高さが強調されています。この販売方法は、現代の美術市場では考えられないほど大胆で、当時の絵画市場の特殊性、そしてタンギーという人物の個性的なビジネス手法を示しています。また、このエピソードは、絵画が単なる芸術作品ではなく、商品として取引されていたという現実を改めて示しています。
3. エミール ベルナールの 発見 と作品の存在意義
エミール・ベルナールが、タンギーの店において『アシル・アンプレールの肖像』を「発見」したという記述は、この絵画の存在意義を際立たせています。様々な画家の作品が積み重ねられた状態から発見されたという描写は、この絵画が埋もれてしまいかねない状況にあったことを示唆しており、その価値の高さを強調しています。もしこの絵画が破棄されていれば、後世に残ることはなかった可能性が高く、ベルナールによる発見は、この作品が保存され、現在まで伝えられた重要な契機となったと言えるでしょう。このエピソードは、偶然の発見によって歴史的な作品が保存されるという、美術史における興味深い側面を示しています。また、タンギーの店に集まっていた数多くの絵画は、当時の美術界の多様性と活気を象徴しており、それらの中から『アシル・アンプレールの肖像』が選ばれ、注目されたという事実は、この作品が持つ特別な価値を再認識させます。ベルナールの視点、そして彼の記述が、この絵画の歴史において重要な役割を果たしていると言えるでしょう。
II.セザンヌのパリ進出と初期の苦悩 ゾラの激励
1861年、セザンヌは画家になる夢を抱きパリへ上京しますが、セザンヌ自身は才能に自信がなく、絵画技術に苦悩していました。友人であるゾラの強い激励が、彼を支え続けました。ゾラはセザンヌの手紙に書かれた「成功の見込みがない」という記述に心を痛め、才能を信じ、継続的な努力の重要性を説き、彼のパリでの絵画制作を強く後押ししました。これはセザンヌの精神的な支えと、初期の絵画制作における困難さを示す重要な描写です。
1. セザンヌのパリ進出と初期の不安
1861年、セザンヌは画家になる決意を固め、故郷エクス=アン=プロヴァンスからパリへと旅立ちます。多くの若き芸術家たちが、未来への希望と根拠のない自信に満ち溢れて新しい生活を始める中、セザンヌは書簡集から窺えるように、そうした自信を全く持っていなかったようです。1857年からエクスの美術館付属デッサン学校に通い始め、絵画の手ほどきを受けていましたが、思うように絵が描けず、自身の才能に絶望し悩んでいました。彼の才能に懐疑的な視線を向け、絵を描くことに苦悩するセザンヌの姿が描かれています。この初期の葛藤は、後の彼の画業を理解する上で非常に重要な要素となっています。彼の才能が、必ずしも一般的な画家のそれとは異なっていたことを示唆しており、その独特の表現方法の源泉を探る上で、この初期の苦悩は重要な手がかりとなります。このセクションでは、セザンヌの才能や才能への自信の欠如が強調されており、彼の内面的な葛藤が浮き彫りにされています。
2. ゾラの激励と友情
セザンヌを絶望の淵から救い上げたのが、親友であるエミール・ゾラです。ゾラは、セザンヌが画家になることを強く勧め、パリへの上京を促し続けました。ゾラとセザンヌ、そして後に大学教授となるバイユは、エクスのリセで出会った親友同士であり、パリでもその友情を継続することをゾラは熱望していました。セザンヌが画家になる夢を諦めることを、ゾラは何よりも恐れていたのです。ゾラはセザンヌの手紙を読み、「成功する見込みがないにもかかわらず、好きなものといったら絵なんだ」という記述に心を痛め、才能を信じ、継続的な努力の重要性を説いて励ましました。セザンヌの才能を信じるゾラの強い友情と激励は、セザンヌの芸術家としての道を切り開く上で大きな力となりました。この友情は、セザンヌの人生において大きな支えとなり、彼の芸術活動に大きな影響を与えたと考えられます。ゾラの言葉は、セザンヌ自身の才能への不安を反映しているものであり、同時にゾラのセザンヌに対する揺るぎない信頼を示すものとなっています。
3. セザンヌのデッサン能力とアカデミックな評価
セザンヌは、形を正確に捉え、的確に描写する才能、つまり一般的な画家にとって必須とされる才能に、必ずしも恵まれていませんでした。ゾラやバイユと共にエクスの名門コレージュ・ブルボンで優秀な成績を収めていた彼ですが、絵画においては、特にデッサンの能力が劣っていました。デッサンコンテストでの成績は、バイユやゾラに大きく後れを取っており、1856年には最下級の賞すら獲得できませんでした。1857年にはゾラが1位、セザンヌは番外、1858年にようやく2位を獲得しましたが、これはデッサン学校に通い始めてからの成果であり、アカデミックな教育を受けた上での結果でした。後年、ピサロは息子への手紙の中で、「美術学校から来た無能どもがこぞってセザンヌの裸体素描をこき下ろしていた」と回想しています。この記述は、セザンヌのデッサン能力が、当時のアカデミックな基準から見ると劣っていたことを示しており、彼の苦悩の背景を理解する上で重要な情報となります。セザンヌの才能は、必ずしもアカデミックな評価基準に合致するものではなかったことがわかります。
III.セザンヌのアカデミーでの苦戦と才能の特殊性
エクス=アン=プロヴァンス時代のセザンヌは、優れた学力にも関わらず、デッサンの成績は常に友人のゾラやバイユに劣っていました。美術学校での評価は低く、同時代の画家たちからは嘲笑の対象にもなりました。しかし、ゾラは技術よりもセザンヌの芸術における「ポエジー」を評価し、技術的な側面は後から習得できると励ましました。この記述は、アカデミー中心の美術教育とセザンヌの独特な才能との摩擦、そしてゾラのセザンヌへの理解を示しています。
1. アカデミーにおけるセザンヌの低評価
セザンヌは、エクス=アン=プロヴァンスの名門コレージュ・ブルボンで優秀な成績を収め、様々な賞を獲得していました。しかし、絵画、特にデッサンにおいては、友人であるゾラやバイユに大きく劣っていました。1856年のデッサンコンクールでは、最下級の賞すら獲得できず、1857年にはゾラが1位、セザンヌは番外という結果に終わっています。1858年にようやく2位を獲得しましたが、これはデッサン学校に通い始めた成果であり、専門教育を受けた上での結果でした。このことは、セザンヌがアカデミックなデッサン技術においては、同世代の他の才能ある学生に比べて劣っていたことを示しています。彼の才能は、アカデミーの評価基準とは異なる独自の特性を持っていたと言えるでしょう。この評価の低さは、彼自身の才能への不安感を増幅させ、パリでの芸術活動への不安を煽る要因の一つになったと考えられます。このセクションでは、セザンヌがアカデミーにおいて認められなかった事実が強調されており、彼の才能の特殊性と、アカデミックな美術教育との間に存在したギャップが浮き彫りにされています。
2. 画塾の悪習とアカデミーの衰退
後年、ピサロは息子への手紙の中で、美術学校出身の画家たちがセザンヌの素描をこき下ろしていたことを回想しています。これは、当時の画塾における悪習であり、正確な素描を重視するアカデミーの伝統と基準が力を失いつつあったことを示しています。アカデミーの教育の魅力が薄れ、その影響力が衰えていく中で、画塾の悪習も衰退していきましたが、セザンヌの青春期はまさにその過渡期に当たっていました。当時、絵画が国家主導のものから市民のものへ、大絵画から小絵画へと移行しつつありましたが、国家による絵画の買収や、記念建造物の装飾といった国家権力が美術界に及ぼす影響力は依然として大きかったのです。そのため、アカデミーの教育と、国立美術学校は、画家を目指す者にとって王道であり、デッサン能力は必須の条件とされていました。セザンヌの不器用なデッサンは、アカデミックな技術を身につけた他の画家たちから軽蔑の対象となったのです。この時代背景と、セザンヌの才能の特殊性を理解することで、彼の芸術家としての苦悩をより深く理解することができるでしょう。
3. ゾラの激励とセザンヌのコンプレックス
ゾラはかねてより、セザンヌには芸術家にとって最も重要な「ポエジー」があり、あとは職人の技術を習得すれば良いと励ましてきました。しかし、この言葉の裏には、セザンヌのコンプレックス、すなわちデッサン能力の低さへの不安が隠されていると言えるでしょう。ゾラの激励は、セザンヌの才能を信じる強い思いの裏返しであり、同時に彼のコンプレックスを理解した上でのものだったと考えられます。ヴォラールは、晩年のセザンヌについても同様のエピソードを伝えています。このことは、セザンヌの才能が、アカデミックな技術とは異なる独自の表現力にあったことを示唆しています。彼の芸術における「ポエジー」とは、技術的な完成度ではなく、独自の感性や表現力、そして彼の内面から湧き上がる創造力のことだと考えられます。ゾラの理解と励ましは、セザンヌが自身の才能を信じて創作活動を続ける上で、大きな支えになったことは間違いありません。
IV.マネの落選作とゾラのサロン批評 伝統への反逆
ゾラのサロン批評において、マネの作品『笛を吹く少年』が落選したことが取り上げられています。ゾラは、この落選作に強い感銘を受け、伝統的なサロンの審査基準に疑問を呈しました。サロン入選作の多くが独創性に欠け、「お菓子」のような刺激のないものだと批判し、マネの作品が持つ独創性を高く評価しました。これは、印象派運動とサロンとの対立、そして伝統的な美術観への反逆を示す重要な部分です。
1. マネの落選とゾラの反発
このセクションでは、エミール・ゾラのサロン批評が中心となっています。記事の対象となっている年、サロンにはマネの作品がありませんでした。マネが応募した『笛を吹く少年』と『悲劇役者』は両方とも落選していたのです。しかし、ゾラはリウォルドによれば、この頃ギュンメとデュランディの紹介でマネと知り合い、サロン批評の連載開始後まもなく、マネのアトリエを訪ね、落選した二作品を見せてもらいました。ゾラは特に『笛を吹く少年』に感銘を受け、その印象に基づいて自身の批評を記しています。この落選によって、ゾラはサロン審査に対する反感と嫌悪感を抱き、伝統に盲従し「自然」を探究しない多くのサロン入選作にも厳しい目を向けたと考えられます。マネの作品がサロンで拒絶された事実は、ゾラにとって、サロンの保守的な審査基準に対する強い批判意識をさらに強めたと言えるでしょう。この落選は、単なる個々の出来事ではなく、当時の美術界における革新と保守の対立を象徴する出来事として捉えることができます。
2. ゾラのサロン批評と伝統絵画への批判
ゾラのサロン批評は、多くの入選作品を「お菓子」のように刺激のないものと評しています。これは、伝統に盲従し、独創性に欠ける作品が多いという批判の表明です。ゾラは、ありのままの対象、つまり「自然」を探究しない絵画に対して、強い批判的視点を示しています。彼の批評は、単なる批評にとどまらず、伝統的な美術観への挑戦、そして新しい美術様式への期待を表明していると言えるでしょう。多くのサロン入選作が、既成の様式や技法に固執し、独創性に欠けるものだったという記述は、当時の美術界の現状を鋭く突いています。ゾラの批評は、単に作品を評価するにとどまらず、当時の美術界の現状や問題点を指摘し、より革新的な美術への展望を示唆していると考えられます。この批評を通して、ゾラは、新たな美術様式や表現方法の模索、そして伝統からの脱却を訴えていると言えるでしょう。
3. マネの芸術と 完成 の問題
ゾラのマネに対する批評には、マネの芸術に対する無理解も含まれていると指摘されています。ゾラの論説の中で最も重要な点は、「完成」あるいは「仕上げ」の問題です。これはドラクロワ以来、19世紀絵画において繰り返し論議されてきた重要な問題です。ドラクロワの『ダンテの小舟』は、完成度が低いとして批判されたことがあります。この「完成」の問題は、絵画における技術的な完成度と、芸術的な表現の両面を考慮する必要があることを示しています。マネの絵画は、主観的な表現が際立っており、15年来彼ほど主観的に描く画家はいなかったと評されています。しかし、技術的な面が、その知覚の真正さに匹敵していれば、彼は19世紀後半の偉大な画家になっていたと述べられています。この記述は、マネの才能と、技術的な完成度が必ずしも芸術的な価値に比例しないことを示しています。また、この「完成」をめぐる議論は、19世紀絵画における重要な論点であったことを示しています。
V.マネと 完成 の問題 ドラクロワ以降の議論
ゾラのマネに関する批評においては、「完成」あるいは「仕上げ」の問題が重要視されています。これは、ドラクロワ以降、19世紀絵画における重要な論点でした。ドラクロワのデビュー作『ダンテの小舟』は、完成度が低いと批判された経緯があります。セザンヌ自身も、技術的な完成度よりも、主観的な表現を重視した画家として位置付けられています。
1. ゾラのマネ批評における 完成 の問題
ゾラによるマネに関する論説において、最も重要な論点として挙げられているのが「完成」あるいは「仕上げ」の問題です。この問題は、ドラクロワ以降、19世紀絵画において繰り返し議論されてきた重要なテーマであり、マネの作品批評においても中心的な位置を占めています。ゾラは、マネの絵画における主観的な表現を高く評価する一方で、技術的な側面における完成度の不足を指摘していると考えられます。これは、マネの絵画が、当時のアカデミックな絵画基準からは逸脱しているものの、独自の芸術的価値を有しているという、ゾラの複雑な評価を表しています。この「完成」という問題は、単なる技術的な問題ではなく、芸術における表現のあり方、そして芸術作品における「完成」の意味自体を問う問題として捉えることができます。ゾラは、マネの作品を通して、19世紀絵画における「完成」という概念への新たな問いを投げかけていると言えるでしょう。
2. ドラクロワと ダンテの小舟 の例
1822年、ドラクロワは『ダンテの小舟』でサロンに入選し華々しいデビューを飾りました。しかし、ダビッドの弟子でサロン批評を担当していたドゥレクリューズは、この作品を「スケッチにすぎない」と批評しました。これは、完成度が低いという批判であり、「完成」の問題が、既に19世紀絵画の初期から議論されていたことを示しています。ドラクロワの『ダンテの小舟』は、ロマン主義絵画を代表する作品の一つとして高く評価されていますが、同時にその完成度に関して、当時から議論の的となっていたのです。このドラクロワの作品に対する批評は、「完成」の問題が、単に技術的な問題にとどまらず、当時の美術界における様式や評価基準に関わる問題であったことを示しています。マネの作品批評においてもこの「完成」の問題が取り上げられていることは、マネの絵画が、当時の美術界における伝統的な基準や評価方法とは異なる新たな地平を開こうとしていたことを示唆しています。
3. マネとセザンヌにおける 完成 の相違点
ゾラの批評は、マネとセザンヌの両者に関する問題点を指摘しています。マネの絵画は、技術的な完成度が、その知覚の真正さに匹敵していれば、19世紀後半の偉大な画家になっていたと述べられています。一方、セザンヌについては、15年来彼ほど主観的に描く画家はいなかったと評されています。これは、セザンヌが技術的な面よりも、主観的な表現を重視していたことを示しています。マネとセザンヌの両者において、「完成」の問題は、技術的な完成度と芸術的な表現のバランスという観点から議論されています。しかし、両者における「完成」へのアプローチは異なっており、マネの場合は技術的な完成度の不足が指摘されているのに対し、セザンヌの場合は技術よりも主観的な表現が重視されている点が対照的です。この違いは、両者の芸術的個性や、それぞれの時代の美術動向を反映していると言えるでしょう。この比較を通して、19世紀絵画における「完成」をめぐる議論の多様性が浮き彫りになります。
