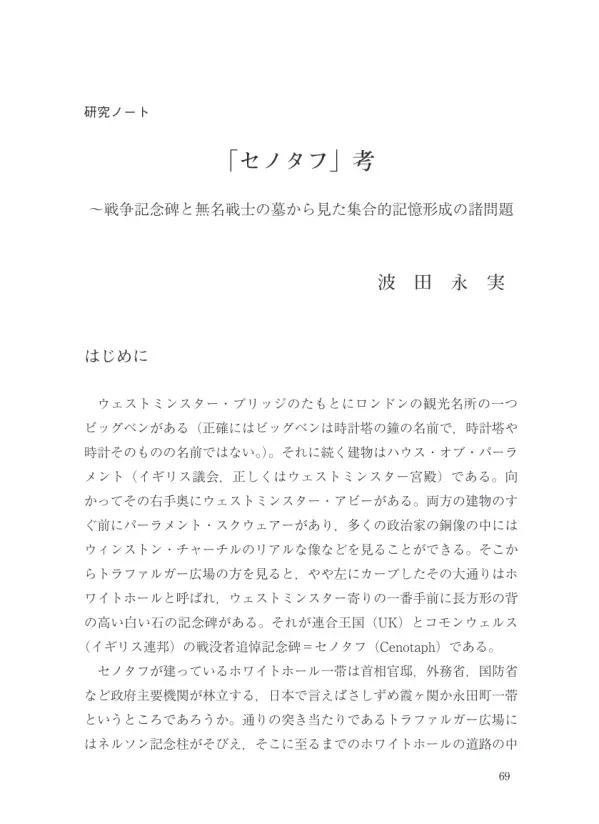
セノタフ:戦没者追悼と国民記憶
文書情報
| 学校 | ロンドン大学歴史研究所 (Institute of Historical Research) |
| 専攻 | 歴史 |
| 場所 | ロンドン |
| 文書タイプ | 研究ノート |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 27.31 MB |
概要
I.ロンドンのセノタフと無名戦士の墓 第一次世界大戦の集合的記憶
本稿は、ロンドンのホワイトホールにあるセノタフ(Cenotaph、戦没者追悼記念碑)を起点に、第一次世界大戦におけるイギリスの集合的記憶の形成と、無名戦士の墓の役割を考察する。1920年、ジョージ5世によって除幕されたセノタフは、帝国全土の戦没者を追悼する無宗教の記念碑とされているが、ウェストミンスター・アビーに埋葬された無名戦士の墓と一体となって機能している。この両者の関係性、特にウェストミンスター・アビーへの埋葬が持つ政治的意味(王室との関係、セノタフとの近接性)が重要な論点となる。 毎年11月11日(Remembrance Sunday)には、セノタフにおいて献花式が行われ、国民の深い哀悼の念が表れる。1919年の木と漆喰による仮設セノタフから、エドワード・ルトウィンズ卿によるポートランド石の恒久的な現在のセノタフへと受け継がれた歴史も重要な要素である。
1. セノタフの建設と意義 ホワイトホールの戦没者追悼記念碑
ロンドンのホワイトホールに位置するセノタフ(Cenotaph)は、第一次世界大戦の戦没者を追悼する記念碑として、1920年11月11日、ジョージ5世によって除幕されました。ギリシャ語で「遺体の入っていない空の墓」を意味するセノタフは、ウェストミンスター宮殿とウェストミンスター・アビーの近くに位置し、トラファルガー広場に通じるホワイトホールという政府機関が集中する場所に建てられています。この立地は、セノタフの政治的・象徴的な意味合いを強調しています。セノタフは、イギリス連邦(コモンウェルス)を含む連合王国の戦没者を追悼するものであり、毎年Remembrance Sunday(11月11日に最も近い日曜日)には、エリザベス女王を始めとする政府要人や軍関係者、遺族などが赤いポピーの花輪を捧げる献花式が行われます。この儀式は、第一次世界大戦における犠牲を記憶し、追悼する重要な国民的行事となっています。セノタフの存在は、イギリスにおける第一次世界大戦の集合的記憶の形成に大きな役割を果たしていると言えるでしょう。
2. 無名戦士の墓 ウェストミンスター アビーへの埋葬
第一次世界大戦の激戦地、イープルやソンムの戦場から回収された身元不明の兵士の遺体の中から選ばれた一人が、1920年11月11日、ウェストミンスター・アビーに埋葬されました。これは、フランスの無名戦士が凱旋門に埋葬された日と同じ日であり、その事実自体が第一次世界大戦の歴史的意義を象徴していると言えるでしょう。G.モッセの『英霊』によると、遺体の選定は負傷した下士官ではなく階級の高い将校が行われ、フランスの駆逐艦ヴェルダン号によって英仏海峡を渡り、パンプトン・コートのブリティッシュ・オークで造られた棺に納められました。棺の中には塹壕用兜、カーキのベルト、そして十字軍兵士の剣が納められていました。ウェストミンスター・アビーへの埋葬という行為は、無名戦士を国家全体の犠牲の象徴として位置付けるものであり、セノタフと併せて、イギリス国民の集合的記憶の形成に重要な役割を果たしています。この埋葬は、単なる葬儀ではなく、国家レベルの重要な儀式であったことが伺えます。
3. セノタフのオリジナルとレプリカ 1919年と1920年の式典
1919年7月19日の戦勝記念パレードに間に合わせるため、当初は木と漆喰で造られた仮設のセノタフが建てられました。これは、当時の首相ロイド・ジョージが「死者に対する何らかの賛辞」を要求したことにより、エドワード・ルトウィンズ卿によって設計されました。この仮設のセノタフは「一時的な非宗派的な棺台」という意匠で、後に現在のセノタフのデザインの基礎となりました。しかし、このオリジナルのセノタフは、第二次世界大戦中の爆撃で失われました。その後、国民の強い要望を受けて、イギリス特産のポートランド石で現在の恒久的なセノタフが作られました。1919年の黙祷の様子はマンチェスター・ガーディアンによって詳細に伝えられており、その時の国民の深い悲しみと静寂が克明に描写されています。1920年11月11日に行われた恒久的なセノタフの除幕式とウェストミンスター・アビーでの無名戦士の埋葬は、「生者による死者の蘇り」として国民に受け止められました。この二つのセノタフの存在は、第一次世界大戦における国民の記憶と感情を反映しています。
4. セノタフの 無宗教性 をめぐる議論とウェストミンスター アビーとの関係
イギリス政府はセノタフを「無宗教」の施設として公式に発表しています。しかし、セノタフが「礼拝用の墓」としての機能を持つこと、そしてウェストミンスター・アビーにある「無名戦士の墓」が英国国教会による祭祀を受けていることを考えると、セノタフの「無宗教性」という主張には疑問が残ります。イギリス議会においても、セノタフにキリスト教の意匠を加えるべきかという議論が交わされ、アンドリュー・ボナー・ロウ(当時、閣僚)は政府としてそれを認めないという明確な答弁をしています。多くのイギリス国民にとって戦没者の祭祀はキリスト教(英国国教会)によって執り行われることが当然と認識されていた可能性が高く、セノタフの「無宗教性」は、政治的な配慮や、国民感情の複雑さを反映した結果と言えるでしょう。セノタフと無名戦士の墓は、物理的に近い距離に位置し、ワンセットとして機能しているため、両者の関係性を理解することが、セノタフの真の意義を理解する上で重要です。この「無宗教性」に関する議論は、靖国問題など、他の国の同様な問題と比較検討する際に重要な視点となります。
II.パンテオンとワルハラ 記念碑と墓の関係
フランスのパリにあるパンテオン(Pantheon)とドイツのレーゲンスブルグにあるワルハラ(Walhalla)を比較することで、記念碑と墓の機能、政治的利用、そして国民的アイデンティティ形成における役割を分析する。パンテオンは当初、聖堂として建設されたが、フランス革命後、「偉人」を祀る栄誉殿堂へと転用された。合祀された人物には、ヴォルテール、ルソー、マラーなどがおり、政治体制の変化によって合祀と除名が行われた歴史を持つ。一方、ワルハラは北方神話の英雄を祀る記念堂だが、宗教的色彩は薄く、ナポレオンからの解放を記念した記念碑としても機能している。これらの事例を通して、記念碑が時の権力によって如何に利用され、その意味合いが変化していくのかを明らかにする。
1. パンテオン フランス革命と 栄誉の殿堂
パリのパンテオンは、元々はサント・ジュヌヴィエーヴ聖堂として建設が始まりましたが、1789年のフランス革命勃発後、国民議会の決定により「フランスの自由の時代の偉人の遺骸」を納める場所として「パンテオン」と改称されました。これは、革命初期の宗教否定を反映した、非キリスト教的な「栄誉の殿堂」への転用と言えるでしょう。当初、ミラボー、マラー、ルソーなど7人の革命家や思想家の遺骸が合祀されましたが、その後、政治情勢の変化に伴い、合祀と除名、そして施設の性格自体が変遷していきます。ナポレオン時代にはカトリック教会と一体となり、復古王政期には教会としての機能が強調され、七月王政期には再びパンテオンとして機能するなど、その性格は時代のイデオロギーや政治体制を反映してきました。 1806年から1815年のナポレオン第一帝政期には多くの軍人や政治家が合祀されており、ナポレオンがパンテオンを自らの支配の象徴として利用していたことがわかります。第三共和制以降も合祀は続き、ヴィクトル・ユーゴー、エミール・ゾラ、レオン・ガンベッタ、ジャン・ジョレスなどが合祀されていますが、1933年以降は中断しています。このようにパンテオンは、単なる記念碑ではなく、フランスの歴史と政治を反映する動的な空間であることがわかります。
2. ワルハラ ドイツの英雄たちの記念堂
ドイツのレーゲンスブルグにあるワルハラは、北方神話の英雄たちの魂の安息の場をイメージした記念堂です。ドナウ川沿いの丘の上に位置し、見晴らしの良い観光地としても人気があります。パンテオンのような宗教的色彩は薄く、多くの著名な人物が合祀されていますが、あくまで英雄を称える記念碑としての性格が強いです。ワルハラの建設は、ナポレオン戦争後のドイツ統一運動と関連しており、民族的アイデンティティの形成に寄与しています。興味深いことに、ワルハラの落成式の翌日に、ルードヴィヒ1世によって対ナポレオン戦争の「解放記念堂」が建設されました。これはローマのパンテオンを模したドームを持つ円形建築で、ナポレオンからの解放を記念するもので、墓としての機能は持ちません。ライプツィッヒの「諸国民戦争記念碑」も同様の意図で建設された例です。これらの例は、記念碑の機能が必ずしも墓としての機能に限定されないこと、そして政治的、民族的アイデンティティの形成に利用されることを示しています。 ウェストミンスター・アビーやセント・ポール大聖堂と比較することで、それぞれの国の歴史的背景や国民性、そして記念碑の役割の違いが浮き彫りになります。
3. パンテオンとワルハラを比較した考察 記念碑の政治的利用と国民的アイデンティティ
パンテオンとワルハラを比較することで、記念碑が持つ多様な機能と、政治体制や国民的アイデンティティとの関係性が明らかになります。パンテオンはフランス革命以降、政治体制の変化とともに合祀者や施設の性格が変化してきました。一方、ワルハラは民族的アイデンティティの形成という文脈で、英雄を称える記念碑として機能しています。両施設とも、宗教的色彩は限定的で、むしろ政治的、文化的象徴としての役割が強調されています。この比較を通じて、記念碑が単なる死者の埋葬場所ではなく、国家や国民の記憶、歴史観、そしてアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしていることがわかります。さらに、無名戦士の墓の設置をめぐる議論(パンテオンか凱旋門か)を通して、国民全体のシンボルとなる場所の選定における政治的配慮や国民感情の複雑さが示されています。これは、セノタフとウェストミンスター・アビーの関係性と比較検討することで、より深い理解が得られます。
III.ノイエ ヴァッヒェ ドイツにおける戦没者追悼と歴史的重層性
ベルリンのノイエ・ヴァッヒェ(Neue Wache)は、当初プロイセンの衛兵詰所だったが、後に戦没者追悼施設となった。ナチス時代にはキリスト教的象徴が追加され、東ドイツ時代には社会主義的色彩が加わった複雑な歴史を持つ。現在は統一ドイツの中央戦争犠牲者追悼所として機能しているが、加害者と被害者の区別が曖昧であるとして批判もある。ケーテ・コルヴィッツの「死んだ息子を抱きかかえる母親像」(ピエタを想起させる)が中央に安置されている点が注目される。この事例は、記念碑の意味が時代や政治体制によってどのように変容し、解釈が分かれるかを示している。
1. ノイエ ヴァッヒェの歴史 衛兵詰所から戦没者追悼施設へ
ベルリンにあるノイエ・ヴァッヒェ(Neue Wache)は、当初はカール・フリードリッヒ・シンケル設計による新古典主義様式のプロイセン王宮衛兵詰所として1818年から1918年まで使用されていました。しかし、第二次世界大戦後、ハインリッヒ・テセノウによる改築を経て、1931年から1945年まではプロイセン州立の戦没兵士追悼所となりました。この建物はギリシャ建築風で、内部に特にキリスト教的な意匠は強調されていませんでした。しかし、ナチス政権下では、祭壇の後方に大きな十字架が掲げられ、キリスト教民族主義的なシンボルとして利用されました。敗戦後、ナチス時代の象徴は取り除かれ、東ドイツ時代には「ファシズムと軍国主義の犠牲者のための警告廟」となり、さらに1993年のドイツ統一後は「中央戦争犠牲者追悼所」として機能しています。このようにノイエ・ヴァッヒェは、その歴史の中で様々な政治イデオロギーを反映し、その機能や意味合いを大きく変えてきたと言えるでしょう。建築様式、内部装飾、そしてその施設の名称からも、時代の変化が明確に読み取れます。
2. ノイエ ヴァッヒェの現在 ケーテ コルヴィッツの作品と解釈の多様性
現在、ノイエ・ヴァッヒェの中央に安置されているのは、ケーテ・コルヴィッツ作の「死んだ息子を抱きかかえる母親像」です。これはピエタを想起させるキリスト教的な図像の変形であり、戦争で亡くなった者への深い悲しみと追悼の念を表しています。コルヴィッツ自身、息子を第一次世界大戦で、孫を第二次世界大戦で失っており、その個人的な経験も作品に反映されていると考えられます。しかし、この作品は、ナチス政権下で「退廃芸術」とレッテルを貼られた社会主義的傾向の芸術家によるものであり、その背景も考慮する必要があります。現在、ノイエ・ヴァッヒェは「中央戦争犠牲者追悼所」として機能していますが、東ドイツ時代の社会主義体制による犠牲者も含まれていること、そしてナチス時代の加害者である兵士も追悼されていることから、「被害と加害の区別が曖昧」との批判を受け、ユダヤ人団体などからのボイコットも発生しています。このことは、ノイエ・ヴァッヒェの歴史的重層性と、その解釈の多様性を示しています。
3. ノイエ ヴァッヒェと靖国神社問題 記念碑の宗教性と政治的利用
ノイエ・ヴァッヒェは、その歴史を通じて宗教性と政治的利用の両面を示す例として挙げられています。 文献『諸外国の主要な戦没者追悼施設について』では「宗教性 なし」と記されていますが、中心に置かれたケーテ・コルヴィッツの作品はピエタを連想させ、宗教的象徴性を帯びていると言えるでしょう。これは、ワイマール共和国時代には無宗教に近く、第三帝国時代にはキリスト教化され、東ドイツ時代には再び無宗教化され、統一後はキリスト教的シンボル性を持ちながら無宗教の施設という、その歴史的変遷と符合します。 このノイエ・ヴァッヒェの事例は、セノタフの「無宗教性」という側面だけが強調され、英国国教会による祭祀を受ける「無名戦士の墓」との関係が軽視されている現状を浮き彫りにします。また、「無宗教の追悼施設」が靖国問題の解決策として提起されている現状に対する警鐘とも捉えられ、安易な「無宗教」施設の建設が新たな問題を生む可能性を示唆しています。 様々な歴史的、政治的、宗教的要素が複雑に絡み合ったノイエ・ヴァッヒェは、記念碑や追悼施設を考える上で重要な示唆を与えてくれます。
IV.セノタフの 無宗教性 に関する議論と靖国問題
イギリス政府はセノタフを「無宗教」の施設と主張するが、ウェストミンスター・アビーにある無名戦士の墓との関係、そして国民感情を踏まえると、この主張には疑問が残る。議会での議論や国民感情を分析することで、セノタフの真の性格と、その宗教的側面を考察する。 この議論を靖国問題と比較することで、戦没者追悼施設のあり方、国民感情、政治的利用、そして国際的な視点からの問題点を明らかにし、安易な「無宗教」の追悼施設建設が新たな問題を生む可能性を指摘する。
1. セノタフの 無宗教性 に関するイギリス政府の公式見解と批判
イギリス政府は、セノタフを「無宗教」の戦没者追悼記念碑と位置づけています。これは日本政府も同様の認識を持っています。しかし、本文ではこの公式見解に対し、様々な批判が提示されています。セノタフは「礼拝用の墓」としての機能も持ち、実際にはウェストミンスター・アビーの無名戦士の墓とワンセットで機能している点を考慮すると、「無宗教」という政府の主張には疑問が残ります。ウェストミンスター・アビーの無名戦士の墓は英国国教会による祭祀を受けているため、セノタフにも何らかの宗教的要素が潜在的に含まれていると考えるのが自然です。 イギリス議会においても、セノタフの「無宗教性」については議論が展開され、キリスト教的な意匠を加えるべきかという質問に対して、当時のアンドリュー・ボナー・ロウは政府としてそれを認めないという強い姿勢を示しました。しかし、この答弁にもかかわらず、セノタフの無宗教性に対するクレームは繰り返し提出されました。これらの批判は、セノタフの象徴性と、国民の宗教観・歴史認識との複雑な関係性を浮き彫りにしています。
2. イギリス議会での議論 セノタフとキリスト教的意匠
セノタフの「将来、キリスト教の意匠が認められるか」という質問がイギリス議会で提起されました。政府の答弁は、セノタフは「宗教的信条に関わりなく、全ての戦没者を追悼するために建立された」というものでした。この答弁はセノタフの無宗教性を強調していますが、多くのイギリス人が戦没者の祭祀を英国国教会によって執り行われるものとして認識していたという事実を踏まえると、この答弁の背後にある複雑な政治的、宗教的背景を考慮する必要があります。 この議論は、セノタフの建設計画段階から、その「無宗教性」が明確に意識されていたことを示唆する一方、国民感情や宗教的慣習との間で、政府が微妙なバランスを取ろうとしていたことを示唆しています。セノタフが「無宗教」であるという政府見解と、国民感情や伝統的な宗教観との間には、常に緊張関係が存在していたと考えられます。この議会での議論は、セノタフという記念碑が単なる石造物ではなく、国民の記憶と感情、そして国家のアイデンティティに深く関わる複雑な存在であることを示しています。
3. セノタフの 無宗教性 と靖国問題の関連性 比較検討と課題
本稿では、セノタフの「無宗教性」をめぐる議論を、日本の靖国神社問題と比較検討しています。 セノタフは、英国国教会による祭祀を受ける「無名戦士の墓」とワンセットで存在し機能しているにもかかわらず、その重要な側面は軽視され、「無宗教」という側面だけが強調されがちです。 さらに、「無宗教の追悼施設」が靖国問題の「現実的解決策」として提起されている現状も指摘されています。しかし、これは靖国神社の存在や靖国信仰を正面から検討した結果ではなく、いわば「現実的な処方箋」としての提案に過ぎない可能性があります。 筆者は、こうした点を考慮せずに議論を進めることは、結果的に新たな問題、例えば「第二の靖国神社」の創出につながる危険性を指摘しています。 どの記念碑や記念廟も、その性格や祀る対象は常に時の権力によって左右されてきた歴史を持つことを踏まえ、靖国問題を含む、戦没者追悼施設のあり方を慎重に検討する必要性を訴えています。
