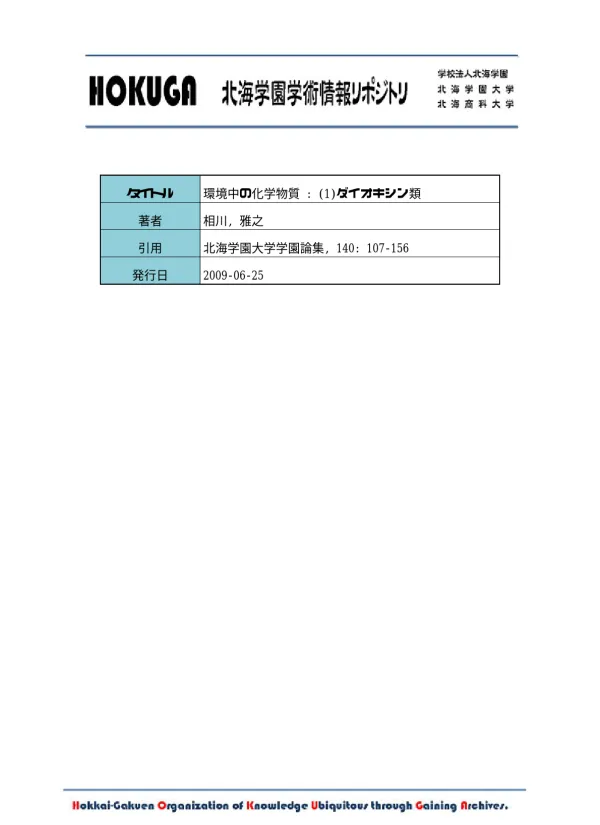
ダイオキシン類:環境汚染と健康リスク
文書情報
| 著者 | 相川雅之 |
| 専攻 | 環境化学 |
| 文書タイプ | 小論 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.69 MB |
概要
I.ダイオキシン類とPCB 歴史的経緯と環境問題
本論文は、ダイオキシン類とPCB(ポリ塩化ビフェニル)による環境汚染と健康影響に関する包括的なレビューです。1940年代から化学プラント作業員における高レベルのダイオキシン類曝露事例が多数発生し、カネミ油症事件(PCB汚染米油による健康被害、被害者2000人以上、台湾でも同様の事件発生)などの歴史的災禍がダイオキシン類の危険性を浮き彫りにしました。現在、主要な発生源はゴミ焼却であり、ダイオキシン類は、大気、土壌、海洋を汚染し、食物連鎖を通じて生物濃縮・生物蓄積され、ヒトを含む生物に深刻な影響を与えています。**残留性有機汚染物質(POPs)**として国際的に規制されており、ストックホルム条約も発効しています。
1. ダイオキシン類の発見と初期の健康被害
1940年代から、特に1950年代以降、除草剤や殺虫剤を製造する化学プラントの作業員の間で、高レベルのダイオキシン類曝露事例が多数発生しました。これらの事例は、ダイオキシン類の毒性に関する初期の知見を提供し、人々にその危険性を認識させるきっかけとなりました。 疫学的追跡調査の結果は、本編の発癌性の項で詳述されるとのことです。 初期段階ではダイオキシン類の危険性に関する知識が不足しており、曝露は非意図的に広がっていきました。このことが、ダイオキシン類の恐ろしさを人々に広く知らしめる結果となりました。 一方で、現代社会におけるダイオキシン類による環境問題は、ゴミ焼却処理という、文明社会の不可欠な過程から発生し、人間自身によって環境中に拡散されているという問題点が指摘されています。 ある地域住民の事例では、ダイオキシン類への曝露後、長期間にわたる追跡調査が行われ、肉腫や癌による死亡との相関関係が示唆されています。ダイオキシン類の高い蓄積性と長い体内滞留時間(体内消失半減期)を考慮すると、曝露量だけでなく、積算曝露量(Cumulative Dose)がより重要な要素となり、長期的な調査が必要であるとされています。
2. 主要なダイオキシン類汚染事件
1980年には、アメリカ合衆国ニューヨーク州ラブキャナル農薬工場の産業廃棄物埋め立て地から高濃度のダイオキシン類が検出され、239家族が立ち退きを余儀なくされました。1983年には、ミズリー州タイムビーチにおいてBliss社がダイオキシン混入廃油をほこり止めとして使用した結果、62頭の馬が死亡し、競馬場のオーナーとその子供たちがインフルエンザ様症状を発症する事件が発生しました。政府はダイオキシン類の被害拡大を防ぐため、町全体を買収し、住民と企業の移転を余儀なくされました。これらの事例はダイオキシン類による環境汚染と健康被害の深刻さを改めて示すものです。日本では、1985年(一部には1983年との記述も)から研究報告が見られるようになり、愛媛大学の研究者らが愛媛県内のゴミ焼却炉の飛灰からポリ塩化ダイオキシン類を検出しました。検出量は欧米とほぼ同レベルでしたが、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-p-ジオキシン(TCDD)の割合が日本の方が高いことが報告され、これは焼却炉の燃焼温度の違いによるものと推測されています。 しかし、日本のゴミ焼却炉からのダイオキシン類検出を最初に報告したのは、皮肉にも日本の研究者ではなく、1979年にカナダの研究グループでした。彼らはGC/MS装置を用いて、日本のゴミ焼却炉の飛灰からポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン類の存在を明らかにしました。
3. PCB汚染とカネミ油症事件
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、ダイオキシン類と共通の毒性を持つ物質で、熱分解しにくく、絶縁媒体や難燃剤として広く使用されてきました。PCBは決して安全な化学物質ではなく、製造工場での作業員に塩素痤瘡(クロロアクネ)の発症や死亡事故が発生しています。また、海外でもPCB漏出事故による環境への影響が報告されています。1968年には日本において、西日本一帯に広がったカネミ油症事件が発生し、皮膚炎、発疹、手足のしびれなどの症状が多数報告され、患者からPCBが検出されました。これはカネミ米油にPCBが混入していたことが原因と判明しました。11年後の1979年には台湾でも同様の事件が発生し、2000人以上が被害を受けました。PCBはダイオキシン類とは異なり、工業用物質(難燃剤)として分類されます。カネミ油症事件を契機に、日本におけるPCB汚染への関心が高まり、1971年以降は開放系の用途での使用が禁止され、1973年には化学物質審査規制法が制定され、製造、輸入、使用が原則禁止されました。しかし、現在でも日本国内には4万8500トンのPCBが保管されていると推定されています。
4. ダイオキシン類対策の現状と課題
2001年5月に採択され、2004年5月に発効した残留性有機汚染化学物質に関するストックホルム条約(POPs条約)は、PCB、DDT、ダイオキシン類などのPOPsの製造・使用の廃絶、排出削減、廃棄物の適正処理などを規定しています。日本は2002年に加盟しています。ダイオキシン類対策特別措置法の施行により、日本のダイオキシン類排出量は減少傾向にありますが、依然としてゴミ焼却が主要な発生源であり、その排出量削減が大きな課題となっています。 特に、小型廃棄物焼却炉や産業廃棄物焼却施設からの排出削減が求められています。 国民の意識向上によるゴミの分別廃棄の推進、焼却炉の技術向上、行政指導の強化などが排出量削減に貢献しているものの、更なる削減に向けた継続的な努力が必要とされています。ダイオキシン類の発生源は多岐にわたり、農薬の副生成物、塩化ビニルの製造過程、製紙工場の排水などからも検出されています。しかし、これまでの環境汚染の主たる原因は、大量生産・大量消費・大量廃棄というライフスタイルにあると指摘されています。日本の狭い国土では、ゴミの焼却が主要な廃棄物処理方法であったため、ダイオキシン類の発生が問題となっています。 近年の10年間で、廃棄物処理分野からのダイオキシン類排出量は大幅に減少していますが、依然として廃棄物処理分野からの排出量は全体の大きな割合を占めており、更なる削減努力が求められています。産業分野からの排出量も無視できない量であるため、継続的な削減への取り組みが重要です。
II.ダイオキシン類の毒性と健康影響
ダイオキシン類、特にTCDD(2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ジオキシン)は、高い毒性を持ちます。その毒性は急性致死毒性だけでなく、催奇形性、発癌性、免疫毒性、生殖毒性など多岐に渡ります。毒性発現メカニズムはアリール炭化水素受容体(AhR)との結合が重要な役割を果たしています。TEF(毒性等価係数)を用いて、様々なダイオキシン類の毒性をTCDDとの比較で評価します。**耐容一日摂取量(TDI)**は、日本において4 pgTEQ/kg/日と設定されていますが、欧米諸国ではこれより低い値が設定されているケースが多いです。
1. ダイオキシン類の毒性と作用機序
ダイオキシン類、特に2,3,7,8-TCDDは非常に強い毒性を持ち、急性致死毒性だけでなく、催奇形性、発癌性、免疫毒性、生殖毒性など、様々な慢性毒性を示します。これらの毒性は、単回または短期間の曝露量だけでなく、血中や体脂肪に蓄積される積算曝露量(Cumulative Dose)に大きく依存します。 mg単位の一時的な高濃度曝露を免れたとしても、ヒトへの無害性を証明するものではなく、慢性毒性への影響は無視できません。ある地域住民の事例では、事故から8年後の調査で住民のダイオキシン類摂取量が8.1 pgTEQ/kg/日と測定され、15年間の追跡調査でダイオキシン類曝露と肉腫や癌による死亡との相関が示唆されています。ダイオキシン類の体内滞留時間が長く、蓄積しやすい性質が、健康への長期的な影響を深刻化させる要因となっています。 毒性発現メカニズムは完全には解明されていませんが、アリール炭化水素受容体(AhR)との結合が重要な役割を担っていると考えられています。 AhRを持たないマウスでは、ダイオキシン類の主要な毒性(肝臓や胸腺への毒性、発生毒性)が観察されないことから、AhRを介した作用が示唆されています。 自然界の毒素とは異なり、ダイオキシン類は合成化学物質であり、ヒトには解毒機構が十分に発達していないため、高い体内蓄積性と有害性が問題となります。ボツリヌス菌毒素など、ダイオキシン類よりはるかに毒性の強い天然物質も存在しますが、異なる性質の毒性物質を単純に比較することは適切ではありません。
2. ダイオキシン類の毒性評価 TEFとTDI
ダイオキシン類は、様々な塩素誘導体や類似化合物が混合物として存在するため、複合毒性の評価が重要になります。そのため、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDの毒性濃度を1(TEF=1)として、他のダイオキシン類の毒性をTCDDに対する相対毒性(毒性等価係数:Toxic Equivalency Factor)で表します。TEFの算出には、in vivoおよびin vitroでの生化学反応試験結果が用いられ、WHOは1990年、1998年、2005年とTEF値を見直しており、今後も新たな科学的知見に基づいて更新されていくでしょう。 耐容一日摂取量(TDI: Tolerable Daily Intake)は、生涯毎日摂取しても健康への有害影響がないとされる1kg体重あたりの摂取量です。日本では4 pg/kg/日と設定されていますが、これは本来混入を望まない環境汚染物質に対する値であり、曝露量は最小限に抑えるべきです。日本のTDI値の妥当性については議論があり、欧米諸国では2 pgTEQ/kg/日以下の値を設定している国が多い中、日本の値はその妥当性について更なる検討が必要とされています。
3. ダイオキシン類の生殖毒性と免疫毒性
ダイオキシン類、特にTCDDは、生殖毒性も示します。動物実験では、TCDD投与により、胚・胎児への影響、出生後の児動物への影響が確認されています。 例えば、妊娠ラットへのTCDD投与によって、子動物の精巣中の精子細胞数の減少、テストステロン濃度低下、精巣組織学的変化などが認められています。低用量でも生殖機能への影響が確認されており、用量依存的な影響が示されています。また、高用量のTCDD連続投与では、マウスの口蓋裂、水腎症、ラットの腎形成異常などの催奇形性が報告されています。妊娠中や授乳期のTCDD曝露は、子の生殖機能、甲状腺機能、免疫機能にも悪影響を及ぼすことが動物実験で示されています。免疫毒性に関しては、動物実験でTCDDによる胸腺萎縮や細胞性・体液性免疫異常が報告されています。マウスの単回投与試験では、低用量でも感染防御機構への影響や抗体生産抑制などがみられ、妊娠マウスへの投与では新生児マウスの胸腺細胞数の変化が観察されています。これらの影響は、単回投与でも100ng/kg以上で認められ、用量依存性が見られます。ヒトに対するTCDDの免疫毒性については、疫学調査でT細胞レベルの変動を示唆する報告があります。
4. ダイオキシン類の感受性 AhRと種差
ダイオキシン類の毒性に対する感受性には、種差や個体差が存在します。ヒトの場合、ダイオキシン-AhR複合体は、AhR核移行分子(Arnt)などの補助因子を必要として核中のDNAに作用します。AhRと類似の分子構造を持つAhRレプレッサー(AhRR)は、慢性的なダイオキシン類曝露によって誘導され、毒性発現を抑制する可能性が示唆されています。AhRRには遺伝的多型が存在し、ある型ではArnt結合能が低いためダイオキシン類に対する感受性が高くなる可能性が示されています。マウスの場合も、AhRのダイオキシン類感受性に系統差があり、感受性の低い系統ではAhRのタンパク質の炭素端末が長く、AhRとの親和性が低下していることが明らかになっています。このことから、マウスにおけるAhRのダイオキシン類感受性は遺伝的多型に依存していると考えられています。ヒトのAhRについても遺伝的多型があることが報告されており、AhRや関連分子の多型により、ヒトでもダイオキシン類感受性に個体差がある可能性が残されています。
III.ダイオキシン類の発癌性
ダイオキシン類の発癌性は、疫学調査(除草剤工場従事者など高レベル曝露事例:アメリカ合衆国、オランダ、ドイツの事例が重要とされています。)と動物実験により裏付けられています。特にTCDDは強い発癌性物質とされており、肝腫瘍、リンパ腫などの発生増加が報告されています。発癌メカニズムは、AhRを介した遺伝子発現の変化と関連しています。**PCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)**についても、発癌性に関するデータが存在しますが、TCDDほど明確な証拠はありません。
1. ヒトにおけるダイオキシン類の発癌性データ
ダイオキシン類、特にTCDDの発癌性を評価するために、高レベル曝露と長期の体内滞留が確認された集団(コホート)を対象とした疫学調査が重要です。IARCは、除草剤製造工場の従事者を対象とした4つの疫学調査(米国、オランダ、ドイツ各1例ずつ)を重要な研究対象として挙げています。これらの調査では、TCDDに高レベルで曝露した化学プラント作業員を長期間追跡し、発癌リスクを評価しています。例えば、米国の一例では、TCDD汚染物質を製造していた12の化学プラントで働いていた5172人の死亡者について20年以上にわたる追跡調査が行われています。ドイツの一例では、1953年の反応塔事故でTCDDに曝露した243人の死亡者について、局外者と比較した調査が行われています。また、別のドイツの例では、PCDD、PCDFなどに汚染された除草剤などを製造していた工場で働いていた1189人の男性労働者を40年間追跡調査し、死亡原因を分析しています。これらの研究は、TCDDへの曝露が最も高かった事例を含んでおり、発癌性評価において重要な情報源となっています。セベソ事件の住民や枯葉剤作戦従事者などは、曝露レベルや追跡期間の観点から、今回の評価対象からは除外されています。
2. 動物実験によるダイオキシン類の発癌性データ
TCDDを投与したラットやマウスの実験では、肝腫瘍の発生増加が雄と雌の両方で確認されています。さらに、甲状腺濾胞細胞腫、リンパ腫、肺胞/気管支の腺腫や癌腫なども増加しており、これらの腫瘍発生の程度は、動物種、性別、TCDDの投与経路によって異なることが示されています。通常の部位以外に、舌、硬口蓋、鼻介などに腫瘍が発生した例もあります。これらの動物実験データから、実験動物におけるTCDDの発癌性については十分な根拠(sufficient evidence)があると結論付けられています。ただし、あるラットで腫瘍が著しく増大した事例において、その体内濃度は高レベル曝露を受けたヒトのそれと同程度であったことから、ヒトへの影響を考える上では注意が必要です。 その他のダイオキシン類、例えば1,2,3,6,7,8-および1,2,3,7,8,9-六塩化ジベンゾ-p-ジオキシンの混合物については、動物実験データに基づき、発癌性については限定的な根拠(limited evidence)があると判断されています。同様に、2,7-二塩化-などの発癌性についても、限られたデータに基づいた評価となっています。
3. ダイオキシン類の発癌メカニズム
TCDDの投与は、細胞増殖、細胞の異常形成、腫瘍の成長という段階を経て発癌に繋がると考えられています。しかし、短期間の実験では、腫瘍のどのプロセスにどの程度の曝露量が影響を与えているのかを明確に特定することは困難です。細胞成長における恒常性の変化は、腫瘍プロモーション過程において、アポトーシス、成長因子の発現、成長因子と核内ホルモン受容体レベルの変化と関連していると考えられています。TCDDの最初の作用は、遺伝子への直接的な働きかけではなく、細胞内アリール炭化水素受容体(AhR)との結合によるものと考えられています。遺伝的に異なるマウスを用いた実験では、TCDDや他のPCDD同族体の毒性がAhRとの結合能力に依存していることが示されています。2,3,7,8-TCDD、1,2,3,7,8-五塩化ジベンゾフラン、2,3,4,7,8-五塩化ジベンゾフランは、TCDDと同程度のAhR結合能を示しています。TCDDの発癌性のほとんどが、AhRとの初期の強い親和性から生じているとすれば、PCDF曝露による生化学的・毒性学的現象もTCDDと同様の作用機序で発生すると考えられます。また、限られたデータではありますが、TCDD同族体の発癌性はAhR親和性に比例する傾向を示しており、PCDD類とPCDF類は全てAhRとの初期結合から発癌に至る同じメカニズムで作用すると考えられています。しかし、TCDDによる発癌メカニズムにおいて、どの応答遺伝子が決定的な役割を果たすかは、現時点では明らかにされていません。AhRは、ヒトと実験動物の両方で高度に保存されている受容体です。
4. PCDF類の発癌性に関する考察
PCDF類の発癌性に関するヒトのデータは限定的です。セベソ事件の住民集団はよく知られていますが、曝露レベルが低く、追跡期間も短かったため、今回の評価では除外されました。 台湾での12年間の追跡調査では、肝癌の死亡者数の増加は認められませんでした。これらのデータに基づき、PCDF類のヒトに対する発癌性については、不十分な根拠があると評価されています。動物実験においても、PCDF類の長期的な発癌性に関する研究は不足しています。短期間の実験では、2,3,7,8-四塩化ジベンゾフランの発癌性については不十分な根拠、2,3,4,7,8-五塩化ジベンゾフランと1,2,3,4,7,8-六塩化ジベンゾフランについては限定的な根拠があると判断されています。
IV.ダイオキシン類の環境中拡散と対策
ダイオキシン類は、主にゴミ焼却からの排出によって大気汚染を引き起こし、その後、土壌や水系を汚染します。生物濃縮と生物蓄積により、食物連鎖の頂点にいるヒトにまで影響が及ぶため、地球規模での海洋汚染も懸念されています。対策としては、ゴミ焼却炉の改善(完全燃焼のための高温維持、高度な集塵)、ゴミの減量化・資源化、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制強化などが挙げられます。POPs条約に基づく国際的な取り組みも重要です。日本においては、ダイオキシン類対策特別措置法の施行により、排出基準の規制強化が図られていますが、小型廃棄物焼却炉や産業廃棄物焼却施設からの排出削減が課題となっています。
1. ダイオキシン類の環境中拡散 一次的拡散
ダイオキシン類は、主に廃棄物処理施設、特にゴミ焼却施設から排出されます。焼却炉から排出される煤煙や飛灰に付着したダイオキシン類は、大気汚染の主要因となります。粒子の大きさによって拡散範囲が異なり、大きな粒子は焼却炉周辺に沈着し土壌汚染を引き起こします。一方、小さな粒子は上昇気流や風に乗って広範囲に拡散し、風向や地形の影響を受けます。このように、煤煙、飛灰、粉塵などを介したダイオキシン類の広範囲への拡散は一次的拡散と呼ばれます。 牛乳からも高濃度のダイオキシン類が検出されており、これは大気からの降下や飼料汚染などによるものと考えられます。水系においては、ダイオキシン類は懸濁物や微粒子に付着して河川を流れ、河口に到達します。 河口ではバクテリア、植物プランクトン、動物プランクトンなどに吸収され、食物連鎖を通じてアミ、小魚、イワシ、サバといった魚類に蓄積され、最終的に鳥類やヒトにまで到達します。 日本の沿岸部では、イボ貝や黒松の若葉にダイオキシン類が検出されており、大気、土壌、海洋の広範囲にわたる汚染が示唆されています。
2. ダイオキシン類の環境中拡散 二次的拡散と海洋汚染
ダイオキシン類は、一次的拡散後、食物連鎖を通じて生態系全体に広がっていきます。これは二次的拡散と呼ばれ、海洋環境においても顕著です。河口で微生物やプランクトンに取り込まれたダイオキシン類は、食物連鎖を介して魚類に蓄積し、さらにそれを捕食する鳥類や海洋哺乳類に高濃度で蓄積されます。 鯨類は海洋における食物連鎖の頂点に位置しており、北太平洋産ミンク鯨、日本近海の歯鯨類、南オーストラリア沖のマッコウ鯨など、様々な鯨類の脂肪や肝臓組織から高濃度のダイオキシン類が検出されています。アザラシやイルカの大量死事例もあり、PCBなどとの関連が疑われています。 このように、ダイオキシン類は、大気、土壌、水系、そして食物連鎖を介して、地球規模で拡散し、海洋汚染も深刻な問題となっています。ヒトがダイオキシン類を発生させる限り、海洋におけるダイオキシン類濃度は増加し続け、汚染は拡大し続けるでしょう。 日本の沿岸部全域において、イボ貝や黒松の若葉からダイオキシン類が検出されているという報告があり、日本の広範囲にわたる汚染の現状を示しています。
3. ダイオキシン類対策 法規制と排出量削減
ダイオキシン類対策として、ダイオキシン類対策特別措置法が2001年に施行されました。この法律により、環境庁(当時)と厚生省(当時)が個別に定めていた基準値が統一され、TDI値(耐容一日摂取量)が4 pgTEQ/kg/日に設定されました。この法律は、ダイオキシン類に対する日本の国家としての姿勢を示す重要な一歩ですが、TDI値の妥当性については当初から議論がありました。2002年の厚生労働省の報告書では、4 pgTEQ/kg/日を変更する十分な科学的根拠がないと結論付けられていますが、欧米諸国では2 pgTEQ/kg/日以下の値を設定している国が多い点が課題として挙げられます。 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、排出基準が強化され、ゴミ焼却施設の改善、焼却技術の向上、集塵器の増設などが進められています。これにより、日本のダイオキシン類排出量は減少傾向にありますが、特に小型廃棄物焼却炉や産業廃棄物焼却施設からの排出削減が今後の課題となっています。 ゴミ焼却以外に、ダイオキシン類は農薬、塩化ビニルの製造過程、パルプの塩素漂白過程などでも生成することが報告されていますが、これまでの環境汚染の主たる原因はゴミ焼却であると理解されています。近年の10年間で、廃棄物処理分野からのダイオキシン類排出量は大幅に減少していますが、依然として廃棄物処理分野からの排出が全体の大きな割合を占めており、更なる削減に向けた取り組みが重要です。
4. ダイオキシン類排出削減のための具体的対策
廃棄物焼却炉からのダイオキシン類排出抑制のためには、ゴミの減量化が最も重要です。これは、私たちのライフスタイルを変えることを意味します。 過去20年以上にわたるゴミの分別回収の推進は、ダイオキシン類発生量の大幅な削減に貢献していますが、更なる削減のためには、ゴミの再資源化・減容化、残渣の無害化処理といった焼却以外の廃棄物処理方法の検討も必要です。 ゴミ焼却においては、完全燃焼(800℃以上、できれば1100℃以上)を目指し、焼却炉の雰囲気制御が重要です。排出基準の強化に伴い、焼却施設の改善、焼却技術の向上、集塵器の増設などが行われていますが、更なる削減のためには、燃焼廃ガスの冷却過程におけるダイオキシン類の再生成抑制、燃焼ガス処理工程でのダイオキシン類除去対策(低温化、高度な煤塵除去フィルター導入など)が求められています。 特に、小型廃棄物焼却炉や産業廃棄物焼却施設からの排出削減に重点を置いた取り組みが必要であり、廃棄物処理分野におけるダイオキシン類排出量のさらなる削減の可能性は高いと判断されます。産業分野からの排出量も無視できない量であるため、継続的な努力が不可欠です。1992年のUNCEDで規制の重要性が指摘され、2001年に採択されたストックホルム条約(POPs条約)に基づく国際的な協調も重要です。
