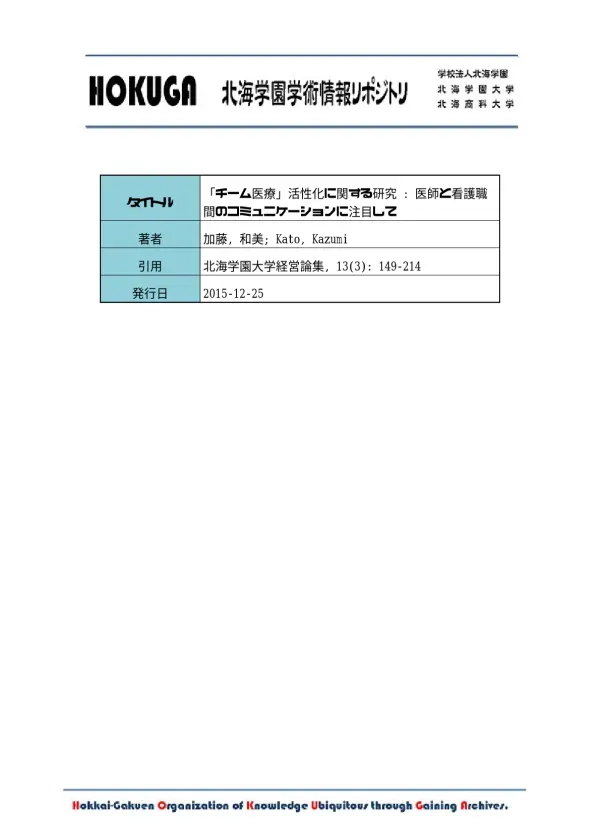
チーム医療活性化:医師・看護師間のコミュニケーションに着目
文書情報
| 著者 | 加藤 和美 |
| 専攻 | 医学、看護学関連 |
| 文書タイプ | 研究論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.71 MB |
概要
I.医療事故とチーム医療の機能不全
本論文は、医療事故、特に患者取り違え事故を契機に、日本の病院におけるチーム医療の機能不全問題を考察する。チーム医療において、階層意識がコミュニケーション障害を引き起こし、患者不利益につながるという問題意識が中心となっている。2010年の厚生労働省の報告書なども参照しながら、この問題の現状と原因究明を試みている。
1. 医療事故事例と研究の動機
論文は、患者の取り違えという医療事故から始まる。2人の患者を1人の看護師が同時に手術室へ搬送した際、カルテと患者が取り違えられ、異なる手術室へ送られたという事例が紹介されている。この事故には医師・看護師26名が関与しており、チーム医療の機能不全が明確に示された。この事例を契機に、チーム医療における機能不全の原因究明、特に階層意識と患者への不利益の関連性を明らかにすることが研究の動機となっている。2010年の厚生労働省の取り組みも背景に、継続的に発生するチーム医療の機能不全の原因解明を目指す点が強調されている。 医療の安全性が叫ばれ、細心の注意が払われているにもかかわらず、事故は発生しており、その原因究明の必要性が強く訴えられている。
2. チーム医療と組織論的視点
Mintzberg(1991)の総合病院を専門職業的組織とする分類や、Max Weberの官僚制モデル(規則と権限、階層性・職務体系、分業・専門化)が紹介されている。しかし、チーム医療はこれらのモデルとは異なる独自の特性を持つと指摘。医師はチーム医療における階層意識を当然のこととして行動する一方、看護師は階層意識から主体的発言や行動を抑制してしまう可能性が示唆されている。医師の強い専門的権威が看護師の行動を制限し、コミュニケーション不足、ひいては患者への不利益につながる可能性が、本研究の主要な問題意識として提示されている。厚生労働省の平成23年度チーム医療実証事業報告書(2011)も引用され、チーム医療の在り方は各医療機関の状況によって異なるため、現場に応じた取り組みが必要であるとされている。
3.先行研究と本研究の位置づけ
既存の研究では、チーム医療における階層意識と患者への不利益の関連性を十分に調査したものが不足しているため、本研究は質問紙調査と先行研究のレビューを通して、この問題に取り組む。 先行研究として、コミュニケーションエラーの要因分析(嶋森ら、2003)、医師を頂点とした支配・被支配関係によるチームワークの困難さ(加部、2004)、医師と看護師の関係における協働条件の検討(中川ら、2008)、地位格差とコミュニケーションの問題(大坪ら、2003)などが挙げられる。これらの研究は、チーム医療における階層意識、コミュニケーション障害、そして患者への不利益という問題の存在を裏付ける重要な資料として位置づけられている。しかしながら、これらの先行研究は、チーム医療全体を捉えきれていない、階層意識に踏み込んでいない、など、本研究が取り組む課題の不足を補うものであると説明している。
4. チーム医療の現状と課題 医師と看護師の関係
長らくチーム医療は医師を頂点とした支配・被支配関係として認識されてきた。医師の指示権限の強さが、対等な参加による機能的なチームワークを阻害してきたと指摘。聖路加国際病院院長石川の意見も引用され、医師とスタッフが主従関係だとチーム機能は発揮されないとの見解が示されている。チーム医療推進の阻害要因として、医師中心の考え方をクライアント中心に変換できない点も指摘。また、主治医制による共同意思決定の困難さ、経験重視の判断、医師間の思考様式の継承などが、チーム医療推進の妨げとなる可能性も示唆。さらに、チーム医療の用語が使用され始めた経緯(1974年、日比)や、医師と看護師のコミュニケーションにおける支配・被支配関係の歴史的背景(日比)も説明されている。
II.医師と看護師間の階層意識とコミュニケーション
医師と看護師間の階層意識は、チーム医療の大きな阻害要因として指摘されている。医師の強い権威と看護師の受動的な姿勢が、情報共有不足や意思決定の遅れを招き、ひいては医療事故のリスクを高める。Mintzberg (1991)の専門職業的組織論やWeberの官僚制モデルを踏まえつつ、日本の医療現場における医師中心の縦型組織構造が問題の本質を深く掘り下げている。
1. 階層意識の存在とコミュニケーション障害
本論文の中心テーマは、日本の医療現場における医師と看護師間の階層意識がコミュニケーション障害を引き起こし、ひいてはチーム医療の機能不全、患者への不利益に繋がっているという点である。医師はチーム医療における階層構造を当然のこととして捉え、行動する。一方、看護師は、その階層意識から、対等な立場で意見を述べたり、主体的行動をとることが抑制されていると分析されている。この階層構造は、医師の高い職業権威に起因する支配的な関係性を生み出し、情報伝達や意思決定のプロセスに支障をきたす。結果として、患者にとって不利益な状況が発生する可能性が高いと指摘されている。この問題意識は、患者取り違え事故などの医療事故を契機に生まれたものであり、医療安全という観点からも極めて重要な問題であると位置付けられている。
2. 組織構造とコミュニケーションの阻害要因
医師と看護師間のコミュニケーション障害は、組織構造と深く関連している。Mintzberg(1991)の専門職業的組織論やMax Weberの官僚制モデルを参考に、日本の医療現場の組織構造が分析されている。医師は複数の準拠集団(医師会、大学医局、専門医学会など)に属し、強い権威を持つ。この構造は、医師間の階層化をもたらし、看護師とのコミュニケーションを困難にしている。特に私立病院では医師の資本所有者的な支配が組織形態を強く規定しており、縦型の組織構造が依然として多く見られる(石原、1980)。ライン・スタッフ組織も紹介されており、専門化による部門間の葛藤や対立、委員会の細分化による日常業務への圧迫などが問題点として挙げられている。 これらの組織構造が、医師と看護師間の非対称的な力関係を強め、コミュニケーションを阻害していることが分析されている。
3. フォーマル インフォーマルなコミュニケーション
医師と看護師間のコミュニケーションには、フォーマルな方法(カンファレンス、指示、連絡、記録、相談、報告など)と、インフォーマルな方法(暗黙の了解や、ベテラン看護師の若手医師への助言など)が存在する。フォーマルなコミュニケーションは、電子カルテシステムなどの情報共有ツールによって効率化できる可能性がある一方、従来の紙カルテでは情報共有に課題があると指摘。インフォーマルなコミュニケーションは、ベテラン看護師が若手医師に助言する際に観察されるが、このプロセスにおいても、階層意識が影響し、円滑な情報伝達が妨げられる可能性がある。 これらのコミュニケーション方法の有効性と課題を、特に階層意識という観点から分析することで、チーム医療におけるコミュニケーション改善への糸口を探っている。
4. チーム医療におけるコミュニケーションの現状と課題
チーム医療の推進に関わらず、医師と看護師間のコミュニケーション障害は依然として存在する。質問紙調査の結果、医師は「誰とでも気軽に話ができる」「協力し合っている」と感じている一方、看護師は「話をしようとしてもできない同僚がいる」「チーム内で相談しにくいと感じている人がいる」と回答しており、階層意識が問題として浮き彫りになっている。しかし、この階層意識は主観的なものであり、客観的な尺度が不足していることも指摘されている。 論文では、医師と看護師のコミュニケーションを円滑にするための具体的な方策が議論されている訳ではないが、チーム医療におけるコミュニケーションの現状と課題を明確に示し、今後の研究の方向性を示唆している。
III.チーム医療における情報共有と責任の所在
効果的なチーム医療には、情報共有と責任の所在の明確化が不可欠である。しかし、多くの病院では、紙媒体のカルテを使用しており、情報共有に課題がある。また、専門性の細分化により、責任の所在が曖昧になるケースも指摘されている。電子カルテ化などの情報システムの導入の必要性、及びチームにおける個人責任と連帯責任の明確化が求められる。
1. 情報共有の現状と課題 紙カルテと電子カルテ
チーム医療における情報共有の現状と課題が論じられている。多くの医療機関では、未だに紙カルテが使用されており、部門間の情報共有が困難な状況にあることが指摘されている。これに対し、国公立病院などでは電子カルテの導入が進み、多職種が容易に情報にアクセスできる環境が構築されている。電子カルテ化は情報共有の迅速化、正確性の向上に繋がる反面、紙カルテを使用する病院では、情報伝達の遅延やミスが発生しやすく、医療の質や安全に影響を与えている可能性が示唆されている。 特に、患者の情報は複数の医療従事者によって共有される必要があるため、情報共有システムの整備がチーム医療の質を大きく左右する重要な要素であることが強調されている。
2. 責任の所在の曖昧さとチーム医療の機能不全
専門分野の細分化に伴い、チーム医療における責任の所在が曖昧になっている点が問題視されている。問題発生時の責任が明確でないこと、専門知識が増える一方で、それらを統合する役割が明確でないことが、チーム医療の機能不全につながる可能性があると指摘されている。Katzenbachら(2004)のチームにおける個人責任と連帯責任の概念が紹介され、チーム医療においてもこれらの責任を明確にする必要があると主張。 責任の所在が曖昧な状態では、迅速かつ的確な意思決定や問題解決が困難になり、患者への不利益につながる可能性が高いとされている。チーム医療の機能を向上させるためには、責任分担の明確化と、それを支える組織的な仕組み作りが重要であることが強調されている。
3. 質問紙調査による情報共有と責任に関する認識
チーム医療を推進している病院における質問紙調査の結果が示されている。医師と看護師の両方から、チーム医療の機能に影響を与える要因として、「メンバー全員の情報共有」「十分なコミュニケーション」「個々の意見を互いに尊重し合う」ことが挙げられている。医師はチーム医療が機能していると回答する割合が高い一方、看護師はその割合が低く、その差が階層意識を示唆している。また、「話をしようとしてもできない同僚がいる」「チーム内で相談しにくいと感じている人がいる」という看護師の回答は、情報共有や意思決定における困難さを示唆している。この調査結果から、チーム医療においては、情報共有と責任分担に関する共通認識の不足が、機能不全の一因であることが示唆されている。
IV.質問紙調査と先行研究の分析
本研究では、チーム医療を推進している病院を対象に看護師を対象とした2回の質問紙調査を実施。その結果、多くの看護師が階層意識を感じており、それがチーム医療の機能不全に繋がっていることが示された。先行研究(嶋森ら(2003)、鷹野(2003)、加部(2004)、中川ら(2008)、大坪ら(2003)など)も参考に、医師と看護師間のコミュニケーション障害と患者不利益の関連性を分析している。 調査対象施設は、チーム医療を病院理念に掲げている施設に限定している。
1. 先行研究のレビュー
本研究は、チーム医療における階層意識と患者への不利益の関連性を明らかにするために、先行研究のレビューを行っている。嶋森ら(2003)のコミュニケーションエラーに関する研究、鷹野(2003)によるチーム医療におけるセクショナリズムと階層性の指摘、加部(2004)の医師中心の医療体制の問題点の指摘、中川ら(2008)の医師と看護師の協働条件に関する研究、大坪ら(2003)の地位格差とコミュニケーションに関する研究などが挙げられている。これらの研究は、チーム医療におけるコミュニケーション障害、階層意識の存在、そして患者への潜在的なリスクを明らかにする上で重要な示唆を与えているものの、階層意識と患者への不利益の関連性については、十分な調査がなされていない点を本研究は問題視している。
2. 質問紙調査の実施と対象施設
チーム医療における階層意識の実態を把握するために、質問紙調査が実施された。調査対象は、チーム医療を病院理念または看護部理念に掲げている施設、あるいは附属大学でチーム医療の教育・訓練プログラムを取り入れている施設に限定されている。これは、チーム医療の目的を理解し、実践している病院組織の現状を分析することで、推進に向けた指針を得るためである。調査は2回実施され、2施設156名の看護師から回答が得られた。 調査対象を限定することで、チーム医療に対する共通認識の程度が高いと考えられる集団を対象とし、より信頼性の高い結果を得ようとしている点が示されている。
3. 質問紙調査の結果と考察 階層意識と機能不全
2回の質問紙調査の結果、多くの看護師が階層意識を感じており、その結果としてチーム医療の機能不全が生じていることが示された。1回目の調査では2割、2回目の調査では5割の看護師が階層意識を認め、そのうち半数が機能不全を認めているという結果になった。チーム医療を推進している病院においても、このような結果が得られたことは、階層意識がチーム医療の機能に大きな影響を与えていることを示唆している。 また、調査結果からは、階層意識を感じながらも、プロフェッショナルとして最善を尽くそうとする看護師の存在も明らかになっている。このことは、階層意識の問題は、単純な意識改革だけで解決できるものではなく、より複雑な要因が絡んでいる可能性を示唆している。
4. 調査結果のまとめと今後の課題
質問紙調査と文献研究から、チーム医療の機能不全は、階層意識による看護師の自律性阻害、情報伝達の不足が原因であることが明らかになった。厚生労働省がチーム医療を推進しているにも関わらず、階層意識の問題は依然として存在し、患者の不利益につながっている。特に、医師と看護師間のコミュニケーション不足が大きな問題点として挙げられている。 2回の調査で得られた結果(1回目2割、2回目5割の看護師が階層意識を認め、その半数が機能不全を認めている)は、チーム医療推進施設においても階層意識が依然として問題であることを示唆しており、二重権限構造の強さが機能不全に繋がっている可能性が示唆されている。今後の研究では、今回調査した施設以外の状況についても調査する必要があるとしている。
V.結論 階層意識とチーム医療の機能不全
本研究の結論として、日本の病院におけるチーム医療の機能不全は、医師と看護師間の階層意識に起因するコミュニケーション障害が主な原因であると結論づけている。階層意識は、看護師の自律性を阻害し、必要な情報共有を妨げ、最終的に患者不利益をもたらす。チーム医療の更なる推進のためには、階層意識の解消に向けた具体的な対策が必要不可欠であると述べている。調査では、2施設156名の看護師からの協力を得ている。
1. 研究の結論 階層意識とチーム医療機能不全の関係
本研究は、文献調査と2回の質問紙調査(2施設156名の看護師を対象)の結果から、チーム医療の機能不全は、医師と看護師間の階層意識に起因するコミュニケーション障害が主要因であると結論付けている。この階層意識は、看護師の専門的自主性を阻害し、必要な情報伝達を妨げ、最終的に患者への不利益をもたらす。厚生労働省によるチーム医療の推進にも関わらず、病院理念にチーム医療を掲げる施設においても、医師と看護師間の階層性問題は依然として存在し、コミュニケーション不足と患者への不利益が継続している実態が明らかになった。特に、調査結果からは、チーム医療推進施設においても、回答者の2割から5割の看護師が階層意識を認識しており、その半数が機能不全を認めているという事実は、この問題の深刻さを示している。
2. 階層意識の影響 看護師の自律性と情報伝達
階層意識は、看護師の自律性を阻害する主要な要因として特定されている。医師と対等な立場で議論することが少ない、医師の強い意見に押さえ込まれる、威圧的な態度により意見を言いづらい、といった状況が報告されている。これらの状況は、情報伝達を妨げ、チーム医療全体の機能不全に繋がっている。 必要な情報のコミュニケーションが不足することで、チーム医療が本来目指す患者中心の医療提供、迅速かつ的確な意思決定、そして効率的な業務遂行といった目標達成が阻害されている。この結果、患者にとって不利益となる様々な状況が生じている可能性が高いと指摘されている。
3. 今後の課題と展望
本研究は、階層意識がチーム医療の機能不全に与える影響を明らかにしたものの、その解消に向けた具体的な方策については、今後の研究課題として残されている。今回の調査結果を踏まえ、より広範な医療機関での調査や、階層意識の程度を客観的に測定できる尺度の開発が必要だとされている。また、階層意識を解消するための組織的な工夫や仕組みの構築についても検討が必要であると示唆されている。 さらに、医師と看護師間のコミュニケーションを改善するための具体的な方法や、責任分担の明確化、情報共有システムの改善といった、チーム医療の質向上に向けた多角的なアプローチが必要とされている。
