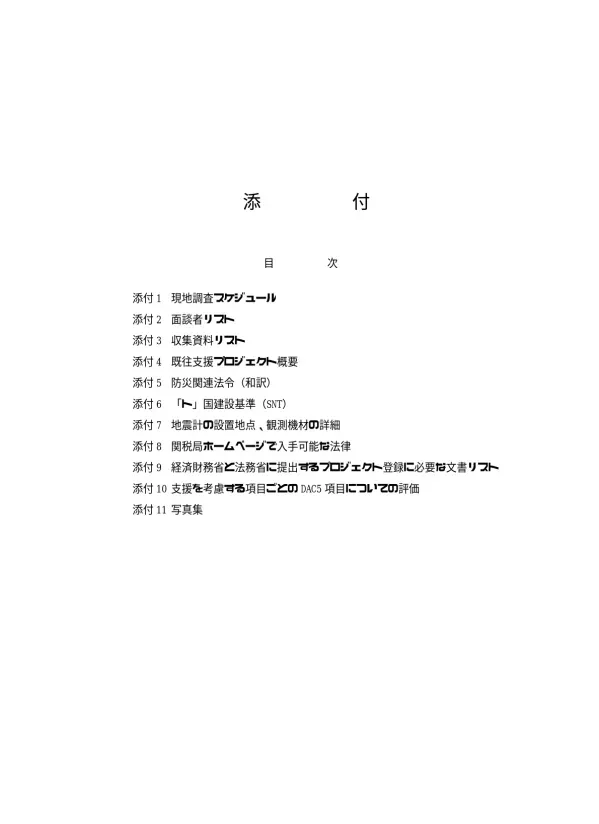
トルクメニスタン地震防災調査:現地調査スケジュール
文書情報
| 著者 | 日本工営(株) |
| 会社 | 日本工営(株) |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.78 MB |
概要
I.トルコにおける地震防災センタープロジェクト
1993年から2000年にかけて実施された日本政府による技術協力プロジェクト。地震防災を目的とした強震観測網実験サブセンター(EDCVE)と地震工学実験サブセンター(EER)が設立され、強震観測システムの構築と耐震設計に関する技術支援が行われた。EDCVEでは、北アナトリア断層近傍を含む地域に9箇所の観測点を設置。地震パラメータの把握と地震直後の被害予測、信頼性の高いデータ伝送を実現した。強震計はアナログタイプ67台、デジタルタイプ59台が導入され、特に地震多発地域にはデジタルタイプが優先的に設置された。 プロジェクトには長期専門家2名、短期専門家計57名が派遣され、機材供与総額は4億9142万9000円であった。
1. プロジェクト概要
本プロジェクトは、日本政府の技術協力の一環として1993年3月から2000年3月まで実施されました。トルコ公共事業住宅省災害総局(GDDA)とイスタンブール工科大学をカウンターパートとして、地震防災研究センターの設立が目的でした。具体的には、アンカラのGDDA地震研究部に強震観測網実験サブセンター(EDCVE)を設置し、強震記録の収集と被災規模の推定を行うシステムを構築しました。1997年から稼働を開始し、地震データの収集と分析を行っています。 さらに、イスタンブール工科大学には、耐震設計や動土質試験を行うための地震工学実験サブセンター(EER)が設置されました。EDCVEとEERにはそれぞれ8名のカウンターパートが配置され、日本側は長期専門家と短期専門家を派遣して技術指導にあたりました。EDCVEへの機材供与額は1億9954万1000円、EERへの機材供与額は2億918万8000円でした。このプロジェクトは、トルコの国家防災行政を支援するための重要な取り組みでした。
2. 強震観測体制
トルコ中北部の北アナトリア断層近傍を含む黒海沿岸地域に9箇所の観測点を設置しました。地震発生と同時に、アンカラ中央センターとサムソン地域センターで観測記録の一括受信、地震パラメータの算定、被災規模の推定を自動的に行うパイロットシステムを構築しました。EDCVEサブセンターのプロジェクト目標は、地震パラメータの把握と地震直後の被害予測、そして主要地域間の信頼できるデータ伝送の提供でした。観測期間中、リーダー1名、業務調整員1名を含む長期専門家と、EDCVEには1994年以降1名の長期専門家と延べ44名の短期専門家、EERには1996年に1名、1997年以降2名の長期専門家と延べ13名の短期専門家が派遣されました。これらの専門家は、地震観測システムの構築と運用、データ解析、技術指導など、幅広い業務に従事しました。観測機材はアナログタイプ67台、デジタルタイプ59台で構成され、地震多発地域であるトルコ東部にはデジタルタイプの強震計が優先的に設置されました。これは、モデムを利用した定期的な状態確認による観測態勢の維持と迅速なデータ収集を目的としています。
3. 強震観測システム
EDCVEシステムの各観測点では、センサーに東京測振製のVSE-355JE、記録装置に東京測振製のSAMTAC-16Xを使用しました。収集された強震記録はウェブサイトで公開され、誰でもアクセスできるようになっています。このシステムは、地震発生時のリアルタイムなデータ取得と迅速な情報伝達を可能にし、地震防災対策の迅速化に大きく貢献しました。強震計の設置やデータ収集、解析方法といった技術は、カウンターパートであるトルコ側の担当者にしっかりと移転されました。プロジェクト終了後も、トルコ側は、導入された先進的な設備を用いて地震データの収集と分析を継続しています。このプロジェクトは、地震観測技術の高度化と人材育成において大きな成功を収めたと言えるでしょう。収集されたデータは、地震研究や防災計画策定に活用され、トルコの地震防災体制強化に貢献しています。
II.カザフスタン アルマティ市における地震防災プロジェクト
2000年から2003年にかけて実施されたJICA技術協力プロジェクト。地震リスク評価とモニタリング向上を目指し、国立地震研究所と協力。強震観測、高感度地震観測、GPS観測に関する機材を供与し、データ収集・解析能力の向上を支援した。機材供与額は1億1679万792円。デジタルデータ収集、高度なデータ解析手法、GPS観測網構築に向けた体制整備を支援。プロジェクトにより、地震観測能力、データ処理能力が大幅に向上した。
1. プロジェクト概要
JICA技術協力プロジェクト「アルマティ市における地震防災及び地震リスク評価に関するモニタリング向上」は、2000年3月から2003年2月までの3年間、カザフスタン国立地震研究所と共同で実施されました。このプロジェクトの目的は、アルマティ市の地震防災と地震リスク評価に関するモニタリング能力の向上でした。プロジェクト期間中、日本側は2名の長期専門家と9名の短期専門家を派遣し、カザフスタン側には各専門家につき1名のカウンターパートが配置されました。さらに、9名の研修生が日本へ派遣され、研修を受けました。機材供与額は1億1679万792円でした。このプロジェクトは、地震観測能力の向上と地震リスク評価の精度向上を目指した重要な取り組みでした。特に、デジタルデータの活用による高度な解析技術の導入が大きな成果として挙げられます。
2. 供与機材とデータ収集
プロジェクトでは、アルマティ市内の観測点でデジタルデータの収集を行うための機材が供与されました。データ収集は通常、月に1~2回人力で行われ、有感地震発生時には担当者が即時にデータ収集を開始します。技術スタッフは記録システムの故障対応もできる体制が整えられました。収集されたデジタルデータは、導入されたソフトウェアを用いて高度な解析が行われます。これにより、従来のアナログ記録方式では困難であった応答スペクトルやフーリエスペクトルなどの解析が可能となり、地震現象のより詳細な理解が可能となりました。このデジタル化と高度な解析手法の導入は、地震研究の質を飛躍的に向上させるものでした。また、このプロジェクトでは、地震観測データの効率的な収集と解析手法の習得が、カザフスタン側の研究者にとって大きな成果となりました。
3. 強震観測 高感度地震観測 GPS観測
強震観測分野では、デジタル式記録システムの導入により、強震記録の分解能と精度が大幅に向上しました。以前の感光フィルムによる記録システムと比較して、データの精度と詳細さが格段に向上し、より精密な地震波形データの取得が可能になりました。高感度地震観測機材の設置により、遠方の地震についても観測能力が向上し、地震波の相の識別、到達時間、振幅の読み取り精度が向上しました。震源計算プログラムの導入もデータ処理能力の向上に貢献しました。GPS観測では、カザフスタン側の研究者はGPS受信機の操作とデータ取得を自立的に行えるようになり、アルマティ周辺の地域的観測網構築計画も作成されました。これらの観測データは、地震リスク評価や地殻変動の研究に役立てられ、地震防災対策の精度向上に貢献しています。ただし、発震機構解を求めるためには、より多くの観測点が必要であり、今後の課題として挙げられています。
III.ルーマニア地震災害軽減計画プロジェクト
2002年から2007年にかけて実施されたJICA技術協力プロジェクト。地震災害軽減センター(NCSRR)を中心に、耐震構造、強震観測、土質調査、市民啓発の4分野で活動。ブカレスト建設技術大学(UTCB)の18名をカウンターパートとして、耐震設計基準、耐震診断・補強基準の策定と教育を実施。構造実験装置、強震計、地盤調査機器などの機材供与を行い、合計8億2700万円の予算が投じられた。ブカレスト市内に強震計設置、地震防災教育も実施した。
1. プロジェクト概要
JICA技術協力プロジェクト「ルーマニア地震災害軽減計画」は、2002年10月から2007年9月までの5年間、ルーマニアの運輸建設観光省(MTCT)の下に新設された地震災害軽減センター(NCSRR)を中心に実施されました。 (独)建築研究所と国総研が、「耐震構造」、「強震観測」、「土質調査」、「市民啓発」の4分野で活動し、NCSRRのカウンターパート(C/P)はブカレスト建設技術大学(UTCB)の教員を含む18名でした。プロジェクト期間中には、ルーマニアの大学や研究機関から29名の研究員が日本へ研修に訪れ、日本からも7名の長期専門家と37名の短期専門家がルーマニアへ派遣されました。日本のマニュアルを基に、ルーマニア独自の耐震設計基準と耐震診断・補強基準が作成され、教育プログラムも実施されました。構造実験、強震計設置、土質試験などに関連する費用は2億6000万円、JICAプロジェクト全体の総額は8億2700万円にのぼりました。このプロジェクトは、ルーマニアの地震防災能力の向上に大きく貢献しました。
2. 耐震補強 耐震設計
耐震設計と耐震補強に関する技術支援が行われ、構造実験装置として水平ジャッキ2台と軸力用ジャッキ1台からなるシステムが供与されました。RC造柱に対する鉄板補強、RC補強、炭素繊維シート補強などの実験を行い、耐震補強方法に関する知見が蓄積されました。1940年以前と1960年以降に建設された耐震性の低い集合住宅2棟を選定し、耐震診断・耐震補強規準案に基づいた耐震補強設計を実施しました。これは、規準案の妥当性を検証するための重要な取り組みであり、ルーマニアへの技術移転の集大成と言える成果です。これらの活動を通して、ルーマニアにおける既存建物の耐震化に関する技術水準の向上に大きく貢献しました。 特に、集合住宅の耐震補強設計は、多くの住民の安全に関わる重要な課題への対応として、大きな意義を持っています。
3. 強震計関連及び地盤試験 土質試験
2003年にはブカレスト市に地表面型と160mのボーリング孔型強震計が設置されました。ブカレスト市と地震発生地点ブランチア方向に距離減衰式を求めるため、計6カ所に設置されました。2006年と2007年にはIA-1地震計が2カ所に追加設置されました。これらの強震計は、建築構造物の地震観測にも用いられました。地盤調査・土質試験関連の機材として、PS検層、常時微動計測装置(単独とアレー観測)、ボーリングマシン、標準貫入試験機、室内3軸圧縮試験機、動的3軸試験機などが供与されました。これらの機材は、地震時の地盤挙動の把握、地震動の特性解明、耐震設計に必要な地盤情報の取得に活用されました。これらの観測データと土質試験データは、地震防災対策において、より精度の高い地震リスク評価を行うための基礎データとして活用されています。
4. 地震防災教育 市民啓発
建物の耐震補強を進めるためには、住民の理解と協力を得ることが不可欠です。そのため、市民向けの地震防災教育・啓発活動が実施されました。地震の怖さや地震対策の重要性を伝える市民セミナーが「ぶるぶる」などの体験装置を用いて開催されました。また、技術者向けの技術移転セミナーも開催され、最新の技術情報やプロジェクト成果の普及に努めました。これらの活動により、地震に対する住民の意識向上と防災意識の醸成が図られ、地震災害軽減に貢献しました。地震防災に関する知識の普及は、将来の地震災害を減らす上で非常に重要な要素であり、このプロジェクトはこの点において大きな役割を果たしたと言えるでしょう。
IV.インドネシアにおける地震観測協力
2004年のスマトラ島沖地震以降、防災科学技術研究所(NIDE)とインドネシア気象地球物理庁(BMG)による共同研究。広帯域地震観測網(JISNET)を構築し、リアルタイムの地震情報の公開を実現。従来のアナログシステムから、衛星テレメータを用いた広帯域地震観測システムに移行し、震源位置、マグニチュード、地震メカニズム等の精緻な解析が可能となった。31箇所の観測点を設置。
1. プロジェクト概要
2004年のスマトラ・アンダマン地震以降、インドネシアにおける地震情報の迅速かつ広範な公開を目指し、防災科学技術研究所(NIDE)とインドネシア気象地球物理庁(BMG)は共同でインドネシア広帯域地震観測網(JISNET)を運用しています。この協力は、インドネシアにおける地震観測体制の抜本的な改善を目的としています。それ以前のBMGの地震観測は、観測周期帯の限定、上下動のみの観測、アナログドラム装置によるオフライン方式など、多くの制約がありました。テレメータも故障が頻発していました。JISNETは、これらの問題点を克服し、リアルタイムでの広帯域地震観測を実現した画期的な取り組みです。2006年5月26日にジャワ島中部で発生したマグニチュード6.3の地震では、JISNETによってリアルタイムの地震記録が取得され、その有効性が実証されました。この共同研究は、インドネシアの地震防災体制強化に大きく貢献しています。
2. 広帯域地震観測網 JISNET
JISNETは、速度計を用いた連続観測によるリアルタイムの広帯域地震観測を特徴としています。観測データから、震源位置、マグニチュード、地震メカニズム、プレートの挙動などをインバージョン法を用いて解析します。強震観測とは異なり、直下の地震では記録が振り切れる可能性があるため、地表面に強震計を併設しています。2006年3月31日時点で31箇所の観測点が設置されており、NIDEが管理するオフラインの広帯域地震観測網と、BMGが2001年から管理する衛星テレメータ(VSAT-IP)広帯域地震観測網を基盤としています。リモート基地から取得された地震波形データは、BMG本庁のWINフォーマットサーバーにリアルタイムで集積され、迅速な情報処理と公開を実現しています。このシステムは、インドネシア全土を網羅する広範囲な地震観測を可能にし、地震災害への対応能力を大幅に向上させました。
3. 観測システム
インドネシアにおける地震観測システムは、衛星テレメータを用いた広帯域地震観測と地表面の強震計による観測を組み合わせた構成となっています。速度計を用いて連続観測を行い、得られたデータから震源位置、マグニチュード、地震メカニズム、プレートの挙動といった重要な情報を解析することが目的です。 このシステムによって、従来のアナログシステムに比べて、はるかに高精度かつリアルタイムな地震観測が可能となりました。リアルタイムでのデータ取得は、地震発生後の迅速な対応に不可欠であり、インドネシアにおける地震防災体制強化に大きく貢献しています。また、広帯域地震観測網の構築は、地震研究の進展にも繋がる重要な成果です。 31箇所の観測点は、NIDEとBMGの既存の観測網を統合・拡張したものであり、広範囲かつ詳細な地震観測データを収集する上で最適な配置となっています。
V.その他機関との協議内容
ウズベキスタンにおいて、国家地震局、地震学研究所、建設省、経済開発省、内務省など多数の機関と地震防災、地震観測、建設基準、機材輸入に関する手続き、法令、都市計画マスタープランなどに関する情報収集と協議を実施。地震計の設置場所や機材仕様、データの利用計画なども検討された。 伊藤忠商事など民間企業との協議では、資機材輸送や観測所建設に関する情報も収集。
1. 国家機関との協議
ウズベキスタンの国家機関との協議では、地震防災に関する多様な情報が収集されました。国家地震局からは地震観測機材の仕様や地震局の組織、課題に関する情報、地震学研究所からはCTBTO機材の輸入手続き、設置状況、今後の計画に関する情報が得られました。建設省からは組織概要、建設基準の入手方法、課題、耐震研究への期待に関する情報、国家設計院からは組織、業務概要、都市計画マスタープランに関する情報が得られました。経済開発省からは役割、プロジェクト登録、活動、組織、経済基盤整備計画に関する情報、内務省消防安全局からは組織・役割、防災教育、関連機関・ドナーとの連携に関する情報が得られました。国防省民間防衛・非常事態総局からは組織、防災における役割、被害想定、防災教育の実施状況、他機関との連携、課題に関する情報、内閣府付非常事態委員会からは組織・役割、活動、課題に関する情報が得られました。これらの機関との協議を通して、ウズベキスタンの地震防災体制の現状と課題、今後の支援の方向性に関する重要な知見が得られました。
2. その他機関 民間企業との協議
教育省からは教育システム、地震教育、防災教育、教育省組織に関する情報が収集されました。通信省からは無線周波数帯の使用、アンテナの配置、住民への啓発に関する情報が得られました。国家設計院からは組織概要、都市計画マスタープラン、震度分布図に関する情報が得られました。国防省第5企業からは地図の整備状況、入手方法、販売・作製価格に関する情報が得られました。建設資材産業省からは建物耐震化の現状、建材の品質確保、建設省との関係に関する情報が得られました。耐震建設研究所からは組織・業務概要、建設基準、地震リスク評価に関する情報が得られました。伊藤忠商事からは資機材の輸送・通関、観測所の建設に関する情報が得られました。これらの機関や企業との協議を通して、地震観測システムの構築、地震防災対策、関連技術の導入、およびそれらに関連する物流や通関手続きに関する幅広い情報が収集され、プロジェクトの実現可能性を検討する上で貴重なデータとなりました。特に、民間企業との協議は、プロジェクトの実施における現実的な課題や解決策の検討に役立ちました。
3. データの利用計画と今後の課題
国家地震局との協議では、地震計の配置、観測所、機材、強震計、予算規模など、将来導入すべき施設や機材の詳細、技術支援の確認が行われました。科学アカデミー付属中央図書館からは地震、地質に関する資料が提供されました。内閣府付国家非常事態委員会からは、将来の地震観測データの利用構想、地震防災施策の重点項目に関する情報が得られました。石油ガス産業天然資源省からは、既往の地質調査資料の管理状況とデルタゲオンによる観測状況、データ管理、国家地震局との連携に関する情報が得られました。これらの情報に基づき、地震観測データの有効活用、地震防災施策の最適化、関連機関との連携強化など、今後の課題が明確になりました。 特に、既存データの活用や関係機関との連携強化は、地震防災対策の効率化と効果の最大化に繋がる重要な要素です。
