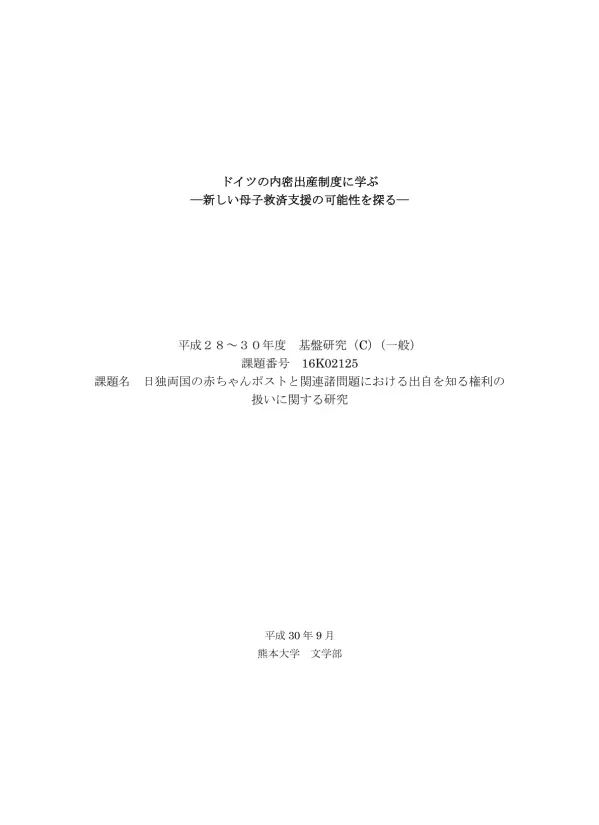
ドイツ式内密出産:日本への導入可能性
文書情報
| 著者 | Yulia Krieger |
| 専攻 | Law, Ethics, Welfare Studies |
| 場所 | 熊本市 (Kumamoto City) |
| 文書タイプ | Symposium Report |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 8.03 MB |
概要
I.日独における匿名出産 内密出産の現状と課題 赤ちゃんポストと出自を知る権利
本資料は、ドイツの赤ちゃんポスト(Babyklappen)と日本のこうのとりのゆりかごを比較検討し、匿名出産 (anmin shussan) と 内密出産 (naimitsu shussan) を巡る議論を分析したものです。特に、子どもの出自を知る権利 (shusshin o shiru kenri) と孤立出産 (koritsu shussan) の問題が両国で大きな論点となっています。ドイツでは2014年、「内密出産法 (vertrauliche Geburt) 」が施行され、匿名性と出自を知る権利のバランスを図る新たな試みが導入されました。一方、日本ではこうのとりのゆりかご(熊本市慈恵病院)の設置以来、倫理的な議論が継続され、内密出産制度導入への検討が活発化しています。熊本市の専門部会も、ドイツの内密出産制度を参考に、日本への導入を強く求めています。
1. ドイツにおける赤ちゃんポストと匿名出産の問題点
ドイツでは2000年から設置が始まり、90か所以上に広がっている赤ちゃんポスト(Babyklappen)は、匿名出産(anonyme Geburt)の手段として利用されてきました。しかし、このシステムは子どもの出自を知る権利(shusshin o shiru kenri)を侵害する可能性や、孤立出産(koritsu shussan)の問題を深刻化させるという批判が数多く寄せられています。赤ちゃんポストの存在が、責任ある親としての役割を果たすことを阻害し、結果として子どもの福祉を損なうという懸念も指摘されています。そのため、より適切な代替策が求められており、その議論が活発に行われています。 これらの批判を踏まえ、ドイツ政府は、匿名性と子どもの権利のバランスを考慮した新たな制度の必要性を認識し始めました。
2. 日本のこうのとりのゆりかご 現状と課題
2007年に熊本市の慈恵病院に設置された「こうのとりのゆりかご」は、赤ちゃんポスト(akachan posuto)として知られ、親が育てられない赤ちゃんを匿名で預かる施設です。設置以来、日本においても匿名出産や、子どもの出自を知る権利、孤立出産の問題を巡る議論が続いてきました。NHKの長期取材による報道は、この問題の深刻さを社会に広く知らしめることとなり、大きな衝撃を与えました。 特に、預け入れられた子どもへの影響や、母親の置かれた状況、そして社会全体の支援体制の不足といった問題点が浮き彫りになりました。こうのとりのゆりかごの第三者検証委員会は、2017年の報告書において、日本の現状を鑑み、内密出産制度(naimitsu shussan)の早急な検討を国に強く求めています。慈恵病院も、この提言を踏まえ、内密出産制度の導入を検討しています。
3. 日独両国の共通点と相違点 代替策としての内密出産制度
日独両国において、赤ちゃんポスト(Babyklappen/akachan posuto)を中心とした匿名出産システムに対しては、子どもの出自を知る権利(shusshin o shiru kenri)や孤立出産(koritsu shussan)の問題が共通の批判点として挙げられています。そして、両国とも、これらのシステムに代わる代替策として内密出産制度(vertrauliche Geburt/naimitsu shussan)の導入が検討されています。しかし、その導入プロセスや制度設計においては、両国間に違いが見られます。ドイツでは、内密出産法(vertrauliche Geburt)の制定を経て、制度の導入と運用が行われ、その後3年で評価報告書が公表されています。一方、日本においては、内密出産制度導入に向けた議論が本格化しつつある段階であり、ドイツの制度を参考にしながら、日本独自の制度設計が模索されています。 この違いは、それぞれの国の法的・社会的な背景や、母子福祉に対する考え方などに起因していると考えられます。
4. シンポジウムと今後の展望
日独両国の関係者や研究者によるシンポジウムでは、ドイツの内密出産制度(vertrauliche Geburt)のメリットと課題について活発な意見交換が行われました。このシンポジウムは、日本における内密出産制度導入検討のための重要な一歩であり、法学、倫理学、福祉学といった多角的な視点からの分析と議論がなされました。 特に、ドイツにおける制度の導入プロセスや、その後の評価報告書の内容が、日本の議論に大きな影響を与えています。シンポジウムの報告書は、今後の日本における内密出産制度導入に関する議論の進展に大きく貢献すると期待されています。 今後、日本の社会状況や法制度を踏まえ、子どもの権利と母親の権利のバランスを考慮した、適切な制度設計が求められます。
II.ドイツの内密出産制度 導入プロセスと現状
ドイツの内密出産法は、困難な状況にある妊婦とその子どもへの支援を目的としています。2017年の評価報告書では、制度のメリットと課題が分析されています。内密出産の手続きには、妊娠相談所、医師、助産師、病院、養子縁組斡旋機関などの連携が不可欠です。pro familiaのような妊娠相談所は、相談員の資格認定と研修を実施し、ネットワーク構築を進めています。しかし、制度運用上、医療面や手続き面での課題も残っており、相談員は複雑なケースに対応する高い能力と、多機関との連携が求められています。特に、匿名出産や赤ちゃんポストを利用する妊婦の増加に繋がる懸念や、子どもの出自を知る権利との調和が今後の課題です。
1. ドイツ内密出産法の目的と背景
2014年5月に施行されたドイツの内密出産法(vertrauliche Geburt)は、赤ちゃんポスト(Babyklappen)や匿名出産の問題点を踏まえ、困難な状況にある妊婦への支援強化と、子どもの出自を知る権利(shusshin o shiru kenri)と妊婦のプライバシー保護の両立を目指して制定されました。従来の匿名出産では、母親と子の双方にとって医療的なケアが十分に保障されない、子どもの出自が不明瞭になるなど、多くの問題がありました。内密出産法は、これらの問題点を解消し、より適切な支援を提供するための新たな試みと言えます。法制定までの過程では、赤ちゃんポストの是非に関する長年の議論が重ねられ、政治的責任者による検討が続けられてきました。 この法律は、匿名出産システムの欠点を克服し、母子双方にとってより良い解決策を提供することを目指しています。
2. 内密出産制度の実施体制と課題
内密出産制度の円滑な運用には、妊娠相談所、医師、助産師、病院、養子縁組斡旋機関、青少年局、身分登録所、家庭裁判所など、様々な機関の連携が不可欠です。そのため、関係機関は内密出産の手続きとそれぞれの役割について十分な知識を持つ必要があります。特に、妊娠相談所(Schwangerschaftsberatungsstellen)は、制度の中核的な役割を担い、相談員(Schwangerschaftsberaterin)の資格認定や研修、地域機関とのネットワーク構築が重要となります。pro familiaのような団体は、相談員の育成に力を入れています。しかし、内密出産のケースは稀であるため、相談員は実践的な経験を積むことが難しく、高い専門性と対応力、そして緊密な連携が求められます。 また、手続きの複雑さや、関係機関間の情報共有の遅れなどが課題として挙げられています。
3. 妊娠相談所の役割と相談員の資格
ドイツの妊娠相談所は、1995年の妊娠葛藤法に基づき、妊娠に関するあらゆる相談に対応する役割を担っています。相談は匿名で行うことも可能で、妊娠継続・中絶の選択に悩む女性や、妊娠を隠さざるを得ない状況にある女性からの相談にも対応しています。内密出産法の導入後、妊娠相談所は内密出産に関する相談の中心的役割を担うことになり、相談員の専門性の向上が重要課題となりました。そのため、法律知識、手続き、関係機関との連携、倫理的な配慮など、多岐にわたる研修カリキュラムが開発され、相談員の資格認定制度が整備されました。 全ての相談所に有資格者を配置することを目指し、研修の普及に努めていますが、人員や時間的な制約など、課題も存在しています。
4. 内密出産制度の評価と今後の課題
内密出産制度導入3年後の2017年には、制度の評価調査報告書が公表されました。この報告書では、制度のメリットや課題、従来の赤ちゃんポスト(Babyklappen)や匿名出産への影響などが分析されています。報告書では、内密出産制度が、困難な状況にある妊婦にとって有効な支援手段となり得る一方で、手続きの複雑さ、関係機関間の連携強化、相談員の専門性向上、そして、情報提供の工夫など、更なる改善が必要であることが指摘されています。特に、ソーシャルメディアを活用した周知活動の効果が示唆されている一方で、内密出産における自宅出産時の対応や、出自証明書の閲覧手続きなど、実践面での課題も残されています。 今後、これらの課題を解決するために、関係機関間の連携強化や、制度の更なる改善が求められています。
III.日本の内密出産導入に向けた議論 こうのとりのゆりかごの検証と将来展望
日本では、こうのとりのゆりかご(熊本市慈恵病院)の設置から10年以上が経過し、その是非をめぐる議論が続いています。内密出産制度の導入に向けた動きは、こうのとりのゆりかごの検証報告書(2017年)で示された提言を背景に、慈恵病院や熊本市など関係機関によって推進されています。しかし、内密出産の導入には、法律上の課題や社会的な合意形成が不可欠です。出自を知る権利との調和、相談窓口の拡充、関係機関の連携強化などが今後の重要な課題となります。 NHKによる10年間にわたる取材報道は、社会問題としての認知度向上に貢献しました。
1. こうのとりのゆりかごの現状と問題点
熊本市の慈恵病院が運営する「こうのとりのゆりかご」(通称赤ちゃんポスト)は、2007年の開設以来、親が育てられない赤ちゃんを匿名で預かる施設として機能してきました。しかし、このシステムは、子どもの出自を知る権利(shusshin o shiru kenri)の侵害や、孤立出産(koritsu shussan)の問題につながるという批判が絶えません。 NHKの長期取材では、ゆりかごに預けられた子どもや、預け入れに至った母親たちの切実な状況が克明に伝えられ、社会に大きな衝撃を与えました。 十数年間に渡る運用において、ゆりかごへの預け入れ件数は減少傾向にないことから、根本的な解決策が必要であることが指摘されています。 熊本市の専門部会は、この問題の解決策として、ドイツの内密出産制度(naimitsu shussan)の導入を検討すべきだと主張しています。
2. 内密出産制度導入への動きと慈恵病院の取り組み
熊本市の専門部会による検証報告書(2017年)では、こうのとりのゆりかごへの預け入れが10年以上に渡って続いている現状を踏まえ、日本でも内密出産制度(naimitsu shussan)を早急に検討すべきだと提言されました。この提言を受け、慈恵病院は現行法の解釈によっては内密出産の導入が可能ではないかという見解を示し、ドイツの制度を参考に独自の案を発表しました。 熊本市の市長も、内密出産制度の導入に理解を示しており、関係機関による具体的な検討が進められています。 しかし、内密出産制度の導入には、法整備や社会的な合意形成が不可欠であり、今後の議論の行方が注目されます。 特に、出自を知る権利(shusshin o shiru kenri)と母親のプライバシー保護のバランスをどのように取るかが重要な課題となっています。
3. 既存の支援体制の限界と新たな制度の必要性
日本においては、妊娠や出産に関する相談窓口の設置は自治体の努力義務に留まっており、全国的な整備は遅れています。そのため、支援が必要な妊婦が既存のセーフティネットからこぼれ落ちるケースも多く、孤立出産(koritsu shussan)のリスクも高まっています。 こうのとりのゆりかごのようなシステムは、緊急時の対応策としては機能していますが、根本的な解決策とは言い難いです。 内密出産制度(naimitsu shussan)の導入は、こうした現状を打破するための重要な選択肢として議論されていますが、導入にあたっては、法律上の課題や、社会全体の理解と合意形成が不可欠です。 母子の視点に立った支援策を社会全体で議論し、新たな制度づくりに向けて、問題意識を共有していく必要があります。
4. 今後の展望 ドイツの内密出産制度からの学び
日本における内密出産制度導入の議論においては、ドイツの内密出産制度(vertrauliche Geburt)の経験が重要な参考資料となっています。 ドイツの制度導入プロセスや、その後の評価報告書から得られた知見は、日本の制度設計に役立てられると期待されています。 特に、関係機関の連携の重要性や、相談員の専門性向上のための研修体制の構築、そして社会全体への周知活動などが重要なポイントとなります。 しかし、ドイツの制度をそのまま導入するのではなく、日本の社会状況や法制度に適合した独自の制度設計が必要であり、多様な意見を取り入れながら、慎重な議論を進めることが重要です。 2016年に熊本で開催された国際シンポジウムや、ドイツへの研究者派遣など、国際的な連携を通して得られた知見も、今後の議論に役立てられていくでしょう。
IV.内密出産制度における法的課題 親子法 養子法との関係
内密出産においては、親子法と養子法との関連が重要な法的課題となります。「母は常に明らかである」という法格言に対し、内密出産は、出生後16年間、母の身元を秘匿する仕組みを有しています。この期間、子どもの監護者や生活に関する権利義務をどのように規定するかが課題であり、多くの場合、特別養子縁組が想定されます。大阪大学や大阪薬科大学の研究者らは、この問題について法学的な視点から考察を行っています。特に、内密出産における子どもの出自を知る権利の保障と、母親のプライバシー保護のバランスをどう取るかが論点となっています。
1. 内密出産と親子関係の成立
内密出産制度においては、出生と同時に法律上の母子関係が成立するという点に法的課題が存在します。ドイツ民法1591条では「子の母は、分娩した女性である」と明記されていますが、日本法には同様の明文規定がありません。しかし、日本の判例や学説においても、分娩事実によって母子関係が成立するとされています。内密出産の場合、出生から16年間、母親の身元が秘匿されるため、この期間における親子関係に基づく権利義務(扶養、親権、氏、相続など)の扱いが複雑になります。 内密出産制度は、母親の身元を秘匿しつつ、将来的に子どもが出自を知る権利(shusshin o shiru kenri)を行使できる仕組みを含んでいます。このため、出生から16年間、子どもの監護者や生活に関わる権利義務をどのように規定するかが大きな法的課題となります。多くのケースでは、特別養子縁組が想定されるため、養子縁組法との関連も重要です。
2. 子どもの出自を知る権利と母親のプライバシー保護のバランス
内密出産制度は、子どもの出自を知る権利(shusshin o shiru kenri)と母親のプライバシー保護という相反する利益のバランスをどのように取るかが、最大の法的課題です。ドイツの内密出産法では、出生から16年間、母親の身元を秘匿する一方、16歳以降は子どもが自身の出自を知るための手続きが設けられています。この期間設定や、情報開示のプロセス、そして母親のプライバシー保護の範囲をどのように法律で規定するかが重要になります。 日本においても同様の課題があり、内密出産制度導入にあたっては、この点に関する十分な議論と、法的整備が必要不可欠です。 特に、子どものアイデンティティ形成への影響を考慮し、出自を知る権利の保障と、母親の安全とプライバシーを両立させる制度設計が求められます。
3. 養子縁組との関係と手続き
内密出産によって生まれた子どもの多くは、養子縁組(特別養子縁組)を通して新たな家庭を築くことが想定されています。そのため、内密出産制度と養子縁組法との整合性も重要な法的課題です。 内密出産の手続きにおいて、養子縁組斡旋機関の役割や、養子縁組成立までのプロセスをどのように規定するかが検討事項となります。 また、内密出産で生まれた子どもと、養親との間の親子関係、そして生物学的親との間の関係を法律上どのように扱うかについても、明確な規定が必要となります。 これらの手続きにおいて、子どもの福祉を最優先し、透明性と公平性を確保するための法的枠組みの整備が不可欠です。
4. その他 法的課題
内密出産制度に関する法的課題は、上記以外にも複数存在します。例えば、内密に行われた自宅出産の場合、新生児の搬送方法や、医療機関との連携などが問題となります。また、出自証明書の閲覧手続きや、子どもが成長後に生物学的母親を探したい場合の手続きについても、明確な法的規定が必要です。 さらに、内密出産制度の利用を促進するために、社会的な支援体制の整備や、関係機関間のネットワーク構築も重要です。 これらの課題を解決するためには、法律の専門家による詳細な検討と、関係機関との連携による協働体制の構築が不可欠です。 大阪大学や大阪薬科大学の研究者らが、親子法や養子法の観点から、これらの法的課題について研究を進めています。
文書参照
- ゆりかごの設立にあたって
