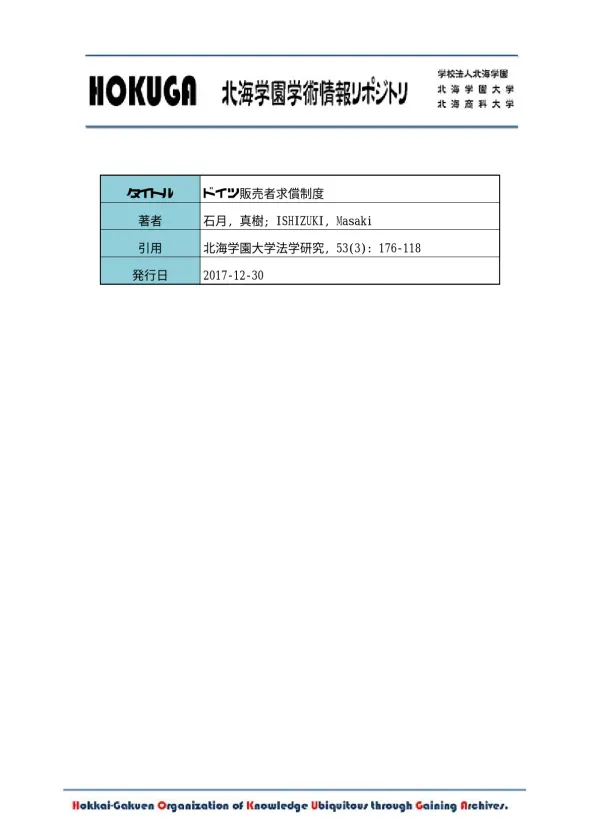
ドイツ販売者求償制度:中間販売者の救済策
文書情報
| 著者 | 石月真樹 |
| 学校 | 不明 |
| 専攻 | 法学 |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.25 MB |
概要
I.中間販売者の責任と製造者への求償 ドイツの供給者求償制度 Klageregress の概要
本論文は、ドイツ民法(BGB)第478条以下に規定される供給者求償制度(Klageregress)、特に消費者向け商品売買における適用について分析しています。瑕疵担保責任(Gewährleistung)に基づき、小売業者(中間販売者)が消費者からのクレームに対応する際、その責任の最終的な帰着先である製造者への求償可能性を検討しています。多くの場合、小売業者は製造上の欠陥などの責任を負わないにもかかわらず、消費者からのクレームに対応せざるを得ない状況に置かれています。この挟み撃ち状態を解消するために、Klageregress制度が重要な役割を果たします。本制度は、小売業者が製造者に対して直接求償できるか否か、催告要件の有無、中古品への適用、問責義務違反の影響など、様々な問題点を分析しています。
1. 中間販売者の責任と 挟み撃ち 問題
ドイツの消費者向け商品売買において、小売業者(中間販売者)は、製造上の欠陥など、自身に責任のない商品の不具合について、消費者からのクレームに対応する法的責任を負うことが多くあります。これは、製造業者であるメーカーが最終的な責任を負うべきにもかかわらず、小売業者が消費者との契約上の責任を負うため、小売業者が不当にコストを負担する「挟み撃ち」状態を生み出します。この状況は、典型的な製造業者→卸売業者→小売業者→消費者の商流において特に顕著です。消費者が商品に不具合を訴えた場合、小売業者は債務不履行責任や瑕疵担保責任を問われ、その対応コストを負うことになります。この問題を解決するために、ドイツでは供給者求償制度(Klageregress)が導入されています。この制度は、小売業者が、本来責任を負うべき製造者などに対して求償できる可能性を検討する上で重要な役割を果たします。民法改正(平成29年法律第44号)による債権法改正によって、消費者の直接請求権が認められる可能性も示唆されていますが、それでも小売業者の負担軽減は不十分です。
2. 損害賠償請求と帰責事由
損害賠償請求権には、催告期間を経ずに主張できるものと、催告期間を要するものがあります。瑕疵惹起損害は前者に、求償準則が想定する商品自体の損害(瑕疵損害)は後者に属します。いずれも売主の帰責事由が必要となります。しかし、製造過程で発生した瑕疵を知らなかった小売業者が、結果的に瑕疵のある商品を販売した場合、売主への帰責事由を認めるかは重要な論点であり、通常は認められないとされています。ドイツの販売者求償制度も、中間販売者には通常帰責事由を認めないことを前提としています。改正された民法では、瑕疵概念に製造者の公の言明や組立説明書も含まれるようになり、製造業者の瑕疵にもかかわらず最終売主が責任を負う状況が生まれ、その責任リスクの増大に対する補償として求償準則が位置づけられます。しかし、消費者保護という観点からは、この規定の妥当性には議論の余地があります。
3. 求償権の基本的性質と既存権利の活用
求償準則は、最終売主が既存の瑕疵担保請求権(§437 BGB)を用いて求償することを原則としています。新たな権利を創設するのではなく、既存の権利を活用することで法体系への影響を最小限に抑える狙いがあります。しかし、現実には、§478 BGBでは、補充的に追完費用の償還に限定された求償固有の権利(追完費用償還請求権)も認められています。この請求権は、供給者の帰責事由の有無に関わらず、最終売主が供給者に対して追完費用を求償できるという点に意義があります。 消費者への販売が行われていない場合、または瑕疵担保責任の履行として瑕疵を清算した場合(約定解除や撤回、従属的保証に基づく場合)には、求償準則は適用されません。このように、求償準則の適用には様々な条件が課せられています。清算局面(消費者との関係)と求償局面(供給者との関係)で瑕疵概念が異なる場合、求償が遮断される可能性もあります。
4. 指令との関係と求償権の強行規定化の議論
欧州連合(EU)の消費財売買指令は、最終売主の求償権を保障する必要性を謳っています。ドイツにおける指令の国内法化の過程では、その射程、つまり最終売主の求償権がどの程度保障されるべきかについて議論がありました。当初、指令は加盟国に広範な裁量を認めたものと解釈され、既存の瑕疵担保責任で十分との見解がありました。しかし、指令が求める担保期間の延長(2年間)や、求償可能性の確保という観点から、ドイツでは最終売主の求償権をより明確に保障する必要性が認識されるようになりました。この過程において、求償権の強行規定化の是非が議論され、最終的には強行規定化は避けられることとなりました。この決定は、事業者間の法的関係における柔軟性の重要性を考慮した結果です。この経緯から、現在のドイツの求償準則は、多様な内容を含む特異な制度として成立していることが分かります。
5. 小売業者の保護と消費者保護との関連性
ドイツの求償準則は、特に小規模な小売業者の保護を目的としているとの指摘があります。大企業と異なり、小規模な小売業者は、供給者との契約において、自身の求償権を確保するための十分な市場力を有していません。そのため、消費者保護の強化に伴う担保責任コストの増加は、小規模な小売業者にとって大きな負担となり、市場競争における不利益につながる可能性があります。このため、小売業者の保護は、消費者保護を間接的に支援する側面も持ちます。最終売主が求償できる可能性は、消費者にとって満足のいく解決を見つけるための最終売主の準備に大きく影響するとの見解も存在します。指令制定過程においても、小売業者の保護と消費者保護の両立が重要な課題として認識されていました。
II.製造者への直接請求と契約関係の重要性
Klageregress制度では、小売業者は、商品を供給した業者(卸売業者など)に対してのみ求償できます。製造者への直接請求は、契約関係が存在しないため認められていません。これは、契約自由の尊重と契約の相対性原則に基づいています。しかし、立法過程においては製造者への直接請求の導入も検討されましたが、契約法と不法行為法との整合性、および事業者間の契約関係における柔軟性の確保といった理由から否定されています。この点において、478条は契約関係の存在を前提としています。また、瑕疵概念の不一致による求償遮断の問題も論じられています。
1. 製造者への直接請求の否定と契約関係の必要性
ドイツの供給者求償制度(Klageregress)においては、最終売主(小売業者など)は、瑕疵のある商品について、販売連鎖内の瑕疵惹起者に対して直接請求することは認められていません。これは、最終売主と製造者との間に、通常、卸売業者などの他の中間販売者が介在し、直接的な契約関係が存在しないことが主な理由です。立法者は、契約関係のない者同士に法定の求償権利義務関係を創設することは、求償権の内容に関する契約上の合意を不可能にし、販売方式の多様性を考慮すると適切ではないと判断しています。そのため、最終売主は、当該商品を最終売主に売却した業者(供給者)に対してのみ求償を行うことができます。これは、民法(BGB)第478条1項に明示的に規定されています。この規定は、契約関係を前提とすることで、事業者間の取引における契約自由を尊重し、柔軟性を確保することを意図しています。 直接請求を認めないことで、契約法と不法行為法との整合性も維持されます。
2. 直接請求導入の検討と拒否の理由
立法過程においては、製造者への直接請求の導入も提案されました。討議草案整理化案では、追完費用の償還については製造者への直接請求を認めていましたが、他の求償権については認められていませんでした。しかし、この直接請求導入案は、契約自由の要請に加え、契約の相対性原則との衝突という問題点がありました。契約の相対性原則に反する直接請求は、不法行為法と契約法の本質的な区別を曖昧にし、ドイツの不法行為法の原則(第一次的な財産損害賠償の排除)との整合性が取れませんでした。そのため、消費財売買という限定的な領域において、ドイツ法の抜本的な変革を行うことは不適切と判断され、直接請求は最終的に否定されました。 代替案として、消費者との瑕疵清算によって生じたコストの賠償を求める新たな請求権の創設も検討されましたが、既存の瑕疵担保請求権との整合性や理論的な正当性の問題から採用されませんでした。
3. 瑕疵担保請求権の活用と求償遮断の回避
最終的に、立法者は、求償を既存の瑕疵担保請求権で行うという立場を採用しました。しかし、瑕疵担保請求権に基づく求償は、様々な原因によって遮断される可能性があります。そのため、EU指令第1条が求める求償を保障するためには、求償の遮断を回避するための措置が必要になります。求償準則の主な内容は、この求償遮断回避のための対応策です。しかし、これらの対応策が適切でなければ、求償遮断のリスクが残るだけでなく、求償すべき範囲を超える請求を最終売主に認めてしまう危険性もあります。多くの批判は、この対応策の不適切さを示しています。 特に、清算局面と求償局面における瑕疵概念の不一致は、求償遮断の大きな原因となります。
4. 契約自由の制限と経済政策上の目標
ドイツの求償準則は、事業者間の取引であることを考慮し、完全に強行規定化することは避けられています。しかしながら、§478条3項では、小売業者の保護を目的として、契約自由をある程度制限する規定が設けられています。これは、小売業者が、卸売業者や製造業者に免責や求償条件を押し付けられることを防ぎ、市場力のある競業者との競争における不利益を回避するためです。学説では、この規定の正当性を、消費者保護への間接的影響(最終売主の支払不能リスク回避、消費者への履行促進)に求めるべきであり、事業者自体の保護に求めるべきではないとの意見もあります。しかし、立法者の意図は、最終売主の求償権を消費者の権利と同程度に保障することにあり、指令の要請を超えるものであり注目に値します。 この規定は、「等価の補償」が認められている場合は適用されず、契約自由への配慮も示されています。
III.求償権の行使と制限 催告要件 の排除と 求償利益 の範囲
Klageregress制度は、小売業者が供給者に対して瑕疵担保請求権(§437 BGB)を行使する際、通常必要な催告期間を要しない点(§478 I BGB)が特徴です。これは、再販売の困難さを考慮した措置です。しかし、求償利益の範囲については、清算局面(消費者との間の取引)と求償局面(供給者との間の取引)での清算内容の不一致による問題が生じることが指摘されています。具体的には、代金減額と解除、あるいは解除と損害賠償の請求に関する不整合などが議論されています。また、転売利益の確保についても、指令との整合性や製造者への過剰な負担の問題が議論されています。
1. 催告要件の排除 478 BGB 1項の意義
ドイツの供給者求償制度(Klageregress)において、民法(BGB)第478条1項は、最終売主が供給者に対して瑕疵担保請求権を行使する際に、通常必要な催告期間を不要とする規定を設けています。これは、最終売主が供給者に対して、追完(修理や交換)を経ることなく、直接に契約解除や代金減額を求めることができることを意味します。改正民法における瑕疵担保責任の階層化を修正するものであり、求償の場面では、最終売主にとって供給者との契約関係維持に利益がなく、解消する形で進むべきという判断に基づいています。立法者は、最終売主が消費者から瑕疵のある商品を引き取った後、供給者へ問題なく商品を転送できることを理由に、殆ど意味のない追完の機会提供を不要とし、直接契約解除を可能にすると説明しています。この規定は、特に販売数量の少ない小規模な小売業者にとって、再販売の負担を軽減するという意味で有益であると考えられます。
2. 求償利益の範囲と清算 求償局面の不一致
求償制度では、契約関係ごとの清算を前提とするため、求償局面における清算が、消費者に対する清算よりも過大になる可能性があります。例えば、清算局面で代金減額がなされたにもかかわらず、求償局面で解除権を行使する場合や、清算局面で解除がなされたにもかかわらず、求償局面で給付に代わる損害賠償を請求する場合などが挙げられます。学説では、このような場合、求償規定の適用は求償利益の限度内とするべきとの主張があります。具体的には、清算局面での代金減額、解除に応じて、求償局面での請求もそれぞれ代金減額、解除に限定すべきとの意見です。解除や損害賠償請求を行う場合、その請求は§478項、§479項の軽減措置に制限されるべきであると主張されています。 清算局面と求償局面での瑕疵概念の不一致も、求償利益の範囲を検討する上で重要な要素となります。
3. 転売利益の求償に関する議論
清算局面で契約が解消された場合、最終売主の求償は供給者に対する瑕疵担保請求権に基づいて行われます。そのため、最終売主は求償によって転売利益を確保することはできません。転売利益の求償については、学説においてEU指令第1条との関係から議論されています。転売利益の賠償を否定する意見は、賠償範囲が商品の販売価格に依存し、求償債務者にとって算定不可能な責任を課すことになると主張します。これに対し、肯定的な意見は、製造者は販売連鎖を管理しており、転売価格の見積もりが可能であると反論しています。指令の効果的な求償は求償遮断の完全回避を要求し、転売利益の喪失は最終売主にとって重大な損害であるため、転売利益の求償が認められるべきだと主張する学者もいます。Schumacherは、転売利益の求償を認めていないドイツの求償規定はEU指令に違反すると結論付けていますが、立法者の決定を考慮し、指令に適合する解釈(§478条2項の類推適用など)の可能性も示唆されています。
IV.問責義務と中古品への適用 商法典第377条 と 指令第1条 との関係
商法典第377条の**問責義務(目的物検査・通知義務)**違反は、Klageregressにおける求償遮断の原因となります。しかし、本論文では、この義務が求償局面(「復路」)にも適用されるべきか否かについて、立法者の意図や学説の対立点を詳細に検討しています。特に、包装済商品や大量製品における検査の実際的な限界などが考慮されています。さらに、中古品への適用については、指令第1条との整合性も考慮しながら、販売連鎖の典型性や製造者の責任の在り方などの観点から、適用範囲を限定する理由が検討されています。
1. 商人の目的物検査 通知義務 問責義務 違反と求償遮断
ドイツの供給者求償制度において、求償連鎖が遮断される典型的な原因の一つに、商法典第377条で規定される商人の目的物検査・通知義務(問責義務)違反があります。商人間の売買では、買主は目的物の受領後速やかに検査し、瑕疵を発見した場合には売主に通知する義務を負います。この義務を怠ると、商品を承認したものとみなされ(追認擬制)、売主に対する瑕疵担保請求権を失います。これは、検査によって発見不可能な隠れた瑕疵についても同様です。 求償関係においても、当事者は商人であることが通例であり、この問責義務が適用される可能性があります。しかし、政府草案では、消費者への転売を予定する販売者にも問責義務が妥当すること、しかし求償関係においてはその違反が権利喪失に繋がらないことを明示していました。立法者は、商品の交付時点では商品の将来の運命が確定していないため、商人たる買主の間に区別を設けず、通知義務を一般的に適用すべきと主張しました。しかし、これは製造者から販売者への「往路」にのみ妥当し、「復路」である求償の場合には妥当しないとして、政府草案商法第378条で「往路」の問責義務違反が「復路」の求償権喪失に繋がらないことを確保しようとしていました。
2. 問責義務に関する学説と判例との相違点
学説では、立法者の問責義務に関する理解に批判的な見解があります。瑕疵が事後的にしか認識できない場合、商法第377条第3項は、顧客が販売者に瑕疵を問責し、瑕疵のあることの根拠のある疑いが生じた場合にのみ、遅滞のない通知義務が生じると解釈しています。つまり、立法者が考慮する事情は、隠れた瑕疵に関する商法第377条第3項の事後的な通知でカバーされるため、新たな規定は不要だと主張しています。さらに、政府草案商法第378条は、認識可能な瑕疵でも通知を怠った場合、転売・消費・加工するだけで問責義務違反の効果を免れると解釈でき、その正当性に疑問を呈しています。実務では、特に包装済商品の場合、事業者間では合意により、消費者相手には事実上最終購入者に検査が委ねられることが多いですが、判例は、最終購入者への検査の転送が売主の問責義務を免除するものではなく、通知期間を延長するものでもないとしています。最終売主は、消費者の適時な瑕疵通知に依存することになり、大きなリスクを抱えることになります。
3. 中古品への求償準則の適用除外とEU指令との関係
ドイツの求償準則は、中古品への適用を明確に排除しています。これは、中古品の場合、求償に関する軽減措置を正当化できる一体的な販売連鎖が存在しないことが理由とされています。しかし、学説では、中古品であっても販売連鎖を介した商品流通は存在し(中古車、美術品など)、求償問題が生じ得るとして、この排除に批判的な意見があります。 販売連鎖の典型性が存在しないという理由だけでは、例外的に販売連鎖が存在する場合の求償排除を説明できず、説得力に欠けると指摘されています。特に、EUの消費財売買指令は中古品への適用を排除しておらず、指令第1条からすれば、最終売主は中古品の販売についても効果的な求償を必要とします。しかし、求償準則の適用がない場合、瑕疵担保請求権では求償遮断に陥り、指令違反になる可能性があります。条文と立法者の意図から、指令に適合する解釈としての中古品への類推適用は困難であるとの見解が一般的です。中古品販売では、新品販売とは異なり、直接の売主に対する人的信頼が依然として重視されるため、特別な販売連鎖の問題は存在しないと主張する意見もあります。
V.原材料供給者への求償と製造者の責任 コスト集中 の原則と限界
Klageregress制度では、製造者が最終的な求償義務者であり、原材料供給者への求償は想定されていません。製造者の責任は、製品の品質管理について見通しを持つ立場であることを考慮し、厳格に規定されています。しかし、原材料の欠陥が原因で最終製品に瑕疵が生じた場合、コスト集中の原則との整合性から原材料供給者への求償を認めるべきとの主張も存在します。本論文は、この点についても、製造者の責任の在り方、消滅時効の問題などを踏まえつつ、Klageregress制度の限界を検討しています。
1. 原材料供給者への求償の不可能性と製造者の最終的責任
ドイツの供給者求償制度(Klageregress)においては、製品の製造業者が最終的な求償義務者であり、製造業者から原材料供給者への求償は原則として予定されていません。たとえ製造業者が調達した原材料に瑕疵があり、それが原因で最終製品に瑕疵が生じた場合でも、製造業者は求償準則に基づく責任を負いますが、その責任を原材料供給者へ転嫁することはできません。これは、製造業者が最終的な求償義務者として、求償準則による責任増大を負う一方、原材料供給者に対しては通常の売買法に基づく責任しか負わないことを意味します。例えば、求償権の時効に関しては、製造業者は消滅時効の完成猶予により最長5年間責任を追及されるリスクがありますが、原材料供給者に対しては原材料の供給から1年以内に求償権を行使しなければなりません。この制度設計は、製造業者の責任を厳格化し、コストを最終的に瑕疵惹起者に集中させることを意図しています。 しかし、この点については異論も存在します。
2. 製造者責任の厳格さと原材料供給者への求償主張
製造者責任の厳格化については、製造業者が販売連鎖の中で唯一、個々の製品の品質に関して見通しを持つ存在であるという点が強調されます。そのため、製造者の責任は、販売連鎖の下流の売主よりも厳格なものとなります。これに対し、販売連鎖内の他の販売業者は、商品に関する情報や品質管理において、最終購入者とそれほど変わらない立場にあることが多いです。また、製造業者は消費者の購買決定に決定的に影響を与える「準売主」としての地位も持ちます。これらの理由から、製造業者が瑕疵のコストを負担することが必須とされ、Klageregress制度の設計にも反映されています。しかしながら、原材料供給者への求償を主張する見解も存在します。この見解は、瑕疵惹起者へのコスト集中という制度の目的を完全に達成するためには、最終製品の瑕疵が原材料供給者による部品の欠陥のみを理由とする場合、求償が原材料供給者にも及ぶべきだと主張します。 この主張は、コスト集中という制度目的だけでは、求償規定の正当性を十分に説明できないという批判を受けています。
3. コスト集中原則の限界と製造者の特徴的地位
求償規定の目的を瑕疵惹起者へのコスト集中のみで正当化することは不十分であるという批判があります。求償規定が最終的な求償債務者(製造業者)に課す負担は、商品販売連鎖における製造者の特徴的な地位にのみ認められるべきものだとする見解が有力です。製造業者は、品質管理において他の販売者よりも大きな責任を負っており、消費者の購買決定にも大きな影響を与えているからです。原材料供給関係への求償の適用を拡大すると、求償が扇状に広がり、かえって原材料供給者の負担軽減に繋がらない可能性も指摘されています。 そのため、原材料供給関係は求償規定の適用対象から除外されるべきであるという結論が導かれます。 この結論は、瑕疵による不利益を、最終的にそれを負担できる製造者にまで遡及させるという、コスト集中原則の解釈に基づいています。
