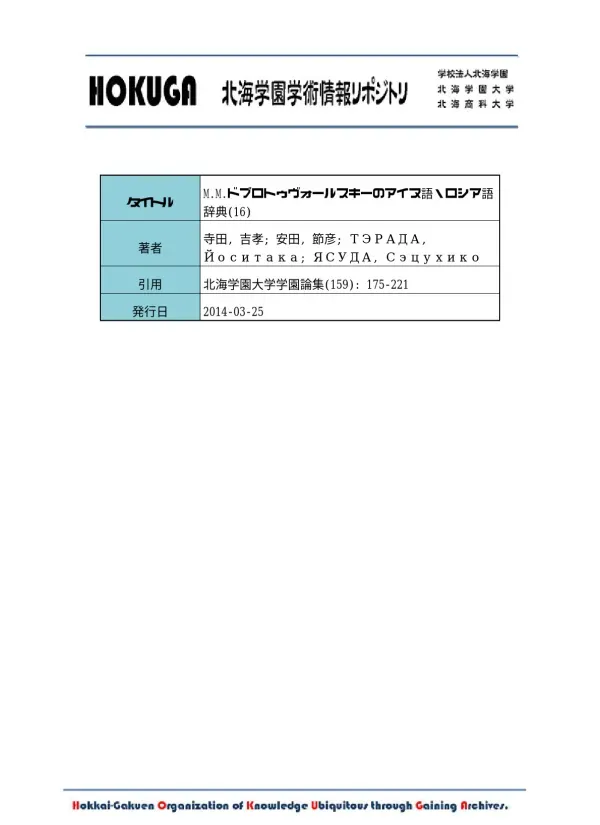
ドブロトゥヴォールスキー アイヌ語辞典 翻訳
文書情報
| 著者 | 寺田 吉孝 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | アイヌ語学 |
| 場所 | 札幌市(北海学園大学所在地) |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 8.17 MB |
概要
I.M
この辞典は、M.M.ドブロトゥヴォールスキーが遺したアイヌ語とロシア語の単語集を基に編纂されたものです。アイヌ語辞典として、アイヌ語の単語とそのロシア語訳、さらに詳細な解説を提供しています。彼の没後、実兄I.M.ドブロトゥヴォールスキー(当時カザン大学教授)が遺稿を編集、刊行しました。Ainu-Russian dictionaryとして貴重な資料であり、多くの単語に意味不明な箇所や省略記号が残されているものの、その内容はアイヌ語学習やアイヌ文化研究に大きく貢献するものです。辞典には、サハリン、千島列島などアイヌ民族の居住地域に関連する地名なども多数収録されています。サハリンアイヌ語、千島アイヌ語などの地域差にも触れられています。また、ダヴィドフのアイヌ語単語集(Davidov's Ainu word list)なども参照されており、比較言語学的な側面も持っています。この辞典は、アイヌ語研究にとって重要な一次資料です。
1. 辞典の編纂と著者の没後
このアイヌ語・ロシア語辞典は、M.M.ドブロトゥヴォールスキーによってほぼ単独で執筆されました。しかし、彼は完成を見ることなく急逝したため、辞典には意味不明な箇所や省略記号が多く残されています。特に、(m)、(n)で始まる約500語の翻訳部分には、多くの未解明な箇所があり、訳者自身も誤った解釈をしている可能性を指摘しています。彼の死後、実兄であるI.M.ドブロトゥヴォールスキー(当時カザン大学教授)が遺稿を収集し、編集、刊行に携わったことが記述されています。 M.M.ドブロトゥヴォールスキーは、辞書のほとんどを単独で完成させたものの、時間的な制約や急逝により、十分な推敲がなされなかったことが推測されます。 弟の遺志を継ぎ、兄が編集作業を通してこの辞典を世に出すまでの過程が、この序文で重要な部分として示されています。 そのため、辞典には未完成の部分や、解釈の余地を残す部分が存在していることを理解する必要があります。
2. 辞典の内容と特徴
この辞典はアイヌ語の単語とそのロシア語訳を収録したもので、アイヌ語の単語の解説には、その意味だけでなく、同義語、地域差(Mos.、Dav.、Kl. Kam.など)、語源に関する推測などが含まれています。例えば、「Myessika (メツシカ)」は乾燥させたネズミイルカで、日本語の「ネズミイルカ」に由来するという説明がなされています。 また、文法的な解説も一部含まれており、特に「可能法」を形成する接尾辞についての記述が見られます。 これはアイヌ語の文法構造を理解する上で重要な情報です。 さらに、地名や人名なども記載されており、アイヌ文化や歴史、地理に関する情報も得られます。例として、サハリン西岸のアイヌの村であるMinabutsiや、クスナイの南方にあるアイヌと日本人の村であるMojri-tomariなどが挙げられています。これらの情報が、辞典の学術的な価値を高めています。
3. 参考文献と未解明な点
辞典の記述の中には、ダヴィドフ(Davidov)の東アジアとアメリカ北西海岸のいくつかの民族の言語の単語集を参照している箇所があります。具体的には、Dav.という略記号は、ロシア語からドイツ語に翻訳されたダヴィドフ作成の単語集からの引用であると推測されます。この単語集は、アイヌ語、つまりサハリン半島、蝦夷、南千島の住民の言語に関する単語集の一部であると推測されています。 また、辞典中には多くの省略記号があり、その意味が不明な箇所も存在します。 訳者は可能な限り解読を試みていますが、誤った理解をしている部分もある可能性があり、読者からの指摘を歓迎する旨が述べられています。 これらの未解明な点こそが、この辞典のさらなる研究と解釈を促す要因となっています。そして、その解釈の過程で、アイヌ語研究は発展していくことが期待されます。
II.辞典の内容 単語の例と解説
辞典には、多くのアイヌ語の単語とそのロシア語訳が掲載されています。例えば、「Myessika (メツシカ) - 乾燥させたネズミイルカ」、「Momat ko gur (mamath kogur) - 夫」、「Mokoru - 眠る」、「Mosiri - 島、土地」など、多様な単語とその意味、関連語、例文などが収録されています。それぞれの単語の説明には、言語学的な分析、地域差(例:Mos.、Dav.、Kl.Kam.など地域別表記)、語源推定などが含まれています。アイヌ語の文法に関する記述もあり、アイヌ語の文法研究にも役立ちます。特に、可能法を形成する接辞などの解説は興味深いものです。
1. 単語の記述形式と情報
辞典の各項目は、アイヌ語の単語、それに続くロシア語訳、そして意味の説明から構成されています。多くの単語には、Mos.、Dav.、Kl. Kam. などの地域的な略語が付けられており、その単語がどの地域で使用されているのかを示しています。 さらに、同義語や類義語が示されている場合もあり、例えば、「Miro」は火口を意味し、「karoma」と同義であるとされています。一部の単語には語源に関する推測も記されています。例えば、「Minagani」は「mina(笑う)」と「gani(小詞gannyeかnanu(顔)か)」から成り立っていると推測されています。 このように、各単語の記述は、単なる翻訳ではなく、言語学的な考察も含んだ詳細な解説となっています。 また、例文が示されている場合もあり、その単語の具体的な用法を理解する上で役立ちます。 例えば、「Mombi」の例文として「kaya shashtye ― 出航する」が挙げられており、出航を帆を急がせるという意味と説明されています。
2. 文法に関する記述
辞典の中には、アイヌ語の文法に関する記述も含まれています。 特に、可能法の活用に関する説明が多く見られます。「Mokora」は「眠ることができる」という意味で、可能法の形で「眠る」ことを示す例として挙げられています。 また、「nankora」や「nankonna」といった接辞は、可能法を表す助詞として解説されており、文法的な機能が示されています。 これらの記述は、アイヌ語の文法構造を理解する上で重要な手がかりとなり、言語学的な分析を深める上で非常に役立ちます。 さらに、接尾辞の活用や、名詞の格変化(例:「小さい」の女性単数生格、与格、造格、前置格)といった文法的特徴も記述されており、アイヌ語の文法体系の理解を助けてくれます。 これらの記述を通して、アイヌ語の文法構造の複雑さと奥深さが垣間見られます。
3. 地名 人名 その他固有名詞の解説
辞典には、地名や人名なども含まれています。「Minabutsi」はサハリン西岸のアイヌの村、「Mojri-tomari」はクスナイの南方にあるアイヌと日本人の村として記述されています。また、「Mongyetsu」はマツマイ島の地域名として記載されています。 これらの地名情報は、アイヌ民族の地理的な分布や歴史的な居住地を知る上で重要です。 さらに、「Brylkin」、「Davidov」、「Pavlovich」などの人名も登場し、これらの個人がアイヌ語研究に関わっていたことが示唆されます。 地名や人名に関する記述は、辞典を単なる単語集ではなく、アイヌ文化や歴史に関する情報源としても位置づけることができます。 これらの固有名詞は、歴史的、地理的な文脈を与え、アイヌ語の単語の理解をより深めるための重要な要素となっています。 例えば、地名を紐解くことで、その地域のアイヌ語の方言の特徴などが理解できる可能性があります。
III.地名 人名など固有名詞
この辞典には、アイヌ民族の居住地や関連する地名が多数収録されています。例えば、「Kusunaj(クスナイ)」「Bussye(ブッセ)湾」「Najbuchi(ナイブチ)川」「Saruntara(サルンタラ)」など、サハリンや千島列島を中心とした地名が多数挙げられています。これらの地名情報は、アイヌの歴史研究や地理研究において重要な手がかりとなります。また、著者であるM.M.ドブロトゥヴォールスキー自身や、編集者であるI.M.ドブロトゥヴォールスキー、そしてダヴィドフ(Davidov)といった研究者の人名も重要な情報です。これらの名前は、アイヌ語研究史において重要な役割を果たした人物を示しており、研究者にとって貴重な情報源となります。
1. 地名に関する記述
この辞典には、アイヌ民族の居住地や関連する地名が数多く記載されています。それらの地名には、サハリンや千島列島といったアイヌ民族が居住していた地域に関するものが多く含まれています。例えば、サハリン西岸のアイヌの村であるMinabutsi(ミナブルチ)、クスナイの南方180露里にあるアイヌと日本人の村Mojri-tomari(モジリ・トマリ)、ドゥーイ哨所の南方の岬であるMoisye(モイスイェ)、ナヤッシの南方にある岬と川Mororo tsi(モロロ・ツィ)、そして石炭層のあるサハリン西岸の湾Nayasyu(ナヤスユ)などが挙げられます。これらの地名は、辞典の中でアイヌ語の単語と共に記載されており、それぞれの単語が使用されていた地域や文化的な背景を理解する上で重要な手がかりとなります。また、これらの地名情報は、アイヌの歴史や文化、地理的な分布状況を研究する上で貴重な資料となります。特に、サハリンや千島列島に関する地名は、アイヌ語と地域の関係性を示す上で重要です。
2. 人名と参考文献
この辞典において重要なのは、著者であるM.M.ドブロトゥヴォールスキーと、編集者であるI.M.ドブロトゥヴォールスキーの名前です。M.M.ドブロトゥヴォールスキーは、この辞典の主要な執筆者であり、彼のアイヌ語研究の成果がここに集約されています。I.M.ドブロトゥヴォールスキーは、弟の遺稿を編集し、この辞典を出版する役割を果たしました。さらに、辞典の中にはダヴィドフ(Davidov)のアイヌ語単語集(Wörter-sammlung aus der Sprache der Aino’s)が言及されており、この単語集が、サハリン半島、蝦夷、南千島の住民の言語に関する部分として参照されていることが示唆されています。これらの名前は、アイヌ語研究の歴史の中で重要な役割を果たした人物を示しており、辞典の編纂背景や参考文献を理解する上で不可欠な情報です。特に、ダヴィドフの単語集との関連は、この辞典の研究方法や信頼性を評価する上で重要な要素となります。
3. その他の固有名詞と解説の補足
辞典には、地名や人名以外にも、様々な固有名詞が登場します。例えば、「Matsmaj(マツマイ)」島、「Gol’dy(ゴリドゥィ)」人、「Gilyami(ギリヤミ)」人などです。これらの固有名詞は、アイヌ語の単語の意味や使用範囲をより詳細に理解するために役立ちます。例えば、「Mongyetsu」はマツマイ島の地域名として記載されており、この地域に特有のアイヌ語が存在していた可能性を示唆します。「Usuro」という地名も、木製の皿の説明において言及されています。 また、「Pavlovich(パヴロヴィッチ)」という人名も、Moromari(モロマリ)というアイヌの村の説明において登場します。 これらの固有名詞は、辞典全体を理解し、アイヌ語の文化的な背景や地理的分布を把握する上で重要な役割を果たしています。 さらに、これらの固有名詞の正確な意味や関連性をより詳細に研究することで、この辞典の学術的な価値がより一層高まります。
