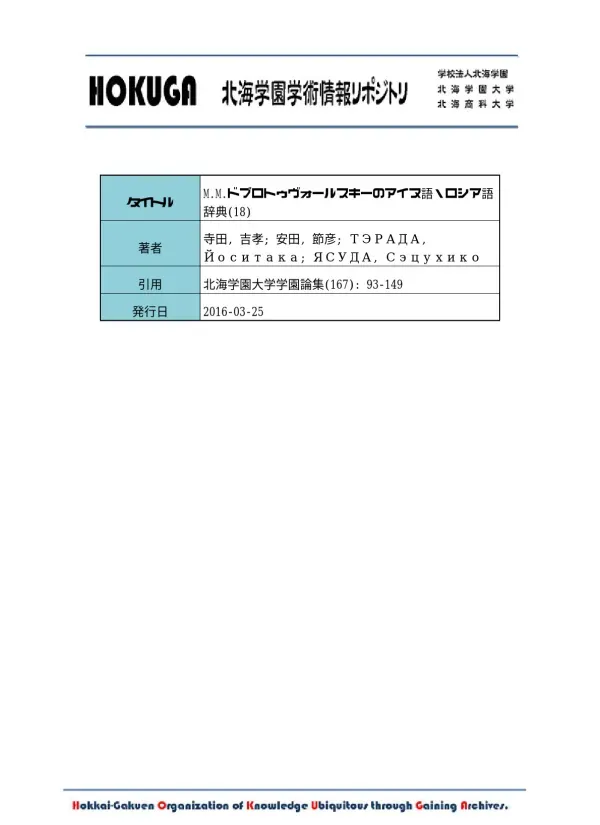
ドブロトゥヴォールスキーアイヌ語辞典翻訳
文書情報
| 著者 | 寺田 吉孝 |
| 専攻 | アイヌ語学、ロシア語学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.95 MB |
概要
I.ダヴィドフのアイヌ語彙集とプフィツマイエールの研究
本資料は、1812年サンクトペテルブルクで編纂された、海軍大尉故ガヴリーラ・ダヴィドフ(Gavriil Davydov)がサハリン半島南端住民の言語から収集したアイヌ語彙集(Ainu vocabulary)のドイツ語訳版に関する記述です。この語彙集は、August Pfizmaier(アウグスト・プフィツマイエール)によって研究され、彼の著作2冊で言及されています。しかし、プフィツマイエールはロシア語原典ではなく、ドイツ語訳を用いていた点が重要です。ダヴィドフの語彙集は、クルゼンシュテルンの世界旅行記(1813年)にも収録されている重要なアイヌ語(Ainu language)の資料であり、サハリンアイヌ(Sakhalin Ainu)の言語研究において基礎的な役割を果たしています。本資料は、その語彙集の翻訳と注釈、特に不明な略語(Dav., Nem., N.)の解明を試みています。これら略語はダヴィドフの語彙集(Davydov's vocabulary)や他の関連資料(related materials)への参照を示唆しており、その解明には原典の調査が不可欠です。関連研究として、1995年発行の『アイヌ語・ロシア語辞典』第85号(Ainu-Russian dictionary)も参照されています。
1. ダヴィドフのアイヌ語彙集の概要
本稿の中心となるのは、1812年サンクトペテルブルクで編纂された、故ガヴリーラ・ダヴィドフ海軍大尉がサハリン半島南端の住民の言語から収集したアイヌ語彙集です。この語彙集は、サハリンアイヌの言語研究において極めて重要な一次資料であり、その内容と背景が詳細に検討されています。特に、語彙集の編纂年代、収集場所、収集者であるダヴィドフの身分、そして語彙集の性質といった点が、このセクションで詳しく説明されています。 この語彙集の存在とその重要性が強調されており、後の研究者、特にアウグスト・プフィツマイエールによる研究への影響が示唆されています。 資料は、このアイヌ語彙集が単なる単語集ではなく、サハリンアイヌの文化や生活を知るための貴重な手がかりとなることを示唆しています。このセクションでは、このアイヌ語彙集の価値と、その後の研究への影響を理解するための基礎的な情報が提供されています。 また、この語彙集が後にドイツ語に翻訳されたこと、そしてその翻訳版がプフィツマイエールの研究に使用されたことも重要なポイントです。
2. プフィツマイエールの研究とその方法
アウグスト・プフィツマイエールは、ダヴィドフのアイヌ語彙集に関する研究を行い、2冊の著作を発表しています。しかし、注目すべきは、彼が研究に使用したのはロシア語原典ではなく、ドイツ語訳であった点です。この事実から、プフィツマイエールの研究が必ずしもロシア語の原文に基づいたものではない可能性、ひいては解釈の差異や誤解が生じる可能性が示唆されます。 プフィツマイエールが利用したドイツ語訳に関する具体的な情報、例えば翻訳者や翻訳の正確性などは、この資料からは明示的に示されていませんが、その存在が研究の解釈に影響を与えていることが強調されています。このセクションでは、プフィツマイエールの研究方法と、それがアイヌ語研究に与えた影響、そしてその方法論的な限界について考察しています。 また、プフィツマイエールが他の言語の単語集、例えば東アジアやアメリカ北西海岸の言語の単語集と比較研究を行った可能性も示唆されています。これは、比較言語学(Comparative Linguistics)的なアプローチが、プフィツマイエールの研究に用いられた可能性を示しています。
3. 未知の省略記号と原典の必要性
本資料では、ダヴィドフのアイヌ語彙集に関する記述の中で、Dav.()、Nem.()、N.()といった複数の省略記号が用いられていますが、その意味が全て明らかになっているわけではありません。特に、N.()の具体的な意味や出典は不明であり、原典の調査が必要であると指摘されています。 これらの省略記号は、ダヴィドフの語彙集、そのドイツ語訳、あるいはその他の関連資料からの引用であると考えられますが、正確な出典を特定するには、更なる調査と資料の精査が不可欠です。 このセクションは、研究における資料の正確さと信頼性の重要性を強調し、未解明な部分が残されていることを示しています。 また、1995年に発行された『アイヌ語・ロシア語辞典』が、ダヴィドフの語彙集やプフィツマイエールの研究に関する情報を提供していることが言及されており、これらの資料の相互参照が今後の研究の進展に不可欠であることが示唆されています。 この部分の解明は、アイヌ語研究(Ainu language research)の精度向上に直結する重要な課題であると言えます。
II.アイヌ語彙集の単語例と解説
資料の中核部分は、約500の単語(多くは「o」で始まる)の翻訳と解説です。各単語には、ダヴィドフの語彙集(Dav.)からの情報、プフィツマイエールの解釈(Pf.)、および他の情報源(Mos., Rud., Kl., Kr.)からの補足説明が記されています。例として、Obitta(すべて)、Ogami-koro(性病)、Oma(置く)、Or ova(〜の後で)、Onye(指尺)などの単語とその意味、語源、文法上の情報が提供されています。ニヴフ語(Nivkh language)からの借用語も含まれています。これらの単語の解説には、アイヌ語の文法や語彙の多様性、および関連する他の言語との関係が示唆されています。それぞれの単語の記述は、アイヌ語研究(Ainu linguistic research)において重要な手がかりとなります。
1. 単語例と情報源の多様性
このセクションでは、ダヴィドフのアイヌ語彙集からの単語例が多数提示されています。各単語には、ダヴィドフ自身による記述(Dav.)、プフィツマイエールの解釈(Pf.)、そしてMos.、Rud.、Kl.、Kr.といった複数の情報源からの補足説明が添えられています。これは、単一の資料に依拠するのではなく、複数の資料を総合的に参照することで、より正確で多角的な解釈を目指していることを示しています。 提示されている単語は、具体的な名詞(例:Obu ssaki-マヌヤの南方にある川とアイヌの村)、動詞(例:Oma-置く、Oma n-去る)、形容詞(例:Oboi-濁った)、副詞(例:Opı sʼ ta-いたるところで)など、多様な品詞にわたっており、アイヌ語の語彙の幅広さと複雑さを垣間見ることができます。 また、ギリヤーク語(ニヴフ語)からの借用語の存在も示されており、アイヌ語と周辺言語との言語接触の歴史や影響を研究する上でも貴重な資料となっています。各単語の記述には、可能な限り複数の情報源からの情報を提示することで、それぞれの単語の意味や用法をより正確に把握しようという意図が読み取れます。
2. 単語解説における多様なアプローチ
単語の解説においては、単なる意味の羅列ではなく、それぞれの単語の語源、文法的特徴、関連語、そして他の言語との関連性といった多様な側面が考慮されています。例えば、Ogami-koro(性病)の解説では、Pf.による解釈として、o、kami(身体)、kots(=koro所有する、取る)といった要素から成る複合語である可能性が示唆されています。 これは、アイヌ語の単語形成に関する知見に基づいた解釈であり、語彙研究における詳細な分析の重要性を示しています。 また、Obitta(すべて)の解説では、複数形を作る働きをすることや、他の言語での対応語との比較がなされています。これは、アイヌ語の文法構造や、他の言語との比較研究による分析の重要性を示唆しています。 このように、各単語の解説は、辞書的な定義にとどまらず、言語学的・文化人類学的知見を踏まえた、多角的な分析に基づいていることが特徴です。 このアプローチは、単なる単語リストではなく、アイヌ語研究(Ainu linguistic research)のための貴重なデータセットを提供しています。
3. 地名 人名 その他固有名詞の扱い
このセクションでは、アイヌ語彙集の中に含まれる地名や人名といった固有名詞も重要な情報として扱われています。 例えば、Obu ssakiやOga kotanといった地名が登場し、それらの地理的位置や関連するアイヌの村落に関する記述があります。これらは、サハリン半島(Sakhalin)におけるアイヌの居住地や生活圏を明らかにする上で重要な手がかりとなり、歴史的地理学(historical geography)や民族誌(ethnography)の研究に貢献します。 また、日本の歴史上の人物である義経のアイヌ語での呼び名(Oki-kurumi)も登場し、アイヌ文化と日本文化との交流の歴史を示唆する要素となっています。 さらに、Ol' chaのように、ギリヤーク語(Nivkh language)からの借用語と思われる単語も含まれており、アイヌ語と周辺言語との関係性を示す重要なデータを提供しています。このように、このセクションでは、アイヌ語彙集における固有名詞の地理的、歴史的、言語学的意義が丁寧に解説されています。
III.地名 人名などの固有名詞
資料には、サハリン半島(Sakhalin)のアイヌの村や地名(Ainu villages and place names)、例えばマヌヤ(Manuya)、クスナイ(Kusunaj)、エビシ(Ebisi)、ナイェロ(Najyero)などが多数登場します。これらは、サハリンアイヌ(Sakhalin Ainu)の居住地や生活圏を示す地理的情報であり、歴史的地理学(historical geography)や民族誌(ethnography)の研究において重要なデータとなります。また、クルゼンシュテルン(Kruzenshtern)、ルダノフスキィ(Rudanovsky)といった人物名も、アイヌ語研究(Ainu studies)の歴史的文脈を理解する上で重要な情報です。これらの固有名詞は、アイヌ語研究(Ainu language research)における空間的・時間的文脈を特定する上で不可欠です。
1. サハリン半島アイヌの地名
この資料では、サハリン半島南端に住むアイヌの人々の生活圏を示す地名が多数登場します。具体的には、Obu ssaki(マヌヤの南方109露里の小さい川とアイヌの村)、Oga kotan(マヌヤの北方1露里のアイヌの村、クスナイの南方238露里のアイヌの村)、Okononaj(クスナイの北方20露里の小川とアイヌの村)、Okonajbu(エビシの南方の川)、Ossyej ga(ドゥーイの南方の岬)などです。これらの地名情報は、当時のアイヌの集落分布や生活空間を理解する上で非常に貴重な史料となります。地名から推測できる範囲では、マヌヤやクスナイといった複数の集落の存在、そしてそれらの集落間の距離関係などが読み取れます。これらの地名情報は、サハリンアイヌの歴史的地理研究(historical geographical research)において重要な役割を果たし、当時のアイヌ社会の空間構造を解明する手がかりとなります。また、これらの地名が、アイヌ語の語彙研究(Ainu vocabulary research)においても重要な文脈を提供している点も注目に値します。
2. 人名と歴史的文脈
資料中には、クルゼンシュテルン(Kruzenshtern)やルダノフスキィ(Rudanovsky)といった人名も登場します。クルゼンシュテルンは、1803~1806年の世界旅行で知られる探検家で、その旅行記にはダヴィドフが収集したアイヌ語彙集も掲載されています。このことは、ダヴィドフのアイヌ語彙集が、当時のロシア帝国による探検や調査活動と密接に関連していることを示唆しています。ルダノフスキィは、『サハリン島の地域観察』の著者として言及されており、彼の研究がダヴィドフの語彙集と関連する可能性が示唆されています。これらの情報は、ダヴィドフのアイヌ語彙集が単なる言語資料ではなく、当時のロシア帝国によるサハリンへの進出や、アイヌ民族に対する研究活動という歴史的文脈の中で位置づけられるべきことを示しています。さらに、義経(Yoshitsune)のアイヌ語での呼び名(Oki-kurumi)も記述されており、アイヌ文化と日本文化との交流を示唆する興味深い例となっています。これらの固有名詞は、アイヌ語研究(Ainu studies)の社会的および歴史的文脈を理解する上で重要な情報を提供します。
3. 地名 人名以外の固有名詞と周辺言語
地名や人名以外にも、資料中には様々な固有名詞が登場します。例えば、Ol' chaはギリヤーク語(ニヴフ語)の単語として言及されており、アイヌ語とニヴフ語との間の言語接触や相互影響を研究する上で重要な情報となります。 また、Osur kuma(ドジョウの一種)のような生物の名前や、Otomushi(チョッキのボタン)のような具体的な物体の名称も含まれています。 これらの固有名詞は、アイヌの生活様式や文化、そして自然環境を理解する上で役立つ手がかりを提供します。 さらに、Kotan-onnye(村)やHajyer o(ナイエロ)といった、アイヌ語彙集における固有名詞の使用方法も示されています。これらは、アイヌ語における空間概念や社会構造を理解するために重要な情報となります。これらの固有名詞は、アイヌ語研究(Ainu linguistic research)において、文化、社会、自然環境といった様々な側面を理解するために必要不可欠な要素です。 特に、周辺言語との関連性が示唆されている単語は、比較言語学(Comparative Linguistics)的な視点からの研究を促すものです。
