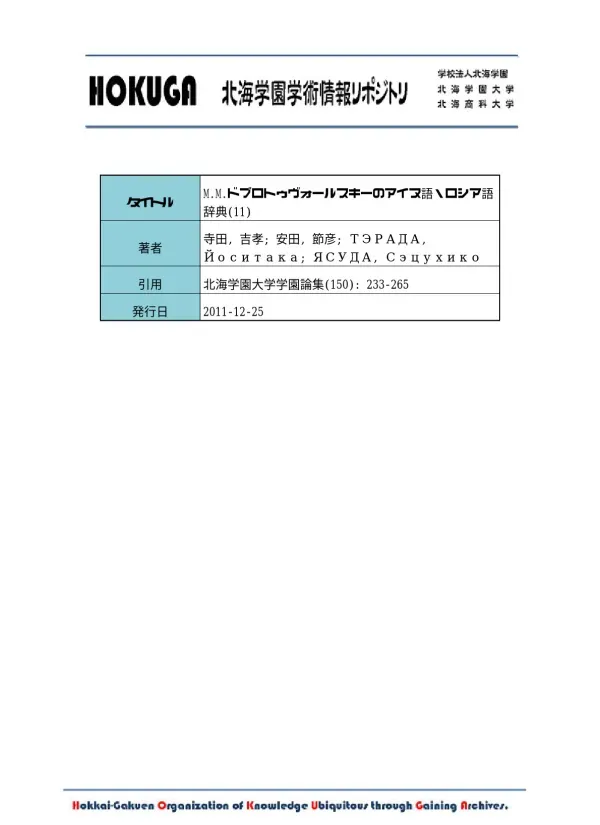
ドブロトゥヴォールスキーアイヌ語辞典:翻訳解説
文書情報
| 著者 | 寺田 吉孝 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | アイヌ語学、ロシア語学、言語学 |
| 場所 | カザン(原文の辞典の出版地) |
| 文書タイプ | 学術論文(北海学園大学学園論集掲載) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.25 MB |
概要
I.アイヌ語彙集 主要語彙の分類と概要
この文書は、主にアイヌ語の単語とその日本語訳、解説を網羅した語彙集です。アイヌ語辞典、アイヌ語彙、アイヌ文化といったキーワードに関連する情報を提供しています。収録されている語彙は、動植物、地名、人物、道具、概念など多岐に渡り、それぞれの語彙には意味、用例、関連語などが記されています。特に、サハリンアイヌ、北海道アイヌの言語や文化に関連する語彙が豊富に含まれています。例えば、地名としては、Inosʼkomanaj、Chyepisani、Manuya、Najbuchi、Kusunkotan、Pyekyeriなどが、動植物名としては、カラフトマス、ギンギツネ、カモメ、ザリガニ、ユリ、オランダイチゴなどが挙げられます。この語彙集は、アイヌ語研究者や、アイヌ文化に興味を持つ学習者にとって貴重な資料となるでしょう。
1. 語彙リストと表記法
このセクションは、アイヌ語の単語リストとその日本語訳を示しています。多くの単語は、Mos.(名詞)、Dav.(動詞)などの品詞表記とともに、意味や用例が記載されています。例えば、「Ibakita. Mos. 外国の、外にある、先端にある。」のように、単語、品詞、そして日本語訳が簡潔に示されています。また、一部の単語には、同義語や関連語が括弧内に示されている場合もあります。「I-e tu nangari. Mos. 誰かに会う、他にietu nankari、誰かを迎えに出る。」のように、複数の意味や表現が提示されている単語も見られます。さらに、原文では女性名詞単数を指す代名詞として記述されているものもあり、詳細な文法的説明も一部に見られます。 分離記号として「・」を使用している点も重要な表記法として挙げられます。これは、例えば「Ik・yup」のように単語を区切るために用いられています。日本語の表現とされている部分もありますが、これは原文に忠実に訳出されていると明記されています。
2. 地名 動植物 その他固有名詞
このセクションでは、地名、動植物名、その他固有名詞を多く含むアイヌ語彙がリストアップされています。地名としては「Ibut. (地)マツマイ(Matsmaj, )のシカリ(Sikari, )河畔のアイヌの村。」のように、具体的な場所を示すものや、「Inausʼ pyekhnaj. (地)ポロペフナイ(Poropyekhnaj, )川の主な(左手の)支流。」のように、より詳細な地理的情報を伴うものがあります。動植物名としては「Ivajsaruspye. (名)トラ(遠い昔にサハリンにいた)。」「Ivaturi. (名)雌鶏。」のように、動物の種類や特徴が示されています。さらに、「Ibopkyerepp. Mos. 植物の名。」のように、植物名も含まれています。これらの固有名詞は、アイヌの人々の生活圏や、彼らが認識していた自然環境を理解する上で重要な手がかりとなります。 特に、サハリン(樺太)に関連する地名や、トラ、カラフトマスといった動植物名は、アイヌ文化とサハリンとの歴史的繋がりを示唆しています。また、マツマイ(Matsmaj)やクスンコタン(Kusunkotan)といった固有名詞は、地域固有の文化や言語変異を研究する上で重要な要素となります。
3. アイヌ語の文法的特徴の例示
このセクションでは、単語の意味だけでなく、文法的特徴の一端も示されています。「I-e (i-i,e-i). Mos. これは協同を表す点では同じであるが、動作が主体の方に向けられる点でu-eと異なる。」のように、類似する単語を比較することで、その微妙な意味合いの違いや、文脈における使い分けが示唆されています。また、「Ibyeru shiuj. Mos. 腹が減っている(ibyeru ― Transitivum,ibye の代わりの尊敬動詞として)、食欲がある。」のように、単語の活用や、尊敬語などの文法的要素が解説されている部分もあります。これらの文法的説明は、アイヌ語の文法体系を理解する上で重要な情報を提供しており、単なる辞書的な意味だけでなく、言語としてのアイヌ語の奥深さを垣間見ることができます。 さらに、「I-unkyeraj. Mos. 贈る、賞として与える(kyeraj 好意から)」のように、語の構成要素や派生関係が示されているケースもあり、語彙の体系的な理解を促しています。 これらの例は、アイヌ語の文法構造や、単語間の関係性を分析する上で貴重な資料となります。
II.アイヌ語の分類と特徴 動詞 名詞 副詞など
文書では、アイヌ語の単語を品詞別に分類し、それぞれの特徴を解説しています。アイヌ語文法の理解に役立つ情報が含まれています。例えば、動詞の活用、名詞の性、副詞の用法などが詳しく説明されています。また、語彙の語源や、関連する他のアイヌ語との関係性についても触れられています。これにより、単なる単語の羅列ではなく、アイヌ語の体系的な理解を促進する内容となっています。
1. 動詞の活用と意味のニュアンス
このセクションでは、アイヌ語の動詞の活用形と、それに伴う意味のニュアンスの変化について考察できます。例えば、「Ibyeri. Dav. ふるまう。Mos. (あるいはibye-ru) 食べさせる、ごちそうする」という記述は、同じ動詞の根幹部分を持つにも関わらず、文脈や文法的要素によって「ふるまう」と「食べさせる、ごちそうする」という異なる意味を持つことを示しています。「I-e karaka-ue. Mos. 着く、来る(⇨ u-e)」のように、別の単語(この場合はu-e)との関連性も示され、単語の意味理解を深める手がかりが与えられています。「Ibyeru shiuj. Mos. 腹が減っている(ibyeru ― Transitivum,ibye の代わりの尊敬動詞として)、食欲がある。」の例では、尊敬語の要素も含まれており、アイヌ語における敬語表現の一端を垣間見ることができます。また、「I-e (i-i,e-i). Mos. これは協同を表す点では同じであるが、動作が主体の方に向けられる点でu-eと異なる。」という比較説明は、単語間の意味の差異を明確に示し、アイヌ語の精緻な表現力を示唆しています。動詞の活用や、同義語・類義語との比較を通して、アイヌ語における動詞の多様な意味と用法を理解することができます。
2. 名詞の性と分類 関連語
アイヌ語における名詞の性や分類、そして関連語についても、このセクションでは確認できます。「Ibautenkye. Mos. 依頼、命令、iba 教え導く、協同行為を示す小詞uおよびtekye 手と意味の等しいtenkyeから。」という記述は、名詞の語源や構成要素を分析することで、その意味をより深く理解させてくれます。また、「⑴原文では(女性名詞単数を指す代名詞)となっている。おそらく女性名詞小詞を指しているのであろう。」という注釈は、名詞の性に関する文法的情報を提供しており、アイヌ語の文法体系の一端を垣間見ることができます。「Iva. Mos. 連山(日本語のiva 岩から)、山の高み。」のように、日本語との関連性も示されており、アイヌ語と日本語の言語的接触を示す例として捉えることができます。さらに、「Ibuj. Mos. 花(単数)、ebujとも言う。」のように、同義語の存在や、単数・複数といった数に関する情報も示されている単語も見られます。これらの例を通して、アイヌ語における名詞の多様な形態や、意味の関連性を理解することができます。
3. 副詞 形容詞等の機能語と文法的特徴
このセクションでは、副詞や形容詞、その他の機能語について、その用法や文法的特徴が示唆されています。「Ikanyebyeka. Mos. きっと、おそらく。」のような副詞は、文のニュアンスを豊かにする役割を果たしており、アイヌ語の表現の柔軟性を示しています。「Ikava. (副) 上方に、上に。―tambye、それは上にある。(名)(板、本の)表、(反)goryeupokhnye.」という記述は、副詞と名詞の両方の機能を持つ単語の存在を示しており、アイヌ語の単語の多義性を示唆しています。また、「I-e-gyets. sye chu. Mos. ため息とともに発音されることば。」という記述は、文における状況や感情表現を補足する機能語の存在を示しています。「Ikonye, あるいはikoni. (形) 病気の、病弱な。Mos.(i goniとも言う)、病気。」という記述では、形容詞と名詞の両方の機能を持つ単語が示され、アイヌ語における単語の多様な用法が示されています。これらの機能語の分析を通して、アイヌ語の文法構造や、単語間の相互作用をより深く理解することができます。
III.アイヌ文化に関連する語彙 儀礼 生活 社会
アイヌ文化に深く関わる語彙も数多く収録されています。例えば、熊祭りに関する語彙(ina u)、儀礼や信仰に関する語彙、衣食住に関する語彙などです。アイヌの伝統、アイヌの儀式、アイヌの信仰といったキーワードに関連する情報が得られます。 これらの語彙の解説を通して、アイヌの人々の生活様式や社会構造、信仰体系の一端を垣間見ることができます。特に、ina uに関する記述は、その種類や用途など、詳細な情報を含んでいます。
1. 儀礼と信仰に関する語彙 ina u と熊祭り
このセクションでは、アイヌの伝統的な儀礼や信仰に関連する語彙が確認できます。特に注目すべきは「ina u」に関する記述です。「Ina u. (名) アイヌの木製の供物、旗。」とあり、その多様な種類と用途が詳細に記されています。「―Iso―、熊祭りのためのinau」、「Nı nʼ-kari―、耳輪のついたinau」、「Nuburi―、山の神への供物」、「Tishye ―、年長の家の神への供物」、「Tusu―、シャーマンのinau」、「Undzhi ―、火の神、あるいは年少の家の神への供物」など、それぞれのina uが異なる神や儀式に関連付けられていることがわかります。これらは、アイヌにおける精霊信仰や、自然との深い関わりを示唆するものです。「ina u」関連の記述は、形状や材質、装飾、さらには配置場所といった詳細な情報も含まれており、アイヌの宗教儀礼を理解する上で極めて重要な資料となります。熊祭り(カムイノミ)に関連する語彙も含まれており、アイヌ文化における熊の特別な位置付けがわかります。
2. 日常生活に関する語彙 衣食住と道具
アイヌの人々の日常生活に関連する語彙も多数含まれています。「Inaci. Mos. (イナシ)、女性用の股引。」は、アイヌの伝統的な衣服に関する記述です。「Imoka. (名) 手みやげ(子供のための)。Mos. 質素な、あるいは白い衣服。」は、衣服の素材や種類を示しています。さらに、「Imushi-ats(イムシアツ). Mos. 負い革、剣帯。」「Imushi-nitsu. Mos. 剣の握り、柄。」といった記述からは、武器や装身具に関する情報が得られます。「Ikunisʼ. (名) 酒を飲むとき口ひげを支えるためのへら(しばしば模様が彫刻されている)。」「Ikusuma. (名) 煙管の灰をたたいて出すための石。」といった、生活用具に関する記述も含まれており、具体的な道具の名称と機能がわかります。「Ik ・ yup. Kl.Kam. 矢筒、箙(えびら)。 」は、狩猟に用いられる道具を示しています。これらの語彙を通して、アイヌの人々の生活様式や、彼らが使用していた道具類について理解を深めることができます。
3. 社会構造と人間関係に関する語彙
このセクションには、アイヌ社会における人間関係や社会構造を反映する語彙が含まれています。「Igokh. (動) igokku (ikhokku)の省略形。商う、売る、買う。―ajnu(あるいは―utara)、商人、商売人。―nu ajnu、商売が上手くいっている人。」は、経済活動や職業に関する語彙です。「Ikoyajryenka. Mos. 挨拶する(お互いに親しいかのように)、お辞儀をする。」は、社会的な相互作用を表す語彙です。「Imontasa. (動) 保つ、集める、生産する(たとえば、農作物)、自らを守る(殴り合いの時)、Chacha-isyam、老人は殴られるままだった(殴り合わなかった)。 」は、社会的な行動や、集団内での役割を示唆する記述です。「Imismoka. Kl. Kam. 怒りっぽい、不機嫌な、退屈している。」のような形容詞は、個人の性格や感情を表す語彙です。これらの語彙を通して、アイヌ社会における人間関係、社会構造、価値観などを推測することができます。特に、「Imontasa」の例は、アイヌ社会における紛争解決や、社会秩序維持のあり方について考察する上で重要な手がかりとなります。
IV.地名 人名に関する語彙 地理的分布と歴史的背景
文書には、アイヌ語で表記された地名や人名に関する語彙が多く含まれています。これらの地名、人名は、サハリンや北海道の特定の地域に関連していることが多く、アイヌの人々の歴史的、地理的な分布を示す貴重な手がかりとなります。このセクションは、アイヌの歴史、アイヌの地理といったキーワードに関連する情報を提供しています。地名や人名に関する記述は、場所の特定や歴史的背景の理解に役立ちます。
1. 地名に関する語彙 地理的分布と地域特性
このセクションでは、アイヌ語で表記された地名とその意味、位置情報などが記載されています。例えば、「Ibut. (地) マツマイ(Matsmaj)のシカリ(Sikari)河畔のアイヌの村。」は、具体的な地名と、その地理的配置を示しています。これにより、アイヌの人々が生活していた地域や、村落の分布状況を推測することができます。「Igyorokakyeum. (地) チェピサニ(Chyepisani)に向かってイノスィコマナイ(Inosʼkomanaj)の近くにある通行困難な絶壁。」のように、地形の特性も示された地名もあり、アイヌの人々の生活環境が自然環境と密接に結びついていた様子がわかります。「Inausʼ pyekhnaj. (地) ポロペフナイ(Poropyekhnaj)川の主な(左手の)支流。」のように、川の名称や位置関係を示す地名もあり、より詳細な地理的情報が提供されています。「Ikusʼ vam ― Pyekyeri. (地) 遠いほうのピェキェリ(Pyekyeri)(話し手の場所から見て);両方のピェキェリ(Pyekyeri)ともマヌヤ(Manuya)の南方13露里にある。」のように、距離や方角といった情報を含む記述もあります。これらの地名情報は、アイヌの居住地や、彼らの生活圏を地理的に把握する上で重要な手がかりとなります。特に、Matsmaj、Sikari、Chyepisani、Inosʼkomanaj、Poropyekhnaj、Pyekyeri、Manuyaといった地名は、アイヌ文化圏の地理的範囲を理解する上で重要です。
2. 人名とそれに関連する語彙 社会構造と信仰
このセクションでは、アイヌの人名、もしくは人名と関連する語彙が記載されています。例えば、「Ivanekhpo. (名) 男の子((同)imaryekhpo)。一方、chikamma(あるいはmirokopu) 女の子。」は、アイヌにおける男女の呼び名を示しています。また、「Igumkuj. Kl. Kam. 船主。」は、職業を示す人名関連の語彙です。「Iko tuki ampa (ajnu), 自分の(酒の)杯を他の人に渡した〜。(同)sokhki-ajnu。」のように、行動や役割を示す記述も人名と関連付けられています。「Ivasuj. (名) 魂がパフナ・シリ(Pakhna-Siri)へ通るための(森の中の)地面の穴。」は、信仰に関連する固有名詞(Pakhna-Siri)を含んでいます。これらの記述から、アイヌ社会における家族構成、社会的地位、そして宗教観などを読み解くことができます。 特に、「Pakhna-Siri」のような固有名詞は、アイヌの宗教や信仰体系を理解する上で重要な要素であり、その存在は、アイヌ文化における精神世界の一端を示しています。これらの情報を通して、アイヌ社会における個人の役割や、社会構造、信仰体系との関わりを理解することができます。
