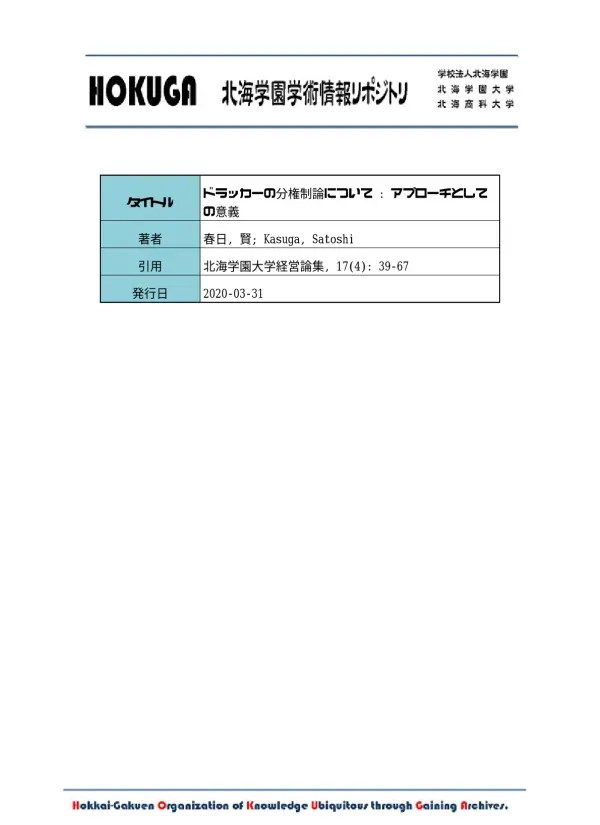
ドラッカーの分権制:自治と自由の経営
文書情報
| 著者 | 春日 賢 |
| 専攻 | 経営学、政治学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 841.10 KB |
概要
I.ドラッカーの分権制論 初期の思想と 企業とは何か
本稿は、ピーター・ドラッカーの分権制 (decentralization) 論を、初期の政治学的思想から『企業とは何か』(原題:The Concept of the Corporation, 1946)における展開、そして後続著作における変遷をたどりながら分析します。初期ドラッカーの権力論、特に権力の集散という視点は、分権制というアプローチの根底にあり、これは政治学的な社会論から導き出されたものです。『企業とは何か』では、GMの内部調査を基に、分権制が広く紹介され、自治(autonomy)と分権制の表裏一体の関係が示唆されています。同書は、自由で機能する社会の実現という社会制度化への試みとして、工場コミュニティの自治を分権制という手法によって実現しようとしたものです。重要なキーワードとして、連邦制(federalism)も挙げられます。これは単なる権限委譲ではなく、各構成単位の本源的自律性を重視する分権制の在り方を示しています。
1. ドラッカーの初期思想と分権制へのアプローチ
本節では、ピーター・ドラッカーの『企業とは何か』(1946)に至るまでの思想的基盤を探り、彼の分権制(decentralization)観の源流を明らかにします。ドラッカーの学問的基盤は政治学にあり、権力論や権力の集散が主要な論点でした。 初期の政治学的社会論から生まれた分権制という視点は、『企業とは何か』において企業組織への応用へと展開され、経営学的な文脈へと移行していきます。 この初期の思想において、既に自由で機能する社会の実現という強い問題意識が存在し、その実現手段として分権制が位置づけられていたことが示唆されます。 この節では、分権制というアプローチが、ドラッカーの思想の深遠な部分に位置づけられていたことを確認し、その後の著作における分権制論の変遷を理解するための基礎を築きます。 特に、分権制と自治(Autonomy)の密接な関係性に注目し、その本質を探ります。 ドラッカー自身の言葉や、彼の思想を理解する上で重要な概念を丁寧に分析し、後の節への橋渡しを行います。
2. 企業とは何か 1946 における分権制の位置づけとGM事例
この節では、ドラッカーの分権制論を広く世に知らしめた代表作、『企業とは何か』(原題:The Concept of the Corporation)に焦点を当て、同書における分権制の位置づけを詳細に分析します。GMの内部調査を基に執筆された本書は、ドラッカー自身の思想にとって大きな転換点であり、その後のマネジメント論に大きな影響を与えました。 本書は、単なる企業論ではなく、ドラッカーが理想とする「自由で機能する社会」の実現という政治社会学的視点を強く持ち合わせています。 ゼネラルモーターズ(GM)の事例は、分権制の実践例として繰り返し取り上げられ、アルフレッド・P・スローンJr. の経営手腕と、GMにおける分権制の成功が強調されています。スローンによる分権制は、単なる経営テクニックではなく、社会秩序の一原則として捉えられており、事業部マネージャーだけでなく、職長を含む全管理職、さらにはディーラーとの関係にも及ぶ広範な適用が示されています。 本書における分権制は、連邦制(federalism)とも表現されており、その本質は自治(Autonomy)にあると解釈できます。 つまり、責任ある選択を行う個人の自治を促進する手法として、分権制が位置づけられているのです。
3. 企業とは何か における自治と工場コミュニティの概念
『企業とは何か』において、ドラッカーが重視するのは、分権制による「工場コミュニティの自治」です。これは、単なる効率性向上のための組織再編ではなく、産業社会における自由と機能性を確保するための社会学的アプローチです。 工場企業体がその構成員に社会的な地位と役割を与え、構成員の責任と意思決定に基づいて権力が行使される時のみ、産業社会は機能し、自由たり得ると主張されます。 これは、19世紀の自由放任主義への回帰でもなければ、総合的な計画経済でもない、現場における分権化された自治に基づく新しい産業組織化の提言です。 この節では、ドラッカーが提示する工場コミュニティの自治の具体的な内容、そしてそれがもたらす効果(円滑なコミュニケーション、労使協調の促進など)を詳細に解説します。 また、本書の結論部分における「自由な産業社会」の実現という最終目標と、その実現のための分権制の役割を明確化します。 これは、ドラッカーの政治思想と経営思想が緊密に結びついていることを示す重要な部分です。
II. 現代の経営 における分権制の展開とMBO
『現代の経営』(原題:Practice of Management, 1954)では、分権制は実践的なマネジメント論の文脈で再考されています。連邦分権制(federal decentralization)と機能別分権制(functional decentralization)の二類型が提示され、前者が理想とされます。しかし、機能別分権制の概念は曖昧であり、議論の不十分さが指摘されています。本書では目標による管理(Management by Objectives, MBO)も提唱され、これは自治の実現手法として位置づけられます。分権制は、多様な自律性を企業全体の業績向上に結びつけるための手段であり、共通の市民意識が不可欠とされます。重要な人物として、アルフレッド・P・スローンJr.(ゼネラルモーターズ)とその分権制モデルが繰り返し言及されています。
1. 現代の経営 におけるマネジメントと社会への関与
『現代の経営』(原題:Practice of Management, 1954)は、一見すると実践的なマネジメント論に見えるが、その本質は社会論にあります。ドラッカーは本書冒頭で繰り返し「マネジメント」を社会的な存在として強調し、社会貢献を第一義的な目的としています。 マネジメントの機能は、事業、経営管理者、働き手と仕事の3つに分類され、その構造や経営管理者の役割が詳細に説明されています。この社会的な機関としてのマネジメント観は、ドラッカーの社会変革への問題意識を反映しており、彼の分権制(decentralization)論もこの文脈で理解する必要があります。 本書では、狭義の分権制に加え、広義の分権制的アプローチが採られており、行為主体の実践的な手法の中に分権化の思想が織り込まれています。 特に、分権制による組織構造の構築方法や、その前提となる「共通の市民意識(common citizenship)」の重要性が論じられています。これは、分権化された組織における統合性と統一性を確保するための重要な要素です。
2. 現代の経営 における分権制の類型と連邦分権制の優位性
本書では、分権制を「連邦分権制(federal decentralization)」と「機能別分権制(functional decentralization)」の二類型に分類しています。 連邦分権制は、独自の製品・市場を持つ独立採算的な事業部ごとに組織を構成する方式であり、可能な限り採用されるべき理想的なモデルとされています。一方、機能別分権制は事業プロセスの段階に応じて組織単位を設置する方式です。 しかし、機能別分権制に関する記述は少なく、その概念の曖昧さが指摘されています。 連邦分権制のメリットとして、経営管理者のビジョンと努力を事業成果に直接結びつけられること、非採算事業の明確化と撤退が促進されること、管理者の育成に効果的であることなどが挙げられています。 機能別組織においても、連邦分権制の原理をできる限り導入すべきだと主張しており、この二つの類型は競合関係ではなく補完関係にあるとされています。 機能別組織の限界を克服し、事業全体の成果に焦点を当てるための組織設計が求められている点が強調されています。
3. MBOと分権制 自律と責任ある選択の実現
『現代の経営』で注目すべき点は、目標による管理(Management by Objectives: MBO)の提唱です。 シアーズやフォードの事例を挙げて、中央集権からの脱却とMBO導入の成功が示されています。 MBOは、メンバー一人ひとりに自由と責任ある選択(Autonomy)を与え、自律的な行動を促す手法として位置づけられています。 これは、分権制によって自由裁量度が増した個人が、自身の目標達成に向けて責任を持って行動することを意味します。 MBOは、分権制における意思決定の中核をなすものであり、個々のレベルでの自治の実践的な手法として捉えることができるでしょう。しかし、ドラッカー自身はMBOと分権制の内的関連性について明確に言及していません。 また、本書では連邦分権制と機能別分権制という二つの類型が提示されていますが、その説明には不明瞭な点があり、特に機能別分権制の概念は曖昧なままです。 この点については、より詳細な分析が必要です。
III.後続著作における分権制と多元社会論
ドラッカーの後続著作では、分権制への直接的な言及は減少しますが、多元社会論、組織社会論、そして独自の国家論といった文脈において、広義の分権制、すなわち権力の分散という考え方が一貫して見られます。『変貌する産業社会』では、近代国家の限界と、民営化(再民営化)のアイディアを提唱し、国家レベルでの分権化を主張しています。この分権制的アプローチは、様々な組織が自律的に機能する社会における重要な概念として位置づけられています。工場コミュニティ(Plant Community)の概念は、後期の著作では職場コミュニティへと変化しますが、自治に関する考察は減少傾向にあります。これはマネジメント概念の成熟による自治概念の統合と捉えることができます。
1. 後続著作における分権制論の変遷と多元社会への展開
この節では、『企業とは何か』(1946)以降のドラッカーの著作における分権制(decentralization)論の変遷を跡付ける。初期の著作では、明確に「分権制」という語が用いられ、その実現手段として工場コミュニティの自治が強調されたが、後期の著作では、分権制への直接的な言及は減少する。しかしながら、彼の思想において、権力の分散という分権化の理念は、多元社会論や独自の国家論といった文脈において一貫して見られる。 これは、単なる組織論の枠を超えた、社会全体のあり方に関する考察へと展開していることを示している。 特に、後期の著作では「多元社会」という概念が重要であり、様々な組織が自律的に機能する社会構造が理想とされている。この多元社会において、各組織は独自の目的と役割を持ち、相互依存的なフラットな関係を築く。巨大組織が社会機能の中枢を担い、中小様々な組織が補完する、多様な組織構造と権力の分散が理想的な社会の姿とされている点が注目される。
2. 現代の経営 以降の分権制とマネジメント概念の統合
『現代の経営』(1954)においては、「マネジメント」という概念が本格的に登場し、その後のドラッカーの著作に大きな影響を与える。 マネジメントは社会的な機関として定義され、その実践は「新しい社会」の実現に向けた取り組みと捉えられる。 この「マネジメント」概念の登場によって、それまでの「工場コミュニティの自治」という概念は、ある程度「マネジメント」の中に統合されていく傾向が見られる。 狭義の分権制に関する考察は減少する一方で、目標による管理(MBO)といった実践的な手法を通して、広義の分権制的アプローチが展開されるようになる。 個人の責任ある選択という、分権制における意思決定のエッセンスが、「マネジメント」概念に統合されていく過程が示されており、後の著作における分権制論の展開を理解する上で重要なポイントとなる。 特に、MBOは、個々のレベルで自治を実践するための具体的な手法として位置づけられるが、ドラッカー自身はMBOと分権制の関連性について直接的には言及していない。
3. 多元社会における国家論と分権化された国家像
ドラッカーの後期著作では、本格的な国家論が展開され、近代国家の限界と、その解決策として分権化された国家像が提示される。 近代国家は、権力の集中による肥大化と機能不全に陥っているという批判がなされ、その解決策として、民間企業における分権制の考え方を国家レベルに適用しようとする試みがみられる。 「民営化」もしくは「再民営化」のアイデアは、この文脈で理解されるべきであり、それは単なる経済政策ではなく、国家における権力分散、すなわち広義の分権制の実現を目指すものである。 政府は、多様な組織から構成される多元社会において、オーケストラの指揮者のような役割を担うべきであり、各組織の自律性を尊重しながら、社会全体の調和を導く存在であると主張されている。 この政府の役割の再定義は、ドラッカーが考える多元的組織社会における理想的な国家像を示しており、彼の分権制論の思想的な深みを理解する上で重要な視点を提供する。
IV.結論 ドラッカー分権制論の統合的理解
ドラッカーの分権制論は、初期の政治学的な権力論と自治の思想に根ざしています。 『企業とは何か』で提示された連邦分権制は、後続著作においても、MBOや多元社会の枠組みの中で発展し、マネジメント論に統合されていきます。 分権制は単なる組織構造ではなく、自由と責任ある選択を実現するための社会制度化へのアプローチであり、工場コミュニティや職場コミュニティの自治を促進する手法として位置づけられています。 彼の思想は、政治学と経営学の橋渡しとなる重要な知見を提供しています。
1. ドラッカー分権制論の全体像 自治と分権制の表裏一体
本論文を通して明らかになったのは、ドラッカーの分権制(decentralization)論が、彼の初期の政治学的思想、特に権力論と自治(Autonomy)の概念に深く根ざしている点です。 彼の生涯にわたる主要なテーマである「自由」と「責任ある選択」の実現という問題意識が、分権制という具体的な手法へと結実しています。 初期の著作では、企業の自治的コミュニティ化という目標を掲げ、その実現手段として分権制が位置付けられていました。 しかし、後期の著作においては、「マネジメント」概念の台頭により、自治に関する議論は減少します。 これは、個人が責任ある選択を行うという分権制のエッセンスが、「マネジメント」という概念の中に統合された結果と解釈できます。 このように、ドラッカーの分権制論は、一貫した思想的基盤の上に、時代や文脈の変化に合わせて発展・変容してきたことが理解できます。 初期の政治学者としてのドラッカーと、後期の経営学者としてのドラッカーの両面を理解することで、彼の分権制論をより深く理解することができます。
2. 分権制の変遷 連邦分権制から多元社会論へのシフト
ドラッカーの分権制論は、初期の『企業とは何か』における連邦分権制(federal decentralization)の提唱から始まり、『現代の経営』では連邦分権制と機能別分権制の二類型が提示されました。しかし、後期の著作では狭義の分権制そのものへの直接的な言及は減少します。これは、彼の思考が多元社会論へと移行し、広義の分権化、すなわち権力の分散という視点がより重要になったためです。 「工場コミュニティ」や「職場コミュニティ」といった、現場レベルの自治の概念も、後期の著作では「マネジメント」概念に統合されていきます。 このシフトは、単なる組織論の枠組みを超え、社会全体の構造と機能に関するより広範な考察へと発展したことを示しています。 彼の分権制論は、単なる組織設計のテクニックではなく、自由で機能する社会、そして多元的な組織社会の実現を目指す、より大きな社会哲学の一部として捉えるべきです。
3. 政治学と経営学の統合 ドラッカー分権制論の学際性
ドラッカーの分権制論を理解する上で重要な点は、その学際的な性格です。彼の思想の出発点は政治学であり、権力論や自治という政治哲学的な概念が、企業組織論や国家論へと応用されています。 初期の著作においては、政治学的な視点が強く、自由な社会の実現という社会学的視点が明確に示されています。しかし、後期の著作では経営学的な視点が強調され、マネジメントという概念が分権制論の中心に位置付けられます。 この政治学と経営学の統合的なアプローチは、ドラッカーの独自性を示すものであり、彼の分権制論の深みと広がりを理解する上で欠かせません。 彼の著作は、政治学、経営学、そして社会学の知見を融合しており、現代社会における組織と社会のあり方について重要な示唆を与えているといえます。 今後、政治学と経営学の両分野からのより深い研究が期待されます。
