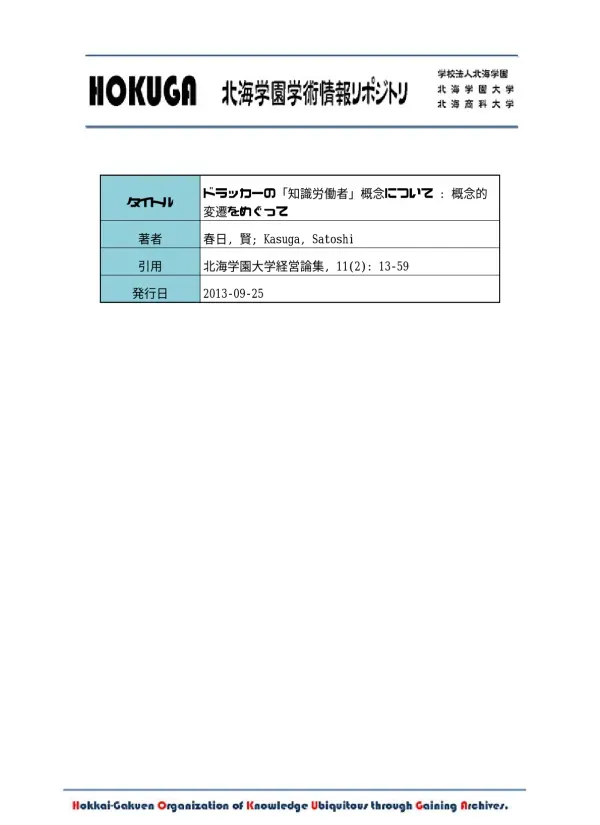
ドラッカーの知識労働者概念:変遷と輪郭
文書情報
| 著者 | 春日 賢 |
| 専攻 | 経営学、社会学、または関連分野 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 894.15 KB |
概要
I.ドラッカーの知識労働者概念 萌芽から本格的誕生へ
本稿は、ピーター・ドラッカーの知識労働者概念の発生から展開、変遷を分析し、その輪郭を明確化することを目的とする。初期のドラッカーは産業社会と産業人という理想像を提示したが、後期には知識社会と知識労働者という概念に転換する。知識労働者は、ドラッカー独自の知識概念の中核をなすものであり、高度な技術発展に伴い注目を集めた新たな人間像である。初期の産業人像とは異なり、知識労働者は避けられない社会状況への適応という側面が強い。この転換は、マネジメントの発明が新しい産業社会の実現に貢献したというよりも、むしろ知識社会への構想転回のきっかけになったと解釈できる。
1. 後期ドラッカーの知識社会構想と知識労働者概念の登場
本稿は、ドラッカーの知識労働者概念の変遷を辿る。初期のドラッカーは、経済至上主義社会(商業社会・経済人)から脱却し、非経済至上主義社会(新しい産業社会・産業人)という望ましい社会像を描いた。マネジメントは、この理想社会実現のための強力な手段と位置づけられていた。しかし、ドラッカーはその後、知識社会と知識労働者という新たな概念へと構想を転換する。これは、マネジメントの発明が新しい産業社会実現の手段になったというよりも、知識社会への構想転換のきっかけになったと解釈できる。後期ドラッカーは、知識社会論とマネジメント論を相即的に展開し、最終的に両者を統合した思想体系を構築した。知識社会、知識労働者、知識という三つの概念は密接に関連し、特に知識労働者は知識社会における新しい個人像として繰り返し強調される。しかし、その概念的範囲は必ずしも明確ではなく、時々の問題意識によってドラッカー自身も柔軟に扱っている点が特徴的である。前期の産業人像が具体的なビジョンであったのに対し、知識労働者は、否応なく適応せざるを得ない不可避のビジョンとして提示されている。そこには、前期に見られた望ましい社会建設への情熱は薄れ、客観的な見通しが淡々と述べられている点が、ポストモダン的なアプローチと言えるだろう。
2. 知識労働者概念の独自性と初期段階における萌芽
知識社会と知識労働者という用語・概念は、ほぼドラッカーオリジナルである。その中核には、ドラッカー独自の知識概念がある。三概念の中で、最初に注目されたのは知識労働者である。技術発展を担う人的主体への注目から、独自の知識概念が形成され、それを担う人間モデルとして知識労働者の着想が生まれた。その着想から、社会構想全体を表す知識社会構想が発展していったと言える。知識労働者概念は、知識社会における新しい個人像として繰り返し説かれるが、その概念的範囲やポイントは必ずしも明確ではない。これは、ドラッカーがその時々の問題意識に応じて概念を便宜的に扱っているためである。知識、知識社会、知識労働者は密接に関連する概念であり、知識労働者の機能と役割が中心的に論じられる。これは、前期において新しい産業社会建設のために産業人が新しい人間モデルとして提示された状況を彷彿とさせる。新しい社会に向けて、人間一人ひとりのあり方を問うという視点は前期と変わらないが、内容的には次元が異なっている。前期は商業社会・経済人の終わりを宣言し、新しい産業社会・産業人を提示したのに対し、後期は、新しい産業社会・産業人の終わりを告げることなく、いきなり知識社会・知識労働者へと移行している。前期の産業人は具体的なビジョンであったが、後期の知識社会・知識労働者は、適応しなければならない不可避のビジョンとして提示されている点が大きな違いである。
3. 新しい社会と新しい経営 における産業中間階級と知識労働者の萌芽
ドラッカーが知識(knowledge)を特別な意味で論じたのは、『変貌する産業社会』(57)が最初であろう。イノベーションの必要性から、知識の意味内容が変化し、新しいものの見方、パターン、態度となったとされる。知識労働者という用語は使われていないものの、後の知識労働者概念の発端と言える記述がある。ドラッカーは、新しい産業中間階級の出現が大量生産社会の社会的発展を決定づけるとし、その割合の大きさを指摘している。この新しい産業中間階級は、非熟練労働から熟練労働への移行という、それまでの50年間の傾向とは逆の現象を示す。機械化が進み未熟練労働者が機械に置き換えられる一方で、それらの機械の設計、組み立て、保守、修理を行う人材が必要となる。この新しいスキルを持つ人々は、機械工などと呼ばれ、それはもはや手作業のスキルではなく、工学原理や製図法などの知識を必要とする知的なスキルである。労働者は、この新しい産業中間階級のメンバーへと転換しつつあるとドラッカーは指摘する。『新しい社会と新しい経営』(50)では、この新しい産業中間階級について、そのルーツを熟練工に求めつつ、監督者、ミドルマネジメント、技術者、職長、エンジニア、セールスマン、会計士、設計技師、工場長などを具体例として挙げている。彼らは、大量生産労働者よりも現代企業の特色であり、企業の神経系・循環系として企業を有効にする組織そのものであると説明している。本書の大部分は、産業秩序という名のもとに労資関係の問題を論じている。新しい秩序の建設によって労資関係を規律づけ、企業をコミュニティ化することで社会の一体性を確保しようとする試みであり、伝統的な労資対立というアポリアを解決しようとする試みと捉えることができる。プロレタリアの廃絶という主張も、この試みの現れと言えるだろう。そして、この新しい産業中間階級こそが、知識労働者概念の萌芽と言える存在である。この段階での知識労働者は、高度な技術的発展とともに社会的な勢力を拡大する新しい階級として位置づけられており、ヴェブレンらの制度学派に見られるテクノクラシーの流れにあることが見て取れる。
II.知識労働者概念の進化 初期段階と本格的誕生
『変貌する産業社会』(57)において、ドラッカーはイノベーションと知識の関係性を論じ、後の知識労働者概念の端緒となる「新しい産業中間階級」の出現を示唆する。この階級は熟練工、技術者、管理者などを含み、大量生産社会における重要な役割を担う。続く『新しい社会と新しい経営』(50)では、この新しい産業中間階級が、知識労働者概念の萌芽と言える存在として描かれる。高度な技術的スキルを有し、企業の神経系・循環系として機能する集団である。 『現代の経営』(54)では、マネジメントの新たな対象として「専門職従業員」が登場、これは後の知識労働者概念に近づく。
1. 変貌する産業社会 57 と新しい産業中間階級 知識労働者概念の萌芽
ドラッカーの知識労働者概念の進化をたどる上で重要なのは、『変貌する産業社会』(57)である。この著作において、ドラッカーは明確に「知識労働者」という用語を用いていないものの、後の概念の萌芽となる重要な要素を提示している。それは、「新しい産業中間階級」の出現である。本書では、イノベーションの必要性から知識の意味内容が変化し、新しいものの見方、パターン、態度へと転換したと論じられている。この新しい産業中間階級は、大量生産社会の社会的発展を決定づける存在であり、労働者階級全体における割合も大きいと指摘されている。興味深いのは、この中間階級の台頭が、それまでの50年間の傾向とは逆、すなわち非熟練労働から熟練労働への移行が始まっている点である。これは、機械化による非熟練労働者の代替と、その機械を設計・保守・修理する高度なスキルを持つ人材の増加というパラドックスを示している。この新しいスキルは、工学原理や製図法、工業数学などの知識を必要とする知的なスキルであり、従来の手作業とは異なる。この新しい産業中間階級のメンバーは、監督者、ミドルマネジメント、技術者、エンジニア、セールスマン、会計士など多様な職種を含み、現代企業の特色を決定づける存在とされている。彼らは企業の神経系・循環系であり、企業を有効に機能させる組織そのものだと位置づけられている。この段階では、知識労働者は、高度な技術的発展に伴い社会的な勢力を拡大する新しい階級という位置づけであり、テクノクラシー的な側面が見て取れる。
2. 新しい社会と新しい経営 50 における知識労働者概念の初期像
『新しい社会と新しい経営』(50)は、知識労働者概念の初期像をより明確に示した著作と言える。この本では、前述の「新しい産業中間階級」が、知識労働者概念の萌芽として位置づけられている。 この中間階級は、熟練工をルーツとし、監督者、ミドルマネジメント、技術者、エンジニアなど具体的な職種が挙げられている。彼らは、企業の神経系・循環系として機能し、企業を有効なものにする組織そのものだと強調されている。本書は「産業秩序」をテーマとしており、労資関係の問題を論じている。ドラッカーは、新しい秩序を建設することで労資関係を規律づけ、企業をコミュニティ化し、社会の一体性を確保しようとしていた。その根底にあるのは、労資対立というアポリアを解決しようという試みであり、プロレタリアの廃絶を唱えている点も注目される。本書で想定される知識労働者は、工学原理や製図法などの知識を持つエンジニアや機械工であり、高度な技術的発展に伴い社会的な勢力を拡大する新しい階級として描かれている。この点は、ヴェブレンら制度学派のテクノクラシー的思想の流れを汲むと言えるだろう。また、この著作では、新しい組織化能力と、専門家、経営者といった知的職業人からなる新しいリーダー集団の出現も指摘されている。これらの知的職業人は、組織に雇用され、組織化される存在でありながら、経営者並みの責任を負っているにも関わらず、報酬や立場では中間階級という特異な集団であると分析されている。このことは、組織の知識と専門的知識が真の生産要素となりつつあり、従来の生産要素(土地、労働、資本)は知識を有効に機能させるための限定条件にすぎないというドラッカーの認識を反映している。
3. 現代の経営 54 における専門職従業員と知識労働者概念への接近
『現代の経営』(54)はマネジメントに関する著作だが、この中でマネジメントの新たな対象として「専門職従業員」が取り上げられている点が重要である。この専門職従業員は、『新しい社会と新しい経営』(50)のような社会階級的な把握ではなく、経営者と一般従業員の中間に位置する、マネジメントに包含される特異な存在として描かれている。この概念は、後の知識労働者概念に非常に近い。 この著作で特筆すべきは、ドラッカーが初めて特別な意味づけをもって知識そのものを取り上げ、哲学的・方法論的な考察を行っている点である。それは知識に関する彼の考察の中でも最も深いもののひとつであり、ポストモダン的な視点の先駆けと言える。デカルト主義世界観=静態的機械論の限界を指摘し、要素還元主義や因果律に代わる新たな哲学・思考方法の必要性を主張している。また、専門職従業員の特徴として、仕事や技能ではなく貢献に焦点を当てること、エグゼクティブとして自己管理を行うこと、職務と企業全体の経済的課題を体系的に遂行することが挙げられている。企業における経営者やプロの貢献者は、産業社会の新しいリーダー的グループとなりつつあると論じられている。さらに、潜在的な経済資源として知識を保有する「知識ある人々」という概念も登場しており、知識労働者には至らないものの、その前提となる人的資源の側面が強調されている。
III.知識労働者像の多面性とマネジメントとの関係
ドラッカーは知識労働者を、肉体的なスキルよりも知識、理論、概念を用いて仕事を行う者として定義する。彼らは専門家、サラリーマン、そして年金基金等を通じて生産手段を所有する資本家の側面も持つ多面的な存在である。知識労働者は、知識社会=組織社会における新たな行為主体であり、組織と対等に協働する自立した個人、すなわち組織人と言える。知識労働者の生産性向上は、マネジメントの重要な課題であり、『マネジメント』(73)では、知識労働者はマネジメントの対象であると同時に、その担い手としても位置づけられる。特に「専門職」「知識専門職」は、企業の業績に大きな影響を与える存在であると強調される。
1. 知識労働者の多面的な側面 専門家 サラリーマン 資本家
ドラッカーの知識労働者像は多面的な側面を持つ。まず、彼らは仕事に知識を用いる職業人、すなわち専門家である。同時に、サラリーマンとしての側面も持ち、組織に雇用されている。さらに、年金基金や投資信託を通じて生産手段を所有していることから、知識社会における真の資本家としての側面も併せ持つ。この三つの側面は、知識労働者という概念を複雑で多層的なものとしている。彼らは組織に依存しながらも、組織と対等に協働する自立した存在であり、新たな組織社会における高度化した個人、すなわち「組織人」として位置づけられる。この知識労働者像は、従来の中間階級概念では捉えきれない、いわば「単一階級」という新たな概念で理解されるべきものであると、本文では述べられている。しかし、ドラッカーによるその説明は必ずしも十分とはいえず、知識労働者概念の定義は、その時々の問題意識や文脈によって微妙に変化している。この複雑性と流動性が、知識労働者概念の理解を難しくしている一つの要因となっている。また、知識そのものについても、活用されてはじめて真の知識となるという点が強調されており、マネジメントとの密接な関係性が示唆されている。
2. マネジメントと知識労働者の相互依存的関係 マネジメントの対象と担い手
ドラッカーの知識労働者概念において、マネジメントとの関係は極めて重要である。知識労働者は、マネジメントの対象であると同時に、その大きな担い手でもある。これは、『マネジメント』(73)で特に強調されている点である。マネジメントは、企業のみならずあらゆる組織体に適用できるものとして体系化され、知識社会論を土台としている。 知識労働者のマネジメントは、単に経営トップのみが行うものではなく、組織内の多くの層、特にミドルマネジメントにおいても重要視されている。従来型のミドルマネジメントとは異なり、新しいタイプのミドルマネジメント、すなわち製造エンジニア、工程の専門家、税理士、マーケットアナリストなど知識専門職の台頭が指摘されている。これらの知識専門職は、企業全体の業績や方向性に大きな影響を与える存在であり、組織内での増加は、組織全体を知識組織へと変質させているとされる。知識組織においては、最下層の専門職からマネジメント層まで、職務は企業の目標に焦点を合わせ、貢献に焦点を当てる必要がある。職務は、情報の流れや意思決定構造に沿って編成されねばならず、伝統的なミドルマネジメントの職務とは異なる多元的なものとして認識されるべきであると主張されている。 つまり、知識労働者は、マネジメントの対象であると同時に、その実践の中核を担う存在であり、両者は相互依存的な関係にあると言える。
3. 知識労働者の生産性向上問題 国家存亡に関わる最重要課題
知識労働者の生産性向上は、ドラッカーが繰り返し強調する最重要課題である。特に、『現代の経営』以降、その重要性は一層増している。知識労働者は、潜在的な生産性は高いもののコストも高い。彼らの生産性を高めるには、個々の強みを把握し、適切な部署に配置することが重要であり、責任の付与と継続的な学習が不可欠であるとされる。知識には責任が伴い、責任を伴わない知識は傲慢ですらあると論じられている。この生産性向上問題は、国家の浮沈にかかわるほど重要な課題であり、知識労働者の生産性が低いままでは、高度な社会・経済は維持できないと警告している。 この生産性向上は、マネジメントの視点からも重要なテーマとなっている。マネジメント自体が、多様な技能や知識を持つ人々を組織で働かせることを可能にした「有用な知識」であり、20世紀のイノベーションであると位置づけられている。 知識労働者の生産性向上に関する議論は、『断絶の時代』(68)から『乱気流時代の経営』(80)まで、一貫して重視されているテーマである。
IV.知識労働者と生産性 そしてテクノロジスト概念の台頭
『乱気流時代の経営』(80)では、知識労働者の生産性向上が最重要課題として強調される。彼らの生産性を高めるには、責任付与と継続学習が不可欠である。 『未来への決断』(95)以降、『明日を支配するもの』(99)、『ネクスト・ソサエティ』(2002)では、テクノロジストという新たな概念が登場する。テクノロジストは知識労働者でありながら肉体労働も担う存在であり、知識労働者全体の核をなす集団として位置付けられる。この概念は、知識労働者とサービス労働者の区別を曖昧にする側面も持ち、ドラッカーの後期思想における重要な転換点を示している。
1. 知識労働者の生産性 最重要課題としての位置づけ
ドラッカーの著作において、知識労働者の生産性向上は、繰り返し強調される最重要課題である。特に『乱気流時代の経営』(80)では、知識労働者の生産性が、国家の浮沈を左右するほど重要な問題として位置づけられている。知識労働者は潜在的な生産性が高い反面、コストも高く、その生産性をマネジメントすることが喫緊の課題となる。そのためには、一人ひとりの強みを理解し、成果に結びつく部署に配置することが必要不可欠である。さらに、責任の明確化と継続的な学習の促進が不可欠であり、知識には責任が伴い、責任を伴わない知識は無責任で傲慢であると強く主張されている。この生産性向上問題は、『断絶の時代』(68)から一貫して議論されており、『変貌する経営者の世界』でも、知識労働者の生産性と満足度の向上が重要な論点として取り上げられている。高度な先進社会・経済において、知識労働者は競争力を獲得・維持するための唯一の生産要素とされ、その生産性の低さが経済的課題として認識されている。また、知識労働者とサービス労働者の生産性向上は、先進国経済の停滞を防ぐために不可欠であると指摘されている。
2. ホワイトカラーと知識労働者 概念の差異と生産性測定の問題
ドラッカーの著作において、「ホワイトカラー」と「知識労働者」の概念的な差異は明確にされていないものの、ホワイトカラーは知識労働者を含むより広義の概念として捉えられている。しかし、ホワイトカラーすべてが知識労働者であるとは限らない点も示唆されている。 『変貌する世界経済』では、知識と資本が肉体労働にとって代わる傾向が加速していると指摘され、「ホワイトカラーの生産性の測定」という章では、知識労働者の生産性測定問題が改めて取り上げられている。ホワイトカラーの生産性測定をそのまま知識労働者の生産性測定に置き換えても問題ない内容であると説明されていることから、両者の概念が密接に関連していることがわかる。しかし、なぜここでホワイトカラーをテーマにしているのかは明確にされておらず、ホワイトカラーと知識労働者の概念的な違いがポイントとなる。この曖昧さは、知識労働者という概念自体の定義の難しさを反映していると言えるだろう。さらに、この著作では知識労働者とマネジメントの差異が強調されており、マネジメントが知識労働者の生産性向上にどう関与するべきかが重要な論点となっている。
3. テクノロジスト概念の台頭 知識労働者像の新たな定義
ドラッカーの後期著作、特に『未来への決断』(95)以降では、「テクノロジスト」という新たな概念が導入される。これは、知識労働と肉体労働の両方をこなす人々を指すものであり、知識労働者像の新たな定義と言える。テクノロジストには、高度な知識を使う者と、知識が中核でありながら肉体労働がメインとなる者とがいる。外科医や事務職員、実験技師などが例として挙げられている。ドラッカーは、知識労働者の多くがテクノロジストであり、彼らが知識労働者の中でも核をなす存在だと主張する。テクノロジストは、知識労働者だけでなく肉体労働者をも含む広範な概念であり、そのルーツは熟練労働者にあるとされる。彼らは知識労働者最大の集団であり、最も急速に成長している集団であるとされ、今後、社会・政治上の支配的な勢力になると予想されている。 しかし、このテクノロジスト概念は、知識労働者概念そのものを曖昧にする可能性も孕んでいる。テクノロジストという概念の導入により、知識労働者の定義がより広範かつ多様になり、従来の知識労働者像とは異なる新たな視点を提示しているが、従来の知識労働者概念を完全に置き換えるものではない。ドラッカーの最晩年に提示されたこのテクノロジスト概念は、その存在意義についてさらなる検討が必要な複雑な概念であると言える。
V.知識社会における知識労働者の位置づけ 総括
ドラッカーの知識労働者概念は、テクノロジーの発展に伴い台頭する専門技術者層から出発し、徐々にその輪郭を明確化していく。知識労働者は、知識を仕事に適用する被雇用者でありながら、プロの専門家、そして資本家の側面も併せ持つ複雑な存在である。知識社会において中心的な役割を担う知識労働者であるが、その概念は著書ごとに微妙な差異があり、特に後期におけるテクノロジスト概念の導入は、既存の知識労働者像を再定義する試みと言える。知識労働者の生産性向上は、知識社会における国家存亡に関わる重要な課題であり続け、マネジメントのあり方と密接に関連している。 知識経済、知識組織といったキーワードも、知識労働者の理解において不可欠である。
1. 知識社会における知識労働者の役割と課題 知識経済と知識組織
ドラッカーは、知識社会において知識労働者が中心的な役割を担うと主張する。知識は、中心的な資本、費用を担う部門、決定的な経済資源となり、労働力、仕事、教授、学習、そして知識そのものの政治的な意味さえも変容させた。知識社会は同時に組織社会であり、知識は個々人や経済全体にわたる主たる資源となる。従来の生産要素(土地、労働、資本)は、知識を有効に機能させるための限定条件にすぎない。専門知識それ自体は何も生み出さず、課題の遂行に向けて統合されることで初めて生産的となる。知識労働者は知識社会における真の「資本家」であると同時に、仕事に頼らなければ生きられない従属者でもある。彼らは教育を受けたサラリーマンという中間層であるが、集団としてみれば年金基金や投資信託を通じて生産手段を所有している。この二重性は知識労働者の複雑な実態を示している。知識労働者の生産性向上は、知識社会における国家存亡に関わる最重要課題とされ、その生産性を高めることが今後の国家の浮沈を左右すると強調されている。知識経済や知識組織といった概念も、この知識労働者の役割を理解する上で不可欠となる。
2. サービス労働者との関係 新たな階級闘争の可能性とマネジメントの責任
知識社会においては、知識労働者とサービス労働者の関係が重要な課題となる。両者は生産性を高める上で共通の課題を持つが、知識、技能、責任、社会的地位、給与において大きな違いがある。知識労働者は高度な専門知識を持つ一方、サービス労働者は定型的な事務的業務に従事する者であり、その多くはホワイトカラーに含まれるが、知識労働者ではない。サービス労働者の多くは低所得であり、知識労働者との格差拡大は、新たな階級闘争を引き起こす可能性も指摘されている。 このため、知識社会におけるマネジメントの第一の社会的責任は、サービス労働者の生産性向上にあるとドラッカーは結論づけている。知識労働者の生産性向上も重要であるが、サービス労働者の生産性向上の方が、より社会的な重要課題だと位置づけられている。知識労働者の生産性向上のためには、明確な使命、適切な配置、継続的な学習と教授、目標と自己管理によるマネジメント、高い要求とそれに応じた責任、そして業績と成果に対する責任などが重要であるとされている。
3. テクノロジスト概念の登場と知識労働者像の再定義
ドラッカーの後期著作では、「テクノロジスト」という新たな概念が登場し、知識労働者像を再定義する試みが行われている。テクノロジストとは、知識労働と肉体労働の両方をこなす者であり、知識労働者の多くがテクノロジストに該当するとされる。高度な知識を使う外科医から、肉体労働がメインとなる事務職員やコンピューターオペレーターまで、幅広い職種を含む。 テクノロジストは、知識労働者の中でも核をなす存在であり、特に「知識テクノロジスト」は、仕事の大半に身体を使う者として定義されている。そのルーツは熟練労働者であり、知識労働者最大の集団として、今後、社会・政治上の支配的な勢力となると予想されている。このテクノロジスト概念は、従来の知識労働者像を拡張するものであり、知識労働者概念の進化を示している。しかし、テクノロジスト概念の導入により、知識労働者とサービス労働者の区別がさらに曖昧になり、知識労働者概念そのものの再定義が必要となる可能性も示唆されている。このテクノロジスト概念は、ドラッカーの後期思想を理解する上で重要な鍵となる概念と言えるだろう。
