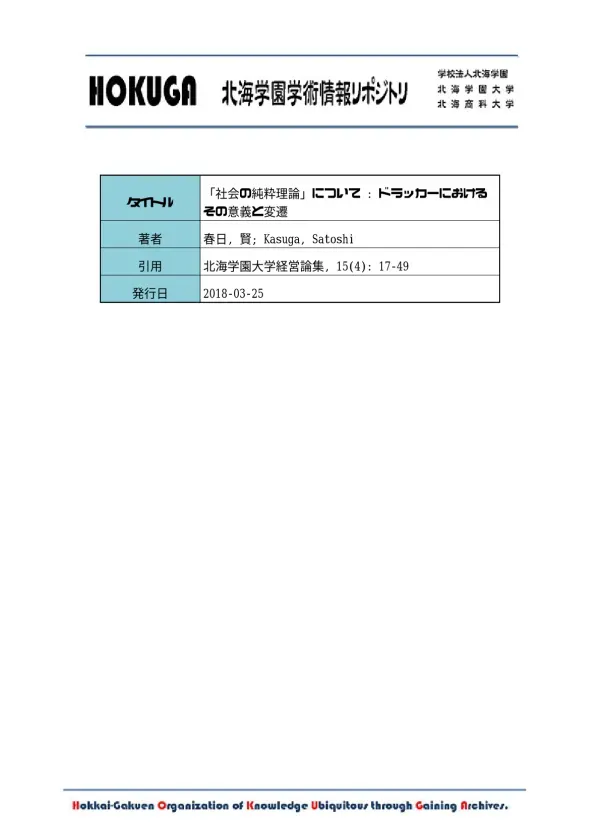
ドラッカーの社会純粋理論:意義と変遷
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 465.44 KB |
| 著者 | 春日 賢 |
| 文書タイプ | 論文 |
概要
I.ドラッカーの社会純粋理論と 産業人の未来
この論文は、ピーター・ドラッカーの代表作である『産業人の未来』(1942年)を中心とし、彼の社会純粋理論を分析しています。ドラッカーは、社会が機能するためには「コミュニティの実現」と「権力の正当性」の二要件が必要だと主張しました。これらのキーワードは、彼の後の著作にも脈々と受け継がれています。
1. ドラッカーの社会純粋理論 二要件の提示
この論文の主題は、ドラッカーの社会純粋理論とその後の著作への影響を分析することです。ドラッカーは、社会が健全に機能するためには、『社会が社会であるために必須の要件』として二つの要件が必要だと主張しました。この社会純粋理論の二要件は、彼の後の著作に影響を与え続け、彼の思想の土台となっています。 特に、『産業人の未来』は、この二要件を明確に提示した唯一の著作とされています。多くの友人や評論家が『産業人の未来』をドラッカーのベストブックと評価していることからも、その重要性がうかがえます。ドラッカー自身も、この本を「もっとも野心的な書」であり、「基本的な社会理論の発展を試みた唯一の書」と評価しており、社会の一般理論と社会の特殊理論の両方を提示したと述べています。特殊理論は、20世紀の産業社会に一般理論の概念を適用したものであり、サブタイトルに「ある保守主義的アプローチ」と記されていることからも、保守主義的な視点をベースにしていることが分かります。保守主義という枠組みの中で、地位と役割、そして正当性がキーコンセプトとして扱われています。フェルディナンド・テニースの『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』に触れ、コミュニティと社会の二面性を産業社会の基本的制度に適用する必要性を強調し、そのための特別な制度が必要であると論じています。このことから、『産業人の未来』は、社会に関する著作として位置づけられることが分かります。
2. 産業人の未来 と戦時下の社会状況
『産業人の未来』は、ドラッカーの著作の中で唯一戦時中に執筆・刊行されたものであり、戦時色が強く反映されています。この著作では、20世紀の産業社会における代表的な社会現象である大量生産工場と株式会社において、社会純粋理論の二要件(コミュニティの実現と権力の正当性)が満たされていない現状を分析しています。大量生産工場では、労働者は機械の一歯車として扱われ、人間としての地位と役割を与えられていません。一方、株式会社では、所有と経営の分離により、社会的に正当な権力ではないとされています。ナチス・ドイツは、戦争を社会目的とすることで、産業組織内の人々を統合し、産業組織の権力を正当化することに成功しました。しかし、この「機能する社会」は戦争の継続という前提に依存しており、自由な社会を犠牲にしているという限界も指摘されています。序文では、西洋人が西洋社会と西洋的な政治信条から疎外されていることを中心的なテーマとしており、ナチス全体主義の興隆をヨーロッパ支配へと導いた、ヨーロッパの社会構造および政治構造の崩壊という歴史的出来事を分析の対象としています。精神的な苦悩よりも、政治・社会・経済的な側面が分析の中心となっています。 先行する『経済人の終わり』との関連性も示されており、『産業人の未来』における社会純粋理論の二要件の萌芽が既に存在していたことが示唆されていますが、権力正当性実現問題への言及はコミュニティ実現問題に比べて少ないとされています。
3. 産業人の未来 におけるキーコンセプト 地位と役割 正当性
『産業人の未来』において、社会純粋理論の二要件、すなわちコミュニティの実現と権力の正当性は、ドラッカーの保守主義的アプローチに基づいて展開されています。 キー・ワードとして、地位(status)と役割(function)、そして正当性(legitimacy)が挙げられます。これらの概念は、彼の保守主義的アプローチと一貫性を持っており、社会の一般理論(=社会の純粋理論)の二要件の普遍性が強調されています。この思想は、社会構想を変えた後期ドラッカーの思想にも通じる、ドラッカー全思想の土台となっています。著者は、この書を「ベスト・ブック」「もっとも野心的な書」と位置付けており、本書への強い自信が感じられます。戦後の社会構想として新しい社会を模索する初期社会論とは異なり、『産業人の未来』は戦時中に執筆されたため、強い戦時色がみられます。フェルディナンド・テニースの『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』は、社会理論と社会学の古典として言及され、テニースが地位に焦点を当てたコミュニティと、役割に焦点を当てた社会を併記したことに対し、『産業人の未来』では、産業社会の基本的制度が両面を備えている必要性を論じています。19世紀や20世紀初頭とは構造的に異なった産業社会の課題・価値・機会を明確に認識していることも強調されています。
II. 産業人の未来 における二要件とナチス ドイツ
『産業人の未来』では、20世紀の産業社会(大量生産工場と株式会社)において、この二要件が満たされていないと指摘。ナチス・ドイツは戦争という社会目的によって、一時的にこの二要件を満たしたものの、自由な社会を犠牲にしたと分析しています。**地位(status)と役割(function)**の重要性が強調されています。
1. 20世紀産業社会における二要件の欠如
ドラッカーは、『産業人の未来』において、20世紀の産業社会を分析し、その機能不全を指摘しています。彼の社会純粋理論における二要件、「コミュニティの実現」と「権力の正当性」が、当時の産業社会、特に大量生産工場と株式会社において満たされていないと主張しています。大量生産工場では、労働者は機械の一歯車として扱われ、人間としての地位(status)と役割(function)が軽視されていると批判しています。また、株式会社においては、所有と経営の分離という構造が、社会的に正当な権力行使を阻害している要因として挙げられています。要するに、当時の産業社会は、個人が社会に属し、意義のある役割を果たせるような仕組みになっておらず、社会の構成員として個人が尊重されていないとドラッカーは見ていたのです。この分析は、単なる経済的な問題ではなく、社会構造そのものの問題として捉えられています。この二要件の欠如が、社会の機能不全、ひいては個人の疎外感につながっていると主張しています。
2. ナチス ドイツ 戦争による二要件の一時的充足
対照的に、ナチス・ドイツは、戦争を社会目的とすることで、この二要件を一時的に満たしたと分析されています。戦争という共通の目的の下、産業組織内の一人ひとりが産業社会に統合され、産業組織の権力が正当化されたのです。つまり、ナチス体制は、強制的な手段ではありましたが、ドラッカーが言うところの「コミュニティの実現」と「権力の正当性」という社会の二つの要件を、ある意味で達成したと捉えられています。しかし、この成功はあくまで戦争という非道徳的な手段によって成り立っており、持続可能性がないことは明白です。戦争を継続する必要性、そして自由な社会を犠牲にしているという点が、この体制の根本的な限界として示されています。ドラッカーは、このナチス・ドイツの例を通して、社会の二要件が満たされない状態が、いかに危険で不安定な社会を生み出すかを示し、真に機能する社会を構築するための課題を提示していると言えます。この分析は、社会純粋理論の二要件が単なる理想論ではなく、現実社会の分析に不可欠な概念であることを示しています。
3. 経済人の終わり との関連性と二要件の萌芽
本文では、『産業人の未来』における社会純粋理論の二要件は、先行する『経済人の終わり』にその萌芽が見られると述べられています。特に、コミュニティ実現問題に関する記述は『経済人の終わり』にも多く見られる一方、権力正当性実現問題への言及は少ないと指摘されています。『経済人の終わり』では、西洋人が西洋社会と西洋的な政治信条から疎外されていることが中心的な主題であり、ナチス全体主義の興隆をヨーロッパ支配へと至らしめたヨーロッパ社会構造と政治構造の崩壊という、特殊な歴史的出来事が分析されています。この分析においては、精神的な苦悩よりも政治・社会・経済が分析の主要な構成要素となっています。 『経済人の終わり』と『産業人の未来』を比較することで、ドラッカーの社会思想の展開が明確になります。『経済人の終わり』では、既にコミュニティの崩壊や権力の問題意識が存在し、それが後の『産業人の未来』でより体系的に社会純粋理論として展開されていることが分かります。しかし、『経済人の終わり』では、地位(status)と役割(function)の概念はまだ明確に整理されておらず、『産業人の未来』において初めて明確な形で提示される点が注目されます。
III. 会社の概念 における社会純粋理論
続く『会社の概念』では、権力の正当性に関する言及は少ないものの、「コミュニティの実現」の問題、特に**産業市民権(industrial citizenship)**が重要なテーマとなっています。アメリカ社会における大企業と自由企業システムの機能性を、**地位(status)と役割(function)**という観点から考察しています。**中間階級社会(middle class society)**の概念も登場します。
1. 会社の概念 における社会純粋理論の焦点 コミュニティ実現問題
『会社の概念』は、ドラッカーの社会純粋理論の二要件のうち、「権力の正当性」に関する記述は少ない一方、「コミュニティの実現」の問題に大きく焦点が当てられています。これは、前著『産業人の未来』の基本的な問題意識を継承しつつ、より具体的な問題設定へと移行したことを示しています。具体的には、アメリカ産業社会における大企業を中心とした自由企業システムをいかに機能させるかという問題が中心テーマとなっています。 ここでは、企業を「社会的制度」と位置づけ、社会的・政治的な分析を通して考察が進められています。分析の枠組みとしては、①自律的なものとしての分析、②社会の信念と約束に照らした分析、③社会の機能的要求との関係における分析という三つの視点が用いられています。特に、社会の信念と約束に照らした分析において、「アメリカの信念」として「産業市民権(industrial citizenship)」の問題が提示され、これが「コミュニティの実現」問題と直接的に結びついています。 『産業人の未来』で提示された地位と役割の問題は、『会社の概念』では「尊厳と実現」という表現で扱われ、その重要性は変わっていません。解決策としては工場コミュニティの形成が示唆されていますが、これはまだアイデアの段階にとどまっているとされています。
2. 産業市民権と中間階級社会 機会均等と地位 役割の統合
『会社の概念』において、重要な概念として「産業市民権」と「中間階級社会(middle class society)」が登場します。産業市民権は、機会均等とワンセットで考えられており、「アメリカの信念」として提示されています。この信念を具現化する場として企業が位置づけられ、企業の社会的機能(social function)が強調されています。この概念は、次の著作『新しい社会』へとつながる重要な橋渡しとなっています。 機会均等と地位・役割という人間的尊厳の特殊な関係、すなわち両者が不可欠な存在であることが強調されています。中間階級社会の実現には、両者が同一の社会的機関で同時に実現される必要があると指摘。一見両立不可能なこれらの要素の統合が、現代企業にとって最大の課題として提示されています。 企業がコミュニティとして果たす社会的機能は、生産者としての経済的機能と同等に重要であるとされ、現代産業社会において個人が社会的な地位と個人的な満足を得るには、企業に所属し仕事をする以外に方法がないという現実が指摘されています。職長と一般労働者を区別し、機会均等を含めた考察がなされており、職長の概念は後の「知識労働者」概念へと繋がっていく重要な萌芽とされています。
3. 工場コミュニティへの期待と限界 企業の社会的機能
『会社の概念』では、社会純粋理論の二要件のうち、権力正当性実現問題はほとんど扱われていません。一方、コミュニティ実現問題は、「産業市民権」という概念を通じて、機会均等とセットで議論されています。企業を社会的制度として位置づけた上で、その社会的機能(social function)として工場コミュニティの形成が提案されています。これは『産業人の未来』の基本的な問題意識を継承しつつ、より具体的な解決策を探る試みと言えるでしょう。工場コミュニティは、労働者一人ひとりに社会的な地位と役割を与えることで、尊厳と実現を満たすための重要な手段とされています。 従来の産業パターナリズムや産業組合主義の失敗を踏まえ、労働者自身の自発的な参加を重視する、主体的アプローチが提示されています。 工場コミュニティの管理を労働者自身に任せることで、多くの労働者にマネジメントの経験を与えることができ、結果として企業にとっても利益になると主張されています。ただし、工場コミュニティ化はあくまでもアイデアの段階であり、その実現可能性や限界についても、ドラッカー自身は認識していたと考えられます。
IV. 新しい社会 における工場コミュニティと二要件の進化
『新しい社会』では、企業を社会的制度と捉え、社会的機能と統治的機能という枠組みで二要件を再解釈しています。工場コミュニティが、コミュニティの実現のための重要な要素として位置付けられ、その自治がマネジメントの権力正当性をも高めると主張しています。地位と役割の獲得は、個人の主体的な行動によってなされるべきだと強調されています。
1. 企業を社会的制度として捉え直す
『新しい社会』において、ドラッカーは企業を単なる経済組織ではなく、「社会的制度」として捉え直します。これは、『産業人の未来』で提示された社会純粋理論の二要件、すなわち「コミュニティの実現」と「権力の正当性」の問題を、より実践的なレベルで考察しようとする試みです。前著『会社の概念』で萌芽的に示されていた企業の社会的機能という概念が、本書ではより体系的に展開されています。企業は、経済的な生産活動を行うだけでなく、社会の一員としての役割を担う存在であり、その機能を社会全体に貢献する形で発揮することが求められていると説いています。 所有と経営の分離という、従来は問題視されていた企業構造を、本書では企業の社会制度化をもたらす要因として肯定的に評価しています。しかし、企業内部の権力関係、つまり統治的機能については、依然として課題が残されていると認識しています。
2. 工場コミュニティの自律性と二要件の充足
『新しい社会』におけるドラッカーの議論の中心は、「工場コミュニティ」です。これは、『会社の概念』で既に触れられていた概念ですが、『新しい社会』では本格的に展開され、産業社会における特有かつ代表的な社会単位として位置づけられています。工場コミュニティは、企業の社会的機能として捉えられ、その自律的な機能が強調されています。 この工場コミュニティの自律的な自治こそが、社会純粋理論の二要件、特に「コミュニティの実現」問題の解決策として提示されています。工場コミュニティにおいて、一人ひとりが地位と役割を獲得し、意義のある生活を送れるようになると考えられています。 従業員一人ひとりが「経営者的態度」を持つことで、工場コミュニティは自律的に機能し、マネジメントの権力も正当化されると主張しています。フーリエやサン・シモン、ホーソン実験などの既存研究も引用され、従業員の関心は経済的なもの以上に、社会的地位と役割にあると論じています。しかし、工場コミュニティの自治が万能薬ではないこと、その限界についても認識している点が重要です。
3. 二要件の統合とマネジメントの役割 秩序論から責任論へ
『新しい社会』では、社会純粋理論の二要件は、企業の「統治的機能」と「社会的機能」という枠組みで再構成されています。 「権力の正当性」問題は、所有と経営の分離を企業の社会制度化をもたらす要因と捉え、肯定的に評価することで、ある程度解消されたとみなされています。しかし、企業内部の権力関係については、依然として統治的機能としての考察が必要です。 一方、「コミュニティの実現」問題は、「社会的機能」として洗練され、工場コミュニティの自治という具体的な姿で提示されています。 従業員は「経営者的態度」を通して、自ら地位と役割を獲得していくべきであり、単に与えられるものではないと強調されています。これは、ドラッカーの思想が「秩序論」から「責任論」へと転換したことを示す重要なポイントです。 従来の労使対立という枠組みを超え、マネジメント、組合、工場コミュニティが三位一体となって、新しい社会が実現すると論じています。この新しい社会像は、企業メンバー一人ひとりが社会的な地位と役割を獲得した状態を意味します。
V. マネジメントの実践 と責任論への転換
『マネジメントの実践』は実践的な側面に重点を置き、目標によるマネジメント(management by objectives and self-control)や分権制といった手法を提示。個人の自主性と責任を重視する責任論への転換が明確に示されています。コミュニティの実現は、個人の主体的な行動と経営者的態度によって達成されるとされています。
1. 行為主体としての個人の自律と責任 目標によるマネジメント
『マネジメントの実践』は、実践的なマネジメント論として、行為主体である個人の自律的な行動を強く強調しています。本書の中心的な主張は、「事業のマネジメントは目標によるマネジメントである」ということです。企業全体レベルから個々人レベルまで、目的や目標の設定を自主的に行わせる手法が提示され、すべての行為主体における自律的な行動を促進する方向性が示されています。「マネジメントの哲学」と銘打たれた「目標と自己統制によるマネジメント(management by objectives and self-control)」は、個人が自身の行動を意思決定できるようにすることを目的としており、個々人を「自由人(a free man)」とすることを目指しています。 分権制や連邦制も、自律的な行動を可能とする組織形態として積極的に提唱されており、個々人の責任、すなわち自己責任と強みの発揮が重要視されています。 本書で提示されている手法やアイデアの多くは、先行する著作で既に提示されていたものですが、『マネジメントの実践』は、それらを具体的な行動へと転換させるための実践的な指針を提供するものです。
2. 社会純粋理論二要件の継承と実践化 責任論への転換
『マネジメントの実践』は、実践書であるため、社会純粋理論の二要件は表面には現れません。しかし、その根底には、社会純粋理論の二要件、特に「コミュニティの実現」問題への強い意識が流れていると分析できます。 権力正当性実現問題についてはほとんど触れられていませんが、「コミュニティの実現」問題への意識は、本書において「実践」として明確に定式化されています。 先行著作で示されていた自主的なアプローチが、本書で実践へと昇華され、労働者一人ひとりが企業活動に主体的に参加することで、自らの地位と役割を自力で獲得していくという考え方が示されています。 これは、ドラッカーの思想全体における「秩序論」から「責任論」への転換を示しています。 「秩序」から「責任」へのキーワードのシフトは、本書以降のドラッカーの著作に一貫して見られる傾向であり、社会論とマネジメント論が並行して展開される中で、ますます明確になっていきます。自己責任論の確立は、社会純粋理論の二要件充足問題の解決へとつながっていくのです。
3. 経営者的態度 と知識労働者の萌芽
本書では、「経営者的態度」という概念が重要です。これは、経営者が全体的視点からマネジメントを行うように、一人ひとりが自身の職務領域を全体と関連付けて捉える姿勢を指します。企業は、メンバー一人ひとりに、彼らが自身の職務・仕事・生産物に対して「経営者的態度」をとることを求めます。 特に、「新しい(産業)中間階級(the new (industrial) middle class)」と呼ばれる層において、「経営者的態度」は重要視されています。この層は、企業の神経系・循環系として企業成果の中枢を担う存在であり、『会社の概念』でその概念的端緒が見られ、後の「知識労働者」へと発展していきます。 この層を中心に、企業メンバー一人ひとりが「経営者的態度」を通して主体的に参加することが、自らの地位と役割を得るための方法であると示唆されています。 経済的成功だけでなく、社会的な地位と役割、そして仕事の意義と尊厳を求める労働者の要求を満たすことが、現代企業にとっての最大の課題であると指摘されています。 労働者一人ひとりが「市民」として企業活動に参加し、責任を持つことが強調されています。
VI.後期ドラッカーと知識労働者
後期ドラッカーの著作では、知識労働者(knowledge worker)の概念が中心となり、社会の純粋理論の二要件は、より実践的な問題として再定義されています。組織社会における個人の責任と役割、そしてNPOによるコミュニティの形成が重要なテーマとなります。**地位(status)と役割(function)**は、もはや同時並列的なものではなく、**機能(function)**重視へとシフトしています。
1. マネジメントの実践 における自主的アプローチと自己責任
『マネジメントの実践』は、ドラッカーの著作の中でも実践的な側面を強く打ち出した書です。本書では、個々の行為主体による自発的な行動が何よりも重要視されており、そのための具体的な手法や考え方が提示されています。目標によるマネジメント(Management by Objectives and Self-Control)が中心的な概念であり、企業全体から個々のメンバーまで、目的や目標の設定を自主的に行い、自律的な行動を促すことを目指しています。 連邦的分権制なども、こうした自律的な行動を可能にする組織形態として提案されています。 本書の中核には、これまでの著作で展開されてきた社会純粋理論の二要件が位置していますが、それは表面的なレベルではなく、より深いところで作用していると言えるでしょう。特に、権力正当性実現問題については、ほとんど言及がありません。しかしながら、コミュニティ実現問題への強い意識は、本書全体を通して感じられます。
2. 社会純粋理論二要件の実践的展開 責任論へのシフト
『マネジメントの実践』は、先行する著作で提示された主要な論点を、実践、すなわち具体的な行動へと転換させたものと言えます。 本書の中心にあるのは、社会純粋理論の二要件ですが、それは直接的に論じられているわけではなく、より実践的なレベルで、特にコミュニティ実現問題の充足が重視されています。 本書では、労働者一人ひとりが企業活動に主体的に参加し、自らの地位と役割を自力で獲得していくという考え方が明確に示されています。これは、ドラッカーの思想全体が「秩序論」から「責任論」へと移行したことを示す重要な転換点です。 「秩序」から「責任」、特に自己責任という概念が、本書以降のドラッカーのキーワードとしてますます重要性を増していきます。 従来の社会論に加え、実践論であるマネジメント論が展開される中で、この傾向は顕著になります。自己責任論の確立は、社会純粋理論の二要件充足問題の最終的な解決へとつながっていくのです。
3. 知識労働者への地ならし 組織における個人の役割と責任
『マネジメントの実践』では、働く者一人ひとりが自らの職務や組織、そして職場コミュニティの社会的課題に対して責任を持つことが重要であると主張されています。 「経営者的態度」や「経営者的視点」といった用語は直接的には使われていませんが、同様の考え方が貫かれています。 本書は、ドラッカー自身のこれまでのマネジメント論の集大成であり、熟成・洗練された内容となっています。 ドラッカー自身も本書を「マネジメントの決定版」と自負しており、その充実ぶりは、マネジメントブームからマネジメント・プロフェッションへの移行を象徴しています。 本書では、未熟練労働者の社会的地位や世界経済のコミュニティ化といった問題にも触れられていますが、組織をコミュニティとはみなしていない点が重要です。 後期ドラッカーの重要なテーマとなる「知識労働者」の概念は、本書ではまだ明確な形では現れませんが、その萌芽と言える要素が見られます。
VII.結論 ドラッカー社会思想の変遷
ドラッカーの著作を通して、社会の純粋理論の二要件(コミュニティの実現と権力の正当性)は、枠組みや用語を変えながらも、彼の思想の根底を貫く重要なテーマでした。初期の地位(status)と役割(function)重視から、後期における知識労働者と責任論への展開をたどり、最終的にはマネジメントの正当性という問題へと収斂されていきます。
1. 社会純粋理論二要件の変遷と知識労働者への焦点移動
ドラッカーの著作全体を通して、社会純粋理論の二要件、「コミュニティの実現」と「権力の正当性」は、常に重要な問題意識として存在し続けていました。しかし、『産業人の未来』で明確に提示された後、その後の著作では、枠組みや用語、概念は変化していきます。初期の著作では、地位と役割、そして正当性が中心的なキーワードでしたが、後期ドラッカーの著作では、知識労働者の概念が中心となり、社会純粋理論の二要件は、より実践的な問題として再定義されていきます。 社会純粋理論の二要件は、マネジメントの正当性実現問題、そしてさらに知識労働者のあり方という問題へと発展的に進化していきます。特に、80年代以降のドラッカーは、知識労働者のあり方に重点を置いています。 初期の著作では、コミュニティ実現問題と権力正当性実現問題はワンセットで論じられていましたが、後期では、それぞれの要素が個別に取り上げられ、全体主義的な社会システムへの批判から、個人の責任と主体的な行動を重視する方向へとシフトしています。
2. 秩序論 から 責任論 へのパラダイムシフト
ドラッカーの思想全体を俯瞰すると、「秩序論」から「責任論」への大きなパラダイムシフトが見て取れます。初期の著作では、社会がどうあるべきかという理想的な社会像(秩序)の提示が中心でしたが、後期になると、個人がどのような責任を持って行動していくべきかという問題(責任)が重要視されるようになります。 このシフトは、『マネジメントの実践』で明確に示され、自己責任論の確立へと繋がっていきます。 後期ドラッカーにおいては、近代国家や政府による社会救済への信仰が終焉し、個人の責任がいかに重要になっているか、そして自ら行動していく必要性が繰り返し強調されます。「自ら行動を起こせ」という呼びかけは、後期ドラッカーの特徴と言えるでしょう。 読者一人ひとりが、これからの社会を担う知識労働者、すなわち望ましい社会実現に向けて行動する主体として位置づけられています。 この責任論は、社会純粋理論の二要件充足問題への解答として位置づけられると共に、知識労働者という新しい時代の人間像を理解する上で不可欠な要素となっています。
3. 組織とコミュニティの再定義 NPOの役割
後期ドラッカーにおいて、組織とコミュニティの関係は再定義されます。 初期の著作では、組織(特に企業)をコミュニティの一形態として捉え、工場コミュニティの形成が理想的な社会像の一部として描かれていました。 しかし、後期になると、組織はあくまでも機能的な存在であり、コミュニティたりえないとされます。代わりに、コミュニティの形成の場としてNPOが重視されるようになります。 組織は成果に基づく機能体であり、純粋なコミュニティにはなり得ない一方、グローバル化の中で人々はコミュニティを求めているという認識から、NPOがコミュニティと共通の目的を与え、市民としての意義のある役割を果たす場を提供すると考えられています。 組織とNPOは、相互補完的な関係にあるとされ、組織が機能的な側面を担う一方、NPOがコミュニティ形成という重要な役割を担うという構図が提示されています。 この組織とNPOによるコミュニティと機能の場を分担するという考え方は、初期のドラッカーには見られない、後期ドラッカーの特徴的な考え方と言えるでしょう。
