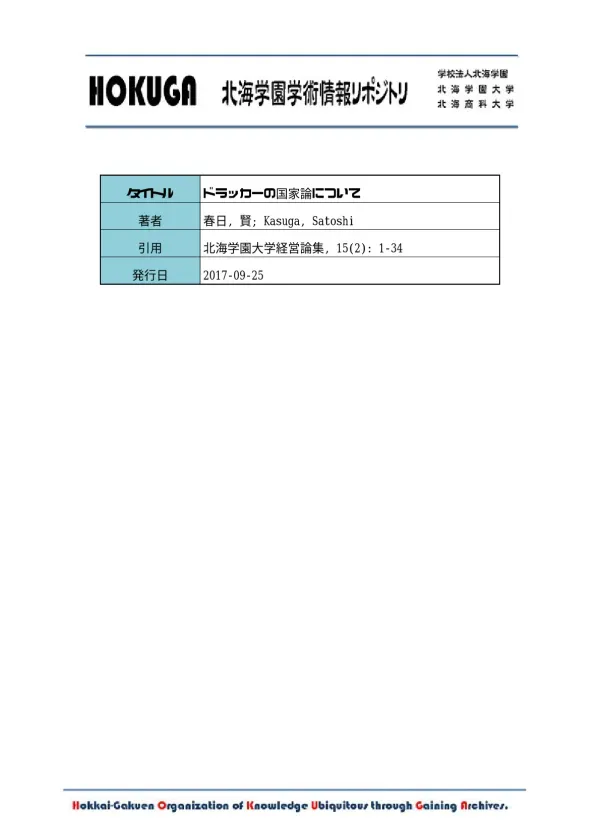
ドラッカー国家論:自由と秩序の探求
文書情報
| 著者 | 春日賢 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.22 MB |
概要
I.ドラッカーの国家論 初期の政治的アプローチ
初期のドラッカーにおいては、国家と権力が中心的な問題でした。彼は自由の実現を重視し、国家はその枠組みとなる一方で、権力集中(専制)すれば自由を脅かす存在とも考えました。そのため、権力の分散、分権化、多元性を生涯にわたって主張しました。これは、彼の国家論の基本的なアプローチです。
1. 国家と権力 自由と専制の対立
初期ドラッカーの国家論の中心は、国家と権力のあり方でした。彼は、理想的な個人と社会の秩序の核心を自由に見出していました。そのため、国家と権力は彼にとって避けられない論点でした。国家は自由を実現するための枠組みと捉えつつも、その権力が間違った方向に向かうと、自由を踏みにじる存在になり得ると警告しました。初期ドラッカーは、専制、つまり権力集中に常に反対し、権力の分散を主張し続けました。この分散という考え方は、分権化、多元化、多様化など様々な言葉で表現され、彼の著作に生涯にわたり登場する基本的なアプローチとなっています。初期ドラッカーの国家論は、自由という理想の実現を阻む専制という脅威への対策として、権力分散という具体的な解決策を提示している点が大きな特徴と言えます。この権力分散という概念は、後年の彼の著作にも脈々と受け継がれ、発展していくことになります。
2. シュタールと保守的国家 ドラッカー国家観への影響
初期ドラッカーの国家論を考える上で、シュタール学説の影響は無視できません。ドラッカーはシュタールが保護主義と歴史の対立という根本的な矛盾を抱えていたと分析しています。そして、シュタールはこの矛盾を「保守的国家」(Konservative Staat)という概念で解決しようとしたと解釈しました。この「保守的国家」とは、人間の最上位にある秩序に基づきつつ、歴史における発展を認め、歴史的に価値のある既存のものを維持し、未来へと継承していく国家像です。ドラッカーは自身の国家観と政治的方向性を、このシュタールの「保守的国家」という概念と重ね合わせています。つまり、ドラッカーの国家観は、人間の不完全さから生まれた自由や諸権利を肯定し保護する存在としての国家像であり、シュタールによる「保守的国家」の解釈は、このドラッカー独自の国家像形成に大きな影響を与えていると言えるでしょう。 しかし、国家が唯一の義務であるべきではないという点も、同時に強調されています。
II.ドラッカーの国家論 シュタールとの関連性
シュタールの学説に内在する矛盾を、ドラッカーは「保守的国家 (Konservative Staat)」という概念で解釈しました。これは、既存の秩序を維持しつつ歴史的な発展を認める国家像です。ドラッカー自身の国家観は、人間の自由と権利を擁護する存在として国家を位置づけています。しかし、国家が唯一の義務ではないと強調しています。
1. シュタール学説の矛盾と保守的国家概念
ドラッカーは、シュタール学説に内在する根本的な矛盾を指摘しています。その矛盾とは、保護主義と歴史的発展という相反する要素が共存している点です。ドラッカーによれば、シュタールはこの矛盾を「保守的国家」(Konservative Staat)という概念で統合しようとしていました。この「保守的国家」は、人間の最上位にある秩序を基礎としながら、同時に歴史的な発展を認め、歴史的に価値のある既存の制度や慣習を維持し、次の世代へと継承していく国家像です。シュタールは、保護主義的な側面と歴史的発展の両立という困難な課題に、保守的国家という概念によってアプローチしようとしたと言えるでしょう。このシュタールの試みは、一見相反する要素を統合しようとする点で、後のドラッカーの国家論にも影響を与えていると考えられます。
2. ドラッカーの国家観 自由と権利の擁護
ドラッカーは、シュタールの「保守的国家」概念を踏まえつつ、自身の国家観を提示しています。彼の国家観において、国家は人間の不完全さから生じる自由や諸権利を肯定し、保護する存在です。国家は、自由や権利を守るという重要な役割を担っていますが、それが国家の唯一の義務ではないことをドラッカーは強調しています。これは、国家権力の限界を意識し、国家による過度の干渉や統制を警戒する姿勢を示しています。シュタールとドラッカーの国家観は、秩序維持と発展の両立という点で共通項を持ちつつも、国家権力の範囲や役割に関して、微妙な違いが見られます。ドラッカーは、国家の役割をより限定的に捉え、個人の自由や権利を尊重する姿勢を明確に示しています。この点が、初期ドラッカーの国家論における独自の視点と言えるでしょう。
III.変貌する産業社会とドラッカーの国家論 後期
『変貌する産業社会』以降、ドラッカーは本格的に後期国家論を展開します。近代政府(modern government)、国民国家(the nation-state)の終焉を指摘し、新しい多元主義(the new pluralism)への移行を主張しました。近代政府は、唯一の権力中枢としての役割を終えつつあり、新たな組織化能力(power to organize)によって、地方政府の崩壊や多様な権力中枢の出現などがその機能不全を招いていると分析しました。
1. 近代政府と国民国家の終焉 デカルト的世界観からの脱却
ドラッカーは、『変貌する産業社会』において、近代政府(modern government)と国民国家(the nation-state)の終焉を論じています。彼は、近代政府が社会における唯一の権力中枢として機能してきたのは、17世紀中頃から19世紀中頃までの約200年間であり、その背景には軍事技術と貨幣経済の発展による職業常備軍と職業官僚の出現があったと分析しています。しかし、近代政府は社会状況の変化、特に「組織化する能力」(power to organize)の台頭によってその土台を蝕まれ、崩壊寸前にあると主張しています。新たな産業社会において生産単位が個人から組織へと移行したことで、国家内部に複数の自律的な権力中枢が生まれ、国民国家としての機能を果たせなくなっているというのです。ドラッカーは、近代政府と国民国家はデカルト的世界観とともに生まれ、その世界観の終焉とともに消滅するとし、新たな世界観に対応した政治的統合と秩序をもたらす機関が未だ存在しない現状を指摘しています。
2. 新しい多元主義への移行 近代国家の限界とアメリカ型多元主義
近代政府の危機を乗り越える方策として、ドラッカーは「新しい多元主義」(the new pluralism)への回帰を提示しています。近代国家の成立は多元主義の崩壊によって起きたため、多元主義への回帰は近代国家の原則を放棄することを意味すると彼は認識しています。しかし、アメリカ合衆国は建国以来多元主義を貫いて発展してきた点を挙げ、アメリカ型の政党制度、高等教育制度、労働組合などをその例として示しています。多元主義には、個々の利益集団が公共の福祉を軽視する危険性があるものの、ドラッカーは公共の福祉と個人の自由の両立のために、新しい多元主義と国家の共存が必要だと主張しています。 この新しい多元主義は、単なる古い多元主義の復活ではなく、変化する社会構造に適応した、より洗練された多元的な政治システムの構築を意味しています。アメリカ合衆国の歴史的経験を踏まえながら、彼は新しい多元主義社会における国家の役割の再定義を促しています。
3. 後期国家論の展開 知識社会における国家の役割
『変貌する産業社会』は、ドラッカーの後期国家論の出発点であり、その後の主要論点を網羅する重要な著作です。国家論におけるキーワードは「多元主義」と「多元社会」であり、これらは知識社会論という枠組みの中で、他の論点と密接に結びついています。ドラッカーは、国内外における国家の変容という観点から論を展開し、国外ではグローバル経済化における国家的枠組みの変容、国内では新しい多元主義=組織社会における国家の役割の変容を論じています。いずれの場合も、主権国家、国民国家、福祉国家、中央政府といった近代国家に対する過信とその限界を指摘し、現実的な力量から国家がなしうることを問い直しています。この後期国家論は、単なる冷戦期の一時的考察ではなく、国家という存在の普遍的な重要性を訴えるものであり、その原型は『明日のための思想』に遡り、『断絶の時代』でさらに本格的に展開されています。
IV.新しい多元主義とグローバル経済化
ドラッカーは、グローバル経済化(global economy)の進展と、それに対応した新しい多元主義の必要性を訴えました。国民国家という枠組みを超えた多国籍企業(multinational corporation)に高い期待を寄せつつ、多元主義は公共の福祉と個人の自由を両立させる重要な政治秩序概念だと主張しました。既存の国民国家、福祉国家、中央政府といった近代国家モデルへの過信と限界を指摘し、新しい現実への対応を迫りました。
1. グローバル経済化の進展と新たな課題
ドラッカーは、世界経済が従来の国際経済(international economy)から世界経済(world economy)へと移行したと指摘しています。これは、個々の国家を単位とする経済から、国家や社会文化の違いを超えた一つの市場へと変化したことを意味します。この新しい世界経済に対応した枠組みや思考は、まだ確立されていませんが、ドラッカーは多国籍企業(multinational corporation)をその例外として挙げています。彼は、多国籍企業が国境を越えた経済圏を創造し、国家主権と現地文化の両方を尊重できる唯一の機関だと高く評価しています。同時に、グローバルマネー(global money)の必要性を訴え、それは超国家的(supernational)である必要はないものの、国家を超えた枠組みが必要であると主張しています。世界経済の統合化が進む中で、国家の枠組みを超えた新たな経済秩序の構築が求められているとドラッカーは分析しています。これは、既存の国際関係や経済理論では対応できない新たな課題を示唆しています。
2. 新しい多元主義の必要性 公共の福祉と個人の自由の両立
グローバル経済化と並行して、ドラッカーは新しい多元主義(the new pluralism)の必要性を強調しています。これは、近代国家の成立が多元主義の崩壊によるものだったという認識に基づいています。多元主義への回帰は近代国家の原則を放棄することを意味するものの、アメリカ合衆国が建国以来多元主義を貫いて発展してきたことを例に、その可能性を示唆しています。アメリカ型の政党、高等教育制度、労働組合などは、多元主義的発展の成果です。しかし、多元主義には、個々の利益集団が近視眼的に自らの利益だけを追求し、公共の福祉を無視する危険性もあります。にもかかわらず、ドラッカーは、公共の福祉と個人の自由の調和のためにも、新しい多元主義と国家を含む様々な組織の共存が不可欠であると結論づけています。この新しい多元主義は、単なる古い多元主義の復活ではなく、グローバル化という新たな現実に対応した、より複雑でダイナミックな社会構造を前提とした、新しい政治秩序概念の確立を目指しています。
3. 多国籍企業と新しい多元主義の連携 グローバルな課題への対応
ドラッカーは、多国籍企業をグローバル経済における重要なプレーヤーとして位置づけ、それらが新しい多元主義と連携することで、グローバルな課題に対応できると考えています。多国籍企業は国境を越えた経済活動を行い、世界市場を形成する上で中心的な役割を果たしています。しかし、世界経済が統合化していく一方で、世界政治は国民国家という単位で分裂しており、国家主権の単位はますます小さくなると彼は分析しています。この経済的現実と政治的現実の乖離は深刻な問題であり、多国籍企業は超国家的連合(transnational confederation)へと発展することで、この乖離を解消する役割を担う可能性があるとドラッカーは期待しています。しかし、同時に途上国の主権喪失という政治的緊張も生じる可能性があり、その点も考慮する必要があると指摘しています。グローバル経済化と新しい多元主義という2つの大きな潮流を踏まえ、ドラッカーは国家の役割や国際関係のあり方を根本的に問い直しています。
V.政府の再生と 小さな政府
ドラッカーは、肥大化した政府の機能不全を指摘し、その再生(reinventing)を主張しました。ケインズ主義的福祉国家(Keynesian Welfare State)の失敗、租税国家の限界を批判し、政府の役割を「実行」から「先導」へと転換すべきだと提言しました。再民営化(privatization)による権力の分散、混合社会(mixed society)の構築が、政府の有効性回復に繋がるとしています。政府は、意思決定者、ビジョン・メーカーとしての役割に集中すべきだと主張しています。
1. 政府の機能不全 肥大化と無能化
ドラッカーは、現代の政府が肥大化し、機能不全に陥っている現状を厳しく批判しています。政府は拡大の一途を辿っていますが、それは真の力強さを示すものではなく、単に組織が大きくなり過ぎた結果、非効率で非力になっているだけだと指摘しています。政府は成果を上げられないにもかかわらず、莫大な費用がかかり、国民からの信頼を失いつつあると分析しています。17、18世紀に出現した近代国家(the modern state)は、それまでの300年間求められてきた政治的コントロールを統合した偉業を成し遂げましたが、現代の政府はそのような力を持っていないとドラッカーは主張しています。現代社会は、活力に満ちた強力な政府を必要としているにも関わらず、現状の政府は「病んでいる」と表現し、その改革の必要性を訴えています。この政府の機能不全は、単なる国内問題にとどまらず、国際的な問題にも影響を及ぼしているとドラッカーは警鐘を鳴らしています。
2. 政府の再生 再民営化と役割転換
政府の機能不全を克服するために、ドラッカーは政府の再生(reinventing)を提唱し、その方法として「再民営化」(privatization)を提案しています。再民営化によって、政府は単なる一つの組織となり、社会を超越した存在ではなく、社会内部に位置づけられるようになります。これにより、これまで分離していた政治理論と社会理論が再び結びつく可能性が開かれます。政府は、多様な社会の「指揮者」として、主要な目的を決定し、各組織に最適な形で課題を配分する役割を担うべきだと主張しています。政府自身は「実行」ではなく「先導」に徹し、民間組織が自主的・自律的に社会課題に取り組む環境を作るべきだと強調しています。これは、政府の役割を、従来の実行主体から、意思決定者、ビジョン・メーカー、政策立案者へと転換することを意味しています。 政府の機能を回復させるために、過剰な拡大や緊張感の欠如を解消し、効率性と効果性を高める必要性を説いています。
3. ケインズ主義批判と 小さな政府 への移行
ドラッカーは、ケインズ主義的福祉国家(Keynesian Welfare State)を批判し、「小さな政府」への移行を提唱しています。20世紀初頭からの「政府への信仰」、つまり政府だけが社会政策・社会活動を有効に推進できるとする信仰は誤りであり、年金基金社会主義の成功例を挙げ、政府よりも民間機関の方が有効だと主張します。政府は政策立案者、ビジョン・メーカー、目標設定者として機能すべきであり、実行は自律的な民間機関に委ねるべきだとします。これは、政府の役割を限定し、民間セクターの活性化を促す「小さな政府」への転換を意味しています。 サッチャー政権やレーガン政権によるケインズ型福祉国家からの「小さな政府」への移行の動きを背景に、ドラッカーは、政府の役割再定義と効率性向上を訴え、市場経済の有効性を強調しています。これは、単なる政府縮小ではなく、より強力で成果を上げる政府を目指すための改革論です。
VI.新しい現実と多元社会
『新しい現実』では、1965年から1973年頃を歴史の分水嶺とし、新しい多元主義、多元社会への移行を分析しました。「社会による救済」(salvation by society)の終焉と経済的利害の連合の終焉を指摘し、主権国家(sovereign nation-state)の終焉と、国民国家が複数の政治的統合単位のひとつとなる未来を予測しました。グローバリズム、地域主義、超国家機関の必要性を論じています。
1. 近代国家の限界と政府の肥大化
ドラッカーは、第二次世界大戦後、急速に肥大化した政府が成果を上げられなくなっている現状を分析しています。特に、近代国家(the modern state)は、それまでの政治的コントロールを統合した偉業を成し遂げましたが、現代社会ではその力が衰えていると指摘しています。政府は拡大する一方で、強力ではなくなり、非効率で成果を上げられない状態に陥っていると批判しています。国民は政府に幻滅し、信頼を失いつつあります。この政府の肥大化は、単なる組織の拡大ではなく、機能不全を招く深刻な問題であるとドラッカーは警告しています。特に、歳入に限界がない「租税国家」の構造が、政府の無制限な支出を招き、無能化を招いていると分析しています。シュムペーターの「租税国家の危機」論を引き合いに出しながら、政府の財政問題の深刻さを訴えています。
2. 政府の再生 再民営化と役割の転換
政府の再生(reinventing)のためには、再民営化(privatization)による政府の役割転換が不可欠だとドラッカーは主張しています。再民営化によって、政府は社会を超越した存在ではなくなり、社会の中核組織の一つに位置づけられます。これにより、長らく分離してきた政治理論と社会理論が再び結びつく可能性が生じます。政府は、多様な社会組織の「指揮者」として、主要な目的を決定し、社会課題を各組織に最適に配分する役割に集中すべきです。政府は自ら「実行」するのではなく、「先導」し、民間組織が自主的・自律的に活動する環境を整備すべきだと説いています。これは、権威主義的な政府から、意思決定者、ビジョン・メーカーとしての役割に特化した政府への転換を意味します。 この転換により、政府の有効性が回復し、社会課題の解決が効率的に行われるようになると期待されています。
3. ケインズ主義的福祉国家の批判と新しい政策アプローチ
ドラッカーは、ケインズ主義的福祉国家(Keynesian Welfare State)を批判し、新たな政策アプローチの必要性を説いています。「政府への信仰」という20世紀初頭の遺産、すなわち政府だけが社会政策を有効に実施できるという信仰は誤りだと主張します。年金基金社会主義の成功例から、民間機関の方が社会政策の推進に有効であることを示しています。政府は、国防や法の執行など、民間機関ではできない役割に集中すべきであり、実行者(doer)ではなく、政策立案者、ビジョン・メーカー、目標設定者として機能すべきだと主張しています。政府と民間機関のそれぞれの長所を生かした混合社会(mixed society)の構築を目指すべきだと結論づけています。 この政府の役割転換は、ケインズ主義からの脱却と、市場経済の有効性への信頼に基づいています。そして、財政赤字の解消と、市民社会の育成が、民主主義国家の課題として挙げられています。
VII.ドラッカーの後期国家論 主要論点の統合
後期ドラッカーの国家論は、『変貌する産業社会』を起点に、『新しい現実』で体系化され、多元主義、多元社会をキーワードに展開されています。国内外の国家の変容、グローバル経済化における国家的枠組みの変容、新しい多元主義における国家の役割の変容などが主要論点であり、これらは知識社会論として統合的に捉えられています。国民国家、福祉国家、中央政府といった近代国家への依存からの脱却、自律的な民間組織への役割分担が強調されています。
1. 後期ドラッカー国家論の全体像 多元主義と多元社会
ドラッカーの後期国家論は、『変貌する産業社会』(1957)を起点に、『新しい現実』(1989)で体系化され、さらに発展しています。その中心となるキーワードは「多元主義」と「多元社会」です。これらの概念は、彼の知識社会論という全体的な枠組みの中で、他の論点と不可分につながっています。後期ドラッカーの国家論は、国内外における国家の変容を主要なテーマとしています。国外ではグローバル経済化における国家的枠組みの変容、国内では新しい多元主義、つまり組織社会における国家の役割の変容が論じられています。いずれも、主権国家、国民国家、福祉国家、中央政府といった近代国家モデルへの過信とその限界を指摘し、国家のあり方を現実的に問い直しています。彼の主張は、近代国家への盲信からの脱却を促し、国家と社会のより現実的で効果的な関係構築を模索するものです。
2. 国内外の国家変容 グローバル化と新しい多元主義
ドラッカーの後期国家論は、グローバル経済化と新しい多元主義という二つの大きな変化を背景に展開されています。グローバル化によって、国家という枠組みを超えた経済活動が盛んになり、国民経済や国境という概念では対応できなくなっています。一方、国内においては、多様な組織が台頭し、多元的な社会構造が形成されています。この変化の中で、国家の役割は大きく変容し、従来の主権国家や福祉国家モデルは限界を迎えているとドラッカーは指摘します。彼は、この変化に対応するために、国家は新しい多元主義に基づいた役割を担う必要があると主張しています。具体的には、国家は、様々な組織を調整し、社会全体のビジョンを示す役割に集中すべきだと提言しています。これは、国家の機能を限定し、民間組織への権限委譲を進めることを意味しています。
3. 知識社会と国家の再構築 多元主義 分権化 そしてマネジメント
ドラッカーの後期国家論は、彼の知識社会論とも深く関連しています。知識社会においては、情報や知識が重要な資源となり、従来の産業社会とは異なる社会構造が形成されると彼は考えました。この知識社会における国家の役割は、従来の「実行者」としての役割から、「意思決定者」、「ビジョン・メーカー」、「目標設定者」へと転換する必要があると主張しています。この転換には、多元主義(pluralism)と分権化、そしてマネジメントの役割が不可欠です。 「新しい多元主義」とは、アメリカ合衆国の多元主義を起源とし、多様な権力を持つ主体が共通の利益に基づいて協力していくシステムを指します。このシステムにおいては、政府は全ての権力を掌握するのではなく、他の組織と協力しながら社会全体の目標達成に向けて貢献していく役割を担います。そして、このシステム全体を効果的に運営するためには、マネジメントの技術が重要になります。
