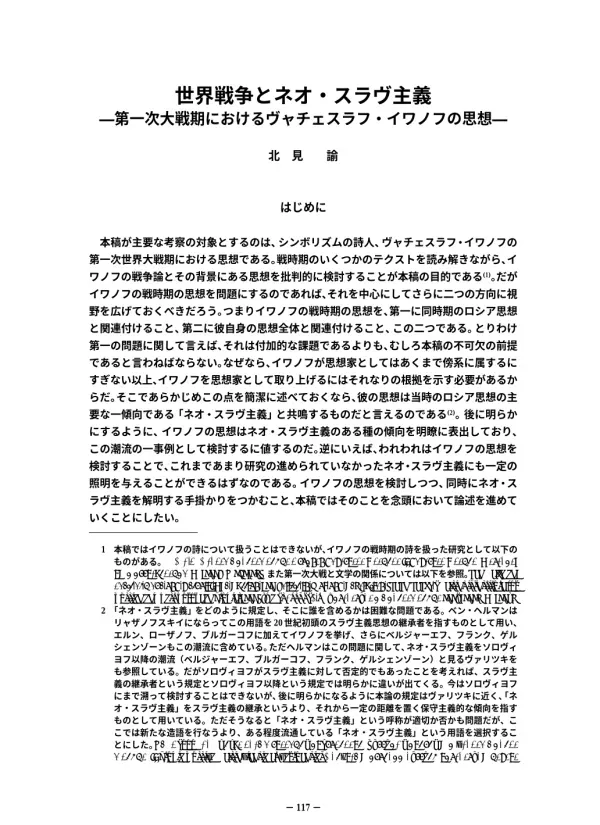
ネオ・スラヴ主義とイワノフ:第一次大戦期の思想
文書情報
| 著者 | 北見諭 |
| 専攻 | ロシア文学、思想史 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 358.21 KB |
概要
I.ネオ スラヴ主義とイワノフの思想 第一次世界大戦期の文脈
本稿は、第一次世界大戦期のヴャチェスラフ・イワノフの思想を、特にネオ・スラヴ主義との関連において分析する。イワノフは傍系の思想家と見なされるが、彼の思想は当時の主要な傾向であるネオ・スラヴ主義と共鳴する。特に、国民論と戦争論が中心的な考察対象となる。イワノフの戦前の美学は国民主体の創出を目的とした政治的なものであり、戦時期の思想へと繋がっている。 1914年10月6日のモスクワ宗教哲学協会講演会(セルゲイ・ブルガーコフ、エルン、ラチンスキイ、エヴゲーニイ・トルベツコイらが参加、セミョーン・フランクが論評)がネオ・スラヴ主義の分析に用いられる。フランクは、戦争を善悪の二項対立で捉える「戦争のスラヴ主義的概念化」を批判し、国民性の本来性を強調する立場(ラチンスキイ、イワノフ、トルベツコイ)を支持した。
1. イワノフ思想の対象と分析枠組み
本稿は、シンボリズムの詩人ヴャチェスラフ・イワノフの第一次世界大戦期の思想を主要な考察対象とする。イワノフの戦争論とその背景にある思想を、複数のテクストを分析することで批判的に検討することが目的である。しかし、イワノフの戦時期の思想を効果的に分析するためには、二つの視点を考慮する必要がある。一つ目は、同時期のロシア思想との関連付け、もう一つはイワノフ自身の思想全体との関連付けである。特に前者、同時期のロシア思想との関連付けは、イワノフが傍系の思想家と見なされるため、彼を思想家として論じるための不可欠な前提となる。この点について簡潔に述べると、イワノフの思想は、当時のロシア思想における主要な傾向の一つである『ネオ・スラヴ主義』と共鳴していると言える。本稿では、イワノフの思想がネオ・スラヴ主義の特定の傾向を明確に示していることを明らかにする。
2. イワノフの戦前 戦時思想の連続性 美学と国民論
イワノフの戦時期の思想を論じる上で、彼の戦前思想との関連性を理解することは重要である。本稿はイワノフの戦時期の思想、特に国民論と戦争論を扱うが、戦前のイワノフの中心的な関心は美学にあった。しかし、彼の美学と政治思想の間に大きな断絶はない。なぜなら、イワノフの美学は、国民主体の創出を意図した政治的な性格を持っていたからである。例えば、国民の無意識を言葉に変換する詩人を育成しようとしたり、ディオニュソス的な悲劇を通して国民という集団的主体の生成を促そうとした試みは、彼の美学が政治的次元を強く持っていたことを示している。国民の問題はイワノフの思想全体に貫流しており、戦前の美学と戦時期の思想を繋ぐ重要な要素となっている。ただし、戦時期の国民論は戦前と比較してより深化している。戦前の美学における国民論は、分裂した国民の統一という内的な問題に焦点を当てていたのに対し、戦時期には、ロシアの国民主体の創出を通して西欧の普遍主義に対抗するという外的な問題が加わった。この深化された戦時期の国民論から振り返ることで、戦前の美学への理解も深まる。
3. イワノフの政治的志向と西欧普遍主義への対抗
イワノフの政治的志向がなぜ国民主体の創出と結びつくのかという疑問が残る。合理的な社会の変革と国民主体の創出には、必然的な関係はない。しかし、戦時期の思想を振り返ることで、国民主体の創出が西欧の普遍主義への対抗意識と不可分であることが理解できる。イワノフは芸術によって合理的な社会を変革しようとしたが、その合理的な社会を、合理性を普遍化しようとする西欧の表象と結び付けていた。逆に、合理性の外部である芸術は、西欧の合理性の外部であるロシアの表象と結び付けられる。イワノフの無意識的な観念連合において、西欧は合理的な社会の代理表象であり、ロシアは合理性の外部である芸術と捉えられていた。芸術による社会変革が国民主体の創出と結びつくのは、この観念連合によるものである。西欧の合理性の外部に位置するロシアの国民主体を確立することが、イワノフにとって芸術による社会変革と等価であったと言える。この点は、戦前の美学のみを検討しただけでは明らかにならない。国民の問題はイワノフの思想全体に遍在するものであり、戦時期の深化された国民論を検討することで初めて完全な理解が可能となる。
4. ネオ スラヴ主義の主要な特徴とモスクワ宗教哲学協会講演会
イワノフの思想を理解するためには、ネオ・スラヴ主義に関する考察が必要不可欠である。本稿では、世界大戦との関連性を中心にネオ・スラヴ主義に焦点を当てる。1914年10月6日に開催されたモスクワ宗教哲学協会の講演会は、この分析に有用である。この講演会にはイワノフに加え、ブルガーコフ、エルン、ラチンスキイ、トルベツコイといった当時の著名な思想家たちが参加し、世界大戦をテーマにした報告を行った。これらの報告とセミョーン・フランクの論評は『ロシア思想』誌に掲載されている。これらの資料を手がかりに、ネオ・スラヴ主義の特徴的な傾向を導き出す。ブルガーコフは、この戦争を近代ヨーロッパの終焉と捉え、ドイツを近代化を徹底した国として批判する。エルンはカント哲学からクルップの兵器製造までを結びつけ、ドイツ軍国主義の根源をドイツ哲学の伝統に見出そうとする。フランクは、これらに「戦争のスラヴ主義的概念化」を見出し、戦争を善悪の二項対立で捉え、ドイツの悪をドイツ国民の本質的なものと見なす傾向を批判する。フランクは、ラチンスキイ、イワノフ、トルベツコイらの、国民性の本来性を強調する立場を支持する。
II.イワノフの普遍主義批判とスラヴのアイデンティティ
イワノフの思想の中核は、普遍主義に対する徹底した批判と、スラヴのアイデンティティの探求にある。ネオ・スラヴ主義と同様、全ての国民性を神聖視するが、それは普遍主義が国民文化の多様性を抑圧するとの認識に基づく。しかし、その批判は、国民の特殊性を神秘化・本質主義化する危険性を孕む特殊主義と表裏一体である。イワノフは、戦時における汎スラヴ主義への傾斜を示し、スラヴの統一を模索する。彼は、経験的な共通性ではなく、実証不可能なディオニュソス的アイデンティティを強調することで、政治的・宗教的統一の欠如を克服しようと試みる。 アポロン的なゲルマン・ロマンス系スラヴと対比される。
1. イワノフにおける普遍主義批判
この節では、イワノフの普遍主義批判を考察する。ネオ・スラヴ主義の思想的傾向である、全ての国民性や国民文化を神聖視するという視点は、イワノフにおいては、普遍主義への徹底的な批判として現れている。イワノフは、一つの原理を世界化しようとする普遍主義が、諸国民の国民性や文化の多様性を抑圧し、隠蔽してしまうと考えていた。しかし、この普遍主義批判は、国民の特殊性を神秘化し、本質主義化する特殊主義の要素を常に伴っているという問題点を孕んでいる。イワノフの普遍主義批判は、一見中立的に見える人間主義をも批判の対象とし、さらにドイツの「文化」概念にも及ぶ。彼は、ドイツが「文化」概念を「市民」「教養」「啓蒙」といった概念に置き換え、他のヨーロッパ諸国民に強制的に押し付けようとしていると主張する。これらの概念も普遍主義的イデオロギーとなりうる危険性があるとイワノフは指摘し、ドイツが「文化」を新たな普遍主義イデオロギーとして利用しようとしていると主張する。西川長夫の文明(civilisation)と文化(Kultur)に関する記述が、このイワノフの主張を裏付けるものとして提示される。
2. スラヴのアイデンティティ ディオニュソスとアポロンの対比
イワノフがロシアではなくスラヴのアイデンティティを問題にする背景には、戦時期における汎スラヴ主義への傾斜がある。しかし、スラヴ世界には政治的統一も、信仰や教養、慣習の統一も存在しないため、統一は容易ではない。イワノフは、この政治的・宗教的統一の欠如を補うため、ディオニュソスという実証不可能なアイデンティティを持ち出す。しかし、それは単なる統一の手段ではない。イワノフは、スラヴには血や言語、心理の共通性があると認めながらも、それらを経験的な事実の共通性に過ぎないと位置づける。真のアイデンティティは経験的事実ではなく、より本質的な、ヌーメン的なものだと主張する。イワノフは、ゲルマン・ロマンス系のスラヴ諸民族をアポロン的、スラヴ民族をディオニュソス的と対比する。アポロン的な諸民族は、秩序と調和を重視するのに対し、ディオニュソス的なスラヴ民族は、奔放な生命力を特徴とする。イワノフはスラヴ人のディオニュソス性を本来的なものとすることで、カント的主体(西欧的人間)から規範性を奪い、スラヴ人を普遍主義の枠組みから解放しようとする。
3. スラヴ主義との関連性と国民共同体の神学化
イワノフは、他のネオ・スラヴ主義者とは異なり、スラヴ主義を積極的に評価する。これは矛盾ではなく、イワノフの視点ではスラヴ主義も国民共同体を神学化しようとした運動と見なせるからである。イワノフは、スラヴ主義を「可想的なルーシを聖なるルーシと見なす、国民的自己規定の形而上学」と定義する。経験的事実に基づく国民論を「現象論」、ヌーメンに基づく国民論を「存在論」と呼び、スラヴ主義は国民の現象論への執着を弁証法的に克服したと評価する。イワノフは西欧的人間をカント的主体と見なし、その内面化された法による自己管理を批判する。一方、ディオニュソス的なスラヴ人は、内面の法を持たないため、西欧の普遍主義的な規範に隷属させられる。イワノフは、カント的主体を相対化することでスラヴ人を解放しようとする。このイワノフの国民共同体を神秘化しようとする傾向は、他のネオ・スラヴ主義者と共通する「国民共同体の神学化」の傾向と捉えられる。
III.ソボールノスチとロシアの特殊性
イワノフは、ロシアの特殊性を担保する概念としてソボールノスチを重視する。ソボールノスチは、当初は自由主義・社会主義の代替案として位置づけられていたが、戦時下ではロシア固有の、他国民には理解不可能な特殊性を表す概念へと転化する。 これは、ドイツの「文化」を新たな普遍主義イデオロギーと見なすイワノフの批判と関連する。イワノフは、オストワルドの世界史観(群棲→個人主義→組織)を批判し、ソボールノスチを対置することでロシアの特殊性を主張する。 ローゼンタールのソボールノスチに関する記述も参照される。
1. ソボールノスチの概念と初期の機能
この節では、イワノフ思想における中心概念である「ソボールノスチ」について考察する。ローゼンタールを参照すると、ソボールノスチは本来、キリスト教神学における教会概念であり、全信仰者の結合を意味する。しかし、それを世俗的な社会理論として応用するのはロシア独自の現象であり、スラヴ主義のホミャコフから始まり、20世紀初頭には宗教的ルネッサンスの支持者によって急進化された。彼らの理論では、ソボールノスチはメンバーの個性を失うことのない、愛と信仰によって結合した自由な共同体であり、社会主義や自由主義への代替案とされた。イワノフにおいても、ソボールノスチは個人主義や社会階級を解体し、国民を全体化しようとする共同体概念として機能する。初期においては、自由主義や社会主義に対する実現可能な代替案として位置づけられていた。
2. 戦時期におけるソボールノスチの変容 ロシア特殊性の担保
しかし、戦時期においてはソボールノスチの機能は変化する。もはや自由主義や社会主義の代替案ではなく、ロシア人の内面にのみ先験的に備わり、直観的に了解される特殊ロシア的な国民的社会体制を表す概念となる。外国語には翻訳不可能で、他国民には理解できないため、他国民に強制することもできない。自由主義や社会主義がロシアに適用できないのと同様に、ソボールノスチも他国民には本来性を持たない。戦時期のイワノフにとって、ソボールノスチはロシア起源の普遍的な社会理論ではなく、ロシアの特殊性を保証し、普遍主義の規範からロシアを免れるための機能を果たす。イワノフは論文「レギオンとソボールノスチ」において、ドイツが「文化的組織」を普及させようとする試みを批判し、ソボールノスチを対置することでロシアの独自性を擁護する。オストワルドの世界史観(群棲→個人主義→組織)を批判し、ソボールノスチを対置することでロシアの特殊性を強調する。
3. ソボールノスチとドイツの普遍主義への対抗 特殊性の原理
ソボールノスチは、ドイツの普遍主義を相対化するための機能を持つ。ロシア国民の内面に先験的に存在し、自由主義やドイツの組織と置き換え不可能であり、それらの未発達な形態でもない。イワノフは、ディオニュソスをアポロンに対置したように、ソボールノスチをロシアの本来的な社会体制とすることで、ドイツが普遍的とする「組織」から規範性を奪おうとする。戦時期のイワノフにとって、ソボールノスチは偽りの普遍主義に対抗するロシアの特殊性の原理となる。ソボールノスチはスラヴ人の内面に先験的に備わり、スラヴ人には直観的に理解できるにもかかわらず、外国語には翻訳不可能なため、他国民には理解できない。ソボールノスチは、スラヴのアイデンティティそのものであるとイワノフは主張する。このソボールノスチの概念が、オブジェクトレベル(ロシアの共同体)とメタレベル(世界秩序)で用いられ、論理的な水準の混同が生じている点を指摘する必要がある。
IV.イワノフの戦争論 二つの全体性
イワノフの戦争論は、聖戦論とは異なる独自なものである。彼は戦争を宗教的な出来事と捉え、ドイツをアンチ・キリスト、ロシアをキリストに喩える。しかし、彼の戦争論はメシアニズムではなく、空間的な全体(ミロヴォイ/всемирный)と深層的な精神的全体(вселенский)という二つの全体性を想定することで特徴づけられる。ドイツは空間的な全体を、ロシアは精神的な全体を追求する。西谷修のヘーゲルの歴史終焉に関する解釈も参照される。 イワノフにとって、世界戦争は、歴史を超越した先験的な秩序、世界秩序としてのソボールノスチを確立する契機となる。
1. イワノフの戦争論 聖戦論からの差異
イワノフの戦争論は、一見聖戦論のように見えるが、決定的に異なる点がある。彼は戦争を宗教的に解釈するものの、ドイツをアンチ・キリスト、ロシアをキリストに喩える表現を用いながらも、それはスラヴ主義的な聖戦論とは異なる。イワノフは、ドイツの「文化」を人間の最高の価値とする主張を批判し、無神論的な幸福を約束して諸国民を誘惑する大審問官とみなす。一方で、「われわれはキリストの十字架とともにあり」、「この神聖なる日々に、我らの祖国は全教会的=世界的な事業を成し遂げつつある」と主張する。しかし、この「全教会的=世界的(вселенский)」という表現が重要である。これは、単なる空間的な全体(ミロヴォイ/всемирный)の領有をめぐる争いではなく、それとは異なる深層的な精神的全体(вселенский)への働きかけを意味する。ドイツは空間的な全体を領有しようとする侵略行為を行なうが、ロシアは空間的な全体ではなく、深層的・精神的な全体、すなわちвселенскийな全体に働きかけている。
2. 二つの全体性 空間的全体と精神的全体
イワノフの戦争論は、空間的な全体と深層的な精神的な全体という二つの全体性を想定することで特徴づけられる。前者は、経験的な事実に基づく可視的な全体であり、恣意的な分割や境界変更が可能で、偽りの普遍主義を生み出す。後者は、経験的な事実から遊離した、無意識的な本質に基づく全体であり、主観的な構成を許容する。スラヴ主義的な戦争論は、西欧的原理の崩壊後にロシア的原理が世界化するという空間的な全体(ミロヴォイ/всемирный)の領有をめぐる争いを想定するが、イワノフの戦争論は異なる。ドイツとロシアは同じ地平に立っていない。ドイツは空間的な全体を領有しようとするが、ロシアは精神的な全体に働きかける。たとえドイツが地球全体を制覇しても、ロシアが追求する精神的な全体はドイツの手には届かない。西谷修のヘーゲルの歴史終焉に関する解釈が、この二つの全体性の理解に役立つとされる。西谷は、ヘーゲルの歴史を人間による世界の人間化過程と捉え、その全体化を歴史の終焉と定義するが、それはナポレオンが象徴するヨーロッパの全体性に過ぎなかったと指摘する。
3. 世界戦争 歴史を超越した段階への移行とソボールノスチ
イワノフにとって、世界戦争は単なる空間的な領土争いではなく、人類が歴史を超越した先験的な秩序を確立するための契機となる出来事である。戦争が始まってからの三ヶ月間を「深淵」や「時間の穴」と表現する箇所は、世界が外面的な歴史の段階から歴史を超越した段階へ移行したことを示唆する。世界戦争という「敷居」の先には、深層的・精神的なвселенскийな全体が開かれ、そこに自己の無意識的な本質を自覚した諸国民による世界秩序としてのソボールノスチが確立されるとイワノフは考える。この移行を実現することが、ソボールノスチの意味を直観的に把握できるロシア国民の使命となる。空間的な全体を領有しようとするドイツの侵略を阻止することは、諸国民が自らのヌーメン的本質を把握し実現するための媒体である固有の空間を守るためにも重要であるとイワノフは主張する。ゲルシェンゾーンが批判されるのも、過去への回帰が歴史の平面からの脱出にならないからである。
4. イワノフ戦争論のまとめと批判的検討
イワノフの国民論と戦争論は、国民共同体の神学化によって、ロシア中心主義に陥ることなく、諸国民の平和共存を理想とする。戦争論は、空間的な全体に深層的な全体を対置することで、恣意的な再分割を許さない世界秩序を構築しようとする試みである。しかし、国民共同体の神学化は、ネーションに回収されない差異や矛盾を抑圧する問題点を抱える。また、ソボールノスチの原理が世界秩序にも適用されることで、新たな普遍主義に陥る危険性がある。イワノフは同化主義的な普遍主義を批判するが、ソボールノスチを特殊ロシア的なものにとどめつつ、世界秩序にも適用しようとすることで、矛盾が生じる。イワノフが時代状況を思想的に問題化していることは認められるものの、国民共同体の神学化と、特殊主義という新たな本質主義への陥穽を指摘する必要がある。結論として、イワノフの戦争論は、ネオ・スラヴ主義的な視点から、歴史を超越した精神的全体性の構築を目指したものであったが、同時にその思想的限界も指摘される。
V.イワノフ思想のまとめと今後の課題
イワノフの思想は、国民共同体の神学化という傾向によって特徴づけられる。これは、ネオ・スラヴ主義全般に見られる傾向であり、国民共同体を先験的に定められた、変更不可能な統一体と見なすことから生じる。 この傾向は、国民的同一性の根拠を「歴史」から「無意識」へと転換することで顕著となる。イワノフの思想は、この二項対立(歴史/無意識)によって方向づけられている。 批判点としては、国民共同体の神学化による差異の抑圧と、新たな普遍主義への転落の可能性が挙げられる。今後の課題としては、「国民共同体の神学化」の背景にある時代状況の分析、そしてイワノフの美学と政治の相互作用の解明が挙げられる。
1. イワノフ思想の主要な特徴とネオ スラヴ主義との共通性
本稿では、ヴャチェスラフ・イワノフの第一次世界大戦期の思想を、国民論と戦争論を中心に多角的に考察してきた。その全体像を捉える上で重要なのは、イワノフの思想とネオ・スラヴ主義との共通性である。両者の思想の根幹には、「国民共同体の神学化」、すなわち国民共同体を先験的に定められた変更不可能な統一体と見なす傾向が存在する。この傾向から、諸国民の平和共存を理想化し、普遍主義やメシアニズムを批判する姿勢が派生する。彼らは、全ての国民共同体を神聖で変更不可能なものと見なしていた。この「国民共同体の神学化」は、国民的同一性の根拠を「歴史」から「無意識」へと転換した結果として現れた。歴史は経験的・現象的・可視的なものを表し、無意識は先験的・超越的・不可視なものを表す。この二項対立がネオ・スラヴ主義とイワノフの思想を貫いている。経験的な歴史を超越する先験的な無意識を想定し、その本質を国民共同体に見出すという傾向が、ネオ・スラヴ主義とイワノフ思想を繋ぐ。
2. イワノフ思想への批判的検討 二つの主要な問題点
イワノフ思想への批判的検討は、大きく分けて二つの点から行われた。第一は、ネオ・スラヴ主義全般に言えることだが、国民共同体を先験的な統一体と見なすことで、ネーションに回収されない多様な差異や矛盾が抑圧されてしまう点である。「国民」を無意識的な本質と同一視することで、歴史的に生成した「階級」を二次的なものと見なすのは、その典型的な現れである。また、イワノフは普遍主義の本質主義的傾向を批判する一方で、特殊主義という新たな本質主義を生み出してしまう。これは、国民を変更不可能な本来性と見なすことに由来する。第二は、イワノフの世界秩序の理念が、新たな普遍主義に陥る危険性がある点である。彼は同化主義的な普遍主義を批判し、ソボールノスチを特殊ロシア的なものにとどめるが、そのソボールノスチの原理を世界秩序にも適用することで、矛盾が生じる。
3. 今後の課題 神学化の背景と美学 政治の相互作用
今後の課題として、二つの点が挙げられる。一つ目は、「国民共同体の神学化」の背景にある理由の解明である。時代状況、すなわち世界の植民地化の完了と世界全体の化、そしてロシアにおける階級化の進展と対立の激化が、国民を神聖視する傾向を生じさせた重要な要因と考えられるが、詳細な検討が必要である。ネオ・スラヴ主義の総合的研究も必要となる。二つ目は、イワノフの戦前美学の政治的志向と、戦時期の思想における普遍主義批判との関係の解明である。イワノフの思想では、美学の政治化だけでなく、政治の美学化も考慮しなければならない。戦時期の思想には美学が直接介入しないものの、両者は切り離せない。戦争論における二つの全体性(空間的な全体と精神的な全体)は、この美学と政治の相互作用を示唆する。経験的な空間的な全体は自然の必然性を伴い、主観的構成を拒絶するが、イワノフが仮構する精神的な全体は主観的・美的な構成を許容する。この政治の美学化については、慎重な検討が必要である。
