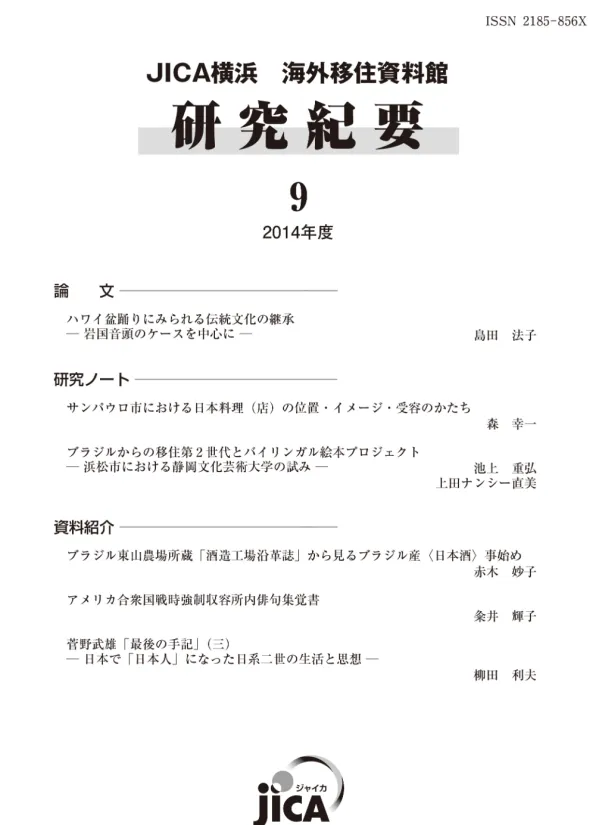
ハワイ盆踊り:文化継承の研究
文書情報
| 著者 | 小幡 俊弘 |
| 学校 | 日本女子大学 |
| 専攻 | 人文科学(推定) |
| 会社 | JICA 横浜海外移住資料館 |
| 場所 | 横浜 |
| 文書タイプ | 研究紀要 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 7.14 MB |
概要
I.横浜海外移住資料館 日系移民の歴史と多文化共生
横浜みなとみらい21地区に位置する横浜海外移住資料館は、創設12周年を迎え、来館者数は年間4万人に迫る勢いを見せています。近年は地域活動との連携強化を図り、沖縄移民特別展(来場者1万人超)など、様々な企画展を開催。今後、日系移民の歴史と移住先での日系社会の現状を紹介する企画展を、和歌山県など主要な移住者送出県と連携して開催予定です。資料館は多文化共生社会における学びの場を提供しており、横浜市立大学との連携講座では約100名の学生が日系社会に関する授業を受講しました。
1. 横浜海外移住資料館の概要と来館者増加
JICA横浜海外移住資料館は、横浜みなとみらい21地区という好立地を活かし、昨年10月に創設12周年を迎えました。地域活性化と連携した企画や、関連媒体を通じた広報活動により、来館者は年々増加し、今年度は4万人を超える見込みです。これは、資料館が地域社会に深く根付き、その存在価値を高めていることを示しています。来館者増加の背景には、資料館が単なる展示施設ではなく、地域社会との連携を積極的に進めていることが挙げられます。具体的には、地域イベントとの連動や、地元大学との協働による教育プログラムの実施など、地域貢献に力を入れている点が来館者増加に繋がっていると考えられます。これらの取り組みは、資料館の知名度向上だけでなく、地域住民の関心を高め、資料館への来場を促す効果も生んでいると考えられます。
2. 沖縄移民特別展と地方自治体との連携
資料館の新たな取り組みとして、昨年3月から5月にかけて、沖縄県と連携した『沖縄移民特別展』を開催しました。期間中の来館者数は1万人を超え、大成功を収めました。この企画展は、沖縄県立博物館・美術館との綿密な連携の下、展示内容から広報活動まで、沖縄県関係各所のご協力を得て実現しました。さらに、沖縄県からの要望を受け、6月18日の海外移住の日(沖縄県における海外移民の日)に合わせて、沖縄県庁ロビーと県立博物館・美術館での巡回展も開催されました。その後、展示パネルは浦添市立図書館、JICA沖縄国際センターでも展示され、多くの沖縄県民の皆様にご覧いただきました。この成功事例は、今後、他の主要な移住者送出県との連携強化を進める上で貴重な経験となります。資料館は、単独での活動にとどまらず、関係各所との連携を深めることで、より効果的な企画展を実施できていることを示しています。
3. 多文化共生社会における教育プログラム
資料館の目的の一つとして、次世代を担う若い世代に多文化共生社会を学ぶ場を提供することが挙げられます。この目的を達成するため、横浜市立大学と連携し、資料館見学を含む日系人・日系社会に関する授業を実施しました。約100名の学生が参加し、受講感想文からは、日本人移住者の海外での生活や、グローバル化・多文化化への示唆を得られた、という声が多数寄せられました。また、移住者になることを想像し、外国籍の方々への理解を深める機会になったという意見も見られました。今年度の教育プログラム参加者数は7000人に達する見込みであり、資料館は学びの場としての役割を着実に果たしています。 今後は、教育プログラムの更なる充実と、日系社会に関する調査研究の推進により、学びの素材となる情報を拡充し、教育効果の更なる向上を目指していくことが重要です。
II.ハワイにおける盆踊り 岩国音頭の伝承
ハワイの日系社会では、盆踊り、特に岩国音頭が重要な文化遺産として継承されています。初期の移民たちはプランテーションで盆踊りを催し、岩国音頭は特に人気がありました。ホノルルの伝説的な音頭取り、ジェイムズ・T・クニチカ氏らの努力により、岩国音頭は現在もハワイ日系文化センター(JCCH)などの協力を得て、寺院やフェスティバルなどで続けられています。日本語の意味が分からなくても、伝統的な盆踊りを先祖からの遺産として継承することに意義を見出す日系人の姿が注目されます。岩国音頭保存会(会員数約70名、会長:リンダ・マーテル氏)がその存続に大きく貢献しています。
1. ハワイにおける盆踊りの歴史と岩国音頭
ハワイの日系移民社会において、盆踊りは重要な伝統行事として定着しました。特に、岩国音頭は初期から人気があり、プランテーションの労働者たちが、畑や長屋の間で踊っていたと推測されています。1905年の『やまと新聞』には盆踊りの記録があり、岩国踊りが演じられる予定だったことが記されています。また、20世紀初頭のカウアイ島リフエで撮影された写真には、岩国音頭の「四十七士」の扮装をした男性たちが写っており、これが現存する最古の写真記録と考えられています。1924年のカウアイ島の新聞記事にも、砂糖精製所の近くで岩国踊りが行われたことが報告されており、岩国音頭がハワイの日系社会に深く根付いていたことがわかります。ある老ミュージシャンは、「昔は岩国ばかりだった。一晩中踊って踊った。」と回想しており、その人気ぶりを伺い知ることができます。これらの記録から、岩国音頭がハワイの日系社会における盆踊りの中心的な存在であったことが明らかです。
2. 岩国音頭の音楽と踊り そしてその特徴
岩国音頭は、櫓の上の囃子と、櫓の下の大太鼓一つのみで奏でられる独特の音楽が特徴です。踊り手は時計回りに回り、優雅に手をくるりと回す仕草が印象的です。その歴史は古く、1630年以降の文献に記述があることから、相当古い歴史を持つと考えられます。元々は農民が踊っていたものが、明治後期に庶民の踊りとなり、現在の形になったとされています。岩国市中央図書館の資料によると、侍の盆踊り(南條踊り)、農民の盆踊り(岩国音頭)、町人の盆踊り(小糠踊り)がそれぞれ別に行われていたという記述もあり、盆踊りの階級性も垣間見えます。また、「チョンガリ」や「チョンガレ」という呼び名もあったようです。明治から昭和にかけては、岩国地方やその他の地方で起きた事件を題材にした演目が創作され、語り継がれてきました。例えば、「佐久間大尉物語」や「肉弾三勇士」などは、ハワイでも人気のある演目として現在も伝えられています。
3. 岩国音頭の後継者育成とハワイ日系文化センターの役割
岩国音頭の伝承において、後継者育成は重要な課題でした。特に、日本語を理解する世代が減っていく中で、ホノルルの伝説的な音頭取り、ジェイムズ・T・クニチカ氏の存在は非常に大きかったです。クニチカ氏は、自ら後継者育成に乗り出し、希望者に惜しみなく指導を行いました。2004年には、ハワイ州文化芸術協会の「民族芸能後継者養成賞」を受賞し、ラルストン・ナガタ氏などを後継者として育て上げました。現在活躍する四世のグレッグ・ナカヤマ氏なども、クニチカ氏に師事した一人です。現在、岩国踊り愛好会は会員数約70名(歌い手6名、太鼓打ち5名)で、毎年7つの寺院やフェスティバルに招待されるなど、活動を続けています。会長であるリンダ・マーテル氏はニューヨーク出身の白人女性という点も注目に値し、多文化化されたボンダンスの象徴と言えるでしょう。ハワイ日本文化センター(JCCH)も盆踊りの開催に協力しており、宗教的なものから世俗的なものまで、様々な形式の盆踊りが開催されています。 日本語を理解しない四世、五世の世代にまで、伝統的な岩国音頭が歌い継がれていることは、文化継承の成功例と言えるでしょう。
III.サンパウロの日本料理 エスニシティを超えた受容
サンパウロ市の日本料理店は、1914年上地旅館の開業から始まり、旅館や簡易食堂、料亭へと発展しました。戦後、日本料理は日本人・日系人社会から非日系人へと広がりを見せ、70年代半ばからは中間層以上の居住地域にも進出。スシやサシミを中心とした日本料理は、ファーストフード化や食べ放題システム(Sushi Festival、Sushi Rodizio)の導入によって大衆化しました。 焼きそばは日系社会と中華料理店双方で人気が高く、日本料理と中華料理の食材や調理法の共通点と相違点も興味深い点です。 調査では、公務員は日本料理を好んで食べる傾向がある一方、調理助手は経済的な理由などからあまり食べないという結果が示唆されています。
1. サンパウロにおける日本料理店の歴史的発展
サンパウロ市における日本料理を提供する外食産業の始まりは、1914年にコンデ・デ・サルゼーダス街に開業した上地旅館に遡ります。当初は、宿泊客向けに白米、味噌汁、漬物といった家庭料理を提供していました。戦前においては、旅館やペンションから、うどん・汁粉などの簡単な料理を提供する簡易食堂、そして座敷や女給を配置するなどサービスを充実させた料亭へと、段階的に発展していきました。しかし、これらの飲食店は、日本人街や中央市場周辺、ピンニェイロスやラッパ地区といった日本人移民の集住地域に限られていました。つまり、戦前における日本料理は、日本人や日系人のみによって消費される、いわば排他的な食文化であったと言えるでしょう。この状況は、日本料理がサンパウロ社会に浸透していく過程において重要な要素となります。
2. 1970年代後半以降の日本料理店の地理的拡大とエスニシティの越境
1970年代半ば頃から、日本料理店の展開は変化を見せ始めます。それまで日本人街などに集中していた日本料理店が、サンパウロ市内の、中間層以上の居住区へと進出し始めました。このことは、日本料理が日本人や日系人のみに限定された食文化ではなくなり、エスニシティの境界を越えて非日系人にも受容され始めたことを示しています。1954年から1994年にかけての街区別日本料理店分布の推移を見ると、その地理的拡大傾向が明確に示されています。この拡大は、日本料理そのものの魅力の高まりと共に、新しいサービス形態の導入によっても促進されたと考えられます。 例えば、ショッピングセンターへの進出やデリバリーサービスの開始などは、日本料理の消費拡大に大きく貢献したでしょう。
3. 日本料理のファーストフード化と大衆化 新しいサービス形態
1990年代には、日本料理のファーストフード化が進行し、寿司・刺身を中心とした日本料理店がショッピングセンターのフードコートに進出するようになりました。マリコ・ライト氏経営のスシダイ(ナガヤマ経営)などがその例です。また、デリバリーサービスも開始され、ジャルジンス、モルンビー、ピンニェイロス、イタイン・ビビなど、様々な地域で日本料理が手軽に楽しめるようになりました。さらに、寿司・刺身は、日本料理店という空間を超えて、シュラスカリア(食べ放題ブラジル式焼肉店)やイタリア料理店などでも提供されるようになり、前菜や冷菜として消費されるようになりました。日本料理の大衆化を促進した要因の一つに、新しいサービスの導入が挙げられます。寿司フェスティバルや寿司ロジージオといった食べ放題システム、そしてコンビナードと呼ばれる、大皿や舟形などの器に美しく盛り付けられた寿司・刺身は、日本料理の価格や量に関する消費者の不満に対応し、その魅力をより多くの人に伝えることに成功しました。
4. 日本料理の受容とイメージ 公務員と調理助手における違い
日本料理の受容に関する調査では、公務員と調理助手の間で大きな違いが見られました。公務員は日本料理を比較的多く消費するのに対し、調理助手はほとんど消費していませんでした。経済的な理由が一つの要因と考えられますが、当時、比較的安価な日本料理を提供するレストランも存在したため、経済的な理由だけでは説明できない部分もあります。テレビ番組などを通して、寿司や刺身といった日本料理へのイメージは一般に浸透しつつありました。しかしながら、調理助手層においては、日本料理の受容は進んでいませんでした。これは、調理助手という職業イメージ(Pastelaria/Pastereiro、キタング、シャーカラなど)と、日本料理、ひいては「生臭い」「生魚」というイメージとの間に、相容れない部分があったことが考えられます。つまり、経済的な条件だけでなく、文化的・象徴的な要因も、日本料理の受容に影響を与えていたと言えるでしょう。
IV.日系人収容所における俳句 戦時下の記録
第二次世界大戦中、アメリカ合衆国における日系人収容所(例:トパーズ収容所)では、厳しい環境下でも俳句が詠まれ続けました。鮑ヶ丘俳句会は収容所生活を記録し、その句集は戦時下の生活と日系人の精神性を伝える貴重な資料です。収容所での俳句活動は、困難な状況下でも文化を維持しようとする日系人の強い意志を示しています。句集には、藤岡細江氏などの著名な俳人が参加しています。
1. 戦時下の日系人収容所と俳句活動の開始
第二次世界大戦中、アメリカ合衆国政府は日系アメリカ人を強制収容所に収容しました。この厳しい環境下においても、日系人たちは俳句を通して、日々の生活や感情を表現し続けました。資料からは、収容所での生活が「無味乾燥な」ものだったことがわかりますが、俳句はそうした生活に潤いを与え、精神的な支えとなったようです。1944年4月2日、保田山晴風居で第一回句会が開かれ、「鮑ヶ丘俳句会」と名付けられました。当初は6~7名程度の参加者でしたが、毎週句会を開催し、俳句創作に励みました。句会は収容所生活の精神的な支えとなり、参加者たちの結束を強める役割を果たしたと考えられます。俳句は、厳しい現実を生き抜く彼らにとって、心の拠り所であり、文化を維持するための重要な手段だったと言えるでしょう。
2. 鮑ヶ丘俳句会の活動と句集の編纂
鮑ヶ丘俳句会は、毎週開催される句会を通して、参加者たちは互いに作品を批評しあい、技術向上に努めました。収容所生活の中で詠まれた俳句は、自然への心情や、故郷への郷愁、そして未来への希望といった、多様な感情を反映しています。第二次交換船以降、収容所の状況は更に厳しくなり、絶望的な状況に置かれた参加者たちもいました。しかし、第三交換船の交渉成立という希望の光が射し込み、句集の編纂へと繋がります。1945年2月17日の句会までに詠まれた2500句の中から670句を選定し、句集を編纂しました。この句集には、蘇村、紫音女などの協力があり、原稿清書は中谷村畔、鉄筆山本茂、表紙題名は岩下蘇村が担当しました。句集は、鮑ヶ丘俳句会の活動の記録であり、同時に、戦時下の厳しい環境の中で俳句を通して生き抜いた日系人たちの証言ともいえるでしょう。
3. 句集の内容と収容生活の描写 そして二世兵士の慰霊
句集には、収容所の厳しい自然環境や生活の様子が、様々な角度から描写されています。「春の野に摘草ならで探る貝」、「立樹なき隔離キヤンプや春日傘」、「灌仏や異教の国の隔離寺」といった句は、収容所の風景や、異文化の中で行われる仏事などを表現しています。また、「交換船出るあてもなし種を蒔く」、「囚はれの愚痴にも飽きて昼寝かな」といった句からは、不確定な未来への不安や、精神的な疲労が読み取れます。句集には、鮑ヶ丘俳句会の会員だけでなく、戦死した二世兵士を慰霊するための句も含まれています。右左木韋城編『慰霊句集』は、戦死した二世兵士の霊を慰めるために作られた句集です。「潔く消え果てにけり霜の花」、「輝けるおん面ざしや冬の星」といった句は、戦死した若者たちの短い生涯と、深い悲しみを表現しています。これらの句は、戦争の悲劇と、それを受け止める人々の苦悩を改めて私たちに突きつけます。この句集は、戦時下の悲惨な状況と、それを乗り越えようとした日系人の精神力を伝える重要な歴史的資料と言えるでしょう。
V.ブラジル東山農場の酒造工場 日本酒製造の挑戦
ブラジル・サンパウロ州カンピーナス市の郊外にある東山農場(三菱財閥ルーツ)では、1934年に日本酒(清酒)の製造を開始しました。当初は合成酒の製造も試みられましたが、後に天然酒へと転換。この酒造工場の設立は、ブラジルの気候条件下で日本酒製造に挑戦したという歴史的意義を持ちます。東山農場の「酒造工場沿革誌」は、当時の日本酒製造の状況や経営状況を伝える貴重な一次資料です。この資料は、日系移民の生活や経済活動、そして文化の維持に対する努力を理解する上で重要な役割を果たします。
1. ブラジル東山農場と日本酒製造の背景
ブラジル東山農場は、三菱財閥(岩崎家)が1927年に取得した農場をルーツとし、コーヒー生産を主軸としながらも多角的な経営を行っていました。サンパウロ州カンピーナス市の郊外に位置し、サンパウロ市からのアクセスも良好なことから、観光農場としての側面も併せ持っていました。 資料によると、日本人移民の生活状況は「殺風景」であり、安価なブラジル産の酒(ピンガ)を常用する者が多かったとあります。より質の高い、日本人の嗜好に合う酒を求める声が高まる中、1930年にはピンガの製造を試み、1932年には日本酒の醸造準備が始まっています。これは、ブラジルにおける日本酒製造の可能性を探る、重要な一歩となります。東山農場は、単なる農場経営にとどまらず、日本人移民社会のニーズに応えるため、新たな事業展開に踏み切ったと言えるでしょう。この試みは、ブラジルの気候条件下で日本酒製造が困難であると考えられていた当時、大きな挑戦であったと言えます。
2. 酒造工場の設立と日本酒製造技術の導入
1934年5月、東山農場は日本酒製造事業の認可を受け、大岩源吾氏を酒造技師としてブラジルに派遣しました。大岩氏は、酒造機械器具を購入し、リオデジャネイロ丸でブラジルに向かいました。本社は、当時実用化されつつあった4種類の合成酒醸造法の中から、「醸造試験所黒野式電化法」を採用し、この方法で清酒製造を実現していた國興酒造株式会社大岩源吾氏に白羽の矢を立てたのです。山本農場長が日本から持ち帰った合成酒「新興國」も、この電化法によって作られたものでした。この技術導入は、ブラジルでの日本酒製造における大きな転換点となります。日本の高度な醸造技術をブラジルに持ち込み、現地で日本酒を製造販売することに成功した東山農場の取り組みは、日系移民社会の経済活動においても大きな意味を持つ出来事でした。1934年6月19日出帆のリオ・デ・ジャネイロ丸に乗船した大岩源吾氏は、この事業の成功に大きく貢献したと言えるでしょう。
3. 日本酒製造における課題と合成酒から天然酒への転換
当初は、ブラジルの気候条件を考慮し「合成日本酒」の製造も検討されました。東山カンピナス農場では、日本酒醸造に関する調査研究を進め、1932年には実験段階に突入しました。しかし、1939年3月のブラジル大蔵省の通達により、合成酒への消費税が厳格化され、酒造工場の存続が危ぶまれる状況に陥ります。そこで、東山農産加工会社は、ブラジル大蔵省に働きかけ、消費税法に「清酒」に関する項目がないことを認めさせ、追徴金の支払いを回避することに成功しました。この出来事をきっかけに、合成酒の製造を中止し、天然酒の生産に力を入れるようになります。1940年7月の大蔵大臣通達により、清酒(Sake)は「果実又は甘蔗の搾汁より製セル酒精発酵飲料」の一種として認められ、最高1500石程度の天然酒生産能力を持つ醸造工場への転換が実現しました。これは、ブラジルでの日本酒製造における大きな転換点であり、東山農場の粘り強い努力と、ブラジル政府との交渉が実を結んだ結果と言えるでしょう。
4. 酒造工場の生産能力と品質 そして将来展望
1937年7月には、156石もの日本酒を製造しており、年間生産量に換算すると1800石に相当します。これは、当時としては驚異的な生産量でした。しかし、ブラジルの高温多湿な気候下では、需要が少ない時期に大量生産し貯蔵すると品質が低下するため、生産量は消費量に合わせた調整が必要でした。合成清酒製造の特徴は、貯蔵期間が短く、設備の回転率を高めることで生産コストを下げられる点にあります。東山農場の酒造工場は小規模な設備でしたが、その生産能力を最大限に発揮していました。当時、綿作景気が好調だったため、品質に多少の難点があっても、製品は不足するほど需要があったと記されています。この「酒造工場沿革誌」は、1941年3月に日本の本社へ提出された報告書であり、ブラジルにおける日本酒製造の取り組みと、その成功と課題を詳細に記した貴重な一次資料です。 東山農場における日本酒製造は、ブラジルにおける日系移民の生活と文化を理解する上で重要な歴史的証言です。
