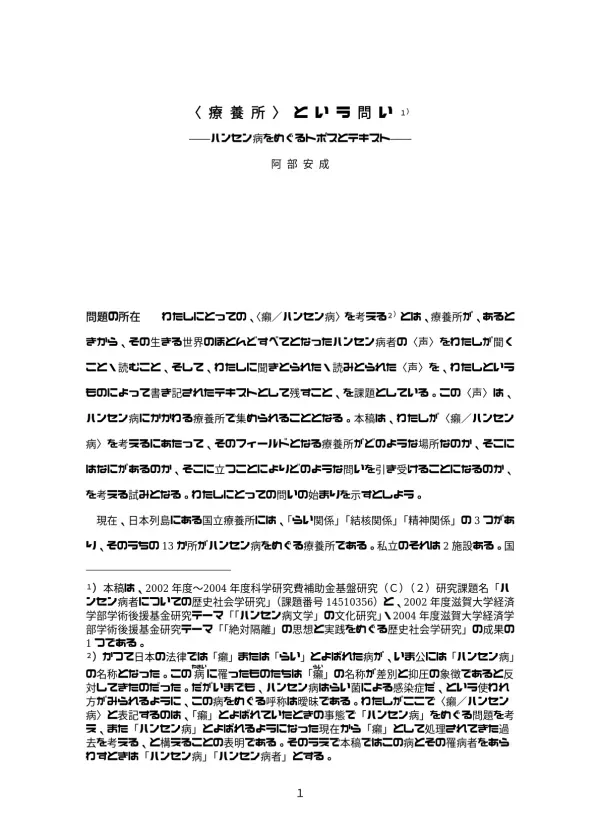
ハンセン病療養所:声なき声の記録
文書情報
| 著者 | 阿部安成 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | 歴史社会学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 176.51 KB |
概要
I.日本の国立療養所とハンセン病 隔離政策と患者の声
本稿は、日本の国立療養所、特にハンセン病に関する13施設と私立施設2施設の歴史社会学的研究をまとめたものである。らい予防法下での強制隔離政策により、多くの患者がこれらの施設で生活を余儀なくされた。研究は、患者の視点に立ち、彼らの声を記録・分析することを目指している。特に、沖縄や奄美の療養所における本土との違い、過酷な環境、患者の体験に焦点を当てている。
1. 国立療養所の現状と研究目的
日本には国立療養所が複数存在し、そのうち13か所がハンセン病関係の施設であると記述されています。私立のハンセン病療養所も2施設存在します。本稿は、2002年度~2004年度の科学研究費補助金(課題名「ハンセン病者についての歴史社会学研究」、課題番号14510356)と、滋賀大学経済学部学術後援基金研究(テーマ「ハンセン病文学」の文化研究」、「絶対隔離」の思想と実践をめぐる歴史社会学研究)の成果の一部として、ハンセン病患者を取り巻く歴史社会学的側面を研究する目的で執筆されています。 研究の根拠として、ハンセン病検証会議の最終報告書とその別冊『ハンセン病問題に関する被害実態調査報告書』が挙げられており、国立療養所入所者、退所者、私立療養所入所者、家族を対象とした調査結果が含まれていることが明記されています。さらに、各療養所で在園者自身が編集・発行した史誌の存在も示唆され、それらの中に患者の生の声が記録されていると述べられています。 厚生労働省が発行したハンセン病に関するパンフレットも紹介され、差別や偏見の解消、患者の名誉回復が目的であると説明されています。 研究では、療養所内で刊行された文芸作品にも注目し、それらが患者の声として貴重な資料となることを強調しています。しかし、既存の資料集には療養所の自治会資料や文芸誌への言及が不足している点が指摘されています。
2. ハンセン病患者の 声 の収集と困難さ
研究の核心は、ハンセン病患者の「声」を聞き取ることにあります。しかし、その収集には困難が伴うことが述べられています。 「らい予防法」廃止後も療養所で生活する患者から聞き取りを行うことは可能ですが、研究開始間もない外部者が短期間の調査で患者の真意を聞き出すのは容易ではありません。患者は、容易に心を開いてくれないとされており、調査における困難さが強調されています。 ハンセン病患者に関する既存の研究としては、『記録映画 見えない壁を越えて−声なき者たちの証言』(監督:中山節夫)や徳永進の『隔離−故郷を追われたハンセン病者たち』などが挙げられていますが、これらの資料は、国家、医療者、宗教者の視点に偏っている、もしくは患者の言説が十分に含まれていないといった問題点が暗に指摘されています。 既存の資料集である『近現代日本ハンセン病問題資料集成』にも、療養所の自治会資料室などに保存されている文芸誌に関する記述が不足していることが、研究の動機付けの一つとして提示されています。
3. 療養所の地理的分布と地域差
日本のハンセン病療養所の地理的分布が分析されています。瀬戸内海沿岸地域(邑久光明園、長島愛生園、大島青松園)と九州以南の島々(奄美和光園、沖縄愛楽園、宮古南静園)に集中していることが示され、特に南西諸島にある療養所の状況に注目が集まっています。 本土と沖縄、あるいは沖縄本島と先島諸島の間で、療養所の運営状況や患者の経験に大きな違いがあったことが述べられています。 具体的には、沖縄や奄美の療養所では職員数が少なく、患者自身が生活に必要な作業(開墾や養豚など)を担っていたという大きな違いが本土の療養所との間で存在したと説明されています。奄美和光園では、設備が整っておらず、患者が自ら水を汲み、沸かす生活をしていたという証言も紹介されています。 さらに、沖縄県内の二つの療養所が太平洋戦争時に空襲を受けたこと、宮古南静園における天然の壕が避難場所として利用されていたことなども、地域的な違いを強調する記述として挙げられています。これらの経験は、本土の療養所とは異なる、より過酷な状況を反映していると言及されています。 大島青松園へのアクセスに関する記述もあり、地元住民ですらその存在を知らない場合があることが、隔離政策の現実を象徴する一例として挙げられています。
4. 療養所の内部構造と患者の生活
療養所の内部構造と、そこで生活する患者の状況について詳細な記述があります。 多くの療養所に、園内を一望できる案内地図が設置されていること、長島愛生園にある光田健輔園長の文化功労賞受賞を記念した模型などが紹介されています。 これらの施設は、園長の権威を示す象徴的なものとして解釈されています。一方、患者の抑圧を示すものとして、監禁室の存在が繰り返し強調されています。菊池恵楓園の旧監禁室(大正6年築)や、栗生楽泉園の監禁所、特別病室(重監房)などが例として挙げられ、これらの施設が逃亡や規則違反に対する懲罰として利用されていたことが説明されています。 また、園内における「有菌地区」と「無菌地区」の区分け、患者と職員の居住区域の分離、現金使用禁止などの措置が、患者の自由を制限する要素として指摘されています。 奉安殿や奉安所の存在も明らかになり、慈悲と抑圧が共存する複雑な空間であったことを示唆しています。 こうした療養所の構造は、患者の隔離と管理を徹底するための設計であり、外部からの視察と内部からの閉塞感を同時に生み出す構造であると結論付けられています。
II.療養所の構造と患者の抑圧
多くの療養所は、患者の隔離と管理を目的とした構造を持っていた。監禁室の存在は、患者の抑圧と強制的な服従を示している。菊池恵楓園の監禁室、栗生楽泉園の監禁所と「患者刑務所(特別病室)」などがその例である。これらの施設は、逃亡の防止や規則違反への罰として利用され、絶対隔離政策の現実を象徴している。一方で、愛生園、敬愛園、愛楽園などに見られる「愛」の名称は、慈悲と抑圧の共存という複雑な現実を反映している。
1. 療養所の物理的構造と患者の抑圧
ハンセン病療養所の物理的構造は、患者の隔離と管理を目的として設計されていたことがわかります。 多くの療養所には、園内を一望できる案内地図が設置されており、これは外部からの訪問者への情報提供という側面もありますが、園内の全容を把握できる構造が、患者の行動を監視し制御するための機能も有していたと考えられます。長島愛生園にある光田健輔園長の文化功労賞受賞記念模型も、園長の権力構造を象徴的に示すものとして解釈できます。 しかし、これらの施設のもう一つの側面として、患者の抑圧を示す構造が明らかになっています。 菊池恵楓園の旧監禁室(大正6年築)は、レンガ造りの土台に木造の家屋という構造で、許可なく療養所外に出た者、規則違反者、職員の命令に従わない者などが収容され、懲罰として謹慎や減食が科せられていたことが説明されています。 さらに、栗生楽泉園には監禁所に加え、「患者刑務所」(特別病室、重監房)が存在し、周囲を高いコンクリート塀で囲まれた厳重な監房であったことが記述されています。これは、園の秩序を乱す者を犯罪者のように厳しく罰するための施設として機能していました。 これらの監禁施設の存在は、療養所における患者の自由の制限と抑圧の現実を如実に示しています。 また、園内では「有菌地区」と「無菌地区」の区分け、患者と職員の居住区域の分離、現金使用禁止などの措置も取られており、患者の行動や生活は厳しく管理されていたことが伺えます。
2. 監禁施設と懲戒権限 抑圧の制度的基盤
療養所における患者の抑圧は、物理的な構造だけでなく、制度的な側面からも裏付けられています。 大正5年、「癩予防ニ関スル件」の一部改正により、療養所長に懲戒検束権が付与されたことが、監禁室設置の法的根拠となっています。 この懲戒検束権は、患者への懲罰を正当化するものであり、逃走、賭博、麻薬中毒といった行為だけでなく、「患者心得」に違反した者にも適用され、不服申し立てを許さない絶対的な権力を行使することを可能にしていました。 菊池恵楓園の監禁室周辺にはレンガ塀が設置され、栗生楽泉園の「患者刑務所」はさらに高い鉄筋コンクリート塀で囲まれ、内部も鉄筋コンクリート柵で区切られていました。これは、患者の逃亡を阻止し、服従を強いるための物理的な障壁として機能していました。 これらの煉瓦塀や鉄筋コンクリート塀は、後に患者側の強い要請によって取り壊されたり移設されたりしていますが、それでもなお、療養所の厳格な管理体制と患者の抑圧状況を示す重要な証拠となっています。 さらに、園内における「有菌」と「無菌」の区別、患者と職員の船着場の分離、脱走防止のための園内通用券発行なども、制度的な抑圧の一端を示しています。 これらの事実から、療養所は、ハンセン病患者を収容し、外界から隔離するだけでなく、内部においても幾重にもわたる抑圧構造を備えた施設であったことが分かります。
3. 相反する要素の共存 慈悲と抑圧の両面性
ハンセン病療養所は、慈悲と抑圧という相反する要素が共存する複雑な空間であったことが示唆されています。 「愛生園」、「敬愛園」、「愛楽園」など、名称に「愛」を含む療養所がある一方で、監禁室や鉄条網といった抑圧の象徴的な構造物が存在しています。 この慈悲と抑圧の共存は、一見矛盾するようですが、文脈によっては互いに補完的に機能していた可能性があります。 慈悲や仁愛が強調されることで、抑圧や懲罰は背景に退き、その正当性が曖昧化されます。逆に、抑圧が前面に出る場合でも、それは慈悲を受けるに値しない者に対する処罰として正当化される可能性があります。 奉安殿の存在も、この相反する要素の共存を示唆しています。 奉安殿は、皇室への忠誠心や敬意を示す空間ですが、同時に、強制隔離された患者の精神的な抑圧の一端を反映しているとも考えられます。 このように、ハンセン病療養所は、患者の抑圧と慈悲の両面性を内包した、複雑で矛盾に満ちた空間であったことが、本文から読み取れます。 この複雑な空間構造は、単なる医療施設という枠を超えて、社会的な排除と統制のメカニズムを反映していると言えるでしょう。
III.患者の文芸活動と記録
療養所内では、ハンセン病文学が盛んに創作・記録されてきた。患者自身の手による機関誌(『愛楽』、『和光』、『星光』など)や作品は、彼らの生活や感情、そして隔離された社会における抵抗の記録である。光田健輔(長島愛生園園長)や内田守(医師)、小笠原登(医師)といった人物も、ハンセン病問題と深く関わってきた。これらの記録は、多磨全生園のハンセン病図書館、長島愛生園の神谷文庫などに保存されているが、散逸の危険性も指摘されている。
1. 療養所における文芸活動の現状と課題
ハンセン病療養所内では、多くの患者が文芸活動を行い、膨大な量の文学作品や記録を残していることが強調されています。近年では、これらの作品が改めて編集・刊行されたり、展示されたりする動きが出てきており、ハンセン病患者自身の「声」を伝える重要な資料として注目されています。 しかし、これらの資料の保存状況や管理体制には課題が残されています。 例えば、各療養所の自治会資料室などに保存されている文芸誌などは、既存の『ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書』や『近現代日本ハンセン病問題資料集成』といった資料集には十分に反映されておらず、その存在が広く知られていない現状があります。 また、自治会の50年史などの刊行後、あるいは図書室の改築後に資料が散逸しているケースも多く、特に逐次刊行物については、療養所間での相互寄贈なども行われていたものの、保存状況は必ずしも良好ではなく、資料の所在や履歴の把握が不十分な状況にあると指摘されています。 宮古南静園では既に『南静』という機関誌が失われていることも、資料の散逸の現状を示す一例として挙げられています。 したがって、各療養所の刊行物の履歴と現存資料の確認が、今後の重要な課題として挙げられています。
2. ハンセン病文学とその意義 患者の主体性と証言
療養所内で創作された文学作品は、単なる慰安のためのものとは異なり、患者自身の主体性を示す重要な証言として位置付けられています。熊本近代文学館の馬場純二氏の言葉として「療養所の患者たちにとって、単に慰安としての俳句や短歌は意味をなさなかった。真に文芸としての短歌に向かい合った時、初めて療養所の中に「人間宣言」とも言える意識が芽生え、声となり、紡ぎ出され始めた」という記述が引用されています。 また、同氏は「文芸や文学は療養所にいたという証し」とも述べており、これらの作品が患者の存在証明、そして隔離生活における抵抗の記録としての意義が強調されています。 しかし、「癩文学」や「ハンセン病文学」といった呼称の起源や意味、それらがどのような分類基準に基づいているのかについては、本稿では明確に議論されていません。 ハンセン病に関する文芸作品が、患者自身にしか書き得ないものなのか、絶滅危惧種のように保護されるべきものなのかといった問いについても、今後の議論が必要であると示唆されています。昭和22年のプロミンの登場以降、ハンセン病文学は、「いのちを見つめた」緊張感から「生の喜び」を表現する方向へ変化していったことも触れられています。
3. 具体的な作品と作者 知られざる存在と資料の現状
本文では、いくつかの療養所で発行された機関誌(『愛楽』、『和光』、『星光』、『藻汐草』、『甲田の裾』など)が紹介されています。これらは、患者たち自身によって制作された文芸誌であり、療養所の状況や園外との交流などを伝える貴重な資料となっています。これらの機関誌を通じて、療養所が完全に外部から隔絶されていたわけではないことが示唆されています。 しかし、これらの機関誌の保存状況は療養所によって異なり、資料の所在や内容が必ずしも明確に把握されていない現状があります。 例えば、大島青松園の長田穂波、菊池恵楓園の島田尺草、伊藤保、津田治子など、多くの患者が作品を残しているものの、園外ではあまり知られていない現状があります。 これらの知られざる作者や作品の存在は、ハンセン病患者による文芸活動の多様性と豊かさを示す一方で、資料の保存と公開の必要性を改めて強調しています。 光田健輔の長島愛生園での活動や、内田守(守人)のコレクション、そして多磨全生園のハンセン病図書館、長島愛生園の神谷文庫などに保存されている資料についても触れられていますが、これらの資料の網羅的な調査と、他施設との情報共有が今後の課題として提示されています。 特に、長島愛生園の神谷文庫には、他の療養所には既にない文献が存在することも示され、資料の保存・管理の重要性が改めて強調されています。
IV.地域差と本土 沖縄の対比
本土と沖縄の療養所の間には大きな違いがあった。沖縄愛楽園や奄美和光園では、職員不足により、患者自身が開墾や養豚といった生活に必要な作業を担っていた。宮古南静園は、本土との確執や戦争の影響も強く受けていた。これらの地域差は、ハンセン病患者が置かれた環境の過酷さを示している。
1. 本土と沖縄 奄美諸島における療養所の違い
本文では、ハンセン病療養所の地理的分布に着目し、瀬戸内海沿岸地域と九州以南の島々、特に沖縄と奄美諸島における療養所の状況に焦点を当てています。 その結果、本土と沖縄・奄美諸島の療養所の間には、設立経緯や運営状況に大きな違いがあったことが指摘されています。 特に職員数の違いが大きく影響を与えており、職員数の少ない沖縄愛楽園や奄美和光園では、患者自身が生活に必要な作業(開墾、養豚など)を担っていたと記述されています。 これは、本土の療養所とは異なる、患者自身の生活への関与の度合いを示す重要な違いです。奄美和光園では、設備も整っておらず、患者が自ら水を汲み、沸かす生活をしていたという証言が紹介されており、本土の療養所とは比べ物にならないほど劣悪な環境下に置かれていたことが伺えます。 これらの違いは、単に施設の規模や設備の違いにとどまらず、本土と離島における行政体制や社会状況の差異が療養所の運営に大きな影響を与えたことを示唆しています。 また、沖縄愛楽園と奄美和光園の在園者たちは、本土の療養所とは異なる経験をしてきたため、日本復帰や日の丸への肯定的な感情を持つ者もいる一方、療養所での抑圧的な経験も共有していることが示されています。この複雑な感情の背景には、療養所以外に生活できる場所がほとんどなかったという、当時の社会状況が大きく関わっていると考えられます。
2. 沖縄 奄美諸島における地域差と歴史的背景
本土と沖縄・奄美諸島における違いは、単に本土と沖縄の間だけでなく、沖縄と奄美、沖縄本島と宮古島の間にも存在したことが指摘されています。 奄美和光園の在園者からは、軍政の違いが療養所の運営にも影響を与えていたという証言が得られています。これは、戦時下や戦後の社会情勢が、離島の療養所の運営に直接的な影響を与えていたことを示唆しています。 宮古南静園の医師からは、宮古島と沖縄本島との間の確執が療養所の運営に影響を与えていたという証言が紹介されています。 この証言は、地域間の対立や歴史的な背景が、ハンセン病療養所の運営にまで影響を及ぼしていたことを示す重要な示唆です。 太平洋戦争時の空襲被害も、沖縄県内の療養所に共通する経験であり、宮古南静園では、天然の壕が避難場所として利用されていたことが紹介されています。 この壕は、戦時下の生活の厳しさと、患者たちが置かれた困難な状況を象徴的に表しています。 このように、沖縄や奄美諸島の療養所は、本土の療養所とは異なり、歴史的、地理的、政治的要因が複雑に絡み合った特殊な状況下で運営されていたことがわかります。 これらの地域差を分析することで、ハンセン病政策の地域的な偏りや、患者が経験した困難さをより深く理解することが可能となります。
3. 地理的辺境と過酷な環境 隔離政策の地域的偏り
本文では、宮古南静園が青森の松丘保養園とともに、「日本」の最も端に位置するハンセン病療養所であると述べられています。 この記述は、地理的に辺境に位置する療養所ほど、患者がより過酷な環境を強いられた可能性を示唆しています。 特に、沖縄本島と先島諸島(宮古島など)の療養所を比較することで、地理的な位置が患者の生活や経験に与えた影響を分析することができます。 宮古南静園の海岸近くにある天然の壕(ぬすどがま)の例は、戦時下の過酷な生活状況を象徴的に表しており、地理的条件が、患者の生活に直接的に影響を与えていたことを示しています。 大島青松園へのアクセスに関する記述も、同様の視点から解釈できます。 高松港から船でしかアクセスできない大島に位置する大島青松園は、地理的な隔絶によって、患者が社会から一層孤立した状況に置かれていたことを示しています。 タクシー運転手に「東京のですか」と聞かれたというエピソードは、大島の存在が地元でも必ずしも知られていないことを示し、療養所の隔離政策が地域社会に与えた影響の大きさを改めて浮き彫りにしています。 このように、地理的条件は、ハンセン病療養所の運営と患者の生活に大きな影響を与えており、その地域差を分析することで、ハンセン病問題の複雑な側面をより深く理解できることが示唆されています。
V.今後の課題
本研究は、ハンセン病に関する療養所資料の保存と公開、そして患者の声の聞き取りを重要視している。患者の多様な体験や感情を正確に記録・分析し、隔離政策やハンセン病問題への理解を深めることが今後の課題である。また、患者が自ら運営する施設(自治会図書室など)との連携も重要となる。
1. 療養所資料の保存と公開 在園者の主体性との調和
本研究の今後の課題として、ハンセン病療養所で収集された史料の保存、公開、活用が挙げられています。 現状では、各療養所の史料に関する目録が十分に作成されているわけではなく、療養所間の情報交換も不十分です。これは、自治会図書室などの運営を在園者自身が行っているという事情が大きく影響していると考えられます。 そのため、在園者の意思を尊重しつつ、外部研究者がどのように資料の保存と公開に関わることができるのかが重要な課題となります。 特に、自治会資料室などに保管されている文芸誌や機関誌、そして個々の患者の作品などは、散逸の危険性が高く、保存状態の確認と、必要に応じて適切なデジタルアーカイブ化などの対策が必要不可欠です。 また、既に散逸している資料もあるため、今後の調査においては、徹底的な悉皆調査と、他の機関との連携による情報収集が不可欠です。 本稿では、ハンセン病療養所で収集された史料の一部を紹介するにとどまっていますが、より包括的な資料目録の作成と、それらの情報の共有化が、今後の研究を進める上で不可欠なステップとなるでしょう。 この過程において、在園者の権利やプライバシーを保護することは、研究を進める上で最も重要な倫理的課題の一つです。
2. 未訪問施設と限定的な調査 今後の調査範囲の拡大
本研究では、東北新生園、栗生楽泉園、駿河診療所の3施設を訪問することができませんでした。 また、多磨全生園のハンセン病図書館、長島愛生園の神谷文庫、大島青松園の教会についても、事情によりおおまかな調査にとどまっています。 これらの施設は、貴重な資料を保管している可能性が高いため、今後の研究においては、これらの施設への訪問と、より詳細な調査を行う必要があります。 特に、神谷文庫には他の療養所にはない文献が存在する可能性があり、これらの資料の調査は、研究の進展に大きく貢献するでしょう。 また、大島青松園のキリスト教会には、クリスチャンであった長田穂波の作品が保管されている可能性があり、今後の調査で発見される可能性も期待できます。 未訪問施設や限定的な調査となった施設についての調査範囲の拡大は、本研究の成果をより充実させるために不可欠な要素です。 これらの施設の調査を行うことで、より多くの患者の「声」を聞き取り、ハンセン病問題を多角的に理解することが可能になります。
3. 患者の なぜ を解き明かす 多様な視点からのアプローチ
本研究で提示された患者の証言には、「療養所があったから生きてこられた」という肯定的な意見と、「抑圧されてきた」という否定的意見が同時に存在します。 この一見矛盾するような意見は、当時の社会状況と、個々の患者の置かれた状況を反映していると言えるでしょう。 患者の多様な「なぜ」という問い、例えば差別と抑圧への抵抗、文芸活動への参加、個人の内省など、様々な形で表出された患者の生の声を、より深く掘り下げていく必要があります。 「元患者」「回復者」といった表現の背後にある、ハンセン病が治癒する病気であるという前提と、実際には後遺症が残るという現実との間のギャップも、今後の研究で検討する必要がある重要な点です。 また、ハンセン病の感染経路や発症メカニズム、国家による制圧、社会の反応といった側面は、医学、公衆衛生学、社会学、歴史学といった学問分野の知見を用いて解明していく必要があり、本研究はその上で、患者の内的世界(コスモロジー)に焦点を当てていく必要があると述べられています。 奄美和光園の在園者数の減少という現実を踏まえ、将来構想の検討も重要な課題となります。 厚生労働省が「最後の一人まで面倒を見る」という方針を掲げている中で、個々の療養所の将来像をどのように描き、実現していくのかについても、今後の議論が必要になります。
