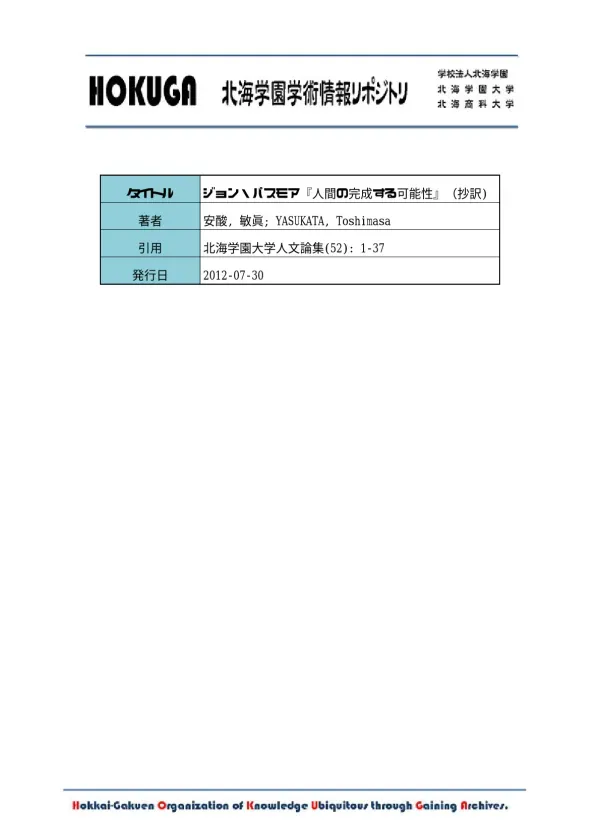
パスモア『人間の完成可能性』:完全性とは何か?
文書情報
| 著者 | 安酸敏眞 |
| 専攻 | 思想史 |
| 文書タイプ | 抄訳 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 660.62 KB |
概要
I.完全試合から哲学的考察へ 完全性 の多様な側面
本文は、メジャーリーグやプロ野球における完全試合(パーフェクトゲーム)という稀有な出来事をきっかけに、完全性という哲学的概念を多角的に考察しています。完全性は、一見単純な概念ですが、実際には技術的完全性、道徳的完全性、目的論的完全性、そして範例的完全性など、複数の側面を持つことが示されています。それぞれの完全性の定義と相互関係、そして人間が真に完全になれるのかという問いが、主要な論点となっています。
1. 完全試合という事例と完全性の概念導入
本文は、アメリカと日本のプロ野球におけるノーヒットノーラン、特に完全試合(perfect game)という稀な事例から始まります。広辞苑の定義によれば完全試合とは『相手チームに一人の走者も許さずに勝った試合』であり、百年以上の歴史の中でごくわずかの投手しか達成していない偉業です。メジャーリーグで22回、プロ野球で15回達成されていますが、2度達成した投手は一人もいません。この稀有な事例は、まさに人生一度の快挙であり、必ずしも偉大な投手だけが達成するものではないという点で、本稿で議論される「完全性」という概念の複雑さを予感させます。英語でperfect gameと呼ばれるこの出来事は、一見分かりやすい「完全性」を示しているように見えますが、この「完全性」の概念を、哲学的な視点から深く掘り下げていくことが、この文章の主題となっています。 続く章では、John Passmoreの『The Perfectibility of Man』をテキストとして、完全性の概念の歴史的変遷と、現代におけるその解釈の多様性について詳細に考察していきます。日常会話で用いられる「完全」という言葉の意味と、哲学的概念としての「完全性」との違い、そしてその背後にある歴史的・哲学的な文脈を丁寧に解き明かしていくことが、この章の重要な役割となります。
2. 広辞苑における 完全 の定義と問題点
広辞苑における「完全」の定義は、「すべてそなっていて、足りないところのないこと。欠点のないこと。すべてに及ぶこと」とされています。一見、問題ないように見えるこの定義ですが、よく考えてみると大きな問題点を孕んでいると本文は指摘します。この定義は、あらゆる側面において欠点がない状態を要求しており、現実の人間や事象に適用しようとすると、その厳しさゆえに、ほとんどすべてが「不完全」という結論に達してしまう可能性があります。この定義の限界は、後続の章で議論される様々な「完全性」の概念、例えば技術的完全性、道徳的完全性、目的論的完全性などを理解する上で重要な前提となります。これらの「完全性」の概念は、広辞苑の定義のように絶対的なものではなく、文脈や視点によってその意味合いが大きく変化することを、本文は示唆しています。 この章では、単なる辞書的な定義を超えて、多様な解釈が存在することを示し、続く章で展開される複雑な議論への導入として機能しています。
3. Passmoreの The Perfectibility of Man と完全性の考察
本稿は、John Passmoreの『The Perfectibility of Man (1970)』を主要なテキストとして、完全性の概念を多角的に考察しています。Passmoreは1914年生まれのオーストラリアの哲学者で、オーストラリア国立大学で長く教鞭を執った世界的な学者です。彼の他の著作『自然に対する人間の責任』も言及されています。この著作をテキストに選び、数回にわたって完全性の概念を考察するという計画が示され、この章は全体を通して、Passmoreの議論を基盤に、様々な哲学的立場からの完全性の概念を分析し、比較検討していくという骨組みを示しています。 特に、人間の完全性という概念は、宗教的、倫理的、そして形而上学的な視点から様々な解釈がなされており、それらを比較・対比しながら、人間が完全になれるのかという根源的な問いを探求していくことが、この章以降の主要な目的となります。
4. 完全性の様々な定義と その限界
この章では、日常的な文脈における「完全」と、哲学的な「完全性」の概念の違いが明確にされています。日常的には、仕事や役割における高い水準の達成が「完全」と評価されることが多い一方、哲学的な「完全性」は、はるかに複雑で多義的な概念です。例えば、完璧な偽造者は完璧な会計士とは限らず、完璧な人間である必要もないという指摘は、技術的な能力と倫理的な善良さ、そして人間の全体像という観点からの「完全性」の多面性を示しています。この多面性こそが、完全性をめぐる議論の複雑さを生み出している重要な要因です。さらに、神学的な視点からの完全性の概念、例えばイエスによる「完全な者となりなさい」という教えも紹介され、人間の能力を超えた領域における完全性の概念も提示されます。この章は、完全性の多様な定義と、その定義の限界を示すことで、続く章で議論されるより深い哲学的問題への橋渡しとしての役割を果たします。
II.技術的 完全性 と人間の 完全性 ゴッドウィンとプラトンの対比
技術的完全性とは、特定の仕事における卓越した能力を指します。19世紀の哲学者ウィリアム・ゴッドウィンは、個人が特定の仕事で完全になれるなら、人間全体も完全になれると主張しました。しかし、この見解は、人間が複数の役割を担うこと、そして道徳的完全性との乖離を考慮すると、単純化されていると批判されています。一方、プラトンの理想国家では、個人が社会に貢献する役割に適切に配置されることで、完全性が実現すると考えられていますが、この理想も現実社会における不完全性とのギャップを無視することはできません。
1. 技術的完全性と人間の完全性の関係 ゴッドウィンの主張
この節では、19世紀の哲学的アナーキスト、ウィリアム・ゴッドウィンの思想が取り上げられています。ゴッドウィンは、個人が特定の仕事において完全性を達成できるならば、人間全体も完全になり得ると主張しました。これは、個々の能力を最大限に発揮させることで、社会全体としての完全性も達成できるとする考え方です。ゴッドウィンは、知的障害者や異常なケースを除けば、すべての人間は特定の才能を持っており、適切な教育や訓練によって、その才能を活かして高いレベルの技能を習得できると考えました。そして、人間全体は個々人の集合体であるため、個々の完全性が社会全体の完全性につながると結論づけています。ただし、この主張は、個人が複数の役割を担う現実や、技術的完全性と道徳的完全性の違いなどを考慮すると、単純化されているという批判も存在します。このゴッドウィンの議論は、人間の完全性という概念を、単なる技術的な熟練度を超えた、より広範な概念として捉えるための重要な論点となります。
2. ゴッドウィンの主張に対する反論とプラトンの理想国家
ゴッドウィンの主張に対しては、二つの強力な反論が提示されています。第一に、人はある役割において完全であっても、別の役割では不完全である可能性があるという点です。例えば、完璧な会計士であっても、人前で話すのが苦手というケースはあり得ます。第二に、技術的完全性と道徳的完全性の間に大きな隔たりがあるという点です。完璧な会計士であっても、それが必ずしも完璧な人間であることを意味するわけではないし、完璧な偽造者や恐喝者も存在する可能性があることを示しています。これらの反論は、人間の完全性を単一的な基準で測ることの困難さを浮き彫りにします。対照的に、プラトンの理想国家では、個人がその才能に合った役割を担うことで、社会全体の調和と完全性が実現すると考えられています。 この理想国家では、偽造者や恐喝者といった社会に害を及ぼす職業は存在せず、各個人が道徳的に正しい役割を担うことで、社会全体の「完全性」が達成されます。しかし、このプラトンの理想国家も、現実社会の不完全性とは対照的な、理想的なモデルであることに注意が必要です。ゴッドウィンとプラトンの対比を通して、人間の完全性という概念の複雑さと、理想と現実のギャップが明確に示されています。
3. プラトンの理想国家における役割分担と完全性
プラトンの理想国家においては、各個人が生まれつき最も適した仕事を行い、それによって社会全体の調和が保たれ、完全性が実現するという考え方が示されています。この社会では、個人の能力が最大限に活かされ、社会に貢献することで、個人の完全性も達成されると考えられています。しかし、このモデルは、現実社会では個人が複数の役割を担うことを考慮しておらず、また、権力者の「完全性」についても、技術的な能力のみを重視するものではなく、道徳的な善良さも不可欠であることを示唆しています。プラトンの理想国家は、技術的完全性と道徳的完全性を両立した社会モデルを示していますが、その実現可能性については、議論の余地があります。この節では、プラトンの理想国家という、ある意味では「完全な社会」のモデルを通して、人間の完全性の達成という問題を考察するための枠組みが提示されています。
III.宗教的視点からの 完全性 ルターとアキナスの考察
ルターは、個々の職業における献身が神の意志に従うことであり、それ自体が完全性への道だと主張しました。しかし、技術的完全性だけでは人間の完全性は達成できないとしています。アキナスは、アリストテレスの目的論的完全性の考えを受け継ぎつつ、人間の完全性は神の恵みによってのみ達成されると述べています。これらの宗教的視点では、人間の完全性は、技術的スキルや世俗的な成功だけでは測れない、より高次な概念であることが強調されます。
1. ルターの職業倫理と完全性
この節では、マルティン・ルターの思想における完全性の概念が論じられています。ルターは、「何某かの委任と召命を与えられていないような人は一人もいない」と述べ、全ての人間は神から与えられた役割(職業)を持っており、その役割を全うすることが神の意志に従うことであり、それ自体が一種の完全性であると主張しました。ルターは、下男、下女、息子、娘など、あらゆる身分の人間が、それぞれの役割を忠実に果たす限り、神の目から見て輝かしい存在であると説いています。しかし、ルターは、地上の生活において人間が完全性を達成できるという考え方を強く否定しています。ルターにとって、技術的な完全性(職務上の高い能力)は、隣人に仕える手段としてのみ価値があり、それ自体が目的ではありません。従って、ルター主義的な道徳神学において、技術的完全性は重要な役割を果たすものの、あくまで手段としての意味しか持たないのです。ルターは、世俗的な職務における完全性と、人間としての完全性を同一視しなかったと考えられます。つまり、どんなに特定の仕事で完璧な技術を身につけても、それが必ずしも人間としての完全性を意味するわけではないという考えです。
2. ルターにおける 罪深い職業 と完全性の条件
ルターは、法王、枢機卿、司教など、当時の人々の観点から「罪深い」と考えられた職業を列挙しています。この一覧は論争を呼ぶものであり、すべての人が法王を売春婦と同じく「罪深い」と考えるわけではないものの、ルターの考え方の本質を示す重要な部分です。このリストは、ルターが「完全性」を達成するために、単なる技術的な能力や社会的成功ではなく、道徳的な善良さ、特に神の意志への従順さを重視していたことを示唆しています。ルターの考えでは、たとえ特定の職業で技術的に完璧な能力を身につけていたとしても、それが道徳的に間違った職業であれば、真の完全性とはみなされません。聖堂売春婦を例に、神の意志への服従が完全性への道であるという考えが示されています。しかし、神の意志が常に明確に分かるわけではないため、この「服従義務的な完全性」にも限界があることを示唆しています。この節は、ルターの宗教観に基づく完全性の概念が、単なる技術的スキルや成果主義とは異なる、倫理的な次元を持つことを明らかにしています。
3. アキナスの目的論的完全性と神の恵み
トマス・アクィナスは、アリストテレスの目的論的完全性の考えを継承し、体系的に発展させました。アクィナスによれば、すべての存在物は、それ自身の本性によって、特定の状態(完全性)に向かって動きます。人間の場合、その完全性は、神を観照すること、より正確には神の摂理を観照することによって達成されます。アクィナスは、人間が技術や技能を発揮するだけでは完全性に到達できず、神の恵みが必要であると強調しています。これは、彫刻家における「ひらめき」や天賦の才と似ており、技術的完全性だけでは目的論的完全性、すなわち人間の究極的な目的を達成できないことを示唆しています。芸術作品が技術的に完璧であっても、ひらめきや天賦の才がなければ不完全であるのと同様に、人間も神の恵みなしには完全な存在にはなれないという考えです。この節では、アクィナスによる神学的な完全性の概念が、技術的完全性や世俗的な成功とは異なる、超越的な次元を持つことを示しています。そして、技術的完全性と目的論的完全性の区別が改めて強調されます。
IV. 完全性 の多様な定義 目的論的 完全性 と形而上学的な 不完全性
完全性の定義は様々です。目的論的完全性は、事物が本来の目的を達成することによって実現します。しかし、人間の「本来の目的」とは何かという疑問が残ります。形而上学的な完全性は、不完全性(例えば、罪や欠陥)がない状態を指しますが、この定義も絶対的な完全性の達成可能性という問題に直面します。デカルトは、物質的実体が絶対的な完全性を持つことは矛盾していると指摘しています。
1. 目的論的完全性の概念とアリストテレス
この節では、目的論的完全性の概念が、アリストテレスの哲学を基に説明されています。アリストテレスによれば、あらゆる活動は特定の目的を持っており、その目的を達成することが完全性であるとされます。例えば、彫刻の目的は人物像の描写であり、医療の目的は患者の健康回復です。この目的論的な視点から見ると、完全性とは、物事がその本性において備わっている自然な目標に到達することです。しかし、人間の場合、彫刻家や大工のように明確な職務や目的がない点が、他の存在物と異なります。様々な職務や活動は、人間を多様化し、責任を分担させますが、人間自身に普遍的な「自然な目標」があるとは言い切れません。 むしろ、人間の活動の目的は、社会や文化的な慣習によって規定される「慣習的な目標」であると考えるべきだと示唆されています。この目的論的完全性の概念は、人間の完全性を考える上で重要な視点となりますが、同時に、人間の目的や目標が社会的に構築されているという側面も考慮する必要があることを示しています。この考え方は、後述する他の完全性の概念との比較において重要な役割を果たします。
2. 技術的完全性と目的論的完全性の違い
技術的完全性と目的論的完全性の違いが、カントの議論を参照しながら説明されています。技術的完全性とは、高いスキルや才能によって職務を効率的に遂行することですが、これは才能や技能に依存するものです。一方、目的論的完全性とは、物事が本来の目的を達成することによって得られる満足感です。これは、努力の結果というよりも、むしろ賜物や幸運に依存する側面が強いとされています。例えば、技術的に優れた彫刻家が必ずしも優れた作品を生み出すとは限らないように、技術的に完璧な医療行為が必ずしも患者の健康回復につながるとは限りません。患者の体質や運なども影響するからです。この技術的完全性と目的論的完全性の区別は、キリスト教的な完全性の理論を考える上で重要な意味を持ちます。なぜなら、キリスト教では、人間の完全性は神の恵みによってのみ達成されると考えられているからです。この節では、人間の完全性を考える際に、技術的な能力だけでなく、偶然性や神の恵みといった要素も考慮する必要があることを強調しています。
3. アクィナスとスピノザの完全性に関する議論
アクィナスは、アリストテレスの考えを受け継ぎ、すべてのものはそれ自身の本性によって特定の状態(完全性)に向かって動くとし、人間の完全性は神の観照にあるとしました。しかし、同時に、この完全性は神の恵みによってのみ達成されるとも述べています。これは、人間の努力だけでは完全性には到達できないという考えを示しています。一方、スピノザは、「完全性」を現実性と同義だと捉え、現実的に存在するものは潜在的に存在するものよりも優れていると主張しました。これは、アリストテレス的な考え方を踏襲したものです。しかし、この見解は、偏狭な考え方に凝り固まった人が、現実的である限り完全であるという、一見矛盾した結論を導いてしまう可能性があります。 さらに、アウグスティヌスやデカルトの悪に関する議論も取り上げられています。悪は善の欠如であり、盲目や誤りは実在的ではないという考えです。これらの議論を通して、完全性という概念が、善や潜在的可能性といった概念と密接に関連していることが示されています。そして、完全性の定義が、善悪の概念や形而上学的な前提に大きく依存していることが明らかになります。この節では、異なる哲学者の視点から完全性の概念を分析することで、その多様性と複雑さを浮き彫りにしています。
4. 潜在的可能性と完全性 そして形而上学的な欠陥
この節では、完全性が潜在的可能性の現実化と同一視される場合の問題点が論じられています。例えば、「あの子は犯罪者になる可能性がある」という表現は、犯罪が現実化される潜在的可能性であると解釈することもできますが、アウグスティヌスやデカルトの考えによれば、犯罪は善の欠如である欠陥状態であり、潜在的可能性とは異なる概念です。このことから、すべての潜在的可能性が善のために存在するという前提が導かれます。この考えは、人間の完成可能性を前提とする多くの思想家にとって自然な前提でした。しかし、この前提は、悪や不完全性の存在をどのように説明するかという問題に直面します。 デカルトは、物質的存在は完全たり得ないことを証明しようと試み、絶対的な完全性は人間や世界の限界を超えたところに存在すると主張しました。カントも、理論的な完全性は人間の手の届かないところにあると述べています。これらの議論を通して、完全性という概念が、倫理的な問題、神学的思考、そして形而上学的な考察と密接に絡み合っていることが示されています。この節は、完全性の概念を、より深い形而上学的なレベルで検討する準備として機能しています。
V. 範例的完全性 と 完全性 の客観的基準 カントとスピノザの議論
範例的完全性は、ソクラテスやイエスのような理想的な人物を模範とすることで完全性を追求する方法です。カントは、完全性の基準を客観的な理想に求め、模範の盲目的な追随を批判しました。スピノザは、完全性の基準が恣意的であると指摘し、完全性の客観的基準設定の難しさを浮き彫りにしています。プラトンも理想的な人間像を提示していますが、それは神を模範とするものでした。
1. 範例的完全性と道徳的理想 カントの批判
この節では、範例的完全性、つまりソクラテスやイエスのような理想的な人物を模範として完全性を定義することに対するカントの批判が論じられています。カントは、道徳性を範例から導き出すことは危険であると主張し、福音書に出てくるイエスでさえ、われわれが抱く道徳的完全性の理想と比較検討されなければ、完全な存在として認識できないと述べています。カントは、完全であることは特定の人物に似ることではなく、われわれが持つ道徳的完全性の理想と比較して判断されるべきだと主張しています。イエスやソクラテスは、その理想を完璧に例証しているという点で完全であるとされるのであり、われわれは、その理想を直接的に参照することで、自身の行為を判断すべきだと主張しています。 カントは、事例(examples)は励ましや模倣の対象となるが、範例(patterns)としては用いるべきではないとしています。特定の人物の模倣に固執するのではなく、道徳的理想を直接的に参照することで、より客観的な判断ができるという主張です。このカントの批判は、完全性の客観的な基準を見出すことの難しさを示唆する重要な論点となります。
2. 理想の客観性と実践的力 プラトンとカントの対比
プラトンとカントの理想観の違いが対比されています。プラトンは、理想は独立した実在性を持ち、理想的なものだけが真に実在的であると考えました(イデア論)。一方、カントは、理想が客観的な実在性を持つことを認めながらも、理想には実践的な力があると主張しました。カントは理想を「原型」と呼び、それによってわれわれは自身の行為を判断できると考えました。しかし、より高次の道徳的完全性の理想が存在するわけではなく、われわれが持つ道徳的完全性の理想が本当に完全であるかどうかを決定する方法はありません。スピノザは、理想に訴えることは常に恣意的であると批判し、完全な家や完全な人間といった理想は、われわれが恣意的に設定したものであり、その理想と比較して、様々な事物が完全であるか不完全であるかを判断する、と指摘しています。 このスピノザの批判は、完全性の定義における主観性の問題を浮き彫りにし、完全性の客観的な基準を見出すことの困難さを示しています。プラトンとカント、そしてスピノザの議論を通して、完全性の基準設定の複雑さと、その客観性の問題が提示されています。
3. 完全性の客観的基準の模索 目的論的定義と機能との関係
この節では、完全性の客観的基準をどのように設定するかという問題が議論されています。もし完全性が目的論的に定義されるのであれば、例えば、人間の理想的な見本は隆々たる筋肉をしているべきかという問いに、肉体の真の機能や自然な目的を達成するために隆々たる筋肉が不可欠である場合に限り、そうであると答えることができます。しかし、人間の肉体の自然な目的が何かは、まだ決定されていません。この議論は、完全性の内容を決定するための客観的な試験を提示するものの、人間の自然な目的の定義が曖昧であるため、完全性の客観的基準の設定は容易ではないことを示しています。 一方、理想が機能の概念から切り離される場合、例えばギリシア人が理想的な形を球形だと考えていたように、その理想に何を組み込むべきかを決定する客観的な方法は存在しない可能性があります。球形が本当に理想的な形であるか、あるいは別の形が理想的なのかを客観的に決定する方法はないのです。この節では、完全性の客観的基準を設定することの困難さと、その基準設定に影響を与える様々な要素が議論されています。
4. プラトンのティマイオスと神を模範とする完全性
プラトンは、『ティマイオス』において、完全性を追求する上で、理想的な人間性ではなく神を模範とすべきだと述べています。プラトンによれば、神的なものにはいささかの不義のかけらもないため、人間は神を模倣することで完全性を追求すべきだと考えます。この考え方は、範例的完全性の概念と密接に関連しており、神を完全性の究極のモデルとして位置づけています。しかし、この神を模範とする完全性の概念は、現実の人間にとって、その達成可能性という問題を孕んでいます。 この節は、プラトンの思想における完全性の概念が、現実の人間のあり方とは異なる、超越的な理想を追求していることを示しています。また、この超越的な理想を追求する際に、人間が抱く「完全性」の概念が、神学的、倫理的、そして形而上学的な様々な要素とどのように関わっているかを考察する、重要な視点を与えています。
VI.美と 完全性 調和と機能性のバランス
本文では、美的な完全性も議論されています。美的な完全性は、調和と統一性を備えた状態であり、機能性とのバランスが重要になります。しかし、機能性と美しさは必ずしも両立するとは限らないため、完全性の定義における複雑さが改めて示されています。文化的な違いも完全性の解釈に影響を与える要素として挙げられています。
1. 美と完全性 機能性との関係
この節では、美と完全性の関係、特に機能性との関連について論じられています。ヒュームの指摘を引用し、人は美しく、かつ効率的に機能するものを特に賞賛する傾向があると説明しています。しかし、予定された職務を十分に果たすためには、ある程度の美的な不完全性も必要となる場合もあると示唆しています。機能主義的な建築やデザインでは、優美さと機能性の適合性が重視されますが、美しく調和のとれた椅子が必ずしも座り心地が良いとは限りません。 社会においても、統一性、調和、安定といった価値を重視する社会は、人間的自由や創造性を抑制するという犠牲を払って秩序を保っている可能性があります。ごまかしを欠点とみなすなら、そのような社会は完全とは言えません。また、進取の気性を育むことも社会の機能の一部であるならば、完全な社会とは必ずしも静的で変化のない社会ではないという示唆も含まれています。この節は、完全性の概念を、単に機能性や効率性だけでなく、美しさや調和といった美的側面からも捉える必要性を示しています。
2. 様々な完全性の概念の統合と分離可能性
これまで議論されてきた技術的完全性、服従義務的完全性、目的論的完全性、そして汚れなき完全性といった様々な完全性の理想は、多くの完全論者の理論において密接に関連しているものの、理論的にも実際的にも分離可能であると指摘されています。だからこそ、それらを区別し、それぞれに異なる名称を与える必要があるとされています。ヴィンケルマンのような批評家は、完全性を「堂々として調和的な形式」と定義しましたが、これは規則性において匿名的で、個人的な特性によって傷つけられておらず、冷ややかで情感を欠くものとして描写されています。 美的な完全性には、非の打ち所のない完全さにおける職務の完璧な遂行が含まれますが、それは形而上学的な完全性とも密接に関係しています。美的に完全な社会や芸術作品は、統一、不変、自足といった形而上学的に完全なものを想起させる言葉で表現されることが多いです。しかし、これらの様々な完全性の理想は、相互に関連している一方で、必ずしも不可分ではなく、独立した基準で評価できる側面があることを強調しています。この節は、完全性の多様な側面を整理し、それらの関係性を明確にすることで、完全性の概念の複雑さを再確認させています。
3. 文化的相違と完全性の解釈 未完成の美学
異なる文化における完全性の解釈の違いが示されています。例えば、英国人はぬるい食べ物を欠陥と見なし、花のない庭を欠陥とみなしますが、ギリシャ人や日本人は必ずしもそうは考えません。同様に、ぶら下がった耳をした女性を欠陥とみなすのは英国人の視点であり、全ての人が未完成なものを欠陥とみなすわけではないとされています。吉田兼好の『徒然草』にも、万事にわたって画一性は望ましいものではなく、未完成な部分があってこそ面白いと述べられていることが紹介されています。 皇居の建設においてさえ、わざと未完成な部分を残すという例が挙げられ、完全性が必ずしも完成度と同義ではないことが強調されています。 この節では、文化的な背景や個人の価値観が、完全性の解釈に大きく影響することを示しています。 完全性は絶対的な概念ではなく、相対的なものであることを示唆し、完全性に関する議論の複雑さをさらに深めています。
