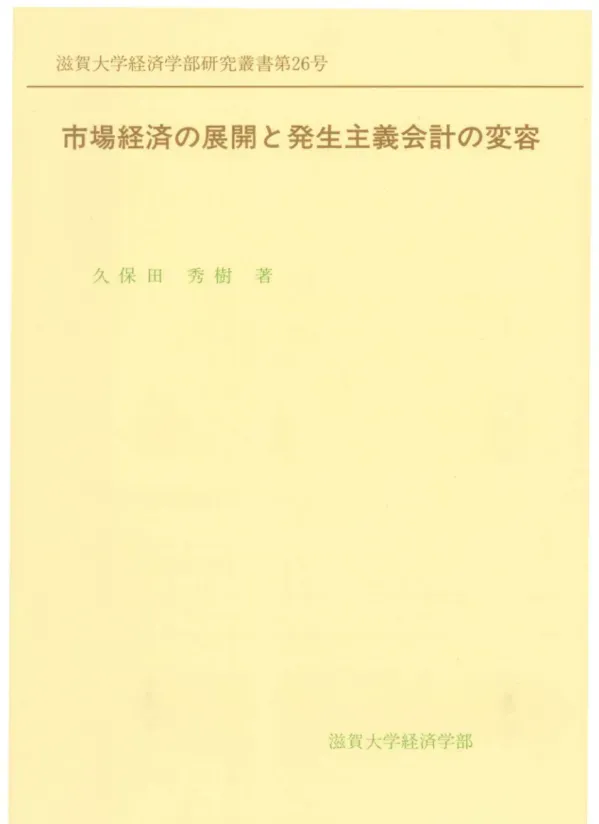
パラダイム・チェンジと企業会計
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 7.58 MB |
| 専攻 | 企業会計 |
| 文書タイプ | 学術論文 |
概要
I.発生主義会計の成立と産業化
20世紀初頭のアメリカにおける大量生産・大量流通経済の隆盛(フォード生産方式、テイラーの科学的管理法など)が、近代会計、特に発生主義会計の成立を促した。ベイトン・リトルトン『会計理論序説』(1940)は、この時代の会計思想を代表する著作で、対応・凝着アプローチ(Matching and Attaching Approach)を提唱。これは、原価計算を導入し、製造業特有の費用(減価償却費など)の原価性を明確にしたアプローチであり、損益計算書重視へと会計の焦点が移行したことを示す。信用取引の拡大も、売掛債権・買掛債務の利益計算への組み込みを必要とした重要な要因となった。
1. 産業化と発生主義会計の成立
1920年代のアメリカは、豊富な天然資源とフォードの生産技術、テイラーの科学的管理法によって生産力が飛躍的に向上しました。これは大規模製造企業による「モノ」の生産中心の経済の成立を意味します。この時代、企業活動の中心は製造であり、製造プロセスを外部取引の記録だけで把握することは不可能でした。そのため、生産設備への支出を収益への貢献として非貨幣的に配分する必要性が生じ、これが発生主義会計の成立に繋がりました。特に、原価計算の導入は、コスト認識とコスト削減による生産性向上というイノベーションをもたらし、商人的な利益計算に原価計算を統合することで、工場や機械の会計処理に対処しました。この時代の利益計算においては、信用取引のウエイトが無視できないものになったという事実が、売掛債権と買掛債務の組み入れの契機となりました。信用取引自体はそれ以前から存在しましたが、その規模が大きくなったことで、利益計算から信用取引を排除することが不可能になったのです。これは、信用経済の発達を示す量的な増加と、信用取引を保証する社会経済システムの成立という質的な問題の両面を示しています。
2. 対応 凝着アプローチと原価配分
Paton and Littletonの『会計理論序説』(1940)は、アメリカ会計文献において非常に大きな影響力を持ったと評されています。この著作で提唱された「対応・凝着アプローチ(Matching and Attaching Approach)」は、発生主義会計の根幹をなす概念です。「対応」は発生主義会計の基本的な計算手続きの説明概念として知られていますが、「凝着」は原価計算を組み込むことの必要性を強調する概念で、大規模製造企業の会計において極めて重要でした。「凝着」は、材料費や労務費とは異なり、生産設備の減価償却費などの製造業特有の経費の原価性を主張するための論拠を構成します。一方、「対応」は、大規模な修繕など、大規模製造企業に不可欠な多額の支出への備えを組み込むための論拠となりました。このアプローチは、原価計算に基づく原価配分によって利益計算を行うもので、大規模製造企業という現実を反映したものでした。しかし、棚却資産に対する償却法による原価配分は、単なる形容矛盾ではなく重要な問題であり、脱産業化の中で、固定資産に対する企業の関わり方が大きく変化してきたこと、そしてリース契約の普及によって、このアプローチの見直しが迫られていることを示唆しています。
3. 損益計算書への重点シフトと会計システムの発展
Brownによれば、Paton and Littletonの『会計理論序説』が公表された1940年には、利益計算の重点が貸借対照表から損益計算書へ完全にシフトしたとされています。1920年代に基礎が築かれ、1930年代に加速されたこのシフトは、損益計算書導入によって会計システムが発展してきたことを意味します。会計システムは、問題解決型の接近法によって個々の計算技法の集積として発展してきました。固定資産の増大がもたらす会計上の問題への対応の試行錯誤の結果として、今日の発生主義会計が成立したと言えます。会計理論は、そうした会計システムに統一性や体系性を付与するために展開されてきました。しかし、体系性を付与するためには、ある程度の抽象化や簡略化が必要であり、特定のファクターに焦点を当てると、他のファクターには影が生じるというトレードオフが存在します。20世紀初頭の30年間における原価計算思考の急速な進展は、会計理論の発展に大きな影響を与え、原価記録を財務会計に組み込むことで企業の損益計算方法が改善されました。大規模製造企業における原価計算は、コスト削減による生産性向上に貢献するイノベーションだったと言えるでしょう。
II.ASOBATと多元的評価 インフレ会計
1966年のASOBAT(A Statement of Basic Accounting Theory)は、意思決定有用性を重視した多元的規準アプローチを提示。情報技術の発達を背景に、会計システムは企業の唯一の情報システムではなくなりつつあった。インフレ会計の文脈では、ASOBATは、時価情報と原価情報の並列開示(多元的評価)を提唱。その後、FASB(Financial Accounting Standards Board)はSFAS第33号「財務報告と物価変動」を公表し、一般物価変動修正情報と個別物価変動修正情報の開示を義務づけたが、有用性の低さやコストの問題から後に廃止された。重要な人物として、FASBやAAAの関係者などが挙げられる。
1. ASOBATと意思決定有用性 多元的規準アプローチ
1966年に公表されたASOBAT(A Statement of Basic Accounting Theory)は、会計の将来像を提示しました。その一部は既に現実のものとなっていますが、コンピュータ技術の発展など、一部の予測は現実と異なっています。ASOBATは、会計システムを応用情報システムと位置づけ、情報利用者にとっての有用性、すなわち意思決定有用性を重視する多元的規準アプローチを提唱しました。これは、コンピュータ・テクノロジーの発展や統計技法の進歩など、他の管理技術の発展が会計システムの地位を脅かす中で生まれた考え方です。ASOBATは、情報利用者の意思決定に役立つあらゆる情報を提供すべきだと主張し、特定の価値概念に限定されるべきではないとしています。そのため、多元的測定による報告書作成を提唱しており、これは、外部利用者への情報提供において、会計担当者が情報に対する特定の要求を受けず、利用者の有力な集団の判断と意思決定に適合するあらゆる情報を報告すべきという考えに基づいています。このアプローチは、原価情報だけでなく時価情報も重要な情報源であると認識し、原価と時価の並列開示(多元的評価)へと繋がります。
2. インフレ会計への対応とFASBの取り組み
インフレ会計に関しては、ASOBATの意義は、その後のインフレ会計への影響という点で注目されます。1970年代のインフレの高まりを受け、FASB(Financial Accounting Standards Board)はインフレ会計の制度化に取り組みました。1974年には公開草案が発表され、1979年にはSFAS第33号「財務報告と物価変動」が公表されました。この基準書は、財務諸表の情報が利用者のキャッシュ・フローの見積りに役立つべきという概念ステートメント第1号の目的に基づき、一般物価変動修正情報と個別物価変動修正情報の両者の開示を一定の大企業に義務付けました。しかし、この取り組みは、当初から有用性やコスト・ベネフィットの観点からの見直しが計画されていました。SFAS第33号は一種の実験として公表され、その結果、開示される情報が機関投資家によって利用されていないこと、理解不可能であること、コスト効果的でないことなどの批判を受けました。「有用性」、「理解可能性」、「コスト・ベネフィット」という特性に欠けるという評価が下され、インフレ率の低下も相まって、1986年には物価変動修正情報の開示要件は撤廃されました。この過程で、ローマクラブの報告書『成長の限界』が示唆する資源枯渇への危機意識や、SECのASR第190号による制度化作業の延期なども影響を与えたと考えられます。
3. 時価情報開示と多元的評価の意義
ASOBATにおける多元的評価、特に時価情報の開示は、Paton and Littletonの『序説』における記述と関連付けられます。『序説』では、損益計算書上での原価の修正は無意味とされていますが、貸借対照表上、特に貨幣性資産に関する時価情報の補足的提供は積極的に推奨されています。このことは、有価証券の時価情報開示が、取得原価を基礎とする対応・凝着アプローチからの離脱や修正ではないことを示しています。時価情報は、少なくとも原価情報に劣らない有用性があるとされ、原価と時価の並列開示につながる多元的評価が勧告されました。これは、情報利用者の情報ニーズに応えるために、いかなる価値概念も単独では要求を満たすことができず、相当広範囲の要求に応えるために多元的測定による一般目的の報告書を作成すべきという結論に基づいています。この多元的評価は、情報利用者である外部利用者の多様なニーズ、すなわち、情報に対する特定の要求がない状況を考慮して、比較的重要な利用者の要求を会計担当者と経済主体との共同責任で一般化し、あらゆる有力な集団の判断と意思決定に適合する情報を報告するという考え方に基づいています。
III.資産 負債アプローチへの移行
脱産業化と経済のファイナンス化、金融商品の複雑化は、従来の収益・費用アプローチの限界を露呈させた。代わりに台頭してきたのが資産・負債アプローチ。これは、企業の純資源の増加に着目し、貸借対照表を重視するアプローチであり、時価評価の重要性が増す。リース契約の資産化やデリバティブの会計処理は、このアプローチの典型例。金融資産の増加、市場変動リスクの増大、そしてオンバランス化、オフバランス化といった概念が重要な論点となる。
1. 資産 負債アプローチへのシフトと背景
脱産業化と経済のファイナンス化、そして金融商品の複雑化により、従来の収益・費用アプローチ(収益と費用を重視するアプローチ)は限界を露呈しました。その結果、企業の純資源の増加に着目し、貸借対照表を重視する資産・負債アプローチが台頭してきました。このシフトの背景には、変動相場制への移行による市場変動リスクの増大、金融資産の増加、経済のファイナンス化などが挙げられます。また、企業は、ALM(総合的資産・負債管理)などの手法を用いて、市場リスクへの対応を迫られました。R.N. Anthonyによると、FASBの概念ステートメント・プロジェクトにおける資産・負債アプローチへの移行の根底には、貸借対照表が何らかの意味で価値の報告書であるべきだという信念があったとされています。このアプローチでは、利益は企業実体の純資源の増加関数と捉えられ、利益の構成要素(収益、費用、利得、損失)の測定は資産と負債側の測定に依存します。そのため、すべての資産の時価による評価が求められることになります。
2. リース契約と減価償却 資産の価値観の変化
近代会計の成立において固定資産の会計処理は最大の問題であり、減価償却の確立は近代会計の確立を意味します。しかし、脱産業化の中で固定資産に対する企業の関わり方が大きく変化し、リース契約の普及が顕著となりました。リース契約の普及の背景には、製造設備の所有が利益の源泉の所有ではなくなり、資金の長期的拘束が利益の源泉を脅かすようになったという経済構造の変化があります。R.B. Reichは、古い大量生産方式では固定費が重要でしたが、高付加価値型製造企業では固定費は不要な負担であると指摘しています。この結果、金融的観点から固定資産が扱われるようになり、資産の価値は所有ではなく利用に基づくと考えられるようになりました。これは、減価償却計算の根底にある思考であり、減価償却計算は資産というストック量を費用としてフロー化することで計算に取り込む技法です。リース契約はまさにこの擬制を具現化したものであり、減価償却計算が不要になり、費用をストック化(資産化)する計算方法へと変化しました。対応・凝着アプローチの根幹である原価配分法による資産分類が妥当しないケース、費用認識が不要なケースが生じています。
3. 新金融商品と会計処理 損益計算書万能時代の終焉
1980年代後半のバブル経済期には、企業は積極的な設備投資や金融資産への投資を行い、貸借対照表の資産側と負債側の両方が同時に拡大しました。しかし、1990年代に入ると状況は逆転し、企業は負債の増加抑制、実物資産の増加抑制、金融資産の縮小を図るようになりました。この経済状況の変化は、従来の収益・費用アプローチ、特に損益計算書中心の会計システムの限界を露呈させました。「作れば売れる」時代は終わり、為替変動などによって利益が一瞬にして失われるリスクが増大したのです。そのため、発生主義による収益認識によって収益性情報を精密化するという従来の戦略は有効性を失い、新しい会計アプローチが必要となりました。新金融商品の登場もこの変化を加速させました。1984年には「先物契約の会計処理」が公表され、1986年には新金融商品プロジェクトが開始されました。資産・負債アプローチへの移行は、新金融商品を扱う土台となったと言えるでしょう。これは、従来の損益計算書万能主義の終焉を意味し、市場経済におけるリスク増大への対応として、資産・負債アプローチが重要性を増していくことを示しています。特にデリバティブは、オフバランス性(資産計上せずに利益を上げられる)が特徴であり、既存の会計システムへの組み込みが課題となっています。
IV.連結会計制度と関連当事者取引の開示
経済のグローバル化は、連結会計の重要性を高めた。日米構造協議なども含め、連結財務諸表の開示強化、特に関連当事者間取引の開示が求められるようになった。これは、市場原理が作用しない取引における会計情報の歪みを是正するため。連結会計制度の目的は、企業集団全体の財政状態と経営成績を正確に記述することにあるが、その適用範囲や基準の解釈をめぐる課題も存在する。ダイムラーベンツ社の例は、異なる会計基準による利益の差を示し、国際会計基準(IAS)の重要性を示唆する。
1. 連結会計制度の目的とFASBの取り組み
経済のグローバル化に伴い、連結会計制度の重要性が高まっています。これは日本に限らず、世界的な傾向です。資金調達のグローバル化は日米間だけでなく、欧米間にも見られます。ダイムラーベンツ社のニューヨーク証券取引所上場や、バイエル等のドイツ多国籍企業による国際会計基準(IAS)に基づく連結財務諸表の公表は、その一例です。FASB(Financial Accounting Standards Board)は、1982年から「連結および持分法」プロジェクトを開始し、連結会計基準の見直しを行いました。1987年にはSFAS第94号を、1991年には討議資料「連結方針および連結手続に係る問題の検討」を公表しました。アメリカにおいて、連結に関する基礎概念が会計基準設定主体によって明確に検討されたのは、この討議資料が初めてでした。この資料は、連結財務諸表を作成する際の会計方針と手続を検討するための基礎を与えることを目的としています。連結会計制度の目的は、経済的実体の財政状態と経営成績を記述することですが、FASBは、非連結子会社の急増という状況を踏まえ、オフバランス金融問題への対応も重要な課題としています。オフバランス金融問題の背景には、ARB第51号公表後、企業が様々な事業ラインへ分岐し、多くの外国市場へ参入したという経済構造の変化があります。
2. 日本の連結会計制度の進展と課題
日本においては、1977年の連結会計制度導入以降、制度の改善が着実に進められてきました。1983年からの持分法の強制適用、1988年からの連結情報の有価証券報告書との同時提出、1990年からのセグメント情報開示制度の適用開始、1991年からの連結財務諸表の有価証券報告書本体への組入れ適用開始、そして1993年以降のセグメント情報開示の充実・強化などが挙げられます。さらに、1995年3月期からは「10%基準」が撤廃され、連結および持分法の適用範囲が拡大されました。これらにより、企業集団の実態に関する透明性は「量的」には改善されたと言えるかもしれません。しかし、「質的」なレベルでは、依然として検討が必要な領域が残されています。日米構造協議の最終報告では、連結財務諸表の有価証券報告書本体への組入れに加え、セグメント情報(事業別売上高・営業損益、国内・在外別売上高)、主要顧客別売上高、そして関連当事者間取引の開示充実が求められました。これを受け、関連当事者との取引に関する情報の開示に関するガイドラインが公表され、その他関連当事者や重要性の取り扱い方が示されています。
3. 関連当事者間取引の情報開示の目的と意義
関連当事者間取引の情報開示は、通常の市場取引とは異なる力学が働くため、会計測定値に歪みが生じることがあります。この開示の目的は、その歪みを情報利用者である程度織り込めるようにすることです。会計測定は市場原理に基づく取引を前提としており、情報利用者は市場原理という合理性を介して情報の背後にある事実を推測します。しかし、市場原理が作用しない関連当事者間取引については、そのことを明示しなければ、情報の背後の事実を誤認してしまう可能性があります。日米構造協議の最終報告において、系列問題に関するディスクロージャーの改善策として関連当事者間取引の開示が取り入れられたのは、いわゆる「系列取引」が市場原理が働かない取引だと考えられたためです。関連当事者間取引は、市場原理外の「内部取引」と見なされるため、通常の市場取引とは異なる力学が働き、会計測定値に歪みが生じることがあります。そのため、これらの取引に関する情報を透明性高く開示することで、投資家の判断に役立つ情報を提供することが重要となります。
V.日米独の会計思想の比較
戦後の日本はアメリカ型の会計規制を導入したが、投資家保護を重視する証券取引法会計と、債権者保護を重視する商法会計との整合性が課題であった。ドイツ会計は、実体維持論を特徴とし、アングロサクソン型会計とは異なり、利害関係者指向が強い。銀行との密接な関係、資本市場の未発達などもドイツ会計の特徴。それぞれの国の経済構造や制度が、会計思想や規制に大きな影響を与えていることを示す。
1. 連結会計制度の導入とグローバル化
経済のグローバル化は、連結会計制度の重要性を高めています。これは日本特有の現象ではなく、資金調達のグローバル化は日米間だけでなく欧米間にも見られます。例えば、ダイムラーベンツ社が1993年にニューヨーク証券取引所に上場した際、ドイツ基準とアメリカ基準の連結決算書の差異を示す調整表が添付されました。翌年には、両基準による1993年度利益に24億マルクの差があることが判明しています。また、1995年にはバイエル等のドイツ多国籍企業が、連結財務諸表を国際会計基準(IAS)で作成・公表しました。これらの事例は、経済グローバル化下での連結会計の重要性と、異なる会計基準間の差異を浮き彫りにしています。 FASBは1982年、「連結および持分法」プロジェクトで連結会計基準全般の見直しを始め、1987年にSFAS第94号、1991年には連結に関する会計方針と手続きに関する討議資料を公表しました。アメリカにおいて連結会計の基礎概念が体系的に検討されたのはこの時が初めてであり、その重要性を示しています。連結会計制度の究極的な目的は、経済的実体の財政状態と経営成績を正確に記述することです。
2. 日本の連結会計制度の改善と関連当事者取引の開示
日本においては、1977年の連結会計制度導入以来、持分法の強制適用、連結情報の有価証券報告書との同時提出、セグメント情報開示制度の適用、連結財務諸表の有価証券報告書本体への組入れ、セグメント情報開示の充実・強化など、制度改善が進みました。1995年3月期からは、子会社の連結における重要性判断基準である「10%基準」が撤廃され、連結および持分法の適用範囲が拡大されました。これらの改善は、企業集団の実態に関する透明性を高める効果がありますが、質的なレベルでの検討は依然として必要です。日米構造協議(1995年6月最終報告)では、連結財務諸表の有価証券報告書本体への組入れに加え、事業別売上高・営業損益、国内・在外別売上高、主要顧客別売上高の開示、そして関連当事者間取引の開示充実が日本側に求められました。これを受けて、関連当事者との取引に関する情報の開示ガイドラインが公表され、「その他関連当事者」や「重要性」の取り扱い方が示されました。関連当事者間取引の開示は、市場原理外の内部取引における会計測定値の歪みを情報利用者が織り込めるようにすることを目的としています。
3. 日米独会計思想の比較 投資家保護と債権者保護
戦後の日本企業会計は、アメリカ型の会計規制導入が大きな課題でした。アメリカ型の証券諸法に基づく資本市場規制の一環としての会計規制を日本に根付かせることが目標とされてきました。しかし、投資家保護を重視する証券取引法会計と、債権者保護を重視する商法会計の間には大きな差異があり、戦後企業会計の歴史は、これらの調整の歴史と言える側面を持っています。 ドイツ会計は、アングロサクソン型の市場中心型とは異なり、利害関係者指向が強いことが特徴です。これは、実体維持論にも表れています。1930年のドイツ株式法草案では、英米の株式法を参考にした開示義務強化が検討されましたが、損益計算書の項目分類規定にはアメリカ流の売上原価法ではなく総原価法のみが採用されるなど、ドイツ独自の修正が行われています。また、1937年の株式法による外部監査では、立法者は義務監査の私的な性格を否定し、株主だけでなく債権者や大衆の利益のためにも監査が重要だと考えました。これは、アングロサクソンの市場中心型に比べて利害関係者指向が強いことを示しています。ドイツでは資本市場の発達が遅れていたため、大銀行が産業企業の初期金融の主要な源泉となり、企業と銀行との密接な関係が会計思想に影響を与えています。
