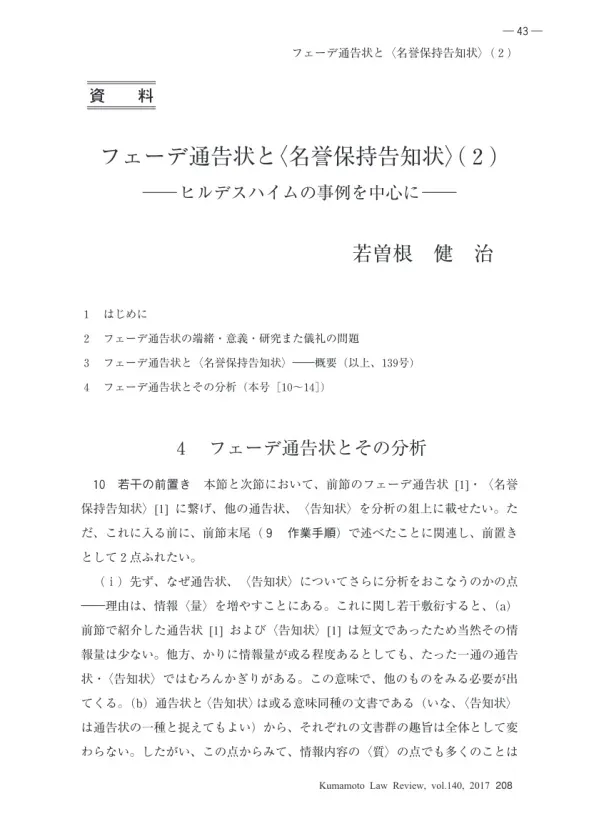
ヒルデスハイムのフェーデ通告状分析
文書情報
| 著者 | 若曽根 健治 |
| 専攻 | 歴史学 (推定) |
| 文書タイプ | 論文 (推定) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.39 MB |
概要
I.中世ヒルデスハイムにおけるフェーデ通告状の分析 情報量と史料の課題
本論文は、14世紀のヒルデスハイム市を舞台としたフェーデ(私闘)に関する通告状(Verkündigungsbriefe)を分析する。ヒルデスハイム市文書集を主な史料とするが、既存の刊本史料は編集方針にばらつきがあり、情報量が少なく、年代も限られている(14世紀80年代までなど)点が課題である。本研究は、限られた史料からフェーデ通告状の実態解明を試みる点に意義がある。
1. フェーデ通告状分析の必要性 情報量の不足と史料の限界
本研究は、中世ヒルデスハイムにおけるフェーデ(私闘)に関する通告状(Verkündigungsbriefe)の分析を目的とする。その背景には、既存研究における情報量の不足という問題がある。先行研究で扱われた通告状や告知状は短文が多く、情報量が限られている。一通の文書だけでは不十分であり、より多くの資料を参照する必要があると判断された。さらに、通告状や告知状を掲載する各都市文書集(刊本)の編集方針が統一されていないという問題も指摘されている。例えば、比較的規模の小さな文書集でも通告状の登録数が多く、逆に大規模な文書集では登録数が少ないケースもある。本稿で扱うヒルデスハイム市文書集も、後者にあたる。この問題は通告状に限らず、例えばヴァフェーデ誓約証書にも同様の問題が見られる。ヴァフェーデ誓約証書自体、刊本史料への登録数が少ないが、通告状はさらに数が限られている。刊行文書集の文書年代が限定されていたり(例:14世紀80年代まで)、通告状の収録方針が不揃いだったり、テキストが掲載されず要録のみだったりするなど、様々な編集上の事情が、通告状や告知状の調査を困難にしている。そのため、刊本史料に頼る本研究の意義が疑問視される可能性もあるが、逆に、こうした困難な状況だからこそ、綿密な調査の意義が強調されるのである。
2. ヒルデスハイム市文書集の特性 史料としての制約と研究の意義
本研究の主要な史料であるヒルデスハイム市文書集は、全8巻に及ぶにもかかわらず、フェーデ通告状の収録数は少ない。この点は、他の都市文書集と比較しても特異な点であり、本研究における史料の限界を示している。例えば、ヘルフォルト市文書集のように、小規模な文書集でありながら通告状の登録数が目立つものもある一方で、ヒルデスハイム市文書集のように、大規模な文書集でありながら登録数が少ないケースもある。これは、各文書集の編集方針の違いによるものと考えられる。さらに、収録されている文書の年代も限定されており、14世紀末までといった制約がある。また、テキストが完全に掲載されているわけではなく、「要録」で済まされているケースも存在する。これらの事情から、本研究で用いるヒルデスハイム市文書集は、フェーデ通告状の調査において、偶然性や断片性に左右される可能性が高い。にもかかわらず、本研究は、こうした史料の限界を踏まえた上で、綿密な調査を行うことで、フェーデ通告状の実態解明に貢献できると考えている。
II.ヒルデスハイム フェーデ通告状の実態 発出者と事由
ヒルデスハイム市文書集(全8巻)に収められたフェーデ通告状は、筆者調べで10点。その多くは、ヒルデスハイム市周辺の世俗領主から同市に対して発せられたものである。通告状の発出に至った事由、フェーデの実行、加害といった問題を、個々の文書の内容を分析することで明らかにする。特に、通告状における事由と加害の関係に着目し、長文通告状の一例も紹介する。
1. ヒルデスハイムにおけるフェーデ通告状の数量と特徴
本節では、ヒルデスハイム市文書集(全8巻)に収録されているフェーデ通告状を分析する。筆者の確認によれば、固有の意味を持つフェーデ通告状は、既述のものを除き10点存在する。ヒルデスハイム市を基準に内訳を見ると、同市宛てのものが7点となっている。残りの3点は、他の都市や個人を宛先としていると考えられる。これらの通告状は、ヒルデスハイム市と周辺の領主、あるいは市民との間の紛争を反映している。分析にあたっては、まず、どのような事由で通告状の発出に至ったのか、その関係事情について考察する。さらに、通告状の内容に基づき、フェーデの実行と加害の問題にも触れる。事由と加害の問題は密接に関連しているが、個々の通告状の内容を明確に把握するために、ここではあえて分けて分析する。最後に、長文通告状の一例を紹介し、本文書の全体像を提示する。なお、掲載テキスト中の省略箇所(主に文書発行者の印章に関するもの)については、必要に応じて後述する。全ての文書には、前節に掲載された文書に続き、通告状・告知状として通し番号を付す。
2. フェーデ通告状の発出事由 フェーデの実行 加害 三者の関係性
ヒルデスハイム・フェーデにおける通告状の分析では、通告状の発出事由、フェーデの実行、そして加害という三つの要素を分析軸とする。これらの要素は互いに密接に関連しており、切り分けることは容易ではない。しかし、個々の通告状の特徴を明らかにするために、あえて分けて検討を進める。まず、通告状の発出に至った事由を詳細に検討する。次に、通告状に記述されている範囲で、フェーデの実行状況と加害の状況を分析する。これらの分析を通じて、ヒルデスハイム・フェーデにおける通告状の役割と意味を明らかにすることを目指す。特に、通告状に記述されている「不法行為」の内容を精査し、それらがフェーデの発端となった経緯を解明する。そして、これらの分析結果に基づいて、長文通告状の一例を提示し、その詳細な内容を分析することで、全体像の解明を目指す。 この分析を通して、一見単純なフェーデ通告状の中に潜む複雑な人間関係と、その社会構造を明らかにしたい。
III.通告状発行をめぐる人物関係 都市と領主 市民
通告状に現れる人物、特にルードルフ・フォン・ヴァルモーデン、ハインリヒ・フォン・ボルトフェルデ、ヴァルネーケ・フォン・ドルンテン、ヒルマール・フォン・シュタインベルクといった重要人物の行動と関係性を、ヒルデスハイム市文書集に収められた通告状以外の文書も参照しながら分析する。これらの関係者は、ブラウンシュヴァイク大公、ヒルデスハイム司教といった有力者や、ミニステリアーレン、騎士などとの複雑な繋がりを持っていたことが明らかとなる。アッセブルク・フェーデ(1255-1258)以来のニーダーザクセンにおける伝統と、遺産相続問題なども絡み合っている。
1. フェーデ通告状に関わる主要人物 ルードルフ ハインリヒ ヴァルネーケ ヒルマール
本節では、フェーデ通告状の発出に関わった主要な人物とその関係性を分析する。まず、通告状に名が登場するルードルフ・フォン・ヴァルモーデンについて、1399年6月5日のヒルデスハイム市参事会からブラウンシュヴァイク=リューネブルク大公フリードリヒへの書簡を参考に、その行動と人脈を考察する。この書簡は、大公への通行安全保障に関するもので、ルードルフは、ヒルデスハイム司教ヨハンとその関係者、8名の貴族とその従者という二つのグループのうちの後者、つまり貴族グループに含まれていた。これは、ルードルフが、同書簡に記載されている他の貴族らとより強い繋がりを持っていたためと考えられる。次に、ハインリヒ・フォン・ボルトフェルデに着目する。市参事会は、ハンス・フォン・デム・ローデとその支援者に対するフェーデ通告にハインリヒの印章が押されていたことを懸念し、ハインリヒ宛に書簡を送っている。この書簡は、ハンスらがフェーデの実行を自制するよう、ハインリヒに仲介を依頼する市長らの意図を示唆している。さらに、ヴァルネーケ・フォン・ドルンテンとハインリヒとの関係も分析される。市参事会は、ヴァルネーケがかつてハインリヒの従者であったと認識し、ハインリヒにヴァルネーケを介してのフェーデ解決への協力を求めている。最後に、ヒルマール・フォン・シュタインベルクを取り上げる。ヴァルネーケらがヒルマールに関するフェーデ通告を行っている(1398年4月25日)ことから、ヒルマールについての情報収集を試みる。
2. ヒルデスハイム市参事会と主要人物との関係 交渉と仲介の役割
ヒルデスハイム市参事会は、フェーデ通告に関わる人物らとの間で、様々な交渉や仲介を行っていた。 例えば、ハインリヒ・フォン・ボルトフェルデに対しては、ハンス・フォン・デム・ローデとその支援者への宿泊提供や匿いをしないよう要請する書簡を送付している。これは、ハンスらによるフェーデ通告にハインリヒの印章が押されていたことへの懸念から発せられたものであり、ハインリヒの権力と人脈を利用してフェーデの回避・解決を図ろうとした市参事会の思惑が伺える。また、ヴァルネーケ・フォン・ドルンテンに関しても、市参事会はハインリヒとの関係性を活かし、ヴァルネーケが関与したウァフェーデ誓約の履行を促す書簡を送っている。これは、市参事会がフェーデの解決に積極的な姿勢を示す一方、当事者間の力関係や人脈を巧みに利用して事態の収拾を図ろうとしたことを示している。これらの出来事から、フェーデ通告や実行は、鉄の輪のように当事者を拘束するものではなく、当事者間の力関係や交渉によって、その行方が変化しうる可能性があることが示唆される。
3. ヒルマール フォン シュタインベルクを取り巻く状況 襲撃事件と遺産相続問題
ヒルマール・フォン・シュタインベルクに関する情報は、ブラウンシュヴァイク市発行の証書(1385年11月13日)と、ヒルデスハイム市参事会が発した5点の書簡(1397年8月30日~1398年10月12日)から得られる。ブラウンシュヴァイク市の証書は、ヒルマールが関与したと疑われる襲撃事件に関するもので、証言に基づき、襲撃された者が巡礼者であったことが立証された。この証書は、ブラウンシュヴァイク市参事会員がヒルデスハイム市に派遣され、外来者法廷を主宰する形で立証手続きが行われたことを示唆している。一方、ヒルデスハイム市参事会の書簡群は、ヒルマールとその従者が関与した遺産相続問題を取り扱っている。これらの書簡では、相続問題の経緯や市参事会への訴え、仲裁への期待などが記述されており、ヒルマール側の主張と市参事会の対応が示されている。この遺産相続問題と襲撃事件は、ヒルマールを取り巻く状況を理解する上で重要な要素であることが分かる。そして、市参事会は、これらの問題に対処する過程で、仲介や訴訟といった様々な手段を用いていた。
IV.ヒルマール フォン シュタインベルクと遺産相続問題
ヒルマール・フォン・シュタインベルクに関する史料として、ブラウンシュヴァイク市発行の証書(1385年)と、ヒルデスハイム市参事会が発した書簡(1397-1398年)の計6点が分析される。ブラウンシュヴァイク市の証書は、襲撃事件におけるヒルマールの関与を示唆する。一方、ヒルデスハイム市参事会の書簡群は、ヒルマールとその従者クラヴェス・ソルトーヴェが関与した遺産相続問題を取り上げており、都市参事会による仲裁の試みがみられる。この問題において、ヒルデスハイム市参事会は、訴訟手続きを促し、フェーデの拡大を防ごうとしていた。
1. ヒルマールに関する史料 ブラウンシュヴァイク市の証書とヒルデスハイム市参事会の書簡
ヒルマール・フォン・シュタインベルクに関する史料は、大きく分けて2種類存在する。一つ目は、ブラウンシュヴァイク市が1385年11月13日に発行した証書である。これは、ヒルマールが関与したとされる襲撃事件に関するもので、事件から約12年後である通告状の時代よりも前の出来事を扱っている。証書には、襲撃事件の被害者(ハンスら2名)、襲撃の容疑者(ヒルマールとその従僕ら)、そして立証を行った者(コルデ・シュターペル老とヘルマン・フォン・ヴェッテルメステーデ)、立証を監視したブラウンシュヴァイク市参事会員(コルト・ウンフォルホーヴェネとティル・シェーフェレ)といった関係者8名が記載されている。立証は聖遺物に誓う宣誓によって行われ、襲撃された2名が巡礼中であったことを証明するものであった。立証が行われた場所は明確に記されていないが、ヒルデスハイム市の裁判所であった可能性が高い。この事件は、巡礼の装いを偽って都市に侵入する者への対応を示唆している。もう一つは、ヒルデスハイム市参事会が1397年8月30日から1398年10月12日にかけて発した5点の書簡である。こちらは、ヒルマールとその従者クラヴェス・ソルトーヴェが関与した遺産相続問題に関するもので、ブラウンシュヴァイク市の証書とは内容が大きく異なる。
2. 1385年の襲撃事件 ヒルマールへの嫌疑と立証手続き
1385年のブラウンシュヴァイク市の証書は、聖ベルンヴァルトの墓所へ巡礼に向かう途中に襲撃を受けたというハンスら2名(A)の主張の立証に関するものである。襲撃容疑者は、ヴェットベルクの手の者、ヒルマール・フォン・シュタインベルク、そして彼らの従僕(B)であり、ヒルマールは容疑者として名指しされている。立証者(コルデ・シュターペル老とヘルマン・フォン・ヴェッテルメステーデ、C)は、聖遺物に誓って、ハンスらが巡礼中であったことを証言した。この立証は、ブラウンシュヴァイク市参事会員2名(コルト・ウンフォルホーヴェネとティル・シェーフェレ、D)の面前で行われた。証書からは立証場所が不明であるが、ヒルデスハイム市の裁判所、特に都市裁判所や市参事会の裁判所の法廷であった可能性が高い。ブラウンシュヴァイク市参事会員が派遣されたことから、ヒルデスハイム市における外来者法廷の主宰という役割も担っていた可能性がある。ハンスら被害者はブラウンシュヴァイク市民またはその関係者であったと考えられ、ヒルデスハイム市の裁判所に訴え出た。この事件は、巡礼を装って都市に侵入するよそ者への対応を示唆しており、ヒルマールの関与の有無だけでなく、当時の社会状況も反映していると考えられる。
3. 遺産相続問題 ヒルマールと市参事会の対応
1397年から1398年にかけてヒルデスハイム市参事会が発信した5通の書簡は、ヒルマールとその従者クラヴェス・ソルトーヴェが関与する遺産相続問題に関するものである。クラヴェスは、クラヴス・クラマーの遺した財産の相続を巡って、クラマーの未亡人やその甥と争っていた。クラヴェスは、その経緯と主張を市参事会に報告し、仲介を依頼していたと考えられる。市参事会はA書簡で、ヒルマールに対し、相続問題における争いは、適切な裁判所で訴訟手続きを取るべきだと主張する。市参事会は、仲裁や職権的な介入を避け、法に基づいた解決を促している。ヒルマール側は、この対応に納得せず、その後も書簡を送付している(B書簡)。市参事会は、ブラウンシュヴァイク=リューネブルク大公フリードリヒやヒルデスハイム司教ゲルハルト・フォン・ベルゲにも書簡を送り、ヒルマールに法的行動を促すよう要請している。最終的な解決方法は不明だが、司教を交えた仲裁も検討されていた。市参事会は、仲裁と並行して、長年の法と慣習に基づいた訴訟手続きを取るよう求めている。
