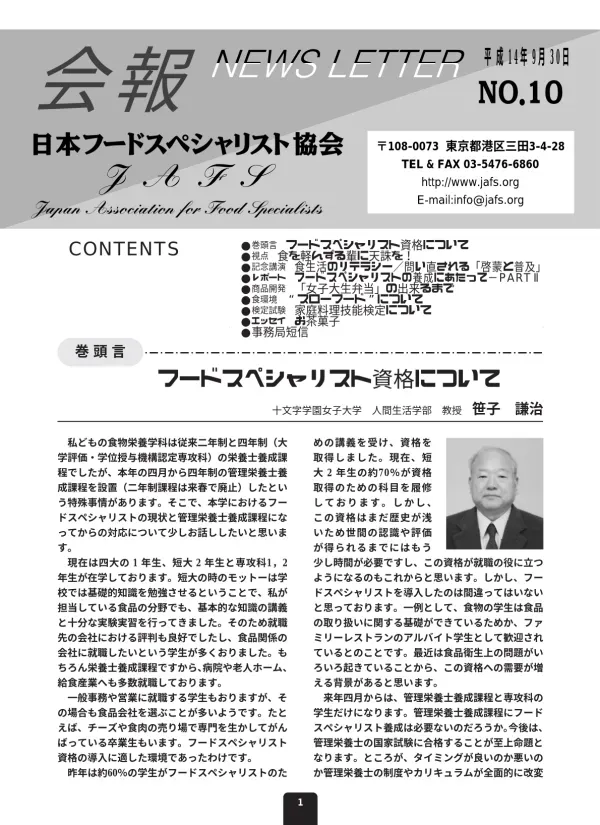
フードスペシャリスト養成:現状と課題
文書情報
| 著者 | 五明紀春 |
| 学校 | 女子栄養大学 |
| 専攻 | 食物栄養学科 |
| 文書タイプ | 会報 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 471.91 KB |
概要
I.フードスペシャリスト養成課程 現状と課題
本学の食物栄養学科では、従来の栄養士養成課程に加え、今年度から管理栄養士養成課程(四年制)を開設しました(二年制課程は廃止)。同時に、フードスペシャリスト資格取得のための科目を3年次に設置しています。フードスペシャリストは、食品業界での就職に有利な資格として期待されていますが、その認知度向上と、具体的な活躍の場を示すことが課題です。卒業生30名全員が第一回フードスペシャリスト資格認定試験に合格した実績を踏まえ、更なる資格取得支援と社会的な認知度向上に努めています。特に、食品の安全性や健康に関する情報提供能力(情報食品)が求められています。
1. 食糧栄養学科におけるフードスペシャリスト養成課程の現状
本学の食物栄養学科では、これまで栄養士養成課程(2年制と4年制)を提供してきましたが、本年度4月より4年制の管理栄養士養成課程を新たに設置し、2年制課程は来春廃止となりました。この変更に伴い、フードスペシャリスト資格取得に向けた教育課程についても検討を進めています。フードスペシャリスト資格は、従来の栄養士養成課程と比較して、より食品業界に特化した知識とスキルを習得できる点が特徴です。短大時代の経験から、基礎的な知識と実験・実習を重視した教育が、学生の就職に良い影響を与えていることを確信しています。特に食品関連企業への就職希望者が多く、企業からの評判も良好です。しかし、フードスペシャリスト資格は比較的新しい資格であるため、その就職への有効性については、今後更なる検証が必要です。現在、フードスペシャリスト関連科目を3年次に配置していますが、受講学生数や資格取得後の就職状況については、今後の推移を見守る必要があります。第一回フードスペシャリスト資格認定試験では、4年生30名全員が合格という結果を得ており、この資格の有用性を示唆しています。しかしながら、社会全体における認知度向上、そして具体的な活躍の場を示すことが、今後の課題となっています。
2. フードスペシャリスト養成課程における課題と今後の展望
フードスペシャリスト養成課程の設置は、複雑化・多様化する食環境の変化への対応という喫緊の課題への取り組みです。学生の進路は多様化しており、管理栄養士資格取得を目指す学生だけでなく、食品会社の製造部門や研究部門への就職を希望する学生も増加しています。そのため、4年間の課程の中で、学生の進路変更の可能性も考慮した柔軟なカリキュラム設計が求められます。フードスペシャリスト資格取得科目を3年次に配置しているのは、学生が他の専門性を深める時間的余裕を確保するためです。しかし、この配置が最適であるか、さらなる検討が必要です。また、フードスペシャリスト協会の意向を踏まえ、四大と短大で資格取得要件に差異を設けることも検討されています。このことは、時間割の制約を受ける食物学専攻(家庭科教員免許取得を目指す学生も多い)にとって、課題となります。フードスペシャリスト協会には、具体的な就職事例の収集と情報提供、そして資格の明確な定義づけなど、養成校への支援強化が求められます。類似の資格との差別化も重要です。研修会や講演会といった情報交換の場を継続的に提供し、質の高い人材育成に繋げていくことが不可欠です。 最終的には、フードスペシャリストが社会的に認知され、活躍の場が広がることを期待しています。
3. フードスペシャリスト資格試験と教育内容の改善
昨年度実施された第一回フードスペシャリスト資格認定試験では、受験した4年生30名全員が合格しました。この成功を踏まえ、今年度も多くの学生が資格取得を目指しており、教員一同、全員合格に向けて指導にあたっています。食品会社の中には、求人条件にフードスペシャリスト有資格者を歓迎する企業も出てきており、この資格への関心の高まりを感じます。しかし、単なる丸暗記ではなく、実践的な能力を養う教育が重要です。そのため、テーブルコーディネートの実演を取り入れるなど、授業内容の工夫を凝らしています。協会による教員向けの研修会なども開催されており、教育内容の質向上に向けた取り組みが継続されています。 フードスペシャリスト関連科目は、学生にとって大変興味深い内容であると好評です。栄養士関連科目では学べない専門的な分野(テーブルセッティング、食材や食器の選び方、マナーなど)を学ぶことができ、学生の知識・技術の幅を広げることに貢献しています。 将来的には、資格試験の問題数増加も予定されており、より高度な知識とスキルを問う試験へと進化していくことが見込まれます。
II.食生活と健康 遺伝子と食文化の視点
不適切な食生活による生活習慣病の増加が深刻な問題となっています。和食の栄養バランスとファストフードの比較を通して、食生活の欧米化が健康に及ぼす影響を解説しています。遺伝子の違いが体質に影響し、ダイエットや健康維持に繋がる食生活への理解が重要です。具体的には、日本人におけるβ3-アドレナリン受容体の遺伝子変異と肥満の関係、また、スローフードの観点からの食生活の見直しについても言及されています。国民栄養調査で指摘されている朝食欠食、カルシウム不足、鉄不足等の問題も時間栄養学や食文化の観点から改善策を検討する必要があることを示しています。
1. 生活習慣病と食生活の現状
現代社会において、不適切な食生活が原因となる生活習慣病が大きな問題となっています。統計によると、生活習慣病が原因で亡くなる人が全体の64.8%を占め、感染症(約10%)、事故・自殺(約25%)を大きく上回っています。この事実から、健康を維持するためには、適切な食生活が不可欠であることがわかります。古くからその効用が謳われてきた日本型食生活ですが、具体的な数値で示された例として、伝統的な和朝食(ご飯、味噌汁、焼き魚、煮物など)と、典型的なファストフード(ハンバーガー、フライドポテト、コーンスープなど)の栄養素を比較したデータが提示されています。カロリーはほぼ同等(和食575kcal、ファストフード582kcal)にも関わらず、脂質含有量がファストフードの方が1.5倍(和食30.7%、ファストフード45.6%)と高く、これが生活習慣病増加の一因と考えられます。また、近年増加傾向にある「ドロドロ血液」も、食生活の欧米化に起因する可能性が示唆されています。これらのことから、現代の食生活を見直し、健康的な食習慣を身につけることの重要性が改めて強調されています。
2. 遺伝子と食生活 日本人の体質とダイエット
日本人の体質と食生活の関係について、遺伝子の観点から考察が行われています。β3-アドレナリン受容体というタンパク質は脂肪代謝に関与するレセプターであり、その遺伝子変異と人種との間に関連性があることが指摘されています。日本人やモンゴル人種では、この受容体の異常型遺伝子を持つ人が多く、皮下脂肪の代謝が苦手で肥満しやすい傾向があるとのことです。一方、コーカソイド(白人)では異常型遺伝子を持つ人が少なく、太りにくい傾向にあるとされています。しかし、白人社会においても、食生活の乱れによって肥満が深刻な問題になっているという事実が示されています。これは、日本人が長年培ってきた遺伝的な体質を無視し、急激な食生活の変化を遂げたことが原因ではないかと推測されています。こうした遺伝的な背景を考慮せずに食生活を変えた場合、健康に悪影響を及ぼす可能性があることを示唆しています。近年、ダイエットに関する書籍や指導法の市場が拡大していることについても、遺伝的な体質と食生活の関係から説明が試みられています。
3. 食文化と健康 スローフードと地産地消
現代の食生活における問題点として、食事空間の質の低下が挙げられています。高齢者や子どもが一人で食事をする「弧食」の問題や、家族で一緒に食事をする機会の減少が指摘され、人間的な食事空間の重要性が強調されています。この問題への対応策として、時間栄養学の視点を取り入れることが提案されており、特に子どもの食事習慣、特に朝食の重要性について、栄養学的根拠に基づいた指導を行う必要性が説かれています。また、食の欧米化だけでなく、食事空間の貧困化も問題視されています。欧米の家庭と日本の家庭の食卓風景の違いに触れ、食事環境の重要性が示唆されています。食材の分類についても、ホウレンソウとニンジンを同じ緑黄色野菜として扱うことの不適切さを指摘し、植物分類学に基づいたより精密な分類を行う必要性が訴えられています。これは、食材本来の遺伝子的な特性と機能成分を理解し、活用していくための第一歩です。さらに、食べ物と薬を地続きのものとして捉える東洋医学の考え方を紹介し、食品に薬理的な要素を取り入れる試みが注目されていると述べています。こうした多角的な視点から、食生活の改善に向けた取り組みが求められています。地産地消の推進も、健康的な食生活と地域社会の活性化に繋がるとして推奨されています。
4. 国民栄養調査と食生活の5つの傾向
国民栄養調査から近年懸念されている5つの傾向が挙げられています。1つ目は朝食欠食率の高さ(WHENの問題)。2つ目はカルシウム不足、女性の鉄不足(WHATの問題)。3つ目は食事に対する自己評価の低さ、わかっているけれどやめられないという現状(WHYの問題)。4つ目は脂肪エネルギー比の増大(WHATとHOWの問題)。5つ目は食の洋風化・欧風化の傾向(HOWの問題)。これらの傾向は、食生活における様々な問題点を浮き彫りにしています。これらの問題点を解決するためには、分析的なアプローチだけでなく、総合的なアプローチ(HOW)が重要であり、食文化を単なるアクセサリーではなく、日本人の遺伝子プロフィールに根ざした重要な要素として捉える視点が必要であると述べられています。5W1H分析を用いて、様々な宣伝文句を分析した結果、WHEN、WHERE、WHYといった重要な要素が抜け落ちている現状が指摘されています。このことから、食に関する情報を発信する際には、これらの要素を考慮する必要があることが強調されています。
III.フードスペシャリストの役割と将来展望
フードスペシャリストは、メーカーと消費者を繋ぐ役割を担い、食に関する幅広い知識と情報提供能力が求められます。地産地消の推進、食のトレーサビリティ(履歴追跡性)の確保、そして食文化の理解と継承も重要な役割です。スローフード運動との関連性も示唆されており、おいしさ、健康、そして食卓におけるアメニティの向上に貢献することが期待されています。桜の聖母短期大学の津田和加子講師によるファミリーマートとの共同企画「女子大生弁当」開発事例も紹介され、実践的な食育の取り組みが示されています。
1. フードスペシャリストの役割 メーカーと消費者を繋ぐパイプ役
フードスペシャリストは、メーカーと消費者を繋ぐパイプ役として、食に関する幅広い知識と、常に食に関心を持ち、様々な情報を適正に判断し、消費者に提供できる能力が求められます。 単に栄養面だけでなく、食文化、食品の安全性、トレーサビリティ(履歴追跡性)、地産地消といった多様な側面を考慮した上で、消費者のニーズに応えることが期待されています。具体的には、食品の選定、テーブルコーディネート、メニュープランニング、食卓空間のアメニティ向上など、食に関わる様々な場面で活躍することが想定されます。 近年、食品衛生上の問題や食の安全に対する消費者の意識の高まりから、フードスペシャリストのニーズはますます高まっていると考えられます。 また、スローフード運動の理念とも通じる部分があり、日本各地の伝統的な食文化や食材の特性(独特の味わい、健康効果)を探求し、その価値を広く伝える役割も担うことが期待されています。 これは、単に食品の知識を持つだけでなく、食文化への深い理解と、消費者の健康を真剣に考える姿勢が求められることを意味しています。
2. フードスペシャリストの将来展望 社会的な認知度向上と活躍の場拡大
今後のフードスペシャリストには、食に関する幅広い知識に加え、常に食に関心を持ち、様々な情報を的確に判断し、消費者に提供できる能力が求められます。一人ひとりが高い能力を発揮し、社会的に認知されることで、フードスペシャリストとしての活躍の場は更に広がると期待されています。 具体的には、食品メーカーにおける商品開発、販売促進、消費者の食生活改善のためのアドバイス、食育活動への参加など、活躍できる分野は多岐に渡ります。 桜の聖母短期大学の学生がファミリーマートと共同で「女子大生弁当」を開発した事例は、フードスペシャリストの将来的な活躍を示唆するものです。この事例では、学生たちはコンビニ弁当という制約の中で、消費者のニーズを捉え、斬新なアイデアで商品開発に成功しました。 しかし、この事例でも、現実的な課題も見えてきました。 商品化にあたっては、食材の変色、麦飯の使用、コストの問題など、様々な困難を乗り越える必要がありました。 このように、フードスペシャリストは、専門知識だけでなく、現実的な課題解決能力や、他者との協調性なども求められる職業と言えるでしょう。
3. フードスペシャリストの成功事例と課題 女子大生弁当開発プロジェクト
桜の聖母短期大学の学生がファミリーマートと協力して「女子大生弁当」を開発した事例は、フードスペシャリスト育成における実践的な取り組みの一例として紹介されています。7月中旬に福島県全店で販売されるという大きなプロジェクトに、学生たちは真剣に取り組みました。1年生チームと2年生チームに分かれてアイデアを出し合い、2週間後に試作品を提出するという厳しいスケジュールの中で作業を進めました。 最初の試作品は、コンビニ弁当の研究に偏りすぎて個性のないものになってしまい、ファミリーマート側から失望の声が上がりました。しかし、学生たちはこれを反省材料として、再度、女子大生らしい夢のある弁当作りに挑戦しました。最終的には、1年生と2年生両方のアイデアが取り入れられ、福島県内だけでなく東北4県約400店舗で販売されることになりました。 この成功の裏には、学生たちの創意工夫と粘り強い努力、そして企業との連携という要素が不可欠であったことがわかります。この事例は、フードスペシャリストが食の現場でどのように活躍できるかを示す、貴重な成功例です。しかしながら、同時に、コンビニ弁当という枠組みの中で、食材の鮮度保持やコスト、製造工程における様々な制約があることも改めて認識させられました。
IV.教育カリキュラムとフードスペシャリストの教育
家庭科教育におけるカリキュラム改善の必要性が述べられています。広島大学での学部間交流の成功事例を参考に、フードスペシャリスト養成課程を充実させることで、学生の進路選択の幅を広げ、栄養士や管理栄養士を目指す学生にとっても有益な教育を提供することを目指しています。フードスペシャリスト関連科目は学生の興味関心を高め、テーブルコーディネートや食材の選択方法といった実践的なスキルを学ぶ機会を提供しています。 協会による研修会や資格認定試験の実施など、フードスペシャリスト育成体制の強化が重要です。
1. 家庭科教育におけるカリキュラムの課題と改善策
中学校・高等学校の家庭科は、扱う範囲が広く、様々なレベルの知識が混在しているため、教員の養成カリキュラムの設計が難しいとされています。幅広い分野の知識を単に羅列するのではなく、受講生がそれぞれの知識を有機的に結びつけ、整理・統合する能力を育成することが重要です。 広島大学では、西条キャンパスへの統合移転を機に学部間交流が促進され、他学部の授業を受講しやすくなりました。これは、教員養成においても、多様な視点を取り入れる柔軟なカリキュラム編成を可能にした好例です。近年、教員以外の職業を目指す学生が増加していることを受け、大学では教員以外の職業を視野に入れたカリキュラムや、具体的な資格取得を目指すカリキュラムの導入が進んでいます。 学生の将来の進路を考慮し、自ら焦点を見据えてカリキュラムを選択できる環境を作る事が理想的ですが、多くの学生は入学時に将来の進路を真剣に考えていないのが現状です。そこで、コアカリキュラムを設定することで、学生の学習意欲を高め、進路選択を支援する一つの方法が提案されています。 この様な状況の中で、フードスペシャリスト資格は、家庭科教育と連携できる有益な資格の一つとして位置づけられています。
2. フードスペシャリスト養成課程 カリキュラム構成と課題
フードスペシャリスト養成課程のカリキュラムは、既存の栄養士資格課程を参考に構成されています。食物学専攻では、資格取得に必要な科目に余裕のある単位数を割り当てています。また、フードスペシャリスト協会の意向を踏まえ、規定科目以外に選択科目を設置することで、四大と短大の資格取得要件に違いを出すことも検討されています。しかし、食物学専攻では家庭科教員免許取得を目指す学生も多く、選択科目の設定は時間割の制約から厳しい状況にあります。 フードスペシャリスト養成課程の改善のためには、各養成校の自助努力に加え、フードスペシャリスト協会による支援が不可欠です。具体的には、協会が就職先に関する具体的な雇用事例を収集し、業務内容や勤務体系などの情報を各養成校に提供する活動が求められます。 現在、フードスペシャリスト資格と類似した名称のライセンスが多く存在し、違いが分かりにくい状況にあります。そのため、フードスペシャリスト協会が認定する資格であることを明確に示し、その有用性を高める必要があります。研修会や講演会、臨時講師の紹介なども、養成校にとって貴重な支援となります。
3. フードスペシャリスト養成課程の成果と今後の展望
昨年の第一回フードスペシャリスト資格認定試験では、受験した4年生30名全員が合格しました。この成功は、本学のフードスペシャリスト養成課程の質の高さを示すものです。今年度も多くの学生が資格取得を目指しており、教員一同、全員の合格に向けて指導にあたっています。近年、食品会社ではフードスペシャリスト有資格者を歓迎する動きも出てきており、この資格の有用性が高まっていることを示しています。 しかし、丸暗記だけの知識では不十分で、実践的な能力を身につけるための教育が重要です。そのため、授業の中に専門家によるテーブルコーディネートの実演を取り入れるなど、工夫を凝らしています。協会では、養成校の教員を対象とした研修会なども開催されています。フードスペシャリスト関連科目は学生の興味関心を集め、栄養士関連科目では学べない専門的な知識・技術を習得できる点が評価されています。 将来的には、資格認定試験の問題数増加なども予定されており、さらに質の高い人材育成が求められています。
V.食文化と歴史 お茶菓子の例
日本の食文化の歴史、特に茶道における菓子の歴史に触れ、天文年間や江戸時代の茶会記から菓子の種類や提供方法の変化を解説しています。村井弦斎の「食道楽」を例に、食への関心の高さと食文化の多様性を示しています。平塚市村井公園の弦斎庵(焼失)や「弦斎カレー」の人気なども記述されています。食文化の理解は、フードスペシャリストにとって重要な要素です。
1. 茶道における菓子の歴史 天文年間から江戸時代
文書では、茶道における菓子の歴史が天文年間から江戸時代にかけて紹介されています。天文年間の茶会記28件と永禄四年(1561年)の茶会記17件を調査した結果、菓子に関する記述が見られました。天文年間の茶会9件では、栗や榧などの木の実、芋や慈姑などの農作物、昆布などの海産物、ミカンや柿などの果実、そして餅や羊羹などの加工品が出されていたことがわかります。永禄四年の茶会11件では、木の実にクルミが加わり、芋や慈姑は出ていませんが、ミカンや柿は同様に見られました。また、イリモチやフサシ(魚の刺身)といった加工品も確認できます。一回の茶会で提供される菓子の種類も天文年間より増え、7種類や5種類もの菓子が出されていた記述も見られます。これらの菓子はどのように縁高に盛られ、取り分けられていたのかは、『続群書類従・食物服用之巻』の「ふちたか」の記述などを参考に推測する必要があります。 現代のお茶席では、人数分の縁高を重ねて主菓子を取り回すスタイルが一般的ですが、当時の状況とは異なる可能性があります。
2. 江戸時代の茶菓子と変化 織部以降の菓子
利休の後継者である古田織部没後、茶菓子は徐々に変化していきました。享保十一年(1726年)の『槐記』には、薯蕷饅頭、焼き餅、青餅、葛饅頭といった菓子の記述が見られます。江戸時代後期、文化六年(1809年)の『不昧公茶会記』では、それまでの菓子に加え、早蕨や山かげといった干菓子も登場します。これらの記述から、時代とともに茶菓子の種類や製法も変化していったことがわかります。 これらの歴史的変遷を踏まえることで、日本の食文化における菓子の役割や、時代背景との関連性を理解することができます。 また、単なる嗜好品としてだけでなく、季節感や素材の特性、そして文化的な背景を反映した、複雑で多様な歴史を持つものであることがわかります。
3. 村井弦斎と食文化 食道楽と弦斎カレー
明治37年(1903年)に報知新聞で連載され、ベストセラーとなった村井弦斎の『食道楽』が紹介されています。村井弦斎(本名:寛、1863~1927年)は食通として知られ、その妻である多嘉夫人も料理に長けていたと言われています。 小説『食道楽』の印税で、神奈川県平塚市に土地を購入し、豪華な調理室と住居を建てたことも記述されています。 弦斎は平塚市に「對岳楼」を建て、自給自足に近い生活を送っていたとされています。 1967年には遺品とともに焼失しましたが、現在でも平塚市内のレストランで「食道楽」のレシピを元に作られた『弦斎カレー』が人気を集めています。 この『食道楽』と『弦斎カレー』の人気は、村井弦斎の食への情熱と、日本の食文化の奥深さ、そして伝統料理の現代への継承を象徴するものです。 この事例は、食文化が人々の生活に深く根付き、時代を超えて受け継がれることを示しています。
