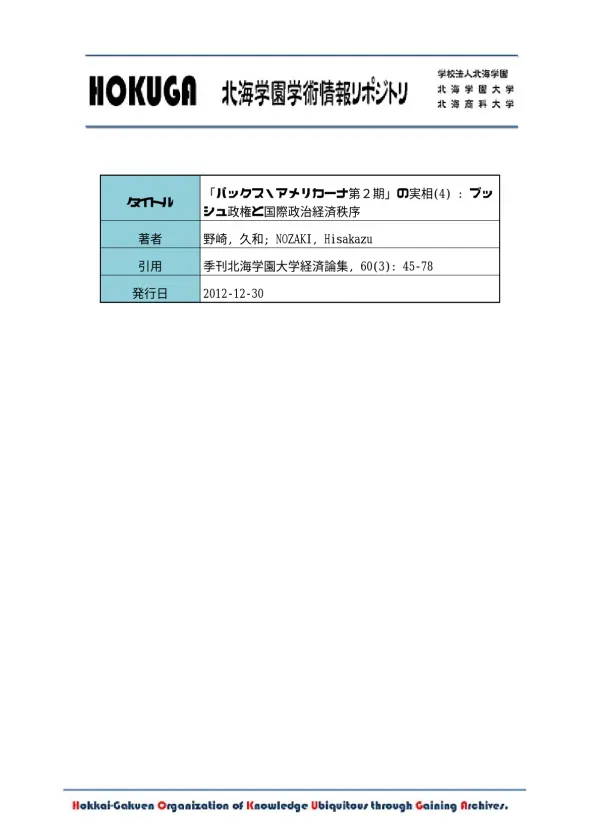
ブッシュ政権とパックス・アメリカーナ
文書情報
| 著者 | 野崎 久和 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 841.31 KB |
概要
I.ブッシュ政権の経済政策と大型減税
ジョージ・W・ブッシュ政権は、クリントン政権時代の財政黒字を基に、2001年、10年間で1兆3500億ドル規模の大型減税(経済成長と減税調整法)を実施しました。これは自由貿易推進と密接に関連しており、WTOドーハ・ラウンド交渉や貿易促進権限法(TPA)の成立にも繋がりました。しかし、大型減税と増大する歳出(特に軍事費)は財政赤字の拡大を招き、ブッシュ政権の対外経済政策は優先順位が低くなりました。農業補助金問題もWTOドーハ・ラウンド交渉の障害となり、国際的な批判を招きました。一方、自由貿易協定(FTA)は積極的に推進されましたが、会計検査院(GAO)は、ブッシュ政権のFTA政策を非効率と批判しました。また、サブプライムローン問題に端を発する世界金融危機も、ブッシュ政権時代の大きな経済問題でした。
1. 大型減税と財政状況
ブッシュ政権は、クリントン政権後期における財政黒字を背景に、2001年6月7日、10年間で1兆3500億ドルに及ぶ大型減税を実施しました。これは『経済成長と減税調整法(EGTRRA)』として成立しました。この減税は、2000年の大統領選挙におけるブッシュの公約であり、財政黒字を国民に還元するという政策目標に基づいています。当時、議会は上下両院とも共和党が多数派を占めており、減税法案の成立を容易にしました。しかし、この大型減税は、政府歳入の減少と歳出の増加を招き、結果として財政収支の悪化という負の側面も生み出しました。軍事費の増加だけでなく、その他の歳出も増加したことが、財政赤字拡大の大きな要因の一つとなりました。
2. 自由貿易推進とWTOドーハ ラウンド
ブッシュ政権は、自由貿易を重視する姿勢を示し、WTOドーハ・ラウンド交渉や自由貿易協定(FTA)の締結を積極的に推進しました。アメリカが強く主張した農業やサービスの自由化は、GATTウルグアイ・ラウンドで決定されており、その後のWTOドーハ・ラウンドはその最初の交渉でした。ブッシュ大統領は2001年4月の米州首脳会議で、自由貿易協定とWTOドーハ・ラウンド交渉の円滑な進展のために、米議会に一括承認手続き(ファストトラック)の権利を与える『貿易促進権限法(TPA)』を含む通商法の成立を表明しました。上院では民主党が僅差で多数派だったため、法案の審議は難航しましたが、最終的に2002年に成立しました。しかし、アメリカの農業補助金は、ブラジルやオーストラリアなどの農産品輸出国、日本、EUなどから猛反発を受け、ドーハ・ラウンド交渉の大きな障害となりました。ブッシュ政権は農業補助金の削減を拒否し続け、多角的自由貿易体制の促進・強化という面では、むしろブレーキとなったと評価できます。
3. 自由貿易協定 FTA 政策と批判
ブッシュ政権は、二国間・地域間の自由貿易協定(FTA)にも積極的な姿勢を示し、中南米、中東、アジアなど多くの地域の国々とFTA交渉を進めました。ブッシュ政権時代に発効したFTAは、ヨルダン、シンガポール、チリ、オーストラリア、モロッコ、バーレーン、中米(DR-CAFTA)、オマーンとの8件ですが、そのうちヨルダン、シンガポール、チリの3件はクリントン政権からの引き継ぎでした。経済規模の大きな国とのFTAは韓国とオーストラリアに限られています。特にFTAに反対する民主党議員を中心に、ブッシュ政権のFTA政策に対する批判が強まりました。民主党議員は会計検査院(GAO)にFTA政策の評価を要請し、GAOは2004年の報告書で、ブッシュ政権の交渉相手国の選定が非効率で、人的資源を浪費していると批判しました。アジア太平洋地域では、シンガポール、オーストラリア、韓国とのFTAが締結されましたが、MEFTA(中東自由貿易圏)の実現は困難でした。
4. 通貨政策と経済危機の伏線
ブッシュ政権は国際的な通貨政策に関してイニシアティブをとることはほとんどありませんでした。8年間、アメリカの貿易収支赤字と経常収支赤字は拡大し続け、中国や日本との間のグローバル・インバランスを生じさせました。ブッシュ政権は、この問題への対応策をほとんど打ち出しませんでした。唯一行ったことは、米議会の圧力も受けて、中国の為替相場制度の自由化に圧力をかけたことです。2005年7月、中国は事実上の固定相場制から管理通貨バスケット方式に移行し、対米ドル相場を約2%切り上げました。しかし、ブッシュ政権時代の大きな経済的課題として、2000年代前半に急増したサブプライムローン問題がありました。これは、ITバブル崩壊後の金融緩和、住宅価格の上昇、住宅ローン担保証券の開発、ブッシュ政権のオーナーシップ社会構想に基づく持家政策推進などが背景にあります。2004年後半以降、アメリカの金融政策が引き締めへと転換し、住宅価格が反落し始めたことで、サブプライムローン問題が表面化し、世界的な金融危機につながる伏線となりました。
II.ブッシュ政権の対外政策とイラク戦争
ブッシュ政権は、9.11同時多発テロを契機に、対テロ戦争を展開しました。イラク戦争は、国際社会の反対を無視した単独行動主義的な政策として批判されました。イラク戦争は、宗派対立の激化、治安悪化、テロの拡大など、多くの問題を引き起こし、ブッシュ政権にとって大きな失敗となりました。イラク復興事業は遅延し、米議会設置のイラク復興特別会計検査院(SIGIR)は、米企業の杜撰な事業運営を指摘しました。2006年の米中間選挙で共和党が敗北したことで、ブッシュ政権はイラク政策の見直しを余儀なくされました。イラク戦争におけるアルカイダとの関係や大量破壊兵器に関する疑惑は、事後に誤りであったと判明しました。
1. イラク戦争への道 国連決議と国際社会の反応
ブッシュ政権は、9.11同時多発テロ後の対テロ戦争において、イラクを主要な標的としました。イラクへの対処は、まず国連の枠組みを通じて行われるとされ、2002年9月12日、ブッシュ大統領は国連総会でイラクの安保理決議違反を批判し、フセイン政権への対決姿勢を示しました。その後、パウエル国務長官は国連を舞台にした外交攻勢を行い、イギリスと共同でイラクの大量破壊兵器査察・廃棄決議案1441を提出し、全会一致で採択に成功しました。この決議案は、イラクに無条件・無制限の国連査察を受け入れ、武装解除を行う最後のチャンスを与え、違反した場合には深刻な結果を招くと規定していました。しかし、この決議案の解釈をめぐって米英と他の安保理常任理事国との間で齟齬が生じることになります。決議案採択に至るまでの交渉は難航しましたが、反米のシリアも賛成したため、全会一致での採択となりました。
2. イラク戦争と占領 治安悪化と復興事業の遅延
2003年春、米軍主導の有志連合軍によるイラク占領が始まりました。戦後復興事業は、イラク戦争に賛同した国の企業(主にアメリカ企業)が中心となって行われましたが、2004年春にはテロや襲撃が急増し、治安が悪化、占領政策も混乱しました。ブッシュ大統領は2004年5月、イラクの民主化と自由化を支援する5段階の計画を発表し、同年6月末に主権移譲を行うことを表明しました。これを受けて国連安保理はイラク主権移譲・復興決議案1546を全会一致で採択しました。しかし、主権移譲後もテロや襲撃は激化し、イラクは事実上内戦状態に陥りました。イラク人犠牲者は増加の一途を辿り、国際テロリストの集積地となりました。イラク復興事業も遅延し、生活関連インフラの整備が遅れたことで、イラク国民の生活環境は劣悪な状態が続きました。米議会に設置されたイラク復興特別会計検査院(SIGIR)は、米企業の杜撰な事業計画・工事運営、予算水増し、不明瞭な会計などを指摘しました。
3. イラク戦争の失敗と政策転換 中間選挙と米軍増派
ブッシュ政権のイラク政策の失敗は、2006年11月の米連邦議会中間選挙で共和党の敗北という結果に繋がり、上下両院とも民主党が多数派となりました。この結果、ブッシュ大統領はイラク政策の見直しを迫られ、ラムズフェルド国防長官を更迭、ロバート・ゲーツ元CIA長官を後任に指名しました。超党派のイラク研究グループ(ISG)は、外交的解決を重視する報告書を提出しましたが、ブッシュ大統領は、米軍増派を柱とするイラク新政策を発表しました。2007年6月、米軍は増派前の約13万人から最大16万8000人に達し、スンニ派武装勢力やシーア派民兵組織に対する大規模な掃討作戦を実施しました。この結果、テロや襲撃は2007年秋以降減少傾向を示し、ブッシュ大統領は米軍増派は成功だったと主張しました。2008年末以降もイラクに米軍を駐留させるための地位交渉が行われ、ブッシュ大統領の退任直前に合意が成立しました。しかし、9.11同時多発テロ独立調査委員会の報告書では、イラクとアルカイダの協力関係を裏付ける信頼できる証拠がないと断定しており、イラク戦争の正当性に疑問符が投げかけられました。
III.ブッシュ政権とイラン 北朝鮮問題
イランの核開発問題では、ブッシュ政権は国連安保理による制裁を主導しました。イラン自由支援法案も成立されました。しかし、ロシアや中国の姿勢などもあり、制裁の効果は限定的でした。北朝鮮については、ブッシュ政権は当初米朝枠組み合意の履行やミサイル開発の検証可能な規制などを求めたものの、北朝鮮のミサイル発射や核実験を受け、国連安保理による制裁決議が採択されました。その後、6カ国協議を通じて、北朝鮮の核放棄に向けた一定の進展が見られましたが、完全な解決には至りませんでした。イランと北朝鮮は、ブッシュ政権のイラク戦争の泥沼化を最大限に利用し、核開発を推進したと指摘されています。
1. イランの核開発問題と国際社会の対応
ブッシュ政権以前のクリントン政権は、国際協調路線に基づきイランの核開発問題の外交的解決を目指していましたが、成果は上がらず、イランは秘密裏に核開発を進めていました。2003年夏、IAEAの査察で核兵器転用可能な高濃縮ウランが検出され、問題が表面化しました。IAEA定例理事会はイランにウラン濃縮計画の開示などを求める決議を採択しましたが、イランは一時的に合意を示したものの、2005年アフマディネジャド大統領就任後はウラン濃縮を継続、核問題を国連安保理に付託する決議に至りました。安保理では、ロシアや中国がイラン寄りの姿勢を示したため、米英仏が求める強力な経済制裁決議は採択されませんでした。2006年7月31日に採択されたイラン制裁決議1696は、ウラン濃縮関連活動を停止しない場合に経済制裁を採択する「意思表明」にとどまり、イランはこれを拒否しました。その後も、米財務省による新たな金融制裁や、国連安保理による追加制裁決議(1747、1803)が採択されるなど、イランへの圧力は強まりましたが、ブッシュ大統領はイランの核武装を「第3次世界大戦」を引き起こしかねない事態とまで表現しました。
2. 北朝鮮の核 ミサイル開発と6カ国協議
ブッシュ政権は、クリントン政権の対北朝鮮政策を批判し、見直しを行いました。2001年6月、ブッシュ大統領は北朝鮮との直接協議に応じる姿勢を示しましたが、北朝鮮は応じませんでした。その後、北朝鮮の核開発継続の情報を受け、2002年10月に初の米朝高官協議が行われ、北朝鮮の核開発が明らかになりました。ブッシュ政権は、国際社会と協調して外交的手段で対応するとし、6カ国協議が再開されました。2005年9月、北朝鮮は核兵器と核計画の破棄、NPT復帰、IAEAの核査察受入れを確約する共同声明を発表しました。しかし、ブッシュ政権による北朝鮮関連口座への制裁措置で6カ国協議は空転し、北朝鮮は2006年7月、ミサイル発射を行いました。国連安保理は対北朝鮮非難決議1695を採択しましたが、北朝鮮はこれを拒否しました。2007年9月、6カ国協議で北朝鮮の寧辺核施設の無能力化、核計画の申告、アメリカによるテロ支援国家指定解除に向けた作業開始などが合意されましたが、これはブッシュ政権のイラク政策の失敗と支持率低下の影響を受けての譲歩と見なされています。2007年2月には、北朝鮮の核放棄に関する共同文書が採択され、寧辺核施設の活動停止、IAEA査察などが行われましたが、テロ支援国家指定解除は進展しませんでした。
3. イラク戦争の泥沼化とイラン 北朝鮮の戦略
イランのアフマディネジャド大統領と北朝鮮の金正日総書記は、アメリカのイラク戦争の泥沼化と、ロシアや中国がアメリカや欧州との距離を置き始めた状況を最大限に利用しようとしたと考えられます。両国が核開発を執拗に推し進めた背景には、「イラクは核兵器を所有していなかったためアメリカに攻撃された」という認識があった可能性があり、核兵器保有がアメリカによる武力行使の抑止力となるとの判断があったと推測されます。少なくとも、イラク戦争はイランと北朝鮮に核開発推進の更なる動機を与え、世界の平和と安全に対する不確実性を増幅する大きな要因となったと言えるでしょう。 ブッシュ政権によるイランへの制裁は、イラン自由支援法案(Iran Freedom Support Act) の成立など、多岐にわたりました。一方、北朝鮮への対応は、6カ国協議という多角的な枠組みを用いて行われましたが、その過程で様々な困難や行き詰まりが見られました。
IV.ブッシュ政権と中東和平
ブッシュ政権は中東和平問題において、当初消極的な姿勢でしたが、イラク戦争への反発を背景に新中東和平構想を発表しました。アラファト議長排除を条件としたこの構想は物議を醸しました。パレスチナ新和平案(ロードマップ)も策定されましたが、ハマスとイスラエルの衝突、ガザ地区の制圧など、和平交渉は難航しました。ブッシュ政権末期には、アナポリスでの3者会談などが行われましたが、結局、和平は実現しませんでした。イスラエルのシャロン首相、パレスチナ自治政府のアッバス議長、そしてオルメルト首相などが重要な人物として登場します。
1. ブッシュ政権の初期姿勢とアラファト議長
ブッシュ政権は、就任当初、中東和平問題に対して消極的な姿勢を示していました。特に、ヤセル・アラファト議長に対しては強い不信感を抱いており、2002年1月のイスラエルによるカリネA号拿捕事件を機に、アラファト議長を信用せず、和平交渉への協力を期待していなかったとされています。ブッシュ大統領は、アラファト議長が権力の座にいる限り平和は実現しないとまで述べています。このため、ブッシュ政権による和平への取り組みは遅れ、初期段階では大きな進展が見られませんでした。イスラエルのシャロン首相とパレスチナ自治政府のアラファト議長(後にアッバス首相)との3者会談なども行われましたが、テロ事件などをきっかけに和平交渉は難航しました。
2. 新中東和平構想とロードマップ
2002年6月24日、ブッシュ大統領は『新中東和平構想』を発表しました。これはパレスチナ国家の樹立を初めて公の政策課題とした点で画期的でしたが、パレスチナにおける新たなリーダーシップの樹立、つまりアラファト議長の排除を条件としており、物議を醸しました。この構想に基づき、アメリカを中心とした欧州連合、国連、ロシアの4者で、オスロ合意に代わる新たな和平案として、2005年末までにパレスチナ独立国家を樹立する『パレスチナ新和平案(ロードマップ)』が策定され、2003年4月30日にイスラエルとパレスチナ双方に提示されました。このロードマップには、イスラエルのヨルダン川西岸からの入植者撤退なども盛り込まれていましたが、実際には交渉は難航し、完全な履行には至りませんでした。重要な人物としては、イスラエルのシャロン首相、パレスチナ自治政府のアラファト議長(後にアッバス議長)、そして後に首相となるオルメルトなどが挙げられます。
3. ハマスの台頭と和平交渉の頓挫
2006年1月、パレスチナ評議会選挙でイスラム原理主義組織ハマスが圧勝し、ハマス単独の自治政府内閣が発足しました。これにより、ハマスとアッバス議長の支持母体であるPLO主流派ファタハの間で対立が激化し、ガザ地区を中心に激しい銃撃戦が続きました。2007年6月、ハマスはガザ地区を制圧・占領し、パレスチナ自治政府の統治は2つの地域に分断されました。ハマスはガザ地区からイスラエルへのロケット弾攻撃などを繰り返し、イスラエル軍も空爆などで対抗し、衝突は拡大しました。国際社会からも批判が高まりました。ブッシュ大統領も問題点を指摘しましたが、シャロン首相はテロから市民を守るために報復攻撃を正当化しました。こうした状況下、ブッシュ政権は2007年7月、中東和平国際会議の開催を提案し、同年11月27日、アナポリスでアッバス議長とオルメルト首相との3者会談を行いました。しかし、2008年末にはイスラエル軍によるガザ地区への大規模空爆・地上侵攻が発生し、和平交渉は頓挫、ブッシュ政権の任期も終了しました。
4. イラク戦争と中東和平への影響
ブッシュ政権が2003年3月20日に開始したイラク戦争(大規模戦闘は5月1日に終結)は、中東和平政策にも大きな影響を与えました。イラク戦争に対する多数の中東諸国からの反対・批判を受けて、ブッシュ政権は中東アラブ諸国を納得させるため、中東和平問題に取り組む必要性に迫られました。また、イラク戦争を中東民主化と結びつけるためにも、中東問題に消極的な姿勢を続けることができなくなりました。2007年に中東和平国際会議を開催した背景には、任期切れ直前に歴史に残るような成果を挙げようとした意図もあったと推測されます。しかし、イラク戦争への対応に多くの資源を割いたこと、そして、そもそもブッシュ政権が中東和平問題に当初から消極的であったことも、和平交渉の頓挫に繋がった大きな要因と言えるでしょう。
V.ブッシュ政権と核軍縮 管理
ブッシュ政権は、クリントン政権とは異なり、核軍縮・管理に消極的な姿勢を示しました。包括的核実験禁止条約(CTBT)への支持を撤回し、戦略攻撃兵器削減条約(モスクワ条約)はアメリカに有利な条約と批判されました。核兵器不拡散条約(NPT)に関しては、核兵器の小型化や核実験再開の準備を進めるなど、非核保有国からの批判を受けました。拡散に関する安全保障構想(PSI)は、大量破壊兵器の拡散防止を目的としたイニシアティブでしたが、国際法の制約など課題を残しました。
1. ブッシュ政権の核軍縮 管理への姿勢と批判
ブッシュ政権は、クリントン政権とは異なり、核軍縮・管理に関する多国間交渉や条約に消極的で懐疑的な姿勢を示しました。クリントン政権時代の2000年5月、NPT(核兵器不拡散条約)第6回再検討会議では、核兵器廃絶に向けた13項目の合意がなされましたが、ブッシュ政権は、この合意に含まれる核兵器全面廃絶への明確な約束、CTBT(包括的核実験禁止条約)の早期発効、カットオフ条約交渉の妥結、START2(第2次戦略兵器削減条約)の早期履行、ABM(弾道弾迎撃ミサイル)制限条約の維持強化などを、現実的ではないとして、目標達成に努めませんでした。むしろ、9.11テロを契機に、核兵器の小型化や核実験再開の準備期間の短縮化などを図り、核兵器を「使える兵器」にする方向へと進みました。この姿勢は、非核保有国などから厳しい批判を受けました。また、クリントン政権が署名したCTBTについても、ブッシュ政権は共和党多数の上院が批准を否決したことを理由に支持を撤回しました。START2に関しても、早期履行どころか、アメリカに有利な「まやかしの核軍縮」とも評された戦略攻撃兵器削減条約に置き換えました。
2. モスクワ条約と核軍縮の現状
ブッシュ政権は、ロシアとの間で2002年5月に戦略攻撃兵器削減条約(モスクワ条約)を締結しました。この条約は、従来のSTART条約と異なり、両国が独自に削減幅と戦略兵器の構成を決定でき、削減した核弾頭や運搬手段を廃棄する義務がなく、検証に関する規定もありませんでした。ブッシュ政権は、削減する弾頭の内2400発程度を、必要に応じて再配備できるよう「反応戦略」として保管するとしました。一方、ロシアは経済混迷・財政破綻の状況にあり、削減した戦略核を保管する余裕はありませんでした。そのため、モスクワ条約はアメリカに有利な「まやかしの核軍縮」と批判され、国際的な評価は高くありませんでした。この条約は、ブッシュ政権が核軍縮に消極的な姿勢を示す一例として挙げられます。
3. 拡散に関する安全保障構想 PSI
ブッシュ政権は、2003年5月31日にポーランドで『拡散に関する安全保障構想(PSI:Proliferation Security Initiative)』を発表しました。これは、2002年12月にイエメン沖でスペイン軍が北朝鮮船を臨検しスカッドミサイルを発見したものの、国際法の根拠がなく没収できなかった事件を背景に、大量破壊兵器やミサイルの拡散防止を目的としたものです。ブッシュ政権は、各国に協力を呼びかけ、2003年6月にPSI第1回総会を開催し、9月の第3回総会では『阻止原則宣言(Statement of Interdiction Principle)』を取りまとめました。しかし、PSIの法的根拠や実施における課題などは、依然として残された問題点として挙げられます。このPSIは、多国間協調とは異なる、ブッシュ政権の単独行動主義的な傾向を反映した政策の一環として位置付けることができます。
VI.ブッシュ政権とその他国際問題
ブッシュ政権は、スーダンにおけるダルフール紛争への対応も課題となりました。国連安保理決議に基づく制裁措置がとられましたが、効果は限定的でした。アフリカ連合スーダン・ミッション(AMIS)が派遣されました。レバノン紛争では、シリア軍のレバノンからの撤退を求める国連安保理決議1559の採択に貢献し、ハリリ首相暗殺事件後にはシーダー革命と称される民主化運動を支援しました。しかし、これらの問題においても、ブッシュ政権は積極的にイニシアティブを取ることは少なかったと評価されています。
1. スーダン ダルフール紛争への対応
スーダンでは、ダルフール地域において、スーダン政府の支援を受けたアラブ系遊牧民民兵組織ジャンジャウィードによる襲撃、略奪、破壊行為が繰り返され、多くの犠牲者と国内外への難民が発生しました。この事態を受け、国際社会は動き始め、ブッシュ政権も国連安保理にアラブ系民兵組織の解体、人道法違反に関与した指導者の拘束・訴追などを求める制裁決議案1556を共同提案し、2004年7月30日に採択されました。スーダン政府は渋々この決議を受け入れ、アフリカ連合スーダン・ミッション(AMIS)が監視団として派遣されましたが、その規模は300名程度と小規模でした。その後も、ブッシュ政権は安保理決議の履行をスーダン政府に求め続け、米議会も両院合同決議でジェノサイドの終結を求めました。パウエル国務長官も国務省報告書でジェノサイドと結論づけ、ブッシュ政権は安保理決議不履行の場合には石油禁輸を警告する決議案1564を提出しました。しかしながら、アメリカは1993年にスーダンをテロ支援国家に指定しており、クリントン政権時代には経済・貿易・金融制裁やミサイル攻撃も行われていました。2008年には、オバマ、マケイン両候補が北京オリンピックのボイコットをブッシュ大統領に要求しましたが、実現しませんでした。
2. レバノン紛争とシリア軍撤退
レバノンは、1975年から内戦状態にありましたが、1989年のタイフ合意で一旦終結しました。しかし、シリア軍が駐留し続け、シリアはレバノンに強い影響力を及ぼしていました。2004年8月、レバノン政府はシリアの圧力下で、ラフード大統領の任期延長を行う憲法改正を行いました。これに対し、ブッシュ大統領はフランスのシラク大統領と共に、シリア軍のレバノンからの即時撤退などを求める国連安保理決議案1559を共同提案し、採択されました。しかし、レバノン国民議会は憲法改正案を可決し、ラフード大統領と対立するハリリ首相と4閣僚が辞任しました。2005年2月14日、ハリリ首相が暗殺され、ブッシュ政権はシリア当局の関与を指摘し圧力をかけました。この事件を機に、レバノン国内でシリアからの独立・主権を訴えるデモが活発化し、親シリア内閣は総辞職しました。この「シーダー革命」と呼ばれる動きの中で、国際社会の圧力もあり、シリア軍はレバノンから撤退しました。ブッシュ政権の外交努力がシリアの影響力排除に一定の貢献を果たしたことは否定できません。
