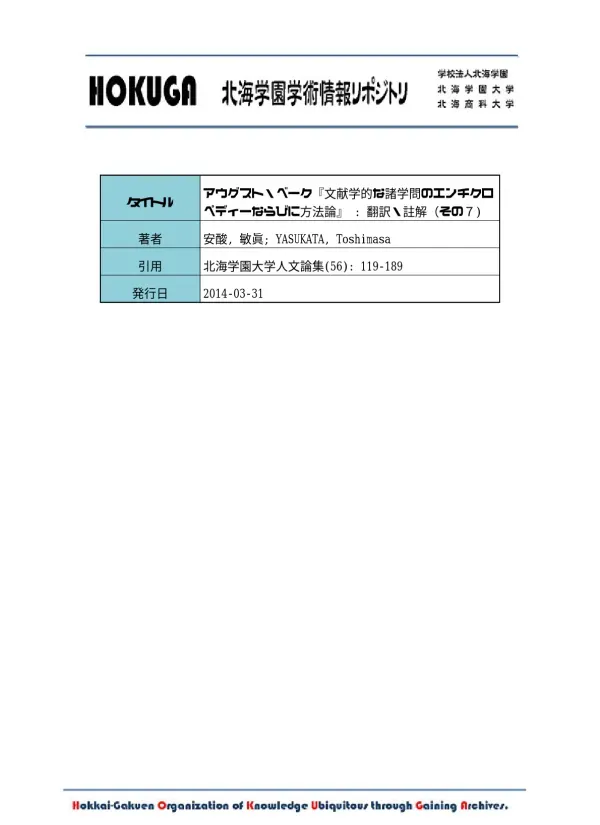
ベーク文献学:個人的批判の翻訳解説
文書情報
| 著者 | 安酸 敏眞 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 人文科学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 場所 | 札幌市(北海学園大学所在地と推定) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 771.12 KB |
概要
I.古代ギリシア ローマ文献の作者鑑定 個人批判 と 種類批判 の役割
本論文は、古代ギリシア・ローマ文献の作者鑑定における本文批判の重要性を論じています。特に、著者の個性(文体、文章構成、言語習慣など)に基づく個人批判と、作品の種類(ジャンル)を考慮した種類批判の両面からのアプローチを強調しています。個人批判では、著者の既知の作品との文体の整合性や、時代・地域的背景との矛盾を検証し、偽書や模倣の可能性を探ります。種類批判では、作品が属するジャンルの特徴を分析し、個人批判の結果と照合することで、より正確な判断を下します。プラトンの著作、特に『ミーノース』と『ヒッパルコス』を例に、これらの方法論が実践的にどのように適用されるかが示されています。
1. 個人批判の基礎と限界 文体の一貫性と個性の変遷
この節では、古代文献の作者を特定するための主要な手法として個人批判が提示されています。個人批判は、著者の既知の文体との比較を通して、対象とするテキストの真正性を検証するアプローチです。しかし、著者の文体には、年齢や経験、あるいは作品の種類によって変化が生じる可能性があり、その点を考慮しなければ誤った結論に至る危険性があると指摘されています。 具体的には、ある箇所が著者の他の作品と調和しない場合でも、それが著者の個性の時間的変化や、作品における意図的な文体変化によるものかを慎重に検討する必要があると強調されています。 また、個性に関する判断が、その判断の基準となる異文に基づいて確定されている場合、論証が循環論法に陥る危険性も指摘されています。これらの困難にも関わらず、個人批判は、絶え間ない検討と解釈を通して、課題解決に近づくための有効な手段であると結論付けられています。リューシアースの演説を例に、文体の多様性が必ずしも偽造を示すものではないことを示唆し、個々の作品をその文脈の中で理解する重要性が強調されています。
2. 種類批判との連携 ジャンルと個人スタイルの峻別
個人批判は単独で行われるものではなく、種類批判と密接に連携する必要があると主張されています。 同一著者の複数の著作間には、個性の統一性と多様性が同時に存在し、その多様性を容易に不調和と誤解してしまう可能性があると警告されています。これは、著者の作品が異なるジャンルに属したり、著者の個性の発展段階を表している場合に特に顕著です。例えば、リューシアースの歴史的演説とプラトンの『パイドロス』におけるエロースに関する演説を比較することで、ジャンルの違いが文体の違いを生み出し、誤った作者特定につながる可能性を示しています。 ディオニュシオス・ハリカルナッソスの意見を引用し、同じ著者であっても、作品の種類によって文体や性格が異なる場合があることを説明しています。墓碑銘の文体も、頌歌というジャンルに特有の形式から説明できると示唆し、文体上の差異だけで作品を偽物と断定してはならないと強調しています。 個人批判は種類批判に依存しつつも、著者の個性の発展という複雑な要素も考慮する必要があるため、高い困難性を持つとされています。
3. 模倣と剽窃の峻別 意図的な借用と無意識の反復
この節では、古代の作家における模倣と剽窃の問題が取り上げられています。 同一の思想や表現の反復が、模倣なのか、偶然の一致なのか、あるいは共通のジャンルの特徴によるものかを区別することの難しさが強調されています。エウリピデスや古代の演説家たちの作品に見られる自己引用を例に、時間的制約や表現の工夫の欠如が、無意識の反復につながることを説明しています。一方、意図的な模倣、つまり剽窃の可能性については、特に慎重な検討が必要であると主張されています。 オランダの批評家たちが、年代的に模倣が不可能な場合にも模倣を安易に仮定してきたことを批判し、古典作家においても模倣が実際に行われていたことを認めつつ、観客の嗜好や時間的制約といった背景も考慮する必要があると指摘しています。 アンドキデースとアイスキネースの演説における類似点を例に、50年前の演説を参考にしたり、準備時間の不足から引用をそのまま用いる行為は、剽窃とは異なる文脈で理解されるべきであると主張しています。 キケローの哲学的著作におけるギリシア哲学からの借用を例に、模倣の許容範囲が作家や時代によって異なることを示し、ギリシアの古典散文家については、あらゆる模倣を独創的な芸術的意図から説明する必要があると結論付けています。
II.外的証拠と内的証拠の統合 伝承 の批判的検討
作者鑑定においては、テクスト自体からの内的証拠(文体、構成、内容)と、歴史的記録や写本伝承といった外的証拠を総合的に検討することが不可欠です。外的証拠としては、アリストテレスの引用や、パウサニアースなどの後世の著述家の証言などが挙げられます。しかし、外的証拠は必ずしも信頼できるものではなく、偽造された記述や、時代による誤解・歪曲の可能性も考慮しなければなりません。特に、アレクサンドリア時代の文献整理や、ローマ時代の書籍販売の隆盛は、伝承の混濁化に大きく影響を与えました。 そのため、伝承を批判的に検証し、外的証拠と内的証拠の整合性を確認することが、正確な作者鑑定を行う上で重要となります。 シモーニデースのような悪質な偽造者の存在も、この作業の難しさを示しています。
1. 内的証拠と外的証拠の矛盾 テキスト改訂の可能性
この節では、古代文献の作者鑑定において、テキストの内容(内的証拠)と、そのテキストに関する歴史的記録や伝承(外的証拠)の間の矛盾が重要な問題となることを指摘しています。 著者の名前や人物像が既に知られている場合でも、テキストの伝承された形態が、テキスト自体から推測される著者の個性と矛盾するケースがあるとしています。このような不調和を解消するための唯一の方法は、テキストの改訂であると主張しています。改訂の際には、複数の異なる個性が混在している場合、元のテキストが複数の書物の合本であるか、後世による改竄が行われたかを検討する必要があると説明しています。 改訂作業は古文書学的批判に基づいて行われ、外的証拠の助けが必要となりますが、著者の個性が歴史的に確立されている場合のみ、改訂は説得力を持つとされています。 プラトンの『法律』の例が挙げられ、その真正性は外的証拠によって確定されているものの、未完の原稿を弟子が編集したという伝承が存在することを指摘し、テキストの改訂の必要性と複雑さを示しています。
2. 外的証拠の信頼性 証言の検証と偽造の可能性
外的証拠に基づいて作者を決定する場合、その証拠の信頼性を慎重に検証する必要性を説いています。外的伝承によって特定された作者に、著作がふさわしくない場合、内的根拠によってその不適合を証明できるとしています。 この場合、不調和をテキストの改訂によって解消すべきか、あるいは著作を作者から完全に切り離すべきかの判断が課題となります。外的証拠が全く信頼できないと証明されない限り、テキスト改訂を優先すべきであると主張しています。 造形芸術の作品の判断を例に挙げ、有名な巨匠の作品とされる彫刻に、巨匠のスタイルと合わない部分があった場合、まずその部分だけが後世の加筆であると考えるべきであるという論理を適用しています。 古代文献の作者特定においては、外的証拠として、著者の同時代人、親戚、友人、弟子などの証言が重要になりますが、これらの証言も絶対的に信用できるものではなく、検証が必要であると述べられています。 シュライアーマッハーがルツィンデに関する書簡の作者を特定した事例や、フィヒテの著作がカントのものと誤認された事例など、誤った判断の例が挙げられています。
3. 伝承の混濁化と古代の証言 時代と信頼性の関係
この節では、時間経過に伴う伝承の混濁化が、作者鑑定の困難さを増大させる要因となることを論じています。 古代文献の伝承は、口承や写本による伝達を経る中で、改変や誤謬が生じる可能性があり、その過程において、作者に関する情報が失われたり、歪められたりする可能性があると指摘されています。 そのため、同時代人の証言の方が、後世の証言よりも信頼できる傾向がある一方、後世の証言でも、綿密な研究に基づいた妥当な判断があれば、古い証言よりも信頼性が高い場合もあるとされています。 パウサニアースやクィンティリアヌスの証言を例に、証言者の専門性や知識の深さが証言の信頼性に影響を与えることを説明しています。 特に、アレクサンドリアの文法学者たちの批判的活動が、伝承の混濁化に対抗する上で重要な役割を果たしたと評価し、彼らの貴重な業績が断片的にしか残されていないことを惜しんでいます。 また、ヴァッローやプラウトゥスの例を挙げ、古代の批評家の判断が、現代の研究者にとっても重要な手がかりとなることを示唆しています。
III.文体分析における 数 と リズム の重要性
文体分析においては、文章構成や言語習慣に加え、散文における数(リズム)も重要な要素となります。古代ギリシアの雄弁家、特にデモステネスの文体における数の規範性と、プラトンの文体との比較を通して、この点が考察されています。 デモステネスの文体は力強く、堅実な数を特徴とする一方、アシアー風の文体は弛緩し、女性的な数を示す、といった分析がなされています。これらの数の分析は、個人批判において、著者の個性をより詳細に特定する上で役立ちます。また、ヘロドトスの文体がその中間的な性格を持つことも指摘されています。
1. 文体分析における数の概念 リズムと文体論
この節では、古代ギリシャ・ローマ文献の文体分析において、散文のリズムを構成する「数」(rhythmus)の重要性が論じられています。 単なる単語の数ではなく、散文におけるリズム、すなわち文の構成や長さ、句読点の位置などが織りなす全体的な音楽性を指しています。 現代においても、文体のリズムに関する判断は曖昧な感覚に頼りがちですが、古代の文体論においては、この感覚を概念的に捉えようとする試みがあったと指摘されています。 特に、デモステネスの文体が、古代においてあらゆる文体の規範と見なされていたことを挙げ、デモステネスの文体に現れる「数」を最も完全な形として提示しています。 この「数」の分析を通して、プラトンの文体には必ずしも正しい散文的な「数」がないことを指摘し、文体の違いを客観的に分析する手法の必要性を示唆しています。 アリストテレスの文体論における、ゆるやかな叙事詩的表現と周期的な抒情的表現の区別も紹介され、文体のリズム分析の複雑さと多様性が示されています。
2. 数と声調の区別 リズムとアクセントの相違点
散文における「数」を分析する際には、「声調」(sonus)との区別が重要であると指摘されています。「数」は単語の位置によるリズム的な側面を指す一方、「声調」は音による強調、すなわちアクセントやメロディー的な側面を指します。 両者は密接に関連しているものの、文章構成への依存度が異なるため、区別して分析する必要があると説明しています。 具体的には、「数」の一つの形式は力強さ、堅実さ、芯の強さを特徴とし、アッティカ人の文体において最も顕著に見られるとされています。対照的に、別の形式の「数」は弛緩し、女性的で芯がないとされ、ヘロドトス風の文体に典型的に見られるとされています。 ヘロドトスの文体は、この二つの「数」の中間的な性格を持つとされ、アッティカ風の力強さと、ヘロドトス風の柔らかさを比較することで、文体の多様性とリズムの重要性を強調しています。これらのリズムの違いは、文体全体を特徴づける重要な要素であると結論付けられています。
3. 模倣と個性 文体模倣の限界とオリジナルの追求
この節では、文体模倣の問題と、真の個性を持った文体の重要性が論じられています。 優れた作家であっても、無意識的なまたは意識的な思想や表現の反復は起こりうるため、模倣と偶然の一致、あるいは共通のジャンルの影響を区別することが難しいと指摘しています。 古代の演説家たちが自身の過去の演説をそのまま繰り返した例を挙げ、時間的制約や表現へのこだわりが、反復につながることを説明しています。 しかし、他者の作品を模倣した可能性を判断する際には、特に慎重な検討が必要であると強調し、オランダの批評家たちが安易に模倣を仮定してきたことを批判しています。 古典作家においても模倣は存在したとして、その背景には観客の趣味があったことを指摘し、ソポクレス、エウリピデス、そして演説家たちの例を挙げ、模倣の実際と、その歴史的・文化的文脈を考慮する必要性を示唆しています。 ローマの作家とギリシアの模範との関係において、オリジナリティの度合いを正確に判断することの重要性が示され、キケローの著作におけるプラトンからの借用を例に、模倣の許容範囲が時代や文化によって異なることを示唆しています。 プラトンの『饗宴』における様々な演説スタイルの模倣を、芸術的な意図に基づくものとして位置付け、模倣と剽窃を区別する重要性を改めて強調しています。
IV.文献学諸学科の相互関係 解釈学と批判の統合
本論文では、古典文献学を文法学、文学史、学問史という3つの現実的諸学科の統合された研究分野として位置づけています。これらの分野は、言語作品(碑文を含む)の解釈学的な分析を通して相互に関連し、発展していきます。解釈学は、本文批判の基礎となり、個人批判や種類批判といった具体的な批判手法を支えます。 古代の知恵の伝承と発展を理解するためには、これらの諸学科を統合的に捉え、古代人の世界観を理解する必要があります。最終的に、古典文献学の研究は、ロゴス(精神が認識を形作る形式)の理解を通して、近代との差異を明らかにし、人類の精神の発展を解明することに繋がると結論づけています。
1. 古典文献学の構成要素 文法学 文学史 学問史の三位一体
この節では、古典文献学が文法学、文学史、学問史という三つの現実的諸学科の有機的な結合によって成り立っているという考え方が示されています。 文法学は言語作品に対する文法的解釈から生じ、種類的解釈を加えることで文体論へと発展すると説明されています。文体論は文学史の基礎となり、文学史は個人とジャンルの解釈を統合することで成立します。そして、文学史は学問史の前提条件となるため、学問史もまた種類的解釈の産物であるとされています。 つまり、古典文献学は、文法的な分析から始まり、文学史、学問史へと段階的に広がり、これらの学問分野が互いに関連し合いながら、古代の言語と文化を解明していく過程であると理解できます。 しかし、言語的記念物のみならず、非言語的な記念碑なども考慮すべきというライヒャルトの批判も紹介され、解釈学の対象範囲の広さが示唆されています。
2. 解釈学と批判の相互作用 直接的認識と批判的検証
この節では、解釈学と批判の密接な関係が論じられています。 古典文献学の研究においては、解釈学に基づいた批判的アプローチが不可欠であり、直接的な認識と批判的検証が相互に補完し合う関係にあるとされています。 プラトンのような偉大な哲学者も、先行する哲学体系を歴史的に批判することで、より高次の真理に到達したと例示されています。 しかし、それぞれの哲学体系が歴史におけるどの段階を占めるのか、真理がどの程度表現されているのかを正確に理解するには、文献学者自身も哲学的な教養を備える必要があると強調されています。 「真の疑り深い意識(animus suspicax)」を持ち、自分の解釈を疑う姿勢が、正しい批判の出発点であるとされ、初心者はまず解釈学に奉仕する形で批判を行うべきだとされています。 文法的批判と歴史的批判が優先されるべき理由として、その基準がより明確で、判断が伝承された個別的事項から出発するからであると説明されています。
3. 古典文献学の体系 ロゴスと国民的知識の発展
本節は、古典文献学の諸学科が、古代人の精神、すなわち「ロゴス」の理解を通してどのように体系化されるかを説明しています。 ロゴスは、認識を形作る精神の形式であり、言語において客観化されると考えられています。言語は認識の素材を知識の内容へと転換し、個人の作用によって精神的形式に組み込まれることで、文学的ジャンルが成立します。 文学的ジャンルの基準に従って、言語表現の形式が形成され、学問史、文学史、言語史という三つの段階を通して、国民の知識が発展していくと説明されています。 興味深いのは、これらの現実的諸学科が、個々の記念物の解釈から出発するのではなく、古代の原理、すなわち古代人の全体的な直観から帰結するという逆説的な主張です。 この全体像を理解するには、言語がアルファとオメガを形成する円環全体をたえず走り抜ける必要があるとされ、古典文献学の研究が、古代生活の様々な側面を把握するための包括的なアプローチであると結論付けられています。
